2014年02月13日
AQUALUNG ジェスロ・タル
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です!
最近、いろいろ事情がありまして、
ほとんど遠出外出が出来ない状況になっており、
だから音楽記事、アルバム紹介記事を連発しております。
まあ、遠征などで上げたくても上げられない時もあるので、
こういう時があってもいいのかな、とは思っていますが・・・
01

ジェスロ・タルは大好きです!
ロック界の「奇人変人怪人」イアン・アンダーソンは、
片手を頭の上に上げてCの字を作るように曲げ、片足も上げて曲げ、
「シェー」のポーズをとってフルートを弾く姿がトレードマーク。
そもそもロックにおいて、メインのメンバーがフルートということからして、
このバンドの人を喰ったユニークさが分かろうというものです。
バンドの音楽の変遷を簡単にまとめると、
1968年デビュー、初期の頃はほとんどブルーズバンドでしたが、
元々持っていた要素でもあるトラッド色をしだいに強めます。
また、J.S.バッハの曲を原曲としたBourreがヒットしたように
クラシックの素養も強く持っていました。
さらに70年代に入ってから、プログレッシヴ・ロックの要素も
大胆に取り入れて、70年代前半にひとつのスタイルが完成し、
バンドは人気面でも創作面でも絶頂期を迎えました。
そして70年代中頃からは、一度完成したスタイルを
再び分解するかのような音楽を展開し、曲の時間も短くもなり、
バラエティに富んだ音を聴かせるようになりました。
もちろん、曲のポップさは一貫して失わずに。
と、今はこうして書くことは出来るのですが、僕も以前は、
あまりにも「ユニーク」で、まあはっきり、避けていましたね(笑)。
僕がリアルタイムで洋楽を聴き始めた1980年代にはもう、
彼らは過去の人というイメージがあって、名前は知っていたけど、
「ああ、なんか変な人ね・・・」というくらいのものでした。
声はダミ声、音楽もよくいえばアーシー、つまり地味だしで、
若い頃は、あまりぱっとしないようなイメージを持っていました。
僕は、いつも言う、ヒットチャート中心に聴いてきた人間でしたが、
過去の年間チャートには彼らのアルバムが何枚か入っていて、しかも
レギュラーチャートで1位になったアルバムもあることが分かり、
そのことが、僕が持っていた彼らのイメージからみると不思議でした。
そして、その不思議は少しずつ、小さな興味の積み重ねとなりました。
30歳を過ぎてからようやく、僕もタルを聴き始めました。
そして、僕がタルで最初に聴いたアルバムが、これでした。
直接のきっかけは、1999年に、ドイツのヘヴィメタルバンド
ハロウィンが発表したカバーアルバムの中で、
タルのLocomotive Breathを演っていて、これがなかなかカッコよく、
その曲が入ったアルバムがどれかと調べたところこれで、
どうやらそれがタルの最高傑作であるらしいと分かって買いました。
聴いてみると、不思議に思った部分が一発で氷解しました。
02 うちの裏の家の庭に現れた雪猫

確かに音的には、派手さもきらびやかさもないですが、
フルートのユニークな響きなど、印象的な音作りに心を奪われました。
しかも、かなりしたたかな人たちのようで、
どういうものが受けるかをよく研究していることが感じ取れ、
一瞬で心を鷲づかみにするよなポップさやインパクトはないけど、
1回聴けば必ず心に引っかかって、それがじわじわとツボを攻める、
独自の世界を構築し追及してゆくバンド、そんなことを感じました。
その基盤になっているのは、
自分たちの音楽はあくまでもエンターテイメントである、
という意識であることが、このアルバムを聴いて見えてきた部分でした。
地味でよく分からない人たちというイメージが強ければ強いほど、
このアルバムのエンターテイメント性が、逆に、
驚きと称賛を持って受け入れられると思います。
そうです、これは立派なエンターテイメント作品で、
地味とは正反対にあるものだったです。
その辺のギャップというかミスマッチ感覚がまた面白いですが、
その辺が「人を喰った」人たちたるゆえんでしょう。
そしてこれはいわゆる「コンセプト・アルバム」でもあり、
全体の流れがとてもうまく練られていて、素晴らしい。
このアルバムは実際に英国のどこかの町が舞台のようで、
どの曲も、いかにも英国的イディオム満載です。
といって、僕は英国には行ったことがないので、それはあくまでも
想像と疑似体験を通して感じたことにすぎないのですが・・・
このアルバムを聴くと、とりわけ英国に行きたくなります(笑)。
まあそれはともかく、コンセプトアルバムなだけに、
「ああ、アルバム聴いたぁ」という充実感は高い1枚ですね。
ジェスロ・タルの魅力の側面を語るもう一つの話があります。
1988年のグラミー賞で
「ハードロック・ヘヴィメタル部門」が創設された際に、
最初に受賞したバンドがこのジェスロ・タルでしたが、
当時、へヴィメタルを聴く人は「なんで・・・???」という反応でした。
だけど、そう感じさせる部分がないかというとそうでもなく、
ブリティッシュ・ハードロックとは直でつながる音作りだし、
ブラック・サバスのGtトニー・アイオミが、サバス結成前に、
1週間だけタルのメンバーだったことがあって、その模様が、
ローリング・ストーンズが主催し、ジョン・レノンも参加した
『ロックンロール・サーカス』に収められていたり、
アイアン・メイデンのBsスティーヴ・ハリスが
影響を受けたアーティストのひとりに挙げていたり、そして
ハロウィンがカバーしていたりと、ヘヴィメタル系とのつがなりも深く、
そうした人たちに訴える音を出しているバンドではあるでしょう。
03 うちにあるMOTHER GOOSEの本とタル

Tr1:Aqualung
曲を聴いて、沖縄の海でダイビング・・・
なんて、さらさら想像できないと思います(笑)。
歌詞を読んでも、ダイビングや海はと関係なく、
公園でひとり寂しく時間を過ごす・・・というような歌です。
重苦しさに穴をあけて新鮮な空気を吸いたい、という比喩かな。
中間部はテンポを落としてトラッド風にじわじわと攻めつつ、
再びテンポアップして軽快に進む部分はカッコいいですね。
1曲目からまさにブルーズ+トラッドの独自の雰囲気をたたえつつ、
ハードさもあり、展開の多彩さと曲の長さはプログレの影響大で、
彼らの音楽をダイジェストした、名曲といっていい曲。
Tr2:Cross-Eyed Mary
フェイドインしながら静かに始まったところを
強烈なギターリフで打ち破ってイアンが歌い出す、
これは音的にはハードロックのとてもカッコいい曲。
ただし、僕が最初に聴いた時には、抽象的表現ですが、
前の曲で乗った波にそのまま乗っかって進むのではなく、
敢えて別のもっと強い波を待って乗り換えるみたいな、
ちょっと「すかした」部分が彼らの面目躍如だな、と感じました。
Aqualungという単語が歌詞に入っているように、
前の曲の続きのような曲でもあり、アルバムを俯瞰した曲。
そうそう、紹介が遅れましたが、
Gtのマーティン・バレは、目立たないけど、
というかイアンだけが目立つようにしているんでしょうけど(笑)、
手堅い中にもアグレッシブさを失わない部分があって、
僕が大好きなギタリストの1人です。
Tr3:Cheap Day Return
インストの1分少々しかないつなぎのトラッド風小品。
Tr4:Mother Goose
アコースティック弾き語りの後ろでフルートが小躍りする、
跳ねたリズムのちょっとかわいらしい曲。
それもそのはず、「マザー・グース」。
でも、直接的にマザーグースの話から取っているのではないようで、
そういう楽しさ、寓意を基に言葉遊びしつつ情景描写している感じ。
いかにも英国小市民的な曲ですが、そういうのが好きなんです。
トラッド風小品が多い中、この曲はそれ系では目玉でしょう。
朝の雰囲気、サンドイッチが食べたくなってくる(笑)。
Tr5:Wond'ring Aloud
前の曲から続いたやはり2分ないトラッド風小品。
こちらは歌もあって、小声でぶつぶつ歌っていますが、
意外なことに(笑)、恋の喜びを軽く歌っています。
ここまでの歌詞がある4曲中3曲にSunという単語が出てきますが、
それがみな、「英国の冷たい太陽」っぽい感じがします。
行ったことはないけど・・・
Tr6:Up To Me
LPではA面の最後、ここでまた音が重くなります。
フルートとベースによる明確なブルーズ風のリフがあって、
これがカッコよく、気持ちをぐいぐいと前に押してくれますが、
前の曲が緩かっただけにこの効果は満点。
曲の並べ方にメリハリがあるのは、アルバムとして素晴らしい。
それにしても、フルートという一見すると「ロックではない」楽器が、
実はこんなにもロックしているなんて、と、ちょっと驚く佳曲。
04 蒸気機関車の絵が入ったメモ帳とタル・・・

Tr7:My God
そういえば教会にいるような雰囲気。
ハンマーで叩きつけるような重たいギターリフに、
なんといっても聴きどころは、中間部のフルートのソロ。
掛け声のようなある種不気味なコーラスをバックに繰り広げられ、
イアンは、フルートを吹きながら自分でも掛け声を出していて、
ちょっと危なくて恐い、スリリングな展開に引き込まれます。
フルートソロの途中に、クリスマスソングでおなじみの
God Rest Ye, Merry Gentlemanの旋律も織り込まれています。
ああ、そうか、Godつながりか・・・(笑)・・・
ある意味このアルバムの白眉ですね。
Tr8:Hymn 43
そして実際に「賛美歌43番」とくる流れがいい。
雰囲気がぱっと明るくなり、リフを刻むギターも少し軽い音に。
そのリフがTr6に似ているのは、トータルアルバムとしての意識でしょう。
しかし賛美歌だけど熱唱しているのがまた面白い。
Tr9:Slipstream
イントロなしに優しげに歌い始める1分強のトラッド小品。
これも朝の雰囲気、というか、このアルバムは、
重い曲でもみんな朝の雰囲気がします。
しかも、まだ多くの人が寝ている朝の時間帯。
Tr10:Locomotive Breath
邦題「蒸気機関車のあえぎ」。
ロックの「てっちゃんソング」の筆頭格でしょうね(笑)。
タルの中でも屈指の名曲、人気曲。
シングルとしてもTop10入りするヒットになりました。
いかにも力強く前進するようなギターリフに導かれる曲、
そしてギターをミュートして出す「カッカッ」という音は、
まさに蒸気機関車のイメージにぴったり!
そうそうこの「カッカッ」というギターの音も、Tr8で一度伏線として
出てきている辺り、やはりかなり練られていますね。
まあ、こういう曲があるだけでもうれしいんですが(笑)。
タルはそれと、このように、言葉の感覚が独特で面白いですね!
Tr11:Wind Up
ラストは、前の曲の余韻を受け、ピアノで静かに始まり、
イアンがつぶやくように囁くように告白するように歌い出す。
なんだか思わせぶりだなと聴いていると楽器が少しずつ増え、
エレクトリック・ギターのフレーズを契機にアップテンポになり、
アルバムでもいちばんのノリの中で曲がぐいぐい進む。
そして最後はまた放り投げるように静かにピアノと歌で締める。
いかにもショーの最後という感じの開放感ある曲で、ノリ的には、
ドリフのコントの最後にかかる音楽っぽい感じもします(笑)。
この曲こそ、この人たちはへそ曲がりなだけじゃない、
そりゃ確かに見てくれはそうだけど(笑)、基本としては、
ちゃんとエンターテイメント性を考えている人たちなんだと気づき、
「この人たちの音楽は聴きやすい」と感じた曲でした。
予定調和というのは、ロックの中にも確かにあるんですよね。
それを否定すると、音楽の楽しさは半減するかもしれないことは、
この曲を聴いた気持ちよさが証明してくれていると思います。
だけどやっぱり、この終わり方は、癖になるなぁ(笑)。
なお、現行のリマスター盤には、
6「曲」のボーナストラックが入っていますが、
それらのボーナスもこのアルバムのイメージが踏襲されていて、
特にTr12:Lick Your Fingers Cleanは、
最初はボーナスだと分からないくらいTr11とうまくつながっています。
ただ、ただし・・・
このアルバム、現在のリマスター盤には、
とても大きな不満があります。
Tr14に、イアン・アンダーソンのインタビューが入っているんです。
CDなので飛ばして聴けばいいのでしょうけど、でも僕は、
一度かけたら飛ばしたくない性分だし、うちの連装CDで
ずっとかけ続ける場合はそれがちょっと邪魔になります。
しかも、最後じゃないのがまた引っかかります。
それと、音が異様に小さいのも、通しで聴くとつらい部分ですが、
これはさほど問題でもないでしょうか。
ジェスロ・タルという名前は何かというと、
17世紀から18世紀にかけてを生きた英国の農政学者の名前です。
これまた変わったところから名前をつけてますよね(笑)。
しかし、彼らの音楽を聴いてみると、その名前に込めた思いが
なんとなく透けて見えるのがまた面白いです。
ちなみに、ジャケットの不思議なおじさんの絵は、
その農政学者でもイアン・アンダーソンでもなく、
「公園にいたただのおじさん」だそうで・・・
ひとつ余談を。
僕は、1996年に刊行されたロックのディスコグラフィーの本を
傍らに常に置いていて、それを見ながら記事も書いていますが、
その本は、個人名については、ファミリーネーム順で並んでいます。
Bob Dylanは「B」ではなく「D」のところにあるという具合に。
ある日、Jethro Tullをその本で探している時に、
バンド名が個人名なので、「T」のところを探していて、
何度探しても該当する部分にないので、あれ、おかしいな・・・
と思ったら、この場合は別にメンバーの名前でもないし、
素直に「J」を探せばいいんだ、と気づきました(笑)。
そうそう、Jethro Tullも略すと「JT」になりますが、
それではJames Taylorと区別がつかなくなるので、
僕はタルと呼んで書いています(笑)。
というか、それがファンの間では一般的だと思いますが・・・(笑)。
ジェスロ・タルは、凝りだすと止まらないですよ!
写真へのコメントも
大歓迎です!
最近、いろいろ事情がありまして、
ほとんど遠出外出が出来ない状況になっており、
だから音楽記事、アルバム紹介記事を連発しております。
まあ、遠征などで上げたくても上げられない時もあるので、
こういう時があってもいいのかな、とは思っていますが・・・
01

ジェスロ・タルは大好きです!
ロック界の「奇人変人怪人」イアン・アンダーソンは、
片手を頭の上に上げてCの字を作るように曲げ、片足も上げて曲げ、
「シェー」のポーズをとってフルートを弾く姿がトレードマーク。
そもそもロックにおいて、メインのメンバーがフルートということからして、
このバンドの人を喰ったユニークさが分かろうというものです。
バンドの音楽の変遷を簡単にまとめると、
1968年デビュー、初期の頃はほとんどブルーズバンドでしたが、
元々持っていた要素でもあるトラッド色をしだいに強めます。
また、J.S.バッハの曲を原曲としたBourreがヒットしたように
クラシックの素養も強く持っていました。
さらに70年代に入ってから、プログレッシヴ・ロックの要素も
大胆に取り入れて、70年代前半にひとつのスタイルが完成し、
バンドは人気面でも創作面でも絶頂期を迎えました。
そして70年代中頃からは、一度完成したスタイルを
再び分解するかのような音楽を展開し、曲の時間も短くもなり、
バラエティに富んだ音を聴かせるようになりました。
もちろん、曲のポップさは一貫して失わずに。
と、今はこうして書くことは出来るのですが、僕も以前は、
あまりにも「ユニーク」で、まあはっきり、避けていましたね(笑)。
僕がリアルタイムで洋楽を聴き始めた1980年代にはもう、
彼らは過去の人というイメージがあって、名前は知っていたけど、
「ああ、なんか変な人ね・・・」というくらいのものでした。
声はダミ声、音楽もよくいえばアーシー、つまり地味だしで、
若い頃は、あまりぱっとしないようなイメージを持っていました。
僕は、いつも言う、ヒットチャート中心に聴いてきた人間でしたが、
過去の年間チャートには彼らのアルバムが何枚か入っていて、しかも
レギュラーチャートで1位になったアルバムもあることが分かり、
そのことが、僕が持っていた彼らのイメージからみると不思議でした。
そして、その不思議は少しずつ、小さな興味の積み重ねとなりました。
30歳を過ぎてからようやく、僕もタルを聴き始めました。
そして、僕がタルで最初に聴いたアルバムが、これでした。
直接のきっかけは、1999年に、ドイツのヘヴィメタルバンド
ハロウィンが発表したカバーアルバムの中で、
タルのLocomotive Breathを演っていて、これがなかなかカッコよく、
その曲が入ったアルバムがどれかと調べたところこれで、
どうやらそれがタルの最高傑作であるらしいと分かって買いました。
聴いてみると、不思議に思った部分が一発で氷解しました。
02 うちの裏の家の庭に現れた雪猫

確かに音的には、派手さもきらびやかさもないですが、
フルートのユニークな響きなど、印象的な音作りに心を奪われました。
しかも、かなりしたたかな人たちのようで、
どういうものが受けるかをよく研究していることが感じ取れ、
一瞬で心を鷲づかみにするよなポップさやインパクトはないけど、
1回聴けば必ず心に引っかかって、それがじわじわとツボを攻める、
独自の世界を構築し追及してゆくバンド、そんなことを感じました。
その基盤になっているのは、
自分たちの音楽はあくまでもエンターテイメントである、
という意識であることが、このアルバムを聴いて見えてきた部分でした。
地味でよく分からない人たちというイメージが強ければ強いほど、
このアルバムのエンターテイメント性が、逆に、
驚きと称賛を持って受け入れられると思います。
そうです、これは立派なエンターテイメント作品で、
地味とは正反対にあるものだったです。
その辺のギャップというかミスマッチ感覚がまた面白いですが、
その辺が「人を喰った」人たちたるゆえんでしょう。
そしてこれはいわゆる「コンセプト・アルバム」でもあり、
全体の流れがとてもうまく練られていて、素晴らしい。
このアルバムは実際に英国のどこかの町が舞台のようで、
どの曲も、いかにも英国的イディオム満載です。
といって、僕は英国には行ったことがないので、それはあくまでも
想像と疑似体験を通して感じたことにすぎないのですが・・・
このアルバムを聴くと、とりわけ英国に行きたくなります(笑)。
まあそれはともかく、コンセプトアルバムなだけに、
「ああ、アルバム聴いたぁ」という充実感は高い1枚ですね。
ジェスロ・タルの魅力の側面を語るもう一つの話があります。
1988年のグラミー賞で
「ハードロック・ヘヴィメタル部門」が創設された際に、
最初に受賞したバンドがこのジェスロ・タルでしたが、
当時、へヴィメタルを聴く人は「なんで・・・???」という反応でした。
だけど、そう感じさせる部分がないかというとそうでもなく、
ブリティッシュ・ハードロックとは直でつながる音作りだし、
ブラック・サバスのGtトニー・アイオミが、サバス結成前に、
1週間だけタルのメンバーだったことがあって、その模様が、
ローリング・ストーンズが主催し、ジョン・レノンも参加した
『ロックンロール・サーカス』に収められていたり、
アイアン・メイデンのBsスティーヴ・ハリスが
影響を受けたアーティストのひとりに挙げていたり、そして
ハロウィンがカバーしていたりと、ヘヴィメタル系とのつがなりも深く、
そうした人たちに訴える音を出しているバンドではあるでしょう。
03 うちにあるMOTHER GOOSEの本とタル

Tr1:Aqualung
曲を聴いて、沖縄の海でダイビング・・・
なんて、さらさら想像できないと思います(笑)。
歌詞を読んでも、ダイビングや海はと関係なく、
公園でひとり寂しく時間を過ごす・・・というような歌です。
重苦しさに穴をあけて新鮮な空気を吸いたい、という比喩かな。
中間部はテンポを落としてトラッド風にじわじわと攻めつつ、
再びテンポアップして軽快に進む部分はカッコいいですね。
1曲目からまさにブルーズ+トラッドの独自の雰囲気をたたえつつ、
ハードさもあり、展開の多彩さと曲の長さはプログレの影響大で、
彼らの音楽をダイジェストした、名曲といっていい曲。
Tr2:Cross-Eyed Mary
フェイドインしながら静かに始まったところを
強烈なギターリフで打ち破ってイアンが歌い出す、
これは音的にはハードロックのとてもカッコいい曲。
ただし、僕が最初に聴いた時には、抽象的表現ですが、
前の曲で乗った波にそのまま乗っかって進むのではなく、
敢えて別のもっと強い波を待って乗り換えるみたいな、
ちょっと「すかした」部分が彼らの面目躍如だな、と感じました。
Aqualungという単語が歌詞に入っているように、
前の曲の続きのような曲でもあり、アルバムを俯瞰した曲。
そうそう、紹介が遅れましたが、
Gtのマーティン・バレは、目立たないけど、
というかイアンだけが目立つようにしているんでしょうけど(笑)、
手堅い中にもアグレッシブさを失わない部分があって、
僕が大好きなギタリストの1人です。
Tr3:Cheap Day Return
インストの1分少々しかないつなぎのトラッド風小品。
Tr4:Mother Goose
アコースティック弾き語りの後ろでフルートが小躍りする、
跳ねたリズムのちょっとかわいらしい曲。
それもそのはず、「マザー・グース」。
でも、直接的にマザーグースの話から取っているのではないようで、
そういう楽しさ、寓意を基に言葉遊びしつつ情景描写している感じ。
いかにも英国小市民的な曲ですが、そういうのが好きなんです。
トラッド風小品が多い中、この曲はそれ系では目玉でしょう。
朝の雰囲気、サンドイッチが食べたくなってくる(笑)。
Tr5:Wond'ring Aloud
前の曲から続いたやはり2分ないトラッド風小品。
こちらは歌もあって、小声でぶつぶつ歌っていますが、
意外なことに(笑)、恋の喜びを軽く歌っています。
ここまでの歌詞がある4曲中3曲にSunという単語が出てきますが、
それがみな、「英国の冷たい太陽」っぽい感じがします。
行ったことはないけど・・・
Tr6:Up To Me
LPではA面の最後、ここでまた音が重くなります。
フルートとベースによる明確なブルーズ風のリフがあって、
これがカッコよく、気持ちをぐいぐいと前に押してくれますが、
前の曲が緩かっただけにこの効果は満点。
曲の並べ方にメリハリがあるのは、アルバムとして素晴らしい。
それにしても、フルートという一見すると「ロックではない」楽器が、
実はこんなにもロックしているなんて、と、ちょっと驚く佳曲。
04 蒸気機関車の絵が入ったメモ帳とタル・・・

Tr7:My God
そういえば教会にいるような雰囲気。
ハンマーで叩きつけるような重たいギターリフに、
なんといっても聴きどころは、中間部のフルートのソロ。
掛け声のようなある種不気味なコーラスをバックに繰り広げられ、
イアンは、フルートを吹きながら自分でも掛け声を出していて、
ちょっと危なくて恐い、スリリングな展開に引き込まれます。
フルートソロの途中に、クリスマスソングでおなじみの
God Rest Ye, Merry Gentlemanの旋律も織り込まれています。
ああ、そうか、Godつながりか・・・(笑)・・・
ある意味このアルバムの白眉ですね。
Tr8:Hymn 43
そして実際に「賛美歌43番」とくる流れがいい。
雰囲気がぱっと明るくなり、リフを刻むギターも少し軽い音に。
そのリフがTr6に似ているのは、トータルアルバムとしての意識でしょう。
しかし賛美歌だけど熱唱しているのがまた面白い。
Tr9:Slipstream
イントロなしに優しげに歌い始める1分強のトラッド小品。
これも朝の雰囲気、というか、このアルバムは、
重い曲でもみんな朝の雰囲気がします。
しかも、まだ多くの人が寝ている朝の時間帯。
Tr10:Locomotive Breath
邦題「蒸気機関車のあえぎ」。
ロックの「てっちゃんソング」の筆頭格でしょうね(笑)。
タルの中でも屈指の名曲、人気曲。
シングルとしてもTop10入りするヒットになりました。
いかにも力強く前進するようなギターリフに導かれる曲、
そしてギターをミュートして出す「カッカッ」という音は、
まさに蒸気機関車のイメージにぴったり!
そうそうこの「カッカッ」というギターの音も、Tr8で一度伏線として
出てきている辺り、やはりかなり練られていますね。
まあ、こういう曲があるだけでもうれしいんですが(笑)。
タルはそれと、このように、言葉の感覚が独特で面白いですね!
Tr11:Wind Up
ラストは、前の曲の余韻を受け、ピアノで静かに始まり、
イアンがつぶやくように囁くように告白するように歌い出す。
なんだか思わせぶりだなと聴いていると楽器が少しずつ増え、
エレクトリック・ギターのフレーズを契機にアップテンポになり、
アルバムでもいちばんのノリの中で曲がぐいぐい進む。
そして最後はまた放り投げるように静かにピアノと歌で締める。
いかにもショーの最後という感じの開放感ある曲で、ノリ的には、
ドリフのコントの最後にかかる音楽っぽい感じもします(笑)。
この曲こそ、この人たちはへそ曲がりなだけじゃない、
そりゃ確かに見てくれはそうだけど(笑)、基本としては、
ちゃんとエンターテイメント性を考えている人たちなんだと気づき、
「この人たちの音楽は聴きやすい」と感じた曲でした。
予定調和というのは、ロックの中にも確かにあるんですよね。
それを否定すると、音楽の楽しさは半減するかもしれないことは、
この曲を聴いた気持ちよさが証明してくれていると思います。
だけどやっぱり、この終わり方は、癖になるなぁ(笑)。
なお、現行のリマスター盤には、
6「曲」のボーナストラックが入っていますが、
それらのボーナスもこのアルバムのイメージが踏襲されていて、
特にTr12:Lick Your Fingers Cleanは、
最初はボーナスだと分からないくらいTr11とうまくつながっています。
ただ、ただし・・・
このアルバム、現在のリマスター盤には、
とても大きな不満があります。
Tr14に、イアン・アンダーソンのインタビューが入っているんです。
CDなので飛ばして聴けばいいのでしょうけど、でも僕は、
一度かけたら飛ばしたくない性分だし、うちの連装CDで
ずっとかけ続ける場合はそれがちょっと邪魔になります。
しかも、最後じゃないのがまた引っかかります。
それと、音が異様に小さいのも、通しで聴くとつらい部分ですが、
これはさほど問題でもないでしょうか。
ジェスロ・タルという名前は何かというと、
17世紀から18世紀にかけてを生きた英国の農政学者の名前です。
これまた変わったところから名前をつけてますよね(笑)。
しかし、彼らの音楽を聴いてみると、その名前に込めた思いが
なんとなく透けて見えるのがまた面白いです。
ちなみに、ジャケットの不思議なおじさんの絵は、
その農政学者でもイアン・アンダーソンでもなく、
「公園にいたただのおじさん」だそうで・・・
ひとつ余談を。
僕は、1996年に刊行されたロックのディスコグラフィーの本を
傍らに常に置いていて、それを見ながら記事も書いていますが、
その本は、個人名については、ファミリーネーム順で並んでいます。
Bob Dylanは「B」ではなく「D」のところにあるという具合に。
ある日、Jethro Tullをその本で探している時に、
バンド名が個人名なので、「T」のところを探していて、
何度探しても該当する部分にないので、あれ、おかしいな・・・
と思ったら、この場合は別にメンバーの名前でもないし、
素直に「J」を探せばいいんだ、と気づきました(笑)。
そうそう、Jethro Tullも略すと「JT」になりますが、
それではJames Taylorと区別がつかなくなるので、
僕はタルと呼んで書いています(笑)。
というか、それがファンの間では一般的だと思いますが・・・(笑)。
ジェスロ・タルは、凝りだすと止まらないですよ!
2014年02月07日
FOREVERLY エヴァリー・ブラザースに捧ぐ
01
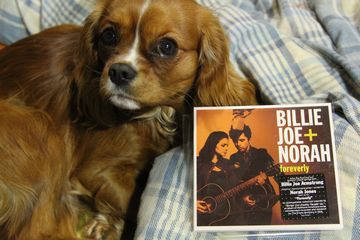
FOREVERLY Billie Joe Armstrong+Norah Jones
フォーエヴァリー
ビリー・ジョー・アームストロング+ノラ・ジョーンズ (2013)
少し前の話、今年に入って、
エヴァリー・ブラザース The Everly Brothers
のフィル(フィリップ)・エヴァリーが亡くなりました。
先ずはBarksからの引用記事です。
☆
エヴァリー・ブラザース、弟フィルが死去
エヴァリー・ブラザーズのフィル・エヴァリーが金曜日(1月3日)、
慢性閉塞肺疾患のため亡くなった。74歳だった。
妻パティによると、長年に渡る喫煙が原因だったという。
『Los Angeles Times』紙に訃報を伝えた彼女は
「私たちは悲嘆に暮れています。彼は長い間、懸命に戦ってきました」
と話した。
ミュージシャンの父、アイク・エヴァリーと共に
幼いときからステージに立っていたドン&フィル兄弟は、
1956年にエヴァリー・ブラザーズとして1stシングルをリリース。
続く「Bye Bye Love」「Wake Up Little Susie」(1957年)が
世界中で大ヒットした。
その後も「Cathy’s Clown」「When Will I Be Loved」
「All I Have To Do Is Dream」「Bird Dog」「Walk Right Back」
などのヒット曲を生み、1986年に<Rock and Roll Hall of Fame>
が創設した際には殿堂入りする初の10アーティストの1組に選ばれた。
数々のミュージシャンに影響を与えた彼らを『Rolling Stone』誌は
「ロック界で最も重要なヴォーカル・デュオ」と称えている。
ニール・ヤング、ポール・マッカートニー、キース・リチャーズ、
サイモン&ガーファンクル、ビーチ・ボーイズ、
レッド・ホット・チリ・ペッパーズのアンソニー・キーディスなど
ミュージシャンの間でもエヴァリー・ブラザーズのファンは多く、最近では、
グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロングとノラ・ジョーンズが、
エヴァリー・ブラザーズの1958年のアルバム
『Songs For Our Daddy Taught Us』のカバー・アルバム
『Foreverly』をリリースしたばかりだった。
合掌。
☆
エヴァリー・ブラザースは、ビートルズを聴き始めた頃に
その名前を知りました。
引用文でもあるように、ポール・マッカートニーが大好きであり、
ジョン・レノンとポールはエヴァリーのようになりたかった、
といった話を本で読んだりラジオで聞いたりしていました。
(ポール・マッカートニー&)ウィングスのLet'em Inの歌詞にある
"Phil & Don"とはまさにエヴァリーの2人のこと。
なお、ドンが兄だけどこの歌詞ではフィルが先になっているのは、
前の節の"Brother John"の"John"と韻を踏むためだと思われます。
その"Brother John"とは誰のことかは、言わずもがなですね。
同様にエヴァリーから影響を受けた「兄弟」がサイモン&ガーファンクル。
S&G最後のアルバム「明日に架ける橋」には、エヴァリーの
Bye Bye Loveをライヴで収録したヴァージョンが入っていますが、
僕が初めてそれと意識して聴いたエヴァリーの曲がそれでした。
その曲はジョージ・ハリスンもカヴァーしていますが、当時の
荒んだ心を反映してかマイナー調に転じた重たい曲になっています。
ちなみに、ウィキペディアによれば
「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」
において第90位(その話題の記事はこちら)であり、
偉大な100人のシンガーの中では、唯一、兄弟でランクインし、
「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」
において第33位にランクインしている、とのこと。
しかし、いつかエヴァリーを聴いてみたい、という思いを抱きながら、
僕が初めて自分のお金でレコードを買って彼らの音楽を聴いたのは、
中学時代から20年以上経った2003年頃、もちろんCDでのことでした。
僕が買ったベスト盤は今は廃盤のようですが、これは
収録曲内容がそれに近い別のベスト盤です。
最初に聴いて思ったこと。
ビートルズとオールディーズの中間の音楽ってやっぱりあったんだ。
このオールディーズとは、エルヴィス・プレスリーも含め、
Rock Around The ClockやBlue Suede Shoesのような
ロックンロール創生期の音楽のことを指して言っていますが、
以前は古い音楽をあまり聴かなかった僕は、それらの音楽があって、
いきなりビートルズに進化したものだと思い込んでいました。
でも、生物だって5本指の馬がいきなり1本指になったのではなく、
その中間段階がいたことが化石などかわ分かっているように、
音楽だって、その間がちゃんとあったんだ、ということ。
ビートルズがカンブリア紀の大爆発ではなかったのだと。
エヴァリーの音楽は、カントリーっぽいけどカントリーではなく、でも
ロックというほどまだ硬くない、しかし一級のポップスという音楽です。
爾来、編集盤やボックスセットなどを買って時々聴いています。
02 エヴァリー・シスターズ(!?)

昨年11月、ノラ・ジョーンズが、グリーン・デイの
ビリー・ジョー・アームストロングと組んだアルバムが出ました。
FOREVERLYというタイトル、辞書には載っていない単語ですが、
エヴァリー・ブラザースの曲を2人で歌ったアルバムで、
「エヴァリーのために」という"for""everly"と
"forever"とかけた造語でしょう。
引用文にあるようにエヴァリーのアルバムを「底本」として
まるごと歌ったものであり、今回はそのアルバムを取り上げて、
フィル・エヴァリーを偲ぶ記事とさせていただきます。
ノラ・ジョーンズは大好きだからもちろんすぐに買って聴きましたが、
記事にするのが遅れ、そうこうしているうちにフィルが亡くなりました。
このタイミングははきっと単なる偶然だと思われますが、でも、
それにしてもというタイミングではあり、ノラも驚いたことでしょう。
そしてもちろん、悲しいという記事をFacebookで上げていました。
記事にするのが遅れた理由。
先に謝っておきます、ファンのかた、ごめんなさい。
僕はグリーン・デイが、ビリー・ジョー・アームストロングが
苦手なのです・・・
嫌い、と書くと過剰反応する方がいらっしゃるかと思いますが、でも
彼らの音楽というよりは、彼の歌い方が生理的に僕はだめなのです。
グリーン・デイは、MTVをよく見ていた1990年代にいつも流れていて、
アルバムは聞いていないけど曲をある程度聴いた上での話だから
食わず嫌いというわけではなく、また生理的にダメというのは
やっぱりどうしようもない、と自己弁護させていただきます。
それでもグリーン・デイの音楽自体は割といいと思い、特に
When I Come Aroundは、MTVで観て聴いて
ギターでコピーしていたくらいで、ブックオフで見る度に買って
聴いてみようと何度も思ってきましたが、やはり手を出せない。
だから今回、大好きなノラの新譜が出るのはうれしいけれど、
よりによって一緒の歌っているのがあの人かい、と・・・
でも聴くと、あれっ!?
ビリー・ジョー・アームストロングの歌い方が普通だ。
そうなんです、変な顔で熱く歌うという僕が知った彼ではないのです。
声も普通にいい、聴けないなんてことはまったくない。
ただ、普通に歌うと普通すぎてあまり特徴がない声かも、とは思い、
だからグリーン・デイではああいう歌い方をするのかもしれない、とも。
「底本」となったのは、SONGS OUR DADDY TAUGHT US、
「父が僕らに教えてくれた歌」というタイトルであり、
トラディショナル・ソングを歌ったものです。
そのアルバムを僕は持っていないのですが、幸いなことに、
THE COMPLETE CADENCE RECORDINGS 1957-1960
という2枚組の編集盤にそのアルバムが丸ごと収録されており、
先ずはオリジナルを聴いて短くまとめて書きます。
これがそのCADENCE RECORDINGS。
余談ですが、このジャケットの2人の衣装、なんとなく
「スター・トレック」の宇宙船のクルーのような感じが・・・
父に教わったということですが、EBの2人の父親が音楽家であり、
2人は音楽が周りにあふれる子ども時代を送ったのでしょう。
2人のハーモニーは、そうして培った音楽的素養から成り立っている、
と考えると納得できます。
そしてこのアルバムを作ったのは、父のおかげでデビューできて
人気者になれた、その恩返しとも受け取れます。
エヴァリーの歌い方は力は入っても決して熱くならないというスタイルで、
そこが後のロックとは大きく違う部分ですが、熱くならないということは
理知的で説得力がある、ということにもなります。
(熱くて説得力がある人もたくさんいますが)。
だから、ロックに慣れた人にはおとなしすぎると感じるかもしれない。
ただし、その涼しさから寂しさや悲しさがにじみ出ていて、
そこが聴く者の胸を打つ、ある意味ソウルです。
やはり声は持って生まれた部分が大きいように思いますが、
ポールもジョンもS&Gも、人の心を動かす彼らの歌い方を
見習って自分たちのののにしたかったのでしょう。
03 家、それもこのアルバムのテーマ

ビリー・ジョーとノラは、オリジナルの12曲すべて取り上げていますが、
曲順を変えています。
流れを考えたのでしょう、そのことは曲の話の中で触れます。
気になるのは、オリジナルのエヴァリーは男2人で歌っていますが、
ビリー・ジョーとノラは男性と女性という組み合わせ。
でも、エヴァリーを聴くと、片方が、知らない人が女性かと思うくらい
高い声で歌うので、ビリー・ジョーとノラも違和感はありません。
むしろノラのほうが声が低いんじゃないかな。
なお、ドンとフィルのどちらが高い声か、ずっと昔本を読んだはずが、
どちらがそうかは覚えておらず、分かりませんでした。
ただ、ビリー・ジョーとノラが男女で歌うことにより、
オリジナルとは違う感覚があります。
10代から20代前半の子どもを持ったお父さんとお母さん、
といった雰囲気に聴こえるのです。
特にノラの母性、これが聴きどころともいえます。
ノラは僕と干支が同じで一回り下だから、それくらいの年齢の
子どもがいても不思議ではないくらいですが、でも若いといえば若い。
その若さでこの母性、僕はそこに驚きました。
これはビリー・ジョーと、男性と歌ったことによる効果でしょう。
少なくとも彼女の普通の作品では感じなかったことです。
ノラはしかし、小さい頃からロック以前の古い音楽を聴きなじみ、
20代に出てきた当初から古い音楽の持つ感覚を自分のものとして
出せる人ではあったんだけど、そこに年齢を重ねることによる
味が出てきた、それが「母性」につながったのだと思います。
そもそも、ジャケット写真のノラ、1960年代のアメリカのドラマの
お母さん役の人みたいな雰囲気があります。
ノラだけではなくビリー・ジョーとの相乗効果と書きましたが、
ビリー・ジョーの歌い方も落ち着いていて、それも驚きました。
彼の声には、心配する、思いやる、という気持ちがよく表れています。
ビリー・ジョー・アームストロングは1972年生まれ、今年で44歳。
ウィキペディアで見ると、1994年に結婚して2児の父とのことで、
まさに10代のお子さんがいるお父さんであり、そのような今の
自分の気持ちが歌に表れたと考えるのは自然なことでしょう。
ただ、親としての気持ちを歌うことを通じて、
自分たちの青春時代も懐かしむようなところも感じられます。
自分たちはこうだった、こんなことはしないよう気をつけていた、
などなど、歌のイメージが二重にも三重にも膨らんでゆきます。
2人のハーモニーは、エヴァリーのように息がぴったりというよりは、
お互いが邪魔をしないように、しかしパートによりビリー・ジョーが
目立ったりノラだったり、といった感じで、これはこれで楽しめます。
このアルバムはトラディショナルを歌っただけに曲がシンプルであり、
だからこそこの2人のヴォーカルこそが最大の魅力といえるでしょう。
しかしもちろん、エヴァリーが歌うくらいだから、
歌メロがいい曲ばかりで、ついつい口ずさんでしまう。
音楽としては、僕が本当のカントリーを聴く前には
カントリーだと思っていた、というスタイルの音楽。
フォークとは少し違う、カントリーっぽさはある、といったところ。
歌い方はカントリーの影響を受けているのが感じられますが、
そもそもエヴァリーがそうだったから、当然のことでしょう。
エヴァリー同様生ギターを基本にした最小限のバンド形態、
時々ハーモニカやペダルスティールそれにフィドルなどが入る、
ほんとうに簡素なアレンジ、だから余計に歌が響いてくる。
ベースもアップライトベースだと思う、温かみがある音に聴こえます。
04

1曲目Roving Gambler
アメリカにはギャンブラーものの曲が多いですよね、脈々と続いている。
アコースティックギター弾き語りにハーモニカが入るおとなしい響き。
ビリー・ジョーはちゃんとレコードを聴いたことがないので、
普通に歌っている、以外は何も言えないけれど、
ノラは、旦那を立てる妻のような雰囲気もありますね。
2曲目Long Time Gone
歌メロが素直に好き。
Aメロの最後のタイトルの言葉を歌う前に声がすうーっと高くなる部分、
2人の息が合っていると感じる、ここが特にいい。
揺ら揺ら揺れるエレクトリックギターの間奏のソロがいい。
ピアノも低く入っていて、洒落たアレンジ。
3曲目Lightning Express
ちょっと悲しげで寂しげなワルツ、でもタイトルは「稲妻急行」。
ビリー・ジョーにはキーが高いのか、ここはノラの声が目立つ。
ブルーグラス風のギターが2人の声を柔らかく包み込む。
この曲を僕は3回目くらいからもう口ずさんでいました。
4曲目Silver Haired Daddy Of Mine
アップテンポで少し元気になる。
Bye Bye Loveを明るくしたような響き、或いは、ビートルズの
Don't Pass Me Byをアップテンポにしたような感じかな。
僕が「カントリーを聴く前にカントリーだと思っていた音楽」の代表。
この歌メロはどこかで聴いたことがあるような感じもします。
ノラの拗ねて甘えるような歌い方が今回は少なくて残念だけど、
ここではビリー・ジョーの向こうにそれが聴こえてほっとする。
4曲目まではオリジナルと曲順が同じです。
5曲目Down In The Willow Garden
オリジナルでは9曲目。
ブルーズ風のエレクトリックギターで始まる重たい響きの曲。
ワルツで、やはり揺ら揺らするギターの音色ともども、
ちょっと恐い、夏に聴くとお化けを想像しそうな曲でもある。
そしてこれはノラが好きなディクシーランド・スタイルに近い。
6曲目Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?
この曲にこんなくだりがあります。
"Who's gonna kiss the ruby red lips"
遊び歌というか、なんだかイメージ膨らんできますよね。
異性への興味が強くなった10代の頃。
しかも男女で歌うと、健全な色っぽさを感じずにはいられない。
最初に聴いた時に引き込まれた曲。
05 今朝の太陽の暈、"halo"

7曲目Oh So Many Years
微妙にシャッフルした明るく軽快な曲。
前のおとなしいワルツが終わってすぐにはいるのがいい。
エレクトリックギターのソロが入るけどビリー・ジョーかな。
音はフェンダー系に聴こえるし。
ずっとおとなしくきた中でこのソロは簡単だけど効果的です。
8曲目Barbara Allen
ここで初めてコーラスではなくビリー・ジョーの独唱で始まる。
3コーラス目でノラが入ってくるけれど、これはビリー・ジョーの歌。
片田舎のバーでおじいさんが歌うと似合いそうなワルツで、
フィドルを前面に出し特にカントリーっぽさを強く感じる曲。
でも、何番まであるんだろう、「鉄道唱歌」並みとは言わないけれど、
同じ12小節を何度も繰り返して歌い継ぐ曲。
9曲目Rockin' Alone (In An Old Rockin' Chair)
イントロのちょっと寂しげなピアノ、讃美歌風の響き。
この辺がアメリカだなと思いますね。
この歌もワルツ、抑制が効いて、胸にしみてくる。
ここはノラの声がよく響いてきます。
10曲目I'm Here To Get My Baby Out Of Jail
今度はノラの独唱で始まり、曲が進むと楽器が増え、
ビリー・ジョーのコーラスが薄く入ってきます。
刑務所に入ってしまった子どもを思いやる母性を感じます。
そりゃ悪いことしたんだけど、子どもはかわいいのでしょう。
そういう複雑な気持ちがよく伝わってきます。
でも、こんなに歌が上手くて声がきれいなお母さんなんて・・・
とは思わない、大スターで唯一無二の声を持った人なのに、
ノラ・ジョーンズの庶民的感覚や人懐っこさを感じます。
僕が選ぶこのアルバムのベストトラックはこれですね。
まあ、ノラの声が前面に出ていることもあるんですが。
なお、エヴァリーのオリジナルではこの曲が最後ですが、
そうですね、最後にしては締まらないというか、
放り出されるような感じになるので、ここでよかったと思います。
11曲目Kentucky
ケンタッキーを離れたところで懐かしむ、郷愁を誘う曲。
自分が死んだら山に葬ってほしいと歌う。
落ち着いて歌うから、余計にノスタルジックに感じる。
この曲は逆にオリジナルでも11曲目で、最後の前に
思いをため込む、そんな感じがしていいですね。
12曲目Put My Little Shoes Away
最後も教会音楽風のゆったりとした荘厳さもある曲。
すべての思いをまとめさらに高みに運ぶような心にしみる響き。
最後ぷっつりと歌が終わってしまうのですが、でも、
そこまでの余韻を心の中に解放してくれるように感じます。
なおこのCDは、ビリー・ジョー・アームストロングとグリーン・デイの
レコード会社であるRepriseからのリリースとなっており、
日本ではワーナー・ミュージック・ジャパンから発売されています。
名義も「ビリー・ジョー+ノラ」となっていて、つまりは
ノラというよりはビリー・ジョーのアルバムということなのかもしれない。
このアルバムは、エヴァリー・ブラザースの歌心や歌への思いを
決して熱くなりすぎず、敬意を込めて表しています。
これがエヴァリーのヴォーカルのスタイルではあります。
ただ、曲についていえば、「オールディーズとビートルズの間」の
スタイルには達していません、そうですよねトラッドだから。
実際、エヴァリーの先述の編集盤を聴いていると、オリジナルの
このアルバムに該当する部分の後ろに出てくる彼らのオリジナルの
ヒット曲を聴くと、より複雑になり、新しく感じられます。
でも、トラッドのエヴァリーを今の時代に取り上げることで、
彼らの音楽の世界の広さや深さを感じられることでしょう。
さて、このアルバム、ノラ・ジョーンズの割には
あまり話題になっていないような気がします。
確かに、特にノラの異様にポップな最新作に比べると地味だし、
ビリー・ジョーはグリーン・デイが日本で人気があるにしても、
こういうこともやるのか、という受け止められ方かもしれない。
そもそもアートワークも地味ですかね。
おまけにエヴァリーが日本でどれだけ聴かれているのか、と。
でも、純粋に音楽として、歌として素晴らしい。
ノラ・ジョーンズの音楽への思い、また新たな展開を見せてくれて
ファンとしてはうれしいし楽しいですね。
そして。
そうだな、グリーン・デイもそろそろ聴いてみるかな。
06

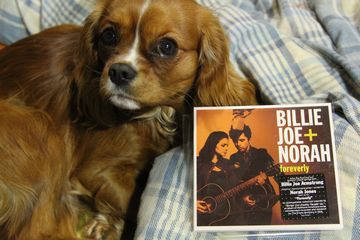
FOREVERLY Billie Joe Armstrong+Norah Jones
フォーエヴァリー
ビリー・ジョー・アームストロング+ノラ・ジョーンズ (2013)
少し前の話、今年に入って、
エヴァリー・ブラザース The Everly Brothers
のフィル(フィリップ)・エヴァリーが亡くなりました。
先ずはBarksからの引用記事です。
☆
エヴァリー・ブラザース、弟フィルが死去
エヴァリー・ブラザーズのフィル・エヴァリーが金曜日(1月3日)、
慢性閉塞肺疾患のため亡くなった。74歳だった。
妻パティによると、長年に渡る喫煙が原因だったという。
『Los Angeles Times』紙に訃報を伝えた彼女は
「私たちは悲嘆に暮れています。彼は長い間、懸命に戦ってきました」
と話した。
ミュージシャンの父、アイク・エヴァリーと共に
幼いときからステージに立っていたドン&フィル兄弟は、
1956年にエヴァリー・ブラザーズとして1stシングルをリリース。
続く「Bye Bye Love」「Wake Up Little Susie」(1957年)が
世界中で大ヒットした。
その後も「Cathy’s Clown」「When Will I Be Loved」
「All I Have To Do Is Dream」「Bird Dog」「Walk Right Back」
などのヒット曲を生み、1986年に<Rock and Roll Hall of Fame>
が創設した際には殿堂入りする初の10アーティストの1組に選ばれた。
数々のミュージシャンに影響を与えた彼らを『Rolling Stone』誌は
「ロック界で最も重要なヴォーカル・デュオ」と称えている。
ニール・ヤング、ポール・マッカートニー、キース・リチャーズ、
サイモン&ガーファンクル、ビーチ・ボーイズ、
レッド・ホット・チリ・ペッパーズのアンソニー・キーディスなど
ミュージシャンの間でもエヴァリー・ブラザーズのファンは多く、最近では、
グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロングとノラ・ジョーンズが、
エヴァリー・ブラザーズの1958年のアルバム
『Songs For Our Daddy Taught Us』のカバー・アルバム
『Foreverly』をリリースしたばかりだった。
合掌。
☆
エヴァリー・ブラザースは、ビートルズを聴き始めた頃に
その名前を知りました。
引用文でもあるように、ポール・マッカートニーが大好きであり、
ジョン・レノンとポールはエヴァリーのようになりたかった、
といった話を本で読んだりラジオで聞いたりしていました。
(ポール・マッカートニー&)ウィングスのLet'em Inの歌詞にある
"Phil & Don"とはまさにエヴァリーの2人のこと。
なお、ドンが兄だけどこの歌詞ではフィルが先になっているのは、
前の節の"Brother John"の"John"と韻を踏むためだと思われます。
その"Brother John"とは誰のことかは、言わずもがなですね。
同様にエヴァリーから影響を受けた「兄弟」がサイモン&ガーファンクル。
S&G最後のアルバム「明日に架ける橋」には、エヴァリーの
Bye Bye Loveをライヴで収録したヴァージョンが入っていますが、
僕が初めてそれと意識して聴いたエヴァリーの曲がそれでした。
その曲はジョージ・ハリスンもカヴァーしていますが、当時の
荒んだ心を反映してかマイナー調に転じた重たい曲になっています。
ちなみに、ウィキペディアによれば
「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」
において第90位(その話題の記事はこちら)であり、
偉大な100人のシンガーの中では、唯一、兄弟でランクインし、
「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」
において第33位にランクインしている、とのこと。
しかし、いつかエヴァリーを聴いてみたい、という思いを抱きながら、
僕が初めて自分のお金でレコードを買って彼らの音楽を聴いたのは、
中学時代から20年以上経った2003年頃、もちろんCDでのことでした。
僕が買ったベスト盤は今は廃盤のようですが、これは
収録曲内容がそれに近い別のベスト盤です。
最初に聴いて思ったこと。
ビートルズとオールディーズの中間の音楽ってやっぱりあったんだ。
このオールディーズとは、エルヴィス・プレスリーも含め、
Rock Around The ClockやBlue Suede Shoesのような
ロックンロール創生期の音楽のことを指して言っていますが、
以前は古い音楽をあまり聴かなかった僕は、それらの音楽があって、
いきなりビートルズに進化したものだと思い込んでいました。
でも、生物だって5本指の馬がいきなり1本指になったのではなく、
その中間段階がいたことが化石などかわ分かっているように、
音楽だって、その間がちゃんとあったんだ、ということ。
ビートルズがカンブリア紀の大爆発ではなかったのだと。
エヴァリーの音楽は、カントリーっぽいけどカントリーではなく、でも
ロックというほどまだ硬くない、しかし一級のポップスという音楽です。
爾来、編集盤やボックスセットなどを買って時々聴いています。
02 エヴァリー・シスターズ(!?)

昨年11月、ノラ・ジョーンズが、グリーン・デイの
ビリー・ジョー・アームストロングと組んだアルバムが出ました。
FOREVERLYというタイトル、辞書には載っていない単語ですが、
エヴァリー・ブラザースの曲を2人で歌ったアルバムで、
「エヴァリーのために」という"for""everly"と
"forever"とかけた造語でしょう。
引用文にあるようにエヴァリーのアルバムを「底本」として
まるごと歌ったものであり、今回はそのアルバムを取り上げて、
フィル・エヴァリーを偲ぶ記事とさせていただきます。
ノラ・ジョーンズは大好きだからもちろんすぐに買って聴きましたが、
記事にするのが遅れ、そうこうしているうちにフィルが亡くなりました。
このタイミングははきっと単なる偶然だと思われますが、でも、
それにしてもというタイミングではあり、ノラも驚いたことでしょう。
そしてもちろん、悲しいという記事をFacebookで上げていました。
記事にするのが遅れた理由。
先に謝っておきます、ファンのかた、ごめんなさい。
僕はグリーン・デイが、ビリー・ジョー・アームストロングが
苦手なのです・・・
嫌い、と書くと過剰反応する方がいらっしゃるかと思いますが、でも
彼らの音楽というよりは、彼の歌い方が生理的に僕はだめなのです。
グリーン・デイは、MTVをよく見ていた1990年代にいつも流れていて、
アルバムは聞いていないけど曲をある程度聴いた上での話だから
食わず嫌いというわけではなく、また生理的にダメというのは
やっぱりどうしようもない、と自己弁護させていただきます。
それでもグリーン・デイの音楽自体は割といいと思い、特に
When I Come Aroundは、MTVで観て聴いて
ギターでコピーしていたくらいで、ブックオフで見る度に買って
聴いてみようと何度も思ってきましたが、やはり手を出せない。
だから今回、大好きなノラの新譜が出るのはうれしいけれど、
よりによって一緒の歌っているのがあの人かい、と・・・
でも聴くと、あれっ!?
ビリー・ジョー・アームストロングの歌い方が普通だ。
そうなんです、変な顔で熱く歌うという僕が知った彼ではないのです。
声も普通にいい、聴けないなんてことはまったくない。
ただ、普通に歌うと普通すぎてあまり特徴がない声かも、とは思い、
だからグリーン・デイではああいう歌い方をするのかもしれない、とも。
「底本」となったのは、SONGS OUR DADDY TAUGHT US、
「父が僕らに教えてくれた歌」というタイトルであり、
トラディショナル・ソングを歌ったものです。
そのアルバムを僕は持っていないのですが、幸いなことに、
THE COMPLETE CADENCE RECORDINGS 1957-1960
という2枚組の編集盤にそのアルバムが丸ごと収録されており、
先ずはオリジナルを聴いて短くまとめて書きます。
これがそのCADENCE RECORDINGS。
余談ですが、このジャケットの2人の衣装、なんとなく
「スター・トレック」の宇宙船のクルーのような感じが・・・
父に教わったということですが、EBの2人の父親が音楽家であり、
2人は音楽が周りにあふれる子ども時代を送ったのでしょう。
2人のハーモニーは、そうして培った音楽的素養から成り立っている、
と考えると納得できます。
そしてこのアルバムを作ったのは、父のおかげでデビューできて
人気者になれた、その恩返しとも受け取れます。
エヴァリーの歌い方は力は入っても決して熱くならないというスタイルで、
そこが後のロックとは大きく違う部分ですが、熱くならないということは
理知的で説得力がある、ということにもなります。
(熱くて説得力がある人もたくさんいますが)。
だから、ロックに慣れた人にはおとなしすぎると感じるかもしれない。
ただし、その涼しさから寂しさや悲しさがにじみ出ていて、
そこが聴く者の胸を打つ、ある意味ソウルです。
やはり声は持って生まれた部分が大きいように思いますが、
ポールもジョンもS&Gも、人の心を動かす彼らの歌い方を
見習って自分たちのののにしたかったのでしょう。
03 家、それもこのアルバムのテーマ

ビリー・ジョーとノラは、オリジナルの12曲すべて取り上げていますが、
曲順を変えています。
流れを考えたのでしょう、そのことは曲の話の中で触れます。
気になるのは、オリジナルのエヴァリーは男2人で歌っていますが、
ビリー・ジョーとノラは男性と女性という組み合わせ。
でも、エヴァリーを聴くと、片方が、知らない人が女性かと思うくらい
高い声で歌うので、ビリー・ジョーとノラも違和感はありません。
むしろノラのほうが声が低いんじゃないかな。
なお、ドンとフィルのどちらが高い声か、ずっと昔本を読んだはずが、
どちらがそうかは覚えておらず、分かりませんでした。
ただ、ビリー・ジョーとノラが男女で歌うことにより、
オリジナルとは違う感覚があります。
10代から20代前半の子どもを持ったお父さんとお母さん、
といった雰囲気に聴こえるのです。
特にノラの母性、これが聴きどころともいえます。
ノラは僕と干支が同じで一回り下だから、それくらいの年齢の
子どもがいても不思議ではないくらいですが、でも若いといえば若い。
その若さでこの母性、僕はそこに驚きました。
これはビリー・ジョーと、男性と歌ったことによる効果でしょう。
少なくとも彼女の普通の作品では感じなかったことです。
ノラはしかし、小さい頃からロック以前の古い音楽を聴きなじみ、
20代に出てきた当初から古い音楽の持つ感覚を自分のものとして
出せる人ではあったんだけど、そこに年齢を重ねることによる
味が出てきた、それが「母性」につながったのだと思います。
そもそも、ジャケット写真のノラ、1960年代のアメリカのドラマの
お母さん役の人みたいな雰囲気があります。
ノラだけではなくビリー・ジョーとの相乗効果と書きましたが、
ビリー・ジョーの歌い方も落ち着いていて、それも驚きました。
彼の声には、心配する、思いやる、という気持ちがよく表れています。
ビリー・ジョー・アームストロングは1972年生まれ、今年で44歳。
ウィキペディアで見ると、1994年に結婚して2児の父とのことで、
まさに10代のお子さんがいるお父さんであり、そのような今の
自分の気持ちが歌に表れたと考えるのは自然なことでしょう。
ただ、親としての気持ちを歌うことを通じて、
自分たちの青春時代も懐かしむようなところも感じられます。
自分たちはこうだった、こんなことはしないよう気をつけていた、
などなど、歌のイメージが二重にも三重にも膨らんでゆきます。
2人のハーモニーは、エヴァリーのように息がぴったりというよりは、
お互いが邪魔をしないように、しかしパートによりビリー・ジョーが
目立ったりノラだったり、といった感じで、これはこれで楽しめます。
このアルバムはトラディショナルを歌っただけに曲がシンプルであり、
だからこそこの2人のヴォーカルこそが最大の魅力といえるでしょう。
しかしもちろん、エヴァリーが歌うくらいだから、
歌メロがいい曲ばかりで、ついつい口ずさんでしまう。
音楽としては、僕が本当のカントリーを聴く前には
カントリーだと思っていた、というスタイルの音楽。
フォークとは少し違う、カントリーっぽさはある、といったところ。
歌い方はカントリーの影響を受けているのが感じられますが、
そもそもエヴァリーがそうだったから、当然のことでしょう。
エヴァリー同様生ギターを基本にした最小限のバンド形態、
時々ハーモニカやペダルスティールそれにフィドルなどが入る、
ほんとうに簡素なアレンジ、だから余計に歌が響いてくる。
ベースもアップライトベースだと思う、温かみがある音に聴こえます。
04

1曲目Roving Gambler
アメリカにはギャンブラーものの曲が多いですよね、脈々と続いている。
アコースティックギター弾き語りにハーモニカが入るおとなしい響き。
ビリー・ジョーはちゃんとレコードを聴いたことがないので、
普通に歌っている、以外は何も言えないけれど、
ノラは、旦那を立てる妻のような雰囲気もありますね。
2曲目Long Time Gone
歌メロが素直に好き。
Aメロの最後のタイトルの言葉を歌う前に声がすうーっと高くなる部分、
2人の息が合っていると感じる、ここが特にいい。
揺ら揺ら揺れるエレクトリックギターの間奏のソロがいい。
ピアノも低く入っていて、洒落たアレンジ。
3曲目Lightning Express
ちょっと悲しげで寂しげなワルツ、でもタイトルは「稲妻急行」。
ビリー・ジョーにはキーが高いのか、ここはノラの声が目立つ。
ブルーグラス風のギターが2人の声を柔らかく包み込む。
この曲を僕は3回目くらいからもう口ずさんでいました。
4曲目Silver Haired Daddy Of Mine
アップテンポで少し元気になる。
Bye Bye Loveを明るくしたような響き、或いは、ビートルズの
Don't Pass Me Byをアップテンポにしたような感じかな。
僕が「カントリーを聴く前にカントリーだと思っていた音楽」の代表。
この歌メロはどこかで聴いたことがあるような感じもします。
ノラの拗ねて甘えるような歌い方が今回は少なくて残念だけど、
ここではビリー・ジョーの向こうにそれが聴こえてほっとする。
4曲目まではオリジナルと曲順が同じです。
5曲目Down In The Willow Garden
オリジナルでは9曲目。
ブルーズ風のエレクトリックギターで始まる重たい響きの曲。
ワルツで、やはり揺ら揺らするギターの音色ともども、
ちょっと恐い、夏に聴くとお化けを想像しそうな曲でもある。
そしてこれはノラが好きなディクシーランド・スタイルに近い。
6曲目Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?
この曲にこんなくだりがあります。
"Who's gonna kiss the ruby red lips"
遊び歌というか、なんだかイメージ膨らんできますよね。
異性への興味が強くなった10代の頃。
しかも男女で歌うと、健全な色っぽさを感じずにはいられない。
最初に聴いた時に引き込まれた曲。
05 今朝の太陽の暈、"halo"

7曲目Oh So Many Years
微妙にシャッフルした明るく軽快な曲。
前のおとなしいワルツが終わってすぐにはいるのがいい。
エレクトリックギターのソロが入るけどビリー・ジョーかな。
音はフェンダー系に聴こえるし。
ずっとおとなしくきた中でこのソロは簡単だけど効果的です。
8曲目Barbara Allen
ここで初めてコーラスではなくビリー・ジョーの独唱で始まる。
3コーラス目でノラが入ってくるけれど、これはビリー・ジョーの歌。
片田舎のバーでおじいさんが歌うと似合いそうなワルツで、
フィドルを前面に出し特にカントリーっぽさを強く感じる曲。
でも、何番まであるんだろう、「鉄道唱歌」並みとは言わないけれど、
同じ12小節を何度も繰り返して歌い継ぐ曲。
9曲目Rockin' Alone (In An Old Rockin' Chair)
イントロのちょっと寂しげなピアノ、讃美歌風の響き。
この辺がアメリカだなと思いますね。
この歌もワルツ、抑制が効いて、胸にしみてくる。
ここはノラの声がよく響いてきます。
10曲目I'm Here To Get My Baby Out Of Jail
今度はノラの独唱で始まり、曲が進むと楽器が増え、
ビリー・ジョーのコーラスが薄く入ってきます。
刑務所に入ってしまった子どもを思いやる母性を感じます。
そりゃ悪いことしたんだけど、子どもはかわいいのでしょう。
そういう複雑な気持ちがよく伝わってきます。
でも、こんなに歌が上手くて声がきれいなお母さんなんて・・・
とは思わない、大スターで唯一無二の声を持った人なのに、
ノラ・ジョーンズの庶民的感覚や人懐っこさを感じます。
僕が選ぶこのアルバムのベストトラックはこれですね。
まあ、ノラの声が前面に出ていることもあるんですが。
なお、エヴァリーのオリジナルではこの曲が最後ですが、
そうですね、最後にしては締まらないというか、
放り出されるような感じになるので、ここでよかったと思います。
11曲目Kentucky
ケンタッキーを離れたところで懐かしむ、郷愁を誘う曲。
自分が死んだら山に葬ってほしいと歌う。
落ち着いて歌うから、余計にノスタルジックに感じる。
この曲は逆にオリジナルでも11曲目で、最後の前に
思いをため込む、そんな感じがしていいですね。
12曲目Put My Little Shoes Away
最後も教会音楽風のゆったりとした荘厳さもある曲。
すべての思いをまとめさらに高みに運ぶような心にしみる響き。
最後ぷっつりと歌が終わってしまうのですが、でも、
そこまでの余韻を心の中に解放してくれるように感じます。
なおこのCDは、ビリー・ジョー・アームストロングとグリーン・デイの
レコード会社であるRepriseからのリリースとなっており、
日本ではワーナー・ミュージック・ジャパンから発売されています。
名義も「ビリー・ジョー+ノラ」となっていて、つまりは
ノラというよりはビリー・ジョーのアルバムということなのかもしれない。
このアルバムは、エヴァリー・ブラザースの歌心や歌への思いを
決して熱くなりすぎず、敬意を込めて表しています。
これがエヴァリーのヴォーカルのスタイルではあります。
ただ、曲についていえば、「オールディーズとビートルズの間」の
スタイルには達していません、そうですよねトラッドだから。
実際、エヴァリーの先述の編集盤を聴いていると、オリジナルの
このアルバムに該当する部分の後ろに出てくる彼らのオリジナルの
ヒット曲を聴くと、より複雑になり、新しく感じられます。
でも、トラッドのエヴァリーを今の時代に取り上げることで、
彼らの音楽の世界の広さや深さを感じられることでしょう。
さて、このアルバム、ノラ・ジョーンズの割には
あまり話題になっていないような気がします。
確かに、特にノラの異様にポップな最新作に比べると地味だし、
ビリー・ジョーはグリーン・デイが日本で人気があるにしても、
こういうこともやるのか、という受け止められ方かもしれない。
そもそもアートワークも地味ですかね。
おまけにエヴァリーが日本でどれだけ聴かれているのか、と。
でも、純粋に音楽として、歌として素晴らしい。
ノラ・ジョーンズの音楽への思い、また新たな展開を見せてくれて
ファンとしてはうれしいし楽しいですね。
そして。
そうだな、グリーン・デイもそろそろ聴いてみるかな。
06

2014年02月06日
PEARL ジャニス・ジョプリン
01

PEARL Janis Joplin
パール ジャニス・ジョプリン (1971)
今回はジャニス・ジョプリンです。
このところ単語ひとつのアルバムが2枚続き、次に用意している
アルバムも実はそうなのですが、しかし今回は、突然聴きたくなり
昔からよく聴いてきたこれがまたたまたま単語がひとつだから、
流れにのって勢いでこれを上げることにしました(笑)。
◇
1980年代、僕の世代では、ロックの伝説化が始まっていました。
ロックがただの流行や一時的な存在を超えた頃でしたが、
1970年から1971年にかけて相次いで亡くなった「3人のJ」、
ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソン
は、その中でもとりわけ光り輝く神話といえるほどの人たちでした。
もうひとつ、当時はそろそろロックが過去を振り返る頃になっていて、
ノスタルジーとともに伝説化が進行していた、今にしてそう思います。
ジャニス・ジョプリンの遺作であるこのアルバムは、
だから僕には、始めから伝説として存在していたものでした。
当時はロックのことをより知りたく、ラジオ、テレビ、本や雑誌
などのメディアで情報に接していました。
でも、今のようなネット社会ではないので、こと洋楽に関しては、
情報があふれるほどたくさんあるわけではなく、限られたもので、
しかもそれは生の情報というよりは、評論家や作家や関係者など
誰かの手によって表現されたものばかりでした。
今ここではそれについてどうこう言うつもりはありませんが、
そんな伝説化が進行する状況の中で洋楽好きの僕は育ちました。
単純な僕は、伝説化していた人やアルバムについて、
良くないと言うことすらいけないのかなと思っていました。
でもこれは、聴くとその通り素直に素晴らしいと感じました。
当たり前のことで、素晴らしいから伝説になったのであって、
伝説が決して作り上げられただけのものでもないということでしょう。
その後に聴いた70年代の名盤は、おしなべてそう感じたと同時に、
僕自身もとても気に入るようになったものばかりでした。
伝説だからといって押しつけられるものではなく、
あくまでも自分の耳で聴いて感じればそれでいいのだと思うと、
ロックの伝説に対して僕は構えずに楽しく聴けるようになりました。
ただし僕は、伝説としてすべてを美化するのはどうかなと思います。
クスリの問題をはじめいろいろな問題があったアーティストは多く、
そのどこを許せてどこは許せないかは人それぞれでしょうけど、
考えて感じる余地もないような伝説というのはどうなのだろう、と。
いずれにせよ、人は伝説を求めているというのはよく言われることで、
僕も、そうではないとは決して言わない、むしろそういう人間です。
このアルバムの話に戻って、僕が聴いて驚いたのは、
ジャニス・ジョプリンという伝説のヴォーカリストが、
意外と親しみやすい人だと感じたことです。
無防備なほどに感情を露わにして歌う姿に僕は、聴く前は
恐い人なのかなと勝手にイメージを作り上げていたのですが、
いざ聴くと、ユーモアもあって人間味あふれる人だと感じ、
他のアーティストよりもむしろ身近に感じました。
彼女にはかわいらしい面も多々あって、彼女はきっと
子どもの心を持ち続けていた人なのだろうなと。
でもやっぱりヴォーカルは凄いですね、上手いというより凄い。
唯一無二という言葉はまさに彼女のためにある、というか。
これがよかったのはもひとつ、ブルーズを基調としたロックであり、
最初に予想していたよりはずっとハードな音だったことでした。
これは僕が買ったCD最初の50枚に入るくらい早くに買いましたが、
僕は当時はレッド・ツェッペリンを夢中で聴いていた頃であり、
クリームを聴き始めたり、ビートルズのYer Bluesをコピーしたりで、
この系の音は僕のデフォルトなのかもしれません(笑)。
だからこのアルバムは素直に心に入ってきて大好きになりました。
さらにこのアルバムを聴いて、演奏がとにかく上手いと思いました。
このアルバムの演奏は、当時新たに結成されたバンド
フル・ティルト・ブギー The Full Tilt Boogieが担当していますが、
音がしっかりと出ていて、節目節目をびしっと決めて曲が進み、
こういうのを「タイトな演奏」というのだろうなと思いました。
ビートルズやローリング・ストーンズが下手とはいわないけれど、
この演奏は、僕がそれまで経験したことがないものだと感じました。
ギターのジョン・ティル John Tilはセミアコ系のギターを使っていて、
ブックレットにもギブソンのセミアコを持った写真がありますが、
厚みよりは広がり系の太いギターの音も当時の僕には新鮮でした。
このアルバムの録音中にジャニスは命を落としてしまったため、
一部の曲は必ずしも望んだ姿ではないようですが、それでも
当時の意欲とバンドのまとまり、時代の息吹が伝わってきます。
そして今や、時代を超えたアルバムの1枚となりました。
作曲者は曲名の下にブックレットにある通りに記します。
ただ、今回はオリジナルや作曲者のことにはほとんどに触れず、
あくまでも僕の思いを綴ってゆくことはどうかお許しください。
02 冬のパール、ツルアジサイのドライフラワー

Tr1:Move Over
(Janis Joplin)
ジャニス自身のペンによるパワフルな彼女の代名詞的な曲。
曲自体はひねりがなくストレートなだけに募る思いは最高潮に
まっすぐに伝わってきます。
ヴォーカルラインをなぞるギターもカッコいい。
今回、このアルバムを聴きたくなったきっかけがこの曲でした。
1989年に、クスリで命を落とした人の曲をカバーして
アンチドラッグ運動を盛り上げる目的のコンピレーションアルバム、
MAKE A DIFFERENSEが作られましたが、そこで
シンデレラ Cinderellaがこの曲をカバーしていたのを、
CDシングルの記事(こちら)で思い出したからです。
これは歌メロがいいので鼻歌で口ずさむようになりましたが、
そこで僕は、こちらもかつて一度記事にした(こちら)
「歌詞と歌い手の性の同一問題」について悩みました。
だって、♪ You know that I need a man と僕が歌うと、
意味が違ってくる恐れがあるじゃないですか(笑)。
でも、鼻歌で歌う時に"man"を"woman"に変えたところ、
それもなんだか妙にこっ恥ずかしかったのです。
まあ、鼻歌は誰に向けて歌うものでもないのだから、
僕はオリジナル通りに"man"で歌っています。
"woman"にすると音節がひとつ増えるのは違和感があるし。
なお、シンデレラのトム・キーファーは"woman"と歌っています。
あ、シンデレラといっても男性ですから(笑)。
Tr2:Cry Baby
(J. Ragovoy-B. Berns)
「ジャッジャッジャッ」と音を切るイントロが印象的。
音が止まってから声を絞り出して叫ぶジャニス。
この切り替えが絶妙で、最初に聴いて名盤だと確信しました。
ゆったりとしたワルツにジャニスが吠えまくります。
ところで、「クライベイビー」というギターのエフェクター、
音が歪んでもわっと広がるワウペダルの一種があります。
エリック・クラプトンがよく使っていたものですが、僕がそれを
知ったのはこの曲より後だったので、てっきり、その名前は、
この曲のイメージからつけられたのだと思い込んでいました。
でも、ジャニスの声はイメージぴったりだと思います。
「ナチュラル・クライベイビー・ヴォイス」、ですね(笑)。
Tr3:A Woman Left Lonely
(D. Penn - S. Oldham)
やはりずっと気持ちを張り詰め続けるのは大変かな。
アルバムでいちばん落ち着いた大人しい曲。
しっとりと歌おうとはしつつも、ジャニスはやはり
感情的に歌っていきます。
この曲はソウルだといわれればそうかもしれません。
Tr4:Half Moon
(J. Hall - J. Hall)
軽快にホップしスウィングするカントリー調の曲。
アルバムでいちばんのりがよくて体が自然と動く曲で、
アルバムの流れに変化をつける点でも効果的な曲。
そしてこれはギターやベースなど、歌以上に
演奏部分に反応して自然と口ずさむ曲です。
Tr5:Buried Alive In The Blues
(N.Graventies)
ジャニスが後にヴォーカルを入れる予定だったインストゥルメンタル曲。
彼女ならどんな歌メロを入れて叫んだのだろう。
「生きながらブルースに葬られて」という曲をこの時期に録音していた、
そう聞くと悲しいですが、曲はむしろ底抜けに明るく楽しい曲。
演奏だけのこの曲があるので、僕は余計に演奏を上手いと感じたのかも。
歌がないことでバンドメンバーのジャニスへの愛情をより強く感じます。
03 2011年2月6日、雲の風景

Tr6:My Baby
(J. Ragovoy - M. Shuman)
これは「一発芸」の典型というか、Aメロで大人しくしていて、
サビで大爆発、そのサビがとても素晴らしいという曲。
Tr7:Me And Bobby McGee
(K. Kristofferson - F. Foster)
60年代後半から、ウッドストックもあって「自由」を謳歌する曲が
増えましたが、でも、僕は、この曲を聴いて、「自由」って結局
誰にも分からなかったじゃないかな、と思ったりもします。
♪ Freedom is just another word for nothing left to lose
「自由ってつまりは何も失うものがないってことなのよ」
このくだりは素晴らしく、意味するところは重いですね。
クリス・クリストファソンの作曲によるこの曲は、
彼女で唯一、シングルが全米No.1に輝いた曲。
アメリカ音楽のよいエッセンスを凝縮して楽しく聴かせてくれる、
僕のようなポップファンにはうれしい曲でもあります。
最後にリズムがジャズっぽくなって全体が弾けるところを
天真爛漫に歌うジャニスには音楽的勘の良さを感じます。
この部分はとにかくカッコよく、感動的だし、それまでの僕が
味わったことがないスタイルの音楽でもありました。
最後の最後、まるで弦を擦るようなギターの音が起こって、
半ば強制終了的に曲が終わる、そのエンディングも見事。
このアルバムも僕は大学時代に目覚まし代わりにタイマーでかけて
毎朝聴いていましたが、ある日、最後まで聴き通せない日があって、
家を出なければいけない時間にこの曲がかかっていたのを、
CDを止めないでそのまま家を出たことがありました。
もちろんタイマーで止まるからなんですが、その時僕は、
あまりにも曲に気持ちが入りすぎていて、曲を途中で止めるのは
なんだか申し訳ない気がしたのでした。
そして、家を出る時に聞こえてきたこの曲がまた素敵に感動的で、
そう感じたのは旅情を誘う歌詞だからかもしれないですね。
ともあれ、僕には特に大切な曲のひとつです。
Tr8:Mercedes Benz
(J. Joplin - M. McClure)
デモだと思うのですが、ジャニスがアカペラで歌って
こんな曲をやりたいよってバンドに聴かせたんじゃないかな。
和やかで明るく楽しいその場の雰囲気が伝わってきて、なぜか、
ほんとうはそこから演奏がついて広がっていったのに残念とは
思わない、僕はそう感じます。
歌っていくとテンポが速くなってずれていくのがまた楽しい。
友達はポルシェに乗ってるから私はベンツが欲しいという
まことに他愛のない曲ですが、ジャニスが歌うと許せてしまう。
この曲はこのまま出たのがよかったのかもしれない。
演奏を加えなかった判断に拍手を送りたいです。
しかし、ブックレットを見ると、この曲は彼女の死の
わずか3日前に録音されていることが分かって、あらためて、
それはあまりにも突然に訪れたことに驚かざるを得ません。
Tr9:Trust Me
(B. Womack)
ボビー・ウーマックの曲で彼自身もアコースティック・ギター
で客演していますが、だからか、ギターの響きがきれいです。
♪ My love is like a sea, baby
愛した後に潮が引いてゆくような虚しさを感じる曲。
前の曲とはあまりにも世界観が違うような気がするのですが、
それらすべてがジャニスという人となりだったのでしょうね。
Tr10:Get It While You Can
(J. Ragovoy - M. Shuman)
このアルバムの曲名はみな人生訓のようですね。
まあ歌というのはそういうものかもしれないけど、
とりわけこのアルバムはそう感じます。
「愛は生きているうちに」という邦題がつけられましたが、
それは、当時のレコード会社の担当者の気持ちでしょう。
アルバムの最後は、彼女の明るいキャラクターからすると、
気持ち、しんみりしすぎかな、寂しくなってしまう曲。
でもそれも彼女の周りで携わってきた人たちの
素直な思いなのかもしれません。
リンクは左が2枚組レガシー・エディション、右が通常盤。
このアルバムは、34分強しかなくて実際に短いのですが、
聴くといつもあっっっという間に終わってしまいます。
もちろん曲が充実していて流れがいいからでしょうけど、
それはあたかも、彼女自身の生きざまの象徴であるかのように。
ジャニス・ジョプリンは周りの人に愛され、助けられながら
生きてきたんだなということがよく分かりますが、しかし彼女は、
しっかりと生きることを学ぶのは忘れていたのかもしれない。
今回聴いて、ふと、ジャニス・ジョプリンという女性は
どのように人を好きになって愛したのだろうって思いました。
伝記などを読めば事実は分かるのかもしれないけど、
僕は昔から、アーティストの私生活にはあまり興味がなく、
事実を知りたいと思ったことはほとんどありません。
でも、どういう風に好きになったのか、事実としてではなく、
普遍的な人間の営みのひとつとして、こうした歌を通して
人の思いに触れることは嫌いではありません。
このアルバムはどこをどう聴いても説得力があります。
そしてもちろん素晴らしい。
04

最後に、わが家の「パール対決」・・・(笑)・・・

PEARL Janis Joplin
パール ジャニス・ジョプリン (1971)
今回はジャニス・ジョプリンです。
このところ単語ひとつのアルバムが2枚続き、次に用意している
アルバムも実はそうなのですが、しかし今回は、突然聴きたくなり
昔からよく聴いてきたこれがまたたまたま単語がひとつだから、
流れにのって勢いでこれを上げることにしました(笑)。
◇
1980年代、僕の世代では、ロックの伝説化が始まっていました。
ロックがただの流行や一時的な存在を超えた頃でしたが、
1970年から1971年にかけて相次いで亡くなった「3人のJ」、
ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソン
は、その中でもとりわけ光り輝く神話といえるほどの人たちでした。
もうひとつ、当時はそろそろロックが過去を振り返る頃になっていて、
ノスタルジーとともに伝説化が進行していた、今にしてそう思います。
ジャニス・ジョプリンの遺作であるこのアルバムは、
だから僕には、始めから伝説として存在していたものでした。
当時はロックのことをより知りたく、ラジオ、テレビ、本や雑誌
などのメディアで情報に接していました。
でも、今のようなネット社会ではないので、こと洋楽に関しては、
情報があふれるほどたくさんあるわけではなく、限られたもので、
しかもそれは生の情報というよりは、評論家や作家や関係者など
誰かの手によって表現されたものばかりでした。
今ここではそれについてどうこう言うつもりはありませんが、
そんな伝説化が進行する状況の中で洋楽好きの僕は育ちました。
単純な僕は、伝説化していた人やアルバムについて、
良くないと言うことすらいけないのかなと思っていました。
でもこれは、聴くとその通り素直に素晴らしいと感じました。
当たり前のことで、素晴らしいから伝説になったのであって、
伝説が決して作り上げられただけのものでもないということでしょう。
その後に聴いた70年代の名盤は、おしなべてそう感じたと同時に、
僕自身もとても気に入るようになったものばかりでした。
伝説だからといって押しつけられるものではなく、
あくまでも自分の耳で聴いて感じればそれでいいのだと思うと、
ロックの伝説に対して僕は構えずに楽しく聴けるようになりました。
ただし僕は、伝説としてすべてを美化するのはどうかなと思います。
クスリの問題をはじめいろいろな問題があったアーティストは多く、
そのどこを許せてどこは許せないかは人それぞれでしょうけど、
考えて感じる余地もないような伝説というのはどうなのだろう、と。
いずれにせよ、人は伝説を求めているというのはよく言われることで、
僕も、そうではないとは決して言わない、むしろそういう人間です。
このアルバムの話に戻って、僕が聴いて驚いたのは、
ジャニス・ジョプリンという伝説のヴォーカリストが、
意外と親しみやすい人だと感じたことです。
無防備なほどに感情を露わにして歌う姿に僕は、聴く前は
恐い人なのかなと勝手にイメージを作り上げていたのですが、
いざ聴くと、ユーモアもあって人間味あふれる人だと感じ、
他のアーティストよりもむしろ身近に感じました。
彼女にはかわいらしい面も多々あって、彼女はきっと
子どもの心を持ち続けていた人なのだろうなと。
でもやっぱりヴォーカルは凄いですね、上手いというより凄い。
唯一無二という言葉はまさに彼女のためにある、というか。
これがよかったのはもひとつ、ブルーズを基調としたロックであり、
最初に予想していたよりはずっとハードな音だったことでした。
これは僕が買ったCD最初の50枚に入るくらい早くに買いましたが、
僕は当時はレッド・ツェッペリンを夢中で聴いていた頃であり、
クリームを聴き始めたり、ビートルズのYer Bluesをコピーしたりで、
この系の音は僕のデフォルトなのかもしれません(笑)。
だからこのアルバムは素直に心に入ってきて大好きになりました。
さらにこのアルバムを聴いて、演奏がとにかく上手いと思いました。
このアルバムの演奏は、当時新たに結成されたバンド
フル・ティルト・ブギー The Full Tilt Boogieが担当していますが、
音がしっかりと出ていて、節目節目をびしっと決めて曲が進み、
こういうのを「タイトな演奏」というのだろうなと思いました。
ビートルズやローリング・ストーンズが下手とはいわないけれど、
この演奏は、僕がそれまで経験したことがないものだと感じました。
ギターのジョン・ティル John Tilはセミアコ系のギターを使っていて、
ブックレットにもギブソンのセミアコを持った写真がありますが、
厚みよりは広がり系の太いギターの音も当時の僕には新鮮でした。
このアルバムの録音中にジャニスは命を落としてしまったため、
一部の曲は必ずしも望んだ姿ではないようですが、それでも
当時の意欲とバンドのまとまり、時代の息吹が伝わってきます。
そして今や、時代を超えたアルバムの1枚となりました。
作曲者は曲名の下にブックレットにある通りに記します。
ただ、今回はオリジナルや作曲者のことにはほとんどに触れず、
あくまでも僕の思いを綴ってゆくことはどうかお許しください。
02 冬のパール、ツルアジサイのドライフラワー

Tr1:Move Over
(Janis Joplin)
ジャニス自身のペンによるパワフルな彼女の代名詞的な曲。
曲自体はひねりがなくストレートなだけに募る思いは最高潮に
まっすぐに伝わってきます。
ヴォーカルラインをなぞるギターもカッコいい。
今回、このアルバムを聴きたくなったきっかけがこの曲でした。
1989年に、クスリで命を落とした人の曲をカバーして
アンチドラッグ運動を盛り上げる目的のコンピレーションアルバム、
MAKE A DIFFERENSEが作られましたが、そこで
シンデレラ Cinderellaがこの曲をカバーしていたのを、
CDシングルの記事(こちら)で思い出したからです。
これは歌メロがいいので鼻歌で口ずさむようになりましたが、
そこで僕は、こちらもかつて一度記事にした(こちら)
「歌詞と歌い手の性の同一問題」について悩みました。
だって、♪ You know that I need a man と僕が歌うと、
意味が違ってくる恐れがあるじゃないですか(笑)。
でも、鼻歌で歌う時に"man"を"woman"に変えたところ、
それもなんだか妙にこっ恥ずかしかったのです。
まあ、鼻歌は誰に向けて歌うものでもないのだから、
僕はオリジナル通りに"man"で歌っています。
"woman"にすると音節がひとつ増えるのは違和感があるし。
なお、シンデレラのトム・キーファーは"woman"と歌っています。
あ、シンデレラといっても男性ですから(笑)。
Tr2:Cry Baby
(J. Ragovoy-B. Berns)
「ジャッジャッジャッ」と音を切るイントロが印象的。
音が止まってから声を絞り出して叫ぶジャニス。
この切り替えが絶妙で、最初に聴いて名盤だと確信しました。
ゆったりとしたワルツにジャニスが吠えまくります。
ところで、「クライベイビー」というギターのエフェクター、
音が歪んでもわっと広がるワウペダルの一種があります。
エリック・クラプトンがよく使っていたものですが、僕がそれを
知ったのはこの曲より後だったので、てっきり、その名前は、
この曲のイメージからつけられたのだと思い込んでいました。
でも、ジャニスの声はイメージぴったりだと思います。
「ナチュラル・クライベイビー・ヴォイス」、ですね(笑)。
Tr3:A Woman Left Lonely
(D. Penn - S. Oldham)
やはりずっと気持ちを張り詰め続けるのは大変かな。
アルバムでいちばん落ち着いた大人しい曲。
しっとりと歌おうとはしつつも、ジャニスはやはり
感情的に歌っていきます。
この曲はソウルだといわれればそうかもしれません。
Tr4:Half Moon
(J. Hall - J. Hall)
軽快にホップしスウィングするカントリー調の曲。
アルバムでいちばんのりがよくて体が自然と動く曲で、
アルバムの流れに変化をつける点でも効果的な曲。
そしてこれはギターやベースなど、歌以上に
演奏部分に反応して自然と口ずさむ曲です。
Tr5:Buried Alive In The Blues
(N.Graventies)
ジャニスが後にヴォーカルを入れる予定だったインストゥルメンタル曲。
彼女ならどんな歌メロを入れて叫んだのだろう。
「生きながらブルースに葬られて」という曲をこの時期に録音していた、
そう聞くと悲しいですが、曲はむしろ底抜けに明るく楽しい曲。
演奏だけのこの曲があるので、僕は余計に演奏を上手いと感じたのかも。
歌がないことでバンドメンバーのジャニスへの愛情をより強く感じます。
03 2011年2月6日、雲の風景

Tr6:My Baby
(J. Ragovoy - M. Shuman)
これは「一発芸」の典型というか、Aメロで大人しくしていて、
サビで大爆発、そのサビがとても素晴らしいという曲。
Tr7:Me And Bobby McGee
(K. Kristofferson - F. Foster)
60年代後半から、ウッドストックもあって「自由」を謳歌する曲が
増えましたが、でも、僕は、この曲を聴いて、「自由」って結局
誰にも分からなかったじゃないかな、と思ったりもします。
♪ Freedom is just another word for nothing left to lose
「自由ってつまりは何も失うものがないってことなのよ」
このくだりは素晴らしく、意味するところは重いですね。
クリス・クリストファソンの作曲によるこの曲は、
彼女で唯一、シングルが全米No.1に輝いた曲。
アメリカ音楽のよいエッセンスを凝縮して楽しく聴かせてくれる、
僕のようなポップファンにはうれしい曲でもあります。
最後にリズムがジャズっぽくなって全体が弾けるところを
天真爛漫に歌うジャニスには音楽的勘の良さを感じます。
この部分はとにかくカッコよく、感動的だし、それまでの僕が
味わったことがないスタイルの音楽でもありました。
最後の最後、まるで弦を擦るようなギターの音が起こって、
半ば強制終了的に曲が終わる、そのエンディングも見事。
このアルバムも僕は大学時代に目覚まし代わりにタイマーでかけて
毎朝聴いていましたが、ある日、最後まで聴き通せない日があって、
家を出なければいけない時間にこの曲がかかっていたのを、
CDを止めないでそのまま家を出たことがありました。
もちろんタイマーで止まるからなんですが、その時僕は、
あまりにも曲に気持ちが入りすぎていて、曲を途中で止めるのは
なんだか申し訳ない気がしたのでした。
そして、家を出る時に聞こえてきたこの曲がまた素敵に感動的で、
そう感じたのは旅情を誘う歌詞だからかもしれないですね。
ともあれ、僕には特に大切な曲のひとつです。
Tr8:Mercedes Benz
(J. Joplin - M. McClure)
デモだと思うのですが、ジャニスがアカペラで歌って
こんな曲をやりたいよってバンドに聴かせたんじゃないかな。
和やかで明るく楽しいその場の雰囲気が伝わってきて、なぜか、
ほんとうはそこから演奏がついて広がっていったのに残念とは
思わない、僕はそう感じます。
歌っていくとテンポが速くなってずれていくのがまた楽しい。
友達はポルシェに乗ってるから私はベンツが欲しいという
まことに他愛のない曲ですが、ジャニスが歌うと許せてしまう。
この曲はこのまま出たのがよかったのかもしれない。
演奏を加えなかった判断に拍手を送りたいです。
しかし、ブックレットを見ると、この曲は彼女の死の
わずか3日前に録音されていることが分かって、あらためて、
それはあまりにも突然に訪れたことに驚かざるを得ません。
Tr9:Trust Me
(B. Womack)
ボビー・ウーマックの曲で彼自身もアコースティック・ギター
で客演していますが、だからか、ギターの響きがきれいです。
♪ My love is like a sea, baby
愛した後に潮が引いてゆくような虚しさを感じる曲。
前の曲とはあまりにも世界観が違うような気がするのですが、
それらすべてがジャニスという人となりだったのでしょうね。
Tr10:Get It While You Can
(J. Ragovoy - M. Shuman)
このアルバムの曲名はみな人生訓のようですね。
まあ歌というのはそういうものかもしれないけど、
とりわけこのアルバムはそう感じます。
「愛は生きているうちに」という邦題がつけられましたが、
それは、当時のレコード会社の担当者の気持ちでしょう。
アルバムの最後は、彼女の明るいキャラクターからすると、
気持ち、しんみりしすぎかな、寂しくなってしまう曲。
でもそれも彼女の周りで携わってきた人たちの
素直な思いなのかもしれません。
リンクは左が2枚組レガシー・エディション、右が通常盤。
このアルバムは、34分強しかなくて実際に短いのですが、
聴くといつもあっっっという間に終わってしまいます。
もちろん曲が充実していて流れがいいからでしょうけど、
それはあたかも、彼女自身の生きざまの象徴であるかのように。
ジャニス・ジョプリンは周りの人に愛され、助けられながら
生きてきたんだなということがよく分かりますが、しかし彼女は、
しっかりと生きることを学ぶのは忘れていたのかもしれない。
今回聴いて、ふと、ジャニス・ジョプリンという女性は
どのように人を好きになって愛したのだろうって思いました。
伝記などを読めば事実は分かるのかもしれないけど、
僕は昔から、アーティストの私生活にはあまり興味がなく、
事実を知りたいと思ったことはほとんどありません。
でも、どういう風に好きになったのか、事実としてではなく、
普遍的な人間の営みのひとつとして、こうした歌を通して
人の思いに触れることは嫌いではありません。
このアルバムはどこをどう聴いても説得力があります。
そしてもちろん素晴らしい。
04

最後に、わが家の「パール対決」・・・(笑)・・・
2014年01月28日
ダフト・パンクがグラミー「最優秀アルバム賞」受賞
01

第58回グラミー賞授賞式が現地1月26日、日本時間27日に行われました。
今年のAlbum of the Year=「年間最優秀アルバム賞」は
ダフト・パンクのRANDOM ACCESS MEMORIESが受賞しました。
最優秀アルバム賞は、アルバム単位で音楽を聴く僕が、
10代の頃から最も重要視しており、受賞したアルバムを持っていなければ
買って聴き、さらに過去に遡って持っていないものも集めることにしています。
しかし今年は、既に買ったものが受賞。
こんなうれしいことはない。
なんといっても素晴らしいアルバムだから。
さらには、シングル曲のGet Luckyが
Record of the Year=「年間最優秀レコード賞」も受賞し、
主要4部門のうち2部門をダフト・パンクが受賞しました。
今日は、再びこのアルバムの話をしたいと思います。
新譜さらりと記事で一度取り上げていましたが、
受賞を記念して、アルバム記事として再度上げることにしました。
RANDOM ACCESS MEMORIES Daft Punk
ランダム・アクセス・メモリーズ ダフト・パンク (2013)
僕がこのアルバムを買った頃は、「あまちゃん」が盛り上がっていました。
「あまちゃん」のおかげで1980年代の音楽が注目を集めました。
もっとも、そこで語られていたのは邦楽限定で、僕は80年代にはもう
「洋楽バカ」になっていたから、80年代の邦楽はテレビやラジオや街角で
当時耳にしたヒット曲くらいしか知りません。
それでも「あまちゃん」を見ながら、小泉今日子の「木枯らしに抱かれて」、
薬師丸ひろ子の「探偵物語」がよく頭の中に流れてきていました。
ドラマの中では現代の2010年に歌われていた「地元へ帰ろう」という曲、
それがもろ80年代打ち込み系ソウルバラード風の曲でしたが、それを聞いて、
80年代のブラックミュージックのヒット曲はああいうの多かったよなって、
洋楽好きとしては、ちょっと驚き、うれしかった。
80年代が注目されるのはやはりうれしいですね。
僕は、このBLOGを始めた頃から、80年代音楽にはこだわってきました。
80年代は僕が洋楽を夢中になって聴き育った年代だし、
純粋に今でも大好き、むしろ当時よりいいと思うものが増えているくらい。
80年代は、音楽的には行き詰っていてつまらないと当時から言われていた。
でも人間は生まれを選べないから、何といわれても僕は80年代が好きです。
80年代ブームは実は「あまちゃん」の日本だけの話ではなく、
「ベストヒットUSA」を見るようになってから、アメリカでもそういう流れが
あるんだなと感じていました。
例えばブルーノ・マーズ、曲もビデオクリップも、70年代ディスコ以降から
80年代と雰囲気があざといほどに作り上げられていました。
当時音楽を聴き育った僕から下10歳くらいの年代が大人になり、子どもができ、
社会でも力のある世代になってきたことで、当時の音楽を懐かしむことが
情報として発信されやすくなったのでしょう。
だからこの流れは、考えてみれば当然のことかもしれない。
「ベストヒットUSA」でも極め付けといえる大きなインパクトがあったのが、
ダフト・パンクのGet Lucky featuring Pharrell Williams
ファレル・ウィリアムズがいかにも80年代に遅れて来たソウル歌手
といった面持ちで明るく楽しく歌う突き抜けた曲。
その横でギターを弾くドレッドヘアにサングラスの人、
あれっ、もしかしてナイル・ロジャース!
とにかく曲がよくて、でも番組では細切れでしか聴けずすぐにCDを買いました。
テレビで見て聴いてレコードを買うのは80年代によくあったことであり、
「ベストヒットUSA」を見るようになってまたそれが復活したのは楽しいですね。
02 ダフト・パンクの2人はグラミーで白い仮面をかぶっていた

CDを買ってアルバムとして聴くと、これが予想以上に気に入った。
とにかくひたすら楽しいし、懐かしい。
ダフト・パンクは何も知らなかったので、ウィキペディアで調べたところ、
フランス出身のハウス/フィルターハウス/エレクトロ・デュオであり、
トーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ド・オメン=クリストの2人組。
ステージではそれぞれを特徴づける仮面をかぶって演奏するということで、
ジャケットの仮面は2人のものを半分にして癒合させたものでしょう。
ちなみに、グラミー授賞式でも2人はずっと白い仮面をかぶったままで、
どんな人たちかは分からずじまいでした。
ただ、Get Luckyを聴くとソウルやファンクからディスコを経て
ブラコン辺りまでの曲の焼き直しを予想していたけれど、全体としてはむしろ
軸足はエレクトロポップ側にあり、そこからソウルやファンクに寄って来た感じ。
曲ごとに誰それに似ているというのはあるとしても、全体がまるっきり
誰かの焼き直しというのではなく、70年代ディスコ以降から80年代の
サウンド全体の雰囲気を集めて取り込んで圧縮して再構築したといった響き。
だから、RAM=「ランダム・アクセス・メモリ」なんだ、ふむふむ。
アルバムを聴いていると、80年代のいろいろな要素がランダムに
頭に浮かんでくるという仕掛けです。
しかし、ブックレットを見て驚いた。
参加ミュージシャンがあまりにも豪華。
ナイル・ロジャースは書きましたが、他、ギターにポール・ジャクソン・Jr、
ベースにエリック・クラプトンを支え続けるネイサン・イースト、
ドラムスにスティングのバンドにもいたオマー・ハキム、
ペダルスティールギターのグレッグ・リーズ、
さらにあのジョルジオ・モロダー、そしてポール・ウィリアムス。
エレクトロポップというと演奏が機械任せで軽いと思いがちであり、
言ってしまえば演奏が下手でも(センスさえよければ)できる音楽、
みたいなイメージに捉えられやすいと思います。
ええ、僕がそうでしたから。
ところが、ダフト・パンクのこのアルバムは、名うての名演奏家を集めて、
演奏のクオリティが高い。
プロジェクトというよりはバンドに近いものがある。
このアルバムは、最初から数回は、楽しく聴ける「だけ」のアルバム
と感じていましたが、聴いてゆくうちに、心の上っ面だけではない、
もっと奥深くに音楽が届いてくるように感じられました。
それは、やはり、演奏が本物だからなのでしょう。
このアルバム評を見ると「すぐに飽きる」という声が結構あったのですが、
そういう人は、あまり演奏を気にしない、少なくとも自分で楽器を
演奏しない人なのかな、と想像しました(違ったらすいません)。
このアルバムは、昨年大晦日に上げた記事でも書きましたが、
「ローリング・ストーン」誌が選ぶ2013年のアルバムで3位に入りました。
(ちなみに4位はポール・マッカートニーのNEWです)。
あの硬派、というか玄人筋、というか本格派とのイメージが強い
RS誌が3位に選ぶのだから、やはりこれは上っ面だけの楽しい音楽
以上のものを目指して作られ、それが成功したということなのでしょう。
グラミーでもそれは同じでした。
考え方によっては、エレクトロポップが大人も聴ける音楽になった、
ということなのでしょう、上述のように年代の話を鑑みても。
でも、やはり、音楽の本質を突いたことが評価されたのでしょう。
さらにいえば、こういうやり方でも本質を突いた音楽が作れる、
という部分が新機軸であるということ。
車で軽く聴けるし、家でじっくりと聴くこともできる贅沢な1枚。
それがこのアルバムでしょう。
03 1曲目はなんとなくこんなイメージかもしれない

1曲目 Give Life Back To Music
「音楽に命を取り戻せ」と高らかに宣言する曲でアルバムは始まる。
これ以上何を言わんかや。
「ジャジャジャーン」といかにもという大仰なイントロで始まり、
昔のボコーダー風にエフェクトをかけた声で歌い出すこの曲は、
音楽がエンターテイメントであるという意識に則っていて安心して聴ける。
ファンク風のぼこぼこ鳴る本物のギターに胸躍る。
そのギターはポール・ジャクソン・ジュニアとナイル・ロジャース。
うん、いい、これはいい、と最初の一発目から胸倉を掴まれました。
2曲目 The Game Of Love
ソウルバラード風の虚しさが漂う曲で、少し向こうに
ピーター・ガブリエルが見えてくるから不思議。
3曲目 Giorgio By Moroder
70年代後半から80年代の顔ともいえる大物、ジョルジオ・モロダーを
テーマにした曲で、なんと、ジョルジオ・モロダー自身が、
いかにして自分が音楽で名を成したかの回顧録を読み上げています。
"My name is Giovanni Giorgio, everybody calls me Giorgio"
と語ったところで、ドナ・サマーやアイリーン・キャラやリマールのバックを
思い起こさせるエレクトロポップのインストゥロメンタル曲に。
間奏のキーボードの盛り上げ方が、なかやるなと思わせる。
しかもこのような電気的な曲でグレッグ・リーズのペダルスティールギター
というのが、少なくとも今までの僕にはまったくない発想で驚いた、贅沢すぎる。
でも、グレッグ・リーズ目当てで聴くとこの曲は失敗しますよ、念のため
4曲目 Within
額(ひたい)にかかった髪の毛から雨のしずくがしたたり落ちてくるような、
どことなく虚しい曲で、やっぱりピーター・ガブリエルがが見えてしまう。
僕の中では、虚しい曲といえばピーガブなのかな・・・
5曲目Instant Crush
これは演奏にアラン・パーソンズ・プロジェクトが見えてくる。
ダフト・パンクは本人たちが歌うも声にはエフェクトがかかっているけれど。
Bメロの早口で歌う部分のほろほろと散ってゆくような歌メロがいい。
6曲目 Lose Yourself To Dance
ファレル・ウィリアムスの切なげなヴォーカルに
ナイル・ロジャースのギターが切れまくるまさにシック風の曲。
タイトルの言葉をこれでもかというくらいに繰り返し、頭にこびりついて離れない。
ファレル・ウィリアムスの歌もいいですね、好きになりました。
7曲目 Touch
この曲はMr. Robotoのスティックス、デニス・デヤングが見えてくる。
或いはThe Final Cutのロジャー・ウォーターズも少しだけ入っている。
歌うはポール・ウィリアムス。
前半は劇的な重たい曲が、後半はラッパが鳴り響く
明るいダンスミュージックへと変貌します。
そう、3曲目のファンキーなピアノでも思ったけど、この人たちは
ファンキーさが時々強く出てくるのが面白い。
後半は救いの手が差し伸べられたかのようなゆったりとした広がりがある曲に。
オーケストラも少年コーラスも電子音も何もかもが盛り上がった後で、
独白風の歌が入って終わり、一人芝居を見たような感慨に襲われる。
ポール・ウィリアムスは今朝見た「めざましテレビ」では、
このアルバムの製作総指揮のように紹介されていましたが、
ブックレットではそれは確認できず、それがほんとうだとすれば、
へえそういうことだったのかと頭の中でつながりました。
ポール・ウィリアムスは、例のあのアルバム、そろそろ真面目に聴かなきゃ。
04

8曲目 Get Lucky
きたきた!
80年代と今の僕の最大の違いは、ソウルやファンクに目覚めたこと。
その上で80年代風のサウンド、これはもう今の僕のど真ん中の曲かも。
これまたタイトルの言葉を執拗に繰り返す、インパクトがあまりにも大きい曲。
ところで僕は、これを聴いているとプリンスのI Wanna Be Your Loverが
頭の中でクロスオーヴァーしながら響いてきます。
曲としては決して似てはいないんだけど、でも、僕にとっての
エレクトロポップ+ファンクの雛型がプリンスなのかもしれない。
そうか、プリンスこそが80年代を代表する音楽だったんだ、
と今更ながらにして思いましたが、プリンスの話はまた場を改めて(笑)。
ところで、この曲は残念ながらというか、ビルボードHot100では
最高位2位、1位を取ることができませんでした。
この曲が2位にいるあいだずっと1位にいたのが、
ロビン・シックのBlurred Lines邦題「今夜はヘイヘイヘイ!」でしたが、
そこには同じファレル・ウィリアムスが参加しています。
つまり、ファレルは、自分自身のせいで自分の曲が1位になれなかった。
でも、グラミーでは逆にロビン・シックはまったく無視され、一方で
ダフト・パンクは見事受賞したという皮肉な結果になりました。
多分、昨年の流行語でいえば「倍返し」というところでしょう(笑)。
余談というか、ダフト・パンクとロビン・シックの違いはやはり、
「演奏が本物かどうか」ではないかと思います。
そうじゃなければ、同じように気持ちいい曲がたくさん入ったアルバムが
あれほどまでに無視されるのは納得できないから。
そしてもうひとつ、グラミー授賞式でもこの曲が演奏されましたが、
ダフト・パンクとナイル・ロジャースになんとスティーヴィー・ワンダーが
入っての演奏、すごい、そしてイメージぴったり。
さらにその演奏で会場が総立ちになり、ポール・マッカートニー夫妻も
リンゴ・スター夫妻もフィンガーティップスを交えながら全身でリズムを
取って踊っていた姿を見て、これが音楽だ、と思いました。
もちろんポールもリンゴもかっこいい!
とにかく、まだこんなに大好きになれる曲が出てくるなんてうれしいですよ。
そうだ、受賞したことだし、シングルCDを買わなきゃ。
9曲目 Beyond
前半は簡単な歌が入るけれど基本インストゥロメンタル曲。
派手なストリングスで始まる映画音楽風の曲の中で、
グレッグ・リースのペダルスティールを探せ、みたいな気もしますが、
目立つのではなくサウンドの中で渾然一体となって響いてきます。
(くどいようだけどだから彼目当てで聴くと失敗する可能性大)。
10曲目Motherboard
ダフト・パンクのPCの基盤はこんな音楽なんだな(笑)。
前の曲の流れそのままのインストゥロメンタル曲だけど、
考えてみればグレッグ・リースをこのような音楽で使っ
てそれほど目立たないというのは贅沢極まりない。
アメリカーナ音楽指向の人が聴くと怒り出すかもしれない・・・
スティーリー・ダンがAJAの録音の際に、ギターのたった1フレーズのために
著名なギタリスト何人もに弾かせた、という話を思い出しました。
11曲目 Fragments Of Time
「時のかけら」をダフト・パンクがデフラグしたのがこのアルバム、
ということなのでしょう。
この曲は演奏が普通のロックバンド形態であれば、
ウェストコーストサウンドになると思います。
先ほどからずっと言及しているグレッグ・リースのペダルスティール、
ここでは水を得た魚のごとく爽快に鳴り響いています。
日本人ならやっぱり「ベストヒットUSA」のテーマ曲につながっていきますね。
さらにいえば、深夜にその番組が終わった後に放送していた
「白バイ野郎ジョン&パンチ」を思い出す。
トッド・エドワーズが歌っていますが、僕はこの人を知らないので調べると、
1972年生まれのアメリカのハウス音楽のプロデューサーとのこと。
こんな曲が入っているというのは意外でしたが、そこが奥深いところでしょう。
12曲目 Doin' It Right
「地」の部分はダフト・パンクがいつものエフェクト声で歌っていますが、
そこに乗っかる爽やかなヴォーカルはパンダ・ベアーなる人。
僕は知らなかったので調べると、1978年アメリカ生まれの音楽家、とのこと。
それにしても、パンダ・ベアーね。
ジェファーソン・エアプレインのグレイス・スリックがパンダの追っかけをやっていて、
スターシップ時代に「ベストヒットUSA」で小林克也さんのインタビューを
受けていた映像を思い出してしまった(笑)。
なんとなく童謡っぽい曲。
13曲目 Contact
最後は宇宙ですよ、宇宙人との遭遇かな。
モジュラー・シンセサイザーの連続音は飛行船の飛ぶ音。
オマー・ハキムのドラムスがここぞとばかりに
ドラムソロのような派手な演奏を聴かせる。
ドラムスは僕は演奏ができないので正直よく分からないんだけど、
このドラムスは引き込まれるものがありますね。
段々と音が大きくなり、高くなってゆくさまが
宇宙に飛び出していく瞬間を想像させる。
気持ちの高揚感がついにスピーカーを突き抜けてしまったかのよう。
なんですが、CDを買った最初の頃は、音が高く大きくなりマックスに
達した辺りで、マーサが吠えたんです、恐かったのかなか。
まあなんであれ、最後は気持ちが行き着くところまで行ってしまって
アルバムが終わります。
正直、買うのは冒険でした。
もっとも僕は、自分でお金を出して冒険をしていい音楽と
たくさん出会ってきたので、それはそれでいつものことなのですが。
でも、実際に聴くと、「楽しければそれでいい」という音楽をはるかに超越した
深みのある音楽だと感じるようになりました。
やはり、卓越したミュージシャンが作り出す音楽だから。
昔は単なる流行りだったこの手の音楽を、力量のあるミュージシャンで
本格的な音楽として作り上げた。
焼き直し以上の新しい本物の音楽といえるのではないかな。
何より、これだけの大物が参加している、その名前を見るだけで
単純な僕は心が躍りますからね(笑)。
だから今回の冒険は大成功でした!
こういう出会いがあるから、今の音楽もまた楽しいですね。
そしてやっぱり、これからも80年代にはこだわってゆきたい。
もちろん「ベストヒットUSA」にもお世話になりながら。
さて、グラミー主要4部門、最優秀新人賞は
マックルモア&ルイスが受賞。
この人たちは名前は知っていましたが、チェックしていなかった。
もうひとつ、Song of the Year=最優秀楽曲賞は、
17歳の天才女性ロードが歌うRoyalsが受賞。
こちらは先行投資で買っていて、それも気に入っています。
ダフト・パンクについて話せば、僕がうれしかったのが、
「僕の耳や感覚はまだ衰えていない」と感じたことです。
さらには、ヒットチャートやグラミー賞を楽しみに聴いていた
10代から20代前半の頃も思い出しました。
それはまさに1980年代のこと。
僕はやっぱり、玄人筋に受ける音楽よりは、
ヒット曲を中心に聴くタイプの人間のようですね(笑)。
グラミー賞を受賞したとなると、とたんによく聴こえてしまう。
正直、それはあります、昔から、、僕は単純な人間でして・・・
だからこの記事もかなり盛っているのではないかと思われるでしょうか。
しかし、このアルバムは盛る必要がないほど素晴らしいですよ。
そうそう、余談で申し訳ないですが、今回のグラミー授賞式では、
ポール・マッカートニーとリンゴ・スターの共演も話題になりましたね。
今朝のテレビでちょっとだけ流れていた映像を見て聴くと、
ポールが歌っていたのはNEWのQueenie Eyeでしたが、
この曲も僕が最初から大好きだったのでうれしかった。
ただ、ポール、声がちょっと、コンサートの時よりは出ていなかったかな。
なんて、やっぱりポールに言及しないと気が済まないのでした(笑)。
まあ、ポールのおかげで今の音楽生活があるのだから。
そして最後はやはりポーラで。
05

このお店でこのCDを買ったわけではないのですが・・・

第58回グラミー賞授賞式が現地1月26日、日本時間27日に行われました。
今年のAlbum of the Year=「年間最優秀アルバム賞」は
ダフト・パンクのRANDOM ACCESS MEMORIESが受賞しました。
最優秀アルバム賞は、アルバム単位で音楽を聴く僕が、
10代の頃から最も重要視しており、受賞したアルバムを持っていなければ
買って聴き、さらに過去に遡って持っていないものも集めることにしています。
しかし今年は、既に買ったものが受賞。
こんなうれしいことはない。
なんといっても素晴らしいアルバムだから。
さらには、シングル曲のGet Luckyが
Record of the Year=「年間最優秀レコード賞」も受賞し、
主要4部門のうち2部門をダフト・パンクが受賞しました。
今日は、再びこのアルバムの話をしたいと思います。
新譜さらりと記事で一度取り上げていましたが、
受賞を記念して、アルバム記事として再度上げることにしました。
RANDOM ACCESS MEMORIES Daft Punk
ランダム・アクセス・メモリーズ ダフト・パンク (2013)
僕がこのアルバムを買った頃は、「あまちゃん」が盛り上がっていました。
「あまちゃん」のおかげで1980年代の音楽が注目を集めました。
もっとも、そこで語られていたのは邦楽限定で、僕は80年代にはもう
「洋楽バカ」になっていたから、80年代の邦楽はテレビやラジオや街角で
当時耳にしたヒット曲くらいしか知りません。
それでも「あまちゃん」を見ながら、小泉今日子の「木枯らしに抱かれて」、
薬師丸ひろ子の「探偵物語」がよく頭の中に流れてきていました。
ドラマの中では現代の2010年に歌われていた「地元へ帰ろう」という曲、
それがもろ80年代打ち込み系ソウルバラード風の曲でしたが、それを聞いて、
80年代のブラックミュージックのヒット曲はああいうの多かったよなって、
洋楽好きとしては、ちょっと驚き、うれしかった。
80年代が注目されるのはやはりうれしいですね。
僕は、このBLOGを始めた頃から、80年代音楽にはこだわってきました。
80年代は僕が洋楽を夢中になって聴き育った年代だし、
純粋に今でも大好き、むしろ当時よりいいと思うものが増えているくらい。
80年代は、音楽的には行き詰っていてつまらないと当時から言われていた。
でも人間は生まれを選べないから、何といわれても僕は80年代が好きです。
80年代ブームは実は「あまちゃん」の日本だけの話ではなく、
「ベストヒットUSA」を見るようになってから、アメリカでもそういう流れが
あるんだなと感じていました。
例えばブルーノ・マーズ、曲もビデオクリップも、70年代ディスコ以降から
80年代と雰囲気があざといほどに作り上げられていました。
当時音楽を聴き育った僕から下10歳くらいの年代が大人になり、子どもができ、
社会でも力のある世代になってきたことで、当時の音楽を懐かしむことが
情報として発信されやすくなったのでしょう。
だからこの流れは、考えてみれば当然のことかもしれない。
「ベストヒットUSA」でも極め付けといえる大きなインパクトがあったのが、
ダフト・パンクのGet Lucky featuring Pharrell Williams
ファレル・ウィリアムズがいかにも80年代に遅れて来たソウル歌手
といった面持ちで明るく楽しく歌う突き抜けた曲。
その横でギターを弾くドレッドヘアにサングラスの人、
あれっ、もしかしてナイル・ロジャース!
とにかく曲がよくて、でも番組では細切れでしか聴けずすぐにCDを買いました。
テレビで見て聴いてレコードを買うのは80年代によくあったことであり、
「ベストヒットUSA」を見るようになってまたそれが復活したのは楽しいですね。
02 ダフト・パンクの2人はグラミーで白い仮面をかぶっていた

CDを買ってアルバムとして聴くと、これが予想以上に気に入った。
とにかくひたすら楽しいし、懐かしい。
ダフト・パンクは何も知らなかったので、ウィキペディアで調べたところ、
フランス出身のハウス/フィルターハウス/エレクトロ・デュオであり、
トーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ド・オメン=クリストの2人組。
ステージではそれぞれを特徴づける仮面をかぶって演奏するということで、
ジャケットの仮面は2人のものを半分にして癒合させたものでしょう。
ちなみに、グラミー授賞式でも2人はずっと白い仮面をかぶったままで、
どんな人たちかは分からずじまいでした。
ただ、Get Luckyを聴くとソウルやファンクからディスコを経て
ブラコン辺りまでの曲の焼き直しを予想していたけれど、全体としてはむしろ
軸足はエレクトロポップ側にあり、そこからソウルやファンクに寄って来た感じ。
曲ごとに誰それに似ているというのはあるとしても、全体がまるっきり
誰かの焼き直しというのではなく、70年代ディスコ以降から80年代の
サウンド全体の雰囲気を集めて取り込んで圧縮して再構築したといった響き。
だから、RAM=「ランダム・アクセス・メモリ」なんだ、ふむふむ。
アルバムを聴いていると、80年代のいろいろな要素がランダムに
頭に浮かんでくるという仕掛けです。
しかし、ブックレットを見て驚いた。
参加ミュージシャンがあまりにも豪華。
ナイル・ロジャースは書きましたが、他、ギターにポール・ジャクソン・Jr、
ベースにエリック・クラプトンを支え続けるネイサン・イースト、
ドラムスにスティングのバンドにもいたオマー・ハキム、
ペダルスティールギターのグレッグ・リーズ、
さらにあのジョルジオ・モロダー、そしてポール・ウィリアムス。
エレクトロポップというと演奏が機械任せで軽いと思いがちであり、
言ってしまえば演奏が下手でも(センスさえよければ)できる音楽、
みたいなイメージに捉えられやすいと思います。
ええ、僕がそうでしたから。
ところが、ダフト・パンクのこのアルバムは、名うての名演奏家を集めて、
演奏のクオリティが高い。
プロジェクトというよりはバンドに近いものがある。
このアルバムは、最初から数回は、楽しく聴ける「だけ」のアルバム
と感じていましたが、聴いてゆくうちに、心の上っ面だけではない、
もっと奥深くに音楽が届いてくるように感じられました。
それは、やはり、演奏が本物だからなのでしょう。
このアルバム評を見ると「すぐに飽きる」という声が結構あったのですが、
そういう人は、あまり演奏を気にしない、少なくとも自分で楽器を
演奏しない人なのかな、と想像しました(違ったらすいません)。
このアルバムは、昨年大晦日に上げた記事でも書きましたが、
「ローリング・ストーン」誌が選ぶ2013年のアルバムで3位に入りました。
(ちなみに4位はポール・マッカートニーのNEWです)。
あの硬派、というか玄人筋、というか本格派とのイメージが強い
RS誌が3位に選ぶのだから、やはりこれは上っ面だけの楽しい音楽
以上のものを目指して作られ、それが成功したということなのでしょう。
グラミーでもそれは同じでした。
考え方によっては、エレクトロポップが大人も聴ける音楽になった、
ということなのでしょう、上述のように年代の話を鑑みても。
でも、やはり、音楽の本質を突いたことが評価されたのでしょう。
さらにいえば、こういうやり方でも本質を突いた音楽が作れる、
という部分が新機軸であるということ。
車で軽く聴けるし、家でじっくりと聴くこともできる贅沢な1枚。
それがこのアルバムでしょう。
03 1曲目はなんとなくこんなイメージかもしれない

1曲目 Give Life Back To Music
「音楽に命を取り戻せ」と高らかに宣言する曲でアルバムは始まる。
これ以上何を言わんかや。
「ジャジャジャーン」といかにもという大仰なイントロで始まり、
昔のボコーダー風にエフェクトをかけた声で歌い出すこの曲は、
音楽がエンターテイメントであるという意識に則っていて安心して聴ける。
ファンク風のぼこぼこ鳴る本物のギターに胸躍る。
そのギターはポール・ジャクソン・ジュニアとナイル・ロジャース。
うん、いい、これはいい、と最初の一発目から胸倉を掴まれました。
2曲目 The Game Of Love
ソウルバラード風の虚しさが漂う曲で、少し向こうに
ピーター・ガブリエルが見えてくるから不思議。
3曲目 Giorgio By Moroder
70年代後半から80年代の顔ともいえる大物、ジョルジオ・モロダーを
テーマにした曲で、なんと、ジョルジオ・モロダー自身が、
いかにして自分が音楽で名を成したかの回顧録を読み上げています。
"My name is Giovanni Giorgio, everybody calls me Giorgio"
と語ったところで、ドナ・サマーやアイリーン・キャラやリマールのバックを
思い起こさせるエレクトロポップのインストゥロメンタル曲に。
間奏のキーボードの盛り上げ方が、なかやるなと思わせる。
しかもこのような電気的な曲でグレッグ・リーズのペダルスティールギター
というのが、少なくとも今までの僕にはまったくない発想で驚いた、贅沢すぎる。
でも、グレッグ・リーズ目当てで聴くとこの曲は失敗しますよ、念のため
4曲目 Within
額(ひたい)にかかった髪の毛から雨のしずくがしたたり落ちてくるような、
どことなく虚しい曲で、やっぱりピーター・ガブリエルがが見えてしまう。
僕の中では、虚しい曲といえばピーガブなのかな・・・
5曲目Instant Crush
これは演奏にアラン・パーソンズ・プロジェクトが見えてくる。
ダフト・パンクは本人たちが歌うも声にはエフェクトがかかっているけれど。
Bメロの早口で歌う部分のほろほろと散ってゆくような歌メロがいい。
6曲目 Lose Yourself To Dance
ファレル・ウィリアムスの切なげなヴォーカルに
ナイル・ロジャースのギターが切れまくるまさにシック風の曲。
タイトルの言葉をこれでもかというくらいに繰り返し、頭にこびりついて離れない。
ファレル・ウィリアムスの歌もいいですね、好きになりました。
7曲目 Touch
この曲はMr. Robotoのスティックス、デニス・デヤングが見えてくる。
或いはThe Final Cutのロジャー・ウォーターズも少しだけ入っている。
歌うはポール・ウィリアムス。
前半は劇的な重たい曲が、後半はラッパが鳴り響く
明るいダンスミュージックへと変貌します。
そう、3曲目のファンキーなピアノでも思ったけど、この人たちは
ファンキーさが時々強く出てくるのが面白い。
後半は救いの手が差し伸べられたかのようなゆったりとした広がりがある曲に。
オーケストラも少年コーラスも電子音も何もかもが盛り上がった後で、
独白風の歌が入って終わり、一人芝居を見たような感慨に襲われる。
ポール・ウィリアムスは今朝見た「めざましテレビ」では、
このアルバムの製作総指揮のように紹介されていましたが、
ブックレットではそれは確認できず、それがほんとうだとすれば、
へえそういうことだったのかと頭の中でつながりました。
ポール・ウィリアムスは、例のあのアルバム、そろそろ真面目に聴かなきゃ。
04

8曲目 Get Lucky
きたきた!
80年代と今の僕の最大の違いは、ソウルやファンクに目覚めたこと。
その上で80年代風のサウンド、これはもう今の僕のど真ん中の曲かも。
これまたタイトルの言葉を執拗に繰り返す、インパクトがあまりにも大きい曲。
ところで僕は、これを聴いているとプリンスのI Wanna Be Your Loverが
頭の中でクロスオーヴァーしながら響いてきます。
曲としては決して似てはいないんだけど、でも、僕にとっての
エレクトロポップ+ファンクの雛型がプリンスなのかもしれない。
そうか、プリンスこそが80年代を代表する音楽だったんだ、
と今更ながらにして思いましたが、プリンスの話はまた場を改めて(笑)。
ところで、この曲は残念ながらというか、ビルボードHot100では
最高位2位、1位を取ることができませんでした。
この曲が2位にいるあいだずっと1位にいたのが、
ロビン・シックのBlurred Lines邦題「今夜はヘイヘイヘイ!」でしたが、
そこには同じファレル・ウィリアムスが参加しています。
つまり、ファレルは、自分自身のせいで自分の曲が1位になれなかった。
でも、グラミーでは逆にロビン・シックはまったく無視され、一方で
ダフト・パンクは見事受賞したという皮肉な結果になりました。
多分、昨年の流行語でいえば「倍返し」というところでしょう(笑)。
余談というか、ダフト・パンクとロビン・シックの違いはやはり、
「演奏が本物かどうか」ではないかと思います。
そうじゃなければ、同じように気持ちいい曲がたくさん入ったアルバムが
あれほどまでに無視されるのは納得できないから。
そしてもうひとつ、グラミー授賞式でもこの曲が演奏されましたが、
ダフト・パンクとナイル・ロジャースになんとスティーヴィー・ワンダーが
入っての演奏、すごい、そしてイメージぴったり。
さらにその演奏で会場が総立ちになり、ポール・マッカートニー夫妻も
リンゴ・スター夫妻もフィンガーティップスを交えながら全身でリズムを
取って踊っていた姿を見て、これが音楽だ、と思いました。
もちろんポールもリンゴもかっこいい!
とにかく、まだこんなに大好きになれる曲が出てくるなんてうれしいですよ。
そうだ、受賞したことだし、シングルCDを買わなきゃ。
9曲目 Beyond
前半は簡単な歌が入るけれど基本インストゥロメンタル曲。
派手なストリングスで始まる映画音楽風の曲の中で、
グレッグ・リースのペダルスティールを探せ、みたいな気もしますが、
目立つのではなくサウンドの中で渾然一体となって響いてきます。
(くどいようだけどだから彼目当てで聴くと失敗する可能性大)。
10曲目Motherboard
ダフト・パンクのPCの基盤はこんな音楽なんだな(笑)。
前の曲の流れそのままのインストゥロメンタル曲だけど、
考えてみればグレッグ・リースをこのような音楽で使っ
てそれほど目立たないというのは贅沢極まりない。
アメリカーナ音楽指向の人が聴くと怒り出すかもしれない・・・
スティーリー・ダンがAJAの録音の際に、ギターのたった1フレーズのために
著名なギタリスト何人もに弾かせた、という話を思い出しました。
11曲目 Fragments Of Time
「時のかけら」をダフト・パンクがデフラグしたのがこのアルバム、
ということなのでしょう。
この曲は演奏が普通のロックバンド形態であれば、
ウェストコーストサウンドになると思います。
先ほどからずっと言及しているグレッグ・リースのペダルスティール、
ここでは水を得た魚のごとく爽快に鳴り響いています。
日本人ならやっぱり「ベストヒットUSA」のテーマ曲につながっていきますね。
さらにいえば、深夜にその番組が終わった後に放送していた
「白バイ野郎ジョン&パンチ」を思い出す。
トッド・エドワーズが歌っていますが、僕はこの人を知らないので調べると、
1972年生まれのアメリカのハウス音楽のプロデューサーとのこと。
こんな曲が入っているというのは意外でしたが、そこが奥深いところでしょう。
12曲目 Doin' It Right
「地」の部分はダフト・パンクがいつものエフェクト声で歌っていますが、
そこに乗っかる爽やかなヴォーカルはパンダ・ベアーなる人。
僕は知らなかったので調べると、1978年アメリカ生まれの音楽家、とのこと。
それにしても、パンダ・ベアーね。
ジェファーソン・エアプレインのグレイス・スリックがパンダの追っかけをやっていて、
スターシップ時代に「ベストヒットUSA」で小林克也さんのインタビューを
受けていた映像を思い出してしまった(笑)。
なんとなく童謡っぽい曲。
13曲目 Contact
最後は宇宙ですよ、宇宙人との遭遇かな。
モジュラー・シンセサイザーの連続音は飛行船の飛ぶ音。
オマー・ハキムのドラムスがここぞとばかりに
ドラムソロのような派手な演奏を聴かせる。
ドラムスは僕は演奏ができないので正直よく分からないんだけど、
このドラムスは引き込まれるものがありますね。
段々と音が大きくなり、高くなってゆくさまが
宇宙に飛び出していく瞬間を想像させる。
気持ちの高揚感がついにスピーカーを突き抜けてしまったかのよう。
なんですが、CDを買った最初の頃は、音が高く大きくなりマックスに
達した辺りで、マーサが吠えたんです、恐かったのかなか。
まあなんであれ、最後は気持ちが行き着くところまで行ってしまって
アルバムが終わります。
正直、買うのは冒険でした。
もっとも僕は、自分でお金を出して冒険をしていい音楽と
たくさん出会ってきたので、それはそれでいつものことなのですが。
でも、実際に聴くと、「楽しければそれでいい」という音楽をはるかに超越した
深みのある音楽だと感じるようになりました。
やはり、卓越したミュージシャンが作り出す音楽だから。
昔は単なる流行りだったこの手の音楽を、力量のあるミュージシャンで
本格的な音楽として作り上げた。
焼き直し以上の新しい本物の音楽といえるのではないかな。
何より、これだけの大物が参加している、その名前を見るだけで
単純な僕は心が躍りますからね(笑)。
だから今回の冒険は大成功でした!
こういう出会いがあるから、今の音楽もまた楽しいですね。
そしてやっぱり、これからも80年代にはこだわってゆきたい。
もちろん「ベストヒットUSA」にもお世話になりながら。
さて、グラミー主要4部門、最優秀新人賞は
マックルモア&ルイスが受賞。
この人たちは名前は知っていましたが、チェックしていなかった。
もうひとつ、Song of the Year=最優秀楽曲賞は、
17歳の天才女性ロードが歌うRoyalsが受賞。
こちらは先行投資で買っていて、それも気に入っています。
ダフト・パンクについて話せば、僕がうれしかったのが、
「僕の耳や感覚はまだ衰えていない」と感じたことです。
さらには、ヒットチャートやグラミー賞を楽しみに聴いていた
10代から20代前半の頃も思い出しました。
それはまさに1980年代のこと。
僕はやっぱり、玄人筋に受ける音楽よりは、
ヒット曲を中心に聴くタイプの人間のようですね(笑)。
グラミー賞を受賞したとなると、とたんによく聴こえてしまう。
正直、それはあります、昔から、、僕は単純な人間でして・・・
だからこの記事もかなり盛っているのではないかと思われるでしょうか。
しかし、このアルバムは盛る必要がないほど素晴らしいですよ。
そうそう、余談で申し訳ないですが、今回のグラミー授賞式では、
ポール・マッカートニーとリンゴ・スターの共演も話題になりましたね。
今朝のテレビでちょっとだけ流れていた映像を見て聴くと、
ポールが歌っていたのはNEWのQueenie Eyeでしたが、
この曲も僕が最初から大好きだったのでうれしかった。
ただ、ポール、声がちょっと、コンサートの時よりは出ていなかったかな。
なんて、やっぱりポールに言及しないと気が済まないのでした(笑)。
まあ、ポールのおかげで今の音楽生活があるのだから。
そして最後はやはりポーラで。
05

このお店でこのCDを買ったわけではないのですが・・・
2014年01月08日
WITH A LITTLE HELP... ジョー・コッカー
01

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Joe Cocker
ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ
ジョー・コッカー (1969)
一昨日から今朝にかけての札幌は雪がたくさん降りました。
特に僕の家の辺りでは、昨夜から今朝が多かった。
寝る前に家の周りの雪かきをしたのですが、起きてみると、
20cmくらいが新たに降っていたようでした。
今日はだから昼からは雪かきに追われて過ごしました。
そんな午後は、ゆっくりと音楽と向き合って、
その勢いでアルバムの記事を上げたくなるものです。
なんせインドア人間の僕ですから(笑)。
というわけで、今日はやや唐突にジョー・コッカーいきます。
ただしもちろん、今年になって聴いているのですが、それは後ほど。
なお、記事のタイトルは、長いので、不承不承に省略しましたが、
でもこの場合はそれで通じるかなと。
ジョー・コッカーとの出会いは、僕の年代ならやはり
映画「愛と青春の旅立ち」のテーマ曲であり、
ジェニファー・ウォーンズ Jennifer Warnsと共演した
Up Where We Belongという人が多いでしょうか、僕もです。
僕は、その前から、ビートルズの曲をカバーしてヒットさせた
ビートルズとほぼ同時代の人として存在は知っていたのですが、
その曲のビデオクリップを見て、手を震わせながら力唱する姿に、
「生きた伝説」という言葉が頭をよぎりました。
翌日の学校でその歌い方が話題になり、手つきを真似したりして、
あの人はアル中なのかな、と。
彼はアルコールと麻薬の中毒を克服したそうなのですが、
でも実際にその手つきがその影響かどうかは分かりません。
しかしとにかく映像が衝撃的だったことは間違いなく、
高校生が大人の世界を知った、という感じもしました。
その曲はとってもいいと思いましたが、でもまだ10代の
若くてとんがったロック野郎だった僕には早すぎたようで、
サントラLPはもちろんドーナツ盤を買うこともありませんでした。
この曲は最近もCMで使われるなどもはやスタンダード化していて、
そんな名曲の最初に出会えたのは、でも、うれしいですね。
それからは意識はする人にはなりましたが、でもやはり
自分が聴くには大人過ぎるかなとずっと思いつつ、
初めてベスト盤のCDを買って聴いたのは30歳の頃でした。
アルバムを聴いたのも、リマスター盤が出てからで、
僕の中では、存在は古いけど音は新しい人です。
まあ、そういう人はいっぱいいるのですが(笑)。
最初に買ったベスト盤に収録のYou Are So Beautiful、
ビリー・プレストンの曲、これが90年代に一時期
ラジオでよく流れていたのを覚えていたのですが、後にそれは、
アル・パチーノ主演の映画「カリートの道」の
テーマ曲として使われていたからだと分かりました。
ジョー・コッカーの音楽スタイルは「ブルーアイドソウル」
に分類されているようですが、このスタイルって、
意識して黒人のソウルっぽく歌ったり音作りをしている人と、
歌うと自然にソウルっぽくなる人がいるような気がしていて、
ジョー・コッカーは後者ではないかと感じます。
ソウルっぽさがイコール黒っぽさというだけではなく、
もっと大きな枠の中の「ソウル=魂」がこもった歌。
あくまでも僕の感じなのですが、ジョー・コッカーの場合は、
大人しく静かに歌おうとしてもどだい無理なのではないかと。
あ、いやもちろん歌の中で熱いだけでは伝わらなくて、
技巧として静かに歌う部分はもちろんあるにしても、
そうした心の熱さが極めて真っ直ぐに伝わってくる人ですね。
前に、ウィリー・ネルソンの時に、ウィリー・ネルソンは
ウィリー・ネルソンでしかあり得ないと書きましたが、
ジョー・コッカーもそうした音の世界を持った人でしょう。
くどくどと書いてきてこんな言い方もなんですが、
ジョー・コッカーの場合は聴けばすべて伝わる、と。
参加メンバーが顔写真付きでブックレットの裏に紹介され、
まさに「友だちからの助け」で完成したことを物語っています。
メンバーの中のクリス・ステイントン Chris Staintonは
当時のジョーの片腕的キーボード奏者で作曲もしています。
僕は、2003年のエリック・クラプトンの札幌ドーム公演で、
彼の姿を見ているように、息の長い活動を続けている人。
ギターのヘンリー・マッカロク Henry McCullouchは
後にウィングスのメンバーになりすぐに脱退します。
そして目を引くのが2人の大物、まずひとりは、
当時若くして既に英国ロック界の重鎮的存在だった(多分)、
スティーヴ・ウィンウッド Steve Winwood、
もうひとりはかのジミー・ペイジ Jimmy Page。
ペイジはレッド・ツェッペリン結成前には、
スタジオ・ミュージシャンとして活躍しており、
彼の名前を他のアーティストで見つけるとうれしくなります。
ただし、ジョー・コッカーのこのアルバムのリリースは、
Zepの1枚目より後なのですが、契約問題その他で何か
からくりがありそうで、もう少し調べてみたいです。
なおペイジはTr2、4、5、7、9とボーナスの11、12に参加。
ウィンウッドは長いキャリアを中抜けで何枚か聴いていますが、
そろそろ真面目に聴きたいと常々思っている人です。
しかしその前に、このアルバムでそれが露呈されるのですが、
また追って話します。
02 今日のA公園の松はジョー・コッカーみたい

Tr1:Feeling Alright
(Dave Mason)
弟が突然デイヴ・メイソンを聴き始めました。
正月にひとまず3枚のCDを買ってきたものですが、
紙ジャケなどで古い年代のものを揃えられることで、
集め始めたのだと思います。
デイヴ・メイソンのことを調べているうちに、
この曲が彼の曲だと知りました。
はい、知らなかったのです。
しかもトラフィック Trafficの曲だったなんて。
はい、聴いていなかったのです、CD持ってますが・・・
それを知ってまたジョー・コッカーを聴き始めた一方、
トラフィックのこの曲が入ったアルバムも聴き始めました。
でも、トラフィックはまだ到底記事にできるほどではないので
今回はよく聴いたジョー・コッカーにしたというわけです。
この曲はジョーのこれを聴いて一発で大好きになりました。
ちょっと洒落たラテンっぽいのりの軽やかな曲で、
タイトルを歌うサビのシンプルさがぐさっと心に刺さってきて、
そこばかり何度も何度も口ずさんでしまう、名曲ですね。
Tr2:Bye Bye Blackbird
(Henderson - Dixon)
あらら「鳥の名前」の曲がここにもありました・・・
これは調べたところ、1920年代の古い曲ということで、
古くさい響きの曲だけどそこまで古いとは予想外、しかし
そんな曲を見つけて歌って自分のものにしたセンスがいいですね。
ギターソロはもうどう聴いてもジミー・ペイジ。
指が弦に引っかかるようなたどたどしい弾き方は、
しかしそれが持ち味なので僕はそこが好きですよ。
キレがいい女性コーラス陣も気持ちが入っています。
Tr3:Change In Louise
(Joe Cocker - Chris Stainton)
自作曲とカバーを混ぜて対等に歌うのはソウルではよくあること。
熱唱型のブルージーな曲で、たとえばバッド・カンパニーとか
ホワイトスネイクといった英国ロックにつながっていくタイプの曲。
Tr4:Marjorine
(Joe Cocker - Chris Stainton)
続いて自作で英国で「再デビュー」を果たした曲。
ロックにはよくある呪文のような重たい響きの曲。
「マージョリーン」というのもちょっと不気味というか
薬か何かを連想させられる名前。
でも曲は胸に迫ってくる厚くて熱い曲。
自作の曲ではやっぱりこれがいちばん印象的かな。
Tr5:Just Like A Woman
(Bob Dylan)
ボブ・ディランのかの名曲を教会音楽風にアレンジ。
こうすることにより、旋律の良さはディランより出ているかな。
この中では最も落ち着いていて、歌と演奏がうまくとろけたアレンジ。
Tr6:Do I Still Figure In Your Life ?
(Peter Dello)
作曲者は英国のシンガー・ソングライターであり、この曲は、
その人が組んでいたバンドの1967年のヒット曲とのこと。
オリジナルはきっともっと明るくアップテンポで乾いているのでは、
と思わせるのがジョー・コッカーの個性でしょうかね。
これは曲自体がソウルっぽいと感じさせますね。
オルガンはスティーヴ・ウィンウッド。
Tr7:Sandpaper Cadillac
(Joe Cocker - Chris Stainton)
ダイナミックなギターとピアノの動きに乗せられ、
落ち着いた流れの中に一瞬だけはちきれた歌メロが出てきて
大人しいけれど劇的な曲。
03 今朝はA公園に着くと散策路は未踏の雪の道

Tr8:Don't Let Me Be Misunderstood
(Bennie Benjamin - Gloria Caldwell - Sol Marcus)
アニマルズの持ち歌としてあまりにも有名であり、
エルヴィス・コステロも僕のリアルタイムで歌っていたし、
それ以上に日本人には尾藤イサオの曲として有名なこの曲、
曲自体についてはあまり言うこともないでしょう。
志村けんもコントの中で歌っていましたし(笑)。
元々はニーナ・シモンの曲ということです。
ただ、あの「てんてれてんてれてぇ~ん てれれんててぇて」
というイントロを排除して、まったく別の、まるで幽霊のような
響きのギターリフに変えているのが面白い。
曲の流れとしては、僕はこんなじゃないともがいていたけれど、
結局は心の迷路にはまりこんで抜け出せなくなってしまい、
友だちの「少しの」助けが必要になる、というわけか・・・
Tr9:With A Little Help From My Friends
(John Lennon - Paul McCartney)
いわずとしれたビートルズ The Beatlesのカバーで、
全英No.1の大ヒットを記録した名演。
僕が聴いたビートルズのカバー曲の中で、ジョーのこれは
或る意味、オリジナルを凌駕していると感じる唯一のものです。
ワルツにしてゴスペル風の大胆なアレンジを施し、
ジミー・ペイジのアタックの強いギターが心を煽りたて、
ジョーのこの世のものとも思えない凄味のあるヴォーカルは、
ただただ聴く者を圧倒して心を踏み倒しまくります。
♪ Do you need anybodyというBメロに入る前の
「でんでんでっでぇ~」というギターには痺れます。
その2回目、3'49"辺りでジョーが歌詞を歌わずに叫ぶところは、
こっちも「あぁ~っ」といろんな感情がないまぜになります。
ただ、ですね。
ジョーが歌うと、「少しだけ」手伝うなんて生易しいものではなく、
助けるほうも命がけみたいな切迫感がありますが、
それは"a little help"というモチーフからすると、どうなのだろう。
ポール・マッカートニーとジョン・レノンがこの曲に
込めた思いは、あくまでも"a little"のはずで、その証拠に、
ビートルズではリンゴ・スターが歌い、力が抜けたよい味が
出ているように思い、その辺のビートルズのセンスはさすが。
でも、じゃあジョー・コッカーのこれが「違う」かといえば、
ぜんぜん違わない、これはこれで「あり」なんです。
音楽が作曲者の手を離れて人によって解釈が違うのは、
当たり前でありそこが楽しみなわけで、大仰に聴こえても、
ジョーにとってはあくまでも"a little"なのでしょうね。
乗り越えるべきものが自分には大きすぎたのかな(酒と薬と)。
なんて能書き言ってますが、とにかくこの曲は、
圧倒的なクオリティですべての人を黙らせます。
逆に、ジョーのこれを聴いてからリンゴのを聴くと、
もっと真面目に助けてやれよと感じるでしょうね(笑)。
Tr10:I Shall Be Released
(Bob Dylan)
ボブ・ディランのプロテストソングサイドの名曲。
前の曲で「少しの」助けを借り、きっと解放されるだろう
という流れがうまいですね、納得。
曲も切迫感から逃れ、まだ頼りなげな中にも明るい兆しがという、
ソフトで落ち着いた響きになっています。
その雰囲気を演出するのに大きな役割を果たすキーボードは
スティーヴ・ウィンウッドによるもの、さすが。
「気分はいいよ」と1曲目で歌い始めて、いろいろ体験して、
最後の3曲をこの感興の流れに仕立てるというのは、
アルバムとしてもよく考えられていることを感じます。
今回は2曲のボーナストラックにも触れます。
Tr11:The New Age Of Lily
(Joe Cocker - Chris Stainton)
これはTr4のシングルB面曲としてリリース。
ジョーの声が他とちょっと違って聴こえてきて、
最初はクリスが歌っているのかと思ったくらい。
他の人が歌うともっと素軽いポップソングになったかな。
まあ、それなりに軽くて楽しい曲ですが。
Tr12:Something's Going On
(Joe Cocker - Chris Stainton)
これは表題曲Tr9のシングルB面曲としてリリース。
こちらはもっと明るく楽しいせっかちな響きの曲。
ジミー・ペイジのギターがうまく煽っています。
後半のマイナー調の歌メロの部分は、なにかどこかで
聴いたことがあるような感じだけど、思い出せない・・・
シングルのB面はどちらも軽い曲なのは興味深いですね。
そちらの面もほんとはもっと押し出したいのかも。
これは、ロックのヴォーカルアルバムとしては
最上の部類の1枚ではないかと。
ジミー・ペイジがいることを知っていれば、
もっと若い頃から聴いていたかなと思いますが(笑)、
そんなこと言っても意味がないですね、音楽はタイミングだから。
ジョー・コッカーを聴くと、落ち着くんだけど熱くなるという、
相反することを不自然なく感じている自分に気づきます。
自分の気持ちが表に出てくるのを感じます。
すっきりした、という感じじゃないんだけど、でも、
大切なものは心に残らなければならないんだと感じます。
◆
それにしても今回の大雪。
足掛け3日に渡って断続的降っていましたが、
だから降っているその瞬間は大雪とはあまり感じなくて、
最後に気がつくと大雪だった、という感じがしました。
今日の午後はほんとに、
雪かきと記事を書くだけで終わりました(笑)。
雪かきで明日は筋肉や関節が痛くならないか心配・・・
というわけで今日のおやつは
04

六花亭の「ほたてまん」を
タジン鍋で蒸して食べました(笑)。
中は味付けしてほぐされたほたての貝柱です。

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Joe Cocker
ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ
ジョー・コッカー (1969)
一昨日から今朝にかけての札幌は雪がたくさん降りました。
特に僕の家の辺りでは、昨夜から今朝が多かった。
寝る前に家の周りの雪かきをしたのですが、起きてみると、
20cmくらいが新たに降っていたようでした。
今日はだから昼からは雪かきに追われて過ごしました。
そんな午後は、ゆっくりと音楽と向き合って、
その勢いでアルバムの記事を上げたくなるものです。
なんせインドア人間の僕ですから(笑)。
というわけで、今日はやや唐突にジョー・コッカーいきます。
ただしもちろん、今年になって聴いているのですが、それは後ほど。
なお、記事のタイトルは、長いので、不承不承に省略しましたが、
でもこの場合はそれで通じるかなと。
ジョー・コッカーとの出会いは、僕の年代ならやはり
映画「愛と青春の旅立ち」のテーマ曲であり、
ジェニファー・ウォーンズ Jennifer Warnsと共演した
Up Where We Belongという人が多いでしょうか、僕もです。
僕は、その前から、ビートルズの曲をカバーしてヒットさせた
ビートルズとほぼ同時代の人として存在は知っていたのですが、
その曲のビデオクリップを見て、手を震わせながら力唱する姿に、
「生きた伝説」という言葉が頭をよぎりました。
翌日の学校でその歌い方が話題になり、手つきを真似したりして、
あの人はアル中なのかな、と。
彼はアルコールと麻薬の中毒を克服したそうなのですが、
でも実際にその手つきがその影響かどうかは分かりません。
しかしとにかく映像が衝撃的だったことは間違いなく、
高校生が大人の世界を知った、という感じもしました。
その曲はとってもいいと思いましたが、でもまだ10代の
若くてとんがったロック野郎だった僕には早すぎたようで、
サントラLPはもちろんドーナツ盤を買うこともありませんでした。
この曲は最近もCMで使われるなどもはやスタンダード化していて、
そんな名曲の最初に出会えたのは、でも、うれしいですね。
それからは意識はする人にはなりましたが、でもやはり
自分が聴くには大人過ぎるかなとずっと思いつつ、
初めてベスト盤のCDを買って聴いたのは30歳の頃でした。
アルバムを聴いたのも、リマスター盤が出てからで、
僕の中では、存在は古いけど音は新しい人です。
まあ、そういう人はいっぱいいるのですが(笑)。
最初に買ったベスト盤に収録のYou Are So Beautiful、
ビリー・プレストンの曲、これが90年代に一時期
ラジオでよく流れていたのを覚えていたのですが、後にそれは、
アル・パチーノ主演の映画「カリートの道」の
テーマ曲として使われていたからだと分かりました。
ジョー・コッカーの音楽スタイルは「ブルーアイドソウル」
に分類されているようですが、このスタイルって、
意識して黒人のソウルっぽく歌ったり音作りをしている人と、
歌うと自然にソウルっぽくなる人がいるような気がしていて、
ジョー・コッカーは後者ではないかと感じます。
ソウルっぽさがイコール黒っぽさというだけではなく、
もっと大きな枠の中の「ソウル=魂」がこもった歌。
あくまでも僕の感じなのですが、ジョー・コッカーの場合は、
大人しく静かに歌おうとしてもどだい無理なのではないかと。
あ、いやもちろん歌の中で熱いだけでは伝わらなくて、
技巧として静かに歌う部分はもちろんあるにしても、
そうした心の熱さが極めて真っ直ぐに伝わってくる人ですね。
前に、ウィリー・ネルソンの時に、ウィリー・ネルソンは
ウィリー・ネルソンでしかあり得ないと書きましたが、
ジョー・コッカーもそうした音の世界を持った人でしょう。
くどくどと書いてきてこんな言い方もなんですが、
ジョー・コッカーの場合は聴けばすべて伝わる、と。
参加メンバーが顔写真付きでブックレットの裏に紹介され、
まさに「友だちからの助け」で完成したことを物語っています。
メンバーの中のクリス・ステイントン Chris Staintonは
当時のジョーの片腕的キーボード奏者で作曲もしています。
僕は、2003年のエリック・クラプトンの札幌ドーム公演で、
彼の姿を見ているように、息の長い活動を続けている人。
ギターのヘンリー・マッカロク Henry McCullouchは
後にウィングスのメンバーになりすぐに脱退します。
そして目を引くのが2人の大物、まずひとりは、
当時若くして既に英国ロック界の重鎮的存在だった(多分)、
スティーヴ・ウィンウッド Steve Winwood、
もうひとりはかのジミー・ペイジ Jimmy Page。
ペイジはレッド・ツェッペリン結成前には、
スタジオ・ミュージシャンとして活躍しており、
彼の名前を他のアーティストで見つけるとうれしくなります。
ただし、ジョー・コッカーのこのアルバムのリリースは、
Zepの1枚目より後なのですが、契約問題その他で何か
からくりがありそうで、もう少し調べてみたいです。
なおペイジはTr2、4、5、7、9とボーナスの11、12に参加。
ウィンウッドは長いキャリアを中抜けで何枚か聴いていますが、
そろそろ真面目に聴きたいと常々思っている人です。
しかしその前に、このアルバムでそれが露呈されるのですが、
また追って話します。
02 今日のA公園の松はジョー・コッカーみたい

Tr1:Feeling Alright
(Dave Mason)
弟が突然デイヴ・メイソンを聴き始めました。
正月にひとまず3枚のCDを買ってきたものですが、
紙ジャケなどで古い年代のものを揃えられることで、
集め始めたのだと思います。
デイヴ・メイソンのことを調べているうちに、
この曲が彼の曲だと知りました。
はい、知らなかったのです。
しかもトラフィック Trafficの曲だったなんて。
はい、聴いていなかったのです、CD持ってますが・・・
それを知ってまたジョー・コッカーを聴き始めた一方、
トラフィックのこの曲が入ったアルバムも聴き始めました。
でも、トラフィックはまだ到底記事にできるほどではないので
今回はよく聴いたジョー・コッカーにしたというわけです。
この曲はジョーのこれを聴いて一発で大好きになりました。
ちょっと洒落たラテンっぽいのりの軽やかな曲で、
タイトルを歌うサビのシンプルさがぐさっと心に刺さってきて、
そこばかり何度も何度も口ずさんでしまう、名曲ですね。
Tr2:Bye Bye Blackbird
(Henderson - Dixon)
あらら「鳥の名前」の曲がここにもありました・・・
これは調べたところ、1920年代の古い曲ということで、
古くさい響きの曲だけどそこまで古いとは予想外、しかし
そんな曲を見つけて歌って自分のものにしたセンスがいいですね。
ギターソロはもうどう聴いてもジミー・ペイジ。
指が弦に引っかかるようなたどたどしい弾き方は、
しかしそれが持ち味なので僕はそこが好きですよ。
キレがいい女性コーラス陣も気持ちが入っています。
Tr3:Change In Louise
(Joe Cocker - Chris Stainton)
自作曲とカバーを混ぜて対等に歌うのはソウルではよくあること。
熱唱型のブルージーな曲で、たとえばバッド・カンパニーとか
ホワイトスネイクといった英国ロックにつながっていくタイプの曲。
Tr4:Marjorine
(Joe Cocker - Chris Stainton)
続いて自作で英国で「再デビュー」を果たした曲。
ロックにはよくある呪文のような重たい響きの曲。
「マージョリーン」というのもちょっと不気味というか
薬か何かを連想させられる名前。
でも曲は胸に迫ってくる厚くて熱い曲。
自作の曲ではやっぱりこれがいちばん印象的かな。
Tr5:Just Like A Woman
(Bob Dylan)
ボブ・ディランのかの名曲を教会音楽風にアレンジ。
こうすることにより、旋律の良さはディランより出ているかな。
この中では最も落ち着いていて、歌と演奏がうまくとろけたアレンジ。
Tr6:Do I Still Figure In Your Life ?
(Peter Dello)
作曲者は英国のシンガー・ソングライターであり、この曲は、
その人が組んでいたバンドの1967年のヒット曲とのこと。
オリジナルはきっともっと明るくアップテンポで乾いているのでは、
と思わせるのがジョー・コッカーの個性でしょうかね。
これは曲自体がソウルっぽいと感じさせますね。
オルガンはスティーヴ・ウィンウッド。
Tr7:Sandpaper Cadillac
(Joe Cocker - Chris Stainton)
ダイナミックなギターとピアノの動きに乗せられ、
落ち着いた流れの中に一瞬だけはちきれた歌メロが出てきて
大人しいけれど劇的な曲。
03 今朝はA公園に着くと散策路は未踏の雪の道

Tr8:Don't Let Me Be Misunderstood
(Bennie Benjamin - Gloria Caldwell - Sol Marcus)
アニマルズの持ち歌としてあまりにも有名であり、
エルヴィス・コステロも僕のリアルタイムで歌っていたし、
それ以上に日本人には尾藤イサオの曲として有名なこの曲、
曲自体についてはあまり言うこともないでしょう。
志村けんもコントの中で歌っていましたし(笑)。
元々はニーナ・シモンの曲ということです。
ただ、あの「てんてれてんてれてぇ~ん てれれんててぇて」
というイントロを排除して、まったく別の、まるで幽霊のような
響きのギターリフに変えているのが面白い。
曲の流れとしては、僕はこんなじゃないともがいていたけれど、
結局は心の迷路にはまりこんで抜け出せなくなってしまい、
友だちの「少しの」助けが必要になる、というわけか・・・
Tr9:With A Little Help From My Friends
(John Lennon - Paul McCartney)
いわずとしれたビートルズ The Beatlesのカバーで、
全英No.1の大ヒットを記録した名演。
僕が聴いたビートルズのカバー曲の中で、ジョーのこれは
或る意味、オリジナルを凌駕していると感じる唯一のものです。
ワルツにしてゴスペル風の大胆なアレンジを施し、
ジミー・ペイジのアタックの強いギターが心を煽りたて、
ジョーのこの世のものとも思えない凄味のあるヴォーカルは、
ただただ聴く者を圧倒して心を踏み倒しまくります。
♪ Do you need anybodyというBメロに入る前の
「でんでんでっでぇ~」というギターには痺れます。
その2回目、3'49"辺りでジョーが歌詞を歌わずに叫ぶところは、
こっちも「あぁ~っ」といろんな感情がないまぜになります。
ただ、ですね。
ジョーが歌うと、「少しだけ」手伝うなんて生易しいものではなく、
助けるほうも命がけみたいな切迫感がありますが、
それは"a little help"というモチーフからすると、どうなのだろう。
ポール・マッカートニーとジョン・レノンがこの曲に
込めた思いは、あくまでも"a little"のはずで、その証拠に、
ビートルズではリンゴ・スターが歌い、力が抜けたよい味が
出ているように思い、その辺のビートルズのセンスはさすが。
でも、じゃあジョー・コッカーのこれが「違う」かといえば、
ぜんぜん違わない、これはこれで「あり」なんです。
音楽が作曲者の手を離れて人によって解釈が違うのは、
当たり前でありそこが楽しみなわけで、大仰に聴こえても、
ジョーにとってはあくまでも"a little"なのでしょうね。
乗り越えるべきものが自分には大きすぎたのかな(酒と薬と)。
なんて能書き言ってますが、とにかくこの曲は、
圧倒的なクオリティですべての人を黙らせます。
逆に、ジョーのこれを聴いてからリンゴのを聴くと、
もっと真面目に助けてやれよと感じるでしょうね(笑)。
Tr10:I Shall Be Released
(Bob Dylan)
ボブ・ディランのプロテストソングサイドの名曲。
前の曲で「少しの」助けを借り、きっと解放されるだろう
という流れがうまいですね、納得。
曲も切迫感から逃れ、まだ頼りなげな中にも明るい兆しがという、
ソフトで落ち着いた響きになっています。
その雰囲気を演出するのに大きな役割を果たすキーボードは
スティーヴ・ウィンウッドによるもの、さすが。
「気分はいいよ」と1曲目で歌い始めて、いろいろ体験して、
最後の3曲をこの感興の流れに仕立てるというのは、
アルバムとしてもよく考えられていることを感じます。
今回は2曲のボーナストラックにも触れます。
Tr11:The New Age Of Lily
(Joe Cocker - Chris Stainton)
これはTr4のシングルB面曲としてリリース。
ジョーの声が他とちょっと違って聴こえてきて、
最初はクリスが歌っているのかと思ったくらい。
他の人が歌うともっと素軽いポップソングになったかな。
まあ、それなりに軽くて楽しい曲ですが。
Tr12:Something's Going On
(Joe Cocker - Chris Stainton)
これは表題曲Tr9のシングルB面曲としてリリース。
こちらはもっと明るく楽しいせっかちな響きの曲。
ジミー・ペイジのギターがうまく煽っています。
後半のマイナー調の歌メロの部分は、なにかどこかで
聴いたことがあるような感じだけど、思い出せない・・・
シングルのB面はどちらも軽い曲なのは興味深いですね。
そちらの面もほんとはもっと押し出したいのかも。
これは、ロックのヴォーカルアルバムとしては
最上の部類の1枚ではないかと。
ジミー・ペイジがいることを知っていれば、
もっと若い頃から聴いていたかなと思いますが(笑)、
そんなこと言っても意味がないですね、音楽はタイミングだから。
ジョー・コッカーを聴くと、落ち着くんだけど熱くなるという、
相反することを不自然なく感じている自分に気づきます。
自分の気持ちが表に出てくるのを感じます。
すっきりした、という感じじゃないんだけど、でも、
大切なものは心に残らなければならないんだと感じます。
◆
それにしても今回の大雪。
足掛け3日に渡って断続的降っていましたが、
だから降っているその瞬間は大雪とはあまり感じなくて、
最後に気がつくと大雪だった、という感じがしました。
今日の午後はほんとに、
雪かきと記事を書くだけで終わりました(笑)。
雪かきで明日は筋肉や関節が痛くならないか心配・・・
というわけで今日のおやつは
04

六花亭の「ほたてまん」を
タジン鍋で蒸して食べました(笑)。
中は味付けしてほぐされたほたての貝柱です。
2013年11月06日
THE LONG RUN イーグルス
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です!
突然思い出して、突然口ずさんで
突然聴きたくなるアルバムってありますよね。
それは、若い頃に聴いたものであればあるほど。
01 今回は鼻が「長く」見えるように撮ってみました

THE LONG RUN The Eagles
ロング・ラン イーグルス released in 1979
曲が揃っているのにアルバムとして通して聴くとどうかな、
というアルバムはままあります。
その多くは、「散漫な」といわれるものでしょうか。
イーグルスのこのアルバムは、僕が思うにその最たるもので、
半分が名曲級の素晴らしい曲なのに、
アルバムとして聴くと、ちょっと待った、となってしまう。
イーグルスは、一昨年、28年振りに新譜を出したとして、
NHK夜9時のニュースでも取り上げられるほど話題になりました。
そのアルバムはもちろんとてもよく、円熟しても枯れてはいない、
むしろ若々しさを感じる、充実したアルバムでした。
本日のお題のこれは、1979年リリース、
ひとまず「現役」当時の最後のアルバムですが、
「エゴのぶつかりあい」「プレッシャーとの闘い」
みたいな感じでよく言われています。
なんせ彼ら、前作があのロック史に燦然と輝く名曲・名盤
HOTEL CALIFORNIA、こんなにも素晴らしいアルバム、
化け物のようなアルバムを作ってしまったがために、彼らは
前作のイメージや幻影と闘わなければならなくなりました。
そして、闘った結果はというと・・・
僕がこのアルバムを初めて聴いたのは大学生の頃ですが、
やはり、世評に流されやすい年ごろだったせいもあり、
はじめから一歩引いて構えて聴いていました。
今から思うと、音楽とまっすぐ向き合っていなかったわけですが、
それは、仕方ないですかね。
でも、このアルバム、「散漫な」、その通り感じました。
これは多分、予備知識がなくてもそう感じたのではないかな。
そして実際もうひとつ、僕自身の体験からも、
このアルバムは最初はあまりいい印象を持ちませんでした。
僕が最初に買ったイーグルスのCDは、後期のベスト盤である
GREATEST HITS VOLUME 2だったのですが、
そのベスト盤の編集がとても素晴らしく、
その中でのこのアルバムの曲の出てくる曲順が、
絶妙ともいえる配置だった、ということがありました。
このベスト盤は、数多いロックのベスト盤の中でも、
僕が編集が素晴らしいと思う5枚のうちの1枚です。
02

これがその僕が最初に買ったベスト盤ですが、
参考までにそのベスト盤アルバムの曲順を記すと
Hotel California
Heartache Tonight
Seven Bridges Road
Victim Of Love
The Sad Cafe
Life In The Fast Lane
I Can't Tell You Why
New Kid In Town
The Long Run
After The Thrill Is Gone
太字の曲がこのアルバムの曲ですが、
特にB面にあたる6曲目からの流れが素晴らしい。
ベスト盤と比べるのは反則かもしれないのは分かりますが、
ここではあくまでも僕個人の体験と考えを語らせてもらうと、
「良いアルバム」と思う要素のうち、このTHE LONG RUNは
曲順、流れがよくないと思いました。
ベスト盤はもちろん、4枚のアルバムから集めたのであるから、
流れを考えて編集できるのはよく分かります。
一方でこのアルバム、手詰まり感があって、曲を選べないし、
とにかく契約があって出すことだけに迫られて、余裕がなかった、
だから曲順なんかどうでもよかったのかもしれない、と。
最後に録音したアルバムといえばやはり、
ビートルズのABBEY ROADを思い浮かべてしまいますが、
イーグルスの場合、状況はまるで違っていたことでしょう。
ビートルズの場合は、誰も口にはしていなかったようだけど、
4人が最後と覚悟を決めてビートルズを「演じきって」みせたけど、
イーグルスは、この時点ではやめることは考えておらず、
むしろ、どう延命するかを考えていたのかもしれません。
でもそれは、契約の上だけからの縛りだけであって、
仲間として続けたかったかはまた別問題だったのではないかな。
まあ、ポップソングはそもそも作り物の世界ですから、
ある程度は外側をつくろうことは可能だと思いますが、
そう考えると、イーグルスはまだ「正直」だったのかな。
ビートルズのように「演じきる」ことが出来なかったというか。
このアルバムは、曲ごとに聴くとさすがの出来なのですが、
「曲間」、文章でいう「行間」からは何も感じ取れません。
曲と曲が有機的につながっていないというか、
ただなんとなくそこに置いただけという感じが強くします。
そこが「散漫」という印象につながるのでしょう。
もうひとつ僕が最初に違和感を覚えたのは、
これ、音が妙に新しく、明るく、浮ついていて軽くて、
ずしんと腹に響いてこない音、そんな感じを受けました。
縛られた状況下、もう開き直って明るくやるしかないというか。
だけどそれも、見え透いた、作られた面であると感じてしまう。
そしてその軽さは、もしイーグルスがその後も続いていれば、
次はもっとAORっぽい音になっていたかもしれない、とも思いました。
だから、28年後に出たアルバムは、このアルバムよりは
むしろ若くなっていたのには、ある面、ほっとしました。
ただ、その音が面白いアルバムではありますね。
後で思えば、僕はそのことに実は最初から気づいてはいたんだけど、
僕は昔はとにかく「鼻歌で歌える歌メロ」を求めていたので、
「音が面白い」というのは、あまり訴えてこなかった部分でした。
でも、クラシックを聴くようになって、自分にもその面が出てきて、
いわば視野が広がったというわけですね(笑)。
何かこう気持ちの隙間にぽっと入り込んでくるような、
ギターをはじめとした楽器の音の面白さは特筆すべき点でしょう。
まあそのようなわけで、
このアルバムは、名曲級が5曲もあるにもかかわらず、
アルバムとして通して聴くと最上とは言い難い、
そんな不思議なアルバムだとずっと思って聴いてきていました。
03 ハシブトガラスのシルエット

Tr1:The Long Run
アルバムタイトル曲で明るくポップで軽快な曲だから、
景気づけに1曲目にあるのは分かるんだけど、
GREATESTでなじんた後ろから2曲目の位置が、
前の曲の「照れ隠し」になっていてよかった・・・
冒頭がこれだと、いきなり置いて行かれる感じがします。
ただ、曲は大好きで、今回これを記事にしようと思ったのは、
この曲を突然思い出したかのように口ずさんだからです。
新しいタイプのR&Bという感じで、ポップで分かりやすく、
ドン・ヘンリーの声がよく出ていてカッコいい。
ただ、声を張り上げる曲なので鼻歌には向かないけど、
車などで声を張り上げて歌うのがまた気持ちがいい!
いや、ほんと、曲自体は大好きです。
Tr2:I Can't Tell You Why
今のティモシー・B・シュミットがあるのはこの曲のおかげ
といっても過言ではない、素晴らしいバラード。
このアルバムからイーグルスに加入したTBSは、
もちろんポコなどでそれまでもいい仕事をしてきていた人ですが、
大ヒットしたアルバムの印象的なバラードを歌うことにより、
多くの人がその魅力に気づいたのではないでしょうか。
もちろん僕だって最初に彼の声を聴いたのはこの曲でしたし、
ポコにいたことを知ったのはかなり後になってのことです。
この曲はほんと、しみじみいい曲だなぁ。
それ以上言うとかえってイメージが壊れそう。
僕が接した2、3人の、この曲を同時代に聴いていた知り合いは
みんな、「異様に」この曲が好きなんです。
ああ、いい曲だよね、以上に、思い入れがある様子で話していました。
僕は前述ベスト盤で最初に聴いて、もちろん最初から
とってもいい曲だなと思いましたが、でも、
若くてとんがったロック野郎には少しソフト過ぎるかな、と(笑)。
だけど、年を追うごとに僕も大好きになってゆき、
今では僕も「異様に好き」の類かもしれません。
これはグレン・フライのギターソロも、
テクニック的には普通だけど、歌うギターソロのお手本といっていい、
わざわざグレンがギターソロであると明記されているくらい、
ほんと素晴らしい音を聴かせてくれる名演ですね。
寂しい中に勇気づけられる部分があるし、このナイーヴさは
イーグルスのみならずロック界広しといえども、TSBにしか出せない味。
ただ、曲として素晴らしいのですが、アルバムの中で見ると、
これが2曲目というのは、なにか落ち着かない感じもします。
1曲目で置いて行かれた上に、もう終わるの、みたいな・・・
まあ、アルバム自体が終わりだから、仕方ないのかな。
ともあれ、ジョン・フォガティのアルバムに参加したり、
ソロアルバムを出したりと(買いました)、
TBSが活発に音楽活動をしているのは、うれしい限りです。
Tr3:In The City
これはいいね。
上述ベスト盤には入っていないけど、それは単に
アルバムごとのバランスを取るのにはじかれただけでしょう。
これも名曲といっていい。
ジョー・ウォルシュの曲(共作)、ヴォーカル。
いかにも都会的な音作りで、ニュー・ヨークの喧騒をイメージするけど、
でも彼らはウェストコーストだぞ・・・
ジョーの声質からして、都会の子どもみたいなイメージ。
ただ、この曲は、ジョーのヴォーカルもこれ1曲だけだし、
アルバムの中でどこに置くか迷う曲かもしれない、というか
アルバムの色には微妙にそぐわない曲かもしれません。
Tr4:The Disco Stranger
ドンがずっと高音で歌い続けるポップな曲だけど、
Tr1と違って歌メロがつかみにくく、空元気みたいな曲。
ディスコを皮肉ったのか、まるで踊れない変わったリズム感は、
皮肉屋ドンの面目躍如。
でもこれ、気がつくと終わっていて、消化不良な感じは否めないですね。
Tr5:King Of Hollywood
重々しくフェイドインして始まるちょっとブルージーな曲。
何を目指しているかいまひとつ読めない曲。
これがA面の最後というのがまた、どうなのか。
04 このミズナラの樹形はハート形に見えないか・・・

Tr6:Heartache Tonight
彼ら5曲目にして最後のNO.1ヒット曲。
ドンとグレンにボブ・シーガーとJ.D.サウザー共作という、
ビルボード誌でNO.1になったロックの曲では
作曲陣が最も豪華なのじゃないかという曲。
それにしてもパワフルなロックンロールで、歌も演奏も、
特に最後のグレンの雄叫びは、「こいつら肉食ってるよなぁ」と、
いかにもアメリカ人、食文化の違いを感じました(笑)。
ギターでイントロを弾くと気持ちいいし、歌もいい。
やはり鼻歌には向かないけど、声を張り上げて歌うといい曲。
トリッキーなギターも相まり、さすがイーグルスというだけあって、
心を「鷲掴み」にされ振り回される強引な曲。
ほんとに心が痛むの、と言いたくもなるけど・・・
この曲がB面の1曲目というのはいいと思います。
が、じゃあA面1曲目、冒頭というのはやっぱり恐いかな・・・
Tr7:Those Shoes
ここでまた沈んだ曲だけど、その中でまるで浮いている
みぃみぃ鳴るギターが面白い。
音の面白さというのは、サウンドでごまかすしかできなかった、
ということなのかな・・・
Tr8:Teenage Jail
どろっとした、うねうねした曲で、
何かから抜け出せないというイメージではありますね。
このアルバム、曲は重いけど音が軽いのは、違和感ですかね・・・
ドン・フェルダーのギターソロは素晴らしいけど。
Tr9:The Greeks Don't Want No Freaks
前の曲が終わりきらないうちに焦ったように始まる、
最後の前に盛り上げるだけ盛り上げとこうという異様に明るい曲。
曲は古臭いR&R風で、そこに贅肉たっぷりの音が乗っかる。
もう、シンプルな曲は作れなかったのかな。
コーラスのゲストはジミー・バフェット。
この曲は、「変な曲」として実は最初から印象に残っていました。
「面白い音」が凝縮された1曲、だけどまた急いたように終わる。
この曲は、最後がそれである以上、ここにあるのはいいと思います。
Tr10:The Sad Cafe
これは名曲ですね、素晴らしい、しみてきます。
僕が洋楽の奥深さを知った曲のひとつ。
これまたニューヨークの街角が似合いそうな曲で、
クリスマスを都会でひとり寂しく過ごす男、というイメージかな。
ドン、グレン、ジョーにJ.D.サウザーの共作、傑作。
寂しさを助長する、あまりにも素晴らしいサックスは
デヴィッド・サンボーン、僕はその名前をこれで覚えました。
救いようがないほど暗い曲というのではないけど、
尋常じゃないくらいに寂しさがこみ上げてくる曲。
俺ってこのまま生きていていいんだろうか、
みたいな感傷にひたらざるを得ない曲。
Tr2とこれはほんと、心に沁みるとはまさにこのことという名曲。
そして、この名曲が最後というのがまた、意味深ですね。
余韻残しまくりで終わりますが、しかし、これを聴くと、
ああ、もう終わってしまったんだな、と感じます。
まあ、28年経って復活するんですが・・・
と書くと、このアルバムは良くない、というか、
guitarbirdは嫌いなのかと思われたかもしれません。
好きです、どちらかというと大好きです、今では。
僕は、ビートルズを聴き育って「研究」していたせいで、
若い頃はとにかく「アルバム至上主義」でした。
全曲歌って、全曲ギターで弾いてやるという意気込みで聴き、
そして、アルバムとして良いことに最大の価値を見出していました。
名曲が1曲あってもアルバムとしてつまらなければだめ、みたいな。
でも今は、それほど真剣に聴き込まないことが多くなったので、
そうなると、いい曲がたくさんあるほうが聴きやすくなりました。
また、前述のように、音の面白さを感じるようになったこともあります。
そういう観点でこのアルバムを聴くと、むしろ、
名曲が5曲も入ったアルバムなんてそうめったにないし、
音は面白いし、ノリは軽くて聴きやすいし、
昔と違って、これは「良いアルバム」だと思えるようになりました。
「良い」の意味が、昔とは違ってきているということでしょう。
よくよく考えると、僕も傲慢でしたね。
こんなに素晴らしいアルバムを、曲順と流れという点だけで、
「良くない」アルバムとして扱っていたのだから・・・
なお、良くない曲は飛ばして聴けばいいのでは、
と言われそうですが、僕は、アルバムを聴く時は、
何があっても絶対に飛ばさないで聴かないと気が済まないので、
それはできませんでした、今でももちろん。
これも「アルバム至上主義」の影響であり、名残です。
まあしかし今は、ずっと集中して聴き続けるわけではないので、
あまり好きじゃない曲は、気がつくと終わっている、
ということも、あるにはありますね(笑)。
ただし、「良い」と感じるようなったのは、もうひとつ、
なんであれかれこれ20年聴き続けてきているということが、
重要なのでしょうね。
音楽は時宜を選ぶものであって、いつ、どのタイミングで
「良い」アルバムになるかは、自分でも分からないのですから。
そしてそれが音楽を聴き続ける楽しみだとも思います。
と、この記事を書きながらもう、3回目を聴いています。
写真へのコメントも
大歓迎です!
突然思い出して、突然口ずさんで
突然聴きたくなるアルバムってありますよね。
それは、若い頃に聴いたものであればあるほど。
01 今回は鼻が「長く」見えるように撮ってみました

THE LONG RUN The Eagles
ロング・ラン イーグルス released in 1979
曲が揃っているのにアルバムとして通して聴くとどうかな、
というアルバムはままあります。
その多くは、「散漫な」といわれるものでしょうか。
イーグルスのこのアルバムは、僕が思うにその最たるもので、
半分が名曲級の素晴らしい曲なのに、
アルバムとして聴くと、ちょっと待った、となってしまう。
イーグルスは、一昨年、28年振りに新譜を出したとして、
NHK夜9時のニュースでも取り上げられるほど話題になりました。
そのアルバムはもちろんとてもよく、円熟しても枯れてはいない、
むしろ若々しさを感じる、充実したアルバムでした。
本日のお題のこれは、1979年リリース、
ひとまず「現役」当時の最後のアルバムですが、
「エゴのぶつかりあい」「プレッシャーとの闘い」
みたいな感じでよく言われています。
なんせ彼ら、前作があのロック史に燦然と輝く名曲・名盤
HOTEL CALIFORNIA、こんなにも素晴らしいアルバム、
化け物のようなアルバムを作ってしまったがために、彼らは
前作のイメージや幻影と闘わなければならなくなりました。
そして、闘った結果はというと・・・
僕がこのアルバムを初めて聴いたのは大学生の頃ですが、
やはり、世評に流されやすい年ごろだったせいもあり、
はじめから一歩引いて構えて聴いていました。
今から思うと、音楽とまっすぐ向き合っていなかったわけですが、
それは、仕方ないですかね。
でも、このアルバム、「散漫な」、その通り感じました。
これは多分、予備知識がなくてもそう感じたのではないかな。
そして実際もうひとつ、僕自身の体験からも、
このアルバムは最初はあまりいい印象を持ちませんでした。
僕が最初に買ったイーグルスのCDは、後期のベスト盤である
GREATEST HITS VOLUME 2だったのですが、
そのベスト盤の編集がとても素晴らしく、
その中でのこのアルバムの曲の出てくる曲順が、
絶妙ともいえる配置だった、ということがありました。
このベスト盤は、数多いロックのベスト盤の中でも、
僕が編集が素晴らしいと思う5枚のうちの1枚です。
02

これがその僕が最初に買ったベスト盤ですが、
参考までにそのベスト盤アルバムの曲順を記すと
Hotel California
Heartache Tonight
Seven Bridges Road
Victim Of Love
The Sad Cafe
Life In The Fast Lane
I Can't Tell You Why
New Kid In Town
The Long Run
After The Thrill Is Gone
太字の曲がこのアルバムの曲ですが、
特にB面にあたる6曲目からの流れが素晴らしい。
ベスト盤と比べるのは反則かもしれないのは分かりますが、
ここではあくまでも僕個人の体験と考えを語らせてもらうと、
「良いアルバム」と思う要素のうち、このTHE LONG RUNは
曲順、流れがよくないと思いました。
ベスト盤はもちろん、4枚のアルバムから集めたのであるから、
流れを考えて編集できるのはよく分かります。
一方でこのアルバム、手詰まり感があって、曲を選べないし、
とにかく契約があって出すことだけに迫られて、余裕がなかった、
だから曲順なんかどうでもよかったのかもしれない、と。
最後に録音したアルバムといえばやはり、
ビートルズのABBEY ROADを思い浮かべてしまいますが、
イーグルスの場合、状況はまるで違っていたことでしょう。
ビートルズの場合は、誰も口にはしていなかったようだけど、
4人が最後と覚悟を決めてビートルズを「演じきって」みせたけど、
イーグルスは、この時点ではやめることは考えておらず、
むしろ、どう延命するかを考えていたのかもしれません。
でもそれは、契約の上だけからの縛りだけであって、
仲間として続けたかったかはまた別問題だったのではないかな。
まあ、ポップソングはそもそも作り物の世界ですから、
ある程度は外側をつくろうことは可能だと思いますが、
そう考えると、イーグルスはまだ「正直」だったのかな。
ビートルズのように「演じきる」ことが出来なかったというか。
このアルバムは、曲ごとに聴くとさすがの出来なのですが、
「曲間」、文章でいう「行間」からは何も感じ取れません。
曲と曲が有機的につながっていないというか、
ただなんとなくそこに置いただけという感じが強くします。
そこが「散漫」という印象につながるのでしょう。
もうひとつ僕が最初に違和感を覚えたのは、
これ、音が妙に新しく、明るく、浮ついていて軽くて、
ずしんと腹に響いてこない音、そんな感じを受けました。
縛られた状況下、もう開き直って明るくやるしかないというか。
だけどそれも、見え透いた、作られた面であると感じてしまう。
そしてその軽さは、もしイーグルスがその後も続いていれば、
次はもっとAORっぽい音になっていたかもしれない、とも思いました。
だから、28年後に出たアルバムは、このアルバムよりは
むしろ若くなっていたのには、ある面、ほっとしました。
ただ、その音が面白いアルバムではありますね。
後で思えば、僕はそのことに実は最初から気づいてはいたんだけど、
僕は昔はとにかく「鼻歌で歌える歌メロ」を求めていたので、
「音が面白い」というのは、あまり訴えてこなかった部分でした。
でも、クラシックを聴くようになって、自分にもその面が出てきて、
いわば視野が広がったというわけですね(笑)。
何かこう気持ちの隙間にぽっと入り込んでくるような、
ギターをはじめとした楽器の音の面白さは特筆すべき点でしょう。
まあそのようなわけで、
このアルバムは、名曲級が5曲もあるにもかかわらず、
アルバムとして通して聴くと最上とは言い難い、
そんな不思議なアルバムだとずっと思って聴いてきていました。
03 ハシブトガラスのシルエット

Tr1:The Long Run
アルバムタイトル曲で明るくポップで軽快な曲だから、
景気づけに1曲目にあるのは分かるんだけど、
GREATESTでなじんた後ろから2曲目の位置が、
前の曲の「照れ隠し」になっていてよかった・・・
冒頭がこれだと、いきなり置いて行かれる感じがします。
ただ、曲は大好きで、今回これを記事にしようと思ったのは、
この曲を突然思い出したかのように口ずさんだからです。
新しいタイプのR&Bという感じで、ポップで分かりやすく、
ドン・ヘンリーの声がよく出ていてカッコいい。
ただ、声を張り上げる曲なので鼻歌には向かないけど、
車などで声を張り上げて歌うのがまた気持ちがいい!
いや、ほんと、曲自体は大好きです。
Tr2:I Can't Tell You Why
今のティモシー・B・シュミットがあるのはこの曲のおかげ
といっても過言ではない、素晴らしいバラード。
このアルバムからイーグルスに加入したTBSは、
もちろんポコなどでそれまでもいい仕事をしてきていた人ですが、
大ヒットしたアルバムの印象的なバラードを歌うことにより、
多くの人がその魅力に気づいたのではないでしょうか。
もちろん僕だって最初に彼の声を聴いたのはこの曲でしたし、
ポコにいたことを知ったのはかなり後になってのことです。
この曲はほんと、しみじみいい曲だなぁ。
それ以上言うとかえってイメージが壊れそう。
僕が接した2、3人の、この曲を同時代に聴いていた知り合いは
みんな、「異様に」この曲が好きなんです。
ああ、いい曲だよね、以上に、思い入れがある様子で話していました。
僕は前述ベスト盤で最初に聴いて、もちろん最初から
とってもいい曲だなと思いましたが、でも、
若くてとんがったロック野郎には少しソフト過ぎるかな、と(笑)。
だけど、年を追うごとに僕も大好きになってゆき、
今では僕も「異様に好き」の類かもしれません。
これはグレン・フライのギターソロも、
テクニック的には普通だけど、歌うギターソロのお手本といっていい、
わざわざグレンがギターソロであると明記されているくらい、
ほんと素晴らしい音を聴かせてくれる名演ですね。
寂しい中に勇気づけられる部分があるし、このナイーヴさは
イーグルスのみならずロック界広しといえども、TSBにしか出せない味。
ただ、曲として素晴らしいのですが、アルバムの中で見ると、
これが2曲目というのは、なにか落ち着かない感じもします。
1曲目で置いて行かれた上に、もう終わるの、みたいな・・・
まあ、アルバム自体が終わりだから、仕方ないのかな。
ともあれ、ジョン・フォガティのアルバムに参加したり、
ソロアルバムを出したりと(買いました)、
TBSが活発に音楽活動をしているのは、うれしい限りです。
Tr3:In The City
これはいいね。
上述ベスト盤には入っていないけど、それは単に
アルバムごとのバランスを取るのにはじかれただけでしょう。
これも名曲といっていい。
ジョー・ウォルシュの曲(共作)、ヴォーカル。
いかにも都会的な音作りで、ニュー・ヨークの喧騒をイメージするけど、
でも彼らはウェストコーストだぞ・・・
ジョーの声質からして、都会の子どもみたいなイメージ。
ただ、この曲は、ジョーのヴォーカルもこれ1曲だけだし、
アルバムの中でどこに置くか迷う曲かもしれない、というか
アルバムの色には微妙にそぐわない曲かもしれません。
Tr4:The Disco Stranger
ドンがずっと高音で歌い続けるポップな曲だけど、
Tr1と違って歌メロがつかみにくく、空元気みたいな曲。
ディスコを皮肉ったのか、まるで踊れない変わったリズム感は、
皮肉屋ドンの面目躍如。
でもこれ、気がつくと終わっていて、消化不良な感じは否めないですね。
Tr5:King Of Hollywood
重々しくフェイドインして始まるちょっとブルージーな曲。
何を目指しているかいまひとつ読めない曲。
これがA面の最後というのがまた、どうなのか。
04 このミズナラの樹形はハート形に見えないか・・・

Tr6:Heartache Tonight
彼ら5曲目にして最後のNO.1ヒット曲。
ドンとグレンにボブ・シーガーとJ.D.サウザー共作という、
ビルボード誌でNO.1になったロックの曲では
作曲陣が最も豪華なのじゃないかという曲。
それにしてもパワフルなロックンロールで、歌も演奏も、
特に最後のグレンの雄叫びは、「こいつら肉食ってるよなぁ」と、
いかにもアメリカ人、食文化の違いを感じました(笑)。
ギターでイントロを弾くと気持ちいいし、歌もいい。
やはり鼻歌には向かないけど、声を張り上げて歌うといい曲。
トリッキーなギターも相まり、さすがイーグルスというだけあって、
心を「鷲掴み」にされ振り回される強引な曲。
ほんとに心が痛むの、と言いたくもなるけど・・・
この曲がB面の1曲目というのはいいと思います。
が、じゃあA面1曲目、冒頭というのはやっぱり恐いかな・・・
Tr7:Those Shoes
ここでまた沈んだ曲だけど、その中でまるで浮いている
みぃみぃ鳴るギターが面白い。
音の面白さというのは、サウンドでごまかすしかできなかった、
ということなのかな・・・
Tr8:Teenage Jail
どろっとした、うねうねした曲で、
何かから抜け出せないというイメージではありますね。
このアルバム、曲は重いけど音が軽いのは、違和感ですかね・・・
ドン・フェルダーのギターソロは素晴らしいけど。
Tr9:The Greeks Don't Want No Freaks
前の曲が終わりきらないうちに焦ったように始まる、
最後の前に盛り上げるだけ盛り上げとこうという異様に明るい曲。
曲は古臭いR&R風で、そこに贅肉たっぷりの音が乗っかる。
もう、シンプルな曲は作れなかったのかな。
コーラスのゲストはジミー・バフェット。
この曲は、「変な曲」として実は最初から印象に残っていました。
「面白い音」が凝縮された1曲、だけどまた急いたように終わる。
この曲は、最後がそれである以上、ここにあるのはいいと思います。
Tr10:The Sad Cafe
これは名曲ですね、素晴らしい、しみてきます。
僕が洋楽の奥深さを知った曲のひとつ。
これまたニューヨークの街角が似合いそうな曲で、
クリスマスを都会でひとり寂しく過ごす男、というイメージかな。
ドン、グレン、ジョーにJ.D.サウザーの共作、傑作。
寂しさを助長する、あまりにも素晴らしいサックスは
デヴィッド・サンボーン、僕はその名前をこれで覚えました。
救いようがないほど暗い曲というのではないけど、
尋常じゃないくらいに寂しさがこみ上げてくる曲。
俺ってこのまま生きていていいんだろうか、
みたいな感傷にひたらざるを得ない曲。
Tr2とこれはほんと、心に沁みるとはまさにこのことという名曲。
そして、この名曲が最後というのがまた、意味深ですね。
余韻残しまくりで終わりますが、しかし、これを聴くと、
ああ、もう終わってしまったんだな、と感じます。
まあ、28年経って復活するんですが・・・
と書くと、このアルバムは良くない、というか、
guitarbirdは嫌いなのかと思われたかもしれません。
好きです、どちらかというと大好きです、今では。
僕は、ビートルズを聴き育って「研究」していたせいで、
若い頃はとにかく「アルバム至上主義」でした。
全曲歌って、全曲ギターで弾いてやるという意気込みで聴き、
そして、アルバムとして良いことに最大の価値を見出していました。
名曲が1曲あってもアルバムとしてつまらなければだめ、みたいな。
でも今は、それほど真剣に聴き込まないことが多くなったので、
そうなると、いい曲がたくさんあるほうが聴きやすくなりました。
また、前述のように、音の面白さを感じるようになったこともあります。
そういう観点でこのアルバムを聴くと、むしろ、
名曲が5曲も入ったアルバムなんてそうめったにないし、
音は面白いし、ノリは軽くて聴きやすいし、
昔と違って、これは「良いアルバム」だと思えるようになりました。
「良い」の意味が、昔とは違ってきているということでしょう。
よくよく考えると、僕も傲慢でしたね。
こんなに素晴らしいアルバムを、曲順と流れという点だけで、
「良くない」アルバムとして扱っていたのだから・・・
なお、良くない曲は飛ばして聴けばいいのでは、
と言われそうですが、僕は、アルバムを聴く時は、
何があっても絶対に飛ばさないで聴かないと気が済まないので、
それはできませんでした、今でももちろん。
これも「アルバム至上主義」の影響であり、名残です。
まあしかし今は、ずっと集中して聴き続けるわけではないので、
あまり好きじゃない曲は、気がつくと終わっている、
ということも、あるにはありますね(笑)。
ただし、「良い」と感じるようなったのは、もうひとつ、
なんであれかれこれ20年聴き続けてきているということが、
重要なのでしょうね。
音楽は時宜を選ぶものであって、いつ、どのタイミングで
「良い」アルバムになるかは、自分でも分からないのですから。
そしてそれが音楽を聴き続ける楽しみだとも思います。
と、この記事を書きながらもう、3回目を聴いています。
2013年10月20日
PYROMANIA デフ・レパード
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です!
人間として生まれた以上、やっぱり、
後悔しないで生きてゆきたいものですよね。
そもそも、後悔というものは、してもしょうがないものですが。
だけど僕は、今でも、ロックに関して、後悔していることが・・・
01

PYROMANIA Def Leppard
炎のターゲット デフ・レパード released in 1983
デフ・レパードのこのアルバムは、1983年、
僕が高校1年生の時にリリースされました。
当時は僕は「FMファン」を購読していましたが、
FMファンは毎号、話題の新譜のジャケットを表紙にしていて、
これはその表紙で見て知りました。
ビルが燃えているジャケットは印象的でしたが、
デフ・レパードという人たちは知りませんでした。
「ベスト・ヒットUSA」で観たことがなかったからです。
実際は流れていたけれど、その時僕がテレビの前で居眠りしたか、
見落としただけかもしれないのですが。
なお、北海道のテレビ朝日系の局であるHTBは、
深夜番組が東京から1週遅れで放送される上に、
半年ごとに放送日時が変わるのが恒例で、これが困りものでした。
時間が変わるだけならその日に対応できますが、
曜日が変わるのは、前の日にずれる場合は、
気がついた時はもう過ぎていた、ということになりますから。
それで確か1、2回くらい見落としたことがあったはずです。
ちなみに、恒例「でした」と書きましたが、実は今もそうで、
僕が大好きな「タモリ倶楽部」も、半年ごとに曜日が変わり、
先月まで月曜深夜だったのが、今月から火曜深夜に変わりました。
今はもう学習して、4月と10月には確認していますが。
今回は「今でも後悔していること」がテーマですが、それは、
「どうして、デフ・レパードのPYROMANIAを
高校時代に買って聴かなかったのか・・・」
FMファンの表紙になるくらいだから気になっていたのと、
僕はそもそもハードなロックが大好きなことが分かってきて、
例えばビートルズならYer BluesやI've Got A Feelingなど、
ハードな曲を聴いてビートルズの凄さを再認識していた頃であり、
レッド・ツェッペリンに興味が湧いてきた頃であり、そんな中で、
「ヘヴィメタルなる音楽」が聴いてみたいと思ったのです。
当時はまだ小さかったタワーレコード札幌店に行き、
手に取って見るところまでゆきましたが、でも結局、買いませんでした。
音楽は聴くタイミングがあるというのは僕の持論であり、
その後CDの時代になり、買って聴いて愛聴盤になったので、
結果としては、早いか遅いかの違いだけかもしれません。
そんなアルバムは他にもたくさんあって、大した問題じゃないはずです。
しかし、なぜかこのアルバムだけは、後悔しているのです。
買わなかった理由が、あまりにも他愛なく、
そんなことで聴くのが遅れたことが彼らに申し訳ないのが、
どうしても「後悔」という言葉を選んでしまうのです。
このアルバムが出た頃は、
「ヘヴィメタル」という音楽形態が確立され、
音楽を聴く人の間にその言葉や概念が行き渡った頃でした。
そしてこの後、ヘヴィメタル専門誌「BURRN!」が創刊され、
いよいよヘヴィメタルが時代の中に入ってきました。
僕が「ヘヴィメタル」を意識したのは中3の頃。
中学の友達が2人、ヘヴィメタルを好んで聴くようになっていて、
うち1人のTは、うちにもよくカセットテープを持って来ていたので、
僕もよく聴かされるようになっていました。
その頃は、「とにかくヘヴィメタルはかっこいい」というのが、
Tの姿勢でしたが、もしTの姿勢がそこまでで止まっていれば、
僕も意固地になってはいなかったかもしれません。
しかし、Tには2つほど大きな問題がありました。
ひとつは、「ヘヴィメタルを聴くのは特別なことである」
という考えの持ち主で、ことあるごとに、
ヘヴィメタルと「普通のロック」との違いを強調し、
「普通のロック」を差別的な目で見ていました。
ましてや僕は、ビルボード中心に、いわば「売れ線」ばかりを
聴いていたので、そんなTには格好の口撃の標的でした(笑)。
そして、特別なことだから、
「あまり多くの人に聴いてほしくない」という態度で、さらに僕には、
「そんな「普通のロック」なんか聴かないでこっちに来いよ」
といつも言っていました。
そしてもうひとつ、こちらのほうが問題ですが、
Tは、音楽に限らずなんについてでも、
「自分がよいと思わないものには価値がない」
という考えの持ち主で、挙句の果てにというか、
「ビートルズなんかどこがいいんだ」と言い始めました。
そんなことまで言われて、反発しないわけがありません。
だから、意固地な僕はいつしか、
「ヘヴィメタルなんか聴いてやるもんか」、と思うようになりました。
今思うと悲しいことです。
興味があったのに、たったそれだけの理由で聴かなかったのが・・・
しかし面白いことにというか、それから数年後に
ヘヴィメタルは「時代の音」になってしまいました。
ボン・ジョヴィ、モトリー・クルー、スキッド・ロウなど新しい人や、
オジー・オスボーン、ジューダス・プリースト、
アイアン・メイデンにヴァン・ヘイレンなどが
ビルボードのチャートで次々と上位に入るようになり、
それにつられてシーン全体が活性化してきて、
それ専門のテレビ番組が放送されるようにまでなりました。
その中にはもちろん、デフ・レパードもいました。
僕の友達Tはというと、最初のうちは喜んでいましたが、
でもやはり、あまり多くの人が聴くのもなぁ、と言い始めました。
そして、ヘヴィメタルを毛嫌いした僕も、
チャートで上位にくるようになって、無視できなくなり、
いつまでも意固地ではいられなくなりました。
というよりむしろ、ヒットチャートを中心に聴いていた人間なので、
売れたことにより、自分が聴くことを正当化できたのです(笑)。
僕が最初に買ったいわゆるヘヴィメタルのアルバムは、
ホワイトスネイクでしたが(記事はこちら)、その次に買ったのが、
デフ・レパードのHYSTERIA(記事はこちら)でした。
ただ、もちろん僕は最初は、それらを買ったことをTに話すのは、
信念を曲げたみたいな恥ずかしさがありましたが、
でも一方で、チャートで上位にくるものは聴くというのは、
僕の信念でもあるので、メタルが売れるようになったのは、
いってみれば幸福な結末だったのでしょう。
そしてTに思い切って話したところ、Tは意外にも、
そのことを喜ぶだけで、責めたりはしませんでした。
(だから本質は悪い奴じゃないのです)。
とまあ、この話、
ヘヴィメタルにもヒットチャートにも特に興味がない人には、
どっちもどっち、お前らアホか、でしょうね・・・
お見苦しい点があればお詫びいたします。
なお、Tとは今でも年に1度くらいは会って話をしていますし、
ここに書いたようなことは、友達だからこそむしろ、
僕も昔から面と向かって話してきていることであって、
決して一方的に批難しているわけでもないので、
その点はどうかご了解、そしてご安心くださればと。
02 最初に買ったピクチャーCDとデラックス・エディション

「炎のターゲット」を買ったのは、大学2年の88年でした。
当時はようやくCDが主流になってきた時代であり、
このアルバムとHYSTERIAのピクチャーCDがリリースされ、
それを機会に買って聴くと
「このアルバム、あまりにも素晴らしい・・・」
後悔の念が始まったのは、その時でした。
音楽の本質とは離れた、食わず嫌いよりもまだひどい、
あまりにもくだらない理由で聴いていなかった、そのことが。
だから、その「失われた日々」を取り戻したいかのように、
買って暫くは毎日聴き込んでいました。
ヘヴィメタルと書きましたが、でも僕は当時、
HYSTERIAを先に聴いていたこともあって、
それよりはちょっとハードだけど基本はポップなロックだな、
ヘヴィメタルとはちょっと違うのかな、と思いました。
でも、全体を包む雰囲気はヘヴィメタルのものと同質ですね。
まあ、この辺の細かいこと、自分が聴く際には気にしないのですが、
話を進める上ではいつも少しこだわって書いています。
AC/DCも手がけたロバート・ジョン・マット・ランジがプロデュースし、
彼は曲作りにも参加していますが、このアルバムは、
デフ・レパードとランジの音楽の趣向というか方向性が
同じようなものであることから生まれた幸運なアルバム、
といえるのではないでしょうか。
ギターの音には重たい響きがありますが、
基本はロックンロール、曲もポップなものが並んでいるし、
独特の厚みのあるコーラスが気持ちよい、
そんなデフ・レパードの音が確立されたのが、このアルバム。
そういう意味では歴史的名盤と言えるでしょう。
ロック界広しといえども、「誰誰っぽい音」というのがあるのは、
大物であるひとつの証しだと僕は考えるのですが、その点、
これは、デフ・レパードが大物に進化したアルバム。
ただし、当時は「意外とポップだな」と思いましたが、
最近聴き直して、「意外とハードだったんだな」と思い直しました。
これは多分、僕が最近はソウル系を傾聴していて、
よりソフトな音に慣れていたからではないかな、と。
でも、元々がハードなロックが好きな人間なので、
ソウル系を聴けば聴くほど、時折むしょうに
ハードロックやヘヴィメタルを聴きたくもなります。
そうやって心のバランスを取っているのかな(笑)。
03 アルバムジャケットの炎のように燃えるヤマモミジ

Tr1:Rock Rock (Till You Drop)
ちょっとかげりがあって重たく引きずる感じはあるけれど、
1曲目は真っ直ぐなロックンロールでスタート。
タイトルにRockと入った曲には無条件で反応(笑)、
つかみは完璧。
Tr2:Photograph
彼らの代表曲のひとつ。
軽快なギターによるイントロのシンプルなロックンロール、
僕はこの手の曲は無条件で大好き!
キッスのRock And Roll All Nite系の曲か、
と思って聴いているとさにあらず、実は結構手の込んだ曲で、
具体的にいえば「A」「B」「C」3つの部分で構成されていて
Aは軽快なR&R、Bに入ると重暗くなり、Cは印象的なサビ、
だんだんと重たく暗くなってゆきます。
そのサビが印象的、やはり彼らの代表曲の1つでしょうね。
ビデオクリップも、マリリン・モンローの映像などを使い印象的。
Tr3:Stagefright
いろいろあるけど基本的には真っ直ぐなロックンロールが続く。
ヒッチコックの映画に同名のものがあります。
ところで、ヴォーカルのジョー・エリオットの声が、
このアルバムを聴いて最初、ちょっとしっくりこなかったのです。
なんというのかな、ずしっと響いてこない声、
ギターの音と同化するような感じの声質というか。
よく言う「線が細い」というのともまた違う
上手いとか下手という点では下手ではないですが。
そしてそれは、HYSTERIAを先に聴いていて、そちらは
しっかりと響く声だったので、余計にそう感じました。
ジョーも、その4年でヴォーカリストとして成長したのでしょうね。
人としては最初から大好きでした。
Tr4:Too Late For Love
ここで一度テンポを落としてバラードを。
重たいギターのアルペジオはいかにもメタル風、
そこに被さる分厚いコーラスがデフ・レパらしさを表す音。
展開が凝っているのは相変わらず。
Tr5:Die Hard The Hunter
いきなり余談、僕はこのCDを買った頃は大学生でしたが、
羽田空港で整備関係の夜勤のアルバイトをしていました。
毎週土、日、水の夜の勤務でしたが、日曜の朝の夜勤明けの帰り、
まだ開いている店がほとんどないアメ横に当時はあった
ロッテリアに寄って朝飯を食べた後、家に帰って寝ていました。
そして夕方にまた起きて夜勤に出てゆくのですが、起きる時には、
このCDをタイマーでかけて目覚まし代わりにしていました。
懐かしいなぁ。
曲は、ヘリコプターの音がSEに使われた緊迫感がある
ミドルテンポの重たくて暗い曲。
兵士や戦争に題をとるのはアイアン・メイデンが得意とするところで、
彼らも同じNew Wave Of British Heavy Metalの流れですが、
でも、デフレパは後に「健康な」イメージを押し出すようになったので、
今となっては、少し毛色が違う曲といえるのかもしれません。
04 A公園の橋も黄色い葉っぱに囲まれる季節

Tr6:Foolin'
このアルバムはほんとにいい曲が多いですね。
いい曲というか、印象に残りやすい曲が。
それはプロデューサーのランジがもたらした部分が大きいのでしょう。
アコースティック・ギターのアルペジオのイントロから始まり、
だんだん盛り上がってサビでハードになるのは、
英国ハードロックの伝統にのっとった感じで、
この曲の音作りには、彼らは英国人なんだなと強く感じます。
Tr7:Rock Of Ages
これも彼らの代表曲のひとつ、ミドルテンポの重たい曲。
最初の変な喋りと最後にジョーが不敵に笑うのが、
いかにもメタル風だなと最初に思いました。
実際、曲としてもこの中ではいちばんヘヴィメタル然としていますね。
2ndコーラスのヴァースの部分のヴォーカルとギターが
コール&レスポンス風に展開し、サビに入る直前で、
それらがユニゾンになるのは、とにかくカッコいい!
歌詞の中にPyromaniaと出てくるように、
このアルバムのテーマ曲のような存在。
アルバムタイトル曲はないけど歌詞の中に
アルバムタイトルが出てくるパターン、ロックには結構あります。
なお、pyromaniaとは「放火癖」、恐いですね・・・
そしてこのタイトルは、ザ・バンドのライヴアルバムにもあって、
やっぱり彼らは広くロックを愛していることが分かる曲。
Tr8:Comin' Under Fire
この辺りはミドルテンポのメタル風な曲が続きますが、
サビの哀愁を帯びたコーラスがこちらは印象的。
彼らの代表曲というわけではないけれど、でも、
このアルバムの曲が粒揃いであることを証明する曲。
Tr9:Action ! Not Words
これはメタルっぽくない、からっと明るい曲。
彼らはスウィートが大好きらしいのですが、
その辺の英国の流れも感じるポップなロックです。
Tr10:BIlly's Got A Gun
ガン=銃もメタル的イディオム、そして雰囲気。
そう思ったのは、この曲を僕が知ったすぐ後に、
エアロスミスがJanie's Got A Gunという曲を出したからです。
変拍子のギターイントロが、切れというよりは、
何かを重たく引きずる、そんな雰囲気を作り出します。
そしてこの曲で思ったのは、リック・サヴェージのベースが
熱くなりがちな他の4人を尻目に、ちょっと粘ついた音で
あくまでも涼しげに貫き通す、そこがまさに「クール」。
リックのベースはあくまでもベースで、フレーズとしては
あまり印象に残らないのですが、でもしっかりと音を支えています。
終わってからも何かを引きずり、余韻を残しまくるアルバムです。
左が通常盤、右がデラックス・エディションのリンク。
今回このアルバムを記事にしたのは、
6月に2枚組デラックス・エディションが出たからです。
6月中にすぐに記事にするつもりでいたのが、
諸事情により遅れてしまった、というわけ。
その事情のひとつはもちろん僕が忙しかったからですが、
他にもうひとつあります。
その前に、
デラックス・エディションのDisc2には、未発表音源である
1983年のL.A.Forumにおけるライヴが収録されていて、
ファンにはとってもうれしい贈り物。
しかも最後の曲、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの
Travelin' Bandのカバーであり、その途中では、
レッド・ツェッペリンのRock And Rollも挟み込んでいます。
そしてなんとなんとその曲のゲストが、
クイーンのブライアン・メイ!
彼らがロックをいかに愛しているかがひしひしと伝わってくる、
ロック好きにはもう涙もののうれしい企画です。
余談ですが、
Travelin' Bandはボン・ジョヴィもカバーしていましたが、
友達Tに、その曲はC.C.R.の曲だと説明しても、
TはC.C.R.には特に興味関心を示さなかったのが、
いろんな意味で悲しかったですね。
ヘヴィメタルも「普通のロック」も、同じロックなのに・・・
最後、もうひとつの事情の前に写真をもう1枚。
05

今回出たデラックス・エディション2枚組。
ディスクを他のケースに移して中を撮影しましたが、
左の赤いほうがDisc2、右の青いほうがDisc1です。
これ、楽しみに待っていて届いたものを、
いざ、Disc1を取り出してCDプレイヤーで再生すると、
拍手歓声がフェイドインしてきて、ライヴ音源が始まりました。
あれ、もしやと思い、一度止めてDisc2を入れると、
昔から聴きなじんだPYROMANIAのアルバムが始まりました。
つまり、Disc1と書かれたほうにDisc2の内容が、
Disc2にDisc1の内容がと、入れ違いになっていたのです。
すぐに「不良品」ということで返品交換に応じるようになりましたが、
別に入れ違っているだけで聴くことができるのだからと、
返品交換には応じずに、そのまま持って聴いています。
あ、別に、プレミア狙いじゃないですよ(笑)。
音飛びとかではなくちゃんと聴けるの以上、
返品してもそれはどうせ捨てられてしまうだけ、
資源がもったいないので、そのままにしているだけです。
とまあ、今回は枝葉の話ばかりになってしまいましたが、
「聴きやすいヘヴィメタル」のアルバムとして、
これは名作名盤傑作であるという思いを新たにしました。
写真へのコメントも
大歓迎です!
人間として生まれた以上、やっぱり、
後悔しないで生きてゆきたいものですよね。
そもそも、後悔というものは、してもしょうがないものですが。
だけど僕は、今でも、ロックに関して、後悔していることが・・・
01

PYROMANIA Def Leppard
炎のターゲット デフ・レパード released in 1983
デフ・レパードのこのアルバムは、1983年、
僕が高校1年生の時にリリースされました。
当時は僕は「FMファン」を購読していましたが、
FMファンは毎号、話題の新譜のジャケットを表紙にしていて、
これはその表紙で見て知りました。
ビルが燃えているジャケットは印象的でしたが、
デフ・レパードという人たちは知りませんでした。
「ベスト・ヒットUSA」で観たことがなかったからです。
実際は流れていたけれど、その時僕がテレビの前で居眠りしたか、
見落としただけかもしれないのですが。
なお、北海道のテレビ朝日系の局であるHTBは、
深夜番組が東京から1週遅れで放送される上に、
半年ごとに放送日時が変わるのが恒例で、これが困りものでした。
時間が変わるだけならその日に対応できますが、
曜日が変わるのは、前の日にずれる場合は、
気がついた時はもう過ぎていた、ということになりますから。
それで確か1、2回くらい見落としたことがあったはずです。
ちなみに、恒例「でした」と書きましたが、実は今もそうで、
僕が大好きな「タモリ倶楽部」も、半年ごとに曜日が変わり、
先月まで月曜深夜だったのが、今月から火曜深夜に変わりました。
今はもう学習して、4月と10月には確認していますが。
今回は「今でも後悔していること」がテーマですが、それは、
「どうして、デフ・レパードのPYROMANIAを
高校時代に買って聴かなかったのか・・・」
FMファンの表紙になるくらいだから気になっていたのと、
僕はそもそもハードなロックが大好きなことが分かってきて、
例えばビートルズならYer BluesやI've Got A Feelingなど、
ハードな曲を聴いてビートルズの凄さを再認識していた頃であり、
レッド・ツェッペリンに興味が湧いてきた頃であり、そんな中で、
「ヘヴィメタルなる音楽」が聴いてみたいと思ったのです。
当時はまだ小さかったタワーレコード札幌店に行き、
手に取って見るところまでゆきましたが、でも結局、買いませんでした。
音楽は聴くタイミングがあるというのは僕の持論であり、
その後CDの時代になり、買って聴いて愛聴盤になったので、
結果としては、早いか遅いかの違いだけかもしれません。
そんなアルバムは他にもたくさんあって、大した問題じゃないはずです。
しかし、なぜかこのアルバムだけは、後悔しているのです。
買わなかった理由が、あまりにも他愛なく、
そんなことで聴くのが遅れたことが彼らに申し訳ないのが、
どうしても「後悔」という言葉を選んでしまうのです。
このアルバムが出た頃は、
「ヘヴィメタル」という音楽形態が確立され、
音楽を聴く人の間にその言葉や概念が行き渡った頃でした。
そしてこの後、ヘヴィメタル専門誌「BURRN!」が創刊され、
いよいよヘヴィメタルが時代の中に入ってきました。
僕が「ヘヴィメタル」を意識したのは中3の頃。
中学の友達が2人、ヘヴィメタルを好んで聴くようになっていて、
うち1人のTは、うちにもよくカセットテープを持って来ていたので、
僕もよく聴かされるようになっていました。
その頃は、「とにかくヘヴィメタルはかっこいい」というのが、
Tの姿勢でしたが、もしTの姿勢がそこまでで止まっていれば、
僕も意固地になってはいなかったかもしれません。
しかし、Tには2つほど大きな問題がありました。
ひとつは、「ヘヴィメタルを聴くのは特別なことである」
という考えの持ち主で、ことあるごとに、
ヘヴィメタルと「普通のロック」との違いを強調し、
「普通のロック」を差別的な目で見ていました。
ましてや僕は、ビルボード中心に、いわば「売れ線」ばかりを
聴いていたので、そんなTには格好の口撃の標的でした(笑)。
そして、特別なことだから、
「あまり多くの人に聴いてほしくない」という態度で、さらに僕には、
「そんな「普通のロック」なんか聴かないでこっちに来いよ」
といつも言っていました。
そしてもうひとつ、こちらのほうが問題ですが、
Tは、音楽に限らずなんについてでも、
「自分がよいと思わないものには価値がない」
という考えの持ち主で、挙句の果てにというか、
「ビートルズなんかどこがいいんだ」と言い始めました。
そんなことまで言われて、反発しないわけがありません。
だから、意固地な僕はいつしか、
「ヘヴィメタルなんか聴いてやるもんか」、と思うようになりました。
今思うと悲しいことです。
興味があったのに、たったそれだけの理由で聴かなかったのが・・・
しかし面白いことにというか、それから数年後に
ヘヴィメタルは「時代の音」になってしまいました。
ボン・ジョヴィ、モトリー・クルー、スキッド・ロウなど新しい人や、
オジー・オスボーン、ジューダス・プリースト、
アイアン・メイデンにヴァン・ヘイレンなどが
ビルボードのチャートで次々と上位に入るようになり、
それにつられてシーン全体が活性化してきて、
それ専門のテレビ番組が放送されるようにまでなりました。
その中にはもちろん、デフ・レパードもいました。
僕の友達Tはというと、最初のうちは喜んでいましたが、
でもやはり、あまり多くの人が聴くのもなぁ、と言い始めました。
そして、ヘヴィメタルを毛嫌いした僕も、
チャートで上位にくるようになって、無視できなくなり、
いつまでも意固地ではいられなくなりました。
というよりむしろ、ヒットチャートを中心に聴いていた人間なので、
売れたことにより、自分が聴くことを正当化できたのです(笑)。
僕が最初に買ったいわゆるヘヴィメタルのアルバムは、
ホワイトスネイクでしたが(記事はこちら)、その次に買ったのが、
デフ・レパードのHYSTERIA(記事はこちら)でした。
ただ、もちろん僕は最初は、それらを買ったことをTに話すのは、
信念を曲げたみたいな恥ずかしさがありましたが、
でも一方で、チャートで上位にくるものは聴くというのは、
僕の信念でもあるので、メタルが売れるようになったのは、
いってみれば幸福な結末だったのでしょう。
そしてTに思い切って話したところ、Tは意外にも、
そのことを喜ぶだけで、責めたりはしませんでした。
(だから本質は悪い奴じゃないのです)。
とまあ、この話、
ヘヴィメタルにもヒットチャートにも特に興味がない人には、
どっちもどっち、お前らアホか、でしょうね・・・
お見苦しい点があればお詫びいたします。
なお、Tとは今でも年に1度くらいは会って話をしていますし、
ここに書いたようなことは、友達だからこそむしろ、
僕も昔から面と向かって話してきていることであって、
決して一方的に批難しているわけでもないので、
その点はどうかご了解、そしてご安心くださればと。
02 最初に買ったピクチャーCDとデラックス・エディション

「炎のターゲット」を買ったのは、大学2年の88年でした。
当時はようやくCDが主流になってきた時代であり、
このアルバムとHYSTERIAのピクチャーCDがリリースされ、
それを機会に買って聴くと
「このアルバム、あまりにも素晴らしい・・・」
後悔の念が始まったのは、その時でした。
音楽の本質とは離れた、食わず嫌いよりもまだひどい、
あまりにもくだらない理由で聴いていなかった、そのことが。
だから、その「失われた日々」を取り戻したいかのように、
買って暫くは毎日聴き込んでいました。
ヘヴィメタルと書きましたが、でも僕は当時、
HYSTERIAを先に聴いていたこともあって、
それよりはちょっとハードだけど基本はポップなロックだな、
ヘヴィメタルとはちょっと違うのかな、と思いました。
でも、全体を包む雰囲気はヘヴィメタルのものと同質ですね。
まあ、この辺の細かいこと、自分が聴く際には気にしないのですが、
話を進める上ではいつも少しこだわって書いています。
AC/DCも手がけたロバート・ジョン・マット・ランジがプロデュースし、
彼は曲作りにも参加していますが、このアルバムは、
デフ・レパードとランジの音楽の趣向というか方向性が
同じようなものであることから生まれた幸運なアルバム、
といえるのではないでしょうか。
ギターの音には重たい響きがありますが、
基本はロックンロール、曲もポップなものが並んでいるし、
独特の厚みのあるコーラスが気持ちよい、
そんなデフ・レパードの音が確立されたのが、このアルバム。
そういう意味では歴史的名盤と言えるでしょう。
ロック界広しといえども、「誰誰っぽい音」というのがあるのは、
大物であるひとつの証しだと僕は考えるのですが、その点、
これは、デフ・レパードが大物に進化したアルバム。
ただし、当時は「意外とポップだな」と思いましたが、
最近聴き直して、「意外とハードだったんだな」と思い直しました。
これは多分、僕が最近はソウル系を傾聴していて、
よりソフトな音に慣れていたからではないかな、と。
でも、元々がハードなロックが好きな人間なので、
ソウル系を聴けば聴くほど、時折むしょうに
ハードロックやヘヴィメタルを聴きたくもなります。
そうやって心のバランスを取っているのかな(笑)。
03 アルバムジャケットの炎のように燃えるヤマモミジ

Tr1:Rock Rock (Till You Drop)
ちょっとかげりがあって重たく引きずる感じはあるけれど、
1曲目は真っ直ぐなロックンロールでスタート。
タイトルにRockと入った曲には無条件で反応(笑)、
つかみは完璧。
Tr2:Photograph
彼らの代表曲のひとつ。
軽快なギターによるイントロのシンプルなロックンロール、
僕はこの手の曲は無条件で大好き!
キッスのRock And Roll All Nite系の曲か、
と思って聴いているとさにあらず、実は結構手の込んだ曲で、
具体的にいえば「A」「B」「C」3つの部分で構成されていて
Aは軽快なR&R、Bに入ると重暗くなり、Cは印象的なサビ、
だんだんと重たく暗くなってゆきます。
そのサビが印象的、やはり彼らの代表曲の1つでしょうね。
ビデオクリップも、マリリン・モンローの映像などを使い印象的。
Tr3:Stagefright
いろいろあるけど基本的には真っ直ぐなロックンロールが続く。
ヒッチコックの映画に同名のものがあります。
ところで、ヴォーカルのジョー・エリオットの声が、
このアルバムを聴いて最初、ちょっとしっくりこなかったのです。
なんというのかな、ずしっと響いてこない声、
ギターの音と同化するような感じの声質というか。
よく言う「線が細い」というのともまた違う
上手いとか下手という点では下手ではないですが。
そしてそれは、HYSTERIAを先に聴いていて、そちらは
しっかりと響く声だったので、余計にそう感じました。
ジョーも、その4年でヴォーカリストとして成長したのでしょうね。
人としては最初から大好きでした。
Tr4:Too Late For Love
ここで一度テンポを落としてバラードを。
重たいギターのアルペジオはいかにもメタル風、
そこに被さる分厚いコーラスがデフ・レパらしさを表す音。
展開が凝っているのは相変わらず。
Tr5:Die Hard The Hunter
いきなり余談、僕はこのCDを買った頃は大学生でしたが、
羽田空港で整備関係の夜勤のアルバイトをしていました。
毎週土、日、水の夜の勤務でしたが、日曜の朝の夜勤明けの帰り、
まだ開いている店がほとんどないアメ横に当時はあった
ロッテリアに寄って朝飯を食べた後、家に帰って寝ていました。
そして夕方にまた起きて夜勤に出てゆくのですが、起きる時には、
このCDをタイマーでかけて目覚まし代わりにしていました。
懐かしいなぁ。
曲は、ヘリコプターの音がSEに使われた緊迫感がある
ミドルテンポの重たくて暗い曲。
兵士や戦争に題をとるのはアイアン・メイデンが得意とするところで、
彼らも同じNew Wave Of British Heavy Metalの流れですが、
でも、デフレパは後に「健康な」イメージを押し出すようになったので、
今となっては、少し毛色が違う曲といえるのかもしれません。
04 A公園の橋も黄色い葉っぱに囲まれる季節

Tr6:Foolin'
このアルバムはほんとにいい曲が多いですね。
いい曲というか、印象に残りやすい曲が。
それはプロデューサーのランジがもたらした部分が大きいのでしょう。
アコースティック・ギターのアルペジオのイントロから始まり、
だんだん盛り上がってサビでハードになるのは、
英国ハードロックの伝統にのっとった感じで、
この曲の音作りには、彼らは英国人なんだなと強く感じます。
Tr7:Rock Of Ages
これも彼らの代表曲のひとつ、ミドルテンポの重たい曲。
最初の変な喋りと最後にジョーが不敵に笑うのが、
いかにもメタル風だなと最初に思いました。
実際、曲としてもこの中ではいちばんヘヴィメタル然としていますね。
2ndコーラスのヴァースの部分のヴォーカルとギターが
コール&レスポンス風に展開し、サビに入る直前で、
それらがユニゾンになるのは、とにかくカッコいい!
歌詞の中にPyromaniaと出てくるように、
このアルバムのテーマ曲のような存在。
アルバムタイトル曲はないけど歌詞の中に
アルバムタイトルが出てくるパターン、ロックには結構あります。
なお、pyromaniaとは「放火癖」、恐いですね・・・
そしてこのタイトルは、ザ・バンドのライヴアルバムにもあって、
やっぱり彼らは広くロックを愛していることが分かる曲。
Tr8:Comin' Under Fire
この辺りはミドルテンポのメタル風な曲が続きますが、
サビの哀愁を帯びたコーラスがこちらは印象的。
彼らの代表曲というわけではないけれど、でも、
このアルバムの曲が粒揃いであることを証明する曲。
Tr9:Action ! Not Words
これはメタルっぽくない、からっと明るい曲。
彼らはスウィートが大好きらしいのですが、
その辺の英国の流れも感じるポップなロックです。
Tr10:BIlly's Got A Gun
ガン=銃もメタル的イディオム、そして雰囲気。
そう思ったのは、この曲を僕が知ったすぐ後に、
エアロスミスがJanie's Got A Gunという曲を出したからです。
変拍子のギターイントロが、切れというよりは、
何かを重たく引きずる、そんな雰囲気を作り出します。
そしてこの曲で思ったのは、リック・サヴェージのベースが
熱くなりがちな他の4人を尻目に、ちょっと粘ついた音で
あくまでも涼しげに貫き通す、そこがまさに「クール」。
リックのベースはあくまでもベースで、フレーズとしては
あまり印象に残らないのですが、でもしっかりと音を支えています。
終わってからも何かを引きずり、余韻を残しまくるアルバムです。
左が通常盤、右がデラックス・エディションのリンク。
今回このアルバムを記事にしたのは、
6月に2枚組デラックス・エディションが出たからです。
6月中にすぐに記事にするつもりでいたのが、
諸事情により遅れてしまった、というわけ。
その事情のひとつはもちろん僕が忙しかったからですが、
他にもうひとつあります。
その前に、
デラックス・エディションのDisc2には、未発表音源である
1983年のL.A.Forumにおけるライヴが収録されていて、
ファンにはとってもうれしい贈り物。
しかも最後の曲、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの
Travelin' Bandのカバーであり、その途中では、
レッド・ツェッペリンのRock And Rollも挟み込んでいます。
そしてなんとなんとその曲のゲストが、
クイーンのブライアン・メイ!
彼らがロックをいかに愛しているかがひしひしと伝わってくる、
ロック好きにはもう涙もののうれしい企画です。
余談ですが、
Travelin' Bandはボン・ジョヴィもカバーしていましたが、
友達Tに、その曲はC.C.R.の曲だと説明しても、
TはC.C.R.には特に興味関心を示さなかったのが、
いろんな意味で悲しかったですね。
ヘヴィメタルも「普通のロック」も、同じロックなのに・・・
最後、もうひとつの事情の前に写真をもう1枚。
05

今回出たデラックス・エディション2枚組。
ディスクを他のケースに移して中を撮影しましたが、
左の赤いほうがDisc2、右の青いほうがDisc1です。
これ、楽しみに待っていて届いたものを、
いざ、Disc1を取り出してCDプレイヤーで再生すると、
拍手歓声がフェイドインしてきて、ライヴ音源が始まりました。
あれ、もしやと思い、一度止めてDisc2を入れると、
昔から聴きなじんだPYROMANIAのアルバムが始まりました。
つまり、Disc1と書かれたほうにDisc2の内容が、
Disc2にDisc1の内容がと、入れ違いになっていたのです。
すぐに「不良品」ということで返品交換に応じるようになりましたが、
別に入れ違っているだけで聴くことができるのだからと、
返品交換には応じずに、そのまま持って聴いています。
あ、別に、プレミア狙いじゃないですよ(笑)。
音飛びとかではなくちゃんと聴けるの以上、
返品してもそれはどうせ捨てられてしまうだけ、
資源がもったいないので、そのままにしているだけです。
とまあ、今回は枝葉の話ばかりになってしまいましたが、
「聴きやすいヘヴィメタル」のアルバムとして、
これは名作名盤傑作であるという思いを新たにしました。
2013年10月19日
J.D.サウザーがとってもいい! HOME BY DAWN
01

HOME BY DAWN J. D. Souther
ホーム・バイ・ドーン J.D.サウザー (1984)
最近の僕のお気に入りのアーティストが
J.D.サウザー John David Southerです。
この記事では、親しみを込め、以降"JD"と記してゆきます。
直接のきっかけは、8月にポコ Pocoを聴いていた流れで、
ポコにいたリッチー・フューリー Ritchie Furayが、JDと、
元バーズ The Byrdsのクリス・ヒルマンChris Hillmanが組んだ
THE SOUTHER, HILLMAN, FURAY BAND
のCDを買ったことです。
当初はJDがめあてではなかったのですが、
このCDはもう1年以上ウィッシュリストに入っていて、
ポコというちょうどいいきっかけがあって、ついに買いました。
その話の前に、僕がJDを最初に買って聴いたのは、
ほんの最近、2007年、イーグルス The Eaglesの28年振りの新譜、
THE LONG ROAD OUT OF EDENの最初のシングルだった
How LongがJDの曲だということで、まずはベスト盤
BORDER TOWN THE VERY BEST OF J. D. SOUTHER
を買いました。
少しして、元々欲しかった、かの名曲を収録した
YOU'RE ONLY LONELYの紙ジャケットを買い、
それがとっても気に入りました。
さらに、2008年、24年振りの新譜
IF THE WORLD WAS YOUが出たとAmazonにおすすめされ、
そうかそうかと買って聴き、これは音楽としてはとてもできがよく
気に入りました。
その後また1年以上が経ち、今年に入って、
ソロの1stであるJOHN DAVID SOUTHERを、
さらにその少し後に2ndのBLACK ROSEを買い、
特に1stは大のお気に入りになりましたが、
それらについては今後も記事にするかもしれないので、
それより前に買ったものについては触れないで進めます。
02 その5枚

ただ、JDという人の名前と存在は10代の頃から知っていました。
イーグルスとよく一緒に曲を作ってる人、という認識でしたが、
僕が、例外はあるけど70年代全ロックの楽曲で最も好きな曲
New Kid In Town(記事はこちら)を一緒に作っていたので、
僕の中では、一目置かれている人ではありました。
しかし、それ以上の存在になるのに20年を費やした、というわけです。
でも、自己弁護するわけじゃないけど、それは仕方ない。
だって、JD自身が24年もアルバムを出していなかったわけだし、
その1984年は僕がヒットチャート中心に洋楽を聴いていた頃で、
JDの曲がヒットしたという記憶もないし、だから、
そのアルバムが出ていたことすら最近まで知らりませんでした。
僕の波とJDの波が合わないままずっと進んでいた、ということでしょう。
さて、8月に買ったサウザー・ヒルマン・フューリー・バンド、
長いので以降は"SHFB"と記しますが、それはとても楽しみでした。
このアルバムは、デヴィッド・ゲフィンが設立したASYLUMレコードの
有望な若手のシンガーソングライターであるJDが、
元バーズ、元ポコの大物2人と組んだバンドであり、
JDのメジャー(当時は新興レーベルでしたが)デビュー作。
その前に、ポコを聴こうと思ったきっかけが、
バッファロー・スプリングフィールド Buffalo Springfield
を遠征で聴いていたことで、カントリー色が濃いロックが
その時の僕の気持ちに合っていたのです。
またまた長いバンド名(笑)、"BS"と記す、BSは元々好きでしたが、
好きなものでもやはり音楽は人それぞれに波があるもので、
いわば「再発見」したという感じでした。
僕は、ビートルズから始まっている人間なので、
作曲者及び歌い手が複数いるバンドは大好きですが、
今回は、メインのスティーヴン・スティルス Stephen Stillsと
ニール・ヤング Neil Youngではなく、いわば「脇役」である
リッチー・フューリーがいい味を出していることに気づき、
家にあるポコを聴き直し、さらにSHFBに行き着きました。
SHFB、アルバムはとってもよかったです。
期待通りのカントリー色があるロックで、すっかり愛聴盤です。
しかし、このアルバム、聴き終わると、
「これはまるでJDのアルバムのようだ」
という印象を受けることに気づきました。
他の2人、クリス・ヒルマンとリッチー・フューリーがお好きな方、
そしてご本人2人にも申し訳ないと思いつつ・・・
真剣に聴くともちろん2人の曲も個性が出ていて素晴らしいですが、
通しで聴くと、それが正直な感想でした。
実際最も印象的な曲も、JDのPretty Goodbyesでしたし。
そこで僕は、JDという人の魅力にあらためて(初めて?)気づき、
慌ててSHFBの残りのもう1枚、2ndの
TROUBLE IN PARADISEを買いました。
聴くと、1st以上にJDの色が強く出てそれだけが印象に残りました。
他の2人は、これじゃ一緒にやっていけないと感じて、
たった2枚でバンドが終わってしまったのではないかと、
いつものように邪推すらしてしまいました。
でも、どうして僕はそう感じたのかな。
僕はいつも言いますが、鼻歌で歌って気持ちがいい
「歌メロ」がいい「歌」としての曲に強くひかれますが、JDは、
単純に、良い歌メロを作る才能とセンスに長けているのでしょう。
もうひとつ感じたのは、例えば上述のイーグルスの曲のように、
他の人と共作した曲を思い浮かべてみても、なんというのかな、
「人間的な要素」を曲に織り込むのことが自然にできる、
だからすっと「心」に伝わってくるんじゃないかな、とも思いました。
JDの人間性についてはまだまったく知る由もなく、
音楽を通して接している人間像とちょっとした情報、
そんな程度ですが、でも、人間的な魅力を感じる人です。
さらに、JDは、音楽を、単に知識としてではなく、
体や心に深くしみ込んでいて、それが表現できるのではないか、
ということも思いました。
歌メロがいいと書きましたが、例えばギターのイントロのフレーズ、
途中のキメのフレーズなど、歌以外の演奏の部分でも、
印象的なフレーズを織り込むことにより曲がいっそう引き立つ、
そのようなつぼを、知識としてではなく、体が知っているのでしょう。
だからJDの曲には、あざとさや嫌味のようなものを感じません。
こうして僕はJDの虜になりました。
03 サウザー・ヒルマン・フューリー・バンドの2枚

SHFBの2ndと一緒に、今回の記事のサウンドトラックともいうべき、
HOME BY DAWNも買いました。
僕は、基本的には好きになったアーティストについては、
すべてのアルバムを買って聴かないと気が済まないたちですが、
JDは、40年になろうというキャリアの中で、SHFB以降では、
正式なアルバムは、ここで紹介したものがすべてなのです。
ということに、SHFBの2ndを注文する際に調べて気づき、
これはそこに追加したもので、最初はいわば「おまけ」でした。
しかし、このアルバムが素晴らしい。
曲がすべていいのはもちろんで後に詳述しますが、
80年代ロックで育った僕としては、80年代サウンドなのがうれしい。
ただ、意味がないくらいシンセが目立ってビートが無機質という、
こてこての80年代サウンドではなく、センスが80年代のもので、
曲の良さを生かすことに主眼を置いた落ち着いた音楽。
初めて聴いたのに、懐かしさに襲われましたが、これは、
キンクス The KinksのSTATE OF CONFUSIONや
元ABBAのフリーダ FridaのSOMETHING'S GOING ONを、
30歳を過ぎてから初めてアルバムとして聴いた際に感じた
懐かしさとまったく同質のものでした。
まあ、落ち着いたというのは、ロックが反骨心という点からは、
当時からつまらないと言われていた部分なんですけど、でも、
人間は自分の生まれは選べない、僕は80年代のロックで育った、
だからやっぱりそれが好きなんですね。
なお、このアルバムの曲の作曲者は、
J.D.サウザーひとりが書いたもの以外のみ
曲名の下に明記しました、ご了承ください。
(All songs written by John David Souther except as noted)
04 2010年10月18日のDawn

Tr1:Home By Dawn
イントロなしに歌い出す、軽快にスウィングした
ちょっとオールディーズ風のロックンロール。
朝までに帰らなきゃならないのに焦っているのかな。
誰が参加しているのか、ブックレットを見るのも楽しいですが、
やはりというか、イーグルスのドン・ヘンリー Don Henleyが参加。
しかし、ブックレットを見て知って驚いたことが。
JDってドラマーだったんだ!
そんなことすら知らなかったのです・・・
そうと分かると、このアルバム、ドラムスにも着目して
聴くようになったから、まったく僕も現金なもんです(笑)。
Tr2:Go Ahead And Rain
このアルバムは、「ニューミュージック」みたいな雰囲気がします。
「ニューミュージック」なんてもう死語ですが、
時代を表す言葉としてここではあえて使っています。
黒人音楽の模倣から始まったロックという音楽が、年月を経て、
演奏者も増え、黒人音楽まで戻らないで、白人のロックの中だけで
受け継がれ再構築されていったという感じの響きですが、
日本でも似たような過程だったのかもしれません。
ただ、じゃあJDが黒人音楽の影響を受けていないかというと、
一昨年の最新作ではジャズっぽい曲もあったように、
そんなことはないとは思います。
だからやっぱり、このアルバムの音は時代の音でしょうかね。
僕の音楽友だちのトニーさんは特に戦後歌謡曲に詳しいのですが、
そのトニーさんがJDが大好きで、それが分かった気がしました。
かといって芯はしっかりとしたロックであるのも、
ロック人間にとっては安心できていいところ。
曲は、パラパラ降る雨のようなギターのイントロが印象的ですが、
こうした効果的な音が歌意外にも多く見受けられるのも、
聴いていて楽しく印象に残りやすい部分だと思います。
JDはここではギターも弾いています。
そして雨を歌った曲は抒情的な曲が多いですね。
Tr3:Say You Will
(J.D.Souther / Danny Kortchmar)
リンダ・ロンシュタットって、かわいいですよね。
声も歌い方も、なんというか、男としてはもう
だだをこねられてもなんでも許しちゃおう、みたいな(笑)。
特に2'37"の"Hold me tight"とアドリブで歌う部分はぐぐっときます。
お互いにお互いを育て合った協力者のようなライバルのような
リンダ・ロンシュタット Linda Ronstadtとのデュエットは、
2人の息がぴったりの、極上のポップチューンに仕上がっています。
ところでこれ、最初はブックレットを見ていなかったのですが、
お喋りしているような面白いギターワークがなんとなく
ダニー・「クーチ」・コーチマー Danny "Kootch" Kortchmar
みたいだなと思いながら聴いていました。
実際のギターはJosh Leo、Billy Walkerの2人でしたが、
しかし曲はJDと「クーチ」の共作、妙に納得しました。
もうひとつ、ビリー・ジョエルっぽい感じなのも僕にはうれしい。
明るく楽しく前向きで、この曲はすっかり僕のものになりました。
Tr4:I'll Take Care Of You
JDのピアノとヴォーカルにギターだけのシンプルなバラード。
JDが聴きやすい要素のひとつが、「過度じゃない」ことかと思いました。
ロマンティックでセンチメンタルだけど押しつけがましくない、
すっきりとした大人のバラードという感じです。
Tr5:All For You
JDはヴォーカリストとしても大好きです。
声も歌い方も好きですし、気持ちの込め方もやはり過度ではない。
この曲は特に80年代を思い出しましたね。
いつも言いますが、深夜に「ベスト・ヒットUSA」を観て、
次の海外ドラマが終わるとテレビ放送が終わる、
その時の妙にすがすがしい空気感みたいな。
時間的にもこのアルバムの主題と合いますし。
Tr6:Night
(J.D.Souther / Waddy Wachtel)
この曲はTr3と同時に一発で気に入りました。
アップテンポで押していく中に曲が劇的に流れていく、
そしてアップテンポで歌メロがよくてちょっと切ない。
僕が好きな要素をすべて詰め込んだ曲です(笑)。
「名手」ワディ・ワクテル Waddy Wachtelのギターが
劇的な曲にさらに豊かな表情をつけています。
曲もJDとワディ・ワクテルの共作です。
Tr7:Don't Know What I'm Gonna Do
ブックレットにJoshと明記されているギターソロが素敵です。
JDは厚めだけど熱くないコーラスワークもセンスいいですね。
きれいに流れていく曲で、やや唐突に早めにささっと
終わってしまうのが、なんとももったいない感じ。
Tr8:Bad News Travels Fast
..." Good news never lasts"...
人生訓みたいな曲も僕はひかれます、好きです。
この曲にはドン・ヘンリーにプラスしてやはりイーグルスの
ティモシー・B・シュミット Timothy B. Schmidtも参加。
西海岸人脈の友情の厚さを感じます。
前の曲からうまく流れている、西海岸の良さを凝縮したような曲。
この中ではいちばん気持ちがこもっている曲で、
JDのドラムスもなかなかいいなあ。
Tr9:All I Want
Tr4のリプライズのような静謐なバラード。
夜明け前に家に帰って、最後にぽつんと絞り出すように歌うと、
期待というよりは寂しさに襲われてしまう・・・
バラードについては、良い意味でのお手本的な曲を書く人ですね。
だから余計に、すっと心に入り込んできます。
Amazonでの順位、204,271位、まあそんなもんでしょう。
今年7月以降に買って初めて聴いた旧譜で
いちばん気に入っているのは、断然、このアルバムですね。
秋に合う響きのアルバムでもあると思いますが、
それはもしかして、音楽自体よりも聴く者の心の在り方かな。
しかし、このアルバムにはひとつ大きな問題が。
アルバムが33分弱しかないのです!
曲も9曲と中途半端な感じがしますが、こんなに素晴らしいのに
すぐに終わってしまうのがもったいない。
ただ、短いので何度も聴けるし、ちょっと時間ができたら聴けるので、
今はそれを良い面に捉えることにしています。
でも、その短さ、中途半端と感じさせる部分は、
当時のJDの悩みや葛藤の表れなのかもしれません。
音楽業界ではよくあることかもしれないですが、
このまま作っていていいのだろうかと悩んだ挙句、
モティヴェイションが続かなかったのかもしれません。
そして、それを取り戻すのに四半世紀を要した・・・
しかし、出来あがって残されたものは極上のポップスであり、
音楽好きとしては、文句を言わずにそれを楽しみたいです。
それにしてもJDはアルバムが少なすぎる!
もっともっと聴きたいという思いが募ってきていますが、
ないものは仕方ないですね・・・
05 2010年10月19日のDawn

最後に・・・
Northernの僕が、Southerを好きになるとは(笑)。

HOME BY DAWN J. D. Souther
ホーム・バイ・ドーン J.D.サウザー (1984)
最近の僕のお気に入りのアーティストが
J.D.サウザー John David Southerです。
この記事では、親しみを込め、以降"JD"と記してゆきます。
直接のきっかけは、8月にポコ Pocoを聴いていた流れで、
ポコにいたリッチー・フューリー Ritchie Furayが、JDと、
元バーズ The Byrdsのクリス・ヒルマンChris Hillmanが組んだ
THE SOUTHER, HILLMAN, FURAY BAND
のCDを買ったことです。
当初はJDがめあてではなかったのですが、
このCDはもう1年以上ウィッシュリストに入っていて、
ポコというちょうどいいきっかけがあって、ついに買いました。
その話の前に、僕がJDを最初に買って聴いたのは、
ほんの最近、2007年、イーグルス The Eaglesの28年振りの新譜、
THE LONG ROAD OUT OF EDENの最初のシングルだった
How LongがJDの曲だということで、まずはベスト盤
BORDER TOWN THE VERY BEST OF J. D. SOUTHER
を買いました。
少しして、元々欲しかった、かの名曲を収録した
YOU'RE ONLY LONELYの紙ジャケットを買い、
それがとっても気に入りました。
さらに、2008年、24年振りの新譜
IF THE WORLD WAS YOUが出たとAmazonにおすすめされ、
そうかそうかと買って聴き、これは音楽としてはとてもできがよく
気に入りました。
その後また1年以上が経ち、今年に入って、
ソロの1stであるJOHN DAVID SOUTHERを、
さらにその少し後に2ndのBLACK ROSEを買い、
特に1stは大のお気に入りになりましたが、
それらについては今後も記事にするかもしれないので、
それより前に買ったものについては触れないで進めます。
02 その5枚

ただ、JDという人の名前と存在は10代の頃から知っていました。
イーグルスとよく一緒に曲を作ってる人、という認識でしたが、
僕が、例外はあるけど70年代全ロックの楽曲で最も好きな曲
New Kid In Town(記事はこちら)を一緒に作っていたので、
僕の中では、一目置かれている人ではありました。
しかし、それ以上の存在になるのに20年を費やした、というわけです。
でも、自己弁護するわけじゃないけど、それは仕方ない。
だって、JD自身が24年もアルバムを出していなかったわけだし、
その1984年は僕がヒットチャート中心に洋楽を聴いていた頃で、
JDの曲がヒットしたという記憶もないし、だから、
そのアルバムが出ていたことすら最近まで知らりませんでした。
僕の波とJDの波が合わないままずっと進んでいた、ということでしょう。
さて、8月に買ったサウザー・ヒルマン・フューリー・バンド、
長いので以降は"SHFB"と記しますが、それはとても楽しみでした。
このアルバムは、デヴィッド・ゲフィンが設立したASYLUMレコードの
有望な若手のシンガーソングライターであるJDが、
元バーズ、元ポコの大物2人と組んだバンドであり、
JDのメジャー(当時は新興レーベルでしたが)デビュー作。
その前に、ポコを聴こうと思ったきっかけが、
バッファロー・スプリングフィールド Buffalo Springfield
を遠征で聴いていたことで、カントリー色が濃いロックが
その時の僕の気持ちに合っていたのです。
またまた長いバンド名(笑)、"BS"と記す、BSは元々好きでしたが、
好きなものでもやはり音楽は人それぞれに波があるもので、
いわば「再発見」したという感じでした。
僕は、ビートルズから始まっている人間なので、
作曲者及び歌い手が複数いるバンドは大好きですが、
今回は、メインのスティーヴン・スティルス Stephen Stillsと
ニール・ヤング Neil Youngではなく、いわば「脇役」である
リッチー・フューリーがいい味を出していることに気づき、
家にあるポコを聴き直し、さらにSHFBに行き着きました。
SHFB、アルバムはとってもよかったです。
期待通りのカントリー色があるロックで、すっかり愛聴盤です。
しかし、このアルバム、聴き終わると、
「これはまるでJDのアルバムのようだ」
という印象を受けることに気づきました。
他の2人、クリス・ヒルマンとリッチー・フューリーがお好きな方、
そしてご本人2人にも申し訳ないと思いつつ・・・
真剣に聴くともちろん2人の曲も個性が出ていて素晴らしいですが、
通しで聴くと、それが正直な感想でした。
実際最も印象的な曲も、JDのPretty Goodbyesでしたし。
そこで僕は、JDという人の魅力にあらためて(初めて?)気づき、
慌ててSHFBの残りのもう1枚、2ndの
TROUBLE IN PARADISEを買いました。
聴くと、1st以上にJDの色が強く出てそれだけが印象に残りました。
他の2人は、これじゃ一緒にやっていけないと感じて、
たった2枚でバンドが終わってしまったのではないかと、
いつものように邪推すらしてしまいました。
でも、どうして僕はそう感じたのかな。
僕はいつも言いますが、鼻歌で歌って気持ちがいい
「歌メロ」がいい「歌」としての曲に強くひかれますが、JDは、
単純に、良い歌メロを作る才能とセンスに長けているのでしょう。
もうひとつ感じたのは、例えば上述のイーグルスの曲のように、
他の人と共作した曲を思い浮かべてみても、なんというのかな、
「人間的な要素」を曲に織り込むのことが自然にできる、
だからすっと「心」に伝わってくるんじゃないかな、とも思いました。
JDの人間性についてはまだまったく知る由もなく、
音楽を通して接している人間像とちょっとした情報、
そんな程度ですが、でも、人間的な魅力を感じる人です。
さらに、JDは、音楽を、単に知識としてではなく、
体や心に深くしみ込んでいて、それが表現できるのではないか、
ということも思いました。
歌メロがいいと書きましたが、例えばギターのイントロのフレーズ、
途中のキメのフレーズなど、歌以外の演奏の部分でも、
印象的なフレーズを織り込むことにより曲がいっそう引き立つ、
そのようなつぼを、知識としてではなく、体が知っているのでしょう。
だからJDの曲には、あざとさや嫌味のようなものを感じません。
こうして僕はJDの虜になりました。
03 サウザー・ヒルマン・フューリー・バンドの2枚

SHFBの2ndと一緒に、今回の記事のサウンドトラックともいうべき、
HOME BY DAWNも買いました。
僕は、基本的には好きになったアーティストについては、
すべてのアルバムを買って聴かないと気が済まないたちですが、
JDは、40年になろうというキャリアの中で、SHFB以降では、
正式なアルバムは、ここで紹介したものがすべてなのです。
ということに、SHFBの2ndを注文する際に調べて気づき、
これはそこに追加したもので、最初はいわば「おまけ」でした。
しかし、このアルバムが素晴らしい。
曲がすべていいのはもちろんで後に詳述しますが、
80年代ロックで育った僕としては、80年代サウンドなのがうれしい。
ただ、意味がないくらいシンセが目立ってビートが無機質という、
こてこての80年代サウンドではなく、センスが80年代のもので、
曲の良さを生かすことに主眼を置いた落ち着いた音楽。
初めて聴いたのに、懐かしさに襲われましたが、これは、
キンクス The KinksのSTATE OF CONFUSIONや
元ABBAのフリーダ FridaのSOMETHING'S GOING ONを、
30歳を過ぎてから初めてアルバムとして聴いた際に感じた
懐かしさとまったく同質のものでした。
まあ、落ち着いたというのは、ロックが反骨心という点からは、
当時からつまらないと言われていた部分なんですけど、でも、
人間は自分の生まれは選べない、僕は80年代のロックで育った、
だからやっぱりそれが好きなんですね。
なお、このアルバムの曲の作曲者は、
J.D.サウザーひとりが書いたもの以外のみ
曲名の下に明記しました、ご了承ください。
(All songs written by John David Souther except as noted)
04 2010年10月18日のDawn

Tr1:Home By Dawn
イントロなしに歌い出す、軽快にスウィングした
ちょっとオールディーズ風のロックンロール。
朝までに帰らなきゃならないのに焦っているのかな。
誰が参加しているのか、ブックレットを見るのも楽しいですが、
やはりというか、イーグルスのドン・ヘンリー Don Henleyが参加。
しかし、ブックレットを見て知って驚いたことが。
JDってドラマーだったんだ!
そんなことすら知らなかったのです・・・
そうと分かると、このアルバム、ドラムスにも着目して
聴くようになったから、まったく僕も現金なもんです(笑)。
Tr2:Go Ahead And Rain
このアルバムは、「ニューミュージック」みたいな雰囲気がします。
「ニューミュージック」なんてもう死語ですが、
時代を表す言葉としてここではあえて使っています。
黒人音楽の模倣から始まったロックという音楽が、年月を経て、
演奏者も増え、黒人音楽まで戻らないで、白人のロックの中だけで
受け継がれ再構築されていったという感じの響きですが、
日本でも似たような過程だったのかもしれません。
ただ、じゃあJDが黒人音楽の影響を受けていないかというと、
一昨年の最新作ではジャズっぽい曲もあったように、
そんなことはないとは思います。
だからやっぱり、このアルバムの音は時代の音でしょうかね。
僕の音楽友だちのトニーさんは特に戦後歌謡曲に詳しいのですが、
そのトニーさんがJDが大好きで、それが分かった気がしました。
かといって芯はしっかりとしたロックであるのも、
ロック人間にとっては安心できていいところ。
曲は、パラパラ降る雨のようなギターのイントロが印象的ですが、
こうした効果的な音が歌意外にも多く見受けられるのも、
聴いていて楽しく印象に残りやすい部分だと思います。
JDはここではギターも弾いています。
そして雨を歌った曲は抒情的な曲が多いですね。
Tr3:Say You Will
(J.D.Souther / Danny Kortchmar)
リンダ・ロンシュタットって、かわいいですよね。
声も歌い方も、なんというか、男としてはもう
だだをこねられてもなんでも許しちゃおう、みたいな(笑)。
特に2'37"の"Hold me tight"とアドリブで歌う部分はぐぐっときます。
お互いにお互いを育て合った協力者のようなライバルのような
リンダ・ロンシュタット Linda Ronstadtとのデュエットは、
2人の息がぴったりの、極上のポップチューンに仕上がっています。
ところでこれ、最初はブックレットを見ていなかったのですが、
お喋りしているような面白いギターワークがなんとなく
ダニー・「クーチ」・コーチマー Danny "Kootch" Kortchmar
みたいだなと思いながら聴いていました。
実際のギターはJosh Leo、Billy Walkerの2人でしたが、
しかし曲はJDと「クーチ」の共作、妙に納得しました。
もうひとつ、ビリー・ジョエルっぽい感じなのも僕にはうれしい。
明るく楽しく前向きで、この曲はすっかり僕のものになりました。
Tr4:I'll Take Care Of You
JDのピアノとヴォーカルにギターだけのシンプルなバラード。
JDが聴きやすい要素のひとつが、「過度じゃない」ことかと思いました。
ロマンティックでセンチメンタルだけど押しつけがましくない、
すっきりとした大人のバラードという感じです。
Tr5:All For You
JDはヴォーカリストとしても大好きです。
声も歌い方も好きですし、気持ちの込め方もやはり過度ではない。
この曲は特に80年代を思い出しましたね。
いつも言いますが、深夜に「ベスト・ヒットUSA」を観て、
次の海外ドラマが終わるとテレビ放送が終わる、
その時の妙にすがすがしい空気感みたいな。
時間的にもこのアルバムの主題と合いますし。
Tr6:Night
(J.D.Souther / Waddy Wachtel)
この曲はTr3と同時に一発で気に入りました。
アップテンポで押していく中に曲が劇的に流れていく、
そしてアップテンポで歌メロがよくてちょっと切ない。
僕が好きな要素をすべて詰め込んだ曲です(笑)。
「名手」ワディ・ワクテル Waddy Wachtelのギターが
劇的な曲にさらに豊かな表情をつけています。
曲もJDとワディ・ワクテルの共作です。
Tr7:Don't Know What I'm Gonna Do
ブックレットにJoshと明記されているギターソロが素敵です。
JDは厚めだけど熱くないコーラスワークもセンスいいですね。
きれいに流れていく曲で、やや唐突に早めにささっと
終わってしまうのが、なんとももったいない感じ。
Tr8:Bad News Travels Fast
..." Good news never lasts"...
人生訓みたいな曲も僕はひかれます、好きです。
この曲にはドン・ヘンリーにプラスしてやはりイーグルスの
ティモシー・B・シュミット Timothy B. Schmidtも参加。
西海岸人脈の友情の厚さを感じます。
前の曲からうまく流れている、西海岸の良さを凝縮したような曲。
この中ではいちばん気持ちがこもっている曲で、
JDのドラムスもなかなかいいなあ。
Tr9:All I Want
Tr4のリプライズのような静謐なバラード。
夜明け前に家に帰って、最後にぽつんと絞り出すように歌うと、
期待というよりは寂しさに襲われてしまう・・・
バラードについては、良い意味でのお手本的な曲を書く人ですね。
だから余計に、すっと心に入り込んできます。
Amazonでの順位、204,271位、まあそんなもんでしょう。
今年7月以降に買って初めて聴いた旧譜で
いちばん気に入っているのは、断然、このアルバムですね。
秋に合う響きのアルバムでもあると思いますが、
それはもしかして、音楽自体よりも聴く者の心の在り方かな。
しかし、このアルバムにはひとつ大きな問題が。
アルバムが33分弱しかないのです!
曲も9曲と中途半端な感じがしますが、こんなに素晴らしいのに
すぐに終わってしまうのがもったいない。
ただ、短いので何度も聴けるし、ちょっと時間ができたら聴けるので、
今はそれを良い面に捉えることにしています。
でも、その短さ、中途半端と感じさせる部分は、
当時のJDの悩みや葛藤の表れなのかもしれません。
音楽業界ではよくあることかもしれないですが、
このまま作っていていいのだろうかと悩んだ挙句、
モティヴェイションが続かなかったのかもしれません。
そして、それを取り戻すのに四半世紀を要した・・・
しかし、出来あがって残されたものは極上のポップスであり、
音楽好きとしては、文句を言わずにそれを楽しみたいです。
それにしてもJDはアルバムが少なすぎる!
もっともっと聴きたいという思いが募ってきていますが、
ないものは仕方ないですね・・・
05 2010年10月19日のDawn

最後に・・・
Northernの僕が、Southerを好きになるとは(笑)。
2013年09月29日
DEEP PURPLE IN ROCK
01

DEEP PURPLE IN ROCK Deep Purple
イン・ロック ディープ・パープル (1971)
先ず初めに、僕は、ディープ・パープルは普通に好きです。
思い入れがある、というほどではないのですが、でも時々
とっても聴きたくなるアルバムが複数枚ある、という存在。
今回取り上げる通称「イン・ロック」はしかし、僕が買ったCDの
最初の30枚に入るほど早くに買って聴いていたのですが、
一方で、レッド・ツェッペリンはその前にLP2枚を買っていた、
というのが、僕の若い頃の気持ちのあり様でした。
まあいずれにせよこのアルバムは大好きですが。
浪人生も終わりの頃、CDを買うようになった10枚目かそこらで
MACHINE HEADを買い、非常によかったので、
大学生になって最初の夏休みに帰省した際にこれを買いました。
買ったのはタワーレコード札幌店の最初の店、五番街ビルの2階。
その後すぐにFIREBALLを買ったように、当時の僕には
ディープ・パープルの波が来ていました。
そうそう余談、FIREBALLのCDは家のCDプレイヤーで再生すると
1曲目の途中から音が進まなくなり、聴けなかった。
不良品ということで店に持って行くと、店のCDプレイヤーでは
ちゃんとかかったのですが、事情を話すと新品と交換してくれました。
それは家でもかかりましたが、記念すべき(!?)僕の初めての
CD不良品がそれで、今でもFIREBALLを見るとそれを思い出します。
さて、2枚目に買うのにこれを選んだのは、名盤だとの情報を
得てはいましたが、それ以上にジャケットに引かれたから。
アメリカのサウスダコタ州にあるラシュモア山に刻まれた、
アメリカの大統領の石像を模倣したものですね。
ちなみに、実際はワシントン、ジェファーソン、Tルーズベルト、
リンカーンと4人ですが、パープルは5人組でひとり増えています。
位置的には右端のイアン・ペイスが増えた部分かな。
ディープ・パープルはそれまでクラシック的な音楽をやっていたのが、
ヴォーカルにイアン・ギランを迎えて心機一転、ロックをやってみた、
という意気込みが非常に単純に(いい意味で)現れていますね。
オリジナリティがないといえばそれまでだけど、ロックのアルバムの
アートワークとしてきわめて印象的なもののひとつには違いない。
パープルは、年代的にはそれほど変わらないですが、
「1968年ブルーズロック大爆発の年」には乗り遅れた口でした。
それまでは、前述のようにクラシックの要素を取り入れた
「アートロック」と呼ばれるプログレっぽいことをやっていた。
しかし、レッド・ツェッペリンの成功に大きな刺激を受けた
リッチー・ブラックモアの主導でハードロックに転向。
これが大成功、大ヒット、以降は、ディープ・パープルといえば
ハードロックの代名詞のひとつに挙げられるほどになりました。
それまでのパープルは、アメリカでHushが大ヒットしたものの、
本国イギリスでは一部玄人受けするバンドであったらしく、そうか、
このジャケットはアメリカでは受けていることも表したかったんだ。
02 この岩には誰も刻まれておりません、念のため・・・

CDを買って聴いて先ず驚いたのが、「うっ、音質が悪い・・・」
ふた時代前のテレコを使っていたのではないかというくらいに
音がざりざりでくぐもった響き。
いまだに、僕が普通に聴くビートルズ以降のアルバムで、
これより音質が悪いものには出会ったことがありません。
後でこれより前のパープルを聴いたけど、音質は別に悪くない。
もしかしてロックっぽい荒々しさを出すのに意図的にそうなのか、
と思わなくもないけれど、それにしてはやり過ぎじゃないか。
最初に買ったCDは最初に出たものでまだCDの技術が未熟だったのか、
とも思うけれど、実際は後にリマスター盤を聴いても、やっぱり悪い。
まあでも、内容の素晴らしさでそれがまったく気にならない、とまでは
言い切れないけれど、小さな汚点くらいのもので済んではいますね。
むしろ、この音を聴くのがある意味、楽しみともいえるし。
音楽的にいえば、ハードロックという音楽の教科書的なもの。
ギターの音は全体の音質と相まってまさにハードロックだし、
プログレの要素は感じられるけれど行き過ぎていないし、
かといって冒険的要素はたくさん織り込まれている。
ある面、レッド・ツェッペリンよりハードロック然としていると感じるのは、
ブルーズの影響が薄まっているからでしょう。
ブルージーだけどブルーズではない、ブリティッシュハードだけど、
ブリティッシュブルーズではない、といった音。
今のハードロックやヘヴィメタルだってブルーズの影響を受けた
音楽の末裔だけど、本人たちがブルーズを意識していないところが
ブルーズロックではない、でもブルージーな音楽たらしめているのだと。
ただ、ホワイトスネイクのデヴィッド・カヴァデイルに
僕はブルーズ的なものを感じていて、もっとブルーズっぽいことを
やってほしいんだけど、本人はあくまでもホワイトスネイクに
こだわりたいみたいで、そこがなんというか・・・、という感じです。
だから、ディープ・パープルが1968年「ブルーズロック大爆発の年」に
乗り遅れたのは、むしろよかったのでしょう。
ブルーズから離れてゆくことに挑んで成功した
ハードロックらしい音がここにあります。
03 深紫の風景

Tr1:Speed King
Highway Starの前触れとなったであろうロックンロール。
1曲目としてつかみは完璧だけど、でも、僕が最初に買ったCDは
アメリカWarner Bros.の盤で、最初のオルガンによるイントロがなく、
いきなりドラムスとギターで始まるテイクとなっています。
オリジナルはオルガンのがあるほうだと思うのですが、僕は
最初に聴いたこのオルガンがないほうが断然好きです。
だって、「スピード王」だから、ドン ジャージャンと始まってほしい。
オルガンがあるのは、「スピード王」はスピードだけが売りじゃない
という深い面を見せているといわれればそうかもしれないけれど。
僕がしかし感銘を受けたのはその歌詞。
1番はリトル・リチャード讃歌となっていて、Good Golly Miss Molly、
Tutti Fruttiと出てきてロックンロールへのオマージュだと分かる。
しかも2番、ジョン・レノンがROCK AND ROLLで歌っていた
Rip It Upの歌詞をそのまま引用していて、僕は最初に聴いて
ただ単にかっこいい以上に気持ちがすぐに入り込みました。
当時はまだイアン・ギランがリトル・リチャードのLucilleを
ステージの持ち歌としていることは知らなかったのですが、そうか
ハードロックといってもやっぱりロックンロールなんだ、と分かり
なんだかほっとしたものでした。
というのも、いつも言うHR/HMにはまってしまった悪友のせいで、
HR/HMは「普通のロック」とは別物という思い込みがあったのです。
今から思えばバカみたいですが、二十歳の頃はまだまだ頭が
柔らかく、いろんな影響を受けてしまっていたのでした。
ともあれ、ジョン・レノンの記事(こちら)でも書いたけれど、
ジョンはこの曲を聴いて、Rip It Upを知っていて大好きなやつが
俺以外にもいるんだと心の中でメラメラと燃えるものがあって、
自分でもカヴァーしたのではないかな、と(笑)。
そういう音楽つながりは楽しい、音楽を聴く醍醐味でもありますね。
もう20年も前、王様が日本語に「直訳」して歌っていましたが、
2番の「米を食え、豆つまめ」というのが笑えた。
ジャケットがそのままこれのパクリでしたね、パクリのパクリ。
もうひとつ個人的な思い出があって、これを買った夏休み、
この曲をギターで耳コピーして弾いて遊んでいたこと。
今はできない、若い頃はいい面でも頭が柔らかかったんだな、と。
特に、歌の最後の"see me fly"のバックに入るギターがいい。
最後のほうでイアン・ギランが笑うのがかっこいいですが、
バンドでコピーした人はみんな同じように笑ったのかな(笑)。
(そして会場で受けるのかな・・・)
ともあれ、パープルには強い思い入れがないと書きましたが、
この曲はなんだかんだで思い入れが多いことが分かりました(笑)。
Tr2:Bloodsucker
ブルージーなギターリフに乗ってイアン・ギランがまるで
攻め立てられるように、焦ったように歌うスリリングな曲。
「血をすする奴」というタイトルは、ハードロックを通り越して
ヘヴィメタルにつながってゆく、そういう点でもパープルは、
そしてこのアルバムには大きな意味があるのでしょう。
この曲も勢いでギターリフを弾いて遊んでました(笑)。
Tr3:Child In Time
英国のHRやHMのバンドには必ずといっていいほど、
長尺ものの大作がありますが、これはその先駆けであり
礎ともいえる曲。
一応書いておくと、「天国への階段」よりも1年早い曲。
プログレっぽいことをやってきたことがハードロックという
枠の中で見事に昇華していますね。
最初に聴いた時、パープルってこんなにすごいんだと
いたく感動したのを覚えています。
あ、別に見下していたわけではなく、誰それと比べてとか
そういうのでもなく、ただ単純に音楽だけを聴いてすごいと。
しかも歌詞は戦争に題をとっていて、深層心理をつく歌詞がいい。
やっぱり、読んで歌って考えさせられる歌詞の曲が好き。
"Waiting for the ricochet"というくだりがありますが、この
"ricochet"、「跳弾」という意味、石でやる水切りのことですが、
デヴィッド・ボウイのLET'S DANCEにそのものの曲があり、
T.レックスにもSpaceball Ricochetという曲があります。
ボウイは当時何かで聴き、T.レックスはちょうどこの少し後に
それが入ったTHE SLIDERを買ってよく聴いていたのですが、
グラムロック系をイメージする単語と思い込んでしまい、
イアン・ギランが歌うのがなんだか妙に感じました。
その直後のロジャー・グローヴァーのベースラインが好き。
そこに被さる幽霊のような声がまたいい。
途中でボレロになるのが劇的に素晴らしい。
さらにはテンポが上がってリッチーのギターショーが始まる。
その最後でギターとオルガンの音がシンクロするのは、
オルガンってこんなに攻撃的な楽器なんだって驚きもしました。
当時の僕はどちらかというとアンチテクニック主義者だったんだけど、
やっぱり、上手い人たちの演奏は素晴らしいと思い直しました。
曲想としてはアイアン・メイデンのFear Or The Darkにつながるし、
タイトルもいかにもメタル的イディオム。
最後に狂想曲のように盛り上がって爆発するように終わるのもそう。
パープルの影響力のすごさがあらためて分かりますね。
ハードロック史上に燦然と輝く名曲。
04 紫のトリカブト

Tr4:Flight Of The Rat
このアルバムを買って聴いていたのは夏でしたが、
夏といえば「新潮文庫の100冊」。
僕は浪人生の頃までは文学作品は読んだことがなくて、
大学1年になって文学を文庫で読むことに目覚めて、
開高健の『パニック/裸の王様』もその時に読みました。
この「パニック」という話は、もう記憶があやふやですが、
新潟県かどこかでネズミが大発生して街に押し寄せるという話で、
その文章をシーンとして頭の中に思い浮かべた時、ふと
この曲がBGMとして頭の中に流れてきました。
ただ、恥ずかしい話を暴露すると、僕はこの曲のタイトルを最初は
"Fright" Of The Ratつまり「ネズミの恐怖」と勘違いしていて
だから「パニック」を読んで頭に思い浮かべたようで、後で
"Flight"と勘違いしていたことを知りました。
一応自己弁護すると、この曲は歌詞の中に曲名が出てこないので
"l"と"r"を取り違えも意識の中にはなかったのでした・・・
それはともかく、一度結びついてしまったものはもう離れない(笑)。
爾来、この曲は開高健と結びついて離れなくなりました。
でも、押し寄せてくる、恐いけれどどこかユーモアがある、
という鼠たちの姿には、やっぱり重なるものがあります。
もし誰かが「パニック」を映像化するなら、これをぜひテーマ曲に!
この曲も7分以上ある長尺ものですが、前半の歌の部分は
明るくて軽いギターリフにのった素軽いロックンロールで、
前の曲とはスタイルが違うのがアルバムに奥行きを感じるところ。
Tr5:Into The Fire
ざっくりとしつつ重たいギターリフに乗ったマーチ風の曲。
イアン・ギランが"Fire"と声を荒らげて叫ぶのが印象的だけど、
「ファイアー」の雄叫びもパープルが走りなのかな。
つくづく、影響力の大きさを感じるアルバム。
Tr6:Living Wreck
少し暗くて切迫感がある曲。
「生きている壊れもの」というのはクスリを連想するけれど、
パープルは、実際はともかくイメージとしてはクスリのイメージが
割と薄いと感じていたので、そんなことはないやっぱりロックだ
と思ったものです。
このアルバムのイアン・ギランのヴォーカルはソウルフルな響き。
もちろん、マナーとしてのソウル音楽のものとは違うけれど。
Tr7:Hard Lovin' Man
個人的な感想を言わせてもらえば(そもそもそればかりですが・・・)
このアルバムでひとつだけ惜しいのは、最後のこの曲が、
あまりひねりのない「普通の」曲に聴こえることです。
嫌いじゃないしいい曲だと思うけれど、ここまで6曲で、
アイディアが豊かで想像力に優れた曲を並べてきただけに、
最後は意外なほどあっさり終わってしまうと感じないでもない。
逆にいえば、このアルバムの6曲は僕は異様なほど好きなのかも。
ただ、彼らは再結成第2弾のアルバムで、Hard Lovin' Woman
という曲を作っているように、本人達は気に入っているのかな。
まあ、ひねりがないというのは、逆にいえばストレートな
ハードロックというひとつの雛型を作ったともいえるのでしょう。
この曲も7分以上あるけれど、長いとは感じないのは、
彼らの創作能力が高かったのでしょうね。
リンクは左が国内通常盤、右が30周年記念盤の輸入盤で
ボーナストラックが13曲入っていて、その中には
Black Nightのシングルヴァージョンもあります。
音はリマスターですが、まあ、前述の通り。
そして右のSpeed Kngはオルガンのイントロ付です。
このアルバムは「イン・ロック」と呼ばれていて
僕も通常はそう呼んでいるけれど、実際は
DEEP PURPLE IN ROCKで意味を成す、はず。
キンクスの「ヴィレッジ・グリーン」だって、本当は
THE KINKS ARE THE VILLAGE GREEN...ですから。
まあでも、それはたいした問題ではない。
ディープ・パープルという名前は小学生の頃から知っていて、
レッド・ツェッペリンよりもずっと早くから知っていたのですが、
僕が高校時代に再結成した際にMTV番組で初めて音を聴くまでは、
もっとソフトな雰囲気のある音楽だと思っていました。
僕が中学生の頃、まだ洋楽を聴く前ですが、日本人の誰かが
「ディープ・パープル」というしっとりとした歌をヒットさせていたのが
余計にその思い込みに拍車をかたのだと。
でも、実際に聴くと、まさにハードロックの中のハードロック。
このアルバムは、ハードロックというダイアモンドの原石ですが、
原石のままずっと輝き続けているという奇跡のような1枚。
その時代にしか生まれ得なかった、時代との幸せな関係を
築き、後の時代にも影響を与えた名盤の中の名盤といえるでしょう。
最後はポーラとマーサの写真。
この2頭が一緒の写真はあまりないんですよね。
フォルダを探して見つかったのは、奇跡のよう(笑)。
05


DEEP PURPLE IN ROCK Deep Purple
イン・ロック ディープ・パープル (1971)
先ず初めに、僕は、ディープ・パープルは普通に好きです。
思い入れがある、というほどではないのですが、でも時々
とっても聴きたくなるアルバムが複数枚ある、という存在。
今回取り上げる通称「イン・ロック」はしかし、僕が買ったCDの
最初の30枚に入るほど早くに買って聴いていたのですが、
一方で、レッド・ツェッペリンはその前にLP2枚を買っていた、
というのが、僕の若い頃の気持ちのあり様でした。
まあいずれにせよこのアルバムは大好きですが。
浪人生も終わりの頃、CDを買うようになった10枚目かそこらで
MACHINE HEADを買い、非常によかったので、
大学生になって最初の夏休みに帰省した際にこれを買いました。
買ったのはタワーレコード札幌店の最初の店、五番街ビルの2階。
その後すぐにFIREBALLを買ったように、当時の僕には
ディープ・パープルの波が来ていました。
そうそう余談、FIREBALLのCDは家のCDプレイヤーで再生すると
1曲目の途中から音が進まなくなり、聴けなかった。
不良品ということで店に持って行くと、店のCDプレイヤーでは
ちゃんとかかったのですが、事情を話すと新品と交換してくれました。
それは家でもかかりましたが、記念すべき(!?)僕の初めての
CD不良品がそれで、今でもFIREBALLを見るとそれを思い出します。
さて、2枚目に買うのにこれを選んだのは、名盤だとの情報を
得てはいましたが、それ以上にジャケットに引かれたから。
アメリカのサウスダコタ州にあるラシュモア山に刻まれた、
アメリカの大統領の石像を模倣したものですね。
ちなみに、実際はワシントン、ジェファーソン、Tルーズベルト、
リンカーンと4人ですが、パープルは5人組でひとり増えています。
位置的には右端のイアン・ペイスが増えた部分かな。
ディープ・パープルはそれまでクラシック的な音楽をやっていたのが、
ヴォーカルにイアン・ギランを迎えて心機一転、ロックをやってみた、
という意気込みが非常に単純に(いい意味で)現れていますね。
オリジナリティがないといえばそれまでだけど、ロックのアルバムの
アートワークとしてきわめて印象的なもののひとつには違いない。
パープルは、年代的にはそれほど変わらないですが、
「1968年ブルーズロック大爆発の年」には乗り遅れた口でした。
それまでは、前述のようにクラシックの要素を取り入れた
「アートロック」と呼ばれるプログレっぽいことをやっていた。
しかし、レッド・ツェッペリンの成功に大きな刺激を受けた
リッチー・ブラックモアの主導でハードロックに転向。
これが大成功、大ヒット、以降は、ディープ・パープルといえば
ハードロックの代名詞のひとつに挙げられるほどになりました。
それまでのパープルは、アメリカでHushが大ヒットしたものの、
本国イギリスでは一部玄人受けするバンドであったらしく、そうか、
このジャケットはアメリカでは受けていることも表したかったんだ。
02 この岩には誰も刻まれておりません、念のため・・・

CDを買って聴いて先ず驚いたのが、「うっ、音質が悪い・・・」
ふた時代前のテレコを使っていたのではないかというくらいに
音がざりざりでくぐもった響き。
いまだに、僕が普通に聴くビートルズ以降のアルバムで、
これより音質が悪いものには出会ったことがありません。
後でこれより前のパープルを聴いたけど、音質は別に悪くない。
もしかしてロックっぽい荒々しさを出すのに意図的にそうなのか、
と思わなくもないけれど、それにしてはやり過ぎじゃないか。
最初に買ったCDは最初に出たものでまだCDの技術が未熟だったのか、
とも思うけれど、実際は後にリマスター盤を聴いても、やっぱり悪い。
まあでも、内容の素晴らしさでそれがまったく気にならない、とまでは
言い切れないけれど、小さな汚点くらいのもので済んではいますね。
むしろ、この音を聴くのがある意味、楽しみともいえるし。
音楽的にいえば、ハードロックという音楽の教科書的なもの。
ギターの音は全体の音質と相まってまさにハードロックだし、
プログレの要素は感じられるけれど行き過ぎていないし、
かといって冒険的要素はたくさん織り込まれている。
ある面、レッド・ツェッペリンよりハードロック然としていると感じるのは、
ブルーズの影響が薄まっているからでしょう。
ブルージーだけどブルーズではない、ブリティッシュハードだけど、
ブリティッシュブルーズではない、といった音。
今のハードロックやヘヴィメタルだってブルーズの影響を受けた
音楽の末裔だけど、本人たちがブルーズを意識していないところが
ブルーズロックではない、でもブルージーな音楽たらしめているのだと。
ただ、ホワイトスネイクのデヴィッド・カヴァデイルに
僕はブルーズ的なものを感じていて、もっとブルーズっぽいことを
やってほしいんだけど、本人はあくまでもホワイトスネイクに
こだわりたいみたいで、そこがなんというか・・・、という感じです。
だから、ディープ・パープルが1968年「ブルーズロック大爆発の年」に
乗り遅れたのは、むしろよかったのでしょう。
ブルーズから離れてゆくことに挑んで成功した
ハードロックらしい音がここにあります。
03 深紫の風景

Tr1:Speed King
Highway Starの前触れとなったであろうロックンロール。
1曲目としてつかみは完璧だけど、でも、僕が最初に買ったCDは
アメリカWarner Bros.の盤で、最初のオルガンによるイントロがなく、
いきなりドラムスとギターで始まるテイクとなっています。
オリジナルはオルガンのがあるほうだと思うのですが、僕は
最初に聴いたこのオルガンがないほうが断然好きです。
だって、「スピード王」だから、ドン ジャージャンと始まってほしい。
オルガンがあるのは、「スピード王」はスピードだけが売りじゃない
という深い面を見せているといわれればそうかもしれないけれど。
僕がしかし感銘を受けたのはその歌詞。
1番はリトル・リチャード讃歌となっていて、Good Golly Miss Molly、
Tutti Fruttiと出てきてロックンロールへのオマージュだと分かる。
しかも2番、ジョン・レノンがROCK AND ROLLで歌っていた
Rip It Upの歌詞をそのまま引用していて、僕は最初に聴いて
ただ単にかっこいい以上に気持ちがすぐに入り込みました。
当時はまだイアン・ギランがリトル・リチャードのLucilleを
ステージの持ち歌としていることは知らなかったのですが、そうか
ハードロックといってもやっぱりロックンロールなんだ、と分かり
なんだかほっとしたものでした。
というのも、いつも言うHR/HMにはまってしまった悪友のせいで、
HR/HMは「普通のロック」とは別物という思い込みがあったのです。
今から思えばバカみたいですが、二十歳の頃はまだまだ頭が
柔らかく、いろんな影響を受けてしまっていたのでした。
ともあれ、ジョン・レノンの記事(こちら)でも書いたけれど、
ジョンはこの曲を聴いて、Rip It Upを知っていて大好きなやつが
俺以外にもいるんだと心の中でメラメラと燃えるものがあって、
自分でもカヴァーしたのではないかな、と(笑)。
そういう音楽つながりは楽しい、音楽を聴く醍醐味でもありますね。
もう20年も前、王様が日本語に「直訳」して歌っていましたが、
2番の「米を食え、豆つまめ」というのが笑えた。
ジャケットがそのままこれのパクリでしたね、パクリのパクリ。
もうひとつ個人的な思い出があって、これを買った夏休み、
この曲をギターで耳コピーして弾いて遊んでいたこと。
今はできない、若い頃はいい面でも頭が柔らかかったんだな、と。
特に、歌の最後の"see me fly"のバックに入るギターがいい。
最後のほうでイアン・ギランが笑うのがかっこいいですが、
バンドでコピーした人はみんな同じように笑ったのかな(笑)。
(そして会場で受けるのかな・・・)
ともあれ、パープルには強い思い入れがないと書きましたが、
この曲はなんだかんだで思い入れが多いことが分かりました(笑)。
Tr2:Bloodsucker
ブルージーなギターリフに乗ってイアン・ギランがまるで
攻め立てられるように、焦ったように歌うスリリングな曲。
「血をすする奴」というタイトルは、ハードロックを通り越して
ヘヴィメタルにつながってゆく、そういう点でもパープルは、
そしてこのアルバムには大きな意味があるのでしょう。
この曲も勢いでギターリフを弾いて遊んでました(笑)。
Tr3:Child In Time
英国のHRやHMのバンドには必ずといっていいほど、
長尺ものの大作がありますが、これはその先駆けであり
礎ともいえる曲。
一応書いておくと、「天国への階段」よりも1年早い曲。
プログレっぽいことをやってきたことがハードロックという
枠の中で見事に昇華していますね。
最初に聴いた時、パープルってこんなにすごいんだと
いたく感動したのを覚えています。
あ、別に見下していたわけではなく、誰それと比べてとか
そういうのでもなく、ただ単純に音楽だけを聴いてすごいと。
しかも歌詞は戦争に題をとっていて、深層心理をつく歌詞がいい。
やっぱり、読んで歌って考えさせられる歌詞の曲が好き。
"Waiting for the ricochet"というくだりがありますが、この
"ricochet"、「跳弾」という意味、石でやる水切りのことですが、
デヴィッド・ボウイのLET'S DANCEにそのものの曲があり、
T.レックスにもSpaceball Ricochetという曲があります。
ボウイは当時何かで聴き、T.レックスはちょうどこの少し後に
それが入ったTHE SLIDERを買ってよく聴いていたのですが、
グラムロック系をイメージする単語と思い込んでしまい、
イアン・ギランが歌うのがなんだか妙に感じました。
その直後のロジャー・グローヴァーのベースラインが好き。
そこに被さる幽霊のような声がまたいい。
途中でボレロになるのが劇的に素晴らしい。
さらにはテンポが上がってリッチーのギターショーが始まる。
その最後でギターとオルガンの音がシンクロするのは、
オルガンってこんなに攻撃的な楽器なんだって驚きもしました。
当時の僕はどちらかというとアンチテクニック主義者だったんだけど、
やっぱり、上手い人たちの演奏は素晴らしいと思い直しました。
曲想としてはアイアン・メイデンのFear Or The Darkにつながるし、
タイトルもいかにもメタル的イディオム。
最後に狂想曲のように盛り上がって爆発するように終わるのもそう。
パープルの影響力のすごさがあらためて分かりますね。
ハードロック史上に燦然と輝く名曲。
04 紫のトリカブト

Tr4:Flight Of The Rat
このアルバムを買って聴いていたのは夏でしたが、
夏といえば「新潮文庫の100冊」。
僕は浪人生の頃までは文学作品は読んだことがなくて、
大学1年になって文学を文庫で読むことに目覚めて、
開高健の『パニック/裸の王様』もその時に読みました。
この「パニック」という話は、もう記憶があやふやですが、
新潟県かどこかでネズミが大発生して街に押し寄せるという話で、
その文章をシーンとして頭の中に思い浮かべた時、ふと
この曲がBGMとして頭の中に流れてきました。
ただ、恥ずかしい話を暴露すると、僕はこの曲のタイトルを最初は
"Fright" Of The Ratつまり「ネズミの恐怖」と勘違いしていて
だから「パニック」を読んで頭に思い浮かべたようで、後で
"Flight"と勘違いしていたことを知りました。
一応自己弁護すると、この曲は歌詞の中に曲名が出てこないので
"l"と"r"を取り違えも意識の中にはなかったのでした・・・
それはともかく、一度結びついてしまったものはもう離れない(笑)。
爾来、この曲は開高健と結びついて離れなくなりました。
でも、押し寄せてくる、恐いけれどどこかユーモアがある、
という鼠たちの姿には、やっぱり重なるものがあります。
もし誰かが「パニック」を映像化するなら、これをぜひテーマ曲に!
この曲も7分以上ある長尺ものですが、前半の歌の部分は
明るくて軽いギターリフにのった素軽いロックンロールで、
前の曲とはスタイルが違うのがアルバムに奥行きを感じるところ。
Tr5:Into The Fire
ざっくりとしつつ重たいギターリフに乗ったマーチ風の曲。
イアン・ギランが"Fire"と声を荒らげて叫ぶのが印象的だけど、
「ファイアー」の雄叫びもパープルが走りなのかな。
つくづく、影響力の大きさを感じるアルバム。
Tr6:Living Wreck
少し暗くて切迫感がある曲。
「生きている壊れもの」というのはクスリを連想するけれど、
パープルは、実際はともかくイメージとしてはクスリのイメージが
割と薄いと感じていたので、そんなことはないやっぱりロックだ
と思ったものです。
このアルバムのイアン・ギランのヴォーカルはソウルフルな響き。
もちろん、マナーとしてのソウル音楽のものとは違うけれど。
Tr7:Hard Lovin' Man
個人的な感想を言わせてもらえば(そもそもそればかりですが・・・)
このアルバムでひとつだけ惜しいのは、最後のこの曲が、
あまりひねりのない「普通の」曲に聴こえることです。
嫌いじゃないしいい曲だと思うけれど、ここまで6曲で、
アイディアが豊かで想像力に優れた曲を並べてきただけに、
最後は意外なほどあっさり終わってしまうと感じないでもない。
逆にいえば、このアルバムの6曲は僕は異様なほど好きなのかも。
ただ、彼らは再結成第2弾のアルバムで、Hard Lovin' Woman
という曲を作っているように、本人達は気に入っているのかな。
まあ、ひねりがないというのは、逆にいえばストレートな
ハードロックというひとつの雛型を作ったともいえるのでしょう。
この曲も7分以上あるけれど、長いとは感じないのは、
彼らの創作能力が高かったのでしょうね。
リンクは左が国内通常盤、右が30周年記念盤の輸入盤で
ボーナストラックが13曲入っていて、その中には
Black Nightのシングルヴァージョンもあります。
音はリマスターですが、まあ、前述の通り。
そして右のSpeed Kngはオルガンのイントロ付です。
このアルバムは「イン・ロック」と呼ばれていて
僕も通常はそう呼んでいるけれど、実際は
DEEP PURPLE IN ROCKで意味を成す、はず。
キンクスの「ヴィレッジ・グリーン」だって、本当は
THE KINKS ARE THE VILLAGE GREEN...ですから。
まあでも、それはたいした問題ではない。
ディープ・パープルという名前は小学生の頃から知っていて、
レッド・ツェッペリンよりもずっと早くから知っていたのですが、
僕が高校時代に再結成した際にMTV番組で初めて音を聴くまでは、
もっとソフトな雰囲気のある音楽だと思っていました。
僕が中学生の頃、まだ洋楽を聴く前ですが、日本人の誰かが
「ディープ・パープル」というしっとりとした歌をヒットさせていたのが
余計にその思い込みに拍車をかたのだと。
でも、実際に聴くと、まさにハードロックの中のハードロック。
このアルバムは、ハードロックというダイアモンドの原石ですが、
原石のままずっと輝き続けているという奇跡のような1枚。
その時代にしか生まれ得なかった、時代との幸せな関係を
築き、後の時代にも影響を与えた名盤の中の名盤といえるでしょう。
最後はポーラとマーサの写真。
この2頭が一緒の写真はあまりないんですよね。
フォルダを探して見つかったのは、奇跡のよう(笑)。
05

2013年09月09日
PARADISE VALLEY ジョン・メイヤーの新譜
01

PARADISE VALLEY John Mayer
パラダイス・ヴァレイ ジョン・メイヤー (2013)
ジョン・メイヤーの新譜の記事です。
犬がいるジャケットだけ先行公開していました(記事はこちら)。
ジョン・メイヤーは昨年5月にスタジオアルバムが出ましたが、
1年と少しでもう新譜が出ました。
情報を得たのは5月頃、最初は何かの編集盤かライヴ盤か
とも思いましたが、正規のスタジオアルバムの新作でした。
さらには、ここ4年で3枚目というのも、最近の人には珍しく
リリースが多いですね、まあニール・ヤングは別として(笑)。
僕はその4年前の前々作から真剣に聴き始めたので、
まだまだジョン・メイヤー歴は浅いですが、前作が出た昨年、
3年振り(実際は2年半)というのはずいぶんと早いと思ったものです。
なお、前作BORN AND RAISEDの記事はこちら
前々作BATTLE STUDIESの記事はこちら、をご覧ください。
さて、今回のアルバム、かけて最初に感じたことを書き表すと、
「レイドバックしたアルバムだなあ」、でした。
具体的にいえば1970年代のエリック・クラプトンの音の雰囲気。
ただし音作りが似ているという意味ではありません、念のため。
と書いて、感じたことに対して随分と穏やかな表現を使ったなあと、
読み返して自分でも思いました。
だから、もう少し自分の心に正直に書くと、こうでした。
「この若さでレイドバックしちゃうのかよ、まいったなあ」
「レイドバック」とは、音楽が全体的に緩くてゆったりとした雰囲気で、
ぐいぐいと気持ちが前に進むのではなく気持ちを投げ出したような感覚、
ギターの音も鋭くなく、リズムは少し引いていて、歌い方も穏やか、
といったところでしょうか。
横暴な言い方をすれば、パンクの正反対の音楽。
前作も、今風のロック然とした前々作から見れば引いた感じがしましたが、
でもそれは直接的にアコースティックギターを前面に出していることと、
ブルーズへの回帰と70年代回顧をひとまとめにしたような音作りが
そのように感じさせたのだと思われます。
しかし今作は、全体的に引いている、どこがどうというものではない。
この若さでと書いたけど、1977年生まれのジョン・メイヤーは今年で36歳。
エリック・クラプトンがレイドバックしていたのはまさに30代のことだから、
実はさして若いというわけでもないことに気づきます。
僕自身もそうでしたが、やはり30代半ばになると、聴く音楽、聴きたいと
自然と思わされる音楽がだんだんと穏やかなものになってゆきました。
今はヘヴィメタルも時々とたまにの間くらいしか聴かないし。
まあ、でも多分、ソウルが大好きな人の中では圧倒的に
ヘヴィメタルもよく聴く方の人だとは思うけれど(笑)。
まあそれはともかく、ジョン・メイヤーが「レイドバック」したのは
人間として自然の成り行きであろうことは理解できます。
ずっと走ってきて、ツアーに出て、そろそろゆっくりとしたいだろうし。
まあ、その割に2年連続でアルバムを作っているので、
音楽の創作意欲は高い、むしろ最盛期を迎えることになるでしょう。
ただ、「まいったなあ」と書いたように、実は最初の数回は
あまり強く響いてきませんでした。
前作と前々作は1回目から心の底に響いてきていたのに、
少々がっかり、だから「まいったなあ」でした。
でも、1回、5回、19回と聴き重ねてゆくにつれて、
じわじわとよくなってきました。
それは「レイドバック」した音楽の真価でもあるのでしょう。
緩いのだから、歌メロが目立ち過ぎるのはよくない。
歌そのものよりも全体を包み込む雰囲気を味わう音楽。
いつも言います、僕は歌メロに人百倍こだわって聴いていますが、
「まいったなあ」なんて言ってしまったけれど、見方や聴き方を
ちょっと変えればいいだけの話でした。
今はほんとうに素晴らしくて大好きで毎日聴いています。
今回、もうひとつ強く感じたこと。
「アウトドアなアルバムだなあ」
犬を連れて荒野に立つジャケットからしてその雰囲気ですからね。
ただ、"valley"=「谷」というには平らだなあと思うんだけど、
それは山が急峻で土地が狭い日本人の感覚なのでしょうね(笑)。
もうひとつ、"valley"には「包み込む場所」という意味も
持たせているのかもしれない、そんな感じがします。
僕は自然の中にいる時には音楽は聴かない人間ですが、
その行き帰りの車の中で、そして家で、街の中で、
自然に思いをはせながら聴くアルバムといえるでしょう。
「自然」という言葉には主に2つの意味がありますが、このアルバムは
そのどちらの「自然」にも通じる心の在り方を示してくれています。
Tr1:Wildfire
1曲目からいきなり"wild"と出てきます。
歌い出しの最初の単語が"river"です。
もうそれだけで自然と自然に心がいきますね。
ミドルテンポの穏やかな曲で、でもギターの音やハンドクラップ
そしてコーラスなどが元気に、でも元気すぎない程度に響いてくる。
サビの声がふうっと裏返るのももはや彼のトレードマーク。
曲で一度しかない中間部でちょっと不安気な響きになるけれど、
それを立て直すように半裏声の元気な部分を持ってくる。
ギターは、キーボードで弾いたホーンのようなちょっと変わった音色で、
軽やかに語りかけてくるよう。
ところで、イントロの最初に入ってくるギターの最初の2音が、
ボブ・ディランの昨年のアルバムTEMPESTの1曲目のそれと同じで、
意識はしていないだろうけど、ディランのそれも久しぶりに聴きました。
Tr2:Dear Marie
アコースティックギター中心のカントリータッチの曲。
ポール・マッカートニーがこの手の曲が上手いんですが、でも
ペダルスティールを入れるのはポールにはないところ。
タッチは軽いけど、歌がどこか沈んだ雰囲気、明るくない。
歌詞を読むと、幼馴染の女性への片思いを描いているのかな。
今の君が雑誌に載っている僕を見るとどう思うかな、
というのは多分に自明なくだりですが、そういえば前作でも、
「ローリング・ストーン」誌が歌詞に出てきたりしていて、
さらりと現実的なことを挟み込んでくる人ですね。
最後の方で開放的なコーラスを入れて曲が高揚してきますが、
胸の中の思いを、今できる背一杯のやりかたで開放している感じ。
「日常生活の中の小さな不安とそれに対峙する心」
僕は、ジョン・メイヤーの音楽のテーマはそれだと思っているのですが、
そういう表現には「レイドバック」はいいのでしょうね。
Tr3:Waiting On The Day
もう少しおとなしくなったやはりカントリータッチの曲。
歌っていることも前の曲の続きと捉えることができますが、
でも、待っている日は、来ないのかもしれない・・・
「待つ」というのは、気持ちが前に進むのとは正反対の行為ですよね。
エレクトリックギターのソロは、気持ちが弱いと泣けてくるかも。
Tr4:Paper Doll
もっともっと大人しくなった、でもこれは最初からエレクトリックギター。
気持ちのかけらがこぼれる、といった感じのこのギターの音色がいい。
彼女を紙人形に喩えていて、君には22の姿があるけれど、
どれが本当の姿か、自分でも分からない。
天使の姿になると、他の誰かが空を描いてくれれば飛べるだろう。
そういうことか、深刻なこともさらりと受け流してしまうのは彼らしいところ。
Tr5:Call Me The Breeze
ジョン・メイヤーは「そよ風」と呼ばれているんだ。
選ぶ単語がまさに自然ですよね。
テンポを上げてシャッフルの小走りするような曲。
まさに心地よい響き。
軽快なエレクトリックギターのソロが調子が出てきたなあ、という
ところで誰かが声をかけてギターが止まり曲が終わってしまうのは、
ユーモアとしては面白いけれど、もう少しギターを聴かせてほしい(笑)。
Tr6:Who You Love (feat. Katy Perry)
「ベストヒットUSA」でもよく見るケイティ・ペリーがゲスト。
曲は穏やかなバラードで、ラブソングといえる。
あ、穏やかな、はもはや書かなくてもいいでしょうかね(笑)。
ケイティ・ペリーはそこで見て耳にしたことがある程度だから、
よく知らないけれど、このアルバムの中では声が少し強いかな。
悪くはないんだけど、ちょっと引っかかるかな、僕には。
ただこれは曲のよさがすべてを覆い尽くしているのでよしとするか。
話題性もあってシングルヒットしそうな曲、ふた昔前なら、ですが。
02

ここでひと休み。
このCD、裏トレイの写真では、ジョン・メイヤーが愛犬(かな)に
表では自分が被っていた帽子を被せていますが、
ロックスターでもこんなことするんだ、とっても親近感を覚えますね(笑)。
さて
Tr7:I Will Be Found (Lost At Sea)
僕が最初に気に入ったのはこの曲でした。
ピアノで荘重に始まる趣きがかなり違う曲であり、
バラードといえるスロウな曲、歌メロが分かりやすい。
そして何より歌詞が非常にいい。
「僕はきっと見つけられるだろう;海で遭難した」というこの歌、
歌詞を読むと、どうやらハイウェイを走っている、どういうこと!?
そこにいるのに、誰にも見られてない孤独感。
スターとはそういうものなのかもしれない。
ほんとうの自分を見せたくても見せられない。
タイトルの言葉に続く歌詞はこうです。
「僕は大きな木の下に葬られるだろう」
だけど、生きていようと死んでしまおうと、きっと見つかるだろうと
歌ってしまうのは、根底の部分で人間の心を信じているから。
そう歌いながらも悲観的ではないし、この世界が無常であり
虚しいものであるとも感じていない。
悟りとまではいわないけれど
どこか開き直ったすがすがしさがあるのもまた、そういうこと。
ジョン・メイヤーの音楽に人間味を感じるのは、そうした部分ですね。
こういう歌詞の曲が僕は大好き。
今年出会った新曲では、僕の心の中心に最も近づいた曲です。
Tr8:Wildfire (feat. Frank Ocean)
ゲストはフランク・オーシャン。
名前すら知らない人でしたが、調べるとアメリカのR&B歌手とのこと。
ゲストの名前まで自然にこだわっていたのかな(笑)。
こちらは傾向としてはジョン・メイヤーに似た感じの声。
1曲目と同じタイトル、リプライズという意識なのかな、でも似ていない。
と思って聴いていると、フランク・オーシャンが、教会音楽風の曲を
ほとんどひとりで歌って1分くらいで終わってしまう。
そのためにゲストを招いたのはある意味贅沢、でも、
そうでなければイメージ通りの音にならなかったのでしょうね。
Tr9:You're No One 'Til Someone Let's You Down
これはいちばんカントリーっぽいかな。
断っておきますが、あくまでもカントリー「っぽい」ロックということで、
間奏の入り方がいかにもカントリーっぽいロックといった趣き。
ギターの感じがビートルズの1965年前半つまりHELP!の頃っぽい。
でも、曲名が説明的で長いのは昔のカントリーっぽいかな。
もっと明るくてもいいのに、やはりここでもいつもの姿勢を崩さず、
かすかな不安を抱えながら歌う。
Tr10:Badge And Gun
アコースティックギターでしっとりと聴かせるカントリーバラード風の曲。
「バッヂと銃」というのは、保安官のことかな。
7か月もここで隠れていたので、そろそろ「バッヂと銃」をくれ、
もっと遠くに行きたいんだ、と、西部劇が頭に浮かぶ内容。
でも洗練されたジョン・メイヤーのセンスは現代的に響いてくる。
それは、大都会の孤独を表しているのでしょう。
この曲は歌い始めてすぐに声がふうっと高くなるのですが、
その歌い方も板についてきた感じがします。
これは歌メロがとってもいいしもう口ずさむようになったんだけど、
どうして最初はそこに気づかなかったのか・・・
鈍くなってますね、僕も(笑)。
Tr11:On The Way Home
最後3曲はカントリータッチの曲。
やっぱり、アメリカの人は家に帰りたいという歌が好きなんだな。
基本的に冷静なジョン・メイヤーはしかし、心が熱くなるわけではなく、
さらりと歌う、それでいて曲には気持ちがこもっている。
曲はこのスタイルの中では盛り上がろうとしているのも感じて、特に
ペダルスティールとハーモニカが気持ちを煽っている。
リンクは左が国内盤、ボーナストラックが入っていますが、
僕が買ったのは右の輸入盤、そのうち国内盤も買わなきゃ。
穏やかで自然を感じる響きは、まさに
「自然と音楽を愛する者」向きのアルバムといえるでしょう。
もちろんジョン・メイヤーが僕のことを知るはずもないけれど(笑)。
そしてこのアルバムは日本の秋にはまさにぴったり。
これからますます聴き入って好きになる1枚です。
ジョン・メイヤーはまだ3枚目だけど、ほんとうにいいなあ。
そういえば昨年のアルバムの後で来日公演がなかったけれど、
今度こそ、もう今年はないだろうから、来年、来日しないかな。
ところで最後に余談。
僕のBLOG、ジョン・メイヤーのアルバム記事がなぜか
アクセス数がよく伸びて、前2作はともに1000を超えました。
ジョン・メイヤーはまだ新しい人なので、昔の大御所ほどには
記事を書く人がまだまだ少ない、ということなのかな。
アクセス数を伸ばしたいという意味ではなく、でもそういうことから、
ジョン・メイヤーの記事は早くに上げたいと今回も思いました。
まあ、ひと月以上経ってしまいましたが、でも早いほうです(笑)。
今日の最後は、マーサがCDを紹介します。
03


PARADISE VALLEY John Mayer
パラダイス・ヴァレイ ジョン・メイヤー (2013)
ジョン・メイヤーの新譜の記事です。
犬がいるジャケットだけ先行公開していました(記事はこちら)。
ジョン・メイヤーは昨年5月にスタジオアルバムが出ましたが、
1年と少しでもう新譜が出ました。
情報を得たのは5月頃、最初は何かの編集盤かライヴ盤か
とも思いましたが、正規のスタジオアルバムの新作でした。
さらには、ここ4年で3枚目というのも、最近の人には珍しく
リリースが多いですね、まあニール・ヤングは別として(笑)。
僕はその4年前の前々作から真剣に聴き始めたので、
まだまだジョン・メイヤー歴は浅いですが、前作が出た昨年、
3年振り(実際は2年半)というのはずいぶんと早いと思ったものです。
なお、前作BORN AND RAISEDの記事はこちら
前々作BATTLE STUDIESの記事はこちら、をご覧ください。
さて、今回のアルバム、かけて最初に感じたことを書き表すと、
「レイドバックしたアルバムだなあ」、でした。
具体的にいえば1970年代のエリック・クラプトンの音の雰囲気。
ただし音作りが似ているという意味ではありません、念のため。
と書いて、感じたことに対して随分と穏やかな表現を使ったなあと、
読み返して自分でも思いました。
だから、もう少し自分の心に正直に書くと、こうでした。
「この若さでレイドバックしちゃうのかよ、まいったなあ」
「レイドバック」とは、音楽が全体的に緩くてゆったりとした雰囲気で、
ぐいぐいと気持ちが前に進むのではなく気持ちを投げ出したような感覚、
ギターの音も鋭くなく、リズムは少し引いていて、歌い方も穏やか、
といったところでしょうか。
横暴な言い方をすれば、パンクの正反対の音楽。
前作も、今風のロック然とした前々作から見れば引いた感じがしましたが、
でもそれは直接的にアコースティックギターを前面に出していることと、
ブルーズへの回帰と70年代回顧をひとまとめにしたような音作りが
そのように感じさせたのだと思われます。
しかし今作は、全体的に引いている、どこがどうというものではない。
この若さでと書いたけど、1977年生まれのジョン・メイヤーは今年で36歳。
エリック・クラプトンがレイドバックしていたのはまさに30代のことだから、
実はさして若いというわけでもないことに気づきます。
僕自身もそうでしたが、やはり30代半ばになると、聴く音楽、聴きたいと
自然と思わされる音楽がだんだんと穏やかなものになってゆきました。
今はヘヴィメタルも時々とたまにの間くらいしか聴かないし。
まあ、でも多分、ソウルが大好きな人の中では圧倒的に
ヘヴィメタルもよく聴く方の人だとは思うけれど(笑)。
まあそれはともかく、ジョン・メイヤーが「レイドバック」したのは
人間として自然の成り行きであろうことは理解できます。
ずっと走ってきて、ツアーに出て、そろそろゆっくりとしたいだろうし。
まあ、その割に2年連続でアルバムを作っているので、
音楽の創作意欲は高い、むしろ最盛期を迎えることになるでしょう。
ただ、「まいったなあ」と書いたように、実は最初の数回は
あまり強く響いてきませんでした。
前作と前々作は1回目から心の底に響いてきていたのに、
少々がっかり、だから「まいったなあ」でした。
でも、1回、5回、19回と聴き重ねてゆくにつれて、
じわじわとよくなってきました。
それは「レイドバック」した音楽の真価でもあるのでしょう。
緩いのだから、歌メロが目立ち過ぎるのはよくない。
歌そのものよりも全体を包み込む雰囲気を味わう音楽。
いつも言います、僕は歌メロに人百倍こだわって聴いていますが、
「まいったなあ」なんて言ってしまったけれど、見方や聴き方を
ちょっと変えればいいだけの話でした。
今はほんとうに素晴らしくて大好きで毎日聴いています。
今回、もうひとつ強く感じたこと。
「アウトドアなアルバムだなあ」
犬を連れて荒野に立つジャケットからしてその雰囲気ですからね。
ただ、"valley"=「谷」というには平らだなあと思うんだけど、
それは山が急峻で土地が狭い日本人の感覚なのでしょうね(笑)。
もうひとつ、"valley"には「包み込む場所」という意味も
持たせているのかもしれない、そんな感じがします。
僕は自然の中にいる時には音楽は聴かない人間ですが、
その行き帰りの車の中で、そして家で、街の中で、
自然に思いをはせながら聴くアルバムといえるでしょう。
「自然」という言葉には主に2つの意味がありますが、このアルバムは
そのどちらの「自然」にも通じる心の在り方を示してくれています。
Tr1:Wildfire
1曲目からいきなり"wild"と出てきます。
歌い出しの最初の単語が"river"です。
もうそれだけで自然と自然に心がいきますね。
ミドルテンポの穏やかな曲で、でもギターの音やハンドクラップ
そしてコーラスなどが元気に、でも元気すぎない程度に響いてくる。
サビの声がふうっと裏返るのももはや彼のトレードマーク。
曲で一度しかない中間部でちょっと不安気な響きになるけれど、
それを立て直すように半裏声の元気な部分を持ってくる。
ギターは、キーボードで弾いたホーンのようなちょっと変わった音色で、
軽やかに語りかけてくるよう。
ところで、イントロの最初に入ってくるギターの最初の2音が、
ボブ・ディランの昨年のアルバムTEMPESTの1曲目のそれと同じで、
意識はしていないだろうけど、ディランのそれも久しぶりに聴きました。
Tr2:Dear Marie
アコースティックギター中心のカントリータッチの曲。
ポール・マッカートニーがこの手の曲が上手いんですが、でも
ペダルスティールを入れるのはポールにはないところ。
タッチは軽いけど、歌がどこか沈んだ雰囲気、明るくない。
歌詞を読むと、幼馴染の女性への片思いを描いているのかな。
今の君が雑誌に載っている僕を見るとどう思うかな、
というのは多分に自明なくだりですが、そういえば前作でも、
「ローリング・ストーン」誌が歌詞に出てきたりしていて、
さらりと現実的なことを挟み込んでくる人ですね。
最後の方で開放的なコーラスを入れて曲が高揚してきますが、
胸の中の思いを、今できる背一杯のやりかたで開放している感じ。
「日常生活の中の小さな不安とそれに対峙する心」
僕は、ジョン・メイヤーの音楽のテーマはそれだと思っているのですが、
そういう表現には「レイドバック」はいいのでしょうね。
Tr3:Waiting On The Day
もう少しおとなしくなったやはりカントリータッチの曲。
歌っていることも前の曲の続きと捉えることができますが、
でも、待っている日は、来ないのかもしれない・・・
「待つ」というのは、気持ちが前に進むのとは正反対の行為ですよね。
エレクトリックギターのソロは、気持ちが弱いと泣けてくるかも。
Tr4:Paper Doll
もっともっと大人しくなった、でもこれは最初からエレクトリックギター。
気持ちのかけらがこぼれる、といった感じのこのギターの音色がいい。
彼女を紙人形に喩えていて、君には22の姿があるけれど、
どれが本当の姿か、自分でも分からない。
天使の姿になると、他の誰かが空を描いてくれれば飛べるだろう。
そういうことか、深刻なこともさらりと受け流してしまうのは彼らしいところ。
Tr5:Call Me The Breeze
ジョン・メイヤーは「そよ風」と呼ばれているんだ。
選ぶ単語がまさに自然ですよね。
テンポを上げてシャッフルの小走りするような曲。
まさに心地よい響き。
軽快なエレクトリックギターのソロが調子が出てきたなあ、という
ところで誰かが声をかけてギターが止まり曲が終わってしまうのは、
ユーモアとしては面白いけれど、もう少しギターを聴かせてほしい(笑)。
Tr6:Who You Love (feat. Katy Perry)
「ベストヒットUSA」でもよく見るケイティ・ペリーがゲスト。
曲は穏やかなバラードで、ラブソングといえる。
あ、穏やかな、はもはや書かなくてもいいでしょうかね(笑)。
ケイティ・ペリーはそこで見て耳にしたことがある程度だから、
よく知らないけれど、このアルバムの中では声が少し強いかな。
悪くはないんだけど、ちょっと引っかかるかな、僕には。
ただこれは曲のよさがすべてを覆い尽くしているのでよしとするか。
話題性もあってシングルヒットしそうな曲、ふた昔前なら、ですが。
02

ここでひと休み。
このCD、裏トレイの写真では、ジョン・メイヤーが愛犬(かな)に
表では自分が被っていた帽子を被せていますが、
ロックスターでもこんなことするんだ、とっても親近感を覚えますね(笑)。
さて
Tr7:I Will Be Found (Lost At Sea)
僕が最初に気に入ったのはこの曲でした。
ピアノで荘重に始まる趣きがかなり違う曲であり、
バラードといえるスロウな曲、歌メロが分かりやすい。
そして何より歌詞が非常にいい。
「僕はきっと見つけられるだろう;海で遭難した」というこの歌、
歌詞を読むと、どうやらハイウェイを走っている、どういうこと!?
そこにいるのに、誰にも見られてない孤独感。
スターとはそういうものなのかもしれない。
ほんとうの自分を見せたくても見せられない。
タイトルの言葉に続く歌詞はこうです。
「僕は大きな木の下に葬られるだろう」
だけど、生きていようと死んでしまおうと、きっと見つかるだろうと
歌ってしまうのは、根底の部分で人間の心を信じているから。
そう歌いながらも悲観的ではないし、この世界が無常であり
虚しいものであるとも感じていない。
悟りとまではいわないけれど
どこか開き直ったすがすがしさがあるのもまた、そういうこと。
ジョン・メイヤーの音楽に人間味を感じるのは、そうした部分ですね。
こういう歌詞の曲が僕は大好き。
今年出会った新曲では、僕の心の中心に最も近づいた曲です。
Tr8:Wildfire (feat. Frank Ocean)
ゲストはフランク・オーシャン。
名前すら知らない人でしたが、調べるとアメリカのR&B歌手とのこと。
ゲストの名前まで自然にこだわっていたのかな(笑)。
こちらは傾向としてはジョン・メイヤーに似た感じの声。
1曲目と同じタイトル、リプライズという意識なのかな、でも似ていない。
と思って聴いていると、フランク・オーシャンが、教会音楽風の曲を
ほとんどひとりで歌って1分くらいで終わってしまう。
そのためにゲストを招いたのはある意味贅沢、でも、
そうでなければイメージ通りの音にならなかったのでしょうね。
Tr9:You're No One 'Til Someone Let's You Down
これはいちばんカントリーっぽいかな。
断っておきますが、あくまでもカントリー「っぽい」ロックということで、
間奏の入り方がいかにもカントリーっぽいロックといった趣き。
ギターの感じがビートルズの1965年前半つまりHELP!の頃っぽい。
でも、曲名が説明的で長いのは昔のカントリーっぽいかな。
もっと明るくてもいいのに、やはりここでもいつもの姿勢を崩さず、
かすかな不安を抱えながら歌う。
Tr10:Badge And Gun
アコースティックギターでしっとりと聴かせるカントリーバラード風の曲。
「バッヂと銃」というのは、保安官のことかな。
7か月もここで隠れていたので、そろそろ「バッヂと銃」をくれ、
もっと遠くに行きたいんだ、と、西部劇が頭に浮かぶ内容。
でも洗練されたジョン・メイヤーのセンスは現代的に響いてくる。
それは、大都会の孤独を表しているのでしょう。
この曲は歌い始めてすぐに声がふうっと高くなるのですが、
その歌い方も板についてきた感じがします。
これは歌メロがとってもいいしもう口ずさむようになったんだけど、
どうして最初はそこに気づかなかったのか・・・
鈍くなってますね、僕も(笑)。
Tr11:On The Way Home
最後3曲はカントリータッチの曲。
やっぱり、アメリカの人は家に帰りたいという歌が好きなんだな。
基本的に冷静なジョン・メイヤーはしかし、心が熱くなるわけではなく、
さらりと歌う、それでいて曲には気持ちがこもっている。
曲はこのスタイルの中では盛り上がろうとしているのも感じて、特に
ペダルスティールとハーモニカが気持ちを煽っている。
リンクは左が国内盤、ボーナストラックが入っていますが、
僕が買ったのは右の輸入盤、そのうち国内盤も買わなきゃ。
穏やかで自然を感じる響きは、まさに
「自然と音楽を愛する者」向きのアルバムといえるでしょう。
もちろんジョン・メイヤーが僕のことを知るはずもないけれど(笑)。
そしてこのアルバムは日本の秋にはまさにぴったり。
これからますます聴き入って好きになる1枚です。
ジョン・メイヤーはまだ3枚目だけど、ほんとうにいいなあ。
そういえば昨年のアルバムの後で来日公演がなかったけれど、
今度こそ、もう今年はないだろうから、来年、来日しないかな。
ところで最後に余談。
僕のBLOG、ジョン・メイヤーのアルバム記事がなぜか
アクセス数がよく伸びて、前2作はともに1000を超えました。
ジョン・メイヤーはまだ新しい人なので、昔の大御所ほどには
記事を書く人がまだまだ少ない、ということなのかな。
アクセス数を伸ばしたいという意味ではなく、でもそういうことから、
ジョン・メイヤーの記事は早くに上げたいと今回も思いました。
まあ、ひと月以上経ってしまいましたが、でも早いほうです(笑)。
今日の最後は、マーサがCDを紹介します。
03




 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト


























