2017年03月13日
BLUE AND LONESOME ローリング・ストーンズ
01

BLUE AND LONESOME
Rolling Stones
ブルー・アンド・ロンサム
ローリング・ストーンズ
(2016)
ローリング・ストーンズの新譜の話をします。
昨年12月にリリースされたBLUE AND LONESOME
あのストーンズが原点に立ち返ってブルーズのカヴァーをやる。
大きな期待を持って迎えられました。
まあ僕もその口のひとりではありましたが。
リリースされるともう絶賛の嵐。
このアルバムをいいと言わなければロックを聴いてはいけない。
とでもいいたいような勢いであったと、僕は感じていました。
「ローリング・ストーン」誌ではリリース後間もないというのに、
2016年ロックアルバム選上位に入っていて少々驚いたり。
まあ、RS誌はその名前からして当然でしょうけれど、でも
そうした雰囲気がネットで意見を書く人の間に漂っていた、
そんな感じを受けました。
そのことに対して批判するつもりも毛頭ありません。
ただ、僕はそう感じて、少しばかり恐かったのです。
しかし、次に書くことは多少批判めいているかもしれない、
という覚悟で続けます。
このアルバムをいいと思い、ブルーズが分からないと
ロックという音楽は分からないし聴いてはいけない。
そんな意識が見え隠れしてやいなかったかな、と、
これはあくまでも僕が感じたことですが。
僕はブルーズは好きです。
数年前からCDを買って聴くようになりました。
僕はブルーズを分かろうとして聴いていました。
ええ、カッコつけたかった部分もあったでしょう。
僕自身が、ブルーズを分からなければロックが分からない、
と思っていた節もありました。
でも、結局、僕にはブルーズは分からなかった。
もちろんこの人はブルーズだ、この音楽はブルーズっぽい
というのは頭では分かります。
でも、体、感覚では分からないし体現できない。
僕はバンドなど人前で演奏しない人間ではあり、
外国に行ったことがない日本人だからか、ブルーズの感覚が
頭ではなく体でなんて分かるはずがない。
ブルーズを歌うなんてできるわけがない。
じゃあ、ブルーズが「分かる」ってどういうことだ?
ここで「分かる」(わかる)という言葉を
「新明解国語辞典第7版」(三省堂)で引いてみると
わかる
未解決(未確認)の事柄について、推理・推論をめぐらしたり
適切な情報を拠りどころにしたり 実際に経験したりして、
確信の持てる(客観性のある)判断が下せる状態になる。
結構難しいですね(笑)。
僕が引っかかったのは「実際に経験したりして」の一文。
上記のように外国にも行ったことがないしバンドなど
人前で演奏したり歌ったりしたこともないので、
僕にはこの部分が欠けています。
この説明では書かれている全てが必須条件ではないと
受け取れますが、でもないよりはあった方がいいのでしょう。
だからやっぱり僕はブルーズは「分からない」。
昨年前半までの僕なら、そこである種の危機感を抱いたでしょう。
ブルーズが分からなきゃロックは分からないぜ。
だからこのアルバムは何が何でも分からなきゃいけないんだ。
僕自身ブルーズが分からないと認めたくなかったのもありました。
でも、今はもう音楽に対してある部分冷めたので、
それで焦ったりなんてことにはならなくなりました。
冷めたというか、冷静に聴けるようになったと
ここは前向きに解釈して先に進めます。
僕は結局ブルーズは分からなかったけれど、
ブルーズを聴くのは大好きになりました。
それまでの自分からすれば意外なほどに。
その結果が、ブルーズに「凝る」のではなく、
ブルーズを「ただ聴くのが楽しい」という境地に達しました。
境地というのも大袈裟か、今日の僕は大袈裟過ぎるかな(笑)。
あ、と思ったけど、60枚CDラックをブルーズ専用にして
それが埋まるほど買って聴いたので、凝ったといえばそうかな、
前言お詫びして訂正した方がいいかもしれない。
02

しばし休憩。
フィッシュアイレンズ=魚眼レンズを使うようになって、
今日が初めてのアルバム記事、ということで撮ってみました。
四角いはずのCDが線が曲がって写るのが面白い。
次もまたやってみよう。
閑話休題(長い閑話だった)。
ローリング・ストーンズのBLUE AND LONESOME
僕は、「普通にとてもいい」くらいに気に入りました。
もう少しいうと「予想していたよりはよかった」。
僕がそう感じたのは、単なるブルーズのコピーではなく、
もうこれはローリング・ストーンズでしかないと感じられたから。
全体のサウンド、チャーリー・ワッツのドラムスの感覚、
ギターの音色と入り方、そしてミック・ジャガーのヴォーカルまで、
僕には「ローリング・ストーンズにしか」聴こえませんでした。
特にミックのヴォーカルは最初に聴いた時(もう3か月前か)、
こりゃブルーズではなくどう聴いてもミックじゃないか
とスピーカーに向かって話しかけそうになったくらい。
ブルーズだと思って聴くとこれはある種滑稽な歌い方じゃない?
4曲目All Of Your Loveの最初"All"と叫ぶところなんか、もう。
6曲目"I was talking to the policeman"と歌うところの
声の軋みや刻み方もミックらしいし。
BLUE AND LONESOMEというアルバムタイトルが
そもそもストーンズらしいイディオムで、
僕は最初に聞いて笑ってしまいました。
(バカにするという意味では決してありません、念のため)。
ミック自身ももしかしてブルーズらしく歌わなくていい
と思えるようになったのではないか。
ミック自身の変化というより、世の中が受け入れるようになった、
ということなのかもしれないと思いました。
時々聴いています、1週間に2回くらいかな。
1月中盤からひと月「クラシック月間」には聴かなかったけれど、
その後やっぱりこれは好きだと思い直しそれくらい聴いてます。
僕にとっては根詰めて聴くものではないけれど、
時々聴くとかなりいい、という感じのアルバムです。
さてここで収録曲。
根詰めて聴いていないのでいつものように
各曲について具には書けません、悪しからず。
1曲目:Just Your Fool
2曲目:Commit A Crime
3曲目:Blue And Lonesome
4曲目:All Of Your Love
5曲目:I Gotta Go
6曲目:Everybody Knows About My Good Thing
7曲目:Ride'em On Down
8曲目:Hate To See You Go
9曲目:Hoo Doo Blues
10曲目:Little Rain
11曲目:Just Like I Treat You
12曲目:I Can't Quit You Baby
僕が知っていたのはたった1曲、12曲目。
レッド・ツェッペリンがアルバムで演奏しているからですが
(1枚目とCODA)、でもあれは最後が"Babe"だったから
これは同じ曲ではないのかな、と思ったり。
まあ僕のブルーズなんてそんなものです。
ただ、ですね、知らない古くていい曲を教えてくれるという点では
やっぱりローリング・ストーンズはロックであり続けている、
というのは嬉しいし心強いですね。
事実この中で新たに気に入った曲もあるし。
結局のところ、これはローリング・ストーンズだからいいのです。
僕はローリング・ストーンズが大好きなのだから、
という身も蓋もないことが今日の結論。
ただし、ブルーズが分からない人間だと自覚した今は、
ストーンズのどこが好きかも分からなくなったのですが・・・
ではアルバムから1曲。
☆
Hate To See You Go
Rolling Stones
(2016)
ところで、ストーンズのこのアルバムに対して感じたことに
デジャヴ感覚があることに気づきました。
ポール・マッカートニーのNEWが新譜で出た時。
やはりRS誌でその年のTop10以内に選ばれていました。
Top50のほとんどは若手であったのに、です。
(ジョン・フォガティもTop10に入っていたのは嬉しかったですが)。
若い聴き手に対してロックを作り上げてきた人だから、
これは聴いておきなさいという教示的な意味もあるのかな、と。
そしてやっぱり、そういう時代になったのかな。
音楽(に限らずだけど)の趣味が多様化し、
ネット上では、「思想」というと大袈裟かもだけど、
核となり拠り所となる考えが求められている。
僕みたいに、「分からないけどこれは好き」という思いは、
レコード盤に静電気で寄ってくる塵みたいなものであり、
戯言に過ぎないのかもしれないですね。
そしてこの記事は、僕のブルーズが分からないという恨み節、
でもありますかね。
まあそれでも、僕は基本、「わかる・わからない」よりは
「好きかどうか」で音楽の話を文章にしている人間だし、
ブルーズが分からない以上好きかどうかを書くしかできないので、
これからもそんな戯言記事を上げてゆこうとは思います。
繰り返し、音楽への愛情は薄れていませんからね。
最後は今朝の3ショットにて。
03


BLUE AND LONESOME
Rolling Stones
ブルー・アンド・ロンサム
ローリング・ストーンズ
(2016)
ローリング・ストーンズの新譜の話をします。
昨年12月にリリースされたBLUE AND LONESOME
あのストーンズが原点に立ち返ってブルーズのカヴァーをやる。
大きな期待を持って迎えられました。
まあ僕もその口のひとりではありましたが。
リリースされるともう絶賛の嵐。
このアルバムをいいと言わなければロックを聴いてはいけない。
とでもいいたいような勢いであったと、僕は感じていました。
「ローリング・ストーン」誌ではリリース後間もないというのに、
2016年ロックアルバム選上位に入っていて少々驚いたり。
まあ、RS誌はその名前からして当然でしょうけれど、でも
そうした雰囲気がネットで意見を書く人の間に漂っていた、
そんな感じを受けました。
そのことに対して批判するつもりも毛頭ありません。
ただ、僕はそう感じて、少しばかり恐かったのです。
しかし、次に書くことは多少批判めいているかもしれない、
という覚悟で続けます。
このアルバムをいいと思い、ブルーズが分からないと
ロックという音楽は分からないし聴いてはいけない。
そんな意識が見え隠れしてやいなかったかな、と、
これはあくまでも僕が感じたことですが。
僕はブルーズは好きです。
数年前からCDを買って聴くようになりました。
僕はブルーズを分かろうとして聴いていました。
ええ、カッコつけたかった部分もあったでしょう。
僕自身が、ブルーズを分からなければロックが分からない、
と思っていた節もありました。
でも、結局、僕にはブルーズは分からなかった。
もちろんこの人はブルーズだ、この音楽はブルーズっぽい
というのは頭では分かります。
でも、体、感覚では分からないし体現できない。
僕はバンドなど人前で演奏しない人間ではあり、
外国に行ったことがない日本人だからか、ブルーズの感覚が
頭ではなく体でなんて分かるはずがない。
ブルーズを歌うなんてできるわけがない。
じゃあ、ブルーズが「分かる」ってどういうことだ?
ここで「分かる」(わかる)という言葉を
「新明解国語辞典第7版」(三省堂)で引いてみると
わかる
未解決(未確認)の事柄について、推理・推論をめぐらしたり
適切な情報を拠りどころにしたり 実際に経験したりして、
確信の持てる(客観性のある)判断が下せる状態になる。
結構難しいですね(笑)。
僕が引っかかったのは「実際に経験したりして」の一文。
上記のように外国にも行ったことがないしバンドなど
人前で演奏したり歌ったりしたこともないので、
僕にはこの部分が欠けています。
この説明では書かれている全てが必須条件ではないと
受け取れますが、でもないよりはあった方がいいのでしょう。
だからやっぱり僕はブルーズは「分からない」。
昨年前半までの僕なら、そこである種の危機感を抱いたでしょう。
ブルーズが分からなきゃロックは分からないぜ。
だからこのアルバムは何が何でも分からなきゃいけないんだ。
僕自身ブルーズが分からないと認めたくなかったのもありました。
でも、今はもう音楽に対してある部分冷めたので、
それで焦ったりなんてことにはならなくなりました。
冷めたというか、冷静に聴けるようになったと
ここは前向きに解釈して先に進めます。
僕は結局ブルーズは分からなかったけれど、
ブルーズを聴くのは大好きになりました。
それまでの自分からすれば意外なほどに。
その結果が、ブルーズに「凝る」のではなく、
ブルーズを「ただ聴くのが楽しい」という境地に達しました。
境地というのも大袈裟か、今日の僕は大袈裟過ぎるかな(笑)。
あ、と思ったけど、60枚CDラックをブルーズ専用にして
それが埋まるほど買って聴いたので、凝ったといえばそうかな、
前言お詫びして訂正した方がいいかもしれない。
02

しばし休憩。
フィッシュアイレンズ=魚眼レンズを使うようになって、
今日が初めてのアルバム記事、ということで撮ってみました。
四角いはずのCDが線が曲がって写るのが面白い。
次もまたやってみよう。
閑話休題(長い閑話だった)。
ローリング・ストーンズのBLUE AND LONESOME
僕は、「普通にとてもいい」くらいに気に入りました。
もう少しいうと「予想していたよりはよかった」。
僕がそう感じたのは、単なるブルーズのコピーではなく、
もうこれはローリング・ストーンズでしかないと感じられたから。
全体のサウンド、チャーリー・ワッツのドラムスの感覚、
ギターの音色と入り方、そしてミック・ジャガーのヴォーカルまで、
僕には「ローリング・ストーンズにしか」聴こえませんでした。
特にミックのヴォーカルは最初に聴いた時(もう3か月前か)、
こりゃブルーズではなくどう聴いてもミックじゃないか
とスピーカーに向かって話しかけそうになったくらい。
ブルーズだと思って聴くとこれはある種滑稽な歌い方じゃない?
4曲目All Of Your Loveの最初"All"と叫ぶところなんか、もう。
6曲目"I was talking to the policeman"と歌うところの
声の軋みや刻み方もミックらしいし。
BLUE AND LONESOMEというアルバムタイトルが
そもそもストーンズらしいイディオムで、
僕は最初に聞いて笑ってしまいました。
(バカにするという意味では決してありません、念のため)。
ミック自身ももしかしてブルーズらしく歌わなくていい
と思えるようになったのではないか。
ミック自身の変化というより、世の中が受け入れるようになった、
ということなのかもしれないと思いました。
時々聴いています、1週間に2回くらいかな。
1月中盤からひと月「クラシック月間」には聴かなかったけれど、
その後やっぱりこれは好きだと思い直しそれくらい聴いてます。
僕にとっては根詰めて聴くものではないけれど、
時々聴くとかなりいい、という感じのアルバムです。
さてここで収録曲。
根詰めて聴いていないのでいつものように
各曲について具には書けません、悪しからず。
1曲目:Just Your Fool
2曲目:Commit A Crime
3曲目:Blue And Lonesome
4曲目:All Of Your Love
5曲目:I Gotta Go
6曲目:Everybody Knows About My Good Thing
7曲目:Ride'em On Down
8曲目:Hate To See You Go
9曲目:Hoo Doo Blues
10曲目:Little Rain
11曲目:Just Like I Treat You
12曲目:I Can't Quit You Baby
僕が知っていたのはたった1曲、12曲目。
レッド・ツェッペリンがアルバムで演奏しているからですが
(1枚目とCODA)、でもあれは最後が"Babe"だったから
これは同じ曲ではないのかな、と思ったり。
まあ僕のブルーズなんてそんなものです。
ただ、ですね、知らない古くていい曲を教えてくれるという点では
やっぱりローリング・ストーンズはロックであり続けている、
というのは嬉しいし心強いですね。
事実この中で新たに気に入った曲もあるし。
結局のところ、これはローリング・ストーンズだからいいのです。
僕はローリング・ストーンズが大好きなのだから、
という身も蓋もないことが今日の結論。
ただし、ブルーズが分からない人間だと自覚した今は、
ストーンズのどこが好きかも分からなくなったのですが・・・
ではアルバムから1曲。
☆
Hate To See You Go
Rolling Stones
(2016)
ところで、ストーンズのこのアルバムに対して感じたことに
デジャヴ感覚があることに気づきました。
ポール・マッカートニーのNEWが新譜で出た時。
やはりRS誌でその年のTop10以内に選ばれていました。
Top50のほとんどは若手であったのに、です。
(ジョン・フォガティもTop10に入っていたのは嬉しかったですが)。
若い聴き手に対してロックを作り上げてきた人だから、
これは聴いておきなさいという教示的な意味もあるのかな、と。
そしてやっぱり、そういう時代になったのかな。
音楽(に限らずだけど)の趣味が多様化し、
ネット上では、「思想」というと大袈裟かもだけど、
核となり拠り所となる考えが求められている。
僕みたいに、「分からないけどこれは好き」という思いは、
レコード盤に静電気で寄ってくる塵みたいなものであり、
戯言に過ぎないのかもしれないですね。
そしてこの記事は、僕のブルーズが分からないという恨み節、
でもありますかね。
まあそれでも、僕は基本、「わかる・わからない」よりは
「好きかどうか」で音楽の話を文章にしている人間だし、
ブルーズが分からない以上好きかどうかを書くしかできないので、
これからもそんな戯言記事を上げてゆこうとは思います。
繰り返し、音楽への愛情は薄れていませんからね。
最後は今朝の3ショットにて。
03

2016年11月29日
57TH & 9TH スティングの新譜
01

57TH & 9TH
Sting
ニューヨーク9番街57丁目
スティング
(2016)
スティングの新作が出ました。
プロモーション来日して今日明日とテレビを賑わせるようですね。
今回のアルバムは実に久しぶりにロックに帰ってきたと
リリース前から話題になっており、僕も期待していました。
そうです、スティングがロックに帰ってきたのです!
僕も最初は、ああそうなんだぁに毛が生えたくらいにしか
思っていなかったのですが、実際の音を聴くとやっぱり
大好きなミュージシャンだから冷静ではいられなくなりますよね。
最近は、日々の生活の中で時々「スティングがロックに帰ってきた」
と思い出し笑いをしそうになるくらい。
あ、変な人ですかね(笑)。
ロックに帰ってきた。
2003年のSACRED LOVEより後はクラシックだったり、
ミュージカルだったりクリスマスっぽいのと、ロックから離れていた。
それらの作品も好きなものはあるけれど、正直、
もうロックはやらないかもしれないと思うと寂しかった。
前作THE LAST SHIPはなんとAC/DCのブライアン・ジョンソンが
参加するなど今度こそロックと期待したのですが、
オリジナルの新曲を使ってはいたものの企画盤でがっかり。
「ああそうなんだに毛が生えたくらい」と書いたのは、
前作で「騙されて」期待度が低かったからなのでした。
もちろんスティングにそのつもりは毛頭ないでしょうけれど。
でも、今度はほんとうにロックに帰ってきた。
しかし、ソロ初期の頃のナイフで切り裂くような
鋭いメッセージを突きつけるというのではまるでない。
聴くだけでこっちが緊張するような音楽ではない。
かといってAOR的にソフトになったというのとも違う。
(断っておきますが決してAORを批判するものではありません)。
そう、ロックなんです。
ロックという音楽は本来は適度にハードな音で聴かせるもの、
と僕は思っていて、ビートルズもストーンズもそうですが、
スティングの新作はまさにロックのど真ん中といった趣の音です。
だから聴きやすい!
洋楽ロックを好んで聴き育った人には素直に受け入れられる。
もちろん細かに聴くとクラシックだったりエスニックだったりの
影響はうかがえますが、それも込みでのロックミュージック。
今の時代、それだけでもう十分嬉しいですね。
スティングらしい鋭さがなくなっているというのも、
昔は久米宏さんが「言いたいことだけ言って帰っちゃいました」
と呆れていたくらいメッセージを伝えたい人でしたが、
まあ人間だから齢を重ねて丸くなったと素直に捉えられますね。
それが予想外だったかといえばまるで正反対、
多分そうだろうなあと思っていたので、その点でも期待通りです。
昔のスティングの鋭さが苦手だったという人もいるかもしれない、
それくらい印象が強かったですが、そういう人が聴くと驚くかも。
タイトルの57TH & 9THとは邦題にあるように
ニューヨークの街区の名前のようですが、
原題にはNew Yorkの文字は入っていません。
でも、スティングにはニューヨークを歌った有名な曲もあるし、
ニューヨークに住んでいることも知っていたし、ジャケット写真の
絵的イメージからしてもニューヨークであると最初から思いました。
しかしそこで使われている数字の意味を考えてしまうのが悪い癖(笑)。
「スティングは57歳でこれは9作目のアルバムなの?」
スティングは1951年生まれの65歳、違いますね。
しかし9作目の方は、前述2013年のTHE LAST SHIPを含めると
これが9作目だからその通りですね、偶然なのだろうか。
スティングのテレビ、今日は「スッキリ」を録画して観ました。
どこよりも早く出るということで、時間も長かった。
まあ、前半のポリスのデビューからの話は「はい知ってます」
とテレビに向かって言いそうになりましたが(笑)、いかんいかん、
スティングをご存知ない方が興味を持っていただけるのであれば
と思いながら観ていましたよ。
「見つめていたい」はこの人の曲だったんだって思った人、
全国で3桁はいらっしゃるのではないかと。
番組でスティングは2曲歌っていました。
最初は、ファンだという司会の加藤浩次が無理矢理リクエストする
というかたちで、ギターの人と2人でShape Of My Heartを。
観ていた弟が、「日本ではスティング(ソロ)といえばこの曲なのか」
と呟いていた、映画『レオン』のテーマ曲として使われた曲。
続いてバンドメンバーを引き連れて新曲のスタジオライヴ。
I Can't Stop Thinking About You。
演奏は「指パク」=アテレコかもしれないけれど、
スティングは本当に歌っていたように思えました。
声がレコードより弱く感じられたというのがその理由ですが。
自信はないですが、まあ、こういうことは
曖昧の方がかえっていいいかもしれないですね(笑)。
話は逸れました、アルバムタイトルの話をしたかったのでして。
「スッキリ」でスティングはアルバムタイトルについて質問され、
自宅のある場所かと聞かれると"No"、では仕事場、それも"No"。
正解は、自宅から仕事場に行く間に通る交差点。
その信号はいつも止まって待つ場所であり、その間にいろいろ、
人生のことについても考えるのだそうです。
車で通勤すると必ず止まる交差点ってありますよね。
スティングの言葉で僕はこのアルバムがますます
身近に感じられました。
さて、聴いてゆきましょうか。
02

1曲目:I Can't Stop Thinking About You
アップテンポでいかにも1曲目、ロックらしい適度にハードな曲で、
最初に聴いて予想していたよりハードだなあと思いました。
でもこれこれ、やったぁ! 思わず叫びそうになりました。
ギターのアルペジオがきらびやかでいかにも街といった感じ。
曲がなんというか素直で、流れに捻りがない。
スティングらしくないといえばそうかもしれない「普通」の曲。
でも今はその普通のロックがいいんだと繰り返し言いたい。
歌メロもよくて僕ももう口ずさむようになりました。
ああでもイントロの最後歌に入る直前のコードが
ズシーンと重たく響いてくるのはちょっと捻っているか。
"Cold, cold, cold"とサビの前に3回繰り返すのが印象的で、
まさに雪が降り始める今の時期にはぴったりの曲ですね。
ただ最初に聴いて少し戸惑ったことが。
演奏の音圧が強くて、スティングの声がべったりとそこに
張り付いていてすべての音が一塊でやってきて
広がりが感じられない録音だったこと。
でも慣れると今のスティングはそれでいいと思いました。
でもやっぱり嬉しかった、嬉しいですね。
余談、この曲を聴いたおかげで今の僕はジョージ・ハリスンの
「帝国」に入っているCan't Stop Thinking About Youが
よく頭の中に流れてくるようになりました(ほんとに蛇足だけど)。
ではこの曲をどうぞ。
☆
I Can't Stop Thinking About You
Sting
(2016)
2曲目:50,000
ミディアムスロウで暗くはないけれど何か影がある響き。
強いギターの音の後ヴァースが始まって急に静かになり、
ぶつぶつ言うようにごちゃついた歌メロを歌う。
ここはいかにも理屈っぽいスティングという感じ。
でもやはりねちねちしたものではなくむしろかわいげがある。
サビは一転して演奏も賑やかで明るくなる。
ここはなんとなくKing Of Painを思い出しました。
曲の前半と後半で印象が違う面白い曲。
今回のアルバムで唯一フェイドアウトで終わる曲でもあります。
3曲目:Down, Down, Down
この曲も前半Aメロはささやくように歌う。
Bメロはいかにもポリス=スティングといった言葉遣い、
歌メロの進み方、でもやはり今は落ち着いている。
これはいい。
曲の終わらせ方、それまでまったく出てこなかったパッセージを
いきなり入れ込んで終わらせる、これがはっとさせられる。
4曲目:One Fine Day
これがいい!!
歌の始まりの旋律がとっても分かりやすくてすぐに口ずさめる。
タイトルを歌う部分ももうそこだけで素晴らしい。
分かりやすいようでやっぱり理屈っぽいスティング。
そんな人がポップなセンスを持ってしまったのだから、
他にはない独特のポップソングができますよね。
ううん、もう嬉しくてたまらない。
1曲目とこっち、昔の感覚ならどっちをシングルに切ってもいい。
ベスト盤にいきなり入っていても違和感ないかも、
それくらい気に入りました。
5曲目:Pretty Young Soldier
12/8のゆったりとしたリズム、でも歌っていることは深刻。
スティングはリズムが遅すぎるとばかりに早口で歌い継ぐ。
でも、突きつけるのではなく包み込む、そんな響き。
結婚を約束したカップル、しかし男性は突然戦争に行くと話す。
2人が会っているのはやはり川のそば。
欧米の人にはそういうイメージがあるのでしょうねきっと。
6曲目:Petrol Head
これはポリスをハードロックにしたような曲。
もっといえばパンクの原初的なパワーを再現した曲。
スティングも怒ったような歌い方で迫力ある。
歪んだ音のギターソロにも怒りが透けて見える。
これを聴いて「スティングさすが」と思いましたね。
ロックを築き、ロックに生きてきた人として。
それにしてもカッコいい!
7曲目:Heading South On The Great North Road
アコースティックギターだけをバックに歌うこの曲は
クラシックっぽい響きでスティングがやって来たことが
うまく取り込まれていますね。
バロックっぽい、かな。
タイトルを見るとカントリーっぽい曲を想像しますが、
そこはちょっとばかり交わしている部分かもしれない。
8曲目:If You Can't Love Me This Way
ギターのアルペジオとドラムスとスティングの歌い方が
バラバラのように聴こえる、あららどうしちゃったんだろうって。
でも、だから逆にしっかりとタイトルを歌う部分が印象に残る。
英語ネイティヴではない僕はカラオケでは歌えないわ(笑)。
それにしても、「こんな風に僕を愛せないなら去ってくれ」
とはなんとも傲慢、スティングだから言えるのかもしれない。
9曲目:Inshallah
ギターの寂し気な音につられて暗く歌い始めるスティング。
哀愁を帯びた美しい響きはどこかアラブ風、それもそのはず、
"Inshallah"とはアラビア語で「なるようになる、そのうちに」の意味。
"let it be"ですね。
歌詞の中に"It shall come to past"というくだりがあり、
この"shall"は予言や祈りの意味ですが、その音が"Inshallah"という
言葉にも含まれているのは決して偶然ではないと思います。
つまりこれは祈りの曲なのでしょう。
こういう曲が書ける人、それがスティングなのです。
この曲を聴いて、スティングがロックに帰ってきた、
その意味がよく分かった気がしました。
祈るように歌うこの曲は胸に迫ってきます。
この曲の最新ライヴ映像がYou-Tubeにありました。
☆
Inshallah
Sting
(2016)
10曲目:The Empty Chair
アルバム本編最後でスティングはアコースティックギターのみを
バックに穏やかに歌う。
スティングにこういう曲はありそうでなかったかも。
大きな木陰でギターを弾きながら周りを描写し歌う、そんな響き。
どこかもの悲しい、そうですよね、誰もいない椅子だから。
ただ、ボーナストラックが入っていない通常盤ではこの曲が
最後となるわけですが、最後に置くには心もとないというか、
あっさりと終わりすぎるよな気もします。
前の曲の印象度が高くて後を引くにしても。
11曲目:I Can't Stop Thinking About You (L.A.Version)
というわけでここからボーナストラック、1曲目の別ヴァージョン。
オリジナル1曲目ではパンチの強い普通のロックの音ですが、
こちらはアコースティックギターの音色がほのかに響くイントロ、
音のメリハリが弱くてスティングの声もおとなしいというミックス。
というより、スティングの歌は違うテイクのようにも感じられるので、
ミックス以上にテイクが違うと思われます。
それがL.A.風なのかどうかは僕には分からないのですが、
同じ歌でもかなり印象が違って少々驚きます。
まあ、L.Aで録ったということで、音自体にL.A.であることの
意味はないのでしょうけれど。
僕は普通の「ニューヨーク」の方が好きかな。
12曲目:Inshallah(Berlin Session Version)
こちらは全体の音圧が抑えられた上で演奏が引っ込み
ヴォーカルが前に出た、そんなミックス。
ただ、この曲については「東西融和の象徴の地」である
「ベルリン」であることに何か意味があるよな気がしてならない。
今世界で対立しているのは東西ではないけれど・・・
13曲目:Next To You with The Last Bandoleros
(Live at Rockwood Music Hall)
最後はパワーパンク(?!)のこの曲のライヴ。
これは絶対にライヴで盛り上がるわ。
ボーナストラックについて、今はもう慣れた人が多いのかな。
それ以前にディスク単位で聴かない人が多いのか・・・
それはともかく、このアルバムこのCDに関しては、
ボーナストラックがあるからいいと僕は思います。
物静かな10曲目で終わるとあまりにもあっけないから。
そしてアルバムの目玉である3曲を別テイクでもう一度聴ける
というのはほんとうにボーナス、得したと感じますね。
ただできればOne Fine Dayの別テイクも欲しかったなあ(笑)。
上がDVD付きデラックスエディション、下が通常盤。
スティングは来年6月に来日公演を行うことが
早くもアナウンスされました。
もちろん場所や会場は未定、決まり次第の発表とのことですが、
札幌には来ないかなあ、来ないだろうなあ・・・
6月に東京に行くのは無理そうだし・・・
今回は積極的ですね。
それだけ、ロックに帰ってきたスティングを喜ぶ人が多いのかと。
今朝の「スッキリ」でもそのフレーズを使っていましたからね。
スティングお帰り!!
今は毎日聴いていますよ。
03


57TH & 9TH
Sting
ニューヨーク9番街57丁目
スティング
(2016)
スティングの新作が出ました。
プロモーション来日して今日明日とテレビを賑わせるようですね。
今回のアルバムは実に久しぶりにロックに帰ってきたと
リリース前から話題になっており、僕も期待していました。
そうです、スティングがロックに帰ってきたのです!
僕も最初は、ああそうなんだぁに毛が生えたくらいにしか
思っていなかったのですが、実際の音を聴くとやっぱり
大好きなミュージシャンだから冷静ではいられなくなりますよね。
最近は、日々の生活の中で時々「スティングがロックに帰ってきた」
と思い出し笑いをしそうになるくらい。
あ、変な人ですかね(笑)。
ロックに帰ってきた。
2003年のSACRED LOVEより後はクラシックだったり、
ミュージカルだったりクリスマスっぽいのと、ロックから離れていた。
それらの作品も好きなものはあるけれど、正直、
もうロックはやらないかもしれないと思うと寂しかった。
前作THE LAST SHIPはなんとAC/DCのブライアン・ジョンソンが
参加するなど今度こそロックと期待したのですが、
オリジナルの新曲を使ってはいたものの企画盤でがっかり。
「ああそうなんだに毛が生えたくらい」と書いたのは、
前作で「騙されて」期待度が低かったからなのでした。
もちろんスティングにそのつもりは毛頭ないでしょうけれど。
でも、今度はほんとうにロックに帰ってきた。
しかし、ソロ初期の頃のナイフで切り裂くような
鋭いメッセージを突きつけるというのではまるでない。
聴くだけでこっちが緊張するような音楽ではない。
かといってAOR的にソフトになったというのとも違う。
(断っておきますが決してAORを批判するものではありません)。
そう、ロックなんです。
ロックという音楽は本来は適度にハードな音で聴かせるもの、
と僕は思っていて、ビートルズもストーンズもそうですが、
スティングの新作はまさにロックのど真ん中といった趣の音です。
だから聴きやすい!
洋楽ロックを好んで聴き育った人には素直に受け入れられる。
もちろん細かに聴くとクラシックだったりエスニックだったりの
影響はうかがえますが、それも込みでのロックミュージック。
今の時代、それだけでもう十分嬉しいですね。
スティングらしい鋭さがなくなっているというのも、
昔は久米宏さんが「言いたいことだけ言って帰っちゃいました」
と呆れていたくらいメッセージを伝えたい人でしたが、
まあ人間だから齢を重ねて丸くなったと素直に捉えられますね。
それが予想外だったかといえばまるで正反対、
多分そうだろうなあと思っていたので、その点でも期待通りです。
昔のスティングの鋭さが苦手だったという人もいるかもしれない、
それくらい印象が強かったですが、そういう人が聴くと驚くかも。
タイトルの57TH & 9THとは邦題にあるように
ニューヨークの街区の名前のようですが、
原題にはNew Yorkの文字は入っていません。
でも、スティングにはニューヨークを歌った有名な曲もあるし、
ニューヨークに住んでいることも知っていたし、ジャケット写真の
絵的イメージからしてもニューヨークであると最初から思いました。
しかしそこで使われている数字の意味を考えてしまうのが悪い癖(笑)。
「スティングは57歳でこれは9作目のアルバムなの?」
スティングは1951年生まれの65歳、違いますね。
しかし9作目の方は、前述2013年のTHE LAST SHIPを含めると
これが9作目だからその通りですね、偶然なのだろうか。
スティングのテレビ、今日は「スッキリ」を録画して観ました。
どこよりも早く出るということで、時間も長かった。
まあ、前半のポリスのデビューからの話は「はい知ってます」
とテレビに向かって言いそうになりましたが(笑)、いかんいかん、
スティングをご存知ない方が興味を持っていただけるのであれば
と思いながら観ていましたよ。
「見つめていたい」はこの人の曲だったんだって思った人、
全国で3桁はいらっしゃるのではないかと。
番組でスティングは2曲歌っていました。
最初は、ファンだという司会の加藤浩次が無理矢理リクエストする
というかたちで、ギターの人と2人でShape Of My Heartを。
観ていた弟が、「日本ではスティング(ソロ)といえばこの曲なのか」
と呟いていた、映画『レオン』のテーマ曲として使われた曲。
続いてバンドメンバーを引き連れて新曲のスタジオライヴ。
I Can't Stop Thinking About You。
演奏は「指パク」=アテレコかもしれないけれど、
スティングは本当に歌っていたように思えました。
声がレコードより弱く感じられたというのがその理由ですが。
自信はないですが、まあ、こういうことは
曖昧の方がかえっていいいかもしれないですね(笑)。
話は逸れました、アルバムタイトルの話をしたかったのでして。
「スッキリ」でスティングはアルバムタイトルについて質問され、
自宅のある場所かと聞かれると"No"、では仕事場、それも"No"。
正解は、自宅から仕事場に行く間に通る交差点。
その信号はいつも止まって待つ場所であり、その間にいろいろ、
人生のことについても考えるのだそうです。
車で通勤すると必ず止まる交差点ってありますよね。
スティングの言葉で僕はこのアルバムがますます
身近に感じられました。
さて、聴いてゆきましょうか。
02

1曲目:I Can't Stop Thinking About You
アップテンポでいかにも1曲目、ロックらしい適度にハードな曲で、
最初に聴いて予想していたよりハードだなあと思いました。
でもこれこれ、やったぁ! 思わず叫びそうになりました。
ギターのアルペジオがきらびやかでいかにも街といった感じ。
曲がなんというか素直で、流れに捻りがない。
スティングらしくないといえばそうかもしれない「普通」の曲。
でも今はその普通のロックがいいんだと繰り返し言いたい。
歌メロもよくて僕ももう口ずさむようになりました。
ああでもイントロの最後歌に入る直前のコードが
ズシーンと重たく響いてくるのはちょっと捻っているか。
"Cold, cold, cold"とサビの前に3回繰り返すのが印象的で、
まさに雪が降り始める今の時期にはぴったりの曲ですね。
ただ最初に聴いて少し戸惑ったことが。
演奏の音圧が強くて、スティングの声がべったりとそこに
張り付いていてすべての音が一塊でやってきて
広がりが感じられない録音だったこと。
でも慣れると今のスティングはそれでいいと思いました。
でもやっぱり嬉しかった、嬉しいですね。
余談、この曲を聴いたおかげで今の僕はジョージ・ハリスンの
「帝国」に入っているCan't Stop Thinking About Youが
よく頭の中に流れてくるようになりました(ほんとに蛇足だけど)。
ではこの曲をどうぞ。
☆
I Can't Stop Thinking About You
Sting
(2016)
2曲目:50,000
ミディアムスロウで暗くはないけれど何か影がある響き。
強いギターの音の後ヴァースが始まって急に静かになり、
ぶつぶつ言うようにごちゃついた歌メロを歌う。
ここはいかにも理屈っぽいスティングという感じ。
でもやはりねちねちしたものではなくむしろかわいげがある。
サビは一転して演奏も賑やかで明るくなる。
ここはなんとなくKing Of Painを思い出しました。
曲の前半と後半で印象が違う面白い曲。
今回のアルバムで唯一フェイドアウトで終わる曲でもあります。
3曲目:Down, Down, Down
この曲も前半Aメロはささやくように歌う。
Bメロはいかにもポリス=スティングといった言葉遣い、
歌メロの進み方、でもやはり今は落ち着いている。
これはいい。
曲の終わらせ方、それまでまったく出てこなかったパッセージを
いきなり入れ込んで終わらせる、これがはっとさせられる。
4曲目:One Fine Day
これがいい!!
歌の始まりの旋律がとっても分かりやすくてすぐに口ずさめる。
タイトルを歌う部分ももうそこだけで素晴らしい。
分かりやすいようでやっぱり理屈っぽいスティング。
そんな人がポップなセンスを持ってしまったのだから、
他にはない独特のポップソングができますよね。
ううん、もう嬉しくてたまらない。
1曲目とこっち、昔の感覚ならどっちをシングルに切ってもいい。
ベスト盤にいきなり入っていても違和感ないかも、
それくらい気に入りました。
5曲目:Pretty Young Soldier
12/8のゆったりとしたリズム、でも歌っていることは深刻。
スティングはリズムが遅すぎるとばかりに早口で歌い継ぐ。
でも、突きつけるのではなく包み込む、そんな響き。
結婚を約束したカップル、しかし男性は突然戦争に行くと話す。
2人が会っているのはやはり川のそば。
欧米の人にはそういうイメージがあるのでしょうねきっと。
6曲目:Petrol Head
これはポリスをハードロックにしたような曲。
もっといえばパンクの原初的なパワーを再現した曲。
スティングも怒ったような歌い方で迫力ある。
歪んだ音のギターソロにも怒りが透けて見える。
これを聴いて「スティングさすが」と思いましたね。
ロックを築き、ロックに生きてきた人として。
それにしてもカッコいい!
7曲目:Heading South On The Great North Road
アコースティックギターだけをバックに歌うこの曲は
クラシックっぽい響きでスティングがやって来たことが
うまく取り込まれていますね。
バロックっぽい、かな。
タイトルを見るとカントリーっぽい曲を想像しますが、
そこはちょっとばかり交わしている部分かもしれない。
8曲目:If You Can't Love Me This Way
ギターのアルペジオとドラムスとスティングの歌い方が
バラバラのように聴こえる、あららどうしちゃったんだろうって。
でも、だから逆にしっかりとタイトルを歌う部分が印象に残る。
英語ネイティヴではない僕はカラオケでは歌えないわ(笑)。
それにしても、「こんな風に僕を愛せないなら去ってくれ」
とはなんとも傲慢、スティングだから言えるのかもしれない。
9曲目:Inshallah
ギターの寂し気な音につられて暗く歌い始めるスティング。
哀愁を帯びた美しい響きはどこかアラブ風、それもそのはず、
"Inshallah"とはアラビア語で「なるようになる、そのうちに」の意味。
"let it be"ですね。
歌詞の中に"It shall come to past"というくだりがあり、
この"shall"は予言や祈りの意味ですが、その音が"Inshallah"という
言葉にも含まれているのは決して偶然ではないと思います。
つまりこれは祈りの曲なのでしょう。
こういう曲が書ける人、それがスティングなのです。
この曲を聴いて、スティングがロックに帰ってきた、
その意味がよく分かった気がしました。
祈るように歌うこの曲は胸に迫ってきます。
この曲の最新ライヴ映像がYou-Tubeにありました。
☆
Inshallah
Sting
(2016)
10曲目:The Empty Chair
アルバム本編最後でスティングはアコースティックギターのみを
バックに穏やかに歌う。
スティングにこういう曲はありそうでなかったかも。
大きな木陰でギターを弾きながら周りを描写し歌う、そんな響き。
どこかもの悲しい、そうですよね、誰もいない椅子だから。
ただ、ボーナストラックが入っていない通常盤ではこの曲が
最後となるわけですが、最後に置くには心もとないというか、
あっさりと終わりすぎるよな気もします。
前の曲の印象度が高くて後を引くにしても。
11曲目:I Can't Stop Thinking About You (L.A.Version)
というわけでここからボーナストラック、1曲目の別ヴァージョン。
オリジナル1曲目ではパンチの強い普通のロックの音ですが、
こちらはアコースティックギターの音色がほのかに響くイントロ、
音のメリハリが弱くてスティングの声もおとなしいというミックス。
というより、スティングの歌は違うテイクのようにも感じられるので、
ミックス以上にテイクが違うと思われます。
それがL.A.風なのかどうかは僕には分からないのですが、
同じ歌でもかなり印象が違って少々驚きます。
まあ、L.Aで録ったということで、音自体にL.A.であることの
意味はないのでしょうけれど。
僕は普通の「ニューヨーク」の方が好きかな。
12曲目:Inshallah(Berlin Session Version)
こちらは全体の音圧が抑えられた上で演奏が引っ込み
ヴォーカルが前に出た、そんなミックス。
ただ、この曲については「東西融和の象徴の地」である
「ベルリン」であることに何か意味があるよな気がしてならない。
今世界で対立しているのは東西ではないけれど・・・
13曲目:Next To You with The Last Bandoleros
(Live at Rockwood Music Hall)
最後はパワーパンク(?!)のこの曲のライヴ。
これは絶対にライヴで盛り上がるわ。
ボーナストラックについて、今はもう慣れた人が多いのかな。
それ以前にディスク単位で聴かない人が多いのか・・・
それはともかく、このアルバムこのCDに関しては、
ボーナストラックがあるからいいと僕は思います。
物静かな10曲目で終わるとあまりにもあっけないから。
そしてアルバムの目玉である3曲を別テイクでもう一度聴ける
というのはほんとうにボーナス、得したと感じますね。
ただできればOne Fine Dayの別テイクも欲しかったなあ(笑)。
上がDVD付きデラックスエディション、下が通常盤。
スティングは来年6月に来日公演を行うことが
早くもアナウンスされました。
もちろん場所や会場は未定、決まり次第の発表とのことですが、
札幌には来ないかなあ、来ないだろうなあ・・・
6月に東京に行くのは無理そうだし・・・
今回は積極的ですね。
それだけ、ロックに帰ってきたスティングを喜ぶ人が多いのかと。
今朝の「スッキリ」でもそのフレーズを使っていましたからね。
スティングお帰り!!
今は毎日聴いていますよ。
03

2015年06月24日
STICKY FINGERS ローリング・ストーンズ
01

STICKY FINGERS
Rolling Stones
スティッキー・フィンガーズ
ローリング・ストーンズ (1971)
ローリング・ストーンズがレコード会社を移籍し、
1971年に発表した名盤のリマスター・リイシュー盤が出ました。
今日はこのアルバムの話です。
結論から先に言います。
僕は、ストーンズでこのアルバムがいちばん好きです!
はい、今日はこれで終わり。
なんて(笑)。
ストーンズは「ビートルズの半年遅れのコピー」と揶揄されながらも
1967年くらいまでは順調にヒット曲を重ね、ロック史に残る名曲
(I Can't Get No) Satisfactionを生み出すなど大成功を収めました。
しかし、コンサートでの事件、メンバーの問題、そして
ブライアン・ジョーンズの死などで、一時勢いを落とす。
しかし、ミック・ジャガーとキース・リチャードの"The grimmer twins"は
起死回生の傑作BEGGAR'S BANQUET(記事はこちら)を作り、
再び名曲名盤を数々と生み出すようになった。
このアルバムまでのストーンズをごく短くまとめると、こんなところ。
ストーンズは当然のことながら元々アメリカのブルーズやR&B、
ソウルといった黒人音楽への志向が強かった。
それはビートルズも同じ、当時のUK勢はみなそう。
しかしストーンズは、実際にツアーなどでアメリカに行くようになり、
「アメリカの深部」、「ディープなアメリカ」を知りたくなる。
ビートルズのSGT. PEPPER'Sを真似した1967年の
THEIR SATANIC MAJESTY'S REQUESTの「失敗」を受け、
いよいよその思いを形に表してゆくことになった。
余談、僕はTHEIR...REQUESTも大好きなんですが、それはまた。
BEGGAR'S...、LET IT BLEEDとその色を強めてきたストーンズ、
次のアルバムの制作にあたり、マスル・ショールズを訪れて録音した。
以前記事にした映画『黄金のメロディ』でその話を見ました。
マスル・ショールズはアラバマ州の小さな町ですが、
敏腕プロデューサーにして無類の音楽好き人間リック・ホールが
ソウルのレコードを吹き込み、次々と全国でヒットさせたことから、
マスル・ショールズはいつしか「ソウルの聖地」と呼ばれるようになった。
映画によれば、ストーンズのメンバは「突然」やって来て録音を始めた。
こう書くと思いつきでいかにも彼ららしい、と思うかもですが、
そこで録音されたこのアルバムを聴くと、決してそうではなく、
上述のように、積年の思いをついに実現する時が来た、
その時間が持てた、ととるべきだと思い直しました。
まあ、映画を観て「突然来る」のはカッコいい、とは思いましたが(笑)。
では、このアルバムがストーンズの「アメリカ深部への旅」の
完成形かというと、さにあらず。
まだこの先が続き、LPでは2枚組のEXILE ON MAIN ST.をもって
ひとまず完結するわけですね。
ストーンズは近年、70年代のアルバムのリイシュー盤を出していて、
EXILE...は既にリイシュー盤が出たのですが、実は僕、
そのアルバムはまだソラで全曲分からないので記事にしていません。
それを機にある程度聴き込んだので、近いうちに今回の続編的に
記事にまとめてみたいと、今、思いました。
ちなみに、リイシューはSOME GIRLSも既に出ていますが、
こちらはリイシュー前に記事(こちら)にしていました。
また、前のアルバムに数曲参加し、No.1ヒットとなった
Honky Tonk Womenから正式メンバーとなった
ミック・テイラーが初めて全曲参加したアルバムでもあります。
僕とこのアルバムの話も少し。
僕はこれ、1990年代に当時SONYから出ていた国内盤CDで
初めて聴きました。
ロックの名盤本などでこれは傑作だと情報は得ていましたが、
最初に聴いて、いいけれどすごくいいかと言われると・・・でした。
大好きなBrown Sugarが入っている時点で僕の中の評価が
自然と高まりはしましたが、逆にいえばその曲がなければこれを
好きと言えるか、自信はいまいちありませんでした。
ただ、曲がいい意味で「心に引っかかるアルバム」だと思いました。
後になって突然フレーズを思い出す、そんな曲が多かった。
その後、VIRGINからリマスター盤が出たので買い直し、
さらにUNIVERSALからまた出直したのも買い直し、
年に1、2回は聴き続けてきましたが、さすがにそれだけ聴くと
曲にもなじみがでてきて、いいアルバムと思えるようになりました。
やっぱり曲が分かる、好き、というのは大きいですね。
そして、今月、このリイシュー盤が届いた時に聴いていて
「やっぱ俺はストーンズでこのアルバムがいちばん好きだわ!」
と、まるで稲妻に打たれたかのように思いました。
実際、その時は最初PCで作業をしながらかけていたのですが、
3曲目くらいになってPCの手が止まり、その後はただ聴くだけ。
昔からよく聴いてきた、大好きなアルバムでも、
或る日突然、すごくよく聴こえる、ということ、ありませんか?
僕は多々あります。
ビートルズとて例外ではなく、それを何十回も繰り返してきました。
「洋楽危機」の記事(こちら)で、古い音源に頼り過ぎていることが
洋楽の現状につながっていると書きましたが、良い物は良いわけで、
リイシュー盤を買い直すと、前よりよく聴こえることはあるのです。
それは音楽の本質でもあるから、古い音源を出し直すのは、
知らない人への新たな発信でもあると同時に、元々好きで
よく聴いてきた人にも訴えている、というわけなのですね。
自分で「洋楽危機」の記事を書いておきながら、今回このアルバムで、
自分自身、あらためてそんなことを思いました。
話は逸れましたが、今回このアルバムに「打たれた」のは、僕は
近年ソウルやブルーズなどを熱心に聴くようになり、このアルバムの
下地にある彼らの音楽への思いが理解できるようになってきた、
ということなのでしょう。
マスル・ショールズで録音したという「魔法」もかかっていますが、
もっと直接的にサザンソウルの影響が色濃く感じられます。
そして、ドクター・ジョンやミーターズ、ネヴィル・ブラザースに
アーロン・ネヴィル、アラン・トゥーサン、古くはファッツ・ドミノといった
ニューオーリンズの音楽は、自分で思っている以上に
僕に大きな影響を与えているんだな、と再確認しました。
なんといっても、Brown Sugarの歌い出し4小節目でミックが
"New Orleans"と歌っていますからね。
なお、録音は他にロンドンとミック・ジャガーの自宅でも行われ、
例の"Mobile"が使われた、アルバム完成となりました。
02

1曲目 Brown Sugar
ここでもうひとつ宣言、というのは大袈裟か。
僕は、ストーンズの曲ではやっぱりこれが一番好き!
この曲は一応ギターで弾けるのですが、でも、楽譜は持っていない。
耳コピーしたのかというとそうではなく、イントロのギターリフと
コード進行は、楽器店で楽譜を「立ち読み」して覚えました。
二十歳くらいの頃、今より頭が柔らかかったんだなあ、と(笑)。
この曲、元々一番好きなグループであり続けてはいましたが、
ギターソロがないのがギター弾きとしてはちょっと弱いかな、と。
ただ、あったところで弾かないという例は数多あるのですが、
最初からないのとは話が違いますよね。
でも、もうそんなことは関係なくなりました。
で、何がいいって、そりゃもう、歌メロ、ギター、すべて。
特に、ソロはなくてもギターワーク、ギターの音色、最高にいい。
そしてこの曲を特徴づけているのは、リズムでしょう。
この跳ね具合いとネバつきそしてグルーヴ感は、スワンプ志向が強く、
またそれができるほど「バンド」として強くなっていたことも感じます。
ライヴ盤では真っ直ぐなロックンロールになっているものもあって、
正直、この曲の魅力が半減と感じたものです。
歌詞の内容は「男尊女卑」的なもので物議を醸したそうで、
マイナスポイントがあるとすればそこかな。
でも、ライムとしては歌メロとリズムに合っていて最高にいい!
そして今回のリイシュー盤に収録された未発表テイクでは、
なんとエリック・クラプトンが参加しています。
正式テイクに比べると当然ラフな作りですが、エリックともども
スワンプをモノにしてやろうという鋭さを感じます。
ところで、このBLOGではまだ触れていませんでしたが、
この曲をはじめストーンズでの名演が多く、昨年の東京ドームにも
来ていたサックス奏者ボビー・キーズが昨年12月に亡くなりました。
ドームで会ったばかりだったので、ショックでした。
この場を借りて、R.I.P.
2曲目 Sway
タイトルのごとく、バンド全体が滑りながらずれていく感覚がいい。
最後にストリングスが入って来るのが洒落ている。
ところで僕はこの曲を最初"Swamp"だと思って聴いていて、
「スワンプってこういう音楽なんだ」と思ったものでした。
僕が「スワンプ」という言葉と概念を知ったのは、トーキング・ヘッズの
ライヴSTOP MAKING SENSEで、そのものSwampという曲があり、
何かで調べて「粘つきのあるアメリカ南部の音楽」と知りました。
これは、曲名を覚える前にアルバムCDを聴き始めて、
"Swa"まで同じなので、勘違いしてしまったのでしょう。
でも、この勘違いは「間違い」ではなかった、ということですね(笑)。
3曲目 Wild Horses
ストーンズはこのアルバムからレコード会社を移籍したと書きましたが、
Brown Sugarとこの曲のみ、それまでのDECCAの音源と同じく
権利がABKCOレコードにあり、この2曲は1960年代の曲を集めた
名編集のベスト盤HOT ROCKSに収録されています。
HOT ROCKSは、僕が初めて買ったストーンズのCDであり、
僕のCD初期50枚に入るほど早くに買って聴いていました。
当時からこの2曲についての話は本か何かで知っていて、
ここから新しいストーンズになっていたんだ、と思いながら聴きました。
Brown Sugarはいかにもストーンズらしくてすぐ好きになりましたが、
この曲は「彼らもこんな曲をやるんだ」と少々戸惑いました。
カントリーっぽさを感じるスロウで抒情的な曲。
本来僕が好きになりそうなものを、素直に好きとはいえなかった。
しかも彼ら自身がこの曲を大好きそうと分かって、なぜだろうって。
でも、この曲は、年を経るごとに徐々に好きになってゆき、
数年前、ああ本当にいい曲だあ、としみじみ思いました。
サビもいいけど、ヴァースの歌メロもいい。
ストーンズの芸の奥深さがよく分かる1曲でしょうね。
4曲目 Can't You Hear Me Knockin’
長いサックスソロを含むジャムセッションを発展させた曲。
この前年にジョージ・ハリスンがスワンプ趣味をかき集めて
作り上げたALL THING MUST PASSが出た、と今ふと
この曲を聴きながら思いましたが、当時の英国ロックには、
「ブルーズロック」の後に「スワンプロック」の波が来ていたようですね。
ほとんどハードロック的な突き刺さるギターリフがいい。
5曲目 You Gotta Move
アコースティックギターによる本格的カントリーブルーズ。
元々は戦後期のゴスペルやブルーズから始まった曲で、
フレッド・マクダウェルが1965年に録音したものがストーンズの
下地になっているようですが、サム・クックも同じモチーフで
1963年に録音している、など、複雑な変遷の曲でもあります。
この曲は「心に引っかかった」曲のひとつで、なんだろう、
けだるい雰囲気が気になって仕方なかった。
こういう音楽はまだ当時あまり聴いていなくて印象的だったのでしょう。
ところで、僕は、CDの時代になってからCDで初めて聴くアルバムは、
可能な限りどこまでがLPのA面でどこからがB面かを調べて
頭の中に刻んで聴くようにしていて、これはLPのA面最後。
最初にLPで聴いたアルバムはそれが頭に刻み込まれていますが、
これはLPで聴いたことがないのに、A面B面の区別が明確なのです。
やっぱり、若い頃にそうして覚えて聴いたからでしょうね。
03 "dead"ではない花、庭で咲いた薔薇「ミュージック」

6曲目 Bitch
この曲は1990年の初来日公演で演奏したことで、
僕の中では特別なものとなりました。
当時はまだストーンズ聴き始めのようなもので、シングルで
大ヒット曲はだいたい分かるけれど、アルバムの中の曲までは
抑えきれていない状態で、この曲をやって驚いたのでした。
ヒット曲と新譜からの曲以外を演奏しそれを聴くというのは、
コンサートの醍醐味なのだ、と、この曲から学んだ気がします。
この曲は「愛すべきパクリ」のひとつですね。
イントロのリフがテンプテーションズのGet Readyとそっくり。
「てってぇ~」と強く打つ場所が違うだけ。
ストーンズはこの後、テンプスのAin't Too Proud To Begや
Just My Imagination (Running Away With Me)をカヴァーしていて、
テンプスが好きであるのは間違いないですね。
そして僕は両方大好き、だから「愛すべきパクリ」なのです。
もっとも僕はストーンズのこれを先に聴いたので、後から
テンプスを聴いてそれに気づいたのでした。
先ほどA面B面の話をしましたが、これはB面のアタマに置くには
これ以上ないというくらい合っている、だから印象的なのでしょうね。
7曲目 I Got The Blues
ブルーズマンのアルバート・キングがマスル・ショールズで録音した
ソウルとブルーズのハイブリッド、これはそのままの音といっていい。
ブラスの入り方は、思わずにやにやしてしまうくらいに。
でもミックの歌い方はソウルのマナーではまったくない。
高音で声が微妙に揺れるのが、ギターのアルペジオと呼応するようで、
それはロックの「ぎこちなさ」、しかし、そこがロックの面白さでしょう。
間奏の印象的なオルガンはビリー・プレストンによるもの。
ビリーは4曲目にも参加しています。
8曲目 Sister Morphine
この曲は前作LET IT BLEEDのアウトテイクで、
マスル・ショールズの録音には関わりがないとのこと。
Wild Horsesとは裏と表のような、アコースティックな響きのスロウな曲。
曲のクレジットには、ミックとキースに、ミックの恋人だった
マリアンヌ・フェイスフルの名前が加わっています。
ということは、この曲の主人公は彼女なのかな。
そしてスライドギターはライ・クーダー。
71年といえば、前年の秋、ジャニス・ジョプリンが亡くなった。
偶然なのだろうか。
もしかして、ジャニスに捧げた曲だったのか。
9曲目 Dead Flowers
明るくポップでのどか、そしてどこか間の抜けた響きが印象的。
しかしなんといってもこの曲はサビでのキースのコーラスがすごい。
コーラスというか、ミックが歌う主旋律とは別に、勝手にテキトーに
歌いたいように歌っているだけ、といった奔放さがありますね。
しかもそのキースの声がいい。
今回はキースが歌う曲がないので、その分張り切っていたのかな。
でもこれ、コーラスをつける勉強にはならない曲かも。
今回のリイシュー盤のDisc2は未発表音源が収録されていますが、
そのテイクはキースやり過ぎ! というくらいにコーラスがすごい。
B面のハイライトともいえるかもしれない。
このリイシューを買ってからは、この曲をよく口ずさんでいます。
時と場合により、ミックだったり、キースだったりします、もちろん(笑)。
10曲目 Moonlight Mile
この曲はタイトルがいいなあと最初から思いました。
抒情的な曲で、夜明け前の大地にひんやりとした空気が広がる、
そんな雰囲気をたたえた、大きく構えた曲。
しかし僕は、最初から大好きだったわけではありません。
「せっかくタイトルがいいのだから、好きにならなきゃ」
などと思いながら最初の頃は聴いていた記憶があります。
無茶ですかね、自然と好きなら好き、でいいじゃないか、と。
いや、僕はそういう思考の持ち主なので、しょうがないのです(笑)。
「好きにならなきゃ」と思ったのは、歌メロが最上級というわけではない
という部分があったかと思います。
でも、特に40歳を過ぎてからは、これは歌メロではなく雰囲気に
ひたって味わいながら聴くものだ、と気づいて漸く好きになりました。
そして俳句をやるようになった今、この曲は、僕の頭の中では、
月を求めて旅をした松尾芭蕉に結びつくようになりました。
いかにも芭蕉が月を求めて歩を進める、そんな雰囲気が漂う、
と書くと強引でしょうかね(そうでしょうね)。
でも、今の僕はこれを聴くと、芭蕉のそんな光景が頭に浮かんできます。
そうか、結局僕はこの曲とは縁があったんだ!
「好きにならなきゃ」というのは、何かを感じていたのかな、と。
満月の夜に暗い道を歩き、角を曲がると月明かりが眩しいほどだった。
そんな余韻を残しまくって、アルバムは終わります。
なお、Disc2のボーナストラックは以下の通りです。
1. "Brown Sugar" (Alternate Version with Eric Clapton)
2. "Wild Horses" (Acoustic version)
3. "Can't You Hear Me Knocking" (Alternate version)
4. "Bitch" (Extended version)
5. "Dead Flowers" (Alternate version)
6. "Live With Me" (Live at the Roundhouse, 1971)
7. "Stray Cat Blues" (Live at the Roundhouse, 1971)
8. "Love in Vain" (Live at the Roundhouse, 1971)
9. "Midnight Rambler" (Live at the Roundhouse, 1971)
10. "Honky Tonk Women" (Live at the Roundhouse, 1971)
ライヴも入っているのがうれしい。
そして特にMidnight Rambler、昨年の東京ドーム公演で
ミック・テイラーがステージに上がって一緒に演奏した曲、
早くもいい思い出になっていることに、これを聴いて気づきました。
アルバムのアートワークはアンディ・ウォーホール。
僕は、CDで初めて買ってアートワークが気に入ったアルバムは、
中古LPを探して買うことがよくあるけど、これはまだ買ってない。
ファスナーがついたジャケットはほしいのですが、でも、正直、
好きかどうかといわれれば、微妙ですね・・・(笑)。
結局のところ、ローリング・ストーンズは長く聴いているし、
僕にとっての基本でもあることがよく分かりました。
僕は、ソウルやブルーズそれにスワンプ系の音楽は、
40歳になってから漸く真面目に聴き始めましたが、
遠回りして結局たどり着いたのはストーンズだった、といったところ。
僕にとってはありがたい存在、それがローリング・ストーンズ。
今回、もうひとつ、ストーンズを熱心に聴き始めた二十歳の頃も
懐かしく思い出しました。
リアルタイムではなくても、音楽の思い出はできるものなのですね。
さて、ストーンズはほんとうにもう来日公演はしないのかな?
そんなはずはない、と、今また思い始めました。
最後は今日の3ショットです。
04


STICKY FINGERS
Rolling Stones
スティッキー・フィンガーズ
ローリング・ストーンズ (1971)
ローリング・ストーンズがレコード会社を移籍し、
1971年に発表した名盤のリマスター・リイシュー盤が出ました。
今日はこのアルバムの話です。
結論から先に言います。
僕は、ストーンズでこのアルバムがいちばん好きです!
はい、今日はこれで終わり。
なんて(笑)。
ストーンズは「ビートルズの半年遅れのコピー」と揶揄されながらも
1967年くらいまでは順調にヒット曲を重ね、ロック史に残る名曲
(I Can't Get No) Satisfactionを生み出すなど大成功を収めました。
しかし、コンサートでの事件、メンバーの問題、そして
ブライアン・ジョーンズの死などで、一時勢いを落とす。
しかし、ミック・ジャガーとキース・リチャードの"The grimmer twins"は
起死回生の傑作BEGGAR'S BANQUET(記事はこちら)を作り、
再び名曲名盤を数々と生み出すようになった。
このアルバムまでのストーンズをごく短くまとめると、こんなところ。
ストーンズは当然のことながら元々アメリカのブルーズやR&B、
ソウルといった黒人音楽への志向が強かった。
それはビートルズも同じ、当時のUK勢はみなそう。
しかしストーンズは、実際にツアーなどでアメリカに行くようになり、
「アメリカの深部」、「ディープなアメリカ」を知りたくなる。
ビートルズのSGT. PEPPER'Sを真似した1967年の
THEIR SATANIC MAJESTY'S REQUESTの「失敗」を受け、
いよいよその思いを形に表してゆくことになった。
余談、僕はTHEIR...REQUESTも大好きなんですが、それはまた。
BEGGAR'S...、LET IT BLEEDとその色を強めてきたストーンズ、
次のアルバムの制作にあたり、マスル・ショールズを訪れて録音した。
以前記事にした映画『黄金のメロディ』でその話を見ました。
マスル・ショールズはアラバマ州の小さな町ですが、
敏腕プロデューサーにして無類の音楽好き人間リック・ホールが
ソウルのレコードを吹き込み、次々と全国でヒットさせたことから、
マスル・ショールズはいつしか「ソウルの聖地」と呼ばれるようになった。
映画によれば、ストーンズのメンバは「突然」やって来て録音を始めた。
こう書くと思いつきでいかにも彼ららしい、と思うかもですが、
そこで録音されたこのアルバムを聴くと、決してそうではなく、
上述のように、積年の思いをついに実現する時が来た、
その時間が持てた、ととるべきだと思い直しました。
まあ、映画を観て「突然来る」のはカッコいい、とは思いましたが(笑)。
では、このアルバムがストーンズの「アメリカ深部への旅」の
完成形かというと、さにあらず。
まだこの先が続き、LPでは2枚組のEXILE ON MAIN ST.をもって
ひとまず完結するわけですね。
ストーンズは近年、70年代のアルバムのリイシュー盤を出していて、
EXILE...は既にリイシュー盤が出たのですが、実は僕、
そのアルバムはまだソラで全曲分からないので記事にしていません。
それを機にある程度聴き込んだので、近いうちに今回の続編的に
記事にまとめてみたいと、今、思いました。
ちなみに、リイシューはSOME GIRLSも既に出ていますが、
こちらはリイシュー前に記事(こちら)にしていました。
また、前のアルバムに数曲参加し、No.1ヒットとなった
Honky Tonk Womenから正式メンバーとなった
ミック・テイラーが初めて全曲参加したアルバムでもあります。
僕とこのアルバムの話も少し。
僕はこれ、1990年代に当時SONYから出ていた国内盤CDで
初めて聴きました。
ロックの名盤本などでこれは傑作だと情報は得ていましたが、
最初に聴いて、いいけれどすごくいいかと言われると・・・でした。
大好きなBrown Sugarが入っている時点で僕の中の評価が
自然と高まりはしましたが、逆にいえばその曲がなければこれを
好きと言えるか、自信はいまいちありませんでした。
ただ、曲がいい意味で「心に引っかかるアルバム」だと思いました。
後になって突然フレーズを思い出す、そんな曲が多かった。
その後、VIRGINからリマスター盤が出たので買い直し、
さらにUNIVERSALからまた出直したのも買い直し、
年に1、2回は聴き続けてきましたが、さすがにそれだけ聴くと
曲にもなじみがでてきて、いいアルバムと思えるようになりました。
やっぱり曲が分かる、好き、というのは大きいですね。
そして、今月、このリイシュー盤が届いた時に聴いていて
「やっぱ俺はストーンズでこのアルバムがいちばん好きだわ!」
と、まるで稲妻に打たれたかのように思いました。
実際、その時は最初PCで作業をしながらかけていたのですが、
3曲目くらいになってPCの手が止まり、その後はただ聴くだけ。
昔からよく聴いてきた、大好きなアルバムでも、
或る日突然、すごくよく聴こえる、ということ、ありませんか?
僕は多々あります。
ビートルズとて例外ではなく、それを何十回も繰り返してきました。
「洋楽危機」の記事(こちら)で、古い音源に頼り過ぎていることが
洋楽の現状につながっていると書きましたが、良い物は良いわけで、
リイシュー盤を買い直すと、前よりよく聴こえることはあるのです。
それは音楽の本質でもあるから、古い音源を出し直すのは、
知らない人への新たな発信でもあると同時に、元々好きで
よく聴いてきた人にも訴えている、というわけなのですね。
自分で「洋楽危機」の記事を書いておきながら、今回このアルバムで、
自分自身、あらためてそんなことを思いました。
話は逸れましたが、今回このアルバムに「打たれた」のは、僕は
近年ソウルやブルーズなどを熱心に聴くようになり、このアルバムの
下地にある彼らの音楽への思いが理解できるようになってきた、
ということなのでしょう。
マスル・ショールズで録音したという「魔法」もかかっていますが、
もっと直接的にサザンソウルの影響が色濃く感じられます。
そして、ドクター・ジョンやミーターズ、ネヴィル・ブラザースに
アーロン・ネヴィル、アラン・トゥーサン、古くはファッツ・ドミノといった
ニューオーリンズの音楽は、自分で思っている以上に
僕に大きな影響を与えているんだな、と再確認しました。
なんといっても、Brown Sugarの歌い出し4小節目でミックが
"New Orleans"と歌っていますからね。
なお、録音は他にロンドンとミック・ジャガーの自宅でも行われ、
例の"Mobile"が使われた、アルバム完成となりました。
02

1曲目 Brown Sugar
ここでもうひとつ宣言、というのは大袈裟か。
僕は、ストーンズの曲ではやっぱりこれが一番好き!
この曲は一応ギターで弾けるのですが、でも、楽譜は持っていない。
耳コピーしたのかというとそうではなく、イントロのギターリフと
コード進行は、楽器店で楽譜を「立ち読み」して覚えました。
二十歳くらいの頃、今より頭が柔らかかったんだなあ、と(笑)。
この曲、元々一番好きなグループであり続けてはいましたが、
ギターソロがないのがギター弾きとしてはちょっと弱いかな、と。
ただ、あったところで弾かないという例は数多あるのですが、
最初からないのとは話が違いますよね。
でも、もうそんなことは関係なくなりました。
で、何がいいって、そりゃもう、歌メロ、ギター、すべて。
特に、ソロはなくてもギターワーク、ギターの音色、最高にいい。
そしてこの曲を特徴づけているのは、リズムでしょう。
この跳ね具合いとネバつきそしてグルーヴ感は、スワンプ志向が強く、
またそれができるほど「バンド」として強くなっていたことも感じます。
ライヴ盤では真っ直ぐなロックンロールになっているものもあって、
正直、この曲の魅力が半減と感じたものです。
歌詞の内容は「男尊女卑」的なもので物議を醸したそうで、
マイナスポイントがあるとすればそこかな。
でも、ライムとしては歌メロとリズムに合っていて最高にいい!
そして今回のリイシュー盤に収録された未発表テイクでは、
なんとエリック・クラプトンが参加しています。
正式テイクに比べると当然ラフな作りですが、エリックともども
スワンプをモノにしてやろうという鋭さを感じます。
ところで、このBLOGではまだ触れていませんでしたが、
この曲をはじめストーンズでの名演が多く、昨年の東京ドームにも
来ていたサックス奏者ボビー・キーズが昨年12月に亡くなりました。
ドームで会ったばかりだったので、ショックでした。
この場を借りて、R.I.P.
2曲目 Sway
タイトルのごとく、バンド全体が滑りながらずれていく感覚がいい。
最後にストリングスが入って来るのが洒落ている。
ところで僕はこの曲を最初"Swamp"だと思って聴いていて、
「スワンプってこういう音楽なんだ」と思ったものでした。
僕が「スワンプ」という言葉と概念を知ったのは、トーキング・ヘッズの
ライヴSTOP MAKING SENSEで、そのものSwampという曲があり、
何かで調べて「粘つきのあるアメリカ南部の音楽」と知りました。
これは、曲名を覚える前にアルバムCDを聴き始めて、
"Swa"まで同じなので、勘違いしてしまったのでしょう。
でも、この勘違いは「間違い」ではなかった、ということですね(笑)。
3曲目 Wild Horses
ストーンズはこのアルバムからレコード会社を移籍したと書きましたが、
Brown Sugarとこの曲のみ、それまでのDECCAの音源と同じく
権利がABKCOレコードにあり、この2曲は1960年代の曲を集めた
名編集のベスト盤HOT ROCKSに収録されています。
HOT ROCKSは、僕が初めて買ったストーンズのCDであり、
僕のCD初期50枚に入るほど早くに買って聴いていました。
当時からこの2曲についての話は本か何かで知っていて、
ここから新しいストーンズになっていたんだ、と思いながら聴きました。
Brown Sugarはいかにもストーンズらしくてすぐ好きになりましたが、
この曲は「彼らもこんな曲をやるんだ」と少々戸惑いました。
カントリーっぽさを感じるスロウで抒情的な曲。
本来僕が好きになりそうなものを、素直に好きとはいえなかった。
しかも彼ら自身がこの曲を大好きそうと分かって、なぜだろうって。
でも、この曲は、年を経るごとに徐々に好きになってゆき、
数年前、ああ本当にいい曲だあ、としみじみ思いました。
サビもいいけど、ヴァースの歌メロもいい。
ストーンズの芸の奥深さがよく分かる1曲でしょうね。
4曲目 Can't You Hear Me Knockin’
長いサックスソロを含むジャムセッションを発展させた曲。
この前年にジョージ・ハリスンがスワンプ趣味をかき集めて
作り上げたALL THING MUST PASSが出た、と今ふと
この曲を聴きながら思いましたが、当時の英国ロックには、
「ブルーズロック」の後に「スワンプロック」の波が来ていたようですね。
ほとんどハードロック的な突き刺さるギターリフがいい。
5曲目 You Gotta Move
アコースティックギターによる本格的カントリーブルーズ。
元々は戦後期のゴスペルやブルーズから始まった曲で、
フレッド・マクダウェルが1965年に録音したものがストーンズの
下地になっているようですが、サム・クックも同じモチーフで
1963年に録音している、など、複雑な変遷の曲でもあります。
この曲は「心に引っかかった」曲のひとつで、なんだろう、
けだるい雰囲気が気になって仕方なかった。
こういう音楽はまだ当時あまり聴いていなくて印象的だったのでしょう。
ところで、僕は、CDの時代になってからCDで初めて聴くアルバムは、
可能な限りどこまでがLPのA面でどこからがB面かを調べて
頭の中に刻んで聴くようにしていて、これはLPのA面最後。
最初にLPで聴いたアルバムはそれが頭に刻み込まれていますが、
これはLPで聴いたことがないのに、A面B面の区別が明確なのです。
やっぱり、若い頃にそうして覚えて聴いたからでしょうね。
03 "dead"ではない花、庭で咲いた薔薇「ミュージック」

6曲目 Bitch
この曲は1990年の初来日公演で演奏したことで、
僕の中では特別なものとなりました。
当時はまだストーンズ聴き始めのようなもので、シングルで
大ヒット曲はだいたい分かるけれど、アルバムの中の曲までは
抑えきれていない状態で、この曲をやって驚いたのでした。
ヒット曲と新譜からの曲以外を演奏しそれを聴くというのは、
コンサートの醍醐味なのだ、と、この曲から学んだ気がします。
この曲は「愛すべきパクリ」のひとつですね。
イントロのリフがテンプテーションズのGet Readyとそっくり。
「てってぇ~」と強く打つ場所が違うだけ。
ストーンズはこの後、テンプスのAin't Too Proud To Begや
Just My Imagination (Running Away With Me)をカヴァーしていて、
テンプスが好きであるのは間違いないですね。
そして僕は両方大好き、だから「愛すべきパクリ」なのです。
もっとも僕はストーンズのこれを先に聴いたので、後から
テンプスを聴いてそれに気づいたのでした。
先ほどA面B面の話をしましたが、これはB面のアタマに置くには
これ以上ないというくらい合っている、だから印象的なのでしょうね。
7曲目 I Got The Blues
ブルーズマンのアルバート・キングがマスル・ショールズで録音した
ソウルとブルーズのハイブリッド、これはそのままの音といっていい。
ブラスの入り方は、思わずにやにやしてしまうくらいに。
でもミックの歌い方はソウルのマナーではまったくない。
高音で声が微妙に揺れるのが、ギターのアルペジオと呼応するようで、
それはロックの「ぎこちなさ」、しかし、そこがロックの面白さでしょう。
間奏の印象的なオルガンはビリー・プレストンによるもの。
ビリーは4曲目にも参加しています。
8曲目 Sister Morphine
この曲は前作LET IT BLEEDのアウトテイクで、
マスル・ショールズの録音には関わりがないとのこと。
Wild Horsesとは裏と表のような、アコースティックな響きのスロウな曲。
曲のクレジットには、ミックとキースに、ミックの恋人だった
マリアンヌ・フェイスフルの名前が加わっています。
ということは、この曲の主人公は彼女なのかな。
そしてスライドギターはライ・クーダー。
71年といえば、前年の秋、ジャニス・ジョプリンが亡くなった。
偶然なのだろうか。
もしかして、ジャニスに捧げた曲だったのか。
9曲目 Dead Flowers
明るくポップでのどか、そしてどこか間の抜けた響きが印象的。
しかしなんといってもこの曲はサビでのキースのコーラスがすごい。
コーラスというか、ミックが歌う主旋律とは別に、勝手にテキトーに
歌いたいように歌っているだけ、といった奔放さがありますね。
しかもそのキースの声がいい。
今回はキースが歌う曲がないので、その分張り切っていたのかな。
でもこれ、コーラスをつける勉強にはならない曲かも。
今回のリイシュー盤のDisc2は未発表音源が収録されていますが、
そのテイクはキースやり過ぎ! というくらいにコーラスがすごい。
B面のハイライトともいえるかもしれない。
このリイシューを買ってからは、この曲をよく口ずさんでいます。
時と場合により、ミックだったり、キースだったりします、もちろん(笑)。
10曲目 Moonlight Mile
この曲はタイトルがいいなあと最初から思いました。
抒情的な曲で、夜明け前の大地にひんやりとした空気が広がる、
そんな雰囲気をたたえた、大きく構えた曲。
しかし僕は、最初から大好きだったわけではありません。
「せっかくタイトルがいいのだから、好きにならなきゃ」
などと思いながら最初の頃は聴いていた記憶があります。
無茶ですかね、自然と好きなら好き、でいいじゃないか、と。
いや、僕はそういう思考の持ち主なので、しょうがないのです(笑)。
「好きにならなきゃ」と思ったのは、歌メロが最上級というわけではない
という部分があったかと思います。
でも、特に40歳を過ぎてからは、これは歌メロではなく雰囲気に
ひたって味わいながら聴くものだ、と気づいて漸く好きになりました。
そして俳句をやるようになった今、この曲は、僕の頭の中では、
月を求めて旅をした松尾芭蕉に結びつくようになりました。
いかにも芭蕉が月を求めて歩を進める、そんな雰囲気が漂う、
と書くと強引でしょうかね(そうでしょうね)。
でも、今の僕はこれを聴くと、芭蕉のそんな光景が頭に浮かんできます。
そうか、結局僕はこの曲とは縁があったんだ!
「好きにならなきゃ」というのは、何かを感じていたのかな、と。
満月の夜に暗い道を歩き、角を曲がると月明かりが眩しいほどだった。
そんな余韻を残しまくって、アルバムは終わります。
なお、Disc2のボーナストラックは以下の通りです。
1. "Brown Sugar" (Alternate Version with Eric Clapton)
2. "Wild Horses" (Acoustic version)
3. "Can't You Hear Me Knocking" (Alternate version)
4. "Bitch" (Extended version)
5. "Dead Flowers" (Alternate version)
6. "Live With Me" (Live at the Roundhouse, 1971)
7. "Stray Cat Blues" (Live at the Roundhouse, 1971)
8. "Love in Vain" (Live at the Roundhouse, 1971)
9. "Midnight Rambler" (Live at the Roundhouse, 1971)
10. "Honky Tonk Women" (Live at the Roundhouse, 1971)
ライヴも入っているのがうれしい。
そして特にMidnight Rambler、昨年の東京ドーム公演で
ミック・テイラーがステージに上がって一緒に演奏した曲、
早くもいい思い出になっていることに、これを聴いて気づきました。
アルバムのアートワークはアンディ・ウォーホール。
僕は、CDで初めて買ってアートワークが気に入ったアルバムは、
中古LPを探して買うことがよくあるけど、これはまだ買ってない。
ファスナーがついたジャケットはほしいのですが、でも、正直、
好きかどうかといわれれば、微妙ですね・・・(笑)。
結局のところ、ローリング・ストーンズは長く聴いているし、
僕にとっての基本でもあることがよく分かりました。
僕は、ソウルやブルーズそれにスワンプ系の音楽は、
40歳になってから漸く真面目に聴き始めましたが、
遠回りして結局たどり着いたのはストーンズだった、といったところ。
僕にとってはありがたい存在、それがローリング・ストーンズ。
今回、もうひとつ、ストーンズを熱心に聴き始めた二十歳の頃も
懐かしく思い出しました。
リアルタイムではなくても、音楽の思い出はできるものなのですね。
さて、ストーンズはほんとうにもう来日公演はしないのかな?
そんなはずはない、と、今また思い始めました。
最後は今日の3ショットです。
04

2015年01月25日
TRUTH ジェフ・ベック
01

TRUTH Jeff Beck
トゥルース ジェフ・ベック (1968)
今日はジェフ・ベックいきます。
ジェフは一応、ソロ以降の全アルバムが家にあるのですが、
よく聴いているかというと、正直、はいとはいえない人です。
嫌いな理由は何もなく、むしろ尊敬しているギタリストですが、
端的にいえば尊敬が大きすぎてなかなか近寄れない、
そんな存在かもしれません、現在進行形で。
だからジェフのプレイがどうのこうのは話せないのですが、
音楽にも情報にもずっと接してきている人ではあって、そんな中、
このアルバムは唯一、そらで曲が思い浮かぶくらいの愛聴盤。
年末から、きっかけは特になく目に留ったので突然また聴き始め、
以前は気づかなかったことを感じたので、記事にしてみました。
僕がこれを初めて聴いたのは大学生の頃、当時はCD時代の初期で、
これと次のBECK-OLAのCD化を楽しみに待っていました。
もちろんそれは、ロッド・スチュワートがいるからです。
ロッドは高校時代から大好きで、遡ってたどり着いたのですが、
ロッドがジェフ・ベックからキャリアをスタートさせたことを
最初に話として聞いた時、僕は違和感のようなものを覚えました。
実際に聴くと、ロッドが歌っているだけでうれしかった(笑)。
声があまり変わっていない、やはり歌メロをつかみやすく歌う人だ、
などなど感心しきりでした。
ただし、やはり多少の違和感はありました。
ハードな音ととのミスマッチ感覚がそうさせたのかなと。
ロッドが2枚で辞めてしまったことも、なんとなく、
分かったとはいわないけど、想像はできました。
ただし、このアルバム自体は音楽としてあまりにも素晴らしく、
すぐに大好きになりました。
このところ聴いていて、気づいたというか新たに感じたこと。
ひとつ、昔思っていたよりも音がうんと土臭い。
音が粘っこくて、もっというとアメリカ南部っぽさがあって
レッド・ツェッペリンのように良くも悪くもスマートではない。
リズム隊がそう感じさせるのかな。
また、クリームのように、個性のぶつかり合いの中から
マジックが生まれてくるというわけでもなくて、
あくまでもジェフが全てを支配し統制をとっているようで、
音楽全体は整っていて、意外と涼しさを感じます。
土臭いけど、あまり気温が高くなく、蒸してもいない。
アメリカのオールマン・ブラザース・バンドに英国っぽい
要素があると言われますが、逆にジェフ・ベックは
英国側からアメリカにアプローチしてったところ、
大西洋上の同じ辺りでオールマンと交錯したという感じかな。
ただ、次のBECK-OLAのほうがより南部っぽいと感じましたが、
今回はこのアルバムだけに絞って話をします。
もうひとつ、僕はロッドから遡って聴いたと書きましたが、
今さら冷静になって聴いてみると、ロッドのヴォーカルの存在感は、
まさに唯一無二、誰も真似できない世界を持った人なんだなと。
こんな声の人はいないですからね。
そりゃプロのヴォーカリストのしかも第一線でやっていく人は、
唯一無二の声を持っているに違いないのですが、しかしロッドは、
声の質というよりは、そもそも世界が違うように感じます。
これが世に出た時に、なんだこの声の持ち主は、と驚いた人が
多かったのではないかと勝手に想像しました。
声はまさに最大の楽器ですね。
このアルバムはよく、ヘヴィメタルのルーツの1枚
のような言い方をされています。
ブルーズ基調で重たくハードなギターの音という点で、
見た目はそうなのかもしれません、そう思う部分はあります。
でも、コンセプト的にはまだまだヘヴィメタルには遠いですね。
ブルーズを感じなくなったところがヘヴィメタル、
と僕は思います、すべてがそうとも限らないですが。
2005年のリマスター盤にはボーナストラックが8曲収録され、
中には、ジェフが歌う最初のシングルHi Ho Silver Lining、
次のシングルのTallymanや、ポール・モーリアで有名な
「恋はみずいろ」 Love Is Blueも収録されています。
ただし今回はあくまでもアルバム本編だけに触れてゆきます。
そのCDのブックレットの裏は、写真03、
おそらくLPの裏面がそのまま使われていると思いますが、
そこにはジェフ自身の曲への短いコメントが記されています。
そうした例は多くはないとは思いますが、ジェフはそれだけ
力を入れてこのアルバムを作り、自信があったのでしょうね。
面白いので、今回は、それを紹介しながら進めます。
JBと記した青文字の文章がジェフ・ベックのコメントです。
なお、翻訳は引用者によるもので、一部補足も加えています。
そしてリマスター盤には、Charles Shaar Murrayなる人物の
解説があって、そこに書かれていることにも少し触れます。
このアルバムのバンドのメンバーは以下の4人ですが、
ジェフ・ベック Jeff Beck (Gt)(Tr5のベース)
ロッド・スチュワート Rod Stewart (Vo)
ロン・ウッド Ron Wood (Bs)
ミッキー・ウォラー Micky Waller (Ds)
このアルバムは参加メンバーが豪華であり、
英国ロック躍動期の縮図ともいうべく興味深いので、
先に名前を挙げて紹介してゆきます。
キース・ムーン Keith Moon
→Tr8のドラムスとTr5のティンパニー
ジミー・ペイジ Jimmy Page
→Tr8の12弦ギター
ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones
→Tr4、5のオルガンとTr8のベース
ニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins
→Tr3、4、8、9のピアノ、彼はサブメンバー的役割の模様
またTr3のバグパイプはMyserious Scottish Blokeと記されています。
ジェフはGibson Les PaulとMarshallのアンプを使用と記され、
ブックレットにはジェフがレス・ポールを弾く写真もあります。
いつものように作曲者は各曲の下に示してゆきますが、今回は、
ブックレットに書いてある通りに記し、本文で補足してきます。
02 2005年リマスター盤CDブックレットの裏面

Tr1:Shapes Of Things
(Sammuel-Smith / Relf / McCarty)
JB:アレンジし直したけどヤードバーズのヒット曲だ。
この曲は何を使って聴くのでも最大音量で聴いてくれ。
もし君が教会の牧師をお茶の時間に呼ぶのなら、
これは最高のBMGになるだろうな。
元々ヤードバーズの曲で、ジェフ自身には再録音になる曲。
イントロのベースとドラムスが真っ直ぐに入ってくるけど、
ヴォーカルとギターが始まったところで横の流れもできて
音が立体的に広がる、最初の5秒で圧倒されること間違いなし。
このアルバムはそれとベースが歌いながら激しく動いていますが、
ロン・ウッドは最初はリズム・ギターとしてジェフに迎えられ、
ベースは他の人を考えていたのが、彼のイメージに合う人がおらず、
ロンをベースにコンバートすることを思いついたそうです。
そしてロンはFender Jazz Bassを弾いているとも書かれています。
ヤードバーズには悪いけどこの曲は「ジェフ・ベックの曲」、かな。
Tr2:Let Me Love You
(Jeffery Rod)
JB:ヘヴィな曲、素晴らしいタンバリンは
ミッキー・モストによるものだ。
ロッドの曲。いろんな状況で映える曲だよ。
作曲者の「ジェフリー・ロッド」とは
ジェフとロッドのことだと思われますが、
オリジナルLPの裏面部分には(Rod)としか記されておらず、
リマスター盤のブックレットにはこのよう書かれています。
なぜだろう、ちょっと不思議、ロッドへの感謝の念からかな。
ただしこれはモチーフをバディ・ガイの曲からいただいている、
と解説にありますが、当時の英国は、ブルーズの名曲に手を加えて
自作の曲として歌う悪しき流行があったようで、これもそうかな。
この曲は歌うには最高によいのですが・・・
ロッドは、歌に感情はこもっているけど、取り乱すこともなく
悠然と歌い続け、若くして既に凄味を感じます。
なお、ミッキー・モスト Micky Mostはプロデューサー。
Tr3:Morning Dew
(Rose - Dobson)
JB:ティム(・ローズ)のこの曲の素晴らしさはみんな知ってる。
だけど僕たちのもなかなか良くないかい。
作曲者のひとりでもあるティム・ローズのヒット曲で、
ジェフは彼への賛辞を送っています。
ただしこれは調べると、ジャンルとしてはフォークであるらしく、
ロッドのその後のカバー曲の選曲との共通性を考えると興味深い。
この空気感を表現できるロッドの素晴らしさに感動しますね。
ロッドの執拗なヴォーカルは、歩いても歩いても足に朝露が着く
草原を進まざるを得ないような感覚に陥ります(笑)。
ジェフの跳ねるようなギターの音もカッコいい。
Tr4:You Shook Me
(Dixon)
JB:むしゃくしゃした時に聴くための曲としてこれはおそらく、
最も適当かついいかげんに録音された曲じゃないかな。
最後の音は僕のギターだけど、きみたちが調子がよくない時に、
この2分28秒でやる気をくじいてくれたまえ。
これはレッド・ツェッペリンで先に聴きましたが、
Zepのそれを最初に聴いて僕は大爆笑してしまいました。
ここはジェフの話なのでそのことには触れないとして、
ジェフのこれは妙に小ぎれいにまとまっていると感じました。
オルガンはジョン・ポール・ジョーンズ。
ニッキーのピアノの高音の連弾も印象に残ります。
ウィリー・ディクソンはブルーズ系のロッカーから
最大限の尊敬の念を集めていた人ですね。
Tr5:O'l Man River
(Kern - Hammerstein II)
JB:アレンジは僕だけど、クレジットはみんなのもので、
ロッド・スチュワートはとりわけ素晴らしい。
これもまた最大音量で聴いてくれ。
白状します。
僕はずっと、オーティス・レディングのO'l Man Troubleと
この曲を混同していました、同じだと思っていました。
しかも、それをオーティスを真面目に聴くまでずっと、
だからつまり、昨年まで、そう思っていたのです・・・
調べるとこれは1920年代のミュージカルの中の曲ということで、
そんなに古い曲だったんだ。
じわじわと迫ってくる演奏が迫力ありますね。
キース・ムーンがわざわざティンパニーをやるだけあります。
これ、ほとんどソウルと言っていい雰囲気もあって、
ソウルっぽさを感じさせるのはロッドの持ち味かな。
今回、かなり奥深い曲だと再認識、再発見しました。
03 CDとハウのアウトテイク写真

Tr6:Greensleeves
(Trad arr. Jeffery Rod)
JB:ミッキー・モストのギターで演奏している。
エルヴィスとも同じものなんだ。
解説にはそのギターはGibson J-200と書いてあります。
ところで、ポール・マッカートニーはこれを聴いて、
Junkを作ることを思いついたのかなと思うことがあります。
違うかもしれないけど、雰囲気が似ています。
特に、McCARTNEYに収録されたオリジナルではなく、
UNPLUGGEDのバージョンは、メドレーで1曲にしたいくらい、
雰囲気以上に演奏も似ています。
なんて、結局はビートルズに言及するのか・・・(笑)・・・
話は逸れましたが、この曲はロックを聴く前から知っていて、
こうしたトラッドをロックで演奏しているのを聴くと、
若い頃は特にうれしくなりました。
Tr7:Rock My Primsoul
(Jeffery Rod)
JB:"Tallyman"のB面として録音していたが、こちらのほうが
オリジナルよりナチュラルな雰囲気でよくできている。
これも一応はオリジナルでも、B.B.キングのRock Me Baby
からいただいているということで、やはりちょっと複雑。
まあしかしこれは歌メロもいいし、素晴らしい曲ですね。
若い頃からよく口ずさんでいました。
ロッドも後にライヴで歌っています。
この曲のロッドのヴォーカルでひとつ思ったのは、
ハスキーヴォイスと言われますが、それと関係あるのかどうか、
ロッドは歌うと声がいい具合に微妙に欠けていることかな。
音が揺れるというべきか、声がただ伸びているのではなく、
作為的というよりは自然とそういう声になっている感じ。
Tr8:Beck's Bolero
(Page)
JB:これについてあまり多くは語れないな。
"(Hi Ho) Silver Lining"のB面と同じテイクで、言い訳になるが、
それ以上に良くすることはできなかったんだ。
トラッドに続いてクラシックの要素まであるなんて、
若い僕はこれを聴いてほんとに楽しかった(笑)。
ジミー・ペイジが作ったこの曲はインストゥルメンタルで、
ギターによるオーケストラといった趣の壮大な響きに
心をかきむしられ、引き込まれます。
ただこれ、音質がもう少し良ければもっと透明感があるのにな
と、昔から思っています。
逆にこの音質だから、喧騒を、時代を感じるのでしょうけど。
Tr9:Blues De Luxe
(Jeffery Rod)
JB:バートとスタンに感謝だ。
僕たちは、やろうとしていた「ライヴ」演奏のブルーズの
完璧なモデルを作ることができたが、ピアノソロについては
言わせてもらいたいことがある。
すいません、バートとスタンが誰かが分かりませんでした。
ピアノソロはニッキーで、ジェフの文章はここまでですが、
これは聴衆の拍手が入っていてライヴのように聴こえるけど、
実際はスタジオ録音で拍手は後から被せたものだそうです。
この曲もまた一応はオリジナルですが、やはり
B.B.キングのGambler's Bluesとよく似ている、ということ。
この辺りのルーツ感覚はジェフもロッドも同じだったのかな。
普通に演奏すればこの半分の時間で終わりそうなほど(笑)、
とにかくゆったりとした、とろい曲。
ロッドはやはり何を歌わせてもさまになっている、うん。
この曲の歌はこの中ではいちばん気持ちが入っていますね。
Tr10:I Ain't Superstitious
(Dixon)
JB:ハウリン・ウルフの古い曲からリフをいただいているけど、
彼は気にしていないよ、だって僕は彼に話をつけたから。
この曲はめくるめくギターが炸裂している、そのための曲だね。
これらの愛すべき曲が僕らの最初のLP、TRUTHさ。
ウィリー・ディクソンの曲にハウリン・ウルフのリフと
凝っているといえば凝っていますね。
ワウペダルを多投したまさにめくるめくギターワークには、
自然と気持ちが高揚してきます、ナチュラル・ハイ。
サイケデリックの影響もあるのでしょうか、時代ですね。
でも、アルバム全体ではそれほどサイケの影響は感じません。
だから僕が大好き、ともいえます。
実は最近、僕は、サイケがやや苦手だと分かってきました。
つまらない人間ですから、僕は(笑)。
この曲はもはやロックのマスターピースのひとつでしょう。
ジェフ・ベックの曲として語り継がれてゆくであろう曲。
アルバムの最後を、緊張感を持ってびしっと締めてくれます。
ううん、ギタリストのジェフ・ベックのアルバムで、
僕自身も一応はギターを弾く人間だというのに、
ロッドの話ばかりで終わってしまった感が・・・
ギターについては、ソロももちろんすごいけど、僕はやはり
バックの特に低音弦の音の動かし方がカッコいいと思います。
なんて、取ってつけたように感じられるかも・・・
1968年といえば、このアルバムの他に、
ジミ・ヘンドリックスのELECTRIC LADYLAND、
クリームのWHEELS OF FIREと、
ブルーズに大きく影響を受けたロックの名盤が
リリースされた年として記されています。
さらにはレッド・ツェッペリンもこの年に結成され、
1stが発表されたのは翌年ですがでも1月にリリースだから
この年に録音されていたわけで、考えてみればすごいですね、
こんなすごいアルバムが4枚も作られたなんて。
ちなみに僕が1歳の年ですね、覚えているわけがない(笑)。
こう書いていると、それらのアルバムも
記事に取り上げたくなってきましたよ。

TRUTH Jeff Beck
トゥルース ジェフ・ベック (1968)
今日はジェフ・ベックいきます。
ジェフは一応、ソロ以降の全アルバムが家にあるのですが、
よく聴いているかというと、正直、はいとはいえない人です。
嫌いな理由は何もなく、むしろ尊敬しているギタリストですが、
端的にいえば尊敬が大きすぎてなかなか近寄れない、
そんな存在かもしれません、現在進行形で。
だからジェフのプレイがどうのこうのは話せないのですが、
音楽にも情報にもずっと接してきている人ではあって、そんな中、
このアルバムは唯一、そらで曲が思い浮かぶくらいの愛聴盤。
年末から、きっかけは特になく目に留ったので突然また聴き始め、
以前は気づかなかったことを感じたので、記事にしてみました。
僕がこれを初めて聴いたのは大学生の頃、当時はCD時代の初期で、
これと次のBECK-OLAのCD化を楽しみに待っていました。
もちろんそれは、ロッド・スチュワートがいるからです。
ロッドは高校時代から大好きで、遡ってたどり着いたのですが、
ロッドがジェフ・ベックからキャリアをスタートさせたことを
最初に話として聞いた時、僕は違和感のようなものを覚えました。
実際に聴くと、ロッドが歌っているだけでうれしかった(笑)。
声があまり変わっていない、やはり歌メロをつかみやすく歌う人だ、
などなど感心しきりでした。
ただし、やはり多少の違和感はありました。
ハードな音ととのミスマッチ感覚がそうさせたのかなと。
ロッドが2枚で辞めてしまったことも、なんとなく、
分かったとはいわないけど、想像はできました。
ただし、このアルバム自体は音楽としてあまりにも素晴らしく、
すぐに大好きになりました。
このところ聴いていて、気づいたというか新たに感じたこと。
ひとつ、昔思っていたよりも音がうんと土臭い。
音が粘っこくて、もっというとアメリカ南部っぽさがあって
レッド・ツェッペリンのように良くも悪くもスマートではない。
リズム隊がそう感じさせるのかな。
また、クリームのように、個性のぶつかり合いの中から
マジックが生まれてくるというわけでもなくて、
あくまでもジェフが全てを支配し統制をとっているようで、
音楽全体は整っていて、意外と涼しさを感じます。
土臭いけど、あまり気温が高くなく、蒸してもいない。
アメリカのオールマン・ブラザース・バンドに英国っぽい
要素があると言われますが、逆にジェフ・ベックは
英国側からアメリカにアプローチしてったところ、
大西洋上の同じ辺りでオールマンと交錯したという感じかな。
ただ、次のBECK-OLAのほうがより南部っぽいと感じましたが、
今回はこのアルバムだけに絞って話をします。
もうひとつ、僕はロッドから遡って聴いたと書きましたが、
今さら冷静になって聴いてみると、ロッドのヴォーカルの存在感は、
まさに唯一無二、誰も真似できない世界を持った人なんだなと。
こんな声の人はいないですからね。
そりゃプロのヴォーカリストのしかも第一線でやっていく人は、
唯一無二の声を持っているに違いないのですが、しかしロッドは、
声の質というよりは、そもそも世界が違うように感じます。
これが世に出た時に、なんだこの声の持ち主は、と驚いた人が
多かったのではないかと勝手に想像しました。
声はまさに最大の楽器ですね。
このアルバムはよく、ヘヴィメタルのルーツの1枚
のような言い方をされています。
ブルーズ基調で重たくハードなギターの音という点で、
見た目はそうなのかもしれません、そう思う部分はあります。
でも、コンセプト的にはまだまだヘヴィメタルには遠いですね。
ブルーズを感じなくなったところがヘヴィメタル、
と僕は思います、すべてがそうとも限らないですが。
2005年のリマスター盤にはボーナストラックが8曲収録され、
中には、ジェフが歌う最初のシングルHi Ho Silver Lining、
次のシングルのTallymanや、ポール・モーリアで有名な
「恋はみずいろ」 Love Is Blueも収録されています。
ただし今回はあくまでもアルバム本編だけに触れてゆきます。
そのCDのブックレットの裏は、写真03、
おそらくLPの裏面がそのまま使われていると思いますが、
そこにはジェフ自身の曲への短いコメントが記されています。
そうした例は多くはないとは思いますが、ジェフはそれだけ
力を入れてこのアルバムを作り、自信があったのでしょうね。
面白いので、今回は、それを紹介しながら進めます。
JBと記した青文字の文章がジェフ・ベックのコメントです。
なお、翻訳は引用者によるもので、一部補足も加えています。
そしてリマスター盤には、Charles Shaar Murrayなる人物の
解説があって、そこに書かれていることにも少し触れます。
このアルバムのバンドのメンバーは以下の4人ですが、
ジェフ・ベック Jeff Beck (Gt)(Tr5のベース)
ロッド・スチュワート Rod Stewart (Vo)
ロン・ウッド Ron Wood (Bs)
ミッキー・ウォラー Micky Waller (Ds)
このアルバムは参加メンバーが豪華であり、
英国ロック躍動期の縮図ともいうべく興味深いので、
先に名前を挙げて紹介してゆきます。
キース・ムーン Keith Moon
→Tr8のドラムスとTr5のティンパニー
ジミー・ペイジ Jimmy Page
→Tr8の12弦ギター
ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones
→Tr4、5のオルガンとTr8のベース
ニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins
→Tr3、4、8、9のピアノ、彼はサブメンバー的役割の模様
またTr3のバグパイプはMyserious Scottish Blokeと記されています。
ジェフはGibson Les PaulとMarshallのアンプを使用と記され、
ブックレットにはジェフがレス・ポールを弾く写真もあります。
いつものように作曲者は各曲の下に示してゆきますが、今回は、
ブックレットに書いてある通りに記し、本文で補足してきます。
02 2005年リマスター盤CDブックレットの裏面

Tr1:Shapes Of Things
(Sammuel-Smith / Relf / McCarty)
JB:アレンジし直したけどヤードバーズのヒット曲だ。
この曲は何を使って聴くのでも最大音量で聴いてくれ。
もし君が教会の牧師をお茶の時間に呼ぶのなら、
これは最高のBMGになるだろうな。
元々ヤードバーズの曲で、ジェフ自身には再録音になる曲。
イントロのベースとドラムスが真っ直ぐに入ってくるけど、
ヴォーカルとギターが始まったところで横の流れもできて
音が立体的に広がる、最初の5秒で圧倒されること間違いなし。
このアルバムはそれとベースが歌いながら激しく動いていますが、
ロン・ウッドは最初はリズム・ギターとしてジェフに迎えられ、
ベースは他の人を考えていたのが、彼のイメージに合う人がおらず、
ロンをベースにコンバートすることを思いついたそうです。
そしてロンはFender Jazz Bassを弾いているとも書かれています。
ヤードバーズには悪いけどこの曲は「ジェフ・ベックの曲」、かな。
Tr2:Let Me Love You
(Jeffery Rod)
JB:ヘヴィな曲、素晴らしいタンバリンは
ミッキー・モストによるものだ。
ロッドの曲。いろんな状況で映える曲だよ。
作曲者の「ジェフリー・ロッド」とは
ジェフとロッドのことだと思われますが、
オリジナルLPの裏面部分には(Rod)としか記されておらず、
リマスター盤のブックレットにはこのよう書かれています。
なぜだろう、ちょっと不思議、ロッドへの感謝の念からかな。
ただしこれはモチーフをバディ・ガイの曲からいただいている、
と解説にありますが、当時の英国は、ブルーズの名曲に手を加えて
自作の曲として歌う悪しき流行があったようで、これもそうかな。
この曲は歌うには最高によいのですが・・・
ロッドは、歌に感情はこもっているけど、取り乱すこともなく
悠然と歌い続け、若くして既に凄味を感じます。
なお、ミッキー・モスト Micky Mostはプロデューサー。
Tr3:Morning Dew
(Rose - Dobson)
JB:ティム(・ローズ)のこの曲の素晴らしさはみんな知ってる。
だけど僕たちのもなかなか良くないかい。
作曲者のひとりでもあるティム・ローズのヒット曲で、
ジェフは彼への賛辞を送っています。
ただしこれは調べると、ジャンルとしてはフォークであるらしく、
ロッドのその後のカバー曲の選曲との共通性を考えると興味深い。
この空気感を表現できるロッドの素晴らしさに感動しますね。
ロッドの執拗なヴォーカルは、歩いても歩いても足に朝露が着く
草原を進まざるを得ないような感覚に陥ります(笑)。
ジェフの跳ねるようなギターの音もカッコいい。
Tr4:You Shook Me
(Dixon)
JB:むしゃくしゃした時に聴くための曲としてこれはおそらく、
最も適当かついいかげんに録音された曲じゃないかな。
最後の音は僕のギターだけど、きみたちが調子がよくない時に、
この2分28秒でやる気をくじいてくれたまえ。
これはレッド・ツェッペリンで先に聴きましたが、
Zepのそれを最初に聴いて僕は大爆笑してしまいました。
ここはジェフの話なのでそのことには触れないとして、
ジェフのこれは妙に小ぎれいにまとまっていると感じました。
オルガンはジョン・ポール・ジョーンズ。
ニッキーのピアノの高音の連弾も印象に残ります。
ウィリー・ディクソンはブルーズ系のロッカーから
最大限の尊敬の念を集めていた人ですね。
Tr5:O'l Man River
(Kern - Hammerstein II)
JB:アレンジは僕だけど、クレジットはみんなのもので、
ロッド・スチュワートはとりわけ素晴らしい。
これもまた最大音量で聴いてくれ。
白状します。
僕はずっと、オーティス・レディングのO'l Man Troubleと
この曲を混同していました、同じだと思っていました。
しかも、それをオーティスを真面目に聴くまでずっと、
だからつまり、昨年まで、そう思っていたのです・・・
調べるとこれは1920年代のミュージカルの中の曲ということで、
そんなに古い曲だったんだ。
じわじわと迫ってくる演奏が迫力ありますね。
キース・ムーンがわざわざティンパニーをやるだけあります。
これ、ほとんどソウルと言っていい雰囲気もあって、
ソウルっぽさを感じさせるのはロッドの持ち味かな。
今回、かなり奥深い曲だと再認識、再発見しました。
03 CDとハウのアウトテイク写真

Tr6:Greensleeves
(Trad arr. Jeffery Rod)
JB:ミッキー・モストのギターで演奏している。
エルヴィスとも同じものなんだ。
解説にはそのギターはGibson J-200と書いてあります。
ところで、ポール・マッカートニーはこれを聴いて、
Junkを作ることを思いついたのかなと思うことがあります。
違うかもしれないけど、雰囲気が似ています。
特に、McCARTNEYに収録されたオリジナルではなく、
UNPLUGGEDのバージョンは、メドレーで1曲にしたいくらい、
雰囲気以上に演奏も似ています。
なんて、結局はビートルズに言及するのか・・・(笑)・・・
話は逸れましたが、この曲はロックを聴く前から知っていて、
こうしたトラッドをロックで演奏しているのを聴くと、
若い頃は特にうれしくなりました。
Tr7:Rock My Primsoul
(Jeffery Rod)
JB:"Tallyman"のB面として録音していたが、こちらのほうが
オリジナルよりナチュラルな雰囲気でよくできている。
これも一応はオリジナルでも、B.B.キングのRock Me Baby
からいただいているということで、やはりちょっと複雑。
まあしかしこれは歌メロもいいし、素晴らしい曲ですね。
若い頃からよく口ずさんでいました。
ロッドも後にライヴで歌っています。
この曲のロッドのヴォーカルでひとつ思ったのは、
ハスキーヴォイスと言われますが、それと関係あるのかどうか、
ロッドは歌うと声がいい具合に微妙に欠けていることかな。
音が揺れるというべきか、声がただ伸びているのではなく、
作為的というよりは自然とそういう声になっている感じ。
Tr8:Beck's Bolero
(Page)
JB:これについてあまり多くは語れないな。
"(Hi Ho) Silver Lining"のB面と同じテイクで、言い訳になるが、
それ以上に良くすることはできなかったんだ。
トラッドに続いてクラシックの要素まであるなんて、
若い僕はこれを聴いてほんとに楽しかった(笑)。
ジミー・ペイジが作ったこの曲はインストゥルメンタルで、
ギターによるオーケストラといった趣の壮大な響きに
心をかきむしられ、引き込まれます。
ただこれ、音質がもう少し良ければもっと透明感があるのにな
と、昔から思っています。
逆にこの音質だから、喧騒を、時代を感じるのでしょうけど。
Tr9:Blues De Luxe
(Jeffery Rod)
JB:バートとスタンに感謝だ。
僕たちは、やろうとしていた「ライヴ」演奏のブルーズの
完璧なモデルを作ることができたが、ピアノソロについては
言わせてもらいたいことがある。
すいません、バートとスタンが誰かが分かりませんでした。
ピアノソロはニッキーで、ジェフの文章はここまでですが、
これは聴衆の拍手が入っていてライヴのように聴こえるけど、
実際はスタジオ録音で拍手は後から被せたものだそうです。
この曲もまた一応はオリジナルですが、やはり
B.B.キングのGambler's Bluesとよく似ている、ということ。
この辺りのルーツ感覚はジェフもロッドも同じだったのかな。
普通に演奏すればこの半分の時間で終わりそうなほど(笑)、
とにかくゆったりとした、とろい曲。
ロッドはやはり何を歌わせてもさまになっている、うん。
この曲の歌はこの中ではいちばん気持ちが入っていますね。
Tr10:I Ain't Superstitious
(Dixon)
JB:ハウリン・ウルフの古い曲からリフをいただいているけど、
彼は気にしていないよ、だって僕は彼に話をつけたから。
この曲はめくるめくギターが炸裂している、そのための曲だね。
これらの愛すべき曲が僕らの最初のLP、TRUTHさ。
ウィリー・ディクソンの曲にハウリン・ウルフのリフと
凝っているといえば凝っていますね。
ワウペダルを多投したまさにめくるめくギターワークには、
自然と気持ちが高揚してきます、ナチュラル・ハイ。
サイケデリックの影響もあるのでしょうか、時代ですね。
でも、アルバム全体ではそれほどサイケの影響は感じません。
だから僕が大好き、ともいえます。
実は最近、僕は、サイケがやや苦手だと分かってきました。
つまらない人間ですから、僕は(笑)。
この曲はもはやロックのマスターピースのひとつでしょう。
ジェフ・ベックの曲として語り継がれてゆくであろう曲。
アルバムの最後を、緊張感を持ってびしっと締めてくれます。
ううん、ギタリストのジェフ・ベックのアルバムで、
僕自身も一応はギターを弾く人間だというのに、
ロッドの話ばかりで終わってしまった感が・・・
ギターについては、ソロももちろんすごいけど、僕はやはり
バックの特に低音弦の音の動かし方がカッコいいと思います。
なんて、取ってつけたように感じられるかも・・・
1968年といえば、このアルバムの他に、
ジミ・ヘンドリックスのELECTRIC LADYLAND、
クリームのWHEELS OF FIREと、
ブルーズに大きく影響を受けたロックの名盤が
リリースされた年として記されています。
さらにはレッド・ツェッペリンもこの年に結成され、
1stが発表されたのは翌年ですがでも1月にリリースだから
この年に録音されていたわけで、考えてみればすごいですね、
こんなすごいアルバムが4枚も作られたなんて。
ちなみに僕が1歳の年ですね、覚えているわけがない(笑)。
こう書いていると、それらのアルバムも
記事に取り上げたくなってきましたよ。
2014年11月20日
BENT OUT OF SHAPE レインボー
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です
今日は先に写真のことを説明すると、
今朝起きて、札幌は一面の雪の世界に様変わりしていて、
その様子を何枚か撮影したのですが、
ただそのダイジェストだけで記事を上げるのではなく、
かねてから、雪が降ってから上げようと思っていた音楽記事に
雪景色の写真を練り込んでみた、というしだいです。
01 ただしこの写真だけ撮影はひと月ほど前、ペンタックスにて

BENT OUT OF SHAPE Rainbow
ストリート・オブ・ドリームス レインボー released in 1983
以前、りるっちさんの虹の記事において
自分は紫時代より虹時代のほうが好きですね。
確かに自分の名前を入れておられました(笑)。
Posted by GBKT at 2008年07月29日 17:19
>虹時代のほうが
えーーっ?!そうなのですか?
んーなんかぎたばさんがよいというと
よさそげだから、聞いてみようかなぁ。
Posted by りるっち at 2008年07月29日 19:28
あ、では、煽るつもりではないですが(笑)、
近々、虹のアルバム記事を上げます。
Posted by GBKT at 2008年07月29日 21:10
>あ、では
楽しみにお待ちしております♪
Posted by りるっち at 2008年07月29日 21:28
というやりとりをしていましたが、
それからもう4か月近くが経っているんですね。
でも、決して忘れていたわけではなく、
その時にすぐにこの記事を上げることを決めていたのですが、
これを上げる時期を待っていたというのが真相です。
その理由は、曲紹介のほうで話します。
02 庭のミズナラも葉の残りが僅か・・・

リッチー・ブラックモアはおそらく、
ハードロック/ヘヴィメタル界では最も偉大な人でしょうね。
ただ、そのことを話してゆくと記事が10個あっても足りないし、
100個書ける人も世の中にはたくさんいらっしゃるでしょうから、
ここでは、僕がそう思っている、ということだけお伝えします。
リッチー・ブラックモアは、もちろんすべて好きな方も多いですが、
ディープ・パープル時代とレインボー時代、
どちらが好きかでも割と分かれるのではないかと思います。
僕はレインボー派です。
パープルが嫌いなわけではなく、もちろん全アルバム聴いてますが、
思い入れというか、それはレインボーのほうがはるかに上です。
どうしてかなと考えると、これはあくまでも僕個人の感じ方ですが、
レインボーのほうが「歌」として親しみやすいから、です。
パープルの曲は「まず演奏がありそして歌がある」一方で、
レインボーは「歌と演奏が対等に近い位置にある」、そんな感じ。
「歌」が好きな僕は、だからレインボーのほうによりひかれるし、
実際、レインボーの曲はよく口ずさんでいます。
繰り返しですが、これはあくまでも僕が感じることです。
レインボーはさらに、ヴォーカルによる好みの違いもあるようです。
スタジオアルバム1から3枚目がロニー・ジェイムス・ディオ、
4枚目がグラハム・ボネット、5から7枚目がジョー・リン・ターナー。
でもやっぱり、正統派で、メタル界ではいちばん巧いと言われている
ディオがいちばん人気があるのかな、そうだろうなぁ。
ただ、ジョーリンは当時はアイドル的な人気もあったようで、
同じバンドだけど毛色が違うのは興味深いところです。
僕はジョーリンの時代のほうが好きですが、しかしこれは、
その時代のほうが僕が好きな「歌」が多いためであって、
必ずしもヴォーカリストとしてどうかという問題だけではありません。
しかし、歌メロを作るのはヴォーカリストの仕事の場合も多いので、
やっぱりヴォーカリストとしてもジョーリンのほうが好きなのかな。
ジョーリンは確かにカッコいいけど、映像で見る服のセンスに
少々、多少、難があるような気が・・・(笑)。
03 ポーラが尻尾を振っている

このアルバムの話をしましょう。
僕は最初、弟に、とにかくいいからといって「聴かされ」ました。
当時、パープルは聴いていましたが、
レインボーはまったく聴いていませんでした。
正直言います。
最初に聴いた時に、これほどの「拒否反応」を示したアルバムは、
それまでも、そしてそれからもなかったかもしれません。
とにかく、「なんだろう、これは・・・」と、戸惑いました。
あまりにも「もの暗い」雰囲気だったからであり、しかも、
一聴して、すべての曲がそんな雰囲気に支配されていて、
そこに戸惑った、そしてそれ以上の反応を示したのでしょう。
大袈裟に言えば、「どうにも逃れられない悩みを抱えてしまった」
そんな心境に陥ったのです。
でも、普通なら、それでまったく聴かなくなるものかもしれませんが、
しかしレインボーは、弟に強力にすすめられていたので、
それからも、「嫌だな」と思いながらも何度か聴きました。
「嫌だな」と思いながらも聴くというのも、普通は違うかもしれません。
僕は、ロックを少し「求道的」に捉えすぎているのかもしれません。
しかし僕は、ロックに関しては、
人が良いというものが自分は良くないと感じるのはなぜか、
それがどうして(そんなに)良いと言われているのか、
それをどうしても突き止めたい
という人間なので、「嫌」でも聴くことは結構あります。
それは自分の「感情」には正直ではないかもしれないですが、
悲しいかな、僕は、そういう人間なのです・・・(笑)。
そして補足、僕が今は「大好き」と言っているアルバムは
ほんとうに100%そう思っていて、それに偽りはありません。
でも、その中にも、かつてあまり好きではなかったアルバムは数多あり、
そういう聴き方をしてきたからこそ、もちろんすべてではないけど、
より多くの良いアルバムに出会えたのであって、だからそれでよかった、
と僕自身は思っています。
あくまでも、個人の聴き方の問題だと思ってください。
04 車も雪にくるまれて・・・

さて、このアルバムは、聴いてゆくうちに、
その「もの暗い」部分が良いと感じるようになったんです。
僕は、気持の振れ幅も大きい人間なのかもしれません(笑)。
この寂寥感、このどうしようもないくらいなロマンティックさ、
ナイーヴでメランコリックな世界。
このアルバムの音世界は、そこに凝縮されています。
そして、このアルバムについては、
それ以上はあまり書くことが思い浮かびません。
思い浮かばないのは、じゃあ良くないんじゃないか、
と思われるかもしれないですが、僕には時として、
曲でもアルバムでも、大好きなのにそういうことがままあります。
レインボーやリッチー・ブラックモアが、
ハードロック或いはヘヴィメタルという枠で語られる音楽である
というイメージで聴くと、これはかなり違います。
そして僕自身も、もっと強い、もっと(いい意味で)荒い音楽を期待し、
それとは違ったので、拒否反応を起こしただけなのでしょう。
実際、僕は弟の影響でHR/HM系も結構聴いていますが、
こんな独特の「音世界」を持つHR/HM系のアルバム、
他には思いつきません。
レインボー自身でも、曲や演奏の「感じ」は似ていても、
「音世界」に関しては、このアルバムだけ違います。
そして、僕がこれまで聴いてきた全ロックのアルバムでも、
これだけ独特の「音世界」を持ったアルバムは、
そうざらにはないでしょう。
音楽的な面で、リッチー以外で特筆すべきは、
キーボードのデイヴ・ローゼンタールの繰り出す音、
こんなにも情緒豊かで雰囲気を持ったキーボードはない、
と言えるくらいの素晴らしい仕事をしています。
05 アイーダは前に進むのを躊躇する・・・

Tr1:Stranded
ドキュメンタリー番組のテーマ曲のような緊張感あるギターでスタート。
このアルバムは最初の数秒で全体が見えるタイプで、
この世界がそのまま展開されてゆくことを予感させますね。
サビの部分の歌メロをサポートするギターフレーズが秀逸で、
巧いギタリストってやっぱり、ソロだけではなく、
バッキングのプレイも巧いということを再認識します。
Tr2:Can't Let You Go
レインボー後期の名曲、名バラード。
ジョーリンの歌心がよく伝わってきます。
自分で歌っていてもいい歌だなと思いますし(笑)。
レインボーには、哀愁系というか、
昭和の歌謡曲っぽい曲が結構ありますが、
これなんかその代表例のひとつでしょうね。
日本で大いに受け理由のひとつも、それだと思います。
なお、この曲のビデオクリップを後に見たのですが、
ジョーリンが吸血鬼になって夜を徘徊するという物語仕立てで、
彼らもそんなことやってたんだ、と、MTV時代を感じましたね(笑)。
Tr3:Fool For The Night
ハードだけどロマンティックな曲の代表。
サビの前の部分の、やはり歌メロをサポートするギターが
ロマンティックな雰囲気を盛り上げています。
歌メロもいいし、歌い方もいいし、言うことないですね。
Tr4:Fire Dance
軽快な曲調にほの暗い歌メロ、メランコリックな狂おしい曲。
タイトルのイメージ通り、そしてさらに想像を掻き立てる。
もうこの世界に足を踏み入れたら抜け出せない・・・
やっぱり、ジョーリンの声だから出来た音世界でしょうね。
Tr5:Anybody There
このアルバム、LPでいうA面B面に1曲ずつ
インストゥルメンタル曲が入っていますが、これはその1曲目。
といいつつ、ヴォーカルがなくても同じ音世界だなぁ(笑)。
ゆったりとしていて、つなぎ以上に聴きどころがある曲。
06 雪が降るとおなじみ「ナナカマドの綿帽子」

Tr6:Desperate Heart
リッチーは後年、トラッド路線に進んで良い作品を残しますが、
後から振り返ると、その下地がよく見える曲。
トラッド風の軽やかなアコースティックギターのイントロで始まり、
ジョーリンの声がぐいぐいと引っ張り、キーボードがタイミングよく入り、
それを手堅くまとめている。
トラッドとロックがかなり高次元で融合した、隠れた名曲だと思います。
Tr7:Street Of Dreams
もう1曲の後期の名曲、名バラード。
このアルバムの邦題は、この曲名になっているくらいですから。
Tr2と同じといえば同じような雰囲気で、正直いえば、
最初の頃はどっちがどっちか分からなかったんですが(笑)、
名曲が2曲も入っていることからも、充実ぶりがうかがえます。
ちなみに、どっちが好きかでよく弟ともめます(笑)。
ロマンティックな曲ですが、やり過ぎていないのがまた味があります。
この曲のビデオクリップは、若い男性が主人公で、
姿を消してしまった彼女が夢の中で呼んでいるというものですが、
最後にちょっとしたオチがあって彼女が救わるという、
やはり物語仕立てになっています。
Tr8:Drinking With The Devil
うんうん、確かに悪酔いしてる(笑)。
アルバムではいちばん素軽いロックンロール。
でもやっぱり、どこか陰りと湿り気と重さが。
カッコいい曲ではあります。
Tr9:Snowman
この曲があるので、このアルバムは冬に紹介したいと思いました。
これはインストの2曲目、確かにほの暗さはあるんだけど、
ほのぼのとした、雪なのに暖かいイメージの曲。
僕は最初にこれを聴いた時、
へえ、リッチーってこんなことも出来るんだ、と、いたく感激し、
それまでよりも3段階くらいリッチーへの敬意が増しました。
インスト2曲も充実していますし、だからキーボードが重要でもあります。
これからの時期にはぐっとくる曲ですね。
Tr10:Make Your Move
ラストもほの暗いながらも素軽いロックンロールで、Tr8と似た曲。
リッチーのアルバムには、よい意味で気が抜けた
素軽くポップなロックンロール系の曲が意外と多いのですが、
このアルバムの場合は、この2曲の意味も大きいのではないかと。
前にも書きましたが、こういう言い方もなんですが、この曲はまあ、
好きな人には申し訳ないですが、それほど好きではありません。
でも、アルバムのすべてが名曲だとかえって疲れてしまいますし、
流れの中にメリハリがあるからこそアルバムとして聴けるのであって、
だからこうした曲は、それはそれで存在意義はあると僕は考えます。
このアルバムについては、このラストがあまりにもあっさりしているので、
逆にすぐにまた聴きたくもなりますし(笑)。
※CDのジャケット写真

BENT OUT OF SHAPE レインボー リンクはこちら
Amazonのこの商品・国内通常盤のリンクにはなぜか写真がないので、
今回、写真だけはうちにある同内容の輸入盤のものを使いました。
なお、この写真と01の写真では
ジャケットのアートワークが微妙に違いますが、
01のものは、最近出たSHM-CD盤です、ご了承ください。
このアルバムのジャケットは素晴らしいですね。
僕が好きなジャケット上位50枚に余裕で入ると思います。
さて、このアルバムをこのタイミングで紹介した理由が
もうひとつあるんです。
ビリー・ジョエル東京公演が終わったばかりですが、
そのコンサートに参加していたミュージシャンのうち、
キーボードのデイヴ・ローゼンタールと
ドラムスのチャック・バーギの2人が、
この時点でのレインボーのメンバーであり、
もちろんこのアルバムにも参加しているからです。
この2人は前回の日本ツアーで、僕が札幌ドームで観た時にも
参加していたので、ビリーにも重要なメンバーということですね。
なお余談、ここでの2人の苗字のカタカナ表記は、
日本での一般的なものにならいましたが、
ビリーは、「ローゼンタール」Rosenthalを「ローゼンソル」、
「バーギ」Burgiを「バージ」を発音していました。
こう書くと、ビリーと近いものがあるのかな、
そういえばビリーのハードな面の曲に近い感じがするかも・・・
と思うかどうかは、聴く方次第です、念のため(笑)。
しかし、僕がこのアルバムをより大好きになった理由は
お分かりになるかと思います(笑)。
音楽は、それ自身のみならず、それを取り巻く事実、
例えば友達が好きだからといった付加価値があるのも、
また楽しい部分ですよね。
07 ハウと雪の上の落ち葉、まるで「立ち会い」・・・

雪の季節が始まりました。
写真へのコメントも
大歓迎です
今日は先に写真のことを説明すると、
今朝起きて、札幌は一面の雪の世界に様変わりしていて、
その様子を何枚か撮影したのですが、
ただそのダイジェストだけで記事を上げるのではなく、
かねてから、雪が降ってから上げようと思っていた音楽記事に
雪景色の写真を練り込んでみた、というしだいです。
01 ただしこの写真だけ撮影はひと月ほど前、ペンタックスにて

BENT OUT OF SHAPE Rainbow
ストリート・オブ・ドリームス レインボー released in 1983
以前、りるっちさんの虹の記事において
自分は紫時代より虹時代のほうが好きですね。
確かに自分の名前を入れておられました(笑)。
Posted by GBKT at 2008年07月29日 17:19
>虹時代のほうが
えーーっ?!そうなのですか?
んーなんかぎたばさんがよいというと
よさそげだから、聞いてみようかなぁ。
Posted by りるっち at 2008年07月29日 19:28
あ、では、煽るつもりではないですが(笑)、
近々、虹のアルバム記事を上げます。
Posted by GBKT at 2008年07月29日 21:10
>あ、では
楽しみにお待ちしております♪
Posted by りるっち at 2008年07月29日 21:28
というやりとりをしていましたが、
それからもう4か月近くが経っているんですね。
でも、決して忘れていたわけではなく、
その時にすぐにこの記事を上げることを決めていたのですが、
これを上げる時期を待っていたというのが真相です。
その理由は、曲紹介のほうで話します。
02 庭のミズナラも葉の残りが僅か・・・

リッチー・ブラックモアはおそらく、
ハードロック/ヘヴィメタル界では最も偉大な人でしょうね。
ただ、そのことを話してゆくと記事が10個あっても足りないし、
100個書ける人も世の中にはたくさんいらっしゃるでしょうから、
ここでは、僕がそう思っている、ということだけお伝えします。
リッチー・ブラックモアは、もちろんすべて好きな方も多いですが、
ディープ・パープル時代とレインボー時代、
どちらが好きかでも割と分かれるのではないかと思います。
僕はレインボー派です。
パープルが嫌いなわけではなく、もちろん全アルバム聴いてますが、
思い入れというか、それはレインボーのほうがはるかに上です。
どうしてかなと考えると、これはあくまでも僕個人の感じ方ですが、
レインボーのほうが「歌」として親しみやすいから、です。
パープルの曲は「まず演奏がありそして歌がある」一方で、
レインボーは「歌と演奏が対等に近い位置にある」、そんな感じ。
「歌」が好きな僕は、だからレインボーのほうによりひかれるし、
実際、レインボーの曲はよく口ずさんでいます。
繰り返しですが、これはあくまでも僕が感じることです。
レインボーはさらに、ヴォーカルによる好みの違いもあるようです。
スタジオアルバム1から3枚目がロニー・ジェイムス・ディオ、
4枚目がグラハム・ボネット、5から7枚目がジョー・リン・ターナー。
でもやっぱり、正統派で、メタル界ではいちばん巧いと言われている
ディオがいちばん人気があるのかな、そうだろうなぁ。
ただ、ジョーリンは当時はアイドル的な人気もあったようで、
同じバンドだけど毛色が違うのは興味深いところです。
僕はジョーリンの時代のほうが好きですが、しかしこれは、
その時代のほうが僕が好きな「歌」が多いためであって、
必ずしもヴォーカリストとしてどうかという問題だけではありません。
しかし、歌メロを作るのはヴォーカリストの仕事の場合も多いので、
やっぱりヴォーカリストとしてもジョーリンのほうが好きなのかな。
ジョーリンは確かにカッコいいけど、映像で見る服のセンスに
少々、多少、難があるような気が・・・(笑)。
03 ポーラが尻尾を振っている

このアルバムの話をしましょう。
僕は最初、弟に、とにかくいいからといって「聴かされ」ました。
当時、パープルは聴いていましたが、
レインボーはまったく聴いていませんでした。
正直言います。
最初に聴いた時に、これほどの「拒否反応」を示したアルバムは、
それまでも、そしてそれからもなかったかもしれません。
とにかく、「なんだろう、これは・・・」と、戸惑いました。
あまりにも「もの暗い」雰囲気だったからであり、しかも、
一聴して、すべての曲がそんな雰囲気に支配されていて、
そこに戸惑った、そしてそれ以上の反応を示したのでしょう。
大袈裟に言えば、「どうにも逃れられない悩みを抱えてしまった」
そんな心境に陥ったのです。
でも、普通なら、それでまったく聴かなくなるものかもしれませんが、
しかしレインボーは、弟に強力にすすめられていたので、
それからも、「嫌だな」と思いながらも何度か聴きました。
「嫌だな」と思いながらも聴くというのも、普通は違うかもしれません。
僕は、ロックを少し「求道的」に捉えすぎているのかもしれません。
しかし僕は、ロックに関しては、
人が良いというものが自分は良くないと感じるのはなぜか、
それがどうして(そんなに)良いと言われているのか、
それをどうしても突き止めたい
という人間なので、「嫌」でも聴くことは結構あります。
それは自分の「感情」には正直ではないかもしれないですが、
悲しいかな、僕は、そういう人間なのです・・・(笑)。
そして補足、僕が今は「大好き」と言っているアルバムは
ほんとうに100%そう思っていて、それに偽りはありません。
でも、その中にも、かつてあまり好きではなかったアルバムは数多あり、
そういう聴き方をしてきたからこそ、もちろんすべてではないけど、
より多くの良いアルバムに出会えたのであって、だからそれでよかった、
と僕自身は思っています。
あくまでも、個人の聴き方の問題だと思ってください。
04 車も雪にくるまれて・・・

さて、このアルバムは、聴いてゆくうちに、
その「もの暗い」部分が良いと感じるようになったんです。
僕は、気持の振れ幅も大きい人間なのかもしれません(笑)。
この寂寥感、このどうしようもないくらいなロマンティックさ、
ナイーヴでメランコリックな世界。
このアルバムの音世界は、そこに凝縮されています。
そして、このアルバムについては、
それ以上はあまり書くことが思い浮かびません。
思い浮かばないのは、じゃあ良くないんじゃないか、
と思われるかもしれないですが、僕には時として、
曲でもアルバムでも、大好きなのにそういうことがままあります。
レインボーやリッチー・ブラックモアが、
ハードロック或いはヘヴィメタルという枠で語られる音楽である
というイメージで聴くと、これはかなり違います。
そして僕自身も、もっと強い、もっと(いい意味で)荒い音楽を期待し、
それとは違ったので、拒否反応を起こしただけなのでしょう。
実際、僕は弟の影響でHR/HM系も結構聴いていますが、
こんな独特の「音世界」を持つHR/HM系のアルバム、
他には思いつきません。
レインボー自身でも、曲や演奏の「感じ」は似ていても、
「音世界」に関しては、このアルバムだけ違います。
そして、僕がこれまで聴いてきた全ロックのアルバムでも、
これだけ独特の「音世界」を持ったアルバムは、
そうざらにはないでしょう。
音楽的な面で、リッチー以外で特筆すべきは、
キーボードのデイヴ・ローゼンタールの繰り出す音、
こんなにも情緒豊かで雰囲気を持ったキーボードはない、
と言えるくらいの素晴らしい仕事をしています。
05 アイーダは前に進むのを躊躇する・・・

Tr1:Stranded
ドキュメンタリー番組のテーマ曲のような緊張感あるギターでスタート。
このアルバムは最初の数秒で全体が見えるタイプで、
この世界がそのまま展開されてゆくことを予感させますね。
サビの部分の歌メロをサポートするギターフレーズが秀逸で、
巧いギタリストってやっぱり、ソロだけではなく、
バッキングのプレイも巧いということを再認識します。
Tr2:Can't Let You Go
レインボー後期の名曲、名バラード。
ジョーリンの歌心がよく伝わってきます。
自分で歌っていてもいい歌だなと思いますし(笑)。
レインボーには、哀愁系というか、
昭和の歌謡曲っぽい曲が結構ありますが、
これなんかその代表例のひとつでしょうね。
日本で大いに受け理由のひとつも、それだと思います。
なお、この曲のビデオクリップを後に見たのですが、
ジョーリンが吸血鬼になって夜を徘徊するという物語仕立てで、
彼らもそんなことやってたんだ、と、MTV時代を感じましたね(笑)。
Tr3:Fool For The Night
ハードだけどロマンティックな曲の代表。
サビの前の部分の、やはり歌メロをサポートするギターが
ロマンティックな雰囲気を盛り上げています。
歌メロもいいし、歌い方もいいし、言うことないですね。
Tr4:Fire Dance
軽快な曲調にほの暗い歌メロ、メランコリックな狂おしい曲。
タイトルのイメージ通り、そしてさらに想像を掻き立てる。
もうこの世界に足を踏み入れたら抜け出せない・・・
やっぱり、ジョーリンの声だから出来た音世界でしょうね。
Tr5:Anybody There
このアルバム、LPでいうA面B面に1曲ずつ
インストゥルメンタル曲が入っていますが、これはその1曲目。
といいつつ、ヴォーカルがなくても同じ音世界だなぁ(笑)。
ゆったりとしていて、つなぎ以上に聴きどころがある曲。
06 雪が降るとおなじみ「ナナカマドの綿帽子」

Tr6:Desperate Heart
リッチーは後年、トラッド路線に進んで良い作品を残しますが、
後から振り返ると、その下地がよく見える曲。
トラッド風の軽やかなアコースティックギターのイントロで始まり、
ジョーリンの声がぐいぐいと引っ張り、キーボードがタイミングよく入り、
それを手堅くまとめている。
トラッドとロックがかなり高次元で融合した、隠れた名曲だと思います。
Tr7:Street Of Dreams
もう1曲の後期の名曲、名バラード。
このアルバムの邦題は、この曲名になっているくらいですから。
Tr2と同じといえば同じような雰囲気で、正直いえば、
最初の頃はどっちがどっちか分からなかったんですが(笑)、
名曲が2曲も入っていることからも、充実ぶりがうかがえます。
ちなみに、どっちが好きかでよく弟ともめます(笑)。
ロマンティックな曲ですが、やり過ぎていないのがまた味があります。
この曲のビデオクリップは、若い男性が主人公で、
姿を消してしまった彼女が夢の中で呼んでいるというものですが、
最後にちょっとしたオチがあって彼女が救わるという、
やはり物語仕立てになっています。
Tr8:Drinking With The Devil
うんうん、確かに悪酔いしてる(笑)。
アルバムではいちばん素軽いロックンロール。
でもやっぱり、どこか陰りと湿り気と重さが。
カッコいい曲ではあります。
Tr9:Snowman
この曲があるので、このアルバムは冬に紹介したいと思いました。
これはインストの2曲目、確かにほの暗さはあるんだけど、
ほのぼのとした、雪なのに暖かいイメージの曲。
僕は最初にこれを聴いた時、
へえ、リッチーってこんなことも出来るんだ、と、いたく感激し、
それまでよりも3段階くらいリッチーへの敬意が増しました。
インスト2曲も充実していますし、だからキーボードが重要でもあります。
これからの時期にはぐっとくる曲ですね。
Tr10:Make Your Move
ラストもほの暗いながらも素軽いロックンロールで、Tr8と似た曲。
リッチーのアルバムには、よい意味で気が抜けた
素軽くポップなロックンロール系の曲が意外と多いのですが、
このアルバムの場合は、この2曲の意味も大きいのではないかと。
前にも書きましたが、こういう言い方もなんですが、この曲はまあ、
好きな人には申し訳ないですが、それほど好きではありません。
でも、アルバムのすべてが名曲だとかえって疲れてしまいますし、
流れの中にメリハリがあるからこそアルバムとして聴けるのであって、
だからこうした曲は、それはそれで存在意義はあると僕は考えます。
このアルバムについては、このラストがあまりにもあっさりしているので、
逆にすぐにまた聴きたくもなりますし(笑)。
※CDのジャケット写真

BENT OUT OF SHAPE レインボー リンクはこちら
Amazonのこの商品・国内通常盤のリンクにはなぜか写真がないので、
今回、写真だけはうちにある同内容の輸入盤のものを使いました。
なお、この写真と01の写真では
ジャケットのアートワークが微妙に違いますが、
01のものは、最近出たSHM-CD盤です、ご了承ください。
このアルバムのジャケットは素晴らしいですね。
僕が好きなジャケット上位50枚に余裕で入ると思います。
さて、このアルバムをこのタイミングで紹介した理由が
もうひとつあるんです。
ビリー・ジョエル東京公演が終わったばかりですが、
そのコンサートに参加していたミュージシャンのうち、
キーボードのデイヴ・ローゼンタールと
ドラムスのチャック・バーギの2人が、
この時点でのレインボーのメンバーであり、
もちろんこのアルバムにも参加しているからです。
この2人は前回の日本ツアーで、僕が札幌ドームで観た時にも
参加していたので、ビリーにも重要なメンバーということですね。
なお余談、ここでの2人の苗字のカタカナ表記は、
日本での一般的なものにならいましたが、
ビリーは、「ローゼンタール」Rosenthalを「ローゼンソル」、
「バーギ」Burgiを「バージ」を発音していました。
こう書くと、ビリーと近いものがあるのかな、
そういえばビリーのハードな面の曲に近い感じがするかも・・・
と思うかどうかは、聴く方次第です、念のため(笑)。
しかし、僕がこのアルバムをより大好きになった理由は
お分かりになるかと思います(笑)。
音楽は、それ自身のみならず、それを取り巻く事実、
例えば友達が好きだからといった付加価値があるのも、
また楽しい部分ですよね。
07 ハウと雪の上の落ち葉、まるで「立ち会い」・・・

雪の季節が始まりました。
2014年07月16日
WHITESNAKE 「白蛇の紋章」
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です!
メタルの話題が続きますが、今夜は、
僕が最初に買った「真性ヘヴィメタル」のアルバム。
01

WHITESNAKE Whitesnake released in 1987
サーペンス・アルバス~白蛇の紋章~ ホワイトスネイク
いまさら何を言わんかという超名盤ですね。
だから、あまり言うこともないですかね(笑)。
ホワイトスネイクこのアルバムが大ブレイクしたこともあって、
当時、ヘヴィメタル時代が本格的に訪れました。
今思い出すと、信じられない世の中でしたし、
当時から「普通のロック」を聴いてきた僕も、不思議でした。
それにしても、当時のへヴィメタのアルバムを今見ると、
「まりもパーマ」は、やっぱり、笑ってしまいますね・・・
当時は真面目だったのでしょうけど、時代の恐ろしさも感じます。
そういえば、アフロは最近復権しましたが、
「まりもパーマ」は復権しないのでしょうかね・・・
このアルバムがブレイクした仕掛け人は、
ジョン・カロドナーなる人物。
この人、当時はGEFFENレコードの重役で、
「落ち目」になった、或いは「いまいち」のアーティストを
「ホンモノ」に仕立て上げて売り出し、次々と成功させた人。
これと前後して、一度は中心人物のジョー・ペリーが脱退し
「死に体」だったエアロスミスも大復活させています。
先日少し逸れて、ジョン・カロドナーの哲学というのを、
以前雑誌で読みましたが、
「とにかく声がいいヴォーカリストを用意すること」、だとか。
それ以外の要素はどうにでもなるけど、
声だけは何物にも代え難い、というわけ。
ホワイトスネイクのVoデヴィッド・カヴァデイルは、
元ディープ・パープルでもありますが、
彼の声の良さは、既に折り紙つきでしたが、
彼本来の音楽的趣向のおかげか、渋くて玄人受けする音楽を
ソロになってからは繰り広げていました。
ホワイトスネイクの場合、アメリカでは「いまいち」だったのを、
彼が大仕掛けをして、大成功したというわけですが、
その「大仕掛け」というのは・・・ずばり、
「ツェッペリンっぽい音」(・・・ぱくり・・・!?)
当時、レッド・ツェッペリンは既になく、音楽市場に、
「ツェッペリンっぽい音」というのものが空白のまま残っていた、
そんな時代で、そこを狙っての大仕掛けが、まんまと大成功。
ただ、僕自身は、これより前にZepは聴いていましたが、
これを最初に聴いて、それほどツェッペリンぽいとは感じず、
数年して、このアルバムが過去のものとして話題になった頃に
ようやくそのことを指摘されて気づきました。
それは僕が鈍かっただけなのかもしれないですが、
でも、そうですね、ぱくりとかそういうことではなく、
これはこれとして「新しい音楽」として接していました。
元々、あまり批評的な耳は持っていなかったのでしょう、僕は(笑)。
02 ノリウツギ (ユキノシタ科)

それはともかく、このアルバムの充実度は誰もが認めるところ。
先日、たまたま引っ張り出してきて聴き、記事にしようと決めてからは、
毎日聴かないと気が済まないくらいになってますし(笑)。
このアルバム、レコーディングではジョン・サイクスがギターを担当し、
かなりいい仕事をしていますが、彼はレコーディング後に解雇され、
代わって呼び集められたのが、名うてのテクニシャンばかり。
エイドリアン・ヴァンデンバーグ Gt(元ヴァンデンバーグ)
ヴィヴィアン・キャンベル Gt(元ディオ、現デフ・レパード)
ルディ・サーゾ Bs(元オジー・オズボーン)
トミー・アルドリッジ Ds(元オジー・オズボーン)
当時は「スーパーグループ」として話題を集め、
このメンバーでツアーに出ましたが、
僕のメタル好きの友達は狂喜乱舞していました。
そして、当時は若い女性にも人気が高く、
コンサートでは「えいどりあぁ~ん」という黄色い歓声が聞こえ、
古くからのファンは「うるさい」と言っていました・・・(笑)。
もっとも、僕も、このアルバムからファンになったので、
古くからのファンには、うっとうしく映っていたでしょうけど・・・
★名曲★・・・ロック史に残る名曲
★ヒット★・・・シングルヒットした曲
★佳曲★・・・通好みの味がある曲
★秘宝★・・・埋もれておくには惜しい隠れた名曲
★カッコいい★・・・ひたすらカッコいい曲
★注目★・・・話題作、問題作、とにかく注目すべき曲
★映画★・・・映画やテレビ番組で使われた曲
★CM★・・・CMで使われた曲
★GB★・・・guitarbird個人の思いが強い曲
03 オニシモツケ (バラ科)

Tr1:Crying In The Rain
★佳曲★★カッコいい★
この曲を最初に聴いて、ビートルズのYer Bluesを思い浮かべました。
Yerは当時のブリティッシュ・ブルーズを茶化したものですが、
つながっていますね、ブリティッシュ・ハードロックは。
僕は実は、Yer Bluesを最初に聴いた時から、なんというか、
存在感が違ったんですよね。
さらにいえばホワイトアルバムのC面はハードな曲のオンパレードで、
しかもその間に、落ち着いたアコースティックな曲が入っているのが
大好きでした。
それはともかく、ビートルズのおかげでこの曲は一発で好きになり、
ホワイトスネイクが、ハードロックが、そしてヘヴィメタルが
一気に身近に感じた、そんな曲でした。
なおこの曲、以前のアルバムに収録されていた曲の再録音です。
Tr2:Bad Boys
★カッコいい★
冒頭のデヴィカヴァの叫びが、それまで僕が聴いてきた世界と違うことを
はっきりと認識しました。
これはロックンロールなのか?と悩みました。
ヴァースからサビに移る前の部分のギターのバッキングが
当時からかっこいいと思ってました。
Tr3:Still Of The Night
★名曲★★カッコいい★★注目★
このアルバムが「ツェッペリンのぱくり」と言われていたことを、
最も顕著に表わしている曲。
この曲のビデオクリップでは、かつてジミー・ペイジがやっていた、
エイドリアンがギターをヴァイオリンの弓で弾くシーンもありますが、
当時はZepの映像をほとんど観たことがなくて、
それがペイジの真似であることを知らなかったのです。
だから、僕が気づくまでに数年かかったんですが・・・(笑)。
それはともかく、ツェッペリンぽい音を出すといったところで、
そんじょそこらのバンドが出来るわけではないでしょうし、
ツェッペリンっぽい音へのニーズはかなりあったものの、
それっぽい「ホンモノの」音を出せるバンドはいなかった。
彼らはそこに挑んで、ある意味期待以上のものを作り上げた、
という感じなのではないでしょうか。
なんて書くと、さっきから僕はまるで批判しているみたいですが、
そんなことはなく、僕にとってはそれは枝葉の部分に過ぎません。
が、ロックが時代を映した音である以上、
その部分を無視して話をすることはできないので、
先ほどからそこにこだわっているのです(ご了承ください)。
いや、この曲は大好きですよ、ほんとに。
凄い曲、という言葉がまさにぴったりの、奇跡的名曲。
究極に進化したブルーズという感じですね、ほんと凄い!
ギターリフがちょっとだけ「移民の歌」っぽかったり・・・
あ、まだ言うか(笑)。
04 アマニュウ (セリ科)

Tr4:Here I Go Again
★名曲★★ヒット★★GB★
この曲も、かつてのアルバムを再録音したもの。
良いアルバム作りに、新しいマテリアルだけでは不足であると
関係者は感じたのでしょうか。
事実、この曲については、再録音したことにより
「隠れた名曲」から、「真の名曲」に進化を遂げました。
この曲を聴いて、ビデオクリップを観て、
このアルバムを買うことを決意しました。
バラードでありながらヘヴィメタル。
そんな曲があるなんて、想像すらしていませんでした。
おまけにこの曲は歌詞が素晴らしくて、
ビートルズ以外で最も歌詞が好きな曲でもあります。
そして、歌詞を読んでいると、
オーティス・レディングのかの名曲The Dock Of The Bayの
「裏と表」という感じがしてきます。
どちらも、追い詰められたというか、
でもオーティスはそんな自分に浸っている、
一方でこちらは、そんな自分から脱しようと前向きになる・・・
ちなみに、デヴィカヴァは、このビデオで共演している
女性と後に結婚しました(がさらに後に離婚しました)が、
このビデオは激しく絡むシーンなどもあり、
「私物化するな」と当時は言われていました(笑)。
この曲は、1980年代でも十指に入る好きな曲ですし、ひいては、
僕のロック人生の中でも、きわめて重要な出会いをした、
そんな曲でもあります。
導入部がソフトで、サビは盛り上がる展開という、
ヘヴィメタルの基本形を教えてもくれましたし
Tr5:Give Me All Your Love
★佳曲★
これはロックンロールというのだろうか、と悩んだ曲・・・
曲自体は、メロディも進行も割合単純なのですが、
圧倒的なクオリティでまっすぐに聴かせる、
ブリティッシュハードロックの王道路線。
Tr6:Is This Love
★名曲★★ヒット★
これは明らかに「売れ線狙い」で、それが見事に成功した曲。
当時は「メタルバラード」なるものが広まりつつある頃で、
ビルボードNO.1にもなったこの曲、その決定版という感じでしょうか。
ただ、僕はこのアルバムの直後の来日公演を
代々木に観に行き、そこでこの曲も演奏したのですが、
アレンジがAORっぽく、大好きだったものの期待外れでした。
デヴィカヴァ自身もあまり気に入ってないように見えましたし・・・
それと、このアルバムでこの曲は少し浮いていますが、
後々の彼らのアルバムを聴くと、むしろこの路線に近づいていた
つまり根の部分では彼ららしい曲だったんだ、ということに
つい最近気づきました(笑)。
ともあれ、レコードとして聴くと、やはり名曲には違いないですね。
05 ヤマブキショウマ (バラ科)

Tr7:Children Of The Night
これはTr2とそっくり(笑)。
実際、ライヴでは、Tr2とこれを混ぜて1曲にして演奏していますし。
いかにもメタル的イディオムというものも、ここで学びました。
なお、僕個人としては、当時から、このアルバムは、
ここから急にトーンダウンするというか、それまでの
異様なまでのハイテンションから解放されたように感じていました。
この曲自体は緊迫感がある系ですが、似た曲、ということで
こちら側の緊迫感は溶けてゆくのを感じます。
ただし、これ以降がよくないのではなく、
この前までがあまりにも充実していて凄すぎるだけですが。
Tr8:Straight For The Heart
★カッコいい★
これは最初からロックンロールだと思ってました(笑)。
誰が聴いてもそう思うのではないかと。
そしてこれは最初に気に入りました。
ただ、後から知ったのですが、この曲は、
前のアルバムに入っている曲の「二番煎じ」であるらしく、
事実、後から、その前のアルバムを聴いて、なるほど、と。
まあ、それはともかく、軽やかなロックンロールで、
これはむしろ、トーンダウンしたことにより、
それまで「普通のロック」を聴いてきた僕が
すんなりと受け入れれたんだと思いますし、この曲があったから、
アルバム自体への親近感もすぐに増したのだと思います。
イントロのギターの音がTr3とまったく同じなのは、
遊び心も感じられ、緊張感がいいほうに緩む曲でもあります。
それからこの曲は、ギターのバッキング演奏の勉強には
とってもいい曲ですね。
今聴いても、カッコよすぎる!
Tr9:Don't Turn Away
★注目★
最後のこの曲、僕は昔からずっと引っかかっています・・・
この曲だけ、AORとまではゆかない、ソフト、は言いすぎだけど、
なんというか、肩の力が抜けすぎている曲であり、
ここまでの流れを自分たちの手でぶち壊す、という感じもします。
ま、それが「ロック」としてのユーモアなのかもしれないですが。
断っておきますが、曲自体はとってもいいし、大好きです。
でも、今回聴いても、やっぱり違和感が、ないでもない・・・
メタル愛の弟は、特に気になっていないようなので、
これは多分に僕の思いすごしかもしれないですが。
このアルバム、不思議なことに、
国内盤では国内でリマスターされたものが再発されましたが、
海外では、1987年当時に出たものが、まだカタログで残っています。
だからこのCD、音量がかなり小さいですね。
なお、国内盤のタイトルである「サーペンス・アルバス」とは、
このジャケットの紋章にSERPENS ALBUSと彫られており、
それがタイトルになったもので、日本ではそれで定着しています。
確かに、ホワイトスネイク、よりは愛着が湧きそうですし。
そうそう、僕が最初に買ったという話がまだでした。
大学1年の時、Tr4がヒットしていたのを聴いたのですが、
その曲がいいと思った自分がしゃくに障りました・・・
というのも当時、へヴィメタが好きな友達が、
普通のロックをことごとくバカにしていて、それが気に食わず、
意地になって買わないと言い張っていたので、
おいそれと「好きだ」とも言えないし、
仮に買ったとしても、それがバレるのも気持ちがよくないし。
でも、やっぱりいい曲だ・・・
かなり悩みました。
自分の耳に素直になってみると、
このアルバムは聴きたい、欲しい、という思いが強くなり、
やがて、それに抗うことが出来なくなりました。
そしてついに、夏休みで札幌に帰っていて、東京に戻る直前の日に、
今は別の場所に移転した、最初のタワー・レコード札幌店に
弟と出向いて、買いました。
でも、やっぱり最後まで素直にはなれなくて、
弟にレジに行ってもらいました(お金は僕が出しましたもちろん)。
買って聴いてみると・・・予想、期待、想像以上に良かったです。
その時、友達に対して意地を張っていた自分がバカだった・・・
と反省し、それ以降、メタル系も含めて、
聴いたことがないアーティストのCDを積極的に買うことにしました。
そのようなわけで、
僕の中でもかなり重要なアルバムです。
だから、余計に、愛情の裏返しで、
ツェッペリンっぽい、とおちょくっていたのです(笑)。
そして、このアルバムも、BLOGを始めてから、
いつかは記事にしようと思っていた1枚です。
繰り返しますが、だからといって
BLOGをやめはしませんよ(笑)。
そういえば今年、彼らの新作が出たんですよね。
こちら、良くも悪くも、相変わらず、という感じで、
このアルバムのマジックがかろうじて残っている、かな・・・
音的にはむしろそれ以前の渋みがある曲で、
なかなかいいとは思います。
でも、記事に出来るほど聴き込んではいませんでした・・・
なので代わりに、このアルバム、というわけでもないんですが。
最後にもうひとつ、その、意地を張っていたメタル好きの友達とは
その後「和解」し、一緒にコンサートに行きました。
今回の写真は、
ホワイトスネイクだから「白い蛇」・・・の写真は撮れなかったので、
ここ数日で撮った「白い花」の写真を集めてみました。
06 岩の崖一面に咲くフランスギク

写真へのコメントも
大歓迎です!
メタルの話題が続きますが、今夜は、
僕が最初に買った「真性ヘヴィメタル」のアルバム。
01

WHITESNAKE Whitesnake released in 1987
サーペンス・アルバス~白蛇の紋章~ ホワイトスネイク
いまさら何を言わんかという超名盤ですね。
だから、あまり言うこともないですかね(笑)。
ホワイトスネイクこのアルバムが大ブレイクしたこともあって、
当時、ヘヴィメタル時代が本格的に訪れました。
今思い出すと、信じられない世の中でしたし、
当時から「普通のロック」を聴いてきた僕も、不思議でした。
それにしても、当時のへヴィメタのアルバムを今見ると、
「まりもパーマ」は、やっぱり、笑ってしまいますね・・・
当時は真面目だったのでしょうけど、時代の恐ろしさも感じます。
そういえば、アフロは最近復権しましたが、
「まりもパーマ」は復権しないのでしょうかね・・・
このアルバムがブレイクした仕掛け人は、
ジョン・カロドナーなる人物。
この人、当時はGEFFENレコードの重役で、
「落ち目」になった、或いは「いまいち」のアーティストを
「ホンモノ」に仕立て上げて売り出し、次々と成功させた人。
これと前後して、一度は中心人物のジョー・ペリーが脱退し
「死に体」だったエアロスミスも大復活させています。
先日少し逸れて、ジョン・カロドナーの哲学というのを、
以前雑誌で読みましたが、
「とにかく声がいいヴォーカリストを用意すること」、だとか。
それ以外の要素はどうにでもなるけど、
声だけは何物にも代え難い、というわけ。
ホワイトスネイクのVoデヴィッド・カヴァデイルは、
元ディープ・パープルでもありますが、
彼の声の良さは、既に折り紙つきでしたが、
彼本来の音楽的趣向のおかげか、渋くて玄人受けする音楽を
ソロになってからは繰り広げていました。
ホワイトスネイクの場合、アメリカでは「いまいち」だったのを、
彼が大仕掛けをして、大成功したというわけですが、
その「大仕掛け」というのは・・・ずばり、
「ツェッペリンっぽい音」(・・・ぱくり・・・!?)
当時、レッド・ツェッペリンは既になく、音楽市場に、
「ツェッペリンっぽい音」というのものが空白のまま残っていた、
そんな時代で、そこを狙っての大仕掛けが、まんまと大成功。
ただ、僕自身は、これより前にZepは聴いていましたが、
これを最初に聴いて、それほどツェッペリンぽいとは感じず、
数年して、このアルバムが過去のものとして話題になった頃に
ようやくそのことを指摘されて気づきました。
それは僕が鈍かっただけなのかもしれないですが、
でも、そうですね、ぱくりとかそういうことではなく、
これはこれとして「新しい音楽」として接していました。
元々、あまり批評的な耳は持っていなかったのでしょう、僕は(笑)。
02 ノリウツギ (ユキノシタ科)

それはともかく、このアルバムの充実度は誰もが認めるところ。
先日、たまたま引っ張り出してきて聴き、記事にしようと決めてからは、
毎日聴かないと気が済まないくらいになってますし(笑)。
このアルバム、レコーディングではジョン・サイクスがギターを担当し、
かなりいい仕事をしていますが、彼はレコーディング後に解雇され、
代わって呼び集められたのが、名うてのテクニシャンばかり。
エイドリアン・ヴァンデンバーグ Gt(元ヴァンデンバーグ)
ヴィヴィアン・キャンベル Gt(元ディオ、現デフ・レパード)
ルディ・サーゾ Bs(元オジー・オズボーン)
トミー・アルドリッジ Ds(元オジー・オズボーン)
当時は「スーパーグループ」として話題を集め、
このメンバーでツアーに出ましたが、
僕のメタル好きの友達は狂喜乱舞していました。
そして、当時は若い女性にも人気が高く、
コンサートでは「えいどりあぁ~ん」という黄色い歓声が聞こえ、
古くからのファンは「うるさい」と言っていました・・・(笑)。
もっとも、僕も、このアルバムからファンになったので、
古くからのファンには、うっとうしく映っていたでしょうけど・・・
★名曲★・・・ロック史に残る名曲
★ヒット★・・・シングルヒットした曲
★佳曲★・・・通好みの味がある曲
★秘宝★・・・埋もれておくには惜しい隠れた名曲
★カッコいい★・・・ひたすらカッコいい曲
★注目★・・・話題作、問題作、とにかく注目すべき曲
★映画★・・・映画やテレビ番組で使われた曲
★CM★・・・CMで使われた曲
★GB★・・・guitarbird個人の思いが強い曲
03 オニシモツケ (バラ科)

Tr1:Crying In The Rain
★佳曲★★カッコいい★
この曲を最初に聴いて、ビートルズのYer Bluesを思い浮かべました。
Yerは当時のブリティッシュ・ブルーズを茶化したものですが、
つながっていますね、ブリティッシュ・ハードロックは。
僕は実は、Yer Bluesを最初に聴いた時から、なんというか、
存在感が違ったんですよね。
さらにいえばホワイトアルバムのC面はハードな曲のオンパレードで、
しかもその間に、落ち着いたアコースティックな曲が入っているのが
大好きでした。
それはともかく、ビートルズのおかげでこの曲は一発で好きになり、
ホワイトスネイクが、ハードロックが、そしてヘヴィメタルが
一気に身近に感じた、そんな曲でした。
なおこの曲、以前のアルバムに収録されていた曲の再録音です。
Tr2:Bad Boys
★カッコいい★
冒頭のデヴィカヴァの叫びが、それまで僕が聴いてきた世界と違うことを
はっきりと認識しました。
これはロックンロールなのか?と悩みました。
ヴァースからサビに移る前の部分のギターのバッキングが
当時からかっこいいと思ってました。
Tr3:Still Of The Night
★名曲★★カッコいい★★注目★
このアルバムが「ツェッペリンのぱくり」と言われていたことを、
最も顕著に表わしている曲。
この曲のビデオクリップでは、かつてジミー・ペイジがやっていた、
エイドリアンがギターをヴァイオリンの弓で弾くシーンもありますが、
当時はZepの映像をほとんど観たことがなくて、
それがペイジの真似であることを知らなかったのです。
だから、僕が気づくまでに数年かかったんですが・・・(笑)。
それはともかく、ツェッペリンぽい音を出すといったところで、
そんじょそこらのバンドが出来るわけではないでしょうし、
ツェッペリンっぽい音へのニーズはかなりあったものの、
それっぽい「ホンモノの」音を出せるバンドはいなかった。
彼らはそこに挑んで、ある意味期待以上のものを作り上げた、
という感じなのではないでしょうか。
なんて書くと、さっきから僕はまるで批判しているみたいですが、
そんなことはなく、僕にとってはそれは枝葉の部分に過ぎません。
が、ロックが時代を映した音である以上、
その部分を無視して話をすることはできないので、
先ほどからそこにこだわっているのです(ご了承ください)。
いや、この曲は大好きですよ、ほんとに。
凄い曲、という言葉がまさにぴったりの、奇跡的名曲。
究極に進化したブルーズという感じですね、ほんと凄い!
ギターリフがちょっとだけ「移民の歌」っぽかったり・・・
あ、まだ言うか(笑)。
04 アマニュウ (セリ科)

Tr4:Here I Go Again
★名曲★★ヒット★★GB★
この曲も、かつてのアルバムを再録音したもの。
良いアルバム作りに、新しいマテリアルだけでは不足であると
関係者は感じたのでしょうか。
事実、この曲については、再録音したことにより
「隠れた名曲」から、「真の名曲」に進化を遂げました。
この曲を聴いて、ビデオクリップを観て、
このアルバムを買うことを決意しました。
バラードでありながらヘヴィメタル。
そんな曲があるなんて、想像すらしていませんでした。
おまけにこの曲は歌詞が素晴らしくて、
ビートルズ以外で最も歌詞が好きな曲でもあります。
そして、歌詞を読んでいると、
オーティス・レディングのかの名曲The Dock Of The Bayの
「裏と表」という感じがしてきます。
どちらも、追い詰められたというか、
でもオーティスはそんな自分に浸っている、
一方でこちらは、そんな自分から脱しようと前向きになる・・・
ちなみに、デヴィカヴァは、このビデオで共演している
女性と後に結婚しました(がさらに後に離婚しました)が、
このビデオは激しく絡むシーンなどもあり、
「私物化するな」と当時は言われていました(笑)。
この曲は、1980年代でも十指に入る好きな曲ですし、ひいては、
僕のロック人生の中でも、きわめて重要な出会いをした、
そんな曲でもあります。
導入部がソフトで、サビは盛り上がる展開という、
ヘヴィメタルの基本形を教えてもくれましたし
Tr5:Give Me All Your Love
★佳曲★
これはロックンロールというのだろうか、と悩んだ曲・・・
曲自体は、メロディも進行も割合単純なのですが、
圧倒的なクオリティでまっすぐに聴かせる、
ブリティッシュハードロックの王道路線。
Tr6:Is This Love
★名曲★★ヒット★
これは明らかに「売れ線狙い」で、それが見事に成功した曲。
当時は「メタルバラード」なるものが広まりつつある頃で、
ビルボードNO.1にもなったこの曲、その決定版という感じでしょうか。
ただ、僕はこのアルバムの直後の来日公演を
代々木に観に行き、そこでこの曲も演奏したのですが、
アレンジがAORっぽく、大好きだったものの期待外れでした。
デヴィカヴァ自身もあまり気に入ってないように見えましたし・・・
それと、このアルバムでこの曲は少し浮いていますが、
後々の彼らのアルバムを聴くと、むしろこの路線に近づいていた
つまり根の部分では彼ららしい曲だったんだ、ということに
つい最近気づきました(笑)。
ともあれ、レコードとして聴くと、やはり名曲には違いないですね。
05 ヤマブキショウマ (バラ科)

Tr7:Children Of The Night
これはTr2とそっくり(笑)。
実際、ライヴでは、Tr2とこれを混ぜて1曲にして演奏していますし。
いかにもメタル的イディオムというものも、ここで学びました。
なお、僕個人としては、当時から、このアルバムは、
ここから急にトーンダウンするというか、それまでの
異様なまでのハイテンションから解放されたように感じていました。
この曲自体は緊迫感がある系ですが、似た曲、ということで
こちら側の緊迫感は溶けてゆくのを感じます。
ただし、これ以降がよくないのではなく、
この前までがあまりにも充実していて凄すぎるだけですが。
Tr8:Straight For The Heart
★カッコいい★
これは最初からロックンロールだと思ってました(笑)。
誰が聴いてもそう思うのではないかと。
そしてこれは最初に気に入りました。
ただ、後から知ったのですが、この曲は、
前のアルバムに入っている曲の「二番煎じ」であるらしく、
事実、後から、その前のアルバムを聴いて、なるほど、と。
まあ、それはともかく、軽やかなロックンロールで、
これはむしろ、トーンダウンしたことにより、
それまで「普通のロック」を聴いてきた僕が
すんなりと受け入れれたんだと思いますし、この曲があったから、
アルバム自体への親近感もすぐに増したのだと思います。
イントロのギターの音がTr3とまったく同じなのは、
遊び心も感じられ、緊張感がいいほうに緩む曲でもあります。
それからこの曲は、ギターのバッキング演奏の勉強には
とってもいい曲ですね。
今聴いても、カッコよすぎる!
Tr9:Don't Turn Away
★注目★
最後のこの曲、僕は昔からずっと引っかかっています・・・
この曲だけ、AORとまではゆかない、ソフト、は言いすぎだけど、
なんというか、肩の力が抜けすぎている曲であり、
ここまでの流れを自分たちの手でぶち壊す、という感じもします。
ま、それが「ロック」としてのユーモアなのかもしれないですが。
断っておきますが、曲自体はとってもいいし、大好きです。
でも、今回聴いても、やっぱり違和感が、ないでもない・・・
メタル愛の弟は、特に気になっていないようなので、
これは多分に僕の思いすごしかもしれないですが。
このアルバム、不思議なことに、
国内盤では国内でリマスターされたものが再発されましたが、
海外では、1987年当時に出たものが、まだカタログで残っています。
だからこのCD、音量がかなり小さいですね。
なお、国内盤のタイトルである「サーペンス・アルバス」とは、
このジャケットの紋章にSERPENS ALBUSと彫られており、
それがタイトルになったもので、日本ではそれで定着しています。
確かに、ホワイトスネイク、よりは愛着が湧きそうですし。
そうそう、僕が最初に買ったという話がまだでした。
大学1年の時、Tr4がヒットしていたのを聴いたのですが、
その曲がいいと思った自分がしゃくに障りました・・・
というのも当時、へヴィメタが好きな友達が、
普通のロックをことごとくバカにしていて、それが気に食わず、
意地になって買わないと言い張っていたので、
おいそれと「好きだ」とも言えないし、
仮に買ったとしても、それがバレるのも気持ちがよくないし。
でも、やっぱりいい曲だ・・・
かなり悩みました。
自分の耳に素直になってみると、
このアルバムは聴きたい、欲しい、という思いが強くなり、
やがて、それに抗うことが出来なくなりました。
そしてついに、夏休みで札幌に帰っていて、東京に戻る直前の日に、
今は別の場所に移転した、最初のタワー・レコード札幌店に
弟と出向いて、買いました。
でも、やっぱり最後まで素直にはなれなくて、
弟にレジに行ってもらいました(お金は僕が出しましたもちろん)。
買って聴いてみると・・・予想、期待、想像以上に良かったです。
その時、友達に対して意地を張っていた自分がバカだった・・・
と反省し、それ以降、メタル系も含めて、
聴いたことがないアーティストのCDを積極的に買うことにしました。
そのようなわけで、
僕の中でもかなり重要なアルバムです。
だから、余計に、愛情の裏返しで、
ツェッペリンっぽい、とおちょくっていたのです(笑)。
そして、このアルバムも、BLOGを始めてから、
いつかは記事にしようと思っていた1枚です。
繰り返しますが、だからといって
BLOGをやめはしませんよ(笑)。
そういえば今年、彼らの新作が出たんですよね。
こちら、良くも悪くも、相変わらず、という感じで、
このアルバムのマジックがかろうじて残っている、かな・・・
音的にはむしろそれ以前の渋みがある曲で、
なかなかいいとは思います。
でも、記事に出来るほど聴き込んではいませんでした・・・
なので代わりに、このアルバム、というわけでもないんですが。
最後にもうひとつ、その、意地を張っていたメタル好きの友達とは
その後「和解」し、一緒にコンサートに行きました。
今回の写真は、
ホワイトスネイクだから「白い蛇」・・・の写真は撮れなかったので、
ここ数日で撮った「白い花」の写真を集めてみました。
06 岩の崖一面に咲くフランスギク

2014年05月09日
ベスト・バラード・コレクション ロッド・スチュワート
※guitarbirdはただ今遠征に出ております
この記事はタイマーで上げています
お返事が遅れることがありますが、予めご了承ください
先日のAll For Loveの記事の際に決めた、このアルバム。
僕がいっちばん好きなヴォーカリスト。
01

IF WE FALL IN LOVE TONIGHT Rod Stewart
ベスト・バラード・コレクション ロッド・スチュワート
released in 1996
その名の通り、
ロッド・スチュワートのバラードを集めた企画ものですが、
新録音・新曲も4曲含まれており、冒頭の4曲がそれ。
ロッド・スチュワートほど
他人の曲のカバーが上手い人はいません!
断言します!
作った人よりも曲の気持ちが分かっているんじゃないだろうか。
というのは言葉のあやですね。
ポップソング=ロックの楽曲は、歌詞は、
聴いた人が好きに解釈できるものでありますし。
しかし、それにしてもロッドの歌は説得力があります。
ひとつは、ロッド自身の感情はあまり反映されていない、
ここがポイントだと僕は考えています。
歌い手=演じ手の感情が色濃く反映されると、
それはもはやポップソングではなくなります。
メガショービジネスであるポピュラー音楽の世界では、
演じ手の私生活や私情は本来見せないものなのですし。
02 白い花の桜、夏にはサクランボがなる木

そしてさらに、聴き手があたかも自分が歌っているように感じる、
そこがまたポピュラー音楽の特徴でもあると思います。
もっというなら、自分がこう歌えたら気持ちいいだろうなぁ。
カラオケはまさにそれを実践しているものにすぎません。
もし、歌い手の感情が色濃く反映されていれば、
多くの人が歌ってみたいとは思わないでしょう。
そうした音楽は、受け付ける人は大好きになるけど、
そうではない多くの人は、自分のものとして聴けない・・・
もちろん僕は、歌い手=演じ手の感情が色濃く反映される音楽を、
否定するものではありません。
ただ、自分はそうした音楽が苦手であり、
小さい頃からポピュラー音楽を聴き続けてきた、というまでです。
さらにいえば、僕は、
多くの人が聴く音楽の中に自分だけの解釈を見つけることが好き、
という面が強い、ただそれだけのつまらない人間です。
長くなりましたが、ロッドの説得力は、
決して「歌い手として歌唱力が優れている」というものではなく、
あくまでも、ポピュラー音楽という世界において、
多くの人に伝わりやすい気持ちを表すことが上手い、
というものなのです。
でも、じゃあそれは何に起因するのかというと・・・
今の僕には、それこそがまさにロッドの個性である、
としか表現することができません。
ということで、ロッドのアルバムの記事を最初に上げる際に、
これは先ず言っておきたい、と思っていたことでした。
03 アオジ(露出オーバー)

Tr1:If We Fall In Love Tonight
ブラック系の名プロデューサーティームの
ジャム&ルイスと組み、彼らが作曲したまったくの新曲。
新し物好きのロッド、嗅覚が鈍っていないことを示した曲。
いかにも1曲目という、爽やかで、軽やかなバラード。
あ、このアルバムは「バラード・コレクション」だから、
みんなバラードなんだっけ(笑)。
Tr2:For The First Time
このアルバムで2番目にいいのはこの曲!
映画音楽で活躍するジェームス・ニュートン・ハワード作(共作)。
ここでは「新曲」となっていますが、同じ頃にこの曲を、
ケニー・ロギンスが、映画「素晴らしき日」のサントラで歌い、
そちらがグラミー賞などにノミネートされています。
というのは、この記事を書くのに調べて分かったことですが、
実は僕、この曲は、最初に聴いた頃からずっと、
オールディーズのカバーだと思い込んでいたんです。
勘違いもはなはだしいですが、だけど、
そういう古き良き時代の雰囲気を持った新しい名曲だと、
今回記事のために聴いて、思いました。
これは素晴らしい!
切なさの極み!
切ない曲が大好きですからね、僕は(笑)。
ちなみに映画「素晴らしき日」の主演は、ジョージ・クルーニーと、
僕が大好きなミシェル・ファイファーです(そいえば映画観たことある)。
Tr3:When I Need You
レオ・セイヤーのヒット曲で、
かつてアルバムを記事で紹介したアルバート・ハモンドが、
作詞家・作曲家のキャロル・ベイヤー・セイガーと組んだ曲。
そうか、レオ・セイヤーのこの曲自体は以前から知ってたけど、
そこで僕は既にアルバート・ハモンドに接していたんだ。
名曲、名バラード。
こちらもジャム&ルイスのプロデュース。
余談ですが、レオ・セイヤーと、キャロル・ベイヤー・セイガーって
紛らわしいですよね。
僕はずっと、キャロル・ベイカー・セイヤーだと思ってましたし・・・
Tr4:Someties When We Touch
そしてまたジェームス・ニュートン・ハワードに戻る。
羽のようにソフトで軽やかな感じの曲。
ここまでの新しい4曲も聴きどころ満載です!
04:落雷で折れて黒焦げになった樹木と新緑、常緑

Tr5:Tonight's The Night (Gonna Be Alright)
1976年のアルバムA NIGHT ON THE TOWNより。
ロッドがカバーの名手であることには何度も触れていますが、
いっぽうで、このような素晴らしい曲を1人で作ってもいます。
全米NO.1ヒットで、1977年の年間チャートNO.1曲でもあり、
ロッドを象徴する曲のひとつでしょう。
なお、オリジナルバージョンのエンディングに入っている
女性のエロティックな声がここでは、それが始まる前に
フェイドアウトされていますが、そうして正解だと僕は思います。
Tr6:I Don't Want To Talk About It
1975年のアルバムATLANTIC CROSSINGより。
この曲はこちらの記事をご参照ください。
Tr7:Have I Told You Lately (studio version remix)
1991年のアルバムVAGABOND HEARTより。
この曲は、ロッド・スチュワートでいちばん好きな曲です。
ロッドのみならず、僕がリアルタイムで聴いた
全てのロックの楽曲の中でも、間違いなく5指に入るくらい、
大切な、思い入れもたっぷりの曲。
だからこの曲は、また、いつか、バラードの記事にします。
ただ、すぐにそれが出来る自信や勇気が、今はないのですが・・・
でもやっぱりひとことだけ。
「普通の1日」の喜びを歌った歌です。
Tr8:Your Song
あのエルトン・ジョンの、ロック史上でも屈指の名曲のカバー。
ロッドとエルトンは若い頃から交流があり、
ロッドの1970年の名作GASOLINE ALLEYでも、
エルトンは自分の曲にヴォーカルでも参加しています。
05:春もみじとシラカンバ

Tr9:Forever Young (1996)
元デュラン・デュランのアンディ・テイラーをギターに迎え、
思い切ったロック路線に打って出た1988年のアルバム
OUT OF ORDERからのヒット曲。
ロッドとバンドメンバーの共作。
ボブ・ディランの名曲とは同名異曲。
元々、バラードというよりミドルテンポの落ち着いた曲ですが、
このアルバムのために、バラードに編曲して再録音しており、
それでタイトルが(1996)になっています。
が、ごめんなさい・・・
はっきり、意欲は買うのですが、僕は、元のバージョンが、
ロッドの中でも10指に入るかというくらいに大好きなので、
このバラードのバージョンは好きではありません。
ただ、ロッド自身がこの曲をそれだけ気に入っていることが分かり、
うれしかったことは確かです。
この曲のいいたいことはタイトル通り。
いつかこの曲も独立して記事に。
Tr10:You're In My Heart
1977年のアルバムFOOT LOOSE AND FANCE FREEより。
これもロッド1人で作曲。
まあ、ロッドの曲は、展開もなく単純な進行なのですが、
それだけに旋律のよさが際立っているともいえます。
この曲は、ヒット当時にテレビかラジオで耳にしていたらしく、
ロッドを聴くようになり自分でLPを買ってこの曲を聴いて、
あ、知ってる、と。
でも、僕個人のレベルを超えて、この曲には何か、
1970年代ノスタルジーを感じさせるものがあります。
そう、ビリー・ジョエルのThe Strangerなどのように。
余談、ロッド大好きな僕の友達は、この曲は
「まあいいけど・・・」と言ってあとは鼻で笑ってました(笑)。
Tr11:My Heart Can't Tell You No
これも先述OUT OF ORDERからの曲。
タイトルの語感、いわゆる「非生物主語」が、
日本人の僕には違和感がありました(今でもあります)。
もがき苦しみ、ためらうような、切なさにあふれた曲。
そのアルバムは、4枚のシングルが、
大ヒットはしなかったんだけどみなTop20くらいに売れ、
アルバムも最高位は低いんだけどじわじわと売れた
不思議なアルバムでもあります。
Tr12:First Cut Is The Deepest
再びアルバムA NIGHT ON THE TOWNより。
これはずっとロッドの曲だと思っていました。
年にシェリル・クロウがベスト盤を出す際に、
新録音としてこの曲をカバーしていましたが、それは、
ロッドの曲をカバーしたのだと思っていましたし・・・
しかしオリジナルは1970年代のシンガー・ソングライターである
キャット・スティーヴンス。
ロッドのカバーのうまさを物語る1曲。
サビの歌い方はロッドにしか出せない味。
ただ、オリジナルは聴いたことがないのですが・・・
06:新緑の森

Tr13:Sailing
再びアルバムATLANTIC CROSSINGより。
この曲はこちらの記事をご参照ください。
Tr14:Downtown Train
1989年に出た4枚組ボックスセットSTORYTELLERより。
これ、僕の中ではいまだに最高のボックスセットです。
ロッドの歴史を、遺漏なく、というといいすぎですが、
最良の形で、各年代万遍なく曲を拾い上げ、
それこそ「ロッドの歴史」を物語る大作に仕上がっています。
ほんと、ロッドのことをある程度詳しくしかし早く知りたければ、
このボックスセットを聴けば理解できます。
これは、そのボックスセット用の新録音曲で、全米3位の大ヒット。
トム・ウェイツの曲。
夜を過ごして朝を迎えた、という雰囲気の曲で、
どこか寂しく、切なく、しかし明るさを絶やさない、そんな曲。
Tr15:Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda)
続いてトム・ウェイツのカバー。
これは、1993年に出た、LEAD VOCALISTという、
半分は過去の曲、半分はロックの名曲の新たなカバーという
まあ、中途半端なアルバムから。
ロッドの中では最も詩情溢れる、劇的な曲でしょう。
もちろんそれは、ロッドの表現力にしてなし得た技ですが、
しかし、それまでのロッドにしては凝りすぎという感じもします。
能天気ともいえる明るさが本来の彼の魅力であり、
重たいバラードをやっても、どこかにその匂いがした、
そんなロッドにしては、真面目すぎ、じめっとしすぎ、
きれいすぎ、きっちりとやりすぎ・・・というか。
それもまたしかし新境地を狙ったのかもしれませんが。
ただ、当時僕は、Tr14に続いてこの路線は少しくどいかな、
と思わなくもなかったです。
嫌いじゃない、好きな曲ですが。
ロッド大好きの友達も、この曲には、いいのかどうなのか、
答えに困っていた記憶があります。
Tr16:All For Love
これは、このアルバムの記事を上げるきっかけとなった、
一昨日のこちらの記事をご参照ください。
ちなみに、ロッドはどこを歌っているか、分かりますか(笑)。
なお、このアルバムは、
UK盤、インターナショナル盤、US盤、日本盤とあり、
それぞれ選曲と曲順が違うので、注意が必要です。
ここで紹介した、僕が持っているのは日本盤で、
Your Songが入っています。
このアルバム、ジャケットの写真もとってもいいなぁ、と思います。
ニュー・ヨークの摩天楼を背景に、ただ、ロッドが
ビルの屋上にいるだけ、しかも曇りで空が白い写真ですが、
それがなんとも、うまくこの切なさのようなものを表していると。
ロッドの青いスーツがまたカッコいいし!
正直、あの曲を入れてほしかった・・・というのはありますが、
それを言ったらキリがないですし、これはこれで素晴らしいです。
ところで。
これからの時期、バラードはどうなんでしょうね・・・
どちらかというと寒い時期、というイメージもしないでもないですが、
ま、いい曲ばかりで楽しめるアルバムではあります。
今回の写真は、ここ数日のA公園の風景写真でした。
さて、最後に問題。
次の写真07は、01とどこが違うでしょう!?
07

正解:CDが07は横、01はタテになっている
・・・ほんとは、これをたてで冒頭に使うつもりでしたが、
タテより横のほうが写真的に収まりがいいので、
CDの向きを変えて01を撮り直しました。
あ、ハウが目を開けている、
も、不正解ではありません、念のため(笑)。
この記事はタイマーで上げています
お返事が遅れることがありますが、予めご了承ください
先日のAll For Loveの記事の際に決めた、このアルバム。
僕がいっちばん好きなヴォーカリスト。
01

IF WE FALL IN LOVE TONIGHT Rod Stewart
ベスト・バラード・コレクション ロッド・スチュワート
released in 1996
その名の通り、
ロッド・スチュワートのバラードを集めた企画ものですが、
新録音・新曲も4曲含まれており、冒頭の4曲がそれ。
ロッド・スチュワートほど
他人の曲のカバーが上手い人はいません!
断言します!
作った人よりも曲の気持ちが分かっているんじゃないだろうか。
というのは言葉のあやですね。
ポップソング=ロックの楽曲は、歌詞は、
聴いた人が好きに解釈できるものでありますし。
しかし、それにしてもロッドの歌は説得力があります。
ひとつは、ロッド自身の感情はあまり反映されていない、
ここがポイントだと僕は考えています。
歌い手=演じ手の感情が色濃く反映されると、
それはもはやポップソングではなくなります。
メガショービジネスであるポピュラー音楽の世界では、
演じ手の私生活や私情は本来見せないものなのですし。
02 白い花の桜、夏にはサクランボがなる木

そしてさらに、聴き手があたかも自分が歌っているように感じる、
そこがまたポピュラー音楽の特徴でもあると思います。
もっというなら、自分がこう歌えたら気持ちいいだろうなぁ。
カラオケはまさにそれを実践しているものにすぎません。
もし、歌い手の感情が色濃く反映されていれば、
多くの人が歌ってみたいとは思わないでしょう。
そうした音楽は、受け付ける人は大好きになるけど、
そうではない多くの人は、自分のものとして聴けない・・・
もちろん僕は、歌い手=演じ手の感情が色濃く反映される音楽を、
否定するものではありません。
ただ、自分はそうした音楽が苦手であり、
小さい頃からポピュラー音楽を聴き続けてきた、というまでです。
さらにいえば、僕は、
多くの人が聴く音楽の中に自分だけの解釈を見つけることが好き、
という面が強い、ただそれだけのつまらない人間です。
長くなりましたが、ロッドの説得力は、
決して「歌い手として歌唱力が優れている」というものではなく、
あくまでも、ポピュラー音楽という世界において、
多くの人に伝わりやすい気持ちを表すことが上手い、
というものなのです。
でも、じゃあそれは何に起因するのかというと・・・
今の僕には、それこそがまさにロッドの個性である、
としか表現することができません。
ということで、ロッドのアルバムの記事を最初に上げる際に、
これは先ず言っておきたい、と思っていたことでした。
03 アオジ(露出オーバー)

Tr1:If We Fall In Love Tonight
ブラック系の名プロデューサーティームの
ジャム&ルイスと組み、彼らが作曲したまったくの新曲。
新し物好きのロッド、嗅覚が鈍っていないことを示した曲。
いかにも1曲目という、爽やかで、軽やかなバラード。
あ、このアルバムは「バラード・コレクション」だから、
みんなバラードなんだっけ(笑)。
Tr2:For The First Time
このアルバムで2番目にいいのはこの曲!
映画音楽で活躍するジェームス・ニュートン・ハワード作(共作)。
ここでは「新曲」となっていますが、同じ頃にこの曲を、
ケニー・ロギンスが、映画「素晴らしき日」のサントラで歌い、
そちらがグラミー賞などにノミネートされています。
というのは、この記事を書くのに調べて分かったことですが、
実は僕、この曲は、最初に聴いた頃からずっと、
オールディーズのカバーだと思い込んでいたんです。
勘違いもはなはだしいですが、だけど、
そういう古き良き時代の雰囲気を持った新しい名曲だと、
今回記事のために聴いて、思いました。
これは素晴らしい!
切なさの極み!
切ない曲が大好きですからね、僕は(笑)。
ちなみに映画「素晴らしき日」の主演は、ジョージ・クルーニーと、
僕が大好きなミシェル・ファイファーです(そいえば映画観たことある)。
Tr3:When I Need You
レオ・セイヤーのヒット曲で、
かつてアルバムを記事で紹介したアルバート・ハモンドが、
作詞家・作曲家のキャロル・ベイヤー・セイガーと組んだ曲。
そうか、レオ・セイヤーのこの曲自体は以前から知ってたけど、
そこで僕は既にアルバート・ハモンドに接していたんだ。
名曲、名バラード。
こちらもジャム&ルイスのプロデュース。
余談ですが、レオ・セイヤーと、キャロル・ベイヤー・セイガーって
紛らわしいですよね。
僕はずっと、キャロル・ベイカー・セイヤーだと思ってましたし・・・
Tr4:Someties When We Touch
そしてまたジェームス・ニュートン・ハワードに戻る。
羽のようにソフトで軽やかな感じの曲。
ここまでの新しい4曲も聴きどころ満載です!
04:落雷で折れて黒焦げになった樹木と新緑、常緑

Tr5:Tonight's The Night (Gonna Be Alright)
1976年のアルバムA NIGHT ON THE TOWNより。
ロッドがカバーの名手であることには何度も触れていますが、
いっぽうで、このような素晴らしい曲を1人で作ってもいます。
全米NO.1ヒットで、1977年の年間チャートNO.1曲でもあり、
ロッドを象徴する曲のひとつでしょう。
なお、オリジナルバージョンのエンディングに入っている
女性のエロティックな声がここでは、それが始まる前に
フェイドアウトされていますが、そうして正解だと僕は思います。
Tr6:I Don't Want To Talk About It
1975年のアルバムATLANTIC CROSSINGより。
この曲はこちらの記事をご参照ください。
Tr7:Have I Told You Lately (studio version remix)
1991年のアルバムVAGABOND HEARTより。
この曲は、ロッド・スチュワートでいちばん好きな曲です。
ロッドのみならず、僕がリアルタイムで聴いた
全てのロックの楽曲の中でも、間違いなく5指に入るくらい、
大切な、思い入れもたっぷりの曲。
だからこの曲は、また、いつか、バラードの記事にします。
ただ、すぐにそれが出来る自信や勇気が、今はないのですが・・・
でもやっぱりひとことだけ。
「普通の1日」の喜びを歌った歌です。
Tr8:Your Song
あのエルトン・ジョンの、ロック史上でも屈指の名曲のカバー。
ロッドとエルトンは若い頃から交流があり、
ロッドの1970年の名作GASOLINE ALLEYでも、
エルトンは自分の曲にヴォーカルでも参加しています。
05:春もみじとシラカンバ

Tr9:Forever Young (1996)
元デュラン・デュランのアンディ・テイラーをギターに迎え、
思い切ったロック路線に打って出た1988年のアルバム
OUT OF ORDERからのヒット曲。
ロッドとバンドメンバーの共作。
ボブ・ディランの名曲とは同名異曲。
元々、バラードというよりミドルテンポの落ち着いた曲ですが、
このアルバムのために、バラードに編曲して再録音しており、
それでタイトルが(1996)になっています。
が、ごめんなさい・・・
はっきり、意欲は買うのですが、僕は、元のバージョンが、
ロッドの中でも10指に入るかというくらいに大好きなので、
このバラードのバージョンは好きではありません。
ただ、ロッド自身がこの曲をそれだけ気に入っていることが分かり、
うれしかったことは確かです。
この曲のいいたいことはタイトル通り。
いつかこの曲も独立して記事に。
Tr10:You're In My Heart
1977年のアルバムFOOT LOOSE AND FANCE FREEより。
これもロッド1人で作曲。
まあ、ロッドの曲は、展開もなく単純な進行なのですが、
それだけに旋律のよさが際立っているともいえます。
この曲は、ヒット当時にテレビかラジオで耳にしていたらしく、
ロッドを聴くようになり自分でLPを買ってこの曲を聴いて、
あ、知ってる、と。
でも、僕個人のレベルを超えて、この曲には何か、
1970年代ノスタルジーを感じさせるものがあります。
そう、ビリー・ジョエルのThe Strangerなどのように。
余談、ロッド大好きな僕の友達は、この曲は
「まあいいけど・・・」と言ってあとは鼻で笑ってました(笑)。
Tr11:My Heart Can't Tell You No
これも先述OUT OF ORDERからの曲。
タイトルの語感、いわゆる「非生物主語」が、
日本人の僕には違和感がありました(今でもあります)。
もがき苦しみ、ためらうような、切なさにあふれた曲。
そのアルバムは、4枚のシングルが、
大ヒットはしなかったんだけどみなTop20くらいに売れ、
アルバムも最高位は低いんだけどじわじわと売れた
不思議なアルバムでもあります。
Tr12:First Cut Is The Deepest
再びアルバムA NIGHT ON THE TOWNより。
これはずっとロッドの曲だと思っていました。
年にシェリル・クロウがベスト盤を出す際に、
新録音としてこの曲をカバーしていましたが、それは、
ロッドの曲をカバーしたのだと思っていましたし・・・
しかしオリジナルは1970年代のシンガー・ソングライターである
キャット・スティーヴンス。
ロッドのカバーのうまさを物語る1曲。
サビの歌い方はロッドにしか出せない味。
ただ、オリジナルは聴いたことがないのですが・・・
06:新緑の森

Tr13:Sailing
再びアルバムATLANTIC CROSSINGより。
この曲はこちらの記事をご参照ください。
Tr14:Downtown Train
1989年に出た4枚組ボックスセットSTORYTELLERより。
これ、僕の中ではいまだに最高のボックスセットです。
ロッドの歴史を、遺漏なく、というといいすぎですが、
最良の形で、各年代万遍なく曲を拾い上げ、
それこそ「ロッドの歴史」を物語る大作に仕上がっています。
ほんと、ロッドのことをある程度詳しくしかし早く知りたければ、
このボックスセットを聴けば理解できます。
これは、そのボックスセット用の新録音曲で、全米3位の大ヒット。
トム・ウェイツの曲。
夜を過ごして朝を迎えた、という雰囲気の曲で、
どこか寂しく、切なく、しかし明るさを絶やさない、そんな曲。
Tr15:Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda)
続いてトム・ウェイツのカバー。
これは、1993年に出た、LEAD VOCALISTという、
半分は過去の曲、半分はロックの名曲の新たなカバーという
まあ、中途半端なアルバムから。
ロッドの中では最も詩情溢れる、劇的な曲でしょう。
もちろんそれは、ロッドの表現力にしてなし得た技ですが、
しかし、それまでのロッドにしては凝りすぎという感じもします。
能天気ともいえる明るさが本来の彼の魅力であり、
重たいバラードをやっても、どこかにその匂いがした、
そんなロッドにしては、真面目すぎ、じめっとしすぎ、
きれいすぎ、きっちりとやりすぎ・・・というか。
それもまたしかし新境地を狙ったのかもしれませんが。
ただ、当時僕は、Tr14に続いてこの路線は少しくどいかな、
と思わなくもなかったです。
嫌いじゃない、好きな曲ですが。
ロッド大好きの友達も、この曲には、いいのかどうなのか、
答えに困っていた記憶があります。
Tr16:All For Love
これは、このアルバムの記事を上げるきっかけとなった、
一昨日のこちらの記事をご参照ください。
ちなみに、ロッドはどこを歌っているか、分かりますか(笑)。
なお、このアルバムは、
UK盤、インターナショナル盤、US盤、日本盤とあり、
それぞれ選曲と曲順が違うので、注意が必要です。
ここで紹介した、僕が持っているのは日本盤で、
Your Songが入っています。
このアルバム、ジャケットの写真もとってもいいなぁ、と思います。
ニュー・ヨークの摩天楼を背景に、ただ、ロッドが
ビルの屋上にいるだけ、しかも曇りで空が白い写真ですが、
それがなんとも、うまくこの切なさのようなものを表していると。
ロッドの青いスーツがまたカッコいいし!
正直、あの曲を入れてほしかった・・・というのはありますが、
それを言ったらキリがないですし、これはこれで素晴らしいです。
ところで。
これからの時期、バラードはどうなんでしょうね・・・
どちらかというと寒い時期、というイメージもしないでもないですが、
ま、いい曲ばかりで楽しめるアルバムではあります。
今回の写真は、ここ数日のA公園の風景写真でした。
さて、最後に問題。
次の写真07は、01とどこが違うでしょう!?
07

正解:CDが07は横、01はタテになっている
・・・ほんとは、これをたてで冒頭に使うつもりでしたが、
タテより横のほうが写真的に収まりがいいので、
CDの向きを変えて01を撮り直しました。
あ、ハウが目を開けている、
も、不正解ではありません、念のため(笑)。
2014年04月30日
5150 ヴァン・ヘイレン
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です!
今回は、メタルマニアで「ある意味てっちゃん」である弟が
いちばん好きなロックアルバムを紹介します。
ただし、多分、レッド・ツェッペリンとアイアン・メイデンを除いて。
01 アイーダ、やっぱり君の仕事だよ

弟がいちばん好きなロックアルバムが、これです。
なぜか。
弟が、自分のお金で買った最初のLPだったんじゃないかな。
1986年だから、僕は浪人生で、弟は中学1年。
弟はそれまでも僕が聴く洋楽を耳にしていて、
クイーンは最初から好きだったと記憶していたけど、
そんな中、このアルバムがリリースされました。
買った日は、秋から冬にかけてかな。
僕は免許を取っていたので、車で出かけて、
札幌の大通地区に当時あった僕の行きつけのレコード屋に行き、
僕は車の中で待っていて、弟が買ってきた、
そんな状況だったと記憶しています。
その後弟はメタル道を突き進むことになり(笑)、
一方僕は相変わらずポップなアメリカンロック。
まあ、そのおかげでお互い、聴くものが広がったともいえますが。
さて、アルバムの話。
02 エンレイソウの花のアップ・・・ヴァン・ヘイレンのロゴみたい(笑)

ヴァン・ヘイレンは、かのポップス史上に残る名曲
Jumpが収録された前作1984が大ヒット。
それを受け、エンターテイメント路線の拡充を狙った
Voのデヴィッド・リー・ロスが、
ビーチ・ボーイズのCalifornia Girlsなど、
オールディーズやアメリカン・スタンダードをカバーした
ミニアルバムCRAZY FROM THE HEATを大ヒットさせ、
それが元でメンバーの間に軋轢が生じ、デイヴはついに脱退。
その後デイヴは、Gtのスティーヴ・ヴァイ、Bsのビリー・シーンなど、
名うてのテクニシャンを集めたスーパーバンドを結成し、
アルバムが大ヒット、大好評のうちに迎えられました。
ただ、失速も意外と早かったですが・・・
一方「本家」ヴァン・ヘイレンは、デイヴの後釜に、
アメリカン・ロックの「永遠のいたずら小僧」(と僕が勝手に呼ぶ)
サミー・ヘイガーをヴォーカル(とギター)に迎えました。
当時、サミー・ヘイガーは、名前は有名、しかし
ベストヒットUSAで数曲を耳(と目)にしていたくらいで、
しっかりと聴いたことはない、という人であって、
「サミー・ヘイガーってあの「ふぃふてぃふぁあ~いぶ」
って人でしょ・・・」という程度の認識でいました。
さらにサミーは、当時、日本ではまったく人気がなく、
この前年かな、来日公演を組んだんだけど、
あまりにチケットの売れ行きが芳しくないので中止になった、
ということがあった人なのです。
だから、日本のヴァン・ヘイレンのファンは当時、
サミーの加入に「困った」人も多いのではないか、と・・・
僕は、困りはしませんでしたが、上記の
コンサートが中止になった件を強烈に覚えていたため、
日本ではどう受け入れられるだろう、と思いました。
ヴァン・ヘイレンの魅力は、なんといっても、
そういってはなんですが、楽曲の出来には目をつぶって、
「悪ガキ」デイヴとエドワードのトリッキーなギターの絡みを楽しむ、
そんなところではなかったかと。
これ、楽曲が「悪い」という意味ではなく、いつもの言い方をすれば、
「鼻歌で口ずさむような歌メロがいい曲が少ない」という意味で、
ノリとテクニックで圧倒し、さらにはステージでこそ魅力が分かる、
一方で、レコードを通しては曲として訴えるものが少ない、
そんなバンドだったと、僕は思っていました。
ただし、今は、デイヴ時代のアルバムも好んで聴きます。
03 つくしももう終わりか

バンドのヴォーカルが変わると、
前任者と後任者、どっちがいいか(好きか)、というのは、
ロック聴きの間ではよく話題になりますが、
このヴァン・ヘイレンも、デイヴとサミーでは、
音楽の方向性がかなり違うことは確かです。
僕は、正直、サミー加入後のほうが好きです。
ライヴはそれはそれとして、音楽が、曲が、
レコードでじっくりと腰を落ち着けて聴くような
しっかりとしたつくりになり、さらに曲の歌メロがよくなり、
つまりは聴きやすくなったのが、その理由です。
そして、サミーのアメリカンロック王道路線が、
トリッキーなヴァン・ヘイレンの音楽と混ざり合い、
うまい具合に僕の好みに入った、というのもありました。
ロックの場合、ともすれば、
古い時代のもののほうが好きであることがエライ、
みたいな話になることがよくあります。
エライ、というのは多少の皮肉をこめた言い方ですが、
でも、R.E.M.の記事でも書きましたが、僕はやっぱり、
歌メロがしっかりした曲のほうが好きすし。
前期、もしくはヴォーカルが前任者のほうが好きなバンドは、
ブラック・サバスとドゥービー・ブラザースくらいなもんです。
ま、これは、あくまでも個人の趣向の問題ですが。
そしてそのサミー・ヘイガー、僕は、
なんというか、人間的に一目置いているんです。
遊び心たっぷりで、信念は曲げずに突き進み、慎み深く、
話したことはもちろんないですが、話してみると気さくで、
軽い話もシリアスな話もなんでもできそうな人、と想像しています。
音楽ももちろん、昔のも好きですし。
ともあれ、そんなわけで僕は、
サミーの加入には、大拍手を持って迎えたクチです。
サミーが隣りに住んでいたら、楽しくていいだろうなぁ(笑)。
そうそう、これ言わなきゃ。
サミーは元モントローズのメンバー。
04 オオウバユリの赤い新葉

そして、心機一転を図ったこのアルバムは、プロデュースに、
フォリナーのミック・ジョーンズを迎えています。
彼は、ビリー・ジョエルで僕がいちばん好きなアルバム
STORM FRONTもプロデュースをしていますが、
自らのバンドのフォリナーを軸とした
ポップなロックを仕立て上げる名手でもあります。
このアルバムは、ヴァン・ヘイレンが元々持っていた、
エドワードのギターとアレックスのドラムスが作り出す、
粘りがあって耳について離れない音が、
さらに粘りが増して響いてくるような音になっています。
要は、ハードでポップなロックのお手本のような音ですね。
ハードロックを聴き慣れていない人でも、
適度に心地よいサウンドに聞こえるのではないでしょうか。
とっても聴きやすい、いいアルバムです。
・・・というようなことを、
ほんとは弟に書いてもらいたかったのですが(笑)。
05 ハートの形のシナノキの新葉

Tr1:Good Enough
"Hello, Baby"
サミーの粘つくような声の「あいさつ」でスタート。
オープニングにふさわしいアップテンポでパワフルな曲。
喩えていうなら、レースのフォーメーションラップを見ただけで、
ポテンシャルのすさまじさ予感させる、そんな感じの曲。
始めから100%でやらないのがロックの醍醐味(笑)。
Tr2:Why Can't This Be Love
こんな曲、聞いたことがなかった!!
僕の最初の感想でした。
ハードで、ブルージーで、ポップで、強くて、優しくて。
そしてあくまでも正統的ハードロックを踏襲している。
そんな曲が、1曲目でもなく3曲目でもなく、
ましてやB面でもない、ここにあるのが効果てきめん!
プロモーションビデオもまた衝撃的でした。
なんといっても、作り物ではなく、ライヴ映像というのが。
しかも音もほんとにそこから取っている(はず)で、
レコードとは微妙に違うあたり、やる気を感じました。
ヘッドギアをつけてギターをかき鳴らしながら歌う
サミー・ヘイガーの姿に、完全にノックアウト。
デイヴ時代には出せなかった「凄み」が、そこにはありました。
Tr3:Get Up
これははっきり、スラッシュ・メタルですね!
メタリカやメガデスなど、超高速で跳ねるような音楽。
時代は、スラッシュ・メタルがそろそろ本筋に合流しつつある、
そんな時代でしたが、ベテランの域に入りかけた彼らは、
そんなの簡単さ、とでもいわんばかりに、さらりと、
しかし他のどんなバンドよりも熱っぽくやってみた。
そんな彼らは最高にクール!
サビのすっとんきょうなヴォーカルラインと、
さらにその上から被さるマイケル・アンソニーの超高音コーラス。
誰か彼らを止めてあげてぇ! という危険すれすれのノリ。
彼らが紛れもない超一級のハードロッカーであることを物語る曲。
Tr4:Dreams
弟がいちばん好きな彼らの曲が、これ!
テンポは速めだけど雰囲気はバラード風の、
メロウな、旋律が美しい、しかし力強いポップソング。
この、メロウだけど力強いというのが、
サミー時代の彼らの特徴かもしえません。
もちろんそれを可能にしているのは、
サミーの、温かみがあるハイトーンヴォイス。
それにしても、この曲の高揚感はたまらない!
この辺りの路線が、後年の、僕がいちばん好きな彼らの曲
Can't Stop Loving Youにつながってゆく曲でしょうね。
ロック史に残る名曲、といって差し支えないでしょう。
06 赤い赤いエゾイタヤの新葉

Tr5:Summer Nights
サミー・ヘイガー色と(それまでの)ヴァン・ヘイレン色が
うまい具合に絡み合ったミドルテンポの明るいポップソング。
どことなく1960年代風、どことなくウェストコーストサウンド風。
そこがまたいい味。
Tr6:Best Of Both Worlds
サミー・ヘイガーは驚いたといいます。
ハイトーンが売りの彼が、マイケル・アンソニーの声を聞いて、
「俺より声が高いやつがいるなんて信じられなかった」
この曲のサビはまるで、サミーとマイケル、
どっちが高い声を出せるか競っているようにすら思え、
なにをアホなこと競って、血管切れるんじゃないのかな、
と心配にもなってしまいます(笑)。
曲自体は、ギターリフを活かしたオーソドックスなハードロック。
この能天気さはやはりアメリカ人ならでは。
Tr7:Love Walks In
このアルバムでは唯一のバラード。
といって、中間部は少しテンポが速いですが、
やはりDreamsとつながる部分でもあります。
この路線はサミーがもたらしたものでしょうか。
今までハメを外しすぎたのを反省するかのように
しっとりと、落ち着いて聴かせるバラード。
泣きも入って、これは美しい曲ですね。
キーボード主体のイントロもぐっときます。
彼らはこの後、バラードの名曲も幾つか生み出すのですが、
この時点で、それが予感できた曲でもあります。
Tr8:"5150"
ここまで触れてこなかったですが、お読みになられたかた、
きっと、そのことが気になっているかと思います。
「5150」の意味。
弟に聞いたところ、
ロス市警の隠語で「犯罪予備軍」
という意味だそうです。
この曲はしかしむしろ、当時は時代の趨勢だった
「LAメタル」っぽい、からっと爽やかで明るく楽しい曲。
しかしそこが、彼ら独特のアイロニーなのかもしれません。
曲としては、いちばん旧来の彼ららしい曲ではあります。
Tr9:Inside
人間の内面的な弱みをえぐるような不気味な曲。
・・・なんだけど、特にマイケルの高音コーラスが入ると、
不気味というよりは、その世界に楽しく誘っているよう。
語りも交えて淡々と曲は進み、まるで、
「レディオ・ステーション・バッドガイ」のジングルのようでもあります。
そしてアルバムは終了。
ポップでありながらも、ちょっと毒づいた世界に
すっかり魅了されていることでしょう。
今聴くと、このクオリティでこの曲数、43分という時間、
ちょっと少なすぎて、あっさりと終わる感じがして、
もっと聴いていたい、と思わざるを得ません。
なお、このCDですが、近年日本で発売されたものは、
以前のCDに比べて音質が良くなっているという噂があります。
噂というのは、レコード会社がリマスターやマスターし直しを
特に謳っていないのですが、音が良くなっているという意味。
実際、弟も新しいプレスのものを買ったのですが、
確かに音量が大きくなり、それに伴い、よく聞こえる、
ということみたいです。
このリンクのCDは、その国内盤です。
今回の写真は、春先の小さな風景を集めてみました。
ヴァン・ヘイレンとは関係もないしイメージでもないのですが・・・
他に使い道がない、けど今を逃すと使えない写真、ということで。
07 エゾエンゴサクの珍しい白花のアップ

写真へのコメントも
大歓迎です!
今回は、メタルマニアで「ある意味てっちゃん」である弟が
いちばん好きなロックアルバムを紹介します。
ただし、多分、レッド・ツェッペリンとアイアン・メイデンを除いて。
01 アイーダ、やっぱり君の仕事だよ

弟がいちばん好きなロックアルバムが、これです。
なぜか。
弟が、自分のお金で買った最初のLPだったんじゃないかな。
1986年だから、僕は浪人生で、弟は中学1年。
弟はそれまでも僕が聴く洋楽を耳にしていて、
クイーンは最初から好きだったと記憶していたけど、
そんな中、このアルバムがリリースされました。
買った日は、秋から冬にかけてかな。
僕は免許を取っていたので、車で出かけて、
札幌の大通地区に当時あった僕の行きつけのレコード屋に行き、
僕は車の中で待っていて、弟が買ってきた、
そんな状況だったと記憶しています。
その後弟はメタル道を突き進むことになり(笑)、
一方僕は相変わらずポップなアメリカンロック。
まあ、そのおかげでお互い、聴くものが広がったともいえますが。
さて、アルバムの話。
02 エンレイソウの花のアップ・・・ヴァン・ヘイレンのロゴみたい(笑)

ヴァン・ヘイレンは、かのポップス史上に残る名曲
Jumpが収録された前作1984が大ヒット。
それを受け、エンターテイメント路線の拡充を狙った
Voのデヴィッド・リー・ロスが、
ビーチ・ボーイズのCalifornia Girlsなど、
オールディーズやアメリカン・スタンダードをカバーした
ミニアルバムCRAZY FROM THE HEATを大ヒットさせ、
それが元でメンバーの間に軋轢が生じ、デイヴはついに脱退。
その後デイヴは、Gtのスティーヴ・ヴァイ、Bsのビリー・シーンなど、
名うてのテクニシャンを集めたスーパーバンドを結成し、
アルバムが大ヒット、大好評のうちに迎えられました。
ただ、失速も意外と早かったですが・・・
一方「本家」ヴァン・ヘイレンは、デイヴの後釜に、
アメリカン・ロックの「永遠のいたずら小僧」(と僕が勝手に呼ぶ)
サミー・ヘイガーをヴォーカル(とギター)に迎えました。
当時、サミー・ヘイガーは、名前は有名、しかし
ベストヒットUSAで数曲を耳(と目)にしていたくらいで、
しっかりと聴いたことはない、という人であって、
「サミー・ヘイガーってあの「ふぃふてぃふぁあ~いぶ」
って人でしょ・・・」という程度の認識でいました。
さらにサミーは、当時、日本ではまったく人気がなく、
この前年かな、来日公演を組んだんだけど、
あまりにチケットの売れ行きが芳しくないので中止になった、
ということがあった人なのです。
だから、日本のヴァン・ヘイレンのファンは当時、
サミーの加入に「困った」人も多いのではないか、と・・・
僕は、困りはしませんでしたが、上記の
コンサートが中止になった件を強烈に覚えていたため、
日本ではどう受け入れられるだろう、と思いました。
ヴァン・ヘイレンの魅力は、なんといっても、
そういってはなんですが、楽曲の出来には目をつぶって、
「悪ガキ」デイヴとエドワードのトリッキーなギターの絡みを楽しむ、
そんなところではなかったかと。
これ、楽曲が「悪い」という意味ではなく、いつもの言い方をすれば、
「鼻歌で口ずさむような歌メロがいい曲が少ない」という意味で、
ノリとテクニックで圧倒し、さらにはステージでこそ魅力が分かる、
一方で、レコードを通しては曲として訴えるものが少ない、
そんなバンドだったと、僕は思っていました。
ただし、今は、デイヴ時代のアルバムも好んで聴きます。
03 つくしももう終わりか

バンドのヴォーカルが変わると、
前任者と後任者、どっちがいいか(好きか)、というのは、
ロック聴きの間ではよく話題になりますが、
このヴァン・ヘイレンも、デイヴとサミーでは、
音楽の方向性がかなり違うことは確かです。
僕は、正直、サミー加入後のほうが好きです。
ライヴはそれはそれとして、音楽が、曲が、
レコードでじっくりと腰を落ち着けて聴くような
しっかりとしたつくりになり、さらに曲の歌メロがよくなり、
つまりは聴きやすくなったのが、その理由です。
そして、サミーのアメリカンロック王道路線が、
トリッキーなヴァン・ヘイレンの音楽と混ざり合い、
うまい具合に僕の好みに入った、というのもありました。
ロックの場合、ともすれば、
古い時代のもののほうが好きであることがエライ、
みたいな話になることがよくあります。
エライ、というのは多少の皮肉をこめた言い方ですが、
でも、R.E.M.の記事でも書きましたが、僕はやっぱり、
歌メロがしっかりした曲のほうが好きすし。
前期、もしくはヴォーカルが前任者のほうが好きなバンドは、
ブラック・サバスとドゥービー・ブラザースくらいなもんです。
ま、これは、あくまでも個人の趣向の問題ですが。
そしてそのサミー・ヘイガー、僕は、
なんというか、人間的に一目置いているんです。
遊び心たっぷりで、信念は曲げずに突き進み、慎み深く、
話したことはもちろんないですが、話してみると気さくで、
軽い話もシリアスな話もなんでもできそうな人、と想像しています。
音楽ももちろん、昔のも好きですし。
ともあれ、そんなわけで僕は、
サミーの加入には、大拍手を持って迎えたクチです。
サミーが隣りに住んでいたら、楽しくていいだろうなぁ(笑)。
そうそう、これ言わなきゃ。
サミーは元モントローズのメンバー。
04 オオウバユリの赤い新葉

そして、心機一転を図ったこのアルバムは、プロデュースに、
フォリナーのミック・ジョーンズを迎えています。
彼は、ビリー・ジョエルで僕がいちばん好きなアルバム
STORM FRONTもプロデュースをしていますが、
自らのバンドのフォリナーを軸とした
ポップなロックを仕立て上げる名手でもあります。
このアルバムは、ヴァン・ヘイレンが元々持っていた、
エドワードのギターとアレックスのドラムスが作り出す、
粘りがあって耳について離れない音が、
さらに粘りが増して響いてくるような音になっています。
要は、ハードでポップなロックのお手本のような音ですね。
ハードロックを聴き慣れていない人でも、
適度に心地よいサウンドに聞こえるのではないでしょうか。
とっても聴きやすい、いいアルバムです。
・・・というようなことを、
ほんとは弟に書いてもらいたかったのですが(笑)。
05 ハートの形のシナノキの新葉

Tr1:Good Enough
"Hello, Baby"
サミーの粘つくような声の「あいさつ」でスタート。
オープニングにふさわしいアップテンポでパワフルな曲。
喩えていうなら、レースのフォーメーションラップを見ただけで、
ポテンシャルのすさまじさ予感させる、そんな感じの曲。
始めから100%でやらないのがロックの醍醐味(笑)。
Tr2:Why Can't This Be Love
こんな曲、聞いたことがなかった!!
僕の最初の感想でした。
ハードで、ブルージーで、ポップで、強くて、優しくて。
そしてあくまでも正統的ハードロックを踏襲している。
そんな曲が、1曲目でもなく3曲目でもなく、
ましてやB面でもない、ここにあるのが効果てきめん!
プロモーションビデオもまた衝撃的でした。
なんといっても、作り物ではなく、ライヴ映像というのが。
しかも音もほんとにそこから取っている(はず)で、
レコードとは微妙に違うあたり、やる気を感じました。
ヘッドギアをつけてギターをかき鳴らしながら歌う
サミー・ヘイガーの姿に、完全にノックアウト。
デイヴ時代には出せなかった「凄み」が、そこにはありました。
Tr3:Get Up
これははっきり、スラッシュ・メタルですね!
メタリカやメガデスなど、超高速で跳ねるような音楽。
時代は、スラッシュ・メタルがそろそろ本筋に合流しつつある、
そんな時代でしたが、ベテランの域に入りかけた彼らは、
そんなの簡単さ、とでもいわんばかりに、さらりと、
しかし他のどんなバンドよりも熱っぽくやってみた。
そんな彼らは最高にクール!
サビのすっとんきょうなヴォーカルラインと、
さらにその上から被さるマイケル・アンソニーの超高音コーラス。
誰か彼らを止めてあげてぇ! という危険すれすれのノリ。
彼らが紛れもない超一級のハードロッカーであることを物語る曲。
Tr4:Dreams
弟がいちばん好きな彼らの曲が、これ!
テンポは速めだけど雰囲気はバラード風の、
メロウな、旋律が美しい、しかし力強いポップソング。
この、メロウだけど力強いというのが、
サミー時代の彼らの特徴かもしえません。
もちろんそれを可能にしているのは、
サミーの、温かみがあるハイトーンヴォイス。
それにしても、この曲の高揚感はたまらない!
この辺りの路線が、後年の、僕がいちばん好きな彼らの曲
Can't Stop Loving Youにつながってゆく曲でしょうね。
ロック史に残る名曲、といって差し支えないでしょう。
06 赤い赤いエゾイタヤの新葉

Tr5:Summer Nights
サミー・ヘイガー色と(それまでの)ヴァン・ヘイレン色が
うまい具合に絡み合ったミドルテンポの明るいポップソング。
どことなく1960年代風、どことなくウェストコーストサウンド風。
そこがまたいい味。
Tr6:Best Of Both Worlds
サミー・ヘイガーは驚いたといいます。
ハイトーンが売りの彼が、マイケル・アンソニーの声を聞いて、
「俺より声が高いやつがいるなんて信じられなかった」
この曲のサビはまるで、サミーとマイケル、
どっちが高い声を出せるか競っているようにすら思え、
なにをアホなこと競って、血管切れるんじゃないのかな、
と心配にもなってしまいます(笑)。
曲自体は、ギターリフを活かしたオーソドックスなハードロック。
この能天気さはやはりアメリカ人ならでは。
Tr7:Love Walks In
このアルバムでは唯一のバラード。
といって、中間部は少しテンポが速いですが、
やはりDreamsとつながる部分でもあります。
この路線はサミーがもたらしたものでしょうか。
今までハメを外しすぎたのを反省するかのように
しっとりと、落ち着いて聴かせるバラード。
泣きも入って、これは美しい曲ですね。
キーボード主体のイントロもぐっときます。
彼らはこの後、バラードの名曲も幾つか生み出すのですが、
この時点で、それが予感できた曲でもあります。
Tr8:"5150"
ここまで触れてこなかったですが、お読みになられたかた、
きっと、そのことが気になっているかと思います。
「5150」の意味。
弟に聞いたところ、
ロス市警の隠語で「犯罪予備軍」
という意味だそうです。
この曲はしかしむしろ、当時は時代の趨勢だった
「LAメタル」っぽい、からっと爽やかで明るく楽しい曲。
しかしそこが、彼ら独特のアイロニーなのかもしれません。
曲としては、いちばん旧来の彼ららしい曲ではあります。
Tr9:Inside
人間の内面的な弱みをえぐるような不気味な曲。
・・・なんだけど、特にマイケルの高音コーラスが入ると、
不気味というよりは、その世界に楽しく誘っているよう。
語りも交えて淡々と曲は進み、まるで、
「レディオ・ステーション・バッドガイ」のジングルのようでもあります。
そしてアルバムは終了。
ポップでありながらも、ちょっと毒づいた世界に
すっかり魅了されていることでしょう。
今聴くと、このクオリティでこの曲数、43分という時間、
ちょっと少なすぎて、あっさりと終わる感じがして、
もっと聴いていたい、と思わざるを得ません。
なお、このCDですが、近年日本で発売されたものは、
以前のCDに比べて音質が良くなっているという噂があります。
噂というのは、レコード会社がリマスターやマスターし直しを
特に謳っていないのですが、音が良くなっているという意味。
実際、弟も新しいプレスのものを買ったのですが、
確かに音量が大きくなり、それに伴い、よく聞こえる、
ということみたいです。
このリンクのCDは、その国内盤です。
今回の写真は、春先の小さな風景を集めてみました。
ヴァン・ヘイレンとは関係もないしイメージでもないのですが・・・
他に使い道がない、けど今を逃すと使えない写真、ということで。
07 エゾエンゴサクの珍しい白花のアップ

2014年04月26日
明日に架ける橋 サイモンとガーファンクル
01
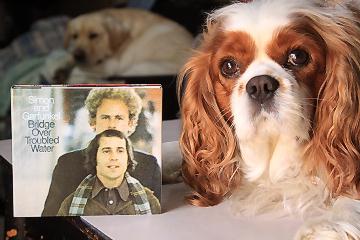
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Simon & Garfunkel
明日に架ける橋 サイモン&ガーファンクル (1970)
サイモン&ガーファンクルの歴史に残る名盤
「明日に架ける橋」の40周年記念盤がリリースされました。
CD2枚とDVDの3枚組で、Disc1にはアルバム本編が、
Disc2には1969年のライヴ音源が収録されています。
最近はこうしたおやじロッカー狙いの商品が増えましたね。
まあそれに乗せられてうれしいクチなので文句は言わないですが。
それから僕はへそ曲がりだから自分のことを「おやじロッカー」の
一員だとも思っていないんですが、それは身の程知らずかな(笑)。
ともあれそれが出たのを機に、BLOGを始めてからずっと記事に
しようと思っていたこのアルバムをついに取り上げることにしました。
僕がビートルズをこれほどまでに好きになったのは
サイモン&ガーファンクルのおかげかもしれない。
おかげとは言い過ぎかな、でも僕がビートルズを聴き始めた頃、
S&Gが再結成コンサートを行い、そのライヴ盤が発売され、
来日公演も行われ、S&Gが世の中で盛り上がっていました。
中学のクラスでもLPを買った人が持ってきて周りの何人かで話が
盛り上がっていたほどにちょっとした社会現象となっていたくらいで、
おそらく当時の日本において瞬間的にはビートルズよりは
S&Gのほうが人気があったのではないかと思っていました。
当時の僕はまだほんとうにビートルズとそのメンバーしか聴いておらず、
へそ曲がりの僕は、S&Gなんてどこがいいんだろうと話に加わらず、
いつか見返してやると意味不明の復讐心を抱きながらビートルズ愛に
燃えてその道を突き進んだ、というわけです。
そのブームはライヴ盤とツアーだけで終息しましたが、そのおかげで
日本では一時的ではなくずっと人気があったことがだんだんと分かり、
高校生の頃には少し興味が出てきました。
しかしまだ高校時代には聴くまでには至りませんでした。
僕がS&Gを聴くようになったのは、高校卒業後、バングルスが
Hazy Shade Of Winter「冬の散歩道」をカバーし大ヒットさせたのを
聴いて気に入ったからでした。
若くてとんがったロック野郎だった僕はそのカッコよさに打たれ、
S&Gって意外とロックなんだって感じました。
カバー曲というのは若い世代には意味があるものなのですね。
だから聴き始めたのはもう二十歳ぎりぎりだったわけで、だけど
その割にはもっと昔からの付き合いであるように感じているのは、
彼らが有名であり曲が覚えやすいからだと思います。
S&Gとカーペンターズ、ビリー・ジョエル、スティーヴィー・ワンダーは
日本における「洋楽」という言葉の代名詞だと僕は思っています。
もちろんビートルズもですがビートルズはビートルズだと思うから(笑)、
洋楽となるとその4者かな、あ、でもやっぱりビートルズも入れて5者。
なぜかというと、その4者については僕が洋楽を聴くようになる前から
テレビやラジオなどで聴き知っていた曲があったからで、音楽好きの
枠を超えて膾炙していてマニア性も薄いと思うからです。
ただそれなら僕より若い世代の人たちには違うのかなと一瞬思うけど、
でもそれらは多分今の若い人の間でも、1970年代までの洋楽の
イメージと結びついているのではないかと思います、思いたいです。
S&Gでいえば僕は、橋、コンドル、セシリア、サイレンス、スカボロー、
これら5曲については、自らの意志で彼らの音楽を初めて聴いた時
「この曲聞いたことある」と思い、タイトルと曲が結びついたのでした。
他の4者についても複数の曲をそうして聞き知っていました。
今回の記事のタイトルにおいてアルバム名を邦題にしているのと
サイモン「と」ガーファンクルとわざわざ書いているのは、そうした
「洋楽」という意識があってのことなのでした。
S&Gにはもうひとつ僕が常日頃思っていることがあります。
「自然が好きで音楽が好きな人はS&Gが好きな人が異様に多い」
僕の鳥の師匠がS&Gの再結成の後楽園球場公演に行った人で、
僕が車に乗せてもらって道東巡りをした時はずっとS&G再結成の
セントラル・パーク・コンサートが流れていました。
その際に師匠の知り合い何人かの家に寄って上らせてもらったところ、
音楽好きの僕はその家にステレオを見つけるとその人がどんな
音楽を聴いているかをチェックしていたのですが、その時は数人、
例外なくすべての人の家にS&GのCDがありました。
最後のほうになるともうきっとあるだろうと確信すら持てました。
その師匠はビートルズ世代より少し下ですがでも若い頃は
周りがビートルズばかり聴いているので自分は反発して
S&Gを聴くようになったと話してくれました。
そこで僕が、僕の中学時代はビートルズよりS&Gのほうが人気があった
と話すと、へえ面白いねと言っていたのを思い出します。
ともあれS&Gはやはり生ギターを中心としたサウンドが自然趣向の
人の心には合うのかもしれない、納得はできますね。
少なくとも破壊的な音楽じゃないですし。
そしてもちろん歌として素晴らしいから。
肝心のアルバムについてまだ触れていませんでした。
ひとことで言うと「S&G版音楽展示会」といった趣で、彼らの、
とりわけポール・サイモンの音楽の幅の広さや懐の深さを感じ、
また、それを表現しきれるまでに成長した姿を見ることができます。
それについて詳しくは曲ごとに触れてゆきます。
アート・ガーファンクルも最高の歌を聴かせてくれますね。
ほんとに「本業」に力が入っていなかったのかという感じですが、
でも彼は才気の人だからかえってそれくらい思い詰めないほうが
よかったのかもしれないですね。
これはS&Gの最後のアルバムとなってしまったわけですが、当時は
アートが俳優業などに精力を注いだ結果ポールを放っておくようになり、
ポールの不満が募っていたということで、後に触れますが
実際にそうした内容の曲があるのも興味深いです。
そして結局それが2人が別々の道を歩む決め手となった。
録音は1969年の秋までに終わっていたのが、諸事情により延びて
Decadeが変わった1970年にようやくリリースに至ったとのこと。
ビートルズも69年に実質上最後のアルバムであるABBEY ROADを、
なんとかビートルズとして作り上げて終わりましたが、本作とともに、
ひとつの時代の終わりを象徴していた意義深いアルバムでしょうね。
奇しくもどちらも音楽的に幅を広げつつバンドの色で覆っただけなのに、
結果として散漫という印象を与えない素晴らしい出来栄えになったのは
興味深い点ですね。
またこれらは逆境も人の力になり得るということを証明しているわけで、
そこは僕も励みにして見習いたいと今は強く思っています。
なお、作曲者は明示していないものはすべてポール・サイモンです。
(all songs written by Paul Simon except as noted)
02 40周年記念盤を開くと・・・あっ2人の髪が(以下略)

Tr1=A1:Bridge Over Troubled Water
この曲はおそらく日本で最も有名な洋楽の曲のひとつでしょうね。
音楽を聴く人でこの曲を知らない人っているのかな、想像できない。
公務員試験の一般教養問題に出すべきだと思うくらい(笑)。
まあ若い人ならいるでしょうけどいずれは知ることになるはずです。
曲については僕が言うべきこともないですね、真の名曲。
しかしそれでは話にならないのでひとつだけ、この曲はソウル系の
アーティストによるカバーがとっても多いんですがなるほどこの曲、
ゴスペルの要素が、ある、とは言わないけど感じさせるもので、
それは人間の荘厳さを歌っているところでつながっているのでしょうね。
これだけ真に感動する曲があるなんて感謝ですね。
札幌ドーム公演のアーティも声を出しきってまさに熱唱していて、
会場もそしてきっと本人もポールも大感動の渦に巻き込まれました。
Tr2=A2:El Condor Pasa (If I Could)
(D.A.Robles - J.Milchberg - English Lyrics by P. Simon)
(Arranged by J. Milchberg)
この曲は小学生の頃から誰のなんという曲か知っていました。
もちろん当時は「コンドルは飛んでゆく」という邦題ですが。
南米のフォルクローレの要素を採り入れ・・・とこれも
いまさら僕が説明する必要もないか。
"I'd rather be a sparrow than a snail"
「僕はカタツムリよりはスズメになりたい」
「僕はAよりBのほうがいい」と連綿と綴ってゆく歌詞ですが、
実はどちらでも不十分であることが伝わってきます。
"I'd rather feel the earth beneath my feet"
結局は人間でいたい、人間であらなければならない。
僕はカタツムリを見るとこの曲が頭に浮かんできます。
スズメを見ても思い出さないのに不思議ですね(笑)。
この曲を聴くと絶滅に瀕しているカリフォルニアコンドルがそして
他のコンドルも、どうか絶滅しませんようにと心の中で祈ります。
この曲はポールが歌っていますがどことなく頼りない声で、
だけどこの曲はそれがとってもいい味を出していると思います。
Tr3=A3:Cecillia
ポール・サイモンは背が低いことへのコンプレックスが強い人だなと
この曲の歌詞を読んで感じました。
ここでは直接的には背が低いことは歌われていないですが、
でもポールの表現の原動力は背の低さにあるのかな、と。
相方が背が高くて歌が上手い人なだけ余計に。
エスニックな要素を感じる強いリズム感を持った曲ですが
彼らが、というかポールが早い頃からエスニック的要素に着目して
自らの曲に採り入れようとしていたことが推察され、その点においても
彼らの存在感が今でも薄まっていない部分ではないかと思います。
それにしてもこれは歌うと気持ちがいい曲。
Tr4=A4:Keep The Customer Satisfied
強烈なシャッフルに乗ったソフトな演奏でぐいぐいと引っ張る曲。
ブラスも入ってポールのソウル好きも垣間見えます。
僕はこの曲で"shoeshine"が靴磨きであると覚えましたが、
東京にいた大学生の頃に上野駅や新宿駅に靴磨きの人がいて、
僕はそれを見るとこの曲が頭の中に浮かんできました。
今は(こちらでは)もう見ないのでそれが懐かしい。
Tr5=A5:So Long, Frank Lloyd Wright
音楽を聴いているといろんなことを学びますよね。
これは亡くなったフランク・ロイド・ライトに捧げる曲で、
僕がF・L・ライトを知ったのはもちろんというかこの曲を聴いたから。
昨年東京に行った際に「上野西洋美術館を世界遺産に」
というのぼりを上野界隈でたくさん見ましたが、その建物は
ライト、ではなくル・コルビジェでしたね・・・
でも僕はそののぼりを見るとこの曲が頭に浮かんでいまいた。
さっきから東京でこの曲が浮かぶ話ばかりですが、でも、
ニューヨークと東京の類似性みたいなものを感じているのかも。
て僕はニューヨークは行ったことないですけどね(笑)。
僕は街歩きや街の写真も(ほんとうは)好きなのですが、
そんな自分を確認する曲でもあります。
この曲はボサノヴァ風ですね、でもどこかもの悲しい。
03 最近お気に入りの被写体がかたつむり

Tr6=A6:The Boxer
これはアルバムに先んじてシングルで大ヒットしましたが、
当時はまだシングルとアルバムは分けていた頃あり、
だいぶ後からこの曲が収録されたのは曲が足りなかったのかな。
なんて邪推もしてしまいますね、単に入れたかったのでしょうけど。
世の中には嘘であってほしいことがあまりにも多すぎる現実に
どうすることもできないでもがく姿が身につまされます。
この曲はギターで弾けるようになりたいと20年も前から思い続け・・・
この曲にもまた恋愛にまつわる個人的な話があるのですが、
もちろんここでは話しません(笑)。
Tr7=B2:Baby Driver
彼らは本質的にロックンローラーなんだってこれを聴いて思いました。
このドライヴ感とグルーヴ感はある意味意表をついていて、
旧来のファンが拒否反応を起こさないかなと心配したくらい。
車かバイクのSEも入っていてやかましいかもしれないし。
ただ静かな音楽を好きな人だってたまにはノリたいでしょうから、
こういう曲もあっていいのだと思います。
あ、僕はもちろん大好きですよ。
ああそれからこの歌詞を読んでポールはちょっとエッチな人だな
と思ったことも付け加えておきます(笑)。
エロではなくエッチ、そこが味噌です。
Tr8=B3:The Only Living Boy In New York
「ニューヨークでひとりぼっちで生きている男」つまりポールのこと。
これはアートへのあてこすりの曲のひとつ。
曲の中で"Tom"と呼びかけていますが、これはS&Gの前身の名前が
トム&ジェリーだった、つまりかなり直接的な間接表現です(笑)。
僕はこの曲を初めて聴いた時から大好きで、なんというのかな、
虚しいというか切ないというか、やるせない気持ちをよく表していて、
僕はそういう曲にはすぐに同情を覚えて近しく感じる人間です。
そんな曲だからコンサートではやらないだろうと思っていたところ、
札幌ドーム公演でなんとこの曲を演奏してもう感激。
ほとんど涙目で聴いて一緒に口ずさむことができないくらいでした。
この曲を演奏したのはポールとアーティが関係を修復して
大人の関係になったことを宣言したかったからかなと思い、
そう思うと余計に胸にしみてきました。
音楽聴きなら誰でも、大好きなアーティストの中に、ヒット曲でもない
あまり知られていないけど異様に大好きな曲があるものでしょうけど
僕にとってS&Gのそれがこの曲です。
最後のコーラスも傷口を湧き水で洗うかのようにしみてきます。
Tr9=B4:Why Don't You Write Me
カリプソのこれは「どうして手紙を書かないの?」
恨み節はまだ続きます。
というかよくよく考えるとB面の後半はみなそうですね。
そういえばヘヴィメタル好きの僕の友だちがS&Gが大嫌いで
理由を尋ねると「女々しいから」と言われました・・・
すいませんこれは友だちが言ったその通りのことを書いていますが、
ううん、そうきたか、と・・・
レゲェも後に大流行しますが、1970年ということはやはり
ポールの先取性がうかがい知れますね。
これもポールの頼りなげな歌声がいい。
このアルバムにいい曲が多いのは、ポールがコンプレックスを
原動力にして表現していることから、アーティがいないという
いわば逆境に身を置かされたからかなと思いました。
Tr10=B5:Bye Bye Love
(F.Bryant - B.Bryant)
敬愛するエヴァリー・ブラザースのカバーでライヴ録音。
普通のアルバムにライヴを入れるのは、やはり曲が足りなかった、
と思ってしまう・・・タイトルもまたまた恨み節だし。
だけどこのアルバムの魔法は、そんなことはまったく関係なしに
素晴らしく響いてきます。
会場の手拍子がわざと大きくミックスされていて、ともすれば
ヴォーカルより大きいのですが、それもサウンドとして効果的。
だけど会場のこの一体感はいいなぁ。
エレクトリック・ギターも何か変わったぶつぶつした音を出しています。
カントリーっぽいこれは曲自体も切ない系に響いてきて大好きですが。
なお、ボックスセットOLD FRIENDSにはこの曲のスタジオヴァージョン
が入っていますが、でもこれはこっちのほうがいいな。
Tr11:Song For The Asking
アルバムの最後もポールのアーティへのあてこすり。
まるでライヴであるかのように前の曲の拍手の中からフェイドインし、
訥々としかし怨念深く歌うポールの姿は或る意味恐いですね。
ライヴからつながっているのはほんとはアーティともっとライヴをしたい
という思いだったのかもしれない。
怨念の割には曲があっさりと終わってほっとしますが、少し経って
後に残されたものが大きくずっと尾を引いていることを感じます。
最後なんだなぁ。
今はこれが最後と知ってこう書いていますが、でも当時の人も
これを聴いて何かが終わるのを感じたのではないかと思います。
リンクはともに国内盤、
左がこの40周年記念盤DVD付き、右が通常盤です。
40周年記念盤のDisc2のライヴは、1969年の秋、
このアルバムの収録が終わって一応はポールとアーティが
一時的に仲直りをしてアメリカをツアーで回ったいわば
彼らの最後のツアーからのライヴ音源ということです。
当然のことながらこのアルバムの曲ばかりではなく、
彼らの名曲がたくさん聴けてなかなかいいライヴです。
2人もプロだから一応は普通にやっている様子も感じますし。
サイモン&ガーファンクルってロックなのかな。
確か国内盤LPの帯には「フォーク」と書いてあった。
中学時代、周りがみんなS&Gで僕だけビートルズだった頃、
僕は帯のその文字を見て「へっ、フォークかい」と思いました。
今だから言いますが当時はとんでもなく生意気な奴で
それは当然のことながら侮蔑の感情が含まれていました。
でも、大学時代になって彼らを真剣に好きになってからは
「フォークと言い切るのはちょっと違うんじゃないか」
と思うようになっていました。
まったくもって自分勝手な奴ですね(笑)。
でも、いろいろな音楽に挑戦しそれを自分の色で表現しようと
前進を続けていた姿勢は、間違いなくロックだと思います。
記事にするのに久し振りに何度も聴いたけど、
やっぱり素晴らしいアルバムで感動しますね。
こういうアルバムが世の中に存在することのよろこびを感じます。
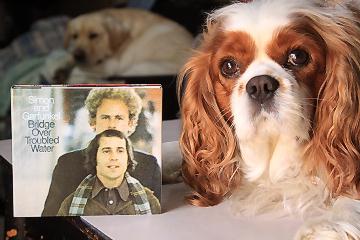
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Simon & Garfunkel
明日に架ける橋 サイモン&ガーファンクル (1970)
サイモン&ガーファンクルの歴史に残る名盤
「明日に架ける橋」の40周年記念盤がリリースされました。
CD2枚とDVDの3枚組で、Disc1にはアルバム本編が、
Disc2には1969年のライヴ音源が収録されています。
最近はこうしたおやじロッカー狙いの商品が増えましたね。
まあそれに乗せられてうれしいクチなので文句は言わないですが。
それから僕はへそ曲がりだから自分のことを「おやじロッカー」の
一員だとも思っていないんですが、それは身の程知らずかな(笑)。
ともあれそれが出たのを機に、BLOGを始めてからずっと記事に
しようと思っていたこのアルバムをついに取り上げることにしました。
僕がビートルズをこれほどまでに好きになったのは
サイモン&ガーファンクルのおかげかもしれない。
おかげとは言い過ぎかな、でも僕がビートルズを聴き始めた頃、
S&Gが再結成コンサートを行い、そのライヴ盤が発売され、
来日公演も行われ、S&Gが世の中で盛り上がっていました。
中学のクラスでもLPを買った人が持ってきて周りの何人かで話が
盛り上がっていたほどにちょっとした社会現象となっていたくらいで、
おそらく当時の日本において瞬間的にはビートルズよりは
S&Gのほうが人気があったのではないかと思っていました。
当時の僕はまだほんとうにビートルズとそのメンバーしか聴いておらず、
へそ曲がりの僕は、S&Gなんてどこがいいんだろうと話に加わらず、
いつか見返してやると意味不明の復讐心を抱きながらビートルズ愛に
燃えてその道を突き進んだ、というわけです。
そのブームはライヴ盤とツアーだけで終息しましたが、そのおかげで
日本では一時的ではなくずっと人気があったことがだんだんと分かり、
高校生の頃には少し興味が出てきました。
しかしまだ高校時代には聴くまでには至りませんでした。
僕がS&Gを聴くようになったのは、高校卒業後、バングルスが
Hazy Shade Of Winter「冬の散歩道」をカバーし大ヒットさせたのを
聴いて気に入ったからでした。
若くてとんがったロック野郎だった僕はそのカッコよさに打たれ、
S&Gって意外とロックなんだって感じました。
カバー曲というのは若い世代には意味があるものなのですね。
だから聴き始めたのはもう二十歳ぎりぎりだったわけで、だけど
その割にはもっと昔からの付き合いであるように感じているのは、
彼らが有名であり曲が覚えやすいからだと思います。
S&Gとカーペンターズ、ビリー・ジョエル、スティーヴィー・ワンダーは
日本における「洋楽」という言葉の代名詞だと僕は思っています。
もちろんビートルズもですがビートルズはビートルズだと思うから(笑)、
洋楽となるとその4者かな、あ、でもやっぱりビートルズも入れて5者。
なぜかというと、その4者については僕が洋楽を聴くようになる前から
テレビやラジオなどで聴き知っていた曲があったからで、音楽好きの
枠を超えて膾炙していてマニア性も薄いと思うからです。
ただそれなら僕より若い世代の人たちには違うのかなと一瞬思うけど、
でもそれらは多分今の若い人の間でも、1970年代までの洋楽の
イメージと結びついているのではないかと思います、思いたいです。
S&Gでいえば僕は、橋、コンドル、セシリア、サイレンス、スカボロー、
これら5曲については、自らの意志で彼らの音楽を初めて聴いた時
「この曲聞いたことある」と思い、タイトルと曲が結びついたのでした。
他の4者についても複数の曲をそうして聞き知っていました。
今回の記事のタイトルにおいてアルバム名を邦題にしているのと
サイモン「と」ガーファンクルとわざわざ書いているのは、そうした
「洋楽」という意識があってのことなのでした。
S&Gにはもうひとつ僕が常日頃思っていることがあります。
「自然が好きで音楽が好きな人はS&Gが好きな人が異様に多い」
僕の鳥の師匠がS&Gの再結成の後楽園球場公演に行った人で、
僕が車に乗せてもらって道東巡りをした時はずっとS&G再結成の
セントラル・パーク・コンサートが流れていました。
その際に師匠の知り合い何人かの家に寄って上らせてもらったところ、
音楽好きの僕はその家にステレオを見つけるとその人がどんな
音楽を聴いているかをチェックしていたのですが、その時は数人、
例外なくすべての人の家にS&GのCDがありました。
最後のほうになるともうきっとあるだろうと確信すら持てました。
その師匠はビートルズ世代より少し下ですがでも若い頃は
周りがビートルズばかり聴いているので自分は反発して
S&Gを聴くようになったと話してくれました。
そこで僕が、僕の中学時代はビートルズよりS&Gのほうが人気があった
と話すと、へえ面白いねと言っていたのを思い出します。
ともあれS&Gはやはり生ギターを中心としたサウンドが自然趣向の
人の心には合うのかもしれない、納得はできますね。
少なくとも破壊的な音楽じゃないですし。
そしてもちろん歌として素晴らしいから。
肝心のアルバムについてまだ触れていませんでした。
ひとことで言うと「S&G版音楽展示会」といった趣で、彼らの、
とりわけポール・サイモンの音楽の幅の広さや懐の深さを感じ、
また、それを表現しきれるまでに成長した姿を見ることができます。
それについて詳しくは曲ごとに触れてゆきます。
アート・ガーファンクルも最高の歌を聴かせてくれますね。
ほんとに「本業」に力が入っていなかったのかという感じですが、
でも彼は才気の人だからかえってそれくらい思い詰めないほうが
よかったのかもしれないですね。
これはS&Gの最後のアルバムとなってしまったわけですが、当時は
アートが俳優業などに精力を注いだ結果ポールを放っておくようになり、
ポールの不満が募っていたということで、後に触れますが
実際にそうした内容の曲があるのも興味深いです。
そして結局それが2人が別々の道を歩む決め手となった。
録音は1969年の秋までに終わっていたのが、諸事情により延びて
Decadeが変わった1970年にようやくリリースに至ったとのこと。
ビートルズも69年に実質上最後のアルバムであるABBEY ROADを、
なんとかビートルズとして作り上げて終わりましたが、本作とともに、
ひとつの時代の終わりを象徴していた意義深いアルバムでしょうね。
奇しくもどちらも音楽的に幅を広げつつバンドの色で覆っただけなのに、
結果として散漫という印象を与えない素晴らしい出来栄えになったのは
興味深い点ですね。
またこれらは逆境も人の力になり得るということを証明しているわけで、
そこは僕も励みにして見習いたいと今は強く思っています。
なお、作曲者は明示していないものはすべてポール・サイモンです。
(all songs written by Paul Simon except as noted)
02 40周年記念盤を開くと・・・あっ2人の髪が(以下略)

Tr1=A1:Bridge Over Troubled Water
この曲はおそらく日本で最も有名な洋楽の曲のひとつでしょうね。
音楽を聴く人でこの曲を知らない人っているのかな、想像できない。
公務員試験の一般教養問題に出すべきだと思うくらい(笑)。
まあ若い人ならいるでしょうけどいずれは知ることになるはずです。
曲については僕が言うべきこともないですね、真の名曲。
しかしそれでは話にならないのでひとつだけ、この曲はソウル系の
アーティストによるカバーがとっても多いんですがなるほどこの曲、
ゴスペルの要素が、ある、とは言わないけど感じさせるもので、
それは人間の荘厳さを歌っているところでつながっているのでしょうね。
これだけ真に感動する曲があるなんて感謝ですね。
札幌ドーム公演のアーティも声を出しきってまさに熱唱していて、
会場もそしてきっと本人もポールも大感動の渦に巻き込まれました。
Tr2=A2:El Condor Pasa (If I Could)
(D.A.Robles - J.Milchberg - English Lyrics by P. Simon)
(Arranged by J. Milchberg)
この曲は小学生の頃から誰のなんという曲か知っていました。
もちろん当時は「コンドルは飛んでゆく」という邦題ですが。
南米のフォルクローレの要素を採り入れ・・・とこれも
いまさら僕が説明する必要もないか。
"I'd rather be a sparrow than a snail"
「僕はカタツムリよりはスズメになりたい」
「僕はAよりBのほうがいい」と連綿と綴ってゆく歌詞ですが、
実はどちらでも不十分であることが伝わってきます。
"I'd rather feel the earth beneath my feet"
結局は人間でいたい、人間であらなければならない。
僕はカタツムリを見るとこの曲が頭に浮かんできます。
スズメを見ても思い出さないのに不思議ですね(笑)。
この曲を聴くと絶滅に瀕しているカリフォルニアコンドルがそして
他のコンドルも、どうか絶滅しませんようにと心の中で祈ります。
この曲はポールが歌っていますがどことなく頼りない声で、
だけどこの曲はそれがとってもいい味を出していると思います。
Tr3=A3:Cecillia
ポール・サイモンは背が低いことへのコンプレックスが強い人だなと
この曲の歌詞を読んで感じました。
ここでは直接的には背が低いことは歌われていないですが、
でもポールの表現の原動力は背の低さにあるのかな、と。
相方が背が高くて歌が上手い人なだけ余計に。
エスニックな要素を感じる強いリズム感を持った曲ですが
彼らが、というかポールが早い頃からエスニック的要素に着目して
自らの曲に採り入れようとしていたことが推察され、その点においても
彼らの存在感が今でも薄まっていない部分ではないかと思います。
それにしてもこれは歌うと気持ちがいい曲。
Tr4=A4:Keep The Customer Satisfied
強烈なシャッフルに乗ったソフトな演奏でぐいぐいと引っ張る曲。
ブラスも入ってポールのソウル好きも垣間見えます。
僕はこの曲で"shoeshine"が靴磨きであると覚えましたが、
東京にいた大学生の頃に上野駅や新宿駅に靴磨きの人がいて、
僕はそれを見るとこの曲が頭の中に浮かんできました。
今は(こちらでは)もう見ないのでそれが懐かしい。
Tr5=A5:So Long, Frank Lloyd Wright
音楽を聴いているといろんなことを学びますよね。
これは亡くなったフランク・ロイド・ライトに捧げる曲で、
僕がF・L・ライトを知ったのはもちろんというかこの曲を聴いたから。
昨年東京に行った際に「上野西洋美術館を世界遺産に」
というのぼりを上野界隈でたくさん見ましたが、その建物は
ライト、ではなくル・コルビジェでしたね・・・
でも僕はそののぼりを見るとこの曲が頭に浮かんでいまいた。
さっきから東京でこの曲が浮かぶ話ばかりですが、でも、
ニューヨークと東京の類似性みたいなものを感じているのかも。
て僕はニューヨークは行ったことないですけどね(笑)。
僕は街歩きや街の写真も(ほんとうは)好きなのですが、
そんな自分を確認する曲でもあります。
この曲はボサノヴァ風ですね、でもどこかもの悲しい。
03 最近お気に入りの被写体がかたつむり

Tr6=A6:The Boxer
これはアルバムに先んじてシングルで大ヒットしましたが、
当時はまだシングルとアルバムは分けていた頃あり、
だいぶ後からこの曲が収録されたのは曲が足りなかったのかな。
なんて邪推もしてしまいますね、単に入れたかったのでしょうけど。
世の中には嘘であってほしいことがあまりにも多すぎる現実に
どうすることもできないでもがく姿が身につまされます。
この曲はギターで弾けるようになりたいと20年も前から思い続け・・・
この曲にもまた恋愛にまつわる個人的な話があるのですが、
もちろんここでは話しません(笑)。
Tr7=B2:Baby Driver
彼らは本質的にロックンローラーなんだってこれを聴いて思いました。
このドライヴ感とグルーヴ感はある意味意表をついていて、
旧来のファンが拒否反応を起こさないかなと心配したくらい。
車かバイクのSEも入っていてやかましいかもしれないし。
ただ静かな音楽を好きな人だってたまにはノリたいでしょうから、
こういう曲もあっていいのだと思います。
あ、僕はもちろん大好きですよ。
ああそれからこの歌詞を読んでポールはちょっとエッチな人だな
と思ったことも付け加えておきます(笑)。
エロではなくエッチ、そこが味噌です。
Tr8=B3:The Only Living Boy In New York
「ニューヨークでひとりぼっちで生きている男」つまりポールのこと。
これはアートへのあてこすりの曲のひとつ。
曲の中で"Tom"と呼びかけていますが、これはS&Gの前身の名前が
トム&ジェリーだった、つまりかなり直接的な間接表現です(笑)。
僕はこの曲を初めて聴いた時から大好きで、なんというのかな、
虚しいというか切ないというか、やるせない気持ちをよく表していて、
僕はそういう曲にはすぐに同情を覚えて近しく感じる人間です。
そんな曲だからコンサートではやらないだろうと思っていたところ、
札幌ドーム公演でなんとこの曲を演奏してもう感激。
ほとんど涙目で聴いて一緒に口ずさむことができないくらいでした。
この曲を演奏したのはポールとアーティが関係を修復して
大人の関係になったことを宣言したかったからかなと思い、
そう思うと余計に胸にしみてきました。
音楽聴きなら誰でも、大好きなアーティストの中に、ヒット曲でもない
あまり知られていないけど異様に大好きな曲があるものでしょうけど
僕にとってS&Gのそれがこの曲です。
最後のコーラスも傷口を湧き水で洗うかのようにしみてきます。
Tr9=B4:Why Don't You Write Me
カリプソのこれは「どうして手紙を書かないの?」
恨み節はまだ続きます。
というかよくよく考えるとB面の後半はみなそうですね。
そういえばヘヴィメタル好きの僕の友だちがS&Gが大嫌いで
理由を尋ねると「女々しいから」と言われました・・・
すいませんこれは友だちが言ったその通りのことを書いていますが、
ううん、そうきたか、と・・・
レゲェも後に大流行しますが、1970年ということはやはり
ポールの先取性がうかがい知れますね。
これもポールの頼りなげな歌声がいい。
このアルバムにいい曲が多いのは、ポールがコンプレックスを
原動力にして表現していることから、アーティがいないという
いわば逆境に身を置かされたからかなと思いました。
Tr10=B5:Bye Bye Love
(F.Bryant - B.Bryant)
敬愛するエヴァリー・ブラザースのカバーでライヴ録音。
普通のアルバムにライヴを入れるのは、やはり曲が足りなかった、
と思ってしまう・・・タイトルもまたまた恨み節だし。
だけどこのアルバムの魔法は、そんなことはまったく関係なしに
素晴らしく響いてきます。
会場の手拍子がわざと大きくミックスされていて、ともすれば
ヴォーカルより大きいのですが、それもサウンドとして効果的。
だけど会場のこの一体感はいいなぁ。
エレクトリック・ギターも何か変わったぶつぶつした音を出しています。
カントリーっぽいこれは曲自体も切ない系に響いてきて大好きですが。
なお、ボックスセットOLD FRIENDSにはこの曲のスタジオヴァージョン
が入っていますが、でもこれはこっちのほうがいいな。
Tr11:Song For The Asking
アルバムの最後もポールのアーティへのあてこすり。
まるでライヴであるかのように前の曲の拍手の中からフェイドインし、
訥々としかし怨念深く歌うポールの姿は或る意味恐いですね。
ライヴからつながっているのはほんとはアーティともっとライヴをしたい
という思いだったのかもしれない。
怨念の割には曲があっさりと終わってほっとしますが、少し経って
後に残されたものが大きくずっと尾を引いていることを感じます。
最後なんだなぁ。
今はこれが最後と知ってこう書いていますが、でも当時の人も
これを聴いて何かが終わるのを感じたのではないかと思います。
リンクはともに国内盤、
左がこの40周年記念盤DVD付き、右が通常盤です。
40周年記念盤のDisc2のライヴは、1969年の秋、
このアルバムの収録が終わって一応はポールとアーティが
一時的に仲直りをしてアメリカをツアーで回ったいわば
彼らの最後のツアーからのライヴ音源ということです。
当然のことながらこのアルバムの曲ばかりではなく、
彼らの名曲がたくさん聴けてなかなかいいライヴです。
2人もプロだから一応は普通にやっている様子も感じますし。
サイモン&ガーファンクルってロックなのかな。
確か国内盤LPの帯には「フォーク」と書いてあった。
中学時代、周りがみんなS&Gで僕だけビートルズだった頃、
僕は帯のその文字を見て「へっ、フォークかい」と思いました。
今だから言いますが当時はとんでもなく生意気な奴で
それは当然のことながら侮蔑の感情が含まれていました。
でも、大学時代になって彼らを真剣に好きになってからは
「フォークと言い切るのはちょっと違うんじゃないか」
と思うようになっていました。
まったくもって自分勝手な奴ですね(笑)。
でも、いろいろな音楽に挑戦しそれを自分の色で表現しようと
前進を続けていた姿勢は、間違いなくロックだと思います。
記事にするのに久し振りに何度も聴いたけど、
やっぱり素晴らしいアルバムで感動しますね。
こういうアルバムが世の中に存在することのよろこびを感じます。
2014年04月01日
BEGGARS BANQUET ザ・ローリング・ストーンズ
いつものように
写真へのコメントも
大歓迎です!
そういえば、ストーンズのアルバム記事は、
新譜を除いてはこれが初めてだ。
01

BEGGARS BANQUET The Rolling Stones
ベガーズ・バンケット ザ・ローリング・ストーンズ released 1968
僕が大学生の頃、最初に買ったストーンズの過去のアルバム。
これと次作のLET IT BLEEDを、秋葉原の石丸電器で買いました。
ストーンズ、リアルタイムではSTILL LIFE以降は買っていましたが、
それ以前については、ベストでお茶を濁していました。
しかし、ベストはベストでいい曲ばかりで聴き応えがあるし、
一方で、リアルタイムで聴いてきたアルバムはみな、
いい曲はあるんだけど・・・という感じを拭えなかったので、
アルバムには期待していなかったのもあるのかもしれません。
このアルバムも最初は、まったく受け付けられませんでした。
彼らのみならず、ロック史に残る名曲が2曲も入っているというのに。
なぜだろう・・・
今となっては、自分でも不思議なことです。
しかも、一緒に買ったLET IT BLEEDは
すぐに気に入って、暫く聴いていたというのだから、
やっぱりこのアルバムには何かあるのでしょうか・・・
考えられるのは、名曲が入っているだけ逆に、
他の曲とのギャップを感じたのかもしれません。
しかしそれを言うなら、LET IT BLEEDだって、
このアルバムの2曲には及ばないけど(あくまでも僕の考え)、
名曲が3曲も入っていて、ギャップを感じそうなものですが、
しかしそっちはそれでも、とっても気に入ったんです。
何をどう聴いてよくないと判断したのか、
そこが自分でも気になります。
02 雪が解けて崩れ落ちた森の家の外の薪

しかし一方で、それほど考えることでもないのかもしれません。
音楽には聴くタイミングがある
年齢によって、その時の気分や環境によって、
同じCDでも、同じアーティストでも、まるで違って聴こえてくる。
というのが僕の持論であり、
これは、音楽が好きな人であれば
誰しも大なり小なり感じることだと思います。
それがなぜかは分からないのですが、
しかし、それが音楽というものではないでしょうか。
説明にはなっていないですが・・・(笑)
このアルバムは、2002年に突然好きになりました。
なぜ2002年なのか。
ハウと一緒に写っている現行のリマスター盤が出て
それを買ったのが2002年だから。
僕と弟は、リマスター盤が出ると買い直しているのですが、
それがきっかけで聴き直すと、前とはまったく違ってよく聴こえた、
というアルバムは無数にあります。
ま、レコード会社の戦略に乗せられているだけといえば、
それまでなのですが(笑)、ただ、
リマスター盤が出て買い直すのは楽しみでもあります。
だって、好きなアルバムがまた買えるんですよ!
まあ、何であれ、
音楽にはきっかけが大事である、ということです。
すっかりストーンズのことから離れてしまいましたが、
ストーンズについてはアルバムも多いので
これからも追々触れてゆきたいです。
そしてこの記事ではここから先、曲ごとに、
どうして昔はよく思わなかったのかも
考えながら書いてゆきます。
03 雲の向こうの冷たい太陽

Tr1:Sympathy For The Devil
僕はストーンズの最高傑作だと思う!
いや、すごいという言葉が幾つあっても足りない。
最初にこの曲を聴いた時、オーバーな表現じゃなく
あまりの気持ち悪さに震える思いをしたものです。
しかも、悪魔だからといっておどろおどろしく暗い音ではなく、
サンバのリズムでむしろからっと明るいのが、余計に・・・
キースのギターソロも屈指のものじゃないかな、キレもあるし。
ミックの歌も、ベースも、軽やかに唸っているし、
「フッフゥー」というコーラスも恐さ倍増。
この曲、助けを求めて縄はしごを登ってみたけれど、
登っても登ってもずり落ちていくような感覚があります。
ロック史に燦然と輝く名曲。
ただ、ひとつだけ。
この曲がアルバムの1曲目というのが、
最初に聴いた時には違和感を覚えたのですが、それも、
アルバムとしての評価が最初は低かった理由かもしれません。
今はこれでいいと納得していますが。
Tr2:No Expectations
たる~ぅいカントリー・ブルーズ。
最初に聴いた当時、「いい曲だなぁ」とは思わなかったけど、
妙に印象に残る歌メロだったようで、何年か聴かなかった後、
ふとこのCDを手に取った時に(リマスター盤の前に)、
この曲の歌メロが最初に頭に浮かびました。
不思議な曲です。
ただ、これは、まだ集中力が高いアルバム2曲目で、しかも、
歴史的名曲の後だから覚えていただけかもしれませんが(笑)。
なお、オリジナルメンバーで、C.W.ニコル氏の同級生だった
ブライアン・ジョーンズが参加した最後の曲だということです。
Tr3:Dear Doctor
やはりカントリー・ブルーズ、ホンキートンク風のワルツ。
ひとつ可能性があるのは、若かりし頃はこの
カントリーブルーズというのがしっくりこなかったのではないか。
それと、アルバムとしてみるとこれは、前の曲と、
リズムが変わっただけで雰囲気が変わらないじゃないか・・・
と感じていたのかも。
若い頃は、この辺は聴いても寝始めていたのではないか
とも思います(笑)。
Tr4:Parachute Woman
アコースティックなブルーズ路線は続く。
サビというかタイトルの言葉のメロディがやたら印象的。
そしてタイトルも何かシュールで不思議なイメージ。
でも、それが基本となった単調な部分の繰り返しだけで終わり、
未完の一片という感じがしないでもない。
ビートルズならメドレーにするだろうなぁ、と思ったり・・・
あ、そうそう、寝かかった頃にこの曲が流れてきて、
夢うつつで不思議な不気味な曲だと思った記憶もあります(笑)。
Tr5:Jigsaw Puzzle
全体的に上滑りしているような妙なイメージの曲。
ミックがわざと力なく歌っているかのよう。
同じ4小節を歌詞を変え抑揚を変えて延々と繰り返すだけの、
単調といえば単調極まりない曲だけど、
なぜは引きずり込まれるのはやはり、彼らの魔力か。
これまた不思議な曲。
04 オオイタドリの新芽が力強く地面から出てくる

Tr6:Street Fighting Man
弟がいちばん好きなストーンズの曲がこれ。
僕ももちろん好き。
これといい、Tr1といい、ミックの表現力には舌を巻くばかり。
そして、これだけ激しい曲を、
アコースティックギターをメインに据えて表現しているのは、
彼らの創作意欲が高かったことを如実に物語っています。
最初に聴いた時、このうねるようなメロディはなんだ、と驚きました。
ミックの言葉は、あの厚い唇に引っかかっているかのようだし(笑)。
そして「そこで歌に入るのか」と意表をつかれるイントロ。
そいえば、途中に入っている「ヒィーン」という妙な音、
最初はマイクノイズだと信じて疑わなかったのですが、
どうも何かの楽器の音のようで、その音は必ず、
曲の中の同じ部分で同じように出てきています。
また、タイトルの語感もまた当時は不思議でした。
というのも、StreetはFightingにかかる言葉で、
Manはそれらをまとめて受けるという形になじみがなかったから。
ストーンズの魅力のひとつに、これといい、Tr4といい、
そしてかの名曲Jumpin' Jack Flashといい、
独特の語感もまたあると思います。
それにしてもすごい、すごすぎる!
これぞまさしくロックの中のロック、歴史的名曲ですね。
Tr7:Prodigal Son
同じくアコースティックギターを中心に据えながらも、
カントリーやブルーズというよりは、トラッド風の軽快な曲。
社会風刺が効いた前の曲の毒消しのような穏やかさ、
この2曲が並ぶことがストーンズの凄みだと実感。
レッド・ツェッペリンの3枚目に通じるものがあります。
Tr8:Stray Cat Blues
このアルバムでエレクトリックギターが前面に出ている曲は、
考えてみれば、Tr1とこれだけなんだ。
そのせいか気のせいか(笑)、Tr1の続編というか、
「裏側を暴く」ような迫りくる不気味な響きに支配されている曲。
あ。
ふむふむ、そうかそうか。
僕は、もちろんビートルズを聴いてきていたので、
昔からアコースティック・ギターの音に抵抗はないのですが、
ストーンズには、もっと激しく攻める音を期待していたために、
アコースティック中心で肩透かしをくらったというか、
期待にそぐわなかった、と感じたのかもしれません。
でもかといって、当時この曲で過剰に反応したわけでもなく、
これは、2002年に聴き直すまで頭の外にありました・・・
というわけで今は、
アコースティック・ギターを前面に出したアルバムとして、
このアルバムはロック界でも屈指の出来だと思います。
ところで、ストレイ・キャッツは、この曲から名前つけたのかな・・・
ローリング・ストーンズも、
マディ・ウォーターズの曲から名前をつけてますが、
そういうつながりは、ロック好きとしてはうれしいものです。
Tr9:Factory Girl
ということでやはりアコースティックに戻る。
メロディがどことなく東洋風でありながら、
英国の片田舎も想像させる不思議な響きの曲。
このアルバムは不思議な曲が多いんですが、
若い頃にはそれも理解できなかったのかもしれません。
ただ、Tr4と同じく未完の一片という感じもしないでもない。
マンドリンの音がいい雰囲気。
偶然かどうか分からないですが、この2年後に出た
ロッド・スチュワートのGasoline Alleyもなぜか東洋風メロディで
マンドリンを使っていて、この2曲、雰囲気とてもよく似てます。
インド音楽の影響もあるのかもしれないですが。
Tr10:Salt Of The Earth
結局最後までアコースティックで押し通す。
若い頃、Tr7以降は、なんとなく盛り上がらないまま終わる、
と感じていたように思います(或いは覚えていないか・・・)
この曲は、リマスターとは別に、つい最近大好きになりました。
彼らが主催した1968年のテレビショーのライヴ盤である
ROCK AND ROLL CIRCUSでこの曲を聴いたのがきっかけ。
そのショーで、ストーンズのメンバーは魔法使いのような服装で、
まるで「笑点」の桂歌丸師匠のように客席に混ざって座り、
アコースティックギターでこれを歌っていました。
そこにはジョンやヨーコ、クラプトンの姿も。
曲は、ピアノとスライドギターもいい雰囲気。
一部をキースが歌うのがまたかっこいい。
彼らにしては珍しく(!?)
肯定的かつ優しいメッセージを感じる曲で、
彼らのアコースティックサイドでは最高傑作かもしれません。
それもまたしかし、後から思ったことなのですが・・・
余談、そるとさんの名前は、最初はてっきり、
この曲から取ったものだと思い込んでいました(笑)。
そして今思い出したことがあります。
これを最初に買った当時、このアルバムには、
Jumpin' Jack Flashが入っているものだと思い込んでいたのですが、
いざ聴くと入っていなくてがっかり、そして失敗したと思った、
そんな記憶があります。
今思うと、どうして事前に調べなかったのかというところですが(笑)。
ただ、それ以上に、そろそろストーンズの古いのも聴きたい、
と思っていたその勢いで買ったものではあるでしょう。
今思うと、元々彼らもアコースティックギターは使ってましたが、
ここでこの時期にアコースティックギターを多用することにより、
トゲトゲしさや激しさを薄めつつ、ソフトを加味するなど、
別の方向性、可能性を求めた転換期にあった作品かもしれません。
そんなこと、二十歳そこそこの若造が
なかなか気づくものではないでしょうかね(笑)。
05 アンモナイトや化石が含まれた「石」をハウが・・・

アンモナイトもハウの前には置いておけないのか・・・(笑)。
写真へのコメントも
大歓迎です!
そういえば、ストーンズのアルバム記事は、
新譜を除いてはこれが初めてだ。
01

BEGGARS BANQUET The Rolling Stones
ベガーズ・バンケット ザ・ローリング・ストーンズ released 1968
僕が大学生の頃、最初に買ったストーンズの過去のアルバム。
これと次作のLET IT BLEEDを、秋葉原の石丸電器で買いました。
ストーンズ、リアルタイムではSTILL LIFE以降は買っていましたが、
それ以前については、ベストでお茶を濁していました。
しかし、ベストはベストでいい曲ばかりで聴き応えがあるし、
一方で、リアルタイムで聴いてきたアルバムはみな、
いい曲はあるんだけど・・・という感じを拭えなかったので、
アルバムには期待していなかったのもあるのかもしれません。
このアルバムも最初は、まったく受け付けられませんでした。
彼らのみならず、ロック史に残る名曲が2曲も入っているというのに。
なぜだろう・・・
今となっては、自分でも不思議なことです。
しかも、一緒に買ったLET IT BLEEDは
すぐに気に入って、暫く聴いていたというのだから、
やっぱりこのアルバムには何かあるのでしょうか・・・
考えられるのは、名曲が入っているだけ逆に、
他の曲とのギャップを感じたのかもしれません。
しかしそれを言うなら、LET IT BLEEDだって、
このアルバムの2曲には及ばないけど(あくまでも僕の考え)、
名曲が3曲も入っていて、ギャップを感じそうなものですが、
しかしそっちはそれでも、とっても気に入ったんです。
何をどう聴いてよくないと判断したのか、
そこが自分でも気になります。
02 雪が解けて崩れ落ちた森の家の外の薪

しかし一方で、それほど考えることでもないのかもしれません。
音楽には聴くタイミングがある
年齢によって、その時の気分や環境によって、
同じCDでも、同じアーティストでも、まるで違って聴こえてくる。
というのが僕の持論であり、
これは、音楽が好きな人であれば
誰しも大なり小なり感じることだと思います。
それがなぜかは分からないのですが、
しかし、それが音楽というものではないでしょうか。
説明にはなっていないですが・・・(笑)
このアルバムは、2002年に突然好きになりました。
なぜ2002年なのか。
ハウと一緒に写っている現行のリマスター盤が出て
それを買ったのが2002年だから。
僕と弟は、リマスター盤が出ると買い直しているのですが、
それがきっかけで聴き直すと、前とはまったく違ってよく聴こえた、
というアルバムは無数にあります。
ま、レコード会社の戦略に乗せられているだけといえば、
それまでなのですが(笑)、ただ、
リマスター盤が出て買い直すのは楽しみでもあります。
だって、好きなアルバムがまた買えるんですよ!
まあ、何であれ、
音楽にはきっかけが大事である、ということです。
すっかりストーンズのことから離れてしまいましたが、
ストーンズについてはアルバムも多いので
これからも追々触れてゆきたいです。
そしてこの記事ではここから先、曲ごとに、
どうして昔はよく思わなかったのかも
考えながら書いてゆきます。
03 雲の向こうの冷たい太陽

Tr1:Sympathy For The Devil
僕はストーンズの最高傑作だと思う!
いや、すごいという言葉が幾つあっても足りない。
最初にこの曲を聴いた時、オーバーな表現じゃなく
あまりの気持ち悪さに震える思いをしたものです。
しかも、悪魔だからといっておどろおどろしく暗い音ではなく、
サンバのリズムでむしろからっと明るいのが、余計に・・・
キースのギターソロも屈指のものじゃないかな、キレもあるし。
ミックの歌も、ベースも、軽やかに唸っているし、
「フッフゥー」というコーラスも恐さ倍増。
この曲、助けを求めて縄はしごを登ってみたけれど、
登っても登ってもずり落ちていくような感覚があります。
ロック史に燦然と輝く名曲。
ただ、ひとつだけ。
この曲がアルバムの1曲目というのが、
最初に聴いた時には違和感を覚えたのですが、それも、
アルバムとしての評価が最初は低かった理由かもしれません。
今はこれでいいと納得していますが。
Tr2:No Expectations
たる~ぅいカントリー・ブルーズ。
最初に聴いた当時、「いい曲だなぁ」とは思わなかったけど、
妙に印象に残る歌メロだったようで、何年か聴かなかった後、
ふとこのCDを手に取った時に(リマスター盤の前に)、
この曲の歌メロが最初に頭に浮かびました。
不思議な曲です。
ただ、これは、まだ集中力が高いアルバム2曲目で、しかも、
歴史的名曲の後だから覚えていただけかもしれませんが(笑)。
なお、オリジナルメンバーで、C.W.ニコル氏の同級生だった
ブライアン・ジョーンズが参加した最後の曲だということです。
Tr3:Dear Doctor
やはりカントリー・ブルーズ、ホンキートンク風のワルツ。
ひとつ可能性があるのは、若かりし頃はこの
カントリーブルーズというのがしっくりこなかったのではないか。
それと、アルバムとしてみるとこれは、前の曲と、
リズムが変わっただけで雰囲気が変わらないじゃないか・・・
と感じていたのかも。
若い頃は、この辺は聴いても寝始めていたのではないか
とも思います(笑)。
Tr4:Parachute Woman
アコースティックなブルーズ路線は続く。
サビというかタイトルの言葉のメロディがやたら印象的。
そしてタイトルも何かシュールで不思議なイメージ。
でも、それが基本となった単調な部分の繰り返しだけで終わり、
未完の一片という感じがしないでもない。
ビートルズならメドレーにするだろうなぁ、と思ったり・・・
あ、そうそう、寝かかった頃にこの曲が流れてきて、
夢うつつで不思議な不気味な曲だと思った記憶もあります(笑)。
Tr5:Jigsaw Puzzle
全体的に上滑りしているような妙なイメージの曲。
ミックがわざと力なく歌っているかのよう。
同じ4小節を歌詞を変え抑揚を変えて延々と繰り返すだけの、
単調といえば単調極まりない曲だけど、
なぜは引きずり込まれるのはやはり、彼らの魔力か。
これまた不思議な曲。
04 オオイタドリの新芽が力強く地面から出てくる

Tr6:Street Fighting Man
弟がいちばん好きなストーンズの曲がこれ。
僕ももちろん好き。
これといい、Tr1といい、ミックの表現力には舌を巻くばかり。
そして、これだけ激しい曲を、
アコースティックギターをメインに据えて表現しているのは、
彼らの創作意欲が高かったことを如実に物語っています。
最初に聴いた時、このうねるようなメロディはなんだ、と驚きました。
ミックの言葉は、あの厚い唇に引っかかっているかのようだし(笑)。
そして「そこで歌に入るのか」と意表をつかれるイントロ。
そいえば、途中に入っている「ヒィーン」という妙な音、
最初はマイクノイズだと信じて疑わなかったのですが、
どうも何かの楽器の音のようで、その音は必ず、
曲の中の同じ部分で同じように出てきています。
また、タイトルの語感もまた当時は不思議でした。
というのも、StreetはFightingにかかる言葉で、
Manはそれらをまとめて受けるという形になじみがなかったから。
ストーンズの魅力のひとつに、これといい、Tr4といい、
そしてかの名曲Jumpin' Jack Flashといい、
独特の語感もまたあると思います。
それにしてもすごい、すごすぎる!
これぞまさしくロックの中のロック、歴史的名曲ですね。
Tr7:Prodigal Son
同じくアコースティックギターを中心に据えながらも、
カントリーやブルーズというよりは、トラッド風の軽快な曲。
社会風刺が効いた前の曲の毒消しのような穏やかさ、
この2曲が並ぶことがストーンズの凄みだと実感。
レッド・ツェッペリンの3枚目に通じるものがあります。
Tr8:Stray Cat Blues
このアルバムでエレクトリックギターが前面に出ている曲は、
考えてみれば、Tr1とこれだけなんだ。
そのせいか気のせいか(笑)、Tr1の続編というか、
「裏側を暴く」ような迫りくる不気味な響きに支配されている曲。
あ。
ふむふむ、そうかそうか。
僕は、もちろんビートルズを聴いてきていたので、
昔からアコースティック・ギターの音に抵抗はないのですが、
ストーンズには、もっと激しく攻める音を期待していたために、
アコースティック中心で肩透かしをくらったというか、
期待にそぐわなかった、と感じたのかもしれません。
でもかといって、当時この曲で過剰に反応したわけでもなく、
これは、2002年に聴き直すまで頭の外にありました・・・
というわけで今は、
アコースティック・ギターを前面に出したアルバムとして、
このアルバムはロック界でも屈指の出来だと思います。
ところで、ストレイ・キャッツは、この曲から名前つけたのかな・・・
ローリング・ストーンズも、
マディ・ウォーターズの曲から名前をつけてますが、
そういうつながりは、ロック好きとしてはうれしいものです。
Tr9:Factory Girl
ということでやはりアコースティックに戻る。
メロディがどことなく東洋風でありながら、
英国の片田舎も想像させる不思議な響きの曲。
このアルバムは不思議な曲が多いんですが、
若い頃にはそれも理解できなかったのかもしれません。
ただ、Tr4と同じく未完の一片という感じもしないでもない。
マンドリンの音がいい雰囲気。
偶然かどうか分からないですが、この2年後に出た
ロッド・スチュワートのGasoline Alleyもなぜか東洋風メロディで
マンドリンを使っていて、この2曲、雰囲気とてもよく似てます。
インド音楽の影響もあるのかもしれないですが。
Tr10:Salt Of The Earth
結局最後までアコースティックで押し通す。
若い頃、Tr7以降は、なんとなく盛り上がらないまま終わる、
と感じていたように思います(或いは覚えていないか・・・)
この曲は、リマスターとは別に、つい最近大好きになりました。
彼らが主催した1968年のテレビショーのライヴ盤である
ROCK AND ROLL CIRCUSでこの曲を聴いたのがきっかけ。
そのショーで、ストーンズのメンバーは魔法使いのような服装で、
まるで「笑点」の桂歌丸師匠のように客席に混ざって座り、
アコースティックギターでこれを歌っていました。
そこにはジョンやヨーコ、クラプトンの姿も。
曲は、ピアノとスライドギターもいい雰囲気。
一部をキースが歌うのがまたかっこいい。
彼らにしては珍しく(!?)
肯定的かつ優しいメッセージを感じる曲で、
彼らのアコースティックサイドでは最高傑作かもしれません。
それもまたしかし、後から思ったことなのですが・・・
余談、そるとさんの名前は、最初はてっきり、
この曲から取ったものだと思い込んでいました(笑)。
そして今思い出したことがあります。
これを最初に買った当時、このアルバムには、
Jumpin' Jack Flashが入っているものだと思い込んでいたのですが、
いざ聴くと入っていなくてがっかり、そして失敗したと思った、
そんな記憶があります。
今思うと、どうして事前に調べなかったのかというところですが(笑)。
ただ、それ以上に、そろそろストーンズの古いのも聴きたい、
と思っていたその勢いで買ったものではあるでしょう。
今思うと、元々彼らもアコースティックギターは使ってましたが、
ここでこの時期にアコースティックギターを多用することにより、
トゲトゲしさや激しさを薄めつつ、ソフトを加味するなど、
別の方向性、可能性を求めた転換期にあった作品かもしれません。
そんなこと、二十歳そこそこの若造が
なかなか気づくものではないでしょうかね(笑)。
05 アンモナイトや化石が含まれた「石」をハウが・・・

アンモナイトもハウの前には置いておけないのか・・・(笑)。



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト


























