2017年12月31日
ヴァン・モリソン2枚と今年の新譜CD
01

大晦日。
今はもうそれほどたくさんCDを買っていないので、
昨年までのように新譜だけでTop10というわけにもゆかず。
そこで今年は弟が買ったものも含めて、
よく聴いた洋楽新譜CDをすべてさらりと紹介します。
☆1枚目
ROLL WITH THE PUNCHES
Van Morrison
(2017)
今年いちばんよかったのはやっぱりヴァン・モリソン!
昨年も新譜を出しましたが、もう出るのかと驚いた。
しかもというかしかしというか、これが素晴らしい!
正直、ここ10年くらいのヴァン・モリソンの新譜では
いちばん好きです、もちろん他も素晴らしいのですが。
音的にいえば「ロック以前のR&Bヒット曲」といった趣き。
強調したいのは「ヒット曲」という部分、つまり聴きやすい。
ブルーズなんだけど完全なブルーズではなくて、
かといってソウルとまでは至っていない。
歌手でいえばボビー・ブルー・ブランドのような味わい。
ジェフ・ベックが参加しているのも大きい。
ヴァン・モリソンに名のあるアーティストが参加するのは珍しい。
しかもそれが超大物ジェフ・ベックとくれば、お得感満載(笑)。
ジェフとは60年代ロックの興隆期に競い合ってきたわけだし、
ジェフもまた「ロック以前のR&Bヒット曲」が大好きなのでしょうね。
当然のことながらギターも攻めていて、その部分は
今までのヴァン・モリソンにはなかった醍醐味です。
僕のベスト曲はTransformation。
ぐにょっとしたバラード風のスロウな曲ですが、
この味わい深さがたまらない。
大物がもうひとりクリス・ファーロウが参加していますが、
彼の暖かくてユーモラスな低音がここでは抑え気味に
ヴァン・モリソンを支えています。
当然彼が前面に出た曲もありますが、これもまたいい。
もう1曲、サム・クックのあのBring It On Home To Me。
僕ですら中学時代から知っていたもう手垢まみれのこの曲、
まだこんなやり方があったのかと驚き感動しました。
もうこれは完全にヴァン・モリソンの曲といえますね。
今年のベストはヴァン・モリソンのこれです!
そして僕のベスト曲を。
☆
Transformation
Van Morrison
(2017)
☆2枚目
VERSATILE
Van Morrison
(2017)
ヴァン・モリソンはしかも、2年連続の上に1年2枚!!
今年はヴァン・モリソン・イヤーと名づけましょう。
こちらは「多様性」というタイトル通り、自作曲から
ガーシュウィンやコール・ポーターといったスタンダード、
「想い出のサンフランシスコ」といった有名曲までを集めた1枚。
ROLL...がR&Bサイドならこちらはジャズサイド。
どちらもヴァン・モリソンの根幹をなす音楽であるわけですが、
ジャズが好きというよりはジャズが当たり前に身の周りにある、
ヴァン・モリソンとはそういう人なんだと思いました。
正直いうと僕はROLL..の方が断然好きです。
僕はジャズにはあまりなじんできていないロック人間である、
ということがよく分かりました。
その上かつての僕はアルバム至上主義者だった名残りで、
ROLL...のようにぴしっと筋が通ったアルバムの方を、
うん、今でもやっぱりどちらをといわれれば取りますね。
もちろんこのアルバムも素晴らしいと思うし好きですが。
ただ、ROLL...はしっかりとアルバムを聴く時に聴きたい1枚ですが、
VERSATILEは逆に気軽に聴けるのはいい点ですね。
僕のベスト曲はヴァンさん自作のBroken Record。
冒頭からスウィングでのせてくれますが、タイトルの如く、
"Talking like this"と執拗なまでに繰り返す。
ヴァン・モリソン得意技早くも炸裂ですが、もしかして
ほんとうにあの言葉の繰り返しはまるで擦り切れた
レコードのようだ、と言われたことがあるのかも。
その自分に向けた茶化し精神がたまらない。
もう1曲カヴァーでBye Bye Blackbird。
僕はジョー・コッカーで知った曲ですが、やはり全然違う。
真面目に歌ったジョー・コッカーが聴くと怒るんじゃないか、
というくらいに手を抜いています、もちろんいい意味で、
そのぬるさが持ち味でしょうね。
タイトルの「多様性」は生き物に関わる僕としても
大切にしたい言葉ではあります。
2017年の洋楽はヴァン・モリソンの年でした!
☆3枚目
THE GREATEST HITS LIVE
Steve Winwood
(2017)
スティーヴ・ウィンウッドのこれが素晴らしい!
その通り、トラフィックから2000年代のソロまでを、
ライヴで振り返る素晴らしい企画、演奏、そして歌。
僕のベスト曲はThe Low Spark Of High Heeled Boys。
こうした企画盤、ベストやライヴって、知ってはいたけれど
こんなにいい曲だったかと思い直すことが多いですよね。
今回はこれがそうでした。
トラフィックが一度解散し再結成した1971年の曲で、
それが入ったアルバムも好きですが、アルバムだと
流れて聴いて曲として浮かび上がりにくいのかもしれない。
カヴァーもあります。
ティミ・トーマスのWhy Can't We Live Together。
2003年のABOUT TIMEからの曲ということになりますが、
僕はそのアルバムがスティーヴのそろではいちばん好きで、
その時からこれは大好きだったので、これが入っていたのは
いろんな意味で嬉しかった。
これももう完全にスティーヴの曲になっていますね。
そしてWhile You See A Chanceでは、2011年に
エリック・クラプトンと札幌に来てくれた時のことを思い出し、
また違った趣きと感動がありました。
当然というかこのアルバムにエリックはいないですが。
エリック絡みでもう1曲、
ブラインド・フェイスのHad To Cry Today。
パワフルさは微塵も失われていない。
円熟はしているけれど若さも保っている。
スティーヴ・ウィンウッドとはそんな恐るべき人なのです。
80年代男としてはThe Finer Thingsが入っていないのが
まあ残念ですが、こういう企画ではそれを言ってもしょうがない。
スティーヴ自身もその曲は好きじゃないかもしれないし(笑)。
まあでも最高に素晴らしいベストライヴアルバムです。
☆4枚目
CARRY FIRE
Robert Plant
(2017)
ロバート・プラント。
元レッド・ツェッペリン。
もちろんそのことを僕も常に意識しますが、悲しいかな、
と言っておく、今のアルバムを聴く時にはもうそのことを
頭から追いやってしまいたい。
今の彼の音楽は「中東風エスニックアコースティック路線」。
前々作、前作ととっても気に入っていたのですが、
今回もやっぱりそれと同じかそれ以上に気に入った。
つまり僕はこの路線がそもそも好きなのでしょう。
人それぞれだから、プラントにはツェッペリンのような
ハードロックを今でも求めているというのであればそれでいい。
だけどやっぱり、プラントがやりたいことに素直に耳を傾けて、
この路線も聴いていただきたいというのが本音ではありますね。
ただ時々、ツェッペリン時代の自分をまるでおちょくるかのような
今回でいえば2曲目冒頭のハードなギターのような音が混ざるのは、
さすが英国人と思わざるを得ないですね。
僕のベスト曲は3曲目Season's Song。
穏やかに愛を語るバラード風の曲ですが、よぉ~く聴くと、Aメロの
歌メロがエルヴィス・プレスリーのDon't Be Cruelに似てる。
そうだった、プラントはエルヴィスフリークでもあるんだ。
うん、悲しいかなと言ったけど、やっぱりツェッペリンとは
切り離せない、昔の上に今がある。
でも、だからこそやっぱり聴いてほしいのです。
この曲のタイトルもいいですよね。
そういう世界観もまた僕は好きなのです。
☆5枚目
NOW
Shania Twain
(2017)
シャナイア・トウェイン実に17年振りの新作。
僕も期待していましたが、ビルボードアルバムチャート
初登場No.1を記録。
アルバムとして端的にいえば聴きやすくていいです。
You're Still The OneやUpのようなキラーチューンはないけれど、
曲はどれも歌心をしっかりと刺激してくれる。
全体のイメージはカントリーというよりはアメリカーナかな。
少なくともどカントリーではないし、かといって
テイラー・スウィフトのような王道ポップスでもない。
もしそうだとすればこれからも期待できますね。
でも10年も待てない、3年以内に次作を出して欲しいな。
ベスト曲は2曲目Home Now。
アメリカのカントリーサイドからアイルランドにつながる。
カントリーといえばカントリーだけど、カントリーも含めたものが
アメリカーナだということなのでしょうね。
このアルバムも根詰めて聴くというよりは気楽に聴きたい1枚。
もちろん僕にとっては、です。
☆6枚目
GIVE MORE LOVE
Ringo Starr
(2017)
今朝6時のNHKニュースで、リンゴ・スターに
英国ナイトの称号が送られることになったと聞きました。
これでリンゴも「サー」になるわけですが、嬉しいことです。
そう、NHKではリンゴは今でも音楽活動をしていることを
殊更強調していたのですが、そこは本人も強調したいところで、
ちょっとだけNHKを見直しました(笑)。
今回もオールスターのメンバーのスティーヴ・ルカサーをはじめ、
ジョー・ウォルシュ、ピーター・フランプトン、ジェフ・リン、
デイヴ・スチュワートといった旧友総出でリンゴを支える。
ほんとうに人徳の厚い人なのですね。
アルバムはもうリンゴといえばこうという音で、
それが嫌いなら聴かなければそれでいい、ただそれだけ。
曲はすべてリンゴと参加メンバー誰かの共作ですが、
僕としては1曲は有名な曲のカヴァーを入れてほしかった。
というのも5年前の前々作に収められていたバディ・ホリーの
Think It Overがよかったからで、前作は(今見直すと)すべて
オリジナル曲だったから、僕も古いねぇ、となるのかな。
リンゴはまだまだ元気で音楽を楽しんでほしいですね。
☆7枚目
THE VISITOR
Neil Young and Promise Of The Real
(2017)
12月に出たばかりでまだ数回しか聴いていない
ニール・ヤング&プロミス・オヴ・ザ・リアルの新作。
ニール・ヤングは今年は過去音源発掘シリーズの
HITCHHIKERも出ていましたが、純粋な新録音である
こちらを取り上げることにします。
バンド名はついているこれはニール・ヤングの今の
ハードな面を出すためのバンドということになるでしょう。
今回は妙なフレーズが耳にこびりつく曲が多いですね。
典型的なのがベスト曲でもある5曲目Carnival。
珍しくラテンのノリにラテンっぽい哀愁系の歌メロで
"Carnival"とコーラスを繰り返すサビは、な、な、なんだ、と。
でも何度か聴くとやっぱり心のどこかに突き刺さって来るのが
ニール・ヤングのニール・ヤングらしいところで、
そこはいささかも失われていないのはよかったです。
これから聴いてゆくかな。
☆8枚目
DARK MATTER
Randy Newman
(2017)
ランディ・ニューマンのこの新譜は8月に出ていたことを
12月になって知り慌てて買ったもの、間に合ってよかった。
ランディ・ニューマンって「大阪のおばちゃん」みたい。
男性ですが、でも「おばちゃん」。
いやこれは僕の勝手なイメージでしかないのですが、
そうかそういうノリの人だったかとあらためて思いました。
音楽でいえば、この人は南部のスウィング感覚が
体の芯までしみ込んでいる人なのだとこちらも再認識。
ロックンロールとかできないのかなぁ。
あ、別にやらなくてもいい、人それぞれ個性があるから、
でもロックンロールを変に歌う「大阪のおばちゃん」を
勝手に想像してひとりで笑ってしまう僕なのでした。
まあ、楽しめる1枚、いい意味で相変わらず、よかったです。
まだ数回しか聴いていなくてベスト曲は選べませんでした。
☆9枚目
HERE
Alicia Keys
(2016)
2016年後半に出て昨年取り上げなかった2枚にも触れます。
アリシア・キーズ現時点での最新作。
これがですね、正直最初は「むむむっ」と。
生の感覚というか、ちょっと昔風にいえばアーシーな音。
都会的に洗練されたネオソウルとは違う。
こんなざらざらした音もできたんだって、ひとまず感心。
でも、2009年リリースのTHE ELEMENT OF FREEDOMを
2000年代で好きなアルバムTOP10くらいに好きな僕としては、
これはちょっと違うのではないかと。
買って10日ほどで何度か聴いて、暫く塩漬けにしておいて、
この記事を書くのに10か月ぶりくらいに聴いたのです、実は。
印象は変わらなかった。
でも、その音が好きな自分がいた。
遅くなりましたがこれから聴き込んでゆくつもりです。
だからこのアルバムのベスト曲はまだ選べません、悪しからず。
☆10枚目
DARKNESS AND LIGHT
John Legend
(2016)
なんだ、結局10枚になりましたね(笑)。
ジョン・レジェンドのこれも2月に既に出ていたことを知り、
やはり慌てて買いました(慌てる必要ないのかも、ですが)。
まあAll Of Meのような大量殺戮キラーチューンは
そうめったに出るものではないとして、それは事前から
そうだろうとは思っていましたが、それを抜きにすれば
やっぱりいい歌が多くて素晴らしい。
Love Me Nowなんて最高レベルのヒット曲だし。
ただこれ、All...とは正反対、アップテンポでなんだか
焦るような、煽るような感じの曲ではあります。
今回は音楽的ギミック感に凝っている曲が多くて、
作り込んでいる感じが強く、その点ややロック寄りかもしれない。
そしてだから僕はそこが好きなのかもしれない。
しかしその割に全体的に落ち着いた雰囲気なのは、
もはや10年選手となった貫禄がもたらすものなのでしょう。
ベスト曲は1曲目I Know Better。
これですが、最初に聴いてローリング・ストーンズの
You Can Always Get What You Wantに似てるなぁ、と。
パクリとかではなくて、でも雰囲気似せてるかもしれない。
ジョン・レジェンドは僕の中で安定期に入りました。
今回記事のために久し振りに聴いて、やっぱりよかったし。
クラシックからも新録音の新譜を1枚。
☆
SIBELIUS
Leif Ove Andsnes
(2017)
クラシックで新録音の新譜は今年はこれ1枚しか買っておらず、
しかもこれも12月になってから知ってのものでしたが、
買ってからは毎日聴いているので取り上げました。
日本盤には「悲しきワルツ~シベリウス」と邦題がついていますが、
その通り、シベリウスのピアノ小品を集めた1枚です。
最近ショパン以外のピアノ曲を聴きたくて(ショパンはあるから)、
でもピアノソナタとなると多少は構えて聴かなきゃと思ってしまう、
何かいいのがないかなと思っていたところでこれをネットで発見。
感情が零れ落ちてゆくような繊細な響きの音は冬によく合う。
アンスヌスはノルウェイのピアニスト、フィンランドではないですが、
まあ北欧ということでイメージは損なわれるものではないですね。
ただ、録音の音が低くて音が小さいのがやや難点かな。
そういうイメージの曲に合っているといえばそうかもですが。
そして、うん、やっぱり今年はこれに触れないわけにはゆかない。
GREATEST HITS
Tom Petty & The Heartbreakers
(1993)
トム・ペティの死。
いまだにそれを語りたいとは思えない。
さすがにもう受け入れてはいるのですが。
シャナイア・トウェインがビルボード初登場No.1の週に
2位だったのがトム達のこのベスト盤でした。
もう14年前に出たアルバムですが、それが2位まで上がる、
シャナイアが相手じゃなきゃ1位だったかもしれないというくらいに
トム・ペティはアメリカで広く親しまれ人気があったんですね。
☆
Refugee
Tom Petty & The Hearbreakers
(1979)
さて、今年もお読みいただきありがとうございました。
どれくらいのペースになるか分からないけれど、
来年もまたよろしくお願いします!

大晦日。
今はもうそれほどたくさんCDを買っていないので、
昨年までのように新譜だけでTop10というわけにもゆかず。
そこで今年は弟が買ったものも含めて、
よく聴いた洋楽新譜CDをすべてさらりと紹介します。
☆1枚目
ROLL WITH THE PUNCHES
Van Morrison
(2017)
今年いちばんよかったのはやっぱりヴァン・モリソン!
昨年も新譜を出しましたが、もう出るのかと驚いた。
しかもというかしかしというか、これが素晴らしい!
正直、ここ10年くらいのヴァン・モリソンの新譜では
いちばん好きです、もちろん他も素晴らしいのですが。
音的にいえば「ロック以前のR&Bヒット曲」といった趣き。
強調したいのは「ヒット曲」という部分、つまり聴きやすい。
ブルーズなんだけど完全なブルーズではなくて、
かといってソウルとまでは至っていない。
歌手でいえばボビー・ブルー・ブランドのような味わい。
ジェフ・ベックが参加しているのも大きい。
ヴァン・モリソンに名のあるアーティストが参加するのは珍しい。
しかもそれが超大物ジェフ・ベックとくれば、お得感満載(笑)。
ジェフとは60年代ロックの興隆期に競い合ってきたわけだし、
ジェフもまた「ロック以前のR&Bヒット曲」が大好きなのでしょうね。
当然のことながらギターも攻めていて、その部分は
今までのヴァン・モリソンにはなかった醍醐味です。
僕のベスト曲はTransformation。
ぐにょっとしたバラード風のスロウな曲ですが、
この味わい深さがたまらない。
大物がもうひとりクリス・ファーロウが参加していますが、
彼の暖かくてユーモラスな低音がここでは抑え気味に
ヴァン・モリソンを支えています。
当然彼が前面に出た曲もありますが、これもまたいい。
もう1曲、サム・クックのあのBring It On Home To Me。
僕ですら中学時代から知っていたもう手垢まみれのこの曲、
まだこんなやり方があったのかと驚き感動しました。
もうこれは完全にヴァン・モリソンの曲といえますね。
今年のベストはヴァン・モリソンのこれです!
そして僕のベスト曲を。
☆
Transformation
Van Morrison
(2017)
☆2枚目
VERSATILE
Van Morrison
(2017)
ヴァン・モリソンはしかも、2年連続の上に1年2枚!!
今年はヴァン・モリソン・イヤーと名づけましょう。
こちらは「多様性」というタイトル通り、自作曲から
ガーシュウィンやコール・ポーターといったスタンダード、
「想い出のサンフランシスコ」といった有名曲までを集めた1枚。
ROLL...がR&Bサイドならこちらはジャズサイド。
どちらもヴァン・モリソンの根幹をなす音楽であるわけですが、
ジャズが好きというよりはジャズが当たり前に身の周りにある、
ヴァン・モリソンとはそういう人なんだと思いました。
正直いうと僕はROLL..の方が断然好きです。
僕はジャズにはあまりなじんできていないロック人間である、
ということがよく分かりました。
その上かつての僕はアルバム至上主義者だった名残りで、
ROLL...のようにぴしっと筋が通ったアルバムの方を、
うん、今でもやっぱりどちらをといわれれば取りますね。
もちろんこのアルバムも素晴らしいと思うし好きですが。
ただ、ROLL...はしっかりとアルバムを聴く時に聴きたい1枚ですが、
VERSATILEは逆に気軽に聴けるのはいい点ですね。
僕のベスト曲はヴァンさん自作のBroken Record。
冒頭からスウィングでのせてくれますが、タイトルの如く、
"Talking like this"と執拗なまでに繰り返す。
ヴァン・モリソン得意技早くも炸裂ですが、もしかして
ほんとうにあの言葉の繰り返しはまるで擦り切れた
レコードのようだ、と言われたことがあるのかも。
その自分に向けた茶化し精神がたまらない。
もう1曲カヴァーでBye Bye Blackbird。
僕はジョー・コッカーで知った曲ですが、やはり全然違う。
真面目に歌ったジョー・コッカーが聴くと怒るんじゃないか、
というくらいに手を抜いています、もちろんいい意味で、
そのぬるさが持ち味でしょうね。
タイトルの「多様性」は生き物に関わる僕としても
大切にしたい言葉ではあります。
2017年の洋楽はヴァン・モリソンの年でした!
☆3枚目
THE GREATEST HITS LIVE
Steve Winwood
(2017)
スティーヴ・ウィンウッドのこれが素晴らしい!
その通り、トラフィックから2000年代のソロまでを、
ライヴで振り返る素晴らしい企画、演奏、そして歌。
僕のベスト曲はThe Low Spark Of High Heeled Boys。
こうした企画盤、ベストやライヴって、知ってはいたけれど
こんなにいい曲だったかと思い直すことが多いですよね。
今回はこれがそうでした。
トラフィックが一度解散し再結成した1971年の曲で、
それが入ったアルバムも好きですが、アルバムだと
流れて聴いて曲として浮かび上がりにくいのかもしれない。
カヴァーもあります。
ティミ・トーマスのWhy Can't We Live Together。
2003年のABOUT TIMEからの曲ということになりますが、
僕はそのアルバムがスティーヴのそろではいちばん好きで、
その時からこれは大好きだったので、これが入っていたのは
いろんな意味で嬉しかった。
これももう完全にスティーヴの曲になっていますね。
そしてWhile You See A Chanceでは、2011年に
エリック・クラプトンと札幌に来てくれた時のことを思い出し、
また違った趣きと感動がありました。
当然というかこのアルバムにエリックはいないですが。
エリック絡みでもう1曲、
ブラインド・フェイスのHad To Cry Today。
パワフルさは微塵も失われていない。
円熟はしているけれど若さも保っている。
スティーヴ・ウィンウッドとはそんな恐るべき人なのです。
80年代男としてはThe Finer Thingsが入っていないのが
まあ残念ですが、こういう企画ではそれを言ってもしょうがない。
スティーヴ自身もその曲は好きじゃないかもしれないし(笑)。
まあでも最高に素晴らしいベストライヴアルバムです。
☆4枚目
CARRY FIRE
Robert Plant
(2017)
ロバート・プラント。
元レッド・ツェッペリン。
もちろんそのことを僕も常に意識しますが、悲しいかな、
と言っておく、今のアルバムを聴く時にはもうそのことを
頭から追いやってしまいたい。
今の彼の音楽は「中東風エスニックアコースティック路線」。
前々作、前作ととっても気に入っていたのですが、
今回もやっぱりそれと同じかそれ以上に気に入った。
つまり僕はこの路線がそもそも好きなのでしょう。
人それぞれだから、プラントにはツェッペリンのような
ハードロックを今でも求めているというのであればそれでいい。
だけどやっぱり、プラントがやりたいことに素直に耳を傾けて、
この路線も聴いていただきたいというのが本音ではありますね。
ただ時々、ツェッペリン時代の自分をまるでおちょくるかのような
今回でいえば2曲目冒頭のハードなギターのような音が混ざるのは、
さすが英国人と思わざるを得ないですね。
僕のベスト曲は3曲目Season's Song。
穏やかに愛を語るバラード風の曲ですが、よぉ~く聴くと、Aメロの
歌メロがエルヴィス・プレスリーのDon't Be Cruelに似てる。
そうだった、プラントはエルヴィスフリークでもあるんだ。
うん、悲しいかなと言ったけど、やっぱりツェッペリンとは
切り離せない、昔の上に今がある。
でも、だからこそやっぱり聴いてほしいのです。
この曲のタイトルもいいですよね。
そういう世界観もまた僕は好きなのです。
☆5枚目
NOW
Shania Twain
(2017)
シャナイア・トウェイン実に17年振りの新作。
僕も期待していましたが、ビルボードアルバムチャート
初登場No.1を記録。
アルバムとして端的にいえば聴きやすくていいです。
You're Still The OneやUpのようなキラーチューンはないけれど、
曲はどれも歌心をしっかりと刺激してくれる。
全体のイメージはカントリーというよりはアメリカーナかな。
少なくともどカントリーではないし、かといって
テイラー・スウィフトのような王道ポップスでもない。
もしそうだとすればこれからも期待できますね。
でも10年も待てない、3年以内に次作を出して欲しいな。
ベスト曲は2曲目Home Now。
アメリカのカントリーサイドからアイルランドにつながる。
カントリーといえばカントリーだけど、カントリーも含めたものが
アメリカーナだということなのでしょうね。
このアルバムも根詰めて聴くというよりは気楽に聴きたい1枚。
もちろん僕にとっては、です。
☆6枚目
GIVE MORE LOVE
Ringo Starr
(2017)
今朝6時のNHKニュースで、リンゴ・スターに
英国ナイトの称号が送られることになったと聞きました。
これでリンゴも「サー」になるわけですが、嬉しいことです。
そう、NHKではリンゴは今でも音楽活動をしていることを
殊更強調していたのですが、そこは本人も強調したいところで、
ちょっとだけNHKを見直しました(笑)。
今回もオールスターのメンバーのスティーヴ・ルカサーをはじめ、
ジョー・ウォルシュ、ピーター・フランプトン、ジェフ・リン、
デイヴ・スチュワートといった旧友総出でリンゴを支える。
ほんとうに人徳の厚い人なのですね。
アルバムはもうリンゴといえばこうという音で、
それが嫌いなら聴かなければそれでいい、ただそれだけ。
曲はすべてリンゴと参加メンバー誰かの共作ですが、
僕としては1曲は有名な曲のカヴァーを入れてほしかった。
というのも5年前の前々作に収められていたバディ・ホリーの
Think It Overがよかったからで、前作は(今見直すと)すべて
オリジナル曲だったから、僕も古いねぇ、となるのかな。
リンゴはまだまだ元気で音楽を楽しんでほしいですね。
☆7枚目
THE VISITOR
Neil Young and Promise Of The Real
(2017)
12月に出たばかりでまだ数回しか聴いていない
ニール・ヤング&プロミス・オヴ・ザ・リアルの新作。
ニール・ヤングは今年は過去音源発掘シリーズの
HITCHHIKERも出ていましたが、純粋な新録音である
こちらを取り上げることにします。
バンド名はついているこれはニール・ヤングの今の
ハードな面を出すためのバンドということになるでしょう。
今回は妙なフレーズが耳にこびりつく曲が多いですね。
典型的なのがベスト曲でもある5曲目Carnival。
珍しくラテンのノリにラテンっぽい哀愁系の歌メロで
"Carnival"とコーラスを繰り返すサビは、な、な、なんだ、と。
でも何度か聴くとやっぱり心のどこかに突き刺さって来るのが
ニール・ヤングのニール・ヤングらしいところで、
そこはいささかも失われていないのはよかったです。
これから聴いてゆくかな。
☆8枚目
DARK MATTER
Randy Newman
(2017)
ランディ・ニューマンのこの新譜は8月に出ていたことを
12月になって知り慌てて買ったもの、間に合ってよかった。
ランディ・ニューマンって「大阪のおばちゃん」みたい。
男性ですが、でも「おばちゃん」。
いやこれは僕の勝手なイメージでしかないのですが、
そうかそういうノリの人だったかとあらためて思いました。
音楽でいえば、この人は南部のスウィング感覚が
体の芯までしみ込んでいる人なのだとこちらも再認識。
ロックンロールとかできないのかなぁ。
あ、別にやらなくてもいい、人それぞれ個性があるから、
でもロックンロールを変に歌う「大阪のおばちゃん」を
勝手に想像してひとりで笑ってしまう僕なのでした。
まあ、楽しめる1枚、いい意味で相変わらず、よかったです。
まだ数回しか聴いていなくてベスト曲は選べませんでした。
☆9枚目
HERE
Alicia Keys
(2016)
2016年後半に出て昨年取り上げなかった2枚にも触れます。
アリシア・キーズ現時点での最新作。
これがですね、正直最初は「むむむっ」と。
生の感覚というか、ちょっと昔風にいえばアーシーな音。
都会的に洗練されたネオソウルとは違う。
こんなざらざらした音もできたんだって、ひとまず感心。
でも、2009年リリースのTHE ELEMENT OF FREEDOMを
2000年代で好きなアルバムTOP10くらいに好きな僕としては、
これはちょっと違うのではないかと。
買って10日ほどで何度か聴いて、暫く塩漬けにしておいて、
この記事を書くのに10か月ぶりくらいに聴いたのです、実は。
印象は変わらなかった。
でも、その音が好きな自分がいた。
遅くなりましたがこれから聴き込んでゆくつもりです。
だからこのアルバムのベスト曲はまだ選べません、悪しからず。
☆10枚目
DARKNESS AND LIGHT
John Legend
(2016)
なんだ、結局10枚になりましたね(笑)。
ジョン・レジェンドのこれも2月に既に出ていたことを知り、
やはり慌てて買いました(慌てる必要ないのかも、ですが)。
まあAll Of Meのような大量殺戮キラーチューンは
そうめったに出るものではないとして、それは事前から
そうだろうとは思っていましたが、それを抜きにすれば
やっぱりいい歌が多くて素晴らしい。
Love Me Nowなんて最高レベルのヒット曲だし。
ただこれ、All...とは正反対、アップテンポでなんだか
焦るような、煽るような感じの曲ではあります。
今回は音楽的ギミック感に凝っている曲が多くて、
作り込んでいる感じが強く、その点ややロック寄りかもしれない。
そしてだから僕はそこが好きなのかもしれない。
しかしその割に全体的に落ち着いた雰囲気なのは、
もはや10年選手となった貫禄がもたらすものなのでしょう。
ベスト曲は1曲目I Know Better。
これですが、最初に聴いてローリング・ストーンズの
You Can Always Get What You Wantに似てるなぁ、と。
パクリとかではなくて、でも雰囲気似せてるかもしれない。
ジョン・レジェンドは僕の中で安定期に入りました。
今回記事のために久し振りに聴いて、やっぱりよかったし。
クラシックからも新録音の新譜を1枚。
☆
SIBELIUS
Leif Ove Andsnes
(2017)
クラシックで新録音の新譜は今年はこれ1枚しか買っておらず、
しかもこれも12月になってから知ってのものでしたが、
買ってからは毎日聴いているので取り上げました。
日本盤には「悲しきワルツ~シベリウス」と邦題がついていますが、
その通り、シベリウスのピアノ小品を集めた1枚です。
最近ショパン以外のピアノ曲を聴きたくて(ショパンはあるから)、
でもピアノソナタとなると多少は構えて聴かなきゃと思ってしまう、
何かいいのがないかなと思っていたところでこれをネットで発見。
感情が零れ落ちてゆくような繊細な響きの音は冬によく合う。
アンスヌスはノルウェイのピアニスト、フィンランドではないですが、
まあ北欧ということでイメージは損なわれるものではないですね。
ただ、録音の音が低くて音が小さいのがやや難点かな。
そういうイメージの曲に合っているといえばそうかもですが。
そして、うん、やっぱり今年はこれに触れないわけにはゆかない。
GREATEST HITS
Tom Petty & The Heartbreakers
(1993)
トム・ペティの死。
いまだにそれを語りたいとは思えない。
さすがにもう受け入れてはいるのですが。
シャナイア・トウェインがビルボード初登場No.1の週に
2位だったのがトム達のこのベスト盤でした。
もう14年前に出たアルバムですが、それが2位まで上がる、
シャナイアが相手じゃなきゃ1位だったかもしれないというくらいに
トム・ペティはアメリカで広く親しまれ人気があったんですね。
☆
Refugee
Tom Petty & The Hearbreakers
(1979)
さて、今年もお読みいただきありがとうございました。
どれくらいのペースになるか分からないけれど、
来年もまたよろしくお願いします!
2017年03月13日
BLUE AND LONESOME ローリング・ストーンズ
01

BLUE AND LONESOME
Rolling Stones
ブルー・アンド・ロンサム
ローリング・ストーンズ
(2016)
ローリング・ストーンズの新譜の話をします。
昨年12月にリリースされたBLUE AND LONESOME
あのストーンズが原点に立ち返ってブルーズのカヴァーをやる。
大きな期待を持って迎えられました。
まあ僕もその口のひとりではありましたが。
リリースされるともう絶賛の嵐。
このアルバムをいいと言わなければロックを聴いてはいけない。
とでもいいたいような勢いであったと、僕は感じていました。
「ローリング・ストーン」誌ではリリース後間もないというのに、
2016年ロックアルバム選上位に入っていて少々驚いたり。
まあ、RS誌はその名前からして当然でしょうけれど、でも
そうした雰囲気がネットで意見を書く人の間に漂っていた、
そんな感じを受けました。
そのことに対して批判するつもりも毛頭ありません。
ただ、僕はそう感じて、少しばかり恐かったのです。
しかし、次に書くことは多少批判めいているかもしれない、
という覚悟で続けます。
このアルバムをいいと思い、ブルーズが分からないと
ロックという音楽は分からないし聴いてはいけない。
そんな意識が見え隠れしてやいなかったかな、と、
これはあくまでも僕が感じたことですが。
僕はブルーズは好きです。
数年前からCDを買って聴くようになりました。
僕はブルーズを分かろうとして聴いていました。
ええ、カッコつけたかった部分もあったでしょう。
僕自身が、ブルーズを分からなければロックが分からない、
と思っていた節もありました。
でも、結局、僕にはブルーズは分からなかった。
もちろんこの人はブルーズだ、この音楽はブルーズっぽい
というのは頭では分かります。
でも、体、感覚では分からないし体現できない。
僕はバンドなど人前で演奏しない人間ではあり、
外国に行ったことがない日本人だからか、ブルーズの感覚が
頭ではなく体でなんて分かるはずがない。
ブルーズを歌うなんてできるわけがない。
じゃあ、ブルーズが「分かる」ってどういうことだ?
ここで「分かる」(わかる)という言葉を
「新明解国語辞典第7版」(三省堂)で引いてみると
わかる
未解決(未確認)の事柄について、推理・推論をめぐらしたり
適切な情報を拠りどころにしたり 実際に経験したりして、
確信の持てる(客観性のある)判断が下せる状態になる。
結構難しいですね(笑)。
僕が引っかかったのは「実際に経験したりして」の一文。
上記のように外国にも行ったことがないしバンドなど
人前で演奏したり歌ったりしたこともないので、
僕にはこの部分が欠けています。
この説明では書かれている全てが必須条件ではないと
受け取れますが、でもないよりはあった方がいいのでしょう。
だからやっぱり僕はブルーズは「分からない」。
昨年前半までの僕なら、そこである種の危機感を抱いたでしょう。
ブルーズが分からなきゃロックは分からないぜ。
だからこのアルバムは何が何でも分からなきゃいけないんだ。
僕自身ブルーズが分からないと認めたくなかったのもありました。
でも、今はもう音楽に対してある部分冷めたので、
それで焦ったりなんてことにはならなくなりました。
冷めたというか、冷静に聴けるようになったと
ここは前向きに解釈して先に進めます。
僕は結局ブルーズは分からなかったけれど、
ブルーズを聴くのは大好きになりました。
それまでの自分からすれば意外なほどに。
その結果が、ブルーズに「凝る」のではなく、
ブルーズを「ただ聴くのが楽しい」という境地に達しました。
境地というのも大袈裟か、今日の僕は大袈裟過ぎるかな(笑)。
あ、と思ったけど、60枚CDラックをブルーズ専用にして
それが埋まるほど買って聴いたので、凝ったといえばそうかな、
前言お詫びして訂正した方がいいかもしれない。
02

しばし休憩。
フィッシュアイレンズ=魚眼レンズを使うようになって、
今日が初めてのアルバム記事、ということで撮ってみました。
四角いはずのCDが線が曲がって写るのが面白い。
次もまたやってみよう。
閑話休題(長い閑話だった)。
ローリング・ストーンズのBLUE AND LONESOME
僕は、「普通にとてもいい」くらいに気に入りました。
もう少しいうと「予想していたよりはよかった」。
僕がそう感じたのは、単なるブルーズのコピーではなく、
もうこれはローリング・ストーンズでしかないと感じられたから。
全体のサウンド、チャーリー・ワッツのドラムスの感覚、
ギターの音色と入り方、そしてミック・ジャガーのヴォーカルまで、
僕には「ローリング・ストーンズにしか」聴こえませんでした。
特にミックのヴォーカルは最初に聴いた時(もう3か月前か)、
こりゃブルーズではなくどう聴いてもミックじゃないか
とスピーカーに向かって話しかけそうになったくらい。
ブルーズだと思って聴くとこれはある種滑稽な歌い方じゃない?
4曲目All Of Your Loveの最初"All"と叫ぶところなんか、もう。
6曲目"I was talking to the policeman"と歌うところの
声の軋みや刻み方もミックらしいし。
BLUE AND LONESOMEというアルバムタイトルが
そもそもストーンズらしいイディオムで、
僕は最初に聞いて笑ってしまいました。
(バカにするという意味では決してありません、念のため)。
ミック自身ももしかしてブルーズらしく歌わなくていい
と思えるようになったのではないか。
ミック自身の変化というより、世の中が受け入れるようになった、
ということなのかもしれないと思いました。
時々聴いています、1週間に2回くらいかな。
1月中盤からひと月「クラシック月間」には聴かなかったけれど、
その後やっぱりこれは好きだと思い直しそれくらい聴いてます。
僕にとっては根詰めて聴くものではないけれど、
時々聴くとかなりいい、という感じのアルバムです。
さてここで収録曲。
根詰めて聴いていないのでいつものように
各曲について具には書けません、悪しからず。
1曲目:Just Your Fool
2曲目:Commit A Crime
3曲目:Blue And Lonesome
4曲目:All Of Your Love
5曲目:I Gotta Go
6曲目:Everybody Knows About My Good Thing
7曲目:Ride'em On Down
8曲目:Hate To See You Go
9曲目:Hoo Doo Blues
10曲目:Little Rain
11曲目:Just Like I Treat You
12曲目:I Can't Quit You Baby
僕が知っていたのはたった1曲、12曲目。
レッド・ツェッペリンがアルバムで演奏しているからですが
(1枚目とCODA)、でもあれは最後が"Babe"だったから
これは同じ曲ではないのかな、と思ったり。
まあ僕のブルーズなんてそんなものです。
ただ、ですね、知らない古くていい曲を教えてくれるという点では
やっぱりローリング・ストーンズはロックであり続けている、
というのは嬉しいし心強いですね。
事実この中で新たに気に入った曲もあるし。
結局のところ、これはローリング・ストーンズだからいいのです。
僕はローリング・ストーンズが大好きなのだから、
という身も蓋もないことが今日の結論。
ただし、ブルーズが分からない人間だと自覚した今は、
ストーンズのどこが好きかも分からなくなったのですが・・・
ではアルバムから1曲。
☆
Hate To See You Go
Rolling Stones
(2016)
ところで、ストーンズのこのアルバムに対して感じたことに
デジャヴ感覚があることに気づきました。
ポール・マッカートニーのNEWが新譜で出た時。
やはりRS誌でその年のTop10以内に選ばれていました。
Top50のほとんどは若手であったのに、です。
(ジョン・フォガティもTop10に入っていたのは嬉しかったですが)。
若い聴き手に対してロックを作り上げてきた人だから、
これは聴いておきなさいという教示的な意味もあるのかな、と。
そしてやっぱり、そういう時代になったのかな。
音楽(に限らずだけど)の趣味が多様化し、
ネット上では、「思想」というと大袈裟かもだけど、
核となり拠り所となる考えが求められている。
僕みたいに、「分からないけどこれは好き」という思いは、
レコード盤に静電気で寄ってくる塵みたいなものであり、
戯言に過ぎないのかもしれないですね。
そしてこの記事は、僕のブルーズが分からないという恨み節、
でもありますかね。
まあそれでも、僕は基本、「わかる・わからない」よりは
「好きかどうか」で音楽の話を文章にしている人間だし、
ブルーズが分からない以上好きかどうかを書くしかできないので、
これからもそんな戯言記事を上げてゆこうとは思います。
繰り返し、音楽への愛情は薄れていませんからね。
最後は今朝の3ショットにて。
03


BLUE AND LONESOME
Rolling Stones
ブルー・アンド・ロンサム
ローリング・ストーンズ
(2016)
ローリング・ストーンズの新譜の話をします。
昨年12月にリリースされたBLUE AND LONESOME
あのストーンズが原点に立ち返ってブルーズのカヴァーをやる。
大きな期待を持って迎えられました。
まあ僕もその口のひとりではありましたが。
リリースされるともう絶賛の嵐。
このアルバムをいいと言わなければロックを聴いてはいけない。
とでもいいたいような勢いであったと、僕は感じていました。
「ローリング・ストーン」誌ではリリース後間もないというのに、
2016年ロックアルバム選上位に入っていて少々驚いたり。
まあ、RS誌はその名前からして当然でしょうけれど、でも
そうした雰囲気がネットで意見を書く人の間に漂っていた、
そんな感じを受けました。
そのことに対して批判するつもりも毛頭ありません。
ただ、僕はそう感じて、少しばかり恐かったのです。
しかし、次に書くことは多少批判めいているかもしれない、
という覚悟で続けます。
このアルバムをいいと思い、ブルーズが分からないと
ロックという音楽は分からないし聴いてはいけない。
そんな意識が見え隠れしてやいなかったかな、と、
これはあくまでも僕が感じたことですが。
僕はブルーズは好きです。
数年前からCDを買って聴くようになりました。
僕はブルーズを分かろうとして聴いていました。
ええ、カッコつけたかった部分もあったでしょう。
僕自身が、ブルーズを分からなければロックが分からない、
と思っていた節もありました。
でも、結局、僕にはブルーズは分からなかった。
もちろんこの人はブルーズだ、この音楽はブルーズっぽい
というのは頭では分かります。
でも、体、感覚では分からないし体現できない。
僕はバンドなど人前で演奏しない人間ではあり、
外国に行ったことがない日本人だからか、ブルーズの感覚が
頭ではなく体でなんて分かるはずがない。
ブルーズを歌うなんてできるわけがない。
じゃあ、ブルーズが「分かる」ってどういうことだ?
ここで「分かる」(わかる)という言葉を
「新明解国語辞典第7版」(三省堂)で引いてみると
わかる
未解決(未確認)の事柄について、推理・推論をめぐらしたり
適切な情報を拠りどころにしたり 実際に経験したりして、
確信の持てる(客観性のある)判断が下せる状態になる。
結構難しいですね(笑)。
僕が引っかかったのは「実際に経験したりして」の一文。
上記のように外国にも行ったことがないしバンドなど
人前で演奏したり歌ったりしたこともないので、
僕にはこの部分が欠けています。
この説明では書かれている全てが必須条件ではないと
受け取れますが、でもないよりはあった方がいいのでしょう。
だからやっぱり僕はブルーズは「分からない」。
昨年前半までの僕なら、そこである種の危機感を抱いたでしょう。
ブルーズが分からなきゃロックは分からないぜ。
だからこのアルバムは何が何でも分からなきゃいけないんだ。
僕自身ブルーズが分からないと認めたくなかったのもありました。
でも、今はもう音楽に対してある部分冷めたので、
それで焦ったりなんてことにはならなくなりました。
冷めたというか、冷静に聴けるようになったと
ここは前向きに解釈して先に進めます。
僕は結局ブルーズは分からなかったけれど、
ブルーズを聴くのは大好きになりました。
それまでの自分からすれば意外なほどに。
その結果が、ブルーズに「凝る」のではなく、
ブルーズを「ただ聴くのが楽しい」という境地に達しました。
境地というのも大袈裟か、今日の僕は大袈裟過ぎるかな(笑)。
あ、と思ったけど、60枚CDラックをブルーズ専用にして
それが埋まるほど買って聴いたので、凝ったといえばそうかな、
前言お詫びして訂正した方がいいかもしれない。
02

しばし休憩。
フィッシュアイレンズ=魚眼レンズを使うようになって、
今日が初めてのアルバム記事、ということで撮ってみました。
四角いはずのCDが線が曲がって写るのが面白い。
次もまたやってみよう。
閑話休題(長い閑話だった)。
ローリング・ストーンズのBLUE AND LONESOME
僕は、「普通にとてもいい」くらいに気に入りました。
もう少しいうと「予想していたよりはよかった」。
僕がそう感じたのは、単なるブルーズのコピーではなく、
もうこれはローリング・ストーンズでしかないと感じられたから。
全体のサウンド、チャーリー・ワッツのドラムスの感覚、
ギターの音色と入り方、そしてミック・ジャガーのヴォーカルまで、
僕には「ローリング・ストーンズにしか」聴こえませんでした。
特にミックのヴォーカルは最初に聴いた時(もう3か月前か)、
こりゃブルーズではなくどう聴いてもミックじゃないか
とスピーカーに向かって話しかけそうになったくらい。
ブルーズだと思って聴くとこれはある種滑稽な歌い方じゃない?
4曲目All Of Your Loveの最初"All"と叫ぶところなんか、もう。
6曲目"I was talking to the policeman"と歌うところの
声の軋みや刻み方もミックらしいし。
BLUE AND LONESOMEというアルバムタイトルが
そもそもストーンズらしいイディオムで、
僕は最初に聞いて笑ってしまいました。
(バカにするという意味では決してありません、念のため)。
ミック自身ももしかしてブルーズらしく歌わなくていい
と思えるようになったのではないか。
ミック自身の変化というより、世の中が受け入れるようになった、
ということなのかもしれないと思いました。
時々聴いています、1週間に2回くらいかな。
1月中盤からひと月「クラシック月間」には聴かなかったけれど、
その後やっぱりこれは好きだと思い直しそれくらい聴いてます。
僕にとっては根詰めて聴くものではないけれど、
時々聴くとかなりいい、という感じのアルバムです。
さてここで収録曲。
根詰めて聴いていないのでいつものように
各曲について具には書けません、悪しからず。
1曲目:Just Your Fool
2曲目:Commit A Crime
3曲目:Blue And Lonesome
4曲目:All Of Your Love
5曲目:I Gotta Go
6曲目:Everybody Knows About My Good Thing
7曲目:Ride'em On Down
8曲目:Hate To See You Go
9曲目:Hoo Doo Blues
10曲目:Little Rain
11曲目:Just Like I Treat You
12曲目:I Can't Quit You Baby
僕が知っていたのはたった1曲、12曲目。
レッド・ツェッペリンがアルバムで演奏しているからですが
(1枚目とCODA)、でもあれは最後が"Babe"だったから
これは同じ曲ではないのかな、と思ったり。
まあ僕のブルーズなんてそんなものです。
ただ、ですね、知らない古くていい曲を教えてくれるという点では
やっぱりローリング・ストーンズはロックであり続けている、
というのは嬉しいし心強いですね。
事実この中で新たに気に入った曲もあるし。
結局のところ、これはローリング・ストーンズだからいいのです。
僕はローリング・ストーンズが大好きなのだから、
という身も蓋もないことが今日の結論。
ただし、ブルーズが分からない人間だと自覚した今は、
ストーンズのどこが好きかも分からなくなったのですが・・・
ではアルバムから1曲。
☆
Hate To See You Go
Rolling Stones
(2016)
ところで、ストーンズのこのアルバムに対して感じたことに
デジャヴ感覚があることに気づきました。
ポール・マッカートニーのNEWが新譜で出た時。
やはりRS誌でその年のTop10以内に選ばれていました。
Top50のほとんどは若手であったのに、です。
(ジョン・フォガティもTop10に入っていたのは嬉しかったですが)。
若い聴き手に対してロックを作り上げてきた人だから、
これは聴いておきなさいという教示的な意味もあるのかな、と。
そしてやっぱり、そういう時代になったのかな。
音楽(に限らずだけど)の趣味が多様化し、
ネット上では、「思想」というと大袈裟かもだけど、
核となり拠り所となる考えが求められている。
僕みたいに、「分からないけどこれは好き」という思いは、
レコード盤に静電気で寄ってくる塵みたいなものであり、
戯言に過ぎないのかもしれないですね。
そしてこの記事は、僕のブルーズが分からないという恨み節、
でもありますかね。
まあそれでも、僕は基本、「わかる・わからない」よりは
「好きかどうか」で音楽の話を文章にしている人間だし、
ブルーズが分からない以上好きかどうかを書くしかできないので、
これからもそんな戯言記事を上げてゆこうとは思います。
繰り返し、音楽への愛情は薄れていませんからね。
最後は今朝の3ショットにて。
03

2016年12月31日
2016年新譜CDTop10プラス
01

大晦日。
その年に良かった新譜CDをまとめて紹介する記事です。
洋楽中心ですがクラシックの新譜もあります。
長いので早速。
【特別枠】 哀悼
2016年はこんな年でしたという記録と記憶の意味も込め、
もちろん哀悼の意を表するために
今年亡くなられた3人のCDから先に話します。
★1人目 デヴィッド・ボウイ
★(BLACK STAR)
David Bowie
(2016)
デヴィッド・ボウイの死の知らせは、僕のリアルタイムでは、
フレディ・マーキュリーと同じ、いやそれ以上の衝撃でした。
フレディの場合は病気であることを公表して割と早くに
亡くなったというショックでしたが、でも事前に知ってはいたから、
あまりの早さに驚いたという部分が大きかったような気が。
対してボウイは新作を1週間前に出したばかり、
病気のことはまったく知らなかっただけに、衝撃は大き過ぎた。
後からネットや本で見ると、ボウイは自分の死を悟った上で、
この録音に臨んでいたようですね。
ボウイは最期までボウイらしく演出していたという。
それは決して悪い意味ではなく、そういう不世出の人だったと。
ところでこのアルバム、実は昨日10か月ぶりに聴きました。
ボウイが命を懸けてまで作ったアルバムに対して、
僕はだんだんと身構えてしまい、軽々しく聴いていいものなのか
と自問自答した挙句、自信がなくなり聴かなくなったのでした。
10か月ぶりに聴いて、素晴らしい。
もうそのように身構えるのはやめ、もう少し気軽に、は無理でも
聴く機会を増やしてゆく方がボウイも喜んでくれるのではないか。
昨日、ようやくそう思うに至った、ということを白状しておきます。
★2人目 プリンス
HITNRUN PHASE TWO
Prince
(2016)
プリンスの死は、衝撃というよりも、なぜ、どうしてという
納得できないという思いが強かった、今でも。
ボウイの場合は遺作があのような内容だっただけに、
亡くなったことが実感できるのですが、
プリンスは正直いまだに死んだことが信じられない。
Warnerに復帰してからのプリンスは期待通りの作品を
聴かせてくれていましたが、今年も、亡くなってから出ました。
これがまたポップもポップでとっても聴きやすい1枚。
この明るさ、まあ当然といえば当然ですがボウイとは正反対、
死などまるで予感させないとにかく楽しいアルバム。
それだけ余計に死が悲しくなり、信じられなくもなりました。
プリンスはアルバム何百枚分の録音ストックがあるそうですが、
でも、今年のアルバムは当然彼自身の意志だとして、
それ以降については正面から受け止めて聴こうと思えるか。
手を加えないのであれば正真正銘プリンスではあるけれど、
そうか、プリンスの場合は中途半端なデモ状態ではなく、
出来上がったもののストックも多そうだから期待できるかな。
しかしそのようにリリースが続くと、僕はいったいいつになったら
プリンスの死を現実のものとして受け止められるのだろうか。
受け止めなくてもいいのかもしれないけれど。
ベストチューンは9曲目Screwdriver
異様なまでのポップさの中、"I'm your driver, you're my screw"と
恥じらうように歌うプリンスに不覚にも胸がきゅんとしてしまった。
これを聴くと、もうこの世にいないとは信じられないですね。
★3人目 ニコラウス・アーノンクール
BEETHOVEN : SYMPHONY NO.4 & NO.5
Nikolaus Harnoncout
Concertus Musicus Wien
(2016)
BEETHOVEN : MISSA SOLEMNIS
Nikolaus Harnoncourt (condt.)
Concentus Musicus Wien
(2016)
僕がいちばん好きな指揮者、ニコラウス・アーノンクール。
古楽器演奏での評価を受けて大指揮者になった人ですが、
サステインが短く切れがいい古楽器演奏の方法論を
モダン楽器にも活用して独特の音を聴かせる人でした。
ただ、その音の響きは審美的或いは耽美的ではなく、
カラヤンやバーンスタインといった大指揮者たちの音に慣れた
人にはともすれば「汚い」と捉えられかねない音なのです。
実は僕も、アーノンクールのブラームスはロマンが足りなくて
もう少し浸れる音で聴きたい、と思います。
しかし一方で、作曲された当時はこのように演奏され、
このように聴かれていたであろうことを想像させてくれる
という点ではむしろ新鮮な響きでもあります。
今回2枚あるのは、1枚が生前、もう1枚が死後に出たものだから。
どちらもベートーヴェンですが、前者が交響曲、後者がミサ曲。
交響曲第4番と第5番の組み合わせですが、これを買って
ライナーノーツには、交響曲全集を予定していたが完結することが
出来ず今回の2曲で終わりになる、と書かれていたのを読んで、
正直不安になりました。
それがあっての訃報だったので、ああそうだったか、と。
86歳だから天寿をまっとうしたといえるでしょうし、僕としても
それなりの覚悟があったのでショックは一瞬で収まりましたが、
やはり寂しさがじわじわとこみ上げてきました。
交響曲第4番は舞踏会のような雰囲気の明るい曲ですが、
浮ついた感がなく地に足がしっかりと着いた演奏。
舞踏ではなくあくまでも音楽が先という意識が感じられます。
だからCDとして聴くにはいい演奏ではないかと。
そして出来としては史上最高と言われる交響曲第5番。
その通り、美に流されると聴き逃してしまいがちな
構築性、テクスチャーが目に見えるように分かり、
説得力という点では僕が今まで聴いた5番では最高でした。
死後に出た「荘厳ミサ曲」は本当の最後の録音。
最後の録音がミサ曲というのは、うん、やっぱり、
予感というよりは準備をしていたのかなと思ってしまう。
リリース情報を知った時、やっぱりか、と思いました。
アーノンクールの死は、もちろん残念だしショックだけど、
今までほんとうにありがとう、ただこれだけを贈りたいです。
ちなみにこの曲は書籍「ベートーヴェンの交響曲」において
指揮者の金聖玉さんが「もっと日本でも注目されていい曲」
として紹介されていたということを付記しておきます。
そして通常のTop10に入ります。
☆1位 スティング
57TH & 9TH
Sting
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
もうほんと、スティングがロックに戻ってきた。
このフレーズを何回使ったか分からない。
それだけで嬉しいのです。
もちろんスティングらしい音楽で。
しかも小難しいことをあまり言わなくなってすっきり(笑)。
結局僕はスティングに思い入れが強いんだなあ。
僕が選ぶベストチューンは9曲目Inshallah
祈りは世界に通じるのだろうか。
スティングが戻ってきたことを最も強く印象づけられる曲。
こういう歌を歌って欲しかったのです、はい。
これは小難しい路線の歌といえばそうですが、でも、
願いの部分がより素直に表現されるようになったと感じました。
☆2位 ジェフ・ベック
LOUD HAILER
Jeff Beck
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
ジェフ・ベックというとインストゥルメンタル主体の
クロスオーバーな音楽を聴かせる人というイメージが
ありますが、今作はR&Bに根ざした本格的ロックを、
不良っぽいイメージで聴かせていることに驚きました。
その実は英国の男女2人組バンド、ボーンズ Bonesを
ジェフが「乗っ取って」作ったものだという。
経緯は分かりましたが、ジェフより若い人たちが
このような古臭いロックをやるというのも驚きの部分。
おまけにみんな歌としていい曲ばかりでついつい口ずさむ。
正直、作品だけの評価ではスティングより上なのですが、
とにかくスティングが嬉しかったので、ジェフさん申し訳ない、
2位ということにさせていただきました。
ベストチューンは9曲目The Ballad Of The Jersey Wives
哀愁を帯びた重たいR&B、ほとんどハードロックといっていい、
途中で"Bang bang"と弾けるのにはぞくぞくっときますね。
☆3位 マッドクラッチ
2
MUDCRUTCH
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
トム・ペティ、マイク・キャンベル、ベンモント・テンチの
トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのメンバーが、
バンド結成以前に組んでいたマッドクラッチ。
そのメンバーが再集結して「新作」を作ったのが8年前。
今回はその2作目となりますが、まあ大筋トム・ペティの音。
だから僕が気に入らないはずがないですね。
このアルバムを聴いて強く感じるのは、
「自分たちが懐かしみながら音楽を作る感覚が強い」、
ということ。
トム達本体のようなロック的はったりが強い曲ではなく、
趣味の世界を高めた余裕のある演奏と曲を聴かせてくれます。
ところで、マッドクラッチに目をつけてトム・ペティに英才教育を施し
バンドとして再デビューさせて大成功に導いた人。
レオン・ラッセルも今年亡くなりましたね。
レオンの作品は紹介しなかった代わりにここでR.I.P.
ベストチューンは2曲目Dreams Of Flying
トムらしい憂いを帯びたマイナー調のアップテンポの曲。
しみてきますよ。
☆4位 レディ・ガガ
JOANNE
Lady GaGa
(2016)
レディ・ガガの新作は今まで一度もここで触れてきていないので、
いきなり4位というのはいささか驚かれるかもしれない。
そう、僕自身、洋楽で今年一番の驚きがレディ・ガガの新作でした。
このアルバムは素晴らしい、そしてすごい!
僕には(というかガガ様を聴いたことがない多くの人はおそらく)
ダンサブルな今風の曲というイメージがあっただけに、
70年代ロックのざらっとした感覚があるのがまず意外。
よく聴くとリズムは今風なんだけど、うん、そう感じる。
しかしでは、70年代にこんなような人がいただろうかと考えると、
いないんです、似たような人、女性歌手は思い浮ばないし、
ガガ様が誰それの真似をしているとも思えない。
と一度結論が出そうになったところでふと気が付いた。
ジョニ・ミッチェルだ。
僕はジョニ・ミッチェルは数年前に真面目に聴き始めて
70年代のは愛聴盤は数枚あるけれど他は一応抑えている
というくらいで偉そうなことはいえないのですが、
音楽としての「音のざらつき感」がジョニ・ミッチェルに近い。
簡単にいえばジョニ・ミッチェルの音をハードにした感じ。
そう考えると僕の頭の中ではつながりました。
でもガガ様は1986年生まれだから、70年代ロックは
リアルタイムで経験していないどころかまだ生まれていない。
だから70年代ロック風のこの音は「経験」から来ているのではない。
もちろん幼少時代にレコード、いや彼女ならCDだろうな、CDで
聴いた経験は彼女の中で積み重なってはいるとは思うけれど、
でも決して彼女のリアルタイムではない。
でも一方で、CDの時代になり70年代ロックが見直されるように
なったのは僕の経験としても言えることえすが、ガガ様は
見直される過程をリアルタイムで経験していた、とは言えますね。
音楽をやる上で1970年代には尊敬のまなざしを向ける。
そこに行き着いたと考えるとこの音は納得できます。
(もしかして、ジョニにエールを送っているのかもしれない)。
このアルバムのもうひとつの驚きが彼女の「神々しさ」。
オーラがある、当たり前だあれだけの人だから、でもそれ以上に、
ガガ様の歌う姿や歌声には「神々しさ」がある。
しかもそれが嫌みではなく納得させられてしまう。
やっぱりこういう人だったかと肯定的に見直すことになる。
トニー・ベネットとの共演などでガガ様がほんとうに歌が上手いのは
分かっていますが、その上でそこを推し進めたのが今回の歌声。
1曲目 からもうその声にぞくぞくっときてしまう。
シングルにもなったPerfect Illusionはダンサブルなビートに
何かが降りてきて憑りついたかのような恐ろしさすら感じる。
そう、黒魔術の宴のような怪しい雰囲気、それこそ70年代的な。
ソフトな曲もあるけれどそれもソフトな中に芯が通っている。
すごい人だ、と、僕はようやく思うようになりました。
このアルバムはほんとうに好きです。
衝撃を受けた、見方が変わったという点で、
元々大好きなノラ・ジョーンズより上に持ってきました。
もしかして後日もう一度記事にして全曲の話をするかも、
というくらいに気に入っています。
ベストチューンは11曲目Angel Down。
まさに神々しさが降臨してきたスケールの大きな曲。
そして感情の琴線に触れまくる歌メロ、歌い方。
☆5位 ヴァン・モリソン
KEEP ME SINGING
Van Morrison
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
あれだけヴァン・モリソンヴァン・モリソンと言い回っているのに
5位というのは低いじゃないか、と思われることでしょう。
まあこれを1位にするとデキレースになってしまうというのは
あるのですが、他にひとつ明確な理由があります。
上位4枚はすべて「いい方に期待を裏切ってくれた」アルバム。
スティングはずっとロックではない作品で交わされ続けていて、
どうせ今回もと思いかけたところでロックに戻ったとの情報が。
ジェフ・ベックもしっかりとしたR&Bルーツの歌物のロックを
聴かせてくれたというのは予想外だった。
マッドクラッチは出ること自体予想していなかった。
レディ・ガガは上に詳しく書いた通り。
それに対してヴァン・モリソンは「安定の1枚」。
きっとこんな音を聴かせてくれるだろうと事前に予想した、
ほぼその通りの音を高いクオリティで聴かせてくれた。
だから作品に対しては不満も何もない、大満足。
ただ、ロック音楽という枠で見るとやはり予想外の出来事が
あるというのは見逃せない要素でもあるのです。
ベストチューンは表題曲Keep Me Singing。
和やかなようで気持ちが盛り上がっている。
派手ではないけれど強く印象に残る。
これがヴァン・モリソンの味ですよ。
【2017年1月2日 追加補足】
☆6位タイ ボニー・レイット
DIG IN DEEP
Bonnie Raitt
(2016)
2016年大晦日の時点で大切な1枚を忘れていました!
ボニー・レイットの新譜、これが素晴らしかった。
正直この前作SLIPSTREAMが期待値より下そこそこだったので、
あまり多くを望まずに聴いたところ、よかった。
これを忘れるなんて、新年早々大いに反省です。
このアルバムはポップで軽やかで心地よい響きの中にも
スワンプ感覚が息づいている。
幾つになっても(失礼!)キュートなボニーの声に
お得意のブルージーなギターを突き刺してゆく。
良い意味で昔から変わらない彼女の音楽ですが、
タイトルにあるように軽やかな響きというだけでは表せない深み、
ちょっとしたかげりのようなものが絶妙にまぶされている。
ベストチューンは変化球ですが2曲目Need You Tonight
インエクセスのカヴァーですが、この曲がスワンプになるなんて、
リアルタイムで経験した者には夢のようです。
☆6位 ノラ・ジョーンズ
THE DAY BREAKS
Norah Jones
(2016)
前作ではポップな音で遊んだ(溺れた?)ノラ・ジョーンズ。
今回はジャズっぽい音楽に帰ってきたというのが売り。
その通りですね。
ある意味1作目3作目よりジャズっぽいかも。
(2作目はカントリーっぽさが少し強かった)。
1曲目からけだるいアンニュイさ満開で攻めてきますが、
ジャズっぽい中にもポップな歌メロのセンスがきらりと光る。
だからスタンダードを歌ったような古臭さ(いい意味)ではなく、
あくまでも今の時代を生きる人の歌声として響いてくる。
かなりいいと思います。
これは独立した記事を上げるつもりなので今回は短く終わります。
ベストチューンは3曲目Flipside。
ベースに引っ張られたアップテンポのマイナー調の曲。
悲壮感があるようで突き放しているようで
男女の仲の複雑さが想像される曲。
☆7位 ボブ・ディラン
FALLEN ANGELS
Bob Dylan
(2016)
ボブ・ディランのスタンダード路線第2弾。
今のディランの気持ちがどこに向いているかが分かりますが、
これを聴いて僕はこう思いました。
「ディランさん、もう好きにして、こっちはついていくだけ!」
ディランは基本的に今歌いたい歌を歌いたい風に歌うだけ。
実はそれは昔からまったく変わっていない。
歌う対象としての曲のえり好みが時代により違うだけ。
それがオリジナルかスタンダードかも関係ない。
四捨五入してついに80の男がいまだに気持ちを失っていない。
もうそれだけで素晴らしいのではないですかね。
弟が行った東京公演では「枯葉」も歌ったそうですが、
こうなったら次は何を歌ってくれるか楽しみでしょうがないですね。
今作はハワイアンっぽいアレンジの曲が多いのがポイントですが、
クリスマスアルバムにもあった、ディランは密かに好きなんですね。
ベストチューンは5曲目Skylark。
「ひばり」、ですね、ディランの歌い方はほのぼのとしていい。
ところで今年はボブ・ディランがノーベル文学賞を授与され、
授賞式に出席するかどうか、一般の人まで巻き込んで
話題になりましたね。
僕はそれ関係の記事の書き込みを興味深く読んでいましたが、
やはりというか少なくとも日本においては、ボブ・ディランは
「風に吹かれて」のイメージが強烈であり、それしかない、
ということが見えてきました。
ディランを批判する人の話が特に面白かったですね。
僕は一応ファンですが、ディランのことはよくは知らない。
本を著している萩原健太さんもディランという人は分からないという。
でも少なくとも僕は、何も知らないでイメージだけで批判をする人よりは
ディランという人を知っているつもりではあります。
どんなことを知っているかというと、分からない人である、ということ。
それが、今回の顛末と「風に吹かれて」のイメージだけで
批判にまでなってしまうというのが、なんというか、恐い世の中ですね。
でも実際、ボブ・ディランという人は分からないですね。
だから僕は面白くてファンでもあるのです。
もちろん音楽が素晴らしいというのは言うまでもないことですが。
☆8位 グレゴリー・ポーター
TAKE ME TO THE ALLEY
Gregory Porter
(2016)
グレゴリー・ポーターはまあ、ジャズヴォーカルなのでしょうけど、
実際はR&Bシンガーという方がよりしっくりきます。
ジャズヴォーカルは本来、歌い手が気持ちよく歌い、
その姿と声を好きな人が聴いて気持ちよくなるものなのでしょう。
不特定多数の人に向けた良い意味でも良くない意味でも無機質な
メッセージを含んだポップソングとは違う。
だから本来は歌い手がより近しく感じられる小さい会場で映える。
僕は逆、はじまりがビートルズという人間だから、より多くの人が聴く
ポップソングから自分だけの思いを見つけ出すのが好きなので、
最初はこの人、このアルバムに戸惑いました。
でも、買った以上は何回も繰り返し聴くわけで、聴いてゆくうちに
僕もこの人がより好きになって来たのを感じました。
そうなると不思議なもので、それまでは曲もまあまあというくらいに
感じていたのが、これいい、こっちの曲もいいじゃん、となりました。
やはりじわじわと魅力が伝わるのはただのポップソングではない、
でもその上で売れなければならないのだから大変でしょうけど、
こういう人が売れるようになったのはやっぱり、90年代以降、
音楽を聴く人の趣味がより多様化したことを感じますね。
じっくりと向かい合いたい音楽を求めている人にはおすすめですが、
CDを1から数回聴いて判断する人には向いていません。
じっくりと聴き込みたい1枚ですね。
ベストチューンは5曲目Consequence Of Love
明るいようで少し裏に入っていく歌メロが絶品。
☆9位 エレーヌ・グリモー
Water
Helene Grimaud
(2016)
フランスのピアニスト、エレーヌ・グリモー。
僕が「グリモー様」と言うようになって初めて新譜が出ました。
ところが。
今回の「アルバム」は、水をテーマにとった古今東西作曲家の
短い曲の間をニティン・ソーニー作曲のパッセージでつなぐというもの。
取り上げられているのは順に、ベリオ、武満徹、フォーレ、ラヴェル、
アルベニス、リスト、ヤナーチェク、ドビュッシー。
それぞれの曲はまさにみずみずしくて素晴らしい。
つなぎの曲を入れ「アルバム」として聴かせるアイディアもいい。
でも、そう言えるのは多分、僕がファンだから。
特に旧来のクラシックファンは、それぞれの曲を楽しみたいのでは。
グリモーはクラシックの枠を超えて「アルバム」として聴かせようと
考えている、と僕は以前何度か書きましたが、今回はそれが
より具体的な形となって表されたものといえるでしょう。
まさに体を流れる水の如く次から次へと曲が流れていく様は
BGM的に流しておくにはとてもいいCDだと思いますが、
それはもしかして「アルバム」としてはほめていないかもしれない。
評価というのは大袈裟だけど、何といっていいか難しいCDです、正直。
ただ、彼女がやりたかったことはこうだったんだと僕の中で
証明できたのは、ファンとしては嬉しくもあります。
それにしてもジャケットの写真はまさに水のごとくみずみずしく、
若くてかわいらしい雰囲気に撮れていますね。
やっぱり大好きです、はい(笑)。
☆10位 ブルーノ・マーズ
24K MAGIC
Bruno Mars
(2016)
最後はブルーノ・マーズの新譜をねじ込みました。
11月に出て買ったものですが、すぐにクリスマスアルバムしか
聴かなくなって、12月26日までひと月ほど聴きませんでした。
だからよく分かっているかと言うと実は自信がないのですが、
でも期待もしていたし、今年出たアルバムとして取り上げない
わけにはゆかないので「ねじ込んだ」というわけ。
「ねじ込んだ」ので順位も少し低めになっています。
前作UNORTHODOX JUKEBOX(記事こちら)では、僕には
懐かし1980年代テイストのポップソングを聴かせてくれましたが、
今作は一転して1990年代「ポストラップ・ヒップホップ」ど真ん中
という音。
幼少の頃から聴きなじんだ音なのでしょうけど、僕には
「新しい」と感じられる音でした。
まあそうですよね今や押しも押されもせぬトップスターだから、
古い年代の音にこだわり続けるわけにはゆかないでしょうし。
その影響なのか、今作は1曲1曲が強いという感じではなく、
通して聴くとファンクグルーヴが盛り上がるという感じがします。
つまり1曲1曲の印象はやや薄い。
まあ曲そのものに凝るのが1980年代の特徴だったので、
そこから脱するとやはりこうはなるでしょうね。
決してつまらないというのではない、ついつい聴きたくなる
強いグルーヴ感がありますが、要は好き好きということ。
それにしても前作とこれだけ違ったテイストのアルバムを作るのは
彼が勢いに乗り自信に満ちている証拠でしょうね。
ジャケットの派手な衣装とポーズも嫌みではない。
むしろよくそこまで大物になってくれたと感謝したいくらい。
ただ、僕の趣味とはちょっとばかり違うのですが・・・(笑)。
ベストチューンは3曲目Perm。
これがもう思いっきりJBファンク。
影響を受けた以上にパクリの心配があるほど(笑)。
今これができるのも俺だけだ、という自負を感じますね。
次点にエリック・クラプトンI STILL DO、
ポール・サイモンSTRANGER TO STRANGER
を挙げておきます。
◇
ところで。
12月にクリスマスアルバムばかり聴いていたあおりで、
12月に買った以下の3枚はまともに聴くことができず、
来年回しとさせていただくことにしました。
●ローリング・ストーンズ
BLUE & LONESOME
Rolling Stones
(2016)
●アリシア・キーズ
HERE
Alicia Keys
(2016)
●ニール・ヤング
PEACE TRAIL
Neil Young
(2016)
これらには敢えて触れないで次にゆきます。
◇
最後に大型リイシュー盤も3点さらりと。
☆ポール・マッカートニー
PURE McCARTNEY
Paul McCartney
(2016)
ポール・マッカートニーのUniversal初のベスト盤、
それまでポールのベスト盤が出回っていないという異常事態で、
これが出た意味は大きかった。
今回は、それまでのベスト盤には入っていなかった曲を
聴き直して新たな発見があったことも楽しかったですね。
同じ曲でも聴き方聴かれ方で解釈は違ってくる。
これもまた音楽の興味深いところです。
このアルバムについては記事を2つほど上げました。
ご興味がある方は
こちらと
こちらを
ご覧ください。
☆ヴァン・モリソン
...IT'S TOO LATE TO STOP NOW...
Van Morrison
(1974)
ヴァン・モリソンは過去の音源の版権がSONY/BMGに移行。
ベスト盤ESSENTIALに続いてライヴ盤のこれが
リイシュー盤として再発されました。
しかも続編或いは補完の意味合いをもつ
DVD付き豪華版2、3、4が出た。
ファンには嬉しい年となりました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
☆エマーソン弦楽四重奏団
EMERSON STRING QUARTET
COMPLETE RECORDINGS ON DG
Emerson String Quartet
エマーソン弦楽四重奏団がドイツグラモフォンに残した音源が
CD52枚組のボックスセットとしてリリースされました。
彼らは現在SONY CLASSICALと契約をしているので、
これはまあ「卒業アルバム」みたいなものでしょうか。
僕は彼らの大ファンで、少しずつ集めていたところに
これが出たので買い求めました。
10セットくらいだぶったのですがそれでも安いし、
何より中古で安く探す手間が省けましたからね。
この中ではグリーグやシベリウスなど「北欧もの」の1枚、
ベートーヴェン弦楽四重奏全曲、ショスタコーヴィチ全曲、
ハイドン選集、メンデルスゾーンが僕は気に入っているし
できもいいと思います。
通しで聴くと後期の方が好きかな、前期はまだ自信に満ちた
という感じではなく探求心が勝っている感じがする。
これは一生かけて聴いてゆく愛聴盤です。
02

記事は毎日上げるので、年末のご挨拶は簡単に。
本年も当BLOGにお付き合いいただきありがとうございます。
2017年、来年もよろしくお願いします。
皆様、よいお年をおむかえください。

大晦日。
その年に良かった新譜CDをまとめて紹介する記事です。
洋楽中心ですがクラシックの新譜もあります。
長いので早速。
【特別枠】 哀悼
2016年はこんな年でしたという記録と記憶の意味も込め、
もちろん哀悼の意を表するために
今年亡くなられた3人のCDから先に話します。
★1人目 デヴィッド・ボウイ
★(BLACK STAR)
David Bowie
(2016)
デヴィッド・ボウイの死の知らせは、僕のリアルタイムでは、
フレディ・マーキュリーと同じ、いやそれ以上の衝撃でした。
フレディの場合は病気であることを公表して割と早くに
亡くなったというショックでしたが、でも事前に知ってはいたから、
あまりの早さに驚いたという部分が大きかったような気が。
対してボウイは新作を1週間前に出したばかり、
病気のことはまったく知らなかっただけに、衝撃は大き過ぎた。
後からネットや本で見ると、ボウイは自分の死を悟った上で、
この録音に臨んでいたようですね。
ボウイは最期までボウイらしく演出していたという。
それは決して悪い意味ではなく、そういう不世出の人だったと。
ところでこのアルバム、実は昨日10か月ぶりに聴きました。
ボウイが命を懸けてまで作ったアルバムに対して、
僕はだんだんと身構えてしまい、軽々しく聴いていいものなのか
と自問自答した挙句、自信がなくなり聴かなくなったのでした。
10か月ぶりに聴いて、素晴らしい。
もうそのように身構えるのはやめ、もう少し気軽に、は無理でも
聴く機会を増やしてゆく方がボウイも喜んでくれるのではないか。
昨日、ようやくそう思うに至った、ということを白状しておきます。
★2人目 プリンス
HITNRUN PHASE TWO
Prince
(2016)
プリンスの死は、衝撃というよりも、なぜ、どうしてという
納得できないという思いが強かった、今でも。
ボウイの場合は遺作があのような内容だっただけに、
亡くなったことが実感できるのですが、
プリンスは正直いまだに死んだことが信じられない。
Warnerに復帰してからのプリンスは期待通りの作品を
聴かせてくれていましたが、今年も、亡くなってから出ました。
これがまたポップもポップでとっても聴きやすい1枚。
この明るさ、まあ当然といえば当然ですがボウイとは正反対、
死などまるで予感させないとにかく楽しいアルバム。
それだけ余計に死が悲しくなり、信じられなくもなりました。
プリンスはアルバム何百枚分の録音ストックがあるそうですが、
でも、今年のアルバムは当然彼自身の意志だとして、
それ以降については正面から受け止めて聴こうと思えるか。
手を加えないのであれば正真正銘プリンスではあるけれど、
そうか、プリンスの場合は中途半端なデモ状態ではなく、
出来上がったもののストックも多そうだから期待できるかな。
しかしそのようにリリースが続くと、僕はいったいいつになったら
プリンスの死を現実のものとして受け止められるのだろうか。
受け止めなくてもいいのかもしれないけれど。
ベストチューンは9曲目Screwdriver
異様なまでのポップさの中、"I'm your driver, you're my screw"と
恥じらうように歌うプリンスに不覚にも胸がきゅんとしてしまった。
これを聴くと、もうこの世にいないとは信じられないですね。
★3人目 ニコラウス・アーノンクール
BEETHOVEN : SYMPHONY NO.4 & NO.5
Nikolaus Harnoncout
Concertus Musicus Wien
(2016)
BEETHOVEN : MISSA SOLEMNIS
Nikolaus Harnoncourt (condt.)
Concentus Musicus Wien
(2016)
僕がいちばん好きな指揮者、ニコラウス・アーノンクール。
古楽器演奏での評価を受けて大指揮者になった人ですが、
サステインが短く切れがいい古楽器演奏の方法論を
モダン楽器にも活用して独特の音を聴かせる人でした。
ただ、その音の響きは審美的或いは耽美的ではなく、
カラヤンやバーンスタインといった大指揮者たちの音に慣れた
人にはともすれば「汚い」と捉えられかねない音なのです。
実は僕も、アーノンクールのブラームスはロマンが足りなくて
もう少し浸れる音で聴きたい、と思います。
しかし一方で、作曲された当時はこのように演奏され、
このように聴かれていたであろうことを想像させてくれる
という点ではむしろ新鮮な響きでもあります。
今回2枚あるのは、1枚が生前、もう1枚が死後に出たものだから。
どちらもベートーヴェンですが、前者が交響曲、後者がミサ曲。
交響曲第4番と第5番の組み合わせですが、これを買って
ライナーノーツには、交響曲全集を予定していたが完結することが
出来ず今回の2曲で終わりになる、と書かれていたのを読んで、
正直不安になりました。
それがあっての訃報だったので、ああそうだったか、と。
86歳だから天寿をまっとうしたといえるでしょうし、僕としても
それなりの覚悟があったのでショックは一瞬で収まりましたが、
やはり寂しさがじわじわとこみ上げてきました。
交響曲第4番は舞踏会のような雰囲気の明るい曲ですが、
浮ついた感がなく地に足がしっかりと着いた演奏。
舞踏ではなくあくまでも音楽が先という意識が感じられます。
だからCDとして聴くにはいい演奏ではないかと。
そして出来としては史上最高と言われる交響曲第5番。
その通り、美に流されると聴き逃してしまいがちな
構築性、テクスチャーが目に見えるように分かり、
説得力という点では僕が今まで聴いた5番では最高でした。
死後に出た「荘厳ミサ曲」は本当の最後の録音。
最後の録音がミサ曲というのは、うん、やっぱり、
予感というよりは準備をしていたのかなと思ってしまう。
リリース情報を知った時、やっぱりか、と思いました。
アーノンクールの死は、もちろん残念だしショックだけど、
今までほんとうにありがとう、ただこれだけを贈りたいです。
ちなみにこの曲は書籍「ベートーヴェンの交響曲」において
指揮者の金聖玉さんが「もっと日本でも注目されていい曲」
として紹介されていたということを付記しておきます。
そして通常のTop10に入ります。
☆1位 スティング
57TH & 9TH
Sting
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
もうほんと、スティングがロックに戻ってきた。
このフレーズを何回使ったか分からない。
それだけで嬉しいのです。
もちろんスティングらしい音楽で。
しかも小難しいことをあまり言わなくなってすっきり(笑)。
結局僕はスティングに思い入れが強いんだなあ。
僕が選ぶベストチューンは9曲目Inshallah
祈りは世界に通じるのだろうか。
スティングが戻ってきたことを最も強く印象づけられる曲。
こういう歌を歌って欲しかったのです、はい。
これは小難しい路線の歌といえばそうですが、でも、
願いの部分がより素直に表現されるようになったと感じました。
☆2位 ジェフ・ベック
LOUD HAILER
Jeff Beck
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
ジェフ・ベックというとインストゥルメンタル主体の
クロスオーバーな音楽を聴かせる人というイメージが
ありますが、今作はR&Bに根ざした本格的ロックを、
不良っぽいイメージで聴かせていることに驚きました。
その実は英国の男女2人組バンド、ボーンズ Bonesを
ジェフが「乗っ取って」作ったものだという。
経緯は分かりましたが、ジェフより若い人たちが
このような古臭いロックをやるというのも驚きの部分。
おまけにみんな歌としていい曲ばかりでついつい口ずさむ。
正直、作品だけの評価ではスティングより上なのですが、
とにかくスティングが嬉しかったので、ジェフさん申し訳ない、
2位ということにさせていただきました。
ベストチューンは9曲目The Ballad Of The Jersey Wives
哀愁を帯びた重たいR&B、ほとんどハードロックといっていい、
途中で"Bang bang"と弾けるのにはぞくぞくっときますね。
☆3位 マッドクラッチ
2
MUDCRUTCH
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
トム・ペティ、マイク・キャンベル、ベンモント・テンチの
トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのメンバーが、
バンド結成以前に組んでいたマッドクラッチ。
そのメンバーが再集結して「新作」を作ったのが8年前。
今回はその2作目となりますが、まあ大筋トム・ペティの音。
だから僕が気に入らないはずがないですね。
このアルバムを聴いて強く感じるのは、
「自分たちが懐かしみながら音楽を作る感覚が強い」、
ということ。
トム達本体のようなロック的はったりが強い曲ではなく、
趣味の世界を高めた余裕のある演奏と曲を聴かせてくれます。
ところで、マッドクラッチに目をつけてトム・ペティに英才教育を施し
バンドとして再デビューさせて大成功に導いた人。
レオン・ラッセルも今年亡くなりましたね。
レオンの作品は紹介しなかった代わりにここでR.I.P.
ベストチューンは2曲目Dreams Of Flying
トムらしい憂いを帯びたマイナー調のアップテンポの曲。
しみてきますよ。
☆4位 レディ・ガガ
JOANNE
Lady GaGa
(2016)
レディ・ガガの新作は今まで一度もここで触れてきていないので、
いきなり4位というのはいささか驚かれるかもしれない。
そう、僕自身、洋楽で今年一番の驚きがレディ・ガガの新作でした。
このアルバムは素晴らしい、そしてすごい!
僕には(というかガガ様を聴いたことがない多くの人はおそらく)
ダンサブルな今風の曲というイメージがあっただけに、
70年代ロックのざらっとした感覚があるのがまず意外。
よく聴くとリズムは今風なんだけど、うん、そう感じる。
しかしでは、70年代にこんなような人がいただろうかと考えると、
いないんです、似たような人、女性歌手は思い浮ばないし、
ガガ様が誰それの真似をしているとも思えない。
と一度結論が出そうになったところでふと気が付いた。
ジョニ・ミッチェルだ。
僕はジョニ・ミッチェルは数年前に真面目に聴き始めて
70年代のは愛聴盤は数枚あるけれど他は一応抑えている
というくらいで偉そうなことはいえないのですが、
音楽としての「音のざらつき感」がジョニ・ミッチェルに近い。
簡単にいえばジョニ・ミッチェルの音をハードにした感じ。
そう考えると僕の頭の中ではつながりました。
でもガガ様は1986年生まれだから、70年代ロックは
リアルタイムで経験していないどころかまだ生まれていない。
だから70年代ロック風のこの音は「経験」から来ているのではない。
もちろん幼少時代にレコード、いや彼女ならCDだろうな、CDで
聴いた経験は彼女の中で積み重なってはいるとは思うけれど、
でも決して彼女のリアルタイムではない。
でも一方で、CDの時代になり70年代ロックが見直されるように
なったのは僕の経験としても言えることえすが、ガガ様は
見直される過程をリアルタイムで経験していた、とは言えますね。
音楽をやる上で1970年代には尊敬のまなざしを向ける。
そこに行き着いたと考えるとこの音は納得できます。
(もしかして、ジョニにエールを送っているのかもしれない)。
このアルバムのもうひとつの驚きが彼女の「神々しさ」。
オーラがある、当たり前だあれだけの人だから、でもそれ以上に、
ガガ様の歌う姿や歌声には「神々しさ」がある。
しかもそれが嫌みではなく納得させられてしまう。
やっぱりこういう人だったかと肯定的に見直すことになる。
トニー・ベネットとの共演などでガガ様がほんとうに歌が上手いのは
分かっていますが、その上でそこを推し進めたのが今回の歌声。
1曲目 からもうその声にぞくぞくっときてしまう。
シングルにもなったPerfect Illusionはダンサブルなビートに
何かが降りてきて憑りついたかのような恐ろしさすら感じる。
そう、黒魔術の宴のような怪しい雰囲気、それこそ70年代的な。
ソフトな曲もあるけれどそれもソフトな中に芯が通っている。
すごい人だ、と、僕はようやく思うようになりました。
このアルバムはほんとうに好きです。
衝撃を受けた、見方が変わったという点で、
元々大好きなノラ・ジョーンズより上に持ってきました。
もしかして後日もう一度記事にして全曲の話をするかも、
というくらいに気に入っています。
ベストチューンは11曲目Angel Down。
まさに神々しさが降臨してきたスケールの大きな曲。
そして感情の琴線に触れまくる歌メロ、歌い方。
☆5位 ヴァン・モリソン
KEEP ME SINGING
Van Morrison
(2016)
アルバム記事はこちらをご覧ください。
あれだけヴァン・モリソンヴァン・モリソンと言い回っているのに
5位というのは低いじゃないか、と思われることでしょう。
まあこれを1位にするとデキレースになってしまうというのは
あるのですが、他にひとつ明確な理由があります。
上位4枚はすべて「いい方に期待を裏切ってくれた」アルバム。
スティングはずっとロックではない作品で交わされ続けていて、
どうせ今回もと思いかけたところでロックに戻ったとの情報が。
ジェフ・ベックもしっかりとしたR&Bルーツの歌物のロックを
聴かせてくれたというのは予想外だった。
マッドクラッチは出ること自体予想していなかった。
レディ・ガガは上に詳しく書いた通り。
それに対してヴァン・モリソンは「安定の1枚」。
きっとこんな音を聴かせてくれるだろうと事前に予想した、
ほぼその通りの音を高いクオリティで聴かせてくれた。
だから作品に対しては不満も何もない、大満足。
ただ、ロック音楽という枠で見るとやはり予想外の出来事が
あるというのは見逃せない要素でもあるのです。
ベストチューンは表題曲Keep Me Singing。
和やかなようで気持ちが盛り上がっている。
派手ではないけれど強く印象に残る。
これがヴァン・モリソンの味ですよ。
【2017年1月2日 追加補足】
☆6位タイ ボニー・レイット
DIG IN DEEP
Bonnie Raitt
(2016)
2016年大晦日の時点で大切な1枚を忘れていました!
ボニー・レイットの新譜、これが素晴らしかった。
正直この前作SLIPSTREAMが期待値より下そこそこだったので、
あまり多くを望まずに聴いたところ、よかった。
これを忘れるなんて、新年早々大いに反省です。
このアルバムはポップで軽やかで心地よい響きの中にも
スワンプ感覚が息づいている。
幾つになっても(失礼!)キュートなボニーの声に
お得意のブルージーなギターを突き刺してゆく。
良い意味で昔から変わらない彼女の音楽ですが、
タイトルにあるように軽やかな響きというだけでは表せない深み、
ちょっとしたかげりのようなものが絶妙にまぶされている。
ベストチューンは変化球ですが2曲目Need You Tonight
インエクセスのカヴァーですが、この曲がスワンプになるなんて、
リアルタイムで経験した者には夢のようです。
☆6位 ノラ・ジョーンズ
THE DAY BREAKS
Norah Jones
(2016)
前作ではポップな音で遊んだ(溺れた?)ノラ・ジョーンズ。
今回はジャズっぽい音楽に帰ってきたというのが売り。
その通りですね。
ある意味1作目3作目よりジャズっぽいかも。
(2作目はカントリーっぽさが少し強かった)。
1曲目からけだるいアンニュイさ満開で攻めてきますが、
ジャズっぽい中にもポップな歌メロのセンスがきらりと光る。
だからスタンダードを歌ったような古臭さ(いい意味)ではなく、
あくまでも今の時代を生きる人の歌声として響いてくる。
かなりいいと思います。
これは独立した記事を上げるつもりなので今回は短く終わります。
ベストチューンは3曲目Flipside。
ベースに引っ張られたアップテンポのマイナー調の曲。
悲壮感があるようで突き放しているようで
男女の仲の複雑さが想像される曲。
☆7位 ボブ・ディラン
FALLEN ANGELS
Bob Dylan
(2016)
ボブ・ディランのスタンダード路線第2弾。
今のディランの気持ちがどこに向いているかが分かりますが、
これを聴いて僕はこう思いました。
「ディランさん、もう好きにして、こっちはついていくだけ!」
ディランは基本的に今歌いたい歌を歌いたい風に歌うだけ。
実はそれは昔からまったく変わっていない。
歌う対象としての曲のえり好みが時代により違うだけ。
それがオリジナルかスタンダードかも関係ない。
四捨五入してついに80の男がいまだに気持ちを失っていない。
もうそれだけで素晴らしいのではないですかね。
弟が行った東京公演では「枯葉」も歌ったそうですが、
こうなったら次は何を歌ってくれるか楽しみでしょうがないですね。
今作はハワイアンっぽいアレンジの曲が多いのがポイントですが、
クリスマスアルバムにもあった、ディランは密かに好きなんですね。
ベストチューンは5曲目Skylark。
「ひばり」、ですね、ディランの歌い方はほのぼのとしていい。
ところで今年はボブ・ディランがノーベル文学賞を授与され、
授賞式に出席するかどうか、一般の人まで巻き込んで
話題になりましたね。
僕はそれ関係の記事の書き込みを興味深く読んでいましたが、
やはりというか少なくとも日本においては、ボブ・ディランは
「風に吹かれて」のイメージが強烈であり、それしかない、
ということが見えてきました。
ディランを批判する人の話が特に面白かったですね。
僕は一応ファンですが、ディランのことはよくは知らない。
本を著している萩原健太さんもディランという人は分からないという。
でも少なくとも僕は、何も知らないでイメージだけで批判をする人よりは
ディランという人を知っているつもりではあります。
どんなことを知っているかというと、分からない人である、ということ。
それが、今回の顛末と「風に吹かれて」のイメージだけで
批判にまでなってしまうというのが、なんというか、恐い世の中ですね。
でも実際、ボブ・ディランという人は分からないですね。
だから僕は面白くてファンでもあるのです。
もちろん音楽が素晴らしいというのは言うまでもないことですが。
☆8位 グレゴリー・ポーター
TAKE ME TO THE ALLEY
Gregory Porter
(2016)
グレゴリー・ポーターはまあ、ジャズヴォーカルなのでしょうけど、
実際はR&Bシンガーという方がよりしっくりきます。
ジャズヴォーカルは本来、歌い手が気持ちよく歌い、
その姿と声を好きな人が聴いて気持ちよくなるものなのでしょう。
不特定多数の人に向けた良い意味でも良くない意味でも無機質な
メッセージを含んだポップソングとは違う。
だから本来は歌い手がより近しく感じられる小さい会場で映える。
僕は逆、はじまりがビートルズという人間だから、より多くの人が聴く
ポップソングから自分だけの思いを見つけ出すのが好きなので、
最初はこの人、このアルバムに戸惑いました。
でも、買った以上は何回も繰り返し聴くわけで、聴いてゆくうちに
僕もこの人がより好きになって来たのを感じました。
そうなると不思議なもので、それまでは曲もまあまあというくらいに
感じていたのが、これいい、こっちの曲もいいじゃん、となりました。
やはりじわじわと魅力が伝わるのはただのポップソングではない、
でもその上で売れなければならないのだから大変でしょうけど、
こういう人が売れるようになったのはやっぱり、90年代以降、
音楽を聴く人の趣味がより多様化したことを感じますね。
じっくりと向かい合いたい音楽を求めている人にはおすすめですが、
CDを1から数回聴いて判断する人には向いていません。
じっくりと聴き込みたい1枚ですね。
ベストチューンは5曲目Consequence Of Love
明るいようで少し裏に入っていく歌メロが絶品。
☆9位 エレーヌ・グリモー
Water
Helene Grimaud
(2016)
フランスのピアニスト、エレーヌ・グリモー。
僕が「グリモー様」と言うようになって初めて新譜が出ました。
ところが。
今回の「アルバム」は、水をテーマにとった古今東西作曲家の
短い曲の間をニティン・ソーニー作曲のパッセージでつなぐというもの。
取り上げられているのは順に、ベリオ、武満徹、フォーレ、ラヴェル、
アルベニス、リスト、ヤナーチェク、ドビュッシー。
それぞれの曲はまさにみずみずしくて素晴らしい。
つなぎの曲を入れ「アルバム」として聴かせるアイディアもいい。
でも、そう言えるのは多分、僕がファンだから。
特に旧来のクラシックファンは、それぞれの曲を楽しみたいのでは。
グリモーはクラシックの枠を超えて「アルバム」として聴かせようと
考えている、と僕は以前何度か書きましたが、今回はそれが
より具体的な形となって表されたものといえるでしょう。
まさに体を流れる水の如く次から次へと曲が流れていく様は
BGM的に流しておくにはとてもいいCDだと思いますが、
それはもしかして「アルバム」としてはほめていないかもしれない。
評価というのは大袈裟だけど、何といっていいか難しいCDです、正直。
ただ、彼女がやりたかったことはこうだったんだと僕の中で
証明できたのは、ファンとしては嬉しくもあります。
それにしてもジャケットの写真はまさに水のごとくみずみずしく、
若くてかわいらしい雰囲気に撮れていますね。
やっぱり大好きです、はい(笑)。
☆10位 ブルーノ・マーズ
24K MAGIC
Bruno Mars
(2016)
最後はブルーノ・マーズの新譜をねじ込みました。
11月に出て買ったものですが、すぐにクリスマスアルバムしか
聴かなくなって、12月26日までひと月ほど聴きませんでした。
だからよく分かっているかと言うと実は自信がないのですが、
でも期待もしていたし、今年出たアルバムとして取り上げない
わけにはゆかないので「ねじ込んだ」というわけ。
「ねじ込んだ」ので順位も少し低めになっています。
前作UNORTHODOX JUKEBOX(記事こちら)では、僕には
懐かし1980年代テイストのポップソングを聴かせてくれましたが、
今作は一転して1990年代「ポストラップ・ヒップホップ」ど真ん中
という音。
幼少の頃から聴きなじんだ音なのでしょうけど、僕には
「新しい」と感じられる音でした。
まあそうですよね今や押しも押されもせぬトップスターだから、
古い年代の音にこだわり続けるわけにはゆかないでしょうし。
その影響なのか、今作は1曲1曲が強いという感じではなく、
通して聴くとファンクグルーヴが盛り上がるという感じがします。
つまり1曲1曲の印象はやや薄い。
まあ曲そのものに凝るのが1980年代の特徴だったので、
そこから脱するとやはりこうはなるでしょうね。
決してつまらないというのではない、ついつい聴きたくなる
強いグルーヴ感がありますが、要は好き好きということ。
それにしても前作とこれだけ違ったテイストのアルバムを作るのは
彼が勢いに乗り自信に満ちている証拠でしょうね。
ジャケットの派手な衣装とポーズも嫌みではない。
むしろよくそこまで大物になってくれたと感謝したいくらい。
ただ、僕の趣味とはちょっとばかり違うのですが・・・(笑)。
ベストチューンは3曲目Perm。
これがもう思いっきりJBファンク。
影響を受けた以上にパクリの心配があるほど(笑)。
今これができるのも俺だけだ、という自負を感じますね。
次点にエリック・クラプトンI STILL DO、
ポール・サイモンSTRANGER TO STRANGER
を挙げておきます。
◇
ところで。
12月にクリスマスアルバムばかり聴いていたあおりで、
12月に買った以下の3枚はまともに聴くことができず、
来年回しとさせていただくことにしました。
●ローリング・ストーンズ
BLUE & LONESOME
Rolling Stones
(2016)
●アリシア・キーズ
HERE
Alicia Keys
(2016)
●ニール・ヤング
PEACE TRAIL
Neil Young
(2016)
これらには敢えて触れないで次にゆきます。
◇
最後に大型リイシュー盤も3点さらりと。
☆ポール・マッカートニー
PURE McCARTNEY
Paul McCartney
(2016)
ポール・マッカートニーのUniversal初のベスト盤、
それまでポールのベスト盤が出回っていないという異常事態で、
これが出た意味は大きかった。
今回は、それまでのベスト盤には入っていなかった曲を
聴き直して新たな発見があったことも楽しかったですね。
同じ曲でも聴き方聴かれ方で解釈は違ってくる。
これもまた音楽の興味深いところです。
このアルバムについては記事を2つほど上げました。
ご興味がある方は
こちらと
こちらを
ご覧ください。
☆ヴァン・モリソン
...IT'S TOO LATE TO STOP NOW...
Van Morrison
(1974)
ヴァン・モリソンは過去の音源の版権がSONY/BMGに移行。
ベスト盤ESSENTIALに続いてライヴ盤のこれが
リイシュー盤として再発されました。
しかも続編或いは補完の意味合いをもつ
DVD付き豪華版2、3、4が出た。
ファンには嬉しい年となりました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
☆エマーソン弦楽四重奏団
EMERSON STRING QUARTET
COMPLETE RECORDINGS ON DG
Emerson String Quartet
エマーソン弦楽四重奏団がドイツグラモフォンに残した音源が
CD52枚組のボックスセットとしてリリースされました。
彼らは現在SONY CLASSICALと契約をしているので、
これはまあ「卒業アルバム」みたいなものでしょうか。
僕は彼らの大ファンで、少しずつ集めていたところに
これが出たので買い求めました。
10セットくらいだぶったのですがそれでも安いし、
何より中古で安く探す手間が省けましたからね。
この中ではグリーグやシベリウスなど「北欧もの」の1枚、
ベートーヴェン弦楽四重奏全曲、ショスタコーヴィチ全曲、
ハイドン選集、メンデルスゾーンが僕は気に入っているし
できもいいと思います。
通しで聴くと後期の方が好きかな、前期はまだ自信に満ちた
という感じではなく探求心が勝っている感じがする。
これは一生かけて聴いてゆく愛聴盤です。
02

記事は毎日上げるので、年末のご挨拶は簡単に。
本年も当BLOGにお付き合いいただきありがとうございます。
2017年、来年もよろしくお願いします。
皆様、よいお年をおむかえください。
2016年07月03日
フィル・コリンズのリイシュー盤がなんだか「妙」だ・・・
01

フィル・コリンズのスタジオアルバム8作のリイシュー・リマスター盤が
昨秋からほぼ隔月で2枚ずつリリースされ、この6月に完結しました。
今のところすべてボーナストラック付き2枚組デラックスエディションのみ、
アルバム単発でのリリースはないですが、今後はどうだろう。
このリイシュー盤がなんだか面白いというか「妙」で、
ぜひ記事にしたいと。
何が面白いかって?
冒頭マーサと一緒に写っている3作目NO JACKET REQUIREDの
ジャケット写真をご覧ください。
なにか「妙」じゃないですか?
どうやらこれ、リイシュー盤に合わせて、今のフィルが
オリジナル通りに新たに撮影し直したもののようです。
つまりリリース当時のジャケット写真ではない。
「妙」というか、面白い、そこからまず
フィル・コリンズのユーモア感覚が伝わってきますね。
ここからは1作ずつ、新ジャケットと旧ジャケットを並べ、
アルバムについてとりあえず短く話してゆきます。
写真は上が新盤、下が旧盤オリジナル、並び順にご注意ください。
◎1st FACES VALUE (1981) ※30歳


下のオリジナル、フィルの肌に張りがありますね。
こんなに若かったのかと逆に今驚いたくらい(笑)。
僕はこのアルバムは完全な後追いですが、高校時代に
ラジオで聴いたIn The Air Tonightにちょっと驚きました。
僕が知っていたフィル・コリンズはポップさ一筋、
曲調で暗いものはあっても、この曲にあるぬめっとした不気味さに
この人の恐さのようなものを感じ、ただのポップな人ではない、
なかなかやるなあ、すごい人じゃんと。
当時はジェネシスのMamaにも驚いたものですが、その後で
これを聴き、なるほどそういう人だったのかと理解できました。
その曲は後にJ-WAVE日曜朝の「トヨタ・カリフォルニア・クラシックス」
という番組で、他の人が
"I can hear the TOYOTA CALIFORNIA CLASSCS on J-WAVE"
と歌詞を変えてジングルのように使われていたことで、
僕の生活に溶け込んだ曲となりました。
しかしアルバムは20代の頃にCD買って何度か聴いただけだったので、
今回リイシュー盤を聴いても他の曲はほぼぼ覚えていませんでした。
今回聴いた感想、意外と重たくなかった。
その曲のイメージに引っ張られ過ぎていたようですね。
5曲目Droned、アフリカンビートにのったアフリカ風の激しい
スキャットを聴いて、やっぱりこの人ただ者じゃないと再認識しました。
そしてビートルズTomorrow Never Knowsを
最後にカヴァー、これが嬉しい、この人カッコいい。
◎2nd HELLO I MUST BE GOING (1982) ※31歳


この角度では今の写真の頬骨の出っ張りが目立ちますね。
そして目つきも、若い頃の真剣さに齢を重ねた
思慮深さが加わっています。
僕がリアルタイムで初めて接したフィル・コリンズは、
中学時代、ここからのシングルヒット曲You Can't Hurry Love、
「ベストヒットUSA」を観始めた頃に流れました。
言わずと知れたダイアナ・ロス&スープリームスNo.1ヒット曲の
カヴァーですが、ビデオクリップのフィルがキューピー人形みたいで、
翌日朝のクラスメートで「おもろいおっさんやな」と
なぜか関西弁もどきでみんな言い合ったものです。
その曲はすぐにカヴァーと知りましたが、
日本ではフィルのカヴァーがあってから
オリジナルも見直されてCMで使われたりもしました。
しかし当時LPは買わず、1作目同様20代にCDを買うだけ買って
ほとんど聴いていないに等しく、アルバムの印象がまるでなかった。
今回やはりこれも思っていたよりずっとポップで、
スープリームスのその曲をカヴァーで選んだ理由も分かったし、
やっぱりジェネシスでABACABを作った人だとよく分かりました。
まあ逆にいえば、僕にとって2作目までのフィルのイメージは
ほとんどIn The Air Tonightだったということで、
イメージの刷り込みって恐ろしいなと。
◎3rd NO JACKET REQUIRED (1985) ※34歳


このアルバムは、なぜか汗をかいているフィルが当時は
恐かったのですが、新盤ではほとんど「妖怪」と化していますね・・・
やっぱり頬がこけたのがいちばん変わったところですね。
アルバムについてはもう話し出すと長いのですが、
フィルのアルバムでもいちばんよく聴いたし、
僕がLPで買ったリアルタイムのアルバムでもいちばん
聴いた回数が多い1枚だと思う、とだけ話して次に行きます。
何曲かは記事にしましたが、アルバムもそのうち。
◎4TH ...BUT SERIOUSLY (1989) ※38歳


新盤では目つきが険しくなっているのは一貫していますね。
そしてこのアルバムも若い頃は意外と
肌の艶がよかったんだって(笑)。
このアルバムは当時、グラミー賞を取った3作目以上の
傑作だと言われました。
今回リイシュー盤を聴いて、僕もそう思う。
「AORではない大人のロック」を構築した、そんな感じですね
(決してAORを非難してはいません念のため・・・)
タイトルも、フィル・コリンズは明るく陽気でお茶ら気もしかねない
おじさんというパブリックイメージが出来上がった後で、
「だけど真面目なんだよ」というそのユーモアがいい。
Another Day In Paradiseは重たいメッセージソングであり、
そこも評価が高かったところ。
I Wish It Would Rain Down邦題「雨にお願い」は
エリック・クラプトンが参加し素晴らしいギターソロを聴かせる
抒情的な名曲で、今回あらためて惚れ直しました。
そして今はこのアルバムをCDプレイヤーに入れっ放しで
聴き込んでいます。
元々このアルバムは当時おざなりに聴いていただけに、
いつかしっかりと聴き込もうと思っていたのです。
◎5th BOTH SIDES (1993) ※42歳


お気づきかと思いますがここまで5作みな顔のアップ。
フィル・コリンズは、かつて「顔のきれいな小遊三」と
「大喜利」で言っていた三遊亭小遊三師匠に通じる
キャラがあるのではないか、と。
ハンサムではない(イケメンという言葉は使いたくない)ことを
逆手に取ったのも、キャラクターとして
フィルが受け入れられた部分でしょうね。
まあ、額から上が写っていないのは内緒ということで・・・
アルバムは当時ほぼまったく聴いていないに等しく、
MTVで流れた曲しか知らない。
この頃から弟がCDを買うようになったのだと思う、
僕は持っておらず、弟が聴き終ったら借りてかけた、
それすらうっすらとそうじゃなかたったかと思うくらい。
フィルへの興味も薄れていました、白状すれば、
それは4作目を真面目に聴かなかったことを引きずっていたのだと
今にして思うけれど。
ただ、表題曲のタイトルを歌う部分が
「おっさんがひとーり」に聞こえる空耳が面白かった。
今回聴くと、うん、やっぱりフィル・コリンズはフィル・コリンズ、悪くない。
そのうち聴き込みたいですね。
◎6th DANCE INTO THE LIGHT (1996) ※45歳


下のオリジナルでは、全体に動きがある中で顔だけ
ぶれが少なくてよく見えるという、写真を撮る人間からいえば
かなり高度なテクニックを駆使していますが、
新盤では意図的かカメラマンが違うからかどうか分からないけれど、
顔がぶれた上で影になっていますね。
正直言えば、顔も同じような感じにしてほしかった、
個人的にはちょっとばかり残念。
(オリジナルはもしかして合成写真で今回はそれを嫌ったのかも)。
で、このアルバム、わけあって当時まったく聴いていません。
わけを聞くのは野暮ということで(笑)。
でも、聴かなかったおかげで音楽に個人的な思い出が
沁み込んではいないので、今なら冷静に聴けるかも。
◎7th TESTIFY (2002) ※51歳


さすがに今との顔の違いが少ないですね。
鼻横の八の字型の小じわはこの頃から目立ってきたんだな。
そしてやっぱり顔のアップに戻っています。
これは当時弟が買いましたが、コピーコントロールCDだったので
聴く気が失せました。
MTVも観なくなっていたので、これはまったく知らないに等しい。
と思ったけれどシングル曲はやっぱり知っていたのは、
さすがフィル・コリンズといったところか。
もちろんそのうち聴き込みたいと思っています。
◎8th GOING BACK (2010) ※59歳


これだけ大きくデザインもポーズも変えているのは、
さすがに子供の頃の写真と今とでは違和感あり過ぎるとの判断か。
それはそれで納得する反面、ここまで来たら
同じでやってほしかった気もしないでもない。
アルバムはほぼモータウンのカヴァー集ですが、
これがとってもいいですね。
昨年また引っ張り出してきて聴いたくらいに気に入っていますが、
ソウルのマナーによる「ソウルフル」な歌い方ではない、
こういうソウルの歌い方もあるのかと感心しました。
これはひとつの芸だと思いますね。
おかしなレトリックですが、「黒っぽくないけどソウルっぽい」、
そんな歌い方。
それを割と自然にやっているのは、
そういう資質があるということなのでしょうね。
曲ではスティーヴィー・ワンダーのBlame It On The Sun、
TALKING BOOKのアルバムの中の1曲としか
それまでは思っていなかったのが、
フィルの歌が僕にその本質と魅力を気づかせてくれました。
Papa Was A Rolling Stoneの緊迫感ある歌い方もはまっています。
ただ、今回のリイシュー盤では曲順を少し変えているのが
ちょっとばかり残念。
キャロル・キングのGoing Backは最後にあるからよかったのに。
まあでもそれは、今は次のアルバムを作っているという
フィルの意気込みなのでしょうね。
新作は期待したいです。
ボーナスディスクはライヴがメインですが、長くなったのでそれはまた。
さて、ここまでほぼほめる一辺倒で来ましたが、
ひとつだけ大きな大きな不満を。
ジャケット写真を今の姿で撮り直すという試みは
非常に面白いし大拍手もので僕も好きです。
しかし、オリジナルの古い写真を今回まったく使っていないのは
納得できない。
ないんですよ、裏にもブックレットの中にもどこにも。
裏をオリジナルの写真にしたり、ブックレットの中に入れたり、
別の紙に印刷して挿入でもよかったのに(コストかかるだろうけど)。
オリジナルはやっぱり大切にしてほしいという思いは、
僕にもありますね、残念。
02

3作目のブックレットは、オリジナルのCD同様、
表が歌詞カード、裏がピンナップとなっていますが、
ここには当時の写真が使われています。
だから余計にオリジナルジャケット写真が欲しかった。
もしかして今の写真はデラックスエディションだけで
アルバムはオリジナルで出直したりするかも。
しかしですね、こうして並べて見ると明らかに違うのに
同じ人だと分かるという人間の能力の不思議も感じました。
人間は相手の目と鼻と口の位置関係でその人を認識している
という話を聞いたことがありますが、それにしても面白いですね。
最後は今朝の3ショットにて。
03


フィル・コリンズのスタジオアルバム8作のリイシュー・リマスター盤が
昨秋からほぼ隔月で2枚ずつリリースされ、この6月に完結しました。
今のところすべてボーナストラック付き2枚組デラックスエディションのみ、
アルバム単発でのリリースはないですが、今後はどうだろう。
このリイシュー盤がなんだか面白いというか「妙」で、
ぜひ記事にしたいと。
何が面白いかって?
冒頭マーサと一緒に写っている3作目NO JACKET REQUIREDの
ジャケット写真をご覧ください。
なにか「妙」じゃないですか?
どうやらこれ、リイシュー盤に合わせて、今のフィルが
オリジナル通りに新たに撮影し直したもののようです。
つまりリリース当時のジャケット写真ではない。
「妙」というか、面白い、そこからまず
フィル・コリンズのユーモア感覚が伝わってきますね。
ここからは1作ずつ、新ジャケットと旧ジャケットを並べ、
アルバムについてとりあえず短く話してゆきます。
写真は上が新盤、下が旧盤オリジナル、並び順にご注意ください。
◎1st FACES VALUE (1981) ※30歳


下のオリジナル、フィルの肌に張りがありますね。
こんなに若かったのかと逆に今驚いたくらい(笑)。
僕はこのアルバムは完全な後追いですが、高校時代に
ラジオで聴いたIn The Air Tonightにちょっと驚きました。
僕が知っていたフィル・コリンズはポップさ一筋、
曲調で暗いものはあっても、この曲にあるぬめっとした不気味さに
この人の恐さのようなものを感じ、ただのポップな人ではない、
なかなかやるなあ、すごい人じゃんと。
当時はジェネシスのMamaにも驚いたものですが、その後で
これを聴き、なるほどそういう人だったのかと理解できました。
その曲は後にJ-WAVE日曜朝の「トヨタ・カリフォルニア・クラシックス」
という番組で、他の人が
"I can hear the TOYOTA CALIFORNIA CLASSCS on J-WAVE"
と歌詞を変えてジングルのように使われていたことで、
僕の生活に溶け込んだ曲となりました。
しかしアルバムは20代の頃にCD買って何度か聴いただけだったので、
今回リイシュー盤を聴いても他の曲はほぼぼ覚えていませんでした。
今回聴いた感想、意外と重たくなかった。
その曲のイメージに引っ張られ過ぎていたようですね。
5曲目Droned、アフリカンビートにのったアフリカ風の激しい
スキャットを聴いて、やっぱりこの人ただ者じゃないと再認識しました。
そしてビートルズTomorrow Never Knowsを
最後にカヴァー、これが嬉しい、この人カッコいい。
◎2nd HELLO I MUST BE GOING (1982) ※31歳


この角度では今の写真の頬骨の出っ張りが目立ちますね。
そして目つきも、若い頃の真剣さに齢を重ねた
思慮深さが加わっています。
僕がリアルタイムで初めて接したフィル・コリンズは、
中学時代、ここからのシングルヒット曲You Can't Hurry Love、
「ベストヒットUSA」を観始めた頃に流れました。
言わずと知れたダイアナ・ロス&スープリームスNo.1ヒット曲の
カヴァーですが、ビデオクリップのフィルがキューピー人形みたいで、
翌日朝のクラスメートで「おもろいおっさんやな」と
なぜか関西弁もどきでみんな言い合ったものです。
その曲はすぐにカヴァーと知りましたが、
日本ではフィルのカヴァーがあってから
オリジナルも見直されてCMで使われたりもしました。
しかし当時LPは買わず、1作目同様20代にCDを買うだけ買って
ほとんど聴いていないに等しく、アルバムの印象がまるでなかった。
今回やはりこれも思っていたよりずっとポップで、
スープリームスのその曲をカヴァーで選んだ理由も分かったし、
やっぱりジェネシスでABACABを作った人だとよく分かりました。
まあ逆にいえば、僕にとって2作目までのフィルのイメージは
ほとんどIn The Air Tonightだったということで、
イメージの刷り込みって恐ろしいなと。
◎3rd NO JACKET REQUIRED (1985) ※34歳


このアルバムは、なぜか汗をかいているフィルが当時は
恐かったのですが、新盤ではほとんど「妖怪」と化していますね・・・
やっぱり頬がこけたのがいちばん変わったところですね。
アルバムについてはもう話し出すと長いのですが、
フィルのアルバムでもいちばんよく聴いたし、
僕がLPで買ったリアルタイムのアルバムでもいちばん
聴いた回数が多い1枚だと思う、とだけ話して次に行きます。
何曲かは記事にしましたが、アルバムもそのうち。
◎4TH ...BUT SERIOUSLY (1989) ※38歳


新盤では目つきが険しくなっているのは一貫していますね。
そしてこのアルバムも若い頃は意外と
肌の艶がよかったんだって(笑)。
このアルバムは当時、グラミー賞を取った3作目以上の
傑作だと言われました。
今回リイシュー盤を聴いて、僕もそう思う。
「AORではない大人のロック」を構築した、そんな感じですね
(決してAORを非難してはいません念のため・・・)
タイトルも、フィル・コリンズは明るく陽気でお茶ら気もしかねない
おじさんというパブリックイメージが出来上がった後で、
「だけど真面目なんだよ」というそのユーモアがいい。
Another Day In Paradiseは重たいメッセージソングであり、
そこも評価が高かったところ。
I Wish It Would Rain Down邦題「雨にお願い」は
エリック・クラプトンが参加し素晴らしいギターソロを聴かせる
抒情的な名曲で、今回あらためて惚れ直しました。
そして今はこのアルバムをCDプレイヤーに入れっ放しで
聴き込んでいます。
元々このアルバムは当時おざなりに聴いていただけに、
いつかしっかりと聴き込もうと思っていたのです。
◎5th BOTH SIDES (1993) ※42歳


お気づきかと思いますがここまで5作みな顔のアップ。
フィル・コリンズは、かつて「顔のきれいな小遊三」と
「大喜利」で言っていた三遊亭小遊三師匠に通じる
キャラがあるのではないか、と。
ハンサムではない(イケメンという言葉は使いたくない)ことを
逆手に取ったのも、キャラクターとして
フィルが受け入れられた部分でしょうね。
まあ、額から上が写っていないのは内緒ということで・・・
アルバムは当時ほぼまったく聴いていないに等しく、
MTVで流れた曲しか知らない。
この頃から弟がCDを買うようになったのだと思う、
僕は持っておらず、弟が聴き終ったら借りてかけた、
それすらうっすらとそうじゃなかたったかと思うくらい。
フィルへの興味も薄れていました、白状すれば、
それは4作目を真面目に聴かなかったことを引きずっていたのだと
今にして思うけれど。
ただ、表題曲のタイトルを歌う部分が
「おっさんがひとーり」に聞こえる空耳が面白かった。
今回聴くと、うん、やっぱりフィル・コリンズはフィル・コリンズ、悪くない。
そのうち聴き込みたいですね。
◎6th DANCE INTO THE LIGHT (1996) ※45歳


下のオリジナルでは、全体に動きがある中で顔だけ
ぶれが少なくてよく見えるという、写真を撮る人間からいえば
かなり高度なテクニックを駆使していますが、
新盤では意図的かカメラマンが違うからかどうか分からないけれど、
顔がぶれた上で影になっていますね。
正直言えば、顔も同じような感じにしてほしかった、
個人的にはちょっとばかり残念。
(オリジナルはもしかして合成写真で今回はそれを嫌ったのかも)。
で、このアルバム、わけあって当時まったく聴いていません。
わけを聞くのは野暮ということで(笑)。
でも、聴かなかったおかげで音楽に個人的な思い出が
沁み込んではいないので、今なら冷静に聴けるかも。
◎7th TESTIFY (2002) ※51歳


さすがに今との顔の違いが少ないですね。
鼻横の八の字型の小じわはこの頃から目立ってきたんだな。
そしてやっぱり顔のアップに戻っています。
これは当時弟が買いましたが、コピーコントロールCDだったので
聴く気が失せました。
MTVも観なくなっていたので、これはまったく知らないに等しい。
と思ったけれどシングル曲はやっぱり知っていたのは、
さすがフィル・コリンズといったところか。
もちろんそのうち聴き込みたいと思っています。
◎8th GOING BACK (2010) ※59歳


これだけ大きくデザインもポーズも変えているのは、
さすがに子供の頃の写真と今とでは違和感あり過ぎるとの判断か。
それはそれで納得する反面、ここまで来たら
同じでやってほしかった気もしないでもない。
アルバムはほぼモータウンのカヴァー集ですが、
これがとってもいいですね。
昨年また引っ張り出してきて聴いたくらいに気に入っていますが、
ソウルのマナーによる「ソウルフル」な歌い方ではない、
こういうソウルの歌い方もあるのかと感心しました。
これはひとつの芸だと思いますね。
おかしなレトリックですが、「黒っぽくないけどソウルっぽい」、
そんな歌い方。
それを割と自然にやっているのは、
そういう資質があるということなのでしょうね。
曲ではスティーヴィー・ワンダーのBlame It On The Sun、
TALKING BOOKのアルバムの中の1曲としか
それまでは思っていなかったのが、
フィルの歌が僕にその本質と魅力を気づかせてくれました。
Papa Was A Rolling Stoneの緊迫感ある歌い方もはまっています。
ただ、今回のリイシュー盤では曲順を少し変えているのが
ちょっとばかり残念。
キャロル・キングのGoing Backは最後にあるからよかったのに。
まあでもそれは、今は次のアルバムを作っているという
フィルの意気込みなのでしょうね。
新作は期待したいです。
ボーナスディスクはライヴがメインですが、長くなったのでそれはまた。
さて、ここまでほぼほめる一辺倒で来ましたが、
ひとつだけ大きな大きな不満を。
ジャケット写真を今の姿で撮り直すという試みは
非常に面白いし大拍手もので僕も好きです。
しかし、オリジナルの古い写真を今回まったく使っていないのは
納得できない。
ないんですよ、裏にもブックレットの中にもどこにも。
裏をオリジナルの写真にしたり、ブックレットの中に入れたり、
別の紙に印刷して挿入でもよかったのに(コストかかるだろうけど)。
オリジナルはやっぱり大切にしてほしいという思いは、
僕にもありますね、残念。
02

3作目のブックレットは、オリジナルのCD同様、
表が歌詞カード、裏がピンナップとなっていますが、
ここには当時の写真が使われています。
だから余計にオリジナルジャケット写真が欲しかった。
もしかして今の写真はデラックスエディションだけで
アルバムはオリジナルで出直したりするかも。
しかしですね、こうして並べて見ると明らかに違うのに
同じ人だと分かるという人間の能力の不思議も感じました。
人間は相手の目と鼻と口の位置関係でその人を認識している
という話を聞いたことがありますが、それにしても面白いですね。
最後は今朝の3ショットにて。
03

2016年06月24日
最近買った新譜CDをさらりと2016年6月
01

最近買って聴いているCDの記事です。
4月以降新録音による新譜アルバムが多く出たので、
今回は新譜に絞りました。
7枚+1枚(点)、早速いきます。
☆1枚目
FALLEN ANGELS
Bob Dylan
(2016)
ボブ・ディランのスタンダードシリーズ第2弾。
基本的に前作の延長で、ほぼ一発録りなのだそうです。
前作SHADOWS IN THE NIGHTよりは曲が小粒かな。
今のディランの気持ちがどこに向いているかが分かりますが、
これを聴いて僕はこう思いました。
「ディランさん、もう好きにして、こっちはついていくだけ!」
ディランは基本的に今歌いたい歌を歌いたい風に歌うだけ。
実はそれは昔からまったく変わっていない。
歌う対象としての曲のえり好みが時代により違うだけ。
それがオリジナルかスタンダードかも関係ない。
四捨五入してついに80の男がいまだに気持ちを失っていない。
もうそれだけで素晴らしいのではないですかね。
弟が行った東京公演では「枯葉」も歌ったそうですが、
こうなったら次は何を歌ってくれるか楽しみでしょうがない。
音楽的にどうこうというのは今回敢えて話すのをやめ、
とにかくボブ・ディランは素晴らしい、とだけ言って終わりますね。
☆2枚目
I STILL DO
Eric Clapton
(2016)
エリック・クラプトンの新作は意外と短い間隔で出ました。
このアルバムはひとこと「悪くない」。
この「悪くない」という言葉はちょっとしたさじ加減で
いかようにも解釈できますが、今回はいい意味で使っています。
多分今のエリックは、いいアルバムを作ろうとは
はなから考えていないのではないか。
もはや自分にはそいう役割は求められていない。
いい演奏が録音できていい曲があればそれ以上は望まない。
偶然かどうかJOURNEYMANという素晴らしい「アルバム」を
作ってしまったエリックに対して、アルバム至上主義者の僕は、
その後のエリックのそこに引っかかっていたのですが
僕が間違っていたと今回気づきました。
(その間のREPTILEはアルバムとしても大好きですが)。
でもクラプトンはもう既にロックに対して多大なる貢献をした、
好きなようにやればいいんじゃないか。
好きなようにやったエリックのブルージーな音楽は、僕も
理屈を超えて好きだから、もうそれ以上を求めるものでもない。
そう、この音がいいのです。
もうひとつ、エリックくらいになれば、新譜で元気な姿に
接したところで旧譜をまた引っ張り出して聴けばいい。
新譜は今の姿を伝えると同時にその人の作品に触れ直す
という意味もまた重要なのだと気づきました。
当たり前ですよね、新譜が出ると旧譜もまた売れるわけだし。
僕は今、たまたま最近でたクリームのオリジナルアルバムの
リマスター盤ボックスセットでクリームを、コンサートに行って
やはり影響を受けた弟が買ったLaylaの40周年ボックスセットで
デレク&ザ・ドミノズを、そして70年代RSOのベスト盤
TIME PIECESをまた引っ張り出してきて聴いています。
新作もCDプレイヤーに入りっ放しなので聴いてますが、
エリックとしてもそういう聴き方をされるのは嬉しいのでは、
と勝手ながら思っています・・・勝手すぎか(笑)。
だって、このアルバムでエリック自身が
「俺はまだやる」と宣言しているのだから、
その気持ちは受け止めたいですよね。
☆3枚目
2
MUDCRUTCH
(2016)
マッドクラッチのは先に記事を上げたので、
ご興味がある方はこちらをご覧ください。
ひとつだけ書き足し。
2曲目Dreams Of Flyingがとってもとっても気に入りました。
今年出会った新曲では多分一番好きになるだろうというくらいに。
CD聴き終ると必ず何度もこの曲を口ずさんでいます。
☆4枚目
STRANGER TO STRANGER
Paul Simon
(2016)
今回はその上ポール・サイモンまで!
今までのこの記事でいちばんの豪華メンバーでしょう。
ソロ13作目の今作は、アフリカ的要素がまた濃くなった印象。
リズム的な部分、和音の取り方、ちょっと変わった裏メロなど、
ここにきてまたこれ、結局、音楽家としてのポール・サイモンにとって
アフリカ音楽とは帰る場所なのかもしれない。
代表的なのが7曲目Proof Of Love、
アコースティックギターによるアフリカ的なアルペジオに
ほの暗い雰囲気、メッセージ性の高い歌詞で、
このギターの音だけでも聴き入ってしまう。
ここまで来るとこれがポール・サイモンらしいといか言いようがない。
そこから後はインストゥルメンタル部分を中心とした小品が並び、
決して派手に盛り上げない自然体のアコースティックギターサウンド。
大きな名を成したミュージシャンのなかで、これほどまでに
自分の音楽性が途中で変わった人もそうはいないのでは。
しかしよくよく考えると、若い頃にアメリカの音楽を追い求めた中で
ルーツを辿ってアフリカにたどり着いたのはある意味必然ともいえ、
そこがポール・サイモンのメッセージだと考えれば納得できます。
何より彼の優しい音楽にまだ触れられるのは嬉しいですね。
僕の場合は連装CDプレイヤーに入れているわけですが、
最初にこれを聴きたい、というよりは、他のCDからの流れで
これが出てくるとほっとする、そんな感じです、いい意味で。
ところで、一昨年から昨年にかけてスティングとジョイントツアーを
行っていたポール・サイモン、結局日本には来なかった。
オーストラリアとニュージーランドにはきていたのですが、
やっぱりそこからが遠かったのかな。
ギャラが高すぎたのかもしれないけれど・・・残念。
☆5枚目
THE HEART SPEAKS IN WHISPERS
Corinne Bailey Rae
(2016)
コリーヌ・ベイリー・レイはノラ・ジョーンズの後に出て来た
ジャズっぽいコケティッシュな女性ヴォーカルの一人、大きく括れば。
1枚目はジャズっぽさが濃かったですが、今作はそこまでではない。
まあアデルよりはうんとジャズですが、彼女の場合、
「けだるさ」がジャズっぽさと直結していた部分があったのでしょう。
4作目のこれ、ひとことでいえば「年齢不詳の不思議ちゃん」。
彼女は1979年生まれ、そうかノラ・ジョーンズと同い年か、
ついでにいえば僕の一回り下の同じ干支ですが、
歌い手のことを考えずに歌を聴いてその世界に想像を巡らすと、
日本でいえば女子大生の恋愛話のような雰囲気。
大学に通っていないとしても20代前半の女性を想像させる。
僕自身の経験ではそんなもの(伝聞としても)遠い昔話ですが(笑)、
だからそれは僕が昔経験した時代のものかもしれない、
もしかして今はそういう話の年代が上がっているのかな。
いや、そんなことはない、やっぱりどう聴いても20代前半。
そう思わされてしまうというのは逆に彼女が仕掛けたことかもですが、
そうだとすればなかなかの役者といえるでしょう。
結局女性はその頃の心を大切にしたいということなのかな。
まあ男性もそうかもしれないですが(きっとそうでしょう)。
今回はちょっとしたフック=仕掛けが印象的な曲が多く、
1曲目表題曲はまず「ささやき」コーラスがフェイドインしてきて、
「わーうおーうおーうおうl」というサビのスキャットに包まれ、
中間部で弾けてしまう。
7曲Horse Print Dressの「うぅっうぅっ」という
かわいらしい声のフレーズも耳について離れない。
(馬のプリントのドレスってどんな服だろう・・・!?・・・)
その他、ヴァースでささやきサビで弾ける曲が多いのは
決して偶然ではないはず。
「心がささやきかける」というタイトル通り思いを紡いでゆく。
最初は個人的な部分が強すぎると感じたのですが、
音楽としては面白いし良質なもので結局のところ気に入っています。
が、でもやっぱり、これは聴きたい気分を選ぶ音楽かな。
そういう話を受け止められる精神的余力があると素晴らしいけれど、
何の気なしに聴くのはできないし、連装CDプレイヤーで流れても
その時の気分に合わないで変えることも多いCDではありますね。
☆6枚目
TAKE ME TO THE ALLEY
Gregory Porter
(2016)
グレゴリー・ポーターはBLUE NOTEから出ているように、
ジャンルとすればジャズヴォーカルなのでしょうけど、
実際はR&Bシンガーという方がよりしっくりきます。
僕は「ベストヒットUSA」で前作LIQUID SPIRITからの曲を
観て聴いて気に入りCDを買ったところ、それからすぐになんと
ヴァン・モリソンがDUETSに招いてThe Eternal Kansas Cityを
共演したことで応援するようになった、そんな人。
ヴァンさんに見初められたほどの人なんだ、と、
まあ僕も単純ですが(笑)、単純ついでにいえば、新譜が出ると聞き、
ヴァン・モリソンとの共演はないかと勝手に期待しすぐ予約。
入っていなかったのですが、まあそれは仕方ない。
今回聴いて、ひとつ分かりました。
ジャズヴォーカルは本来、歌い手が気持ちよく歌い、
その姿と声を好きな人が聴いて気持ちよくなるものだろう。
このアルバムでは1曲目Holding Onからまさにそんな響き。
つまり、好きかどうかの分岐点が早くも1曲目で現れる。
不特定多数の人に向けた良い意味でも良くない意味でも無機質な
メッセージを含んだポップソングとは違う。
だから本来は歌い手がより近しく感じられる小さい会場で映える。
これ実はひとつ前のコリーヌ・ベイリー・レイとも共通するのですが、
最初は個人的な部分が強く出過ぎていると感じてやや抵抗があった。
僕は逆、はじまりがビートルズという人間だから、より多くの人が聴く
ポップソングから自分だけの思いを見つけ出すのが好きだから。
でも、買った以上は何回も繰り返し聴くわけで、聴いてゆくうちに
僕もこの人がより好きになって来たのを感じました。
そうなると不思議なもので、それまでは曲もまあまあというくらいに
感じていたのが、これいい、こっちの曲もいいじゃん、となりました。
やはりじわじわと魅力が伝わるのはただのポップソングではない。
しかしその上で売れなければならないのだから大変でしょうけど、
こういう人が売れるようになったのはやっぱり、90年代以降、
音楽を聴く人の趣味がより多様化したことを感じますね。
5曲目Consequence Of Loveが僕はいちばん気に入った。
明るいようで少し裏に入っていく歌メロが絶品で、先述の
マッドクラッチにつづいて今年出会った中では特に好きな曲に。
7曲目More Than A Womanの女性を見つめる優しさは、
僕が慣れ親しんだポップソングの枠をはみ出していて、最初は
聴いていてこちらが恥ずかしくなったけれど、うん、それもあり。
今作は「希望へのアレイ」という邦題がついていますが、
3曲目表題曲はまさに「小さな希望」が散らばる路地をうまく表現。
じっくりと向かい合いたい音楽を求めている人にはおすすめですが、
CDを1から数回聴いて判断する人には向いていません。
これは軽く聴けない、じっくりと聴き込みたい1枚ですね。
☆7枚目
BEETHOVEN : MISSA SOLEMNIS
Nikolaus Harnoncourt (condt.)
Concentus Musicus Wien
(2016)
ロック、(一応は)ジャズときて最後はクラシック。
ニコラウス・アーノンクール。
"THE LAST RECORDING"とのシールが
スリップケースを覆うビニールに貼られていますが、
2015年夏に人前で演奏した最後の演奏が収められています。
最後の曲が「荘厳ミサ曲」。
偶然なのだろうか。
いや偶然に違いない。
2月に出たベートーヴェン交響曲4&5番のライナーノーツに、
ベートーヴェン交響曲のチックルス(全集)は終わらせるつもりで
臨んでいたことが書かれていたし。
しかし、結果として自らを送る曲であり演奏となってしまったのは、
感慨深いものがありますね。
僕は実はクラシックの宗教合唱曲が大好きなのです。
言葉の意味は分からないしクリスチャンでもないけれど(無宗教)、
気持ちの清らかさ、純粋さはどの宗教であっても、
人間である以上変わらないはず。
これは休みの日にゆっくりと聴きたいですね。
そしてあらためてニコラウス・アーノンクールという
偉大なる指揮者への感謝と尊敬の念が強くなりました。
☆おまけの8枚目
PURE McCARTNEY
Paul McCartney
(2016)
ポール・マッカートニーのUniversal初のベスト盤、
新曲はないけれどやっぱり入れておかなければ。
これが出た意味は大きいですからね。
そして今回は、それまでのベスト盤には入っていなかった曲を
聴き直して新たな発見があったことも楽しかった。
同じ曲でも聴き方聴かれ方で解釈は違ってくる。
これもまた音楽の興味深いところです。
ところで今回また一つ気づきました。
Junior's Farmも入っていない。
これもポールのベスト盤では裏人気的な曲でしたが、
C Moonともども70年代のそうした曲を今回落としたのは、
ポール・マッカートニーという人はやっぱり面白い、と。
02

ポーラ隠れキャラシリーズ第2弾・・・
いかがでしたか。
さて、まさに今日届いたばかりで聴いていない新譜や
まだ出ていない予約中の新譜もあり、リイシュー盤もあるなど、
CDの話題に事欠かないので、それらは新譜旧譜まとめて
7月にまた記事を上げることにしました。
最後は今朝の3ショットにて。
03


最近買って聴いているCDの記事です。
4月以降新録音による新譜アルバムが多く出たので、
今回は新譜に絞りました。
7枚+1枚(点)、早速いきます。
☆1枚目
FALLEN ANGELS
Bob Dylan
(2016)
ボブ・ディランのスタンダードシリーズ第2弾。
基本的に前作の延長で、ほぼ一発録りなのだそうです。
前作SHADOWS IN THE NIGHTよりは曲が小粒かな。
今のディランの気持ちがどこに向いているかが分かりますが、
これを聴いて僕はこう思いました。
「ディランさん、もう好きにして、こっちはついていくだけ!」
ディランは基本的に今歌いたい歌を歌いたい風に歌うだけ。
実はそれは昔からまったく変わっていない。
歌う対象としての曲のえり好みが時代により違うだけ。
それがオリジナルかスタンダードかも関係ない。
四捨五入してついに80の男がいまだに気持ちを失っていない。
もうそれだけで素晴らしいのではないですかね。
弟が行った東京公演では「枯葉」も歌ったそうですが、
こうなったら次は何を歌ってくれるか楽しみでしょうがない。
音楽的にどうこうというのは今回敢えて話すのをやめ、
とにかくボブ・ディランは素晴らしい、とだけ言って終わりますね。
☆2枚目
I STILL DO
Eric Clapton
(2016)
エリック・クラプトンの新作は意外と短い間隔で出ました。
このアルバムはひとこと「悪くない」。
この「悪くない」という言葉はちょっとしたさじ加減で
いかようにも解釈できますが、今回はいい意味で使っています。
多分今のエリックは、いいアルバムを作ろうとは
はなから考えていないのではないか。
もはや自分にはそいう役割は求められていない。
いい演奏が録音できていい曲があればそれ以上は望まない。
偶然かどうかJOURNEYMANという素晴らしい「アルバム」を
作ってしまったエリックに対して、アルバム至上主義者の僕は、
その後のエリックのそこに引っかかっていたのですが
僕が間違っていたと今回気づきました。
(その間のREPTILEはアルバムとしても大好きですが)。
でもクラプトンはもう既にロックに対して多大なる貢献をした、
好きなようにやればいいんじゃないか。
好きなようにやったエリックのブルージーな音楽は、僕も
理屈を超えて好きだから、もうそれ以上を求めるものでもない。
そう、この音がいいのです。
もうひとつ、エリックくらいになれば、新譜で元気な姿に
接したところで旧譜をまた引っ張り出して聴けばいい。
新譜は今の姿を伝えると同時にその人の作品に触れ直す
という意味もまた重要なのだと気づきました。
当たり前ですよね、新譜が出ると旧譜もまた売れるわけだし。
僕は今、たまたま最近でたクリームのオリジナルアルバムの
リマスター盤ボックスセットでクリームを、コンサートに行って
やはり影響を受けた弟が買ったLaylaの40周年ボックスセットで
デレク&ザ・ドミノズを、そして70年代RSOのベスト盤
TIME PIECESをまた引っ張り出してきて聴いています。
新作もCDプレイヤーに入りっ放しなので聴いてますが、
エリックとしてもそういう聴き方をされるのは嬉しいのでは、
と勝手ながら思っています・・・勝手すぎか(笑)。
だって、このアルバムでエリック自身が
「俺はまだやる」と宣言しているのだから、
その気持ちは受け止めたいですよね。
☆3枚目
2
MUDCRUTCH
(2016)
マッドクラッチのは先に記事を上げたので、
ご興味がある方はこちらをご覧ください。
ひとつだけ書き足し。
2曲目Dreams Of Flyingがとってもとっても気に入りました。
今年出会った新曲では多分一番好きになるだろうというくらいに。
CD聴き終ると必ず何度もこの曲を口ずさんでいます。
☆4枚目
STRANGER TO STRANGER
Paul Simon
(2016)
今回はその上ポール・サイモンまで!
今までのこの記事でいちばんの豪華メンバーでしょう。
ソロ13作目の今作は、アフリカ的要素がまた濃くなった印象。
リズム的な部分、和音の取り方、ちょっと変わった裏メロなど、
ここにきてまたこれ、結局、音楽家としてのポール・サイモンにとって
アフリカ音楽とは帰る場所なのかもしれない。
代表的なのが7曲目Proof Of Love、
アコースティックギターによるアフリカ的なアルペジオに
ほの暗い雰囲気、メッセージ性の高い歌詞で、
このギターの音だけでも聴き入ってしまう。
ここまで来るとこれがポール・サイモンらしいといか言いようがない。
そこから後はインストゥルメンタル部分を中心とした小品が並び、
決して派手に盛り上げない自然体のアコースティックギターサウンド。
大きな名を成したミュージシャンのなかで、これほどまでに
自分の音楽性が途中で変わった人もそうはいないのでは。
しかしよくよく考えると、若い頃にアメリカの音楽を追い求めた中で
ルーツを辿ってアフリカにたどり着いたのはある意味必然ともいえ、
そこがポール・サイモンのメッセージだと考えれば納得できます。
何より彼の優しい音楽にまだ触れられるのは嬉しいですね。
僕の場合は連装CDプレイヤーに入れているわけですが、
最初にこれを聴きたい、というよりは、他のCDからの流れで
これが出てくるとほっとする、そんな感じです、いい意味で。
ところで、一昨年から昨年にかけてスティングとジョイントツアーを
行っていたポール・サイモン、結局日本には来なかった。
オーストラリアとニュージーランドにはきていたのですが、
やっぱりそこからが遠かったのかな。
ギャラが高すぎたのかもしれないけれど・・・残念。
☆5枚目
THE HEART SPEAKS IN WHISPERS
Corinne Bailey Rae
(2016)
コリーヌ・ベイリー・レイはノラ・ジョーンズの後に出て来た
ジャズっぽいコケティッシュな女性ヴォーカルの一人、大きく括れば。
1枚目はジャズっぽさが濃かったですが、今作はそこまでではない。
まあアデルよりはうんとジャズですが、彼女の場合、
「けだるさ」がジャズっぽさと直結していた部分があったのでしょう。
4作目のこれ、ひとことでいえば「年齢不詳の不思議ちゃん」。
彼女は1979年生まれ、そうかノラ・ジョーンズと同い年か、
ついでにいえば僕の一回り下の同じ干支ですが、
歌い手のことを考えずに歌を聴いてその世界に想像を巡らすと、
日本でいえば女子大生の恋愛話のような雰囲気。
大学に通っていないとしても20代前半の女性を想像させる。
僕自身の経験ではそんなもの(伝聞としても)遠い昔話ですが(笑)、
だからそれは僕が昔経験した時代のものかもしれない、
もしかして今はそういう話の年代が上がっているのかな。
いや、そんなことはない、やっぱりどう聴いても20代前半。
そう思わされてしまうというのは逆に彼女が仕掛けたことかもですが、
そうだとすればなかなかの役者といえるでしょう。
結局女性はその頃の心を大切にしたいということなのかな。
まあ男性もそうかもしれないですが(きっとそうでしょう)。
今回はちょっとしたフック=仕掛けが印象的な曲が多く、
1曲目表題曲はまず「ささやき」コーラスがフェイドインしてきて、
「わーうおーうおーうおうl」というサビのスキャットに包まれ、
中間部で弾けてしまう。
7曲Horse Print Dressの「うぅっうぅっ」という
かわいらしい声のフレーズも耳について離れない。
(馬のプリントのドレスってどんな服だろう・・・!?・・・)
その他、ヴァースでささやきサビで弾ける曲が多いのは
決して偶然ではないはず。
「心がささやきかける」というタイトル通り思いを紡いでゆく。
最初は個人的な部分が強すぎると感じたのですが、
音楽としては面白いし良質なもので結局のところ気に入っています。
が、でもやっぱり、これは聴きたい気分を選ぶ音楽かな。
そういう話を受け止められる精神的余力があると素晴らしいけれど、
何の気なしに聴くのはできないし、連装CDプレイヤーで流れても
その時の気分に合わないで変えることも多いCDではありますね。
☆6枚目
TAKE ME TO THE ALLEY
Gregory Porter
(2016)
グレゴリー・ポーターはBLUE NOTEから出ているように、
ジャンルとすればジャズヴォーカルなのでしょうけど、
実際はR&Bシンガーという方がよりしっくりきます。
僕は「ベストヒットUSA」で前作LIQUID SPIRITからの曲を
観て聴いて気に入りCDを買ったところ、それからすぐになんと
ヴァン・モリソンがDUETSに招いてThe Eternal Kansas Cityを
共演したことで応援するようになった、そんな人。
ヴァンさんに見初められたほどの人なんだ、と、
まあ僕も単純ですが(笑)、単純ついでにいえば、新譜が出ると聞き、
ヴァン・モリソンとの共演はないかと勝手に期待しすぐ予約。
入っていなかったのですが、まあそれは仕方ない。
今回聴いて、ひとつ分かりました。
ジャズヴォーカルは本来、歌い手が気持ちよく歌い、
その姿と声を好きな人が聴いて気持ちよくなるものだろう。
このアルバムでは1曲目Holding Onからまさにそんな響き。
つまり、好きかどうかの分岐点が早くも1曲目で現れる。
不特定多数の人に向けた良い意味でも良くない意味でも無機質な
メッセージを含んだポップソングとは違う。
だから本来は歌い手がより近しく感じられる小さい会場で映える。
これ実はひとつ前のコリーヌ・ベイリー・レイとも共通するのですが、
最初は個人的な部分が強く出過ぎていると感じてやや抵抗があった。
僕は逆、はじまりがビートルズという人間だから、より多くの人が聴く
ポップソングから自分だけの思いを見つけ出すのが好きだから。
でも、買った以上は何回も繰り返し聴くわけで、聴いてゆくうちに
僕もこの人がより好きになって来たのを感じました。
そうなると不思議なもので、それまでは曲もまあまあというくらいに
感じていたのが、これいい、こっちの曲もいいじゃん、となりました。
やはりじわじわと魅力が伝わるのはただのポップソングではない。
しかしその上で売れなければならないのだから大変でしょうけど、
こういう人が売れるようになったのはやっぱり、90年代以降、
音楽を聴く人の趣味がより多様化したことを感じますね。
5曲目Consequence Of Loveが僕はいちばん気に入った。
明るいようで少し裏に入っていく歌メロが絶品で、先述の
マッドクラッチにつづいて今年出会った中では特に好きな曲に。
7曲目More Than A Womanの女性を見つめる優しさは、
僕が慣れ親しんだポップソングの枠をはみ出していて、最初は
聴いていてこちらが恥ずかしくなったけれど、うん、それもあり。
今作は「希望へのアレイ」という邦題がついていますが、
3曲目表題曲はまさに「小さな希望」が散らばる路地をうまく表現。
じっくりと向かい合いたい音楽を求めている人にはおすすめですが、
CDを1から数回聴いて判断する人には向いていません。
これは軽く聴けない、じっくりと聴き込みたい1枚ですね。
☆7枚目
BEETHOVEN : MISSA SOLEMNIS
Nikolaus Harnoncourt (condt.)
Concentus Musicus Wien
(2016)
ロック、(一応は)ジャズときて最後はクラシック。
ニコラウス・アーノンクール。
"THE LAST RECORDING"とのシールが
スリップケースを覆うビニールに貼られていますが、
2015年夏に人前で演奏した最後の演奏が収められています。
最後の曲が「荘厳ミサ曲」。
偶然なのだろうか。
いや偶然に違いない。
2月に出たベートーヴェン交響曲4&5番のライナーノーツに、
ベートーヴェン交響曲のチックルス(全集)は終わらせるつもりで
臨んでいたことが書かれていたし。
しかし、結果として自らを送る曲であり演奏となってしまったのは、
感慨深いものがありますね。
僕は実はクラシックの宗教合唱曲が大好きなのです。
言葉の意味は分からないしクリスチャンでもないけれど(無宗教)、
気持ちの清らかさ、純粋さはどの宗教であっても、
人間である以上変わらないはず。
これは休みの日にゆっくりと聴きたいですね。
そしてあらためてニコラウス・アーノンクールという
偉大なる指揮者への感謝と尊敬の念が強くなりました。
☆おまけの8枚目
PURE McCARTNEY
Paul McCartney
(2016)
ポール・マッカートニーのUniversal初のベスト盤、
新曲はないけれどやっぱり入れておかなければ。
これが出た意味は大きいですからね。
そして今回は、それまでのベスト盤には入っていなかった曲を
聴き直して新たな発見があったことも楽しかった。
同じ曲でも聴き方聴かれ方で解釈は違ってくる。
これもまた音楽の興味深いところです。
ところで今回また一つ気づきました。
Junior's Farmも入っていない。
これもポールのベスト盤では裏人気的な曲でしたが、
C Moonともども70年代のそうした曲を今回落としたのは、
ポール・マッカートニーという人はやっぱり面白い、と。
02

ポーラ隠れキャラシリーズ第2弾・・・
いかがでしたか。
さて、まさに今日届いたばかりで聴いていない新譜や
まだ出ていない予約中の新譜もあり、リイシュー盤もあるなど、
CDの話題に事欠かないので、それらは新譜旧譜まとめて
7月にまた記事を上げることにしました。
最後は今朝の3ショットにて。
03

2016年05月11日
最近買ったCDとレコードをさらりと2016年5月
01

最近買ったCDをさらりと紹介する記事です。
今回は特別にレコードもあります。
5月6月が新作新譜のラッシュとなっており、
今回は早めにこの記事を上げます。
☆1枚目
HITNRUN PHASE TWO
Prince
2016
今回はプリンスの新譜から紹介しないわけにはゆかない。
今作は、もしプリンスが80年代にいろいろなことを試さずに
ポップな音楽だけをやっていたらこうなっていたであろうという音。
というのはもちろんレトリックで、実際はプリンスがここまでいろいろな
ことを試したものが熟成されてこのかたちになったのでしょうけど、
80年代育ちには80年代を感じさせる音であるのは確かです。
1曲目Baltimoreのイントロなんて、絶対どこかで聴いたことがある
という感覚で最初から嬉しくなる。
ところでミネアポリスのプリンスがボルティモアを歌って大丈夫かな、
などとNFLファンとしては余計なことも思ってしまいますが(笑)。
5曲目Stareでは歌詞で"kiss"と歌った後、80年代のNo.1ヒット曲
Kissのイントロのギターが入るというお遊びも。
そして9曲目Screwdriverの異様なまでのポップさ、
"I'm your driver, you're my screw"と恥じらうように歌うプリンスに
胸がきゅんとなる、なんて自分で言うのも恥ずかしいけれど(笑)、
思わずそういう気持ちになってしまう音の響きと曲で気に入りました。
80年代からのファンにとっては嬉しい贈り物ではありますが、でも、
果たしてこれはプリンスがほんとにやりたかったことなのだろうかと
しばし悩む。
同窓会的に仲間内で盛り上がるプリンスというのも想像しがたい。
80年代にそれをやらなかったのがプリンスの偉大なところですが、
今の時代に80年代を懐かしく思い出させてくれるのは
プリンスの人間臭さなのかもしれない。
このアルバムがいいのは、聴いている瞬間は
「プリンスが死んだ」とはあまり思わないこと。
死を謳ったり示唆するような曲や音がなく、前向きに生きてゆこう、
毎日の生活は楽しいんだよ、というメッセージを感じる。
あたり前なのかもしれないけれど、でも、デヴィッド・ボウイの
遺作のことがあり、それとの対比で余計にそう感じてしまう。
プリンスというミュージシャンがこの世にいてよかったと、
現在形で思える、とても楽しいアルバムですね。
ところでこのアルバム、異様に音が大きい。
連装CDプレイヤーで続けて聴くとこれの時は音量を必ず下げる。
こんなに音が大きいCD初めて、というくらいです。
まあ、だからといって大きな問題ではないのですが、それが
わざとであればいかにもプリンスらしいいたずらだなぁ、と。
☆2枚目
360 DEGREES OF BILLY PAUL
Billy Paul
1972
ビリー・ポールが亡くなりました。享年81。
1970年代にフィラデルフィア「フィリー」ソウルを盛り上げたひとりで、
Me And Mrs. JonesをビルボードNo.1に送り込んだソウル歌手。
僕は聴いたことがなかったのですが、その曲はビルボードNo.1に
なった曲の逸話を集めた本で知っていたし、ビリー・ポールも、
さいたまのソウルマニア友だちMがよく話をしていました。
今回、亡くなられたのを機に、その曲を収めたこのアルバム、
リイシュー盤のCDを買って聴きました。
亡くなったミュージシャンの音楽を聴くことが一番の供養になる、と。
R.I.P.
件のMe And Mrs. Jones、1位になっただけあってもしかして
どこかで耳にしたことがあるかなと思いCDをかけると、残念、
おぼろげにでも耳にしたことがある記憶はなかった。
全体的にジャズっぽい雰囲気で、タイトルを歌うところで
声を張り上げて演奏が終わるのが印象的。
いかにもソウルが幸福だった時代の曲、といったところですね。
全体的には刑事ものの映画のサントラのような響き。
まあそれってカーティス・メイフィールドのイメージかもですが。
「こってり度」が予想よりも薄かったかな、意外と爽やか。
声質が鋭いのではなく拡散してゆくタイプだからかもしれない。
今回あらためて思ったのは、60年代後半から70年代前半は
ロックの楽曲をソウル風に楽しく趣向を凝らしてカヴァーするかが
流行っていた、そんな時代だったということ。
しかも今回は、キャロル・キングIt's Too Lateと
エルトン・ジョンYour Songという、シンガーソングライター時代の
定番中の定番を2曲も選んでいるのが興味深い。
どちらもAメロは大きく崩してイメージを変えていて、
Bメロつまりサビに来たところで「ああこの曲だったか」と思う、
もう完全に自分の曲にしている。
もう1曲アル・グリーンLet's Stay Togetherも歌ってますが、
こちらもテンポを落として形だけは「ねっとり度」が増しているけど、
アルの彼女の心をくすぐるような感触ではなく、
実直に言ってしまおう、といった心意気に聴こえるかな。
時代を強く感じる音であり、僕の中の洋楽ソウルのイメージ
そのままの音でした。
ところで、ビリー・ポールの訃報に接した瞬間、
僕は秋葉原のタワーレコードを思い出しました。
6年前東京に行った際に、Columbia系のソウル輸入盤CDが
1000円というワゴンがあり、中にこのCDもありました。
当時はソウル熱が盛り上がっていたこともあり、買おうかどうか
迷いましたが、リマスター盤が出るかもしれないと思い買わず。
代わりにビル・ウィザースのカーネギーホールのライヴを買いました。
爾来、ビリー・ポールといえばその時のことを思い出しますが、
買わなくても思い出になるという貴重な経験でもありました。
遅くなりましたが、結果として買い直すことなくリイシュー盤が
買えたので、これが僕の聴くタイミングだったのでしょう。
☆3枚目
IN YOUR EYES
George Benson
1983
ジョージ・ベンソン1080円シリーズをもう1枚買いました。
はい、今の自分はこの音が好きなのです。
アルバムとしては前回紹介したGIVE ME THE NIGHTの
次で20/20の3つ前の作品ということになります。
音楽としては前作のいい流れにありますが、今作は
アリフ・マーディンがほとんどの曲をプロデュースしていて、
前のクインシー・ジョーンズが(いい意味での)はったりを効かせた
サウンドとは違い、おとなしくじわじわと盛り上がる感じの音。
プロデューサーでこれだけ違うものなのだ、と実感しました。
かといって20/20ほど80年代ベッタリのサウンドではなくて、
80年代を経験していない(あるいは通過した)人には
入りやすいのではないかと、20/20と比べて思いました。
1曲目Feel Like Making Loveはどこかで聴いたことがある。
曲名は知らないけどジョージ・ベンソンの曲と知っていたもので、
CMの曲だったかな、或いはラジオやテレビで耳にしたのかも。
1曲目からとても懐かしくて気持ちが33年前に飛びました。
力強く歌うバラードの表題曲も、こちらはおぼろげながらも
聴いたことがあると思いましたが、そういう時代だったのでしょうね。
チャカ・カーンをフィーチャーしたLove Will Come Againの
作曲者にはアリフ・マーディンに加えて、元AWBにして
元ポール・マッカートニー・バンドのヘイミッシュ・スチュワート
の名前があるのがなんとも嬉しいじゃないですか。
今作もとても気に入りましたが、気づいていなかったけれど、
僕はどうやらジョージ・ベンソンが好きなようです。
この齢だから懐かしさもあるのでしょうね(笑)。
☆4枚目
STOLEN MOMENTS
John Hiatt
1990
今僕の中で密かな「流れ」にあるジョン・ハイアット。
弟が東京に行くと渋谷レコファンとディスクユニオン数店に行くのが
恒例で、僕が欲しい中古CDがあれば買ってきてもらいます。
今回のこれはレコファンで450円(!)の値札がついていたものが、
中古CDレコードを5枚以上買うと1枚あたり200円引きセール中で、
5枚買い(すべて今回紹介)、なんと250円で買えました。
状態もよく、1990年でCDの音質が良くなってきた頃のものでもあり、
お買い得でしたが、でもやはりジョン・ハイアット人気ないんだなあと・・・
それはともかく、うん、やっぱり僕はジョン・ハイアット大好き。
何がいいとか言われても答えられない。
曲も、歌も、声も、演奏も、音もみんな素直に受け入れてしまう。
ということを再確認しました。
僕は以前彼を「ムカシトカゲ」と表現しましたが、その通りで、
細かなサウンドの違い以外はいつの作品でもまったく変わらない。
良くない作品はない、どれもみな好きです。
しかしいくらムカシトカゲでも、生きてきた時代により音が微妙に
変わるのはむしろ人間として当然のこと。
このアルバムを聴いてまずこう思いました。
「当時はまだ真剣に大売れすることを考えていたんだな」
もう20年選手が近づいたものの、いまだ大ヒットには恵まれず、
一方で玄人好みのミュージシャンとして定着しつつあった。
CDの時代に音楽市場そのものが大きくなったこともあるでしょう。
グリン・ジョンズをプロデューサーに迎えた今作は、
音のメリハリがありしゃきっとしていて聴きやすい。
曲もいつものクオリティで、人の心を鷲掴みにはしないけれど、
なぜか後になってああいい曲だったんだと思い出す、というもの。
と書いてしまいましたが、なぜ大売れしないかはそこであって、
悲しいかな、ジョン・ハイアットがジョン・ハイアットである限り、
やはり大売れすることはないのだろうな、と。
今作も残念ながら最高61位でしたし、次作の僕が初めて買った
PERFECTLY GOOD GUITARも47位、以降最新作まで、
彼の「居場所」はその辺りで定着しました。
ジョン・ハイアットでもっとも順位が高いアルバムは、
2012年のMYSTIC PINBALLの39位、ですから。
まあそれでも、ファンとしては彼の音楽を聴けるのは幸せであり、
大売れは期待できなくてもCDを出し続けていられるのは、
彼自身も幸せなのではないかな、とも思います。
いつもいう、チャートで上位に来たからいい音楽であり、
低かったり入らなかったらよくないとはまったく思っていませんが、
チャートを通して聴く人の心が透けて見えるのが面白いのです。
☆5枚目
LIVE 1977 & 1979
Bad Company
バッド・カンパニーの公式ライヴアルバムがついに出ました。
正しくいえばポール・ロジャース脱退後や再結成後の
ライヴ盤は出ていますが、そうではない、「現役」の頃のものであり、
レーベルもCD盤面もSwan Song、これは嬉しいじゃないですか。
世の中ではあまり(ほとんど?)話題になっていないようですが、
バドカンのファンとしていえば、これは今年のロック界のいける
かなり大きなニュースなのです。
CD2枚組で、Disc1は1977年5月23日ヒューストン公演、
4作目のアルバムBURNIN' SKYを受けたツアーのもので、
そのアルバムからの曲が中心となっていいます。
そしてDisc2は1979年3月9日ロンドンのウェンブリー公演。
こちらは5作目DESOLATION ANGELESのツアーからですが、
Hey Joeのみ1979年6月26日ワシントン公演のものです。
インナースリーヴには1979年英国ツアーのパンフレットか
何かの宣伝写真があってこれがまた嬉しい。
CD1枚なので何曲かはカットしているかもしれないですが、
ライヴの雰囲気をたっぷりと味わうことができますね。
2枚で同じ曲はShooting StarとFeel Like Making Love
の2曲だけというのも嬉しいところですが、そうするために、
やはり何曲かカットしたのかなと思わなくもない。
あああとどちらにもサイモン・カークのDrum Soloがあります。
まあしかしそれは些細なことで、やっぱりバドカンいいですね。
演奏も歌もレコードとあまり変えていないのが何よりいい。
観客との一体感もあってその場が幸せそう。
そうそう音質は1枚目はまあまあで2枚目は少しいいかな。
2枚通して聴くと、最後の最後にCan't Get Enouoghが出てきて、
やっぱりこの曲のグルーヴ感と歌心は最高、となりますね。
個人的には、最も好きなアルバムRUN WITH THE PACK
からの曲が少ないのがちょっとだけ残念なところですが、だから
できれば続けてもう少し前のライヴも出してほしい、と(笑)。
☆6枚目
ANTONIN DVORAK : SLAVONIC DANCES
Nikolaus Harnoncourt
Chamber Orchestra of Europe
2002
クラシックも2枚、先ずは、先日亡くなられた
アーノンクールが手兵のヨーロッパ室内管弦楽団を振った
ドヴォルザーク「スラヴ舞曲集」。
アーノンクールの演奏はテンポが速いと前に触れましたが、
舞曲集であるこれはその速さが切れの鋭さにつながっていて
気持ちが舞い上がらざるを得ない高揚感があります。
1曲目のNo.1 Furiant (Presto)からもう気持ち掴まれます。
もちろんそういう速い曲ばかりではないのですが、これは
アーノンクールの中でもとりわけお気に入りの演奏になりましたね。
賑やかなので寝る前には聴けないのが難点ですが(笑)、
仕事から帰宅して元気づけにはとてもいい1枚です。
これも弟にレコファンで買ってきてもらった5枚の中の1枚ですが、
Amazonの中古にも出品されていて、ネットでは580円、
一方店頭では800円、ネットの方が安いことが分かりました。
ただ、Amazonの中古は送料257円が加算されるので、
それを考えると店頭価格の方が安いということになりますね。
ただし今回は5枚買うと200円引きだから600円で買えて、
結果としては安かったということになりました。
ところでレコファンは以前新宿や池袋など何軒かあり、
秋葉原にもあって東京にいた頃はよく行っていましたが、
今は店舗が渋谷と横浜だけになったようです。
CDが売れない時代だからとはいえ、寂しいですね。
せめて渋谷店は残ってもらいたい、東京の楽しみでもあるし。
弟に店の様子を聞いたところ、免税となっているため、
平日午後は外国人客が多かったとのことですが、そうか、
そういう道もあったのだと少しほっとしました。
さてここからは「5枚で200円引き」の残り3枚。
これが実はドーナツ盤ですが、それを紹介します。
☆7枚目

#9 Dream
John Lennon
1974
「夢の夢」
ビートルズとそのメンバーのシングル盤を集めています。
なんていきなり宣言してしまいましたが、中高生の頃に
中古ドーナツ盤を結構買っていて、ポールのは8割くらい
あるんじゃないかなというくらいに揃っています。
当時はものによっては1000円で3枚買えましたからね。
少し前、ここまで揃っているのだからいっそのこと今後少しずつ
買い集めて揃えようと、決意は大袈裟だけど、思いました。
ところがビートルズ関係のレコードは近年やはり
プレミアがつくようになり、ヒットしたもので500円以下、
1000円するのも珍しくなくなりました。
中古ドーナツ盤となると札幌では数店しかない上に少ない。
ブックオフでもLPはありますがシングルレコードは見たことがない。
だからやはり東京で買う、となりますね。
今回弟にレコファンで見てもらったところ、2枚ありました。
その1枚目がジョン・レノン「夢の夢」。
当時の定価500円ですが、これは1450円の200円引き。
ううん、ちょっとした出費ですかね。
シングルレコードは使われている写真も見ものですが、
これはジョンらしくていいスナップ写真ですね。
そして昔のドーナツ盤は「タタキ文句」も面白い。
書き出しましょう。
素敵な想い出も今は昔・・・
胸にしみわたるようなジョンの優しさあふれるロッカ・バラード!!
ジム・ケルトナー、ジェシー・エド・デイヴィス、
ニッキー・ホプキンス等が共演!
「ロッカ・バラード」という言葉は実に久し振りにきいた(笑)。
ジョンはまだまだ有名曲で持っていないのが多いですが、
高いんですよね、やっぱり、ポールよりも。
☆8枚目

Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
George Harrison
1973
「ギヴ・ミー・ラヴ」
続いてジョージ・ハリスン2曲目のNo.1ヒット曲。
写真は「バングラデシュ・コンサート」のものでしょうきっと。
しかし顔がピンボケ気味なのが気になります。
「タタキ文句」はないのですが、「歌とギター・ジョージ・ハリスン」
という表記に時代を感じます。
ジョージは持っていないものの方が多いですが、
そもそも出回った数が少なくて集めるのは大変そうです。
これは750円の200円引き。
☆9枚目
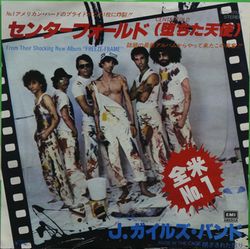
Centerfold
The J. Geils Band
1981
「センターフォールド(堕ちた天使)」
最後はビートルズ関係以外のJ・ガイルズ・バンド。
"J"でジョン・レノンを探していた時にたまたまあったものだとか。
これが入ったアルバムFREEZE-FRAMEは、僕が
ビートルズ以外で初めて買った洋楽LPであり、
思い出も思い入れも愛着もとても深いのですが、
ドーナツ盤は持っていなかったので「記念買い」しました。
これは450円の200円引き。
こちらも「タタキ文句」を
No.1アメリカン・ハードのプライドがこの1枚に炸裂!!
話題の最新アルバムからやって来たこの興奮!!
全米No.1
そうか、Jガイルズ・バンドはアメリカン「ハード」だったんだ。
でもこの「ハード」の捉え方が今とは少し違う気もします。
それとこの曲は「堕ちた天使」が正式な邦題ではなく、
原題をカタカナ表記したものとの併記だったんですね。
それにしても懐かしすぎる、ということで今回は終わります。
02

いかがでしたか。
今日のA公園展望台の一本桜。
近寄ると何輪か花が残っているのですが、もう葉桜ですね。
先述の通り今月来月は新譜ラッシュである上、
旧譜でもまだ紹介しきれていないものがあるので、
6月にならないうちにまたこの記事を上げるかもしれません。
最後は昨日の3ショット、車に戻った1枚を。
03


最近買ったCDをさらりと紹介する記事です。
今回は特別にレコードもあります。
5月6月が新作新譜のラッシュとなっており、
今回は早めにこの記事を上げます。
☆1枚目
HITNRUN PHASE TWO
Prince
2016
今回はプリンスの新譜から紹介しないわけにはゆかない。
今作は、もしプリンスが80年代にいろいろなことを試さずに
ポップな音楽だけをやっていたらこうなっていたであろうという音。
というのはもちろんレトリックで、実際はプリンスがここまでいろいろな
ことを試したものが熟成されてこのかたちになったのでしょうけど、
80年代育ちには80年代を感じさせる音であるのは確かです。
1曲目Baltimoreのイントロなんて、絶対どこかで聴いたことがある
という感覚で最初から嬉しくなる。
ところでミネアポリスのプリンスがボルティモアを歌って大丈夫かな、
などとNFLファンとしては余計なことも思ってしまいますが(笑)。
5曲目Stareでは歌詞で"kiss"と歌った後、80年代のNo.1ヒット曲
Kissのイントロのギターが入るというお遊びも。
そして9曲目Screwdriverの異様なまでのポップさ、
"I'm your driver, you're my screw"と恥じらうように歌うプリンスに
胸がきゅんとなる、なんて自分で言うのも恥ずかしいけれど(笑)、
思わずそういう気持ちになってしまう音の響きと曲で気に入りました。
80年代からのファンにとっては嬉しい贈り物ではありますが、でも、
果たしてこれはプリンスがほんとにやりたかったことなのだろうかと
しばし悩む。
同窓会的に仲間内で盛り上がるプリンスというのも想像しがたい。
80年代にそれをやらなかったのがプリンスの偉大なところですが、
今の時代に80年代を懐かしく思い出させてくれるのは
プリンスの人間臭さなのかもしれない。
このアルバムがいいのは、聴いている瞬間は
「プリンスが死んだ」とはあまり思わないこと。
死を謳ったり示唆するような曲や音がなく、前向きに生きてゆこう、
毎日の生活は楽しいんだよ、というメッセージを感じる。
あたり前なのかもしれないけれど、でも、デヴィッド・ボウイの
遺作のことがあり、それとの対比で余計にそう感じてしまう。
プリンスというミュージシャンがこの世にいてよかったと、
現在形で思える、とても楽しいアルバムですね。
ところでこのアルバム、異様に音が大きい。
連装CDプレイヤーで続けて聴くとこれの時は音量を必ず下げる。
こんなに音が大きいCD初めて、というくらいです。
まあ、だからといって大きな問題ではないのですが、それが
わざとであればいかにもプリンスらしいいたずらだなぁ、と。
☆2枚目
360 DEGREES OF BILLY PAUL
Billy Paul
1972
ビリー・ポールが亡くなりました。享年81。
1970年代にフィラデルフィア「フィリー」ソウルを盛り上げたひとりで、
Me And Mrs. JonesをビルボードNo.1に送り込んだソウル歌手。
僕は聴いたことがなかったのですが、その曲はビルボードNo.1に
なった曲の逸話を集めた本で知っていたし、ビリー・ポールも、
さいたまのソウルマニア友だちMがよく話をしていました。
今回、亡くなられたのを機に、その曲を収めたこのアルバム、
リイシュー盤のCDを買って聴きました。
亡くなったミュージシャンの音楽を聴くことが一番の供養になる、と。
R.I.P.
件のMe And Mrs. Jones、1位になっただけあってもしかして
どこかで耳にしたことがあるかなと思いCDをかけると、残念、
おぼろげにでも耳にしたことがある記憶はなかった。
全体的にジャズっぽい雰囲気で、タイトルを歌うところで
声を張り上げて演奏が終わるのが印象的。
いかにもソウルが幸福だった時代の曲、といったところですね。
全体的には刑事ものの映画のサントラのような響き。
まあそれってカーティス・メイフィールドのイメージかもですが。
「こってり度」が予想よりも薄かったかな、意外と爽やか。
声質が鋭いのではなく拡散してゆくタイプだからかもしれない。
今回あらためて思ったのは、60年代後半から70年代前半は
ロックの楽曲をソウル風に楽しく趣向を凝らしてカヴァーするかが
流行っていた、そんな時代だったということ。
しかも今回は、キャロル・キングIt's Too Lateと
エルトン・ジョンYour Songという、シンガーソングライター時代の
定番中の定番を2曲も選んでいるのが興味深い。
どちらもAメロは大きく崩してイメージを変えていて、
Bメロつまりサビに来たところで「ああこの曲だったか」と思う、
もう完全に自分の曲にしている。
もう1曲アル・グリーンLet's Stay Togetherも歌ってますが、
こちらもテンポを落として形だけは「ねっとり度」が増しているけど、
アルの彼女の心をくすぐるような感触ではなく、
実直に言ってしまおう、といった心意気に聴こえるかな。
時代を強く感じる音であり、僕の中の洋楽ソウルのイメージ
そのままの音でした。
ところで、ビリー・ポールの訃報に接した瞬間、
僕は秋葉原のタワーレコードを思い出しました。
6年前東京に行った際に、Columbia系のソウル輸入盤CDが
1000円というワゴンがあり、中にこのCDもありました。
当時はソウル熱が盛り上がっていたこともあり、買おうかどうか
迷いましたが、リマスター盤が出るかもしれないと思い買わず。
代わりにビル・ウィザースのカーネギーホールのライヴを買いました。
爾来、ビリー・ポールといえばその時のことを思い出しますが、
買わなくても思い出になるという貴重な経験でもありました。
遅くなりましたが、結果として買い直すことなくリイシュー盤が
買えたので、これが僕の聴くタイミングだったのでしょう。
☆3枚目
IN YOUR EYES
George Benson
1983
ジョージ・ベンソン1080円シリーズをもう1枚買いました。
はい、今の自分はこの音が好きなのです。
アルバムとしては前回紹介したGIVE ME THE NIGHTの
次で20/20の3つ前の作品ということになります。
音楽としては前作のいい流れにありますが、今作は
アリフ・マーディンがほとんどの曲をプロデュースしていて、
前のクインシー・ジョーンズが(いい意味での)はったりを効かせた
サウンドとは違い、おとなしくじわじわと盛り上がる感じの音。
プロデューサーでこれだけ違うものなのだ、と実感しました。
かといって20/20ほど80年代ベッタリのサウンドではなくて、
80年代を経験していない(あるいは通過した)人には
入りやすいのではないかと、20/20と比べて思いました。
1曲目Feel Like Making Loveはどこかで聴いたことがある。
曲名は知らないけどジョージ・ベンソンの曲と知っていたもので、
CMの曲だったかな、或いはラジオやテレビで耳にしたのかも。
1曲目からとても懐かしくて気持ちが33年前に飛びました。
力強く歌うバラードの表題曲も、こちらはおぼろげながらも
聴いたことがあると思いましたが、そういう時代だったのでしょうね。
チャカ・カーンをフィーチャーしたLove Will Come Againの
作曲者にはアリフ・マーディンに加えて、元AWBにして
元ポール・マッカートニー・バンドのヘイミッシュ・スチュワート
の名前があるのがなんとも嬉しいじゃないですか。
今作もとても気に入りましたが、気づいていなかったけれど、
僕はどうやらジョージ・ベンソンが好きなようです。
この齢だから懐かしさもあるのでしょうね(笑)。
☆4枚目
STOLEN MOMENTS
John Hiatt
1990
今僕の中で密かな「流れ」にあるジョン・ハイアット。
弟が東京に行くと渋谷レコファンとディスクユニオン数店に行くのが
恒例で、僕が欲しい中古CDがあれば買ってきてもらいます。
今回のこれはレコファンで450円(!)の値札がついていたものが、
中古CDレコードを5枚以上買うと1枚あたり200円引きセール中で、
5枚買い(すべて今回紹介)、なんと250円で買えました。
状態もよく、1990年でCDの音質が良くなってきた頃のものでもあり、
お買い得でしたが、でもやはりジョン・ハイアット人気ないんだなあと・・・
それはともかく、うん、やっぱり僕はジョン・ハイアット大好き。
何がいいとか言われても答えられない。
曲も、歌も、声も、演奏も、音もみんな素直に受け入れてしまう。
ということを再確認しました。
僕は以前彼を「ムカシトカゲ」と表現しましたが、その通りで、
細かなサウンドの違い以外はいつの作品でもまったく変わらない。
良くない作品はない、どれもみな好きです。
しかしいくらムカシトカゲでも、生きてきた時代により音が微妙に
変わるのはむしろ人間として当然のこと。
このアルバムを聴いてまずこう思いました。
「当時はまだ真剣に大売れすることを考えていたんだな」
もう20年選手が近づいたものの、いまだ大ヒットには恵まれず、
一方で玄人好みのミュージシャンとして定着しつつあった。
CDの時代に音楽市場そのものが大きくなったこともあるでしょう。
グリン・ジョンズをプロデューサーに迎えた今作は、
音のメリハリがありしゃきっとしていて聴きやすい。
曲もいつものクオリティで、人の心を鷲掴みにはしないけれど、
なぜか後になってああいい曲だったんだと思い出す、というもの。
と書いてしまいましたが、なぜ大売れしないかはそこであって、
悲しいかな、ジョン・ハイアットがジョン・ハイアットである限り、
やはり大売れすることはないのだろうな、と。
今作も残念ながら最高61位でしたし、次作の僕が初めて買った
PERFECTLY GOOD GUITARも47位、以降最新作まで、
彼の「居場所」はその辺りで定着しました。
ジョン・ハイアットでもっとも順位が高いアルバムは、
2012年のMYSTIC PINBALLの39位、ですから。
まあそれでも、ファンとしては彼の音楽を聴けるのは幸せであり、
大売れは期待できなくてもCDを出し続けていられるのは、
彼自身も幸せなのではないかな、とも思います。
いつもいう、チャートで上位に来たからいい音楽であり、
低かったり入らなかったらよくないとはまったく思っていませんが、
チャートを通して聴く人の心が透けて見えるのが面白いのです。
☆5枚目
LIVE 1977 & 1979
Bad Company
バッド・カンパニーの公式ライヴアルバムがついに出ました。
正しくいえばポール・ロジャース脱退後や再結成後の
ライヴ盤は出ていますが、そうではない、「現役」の頃のものであり、
レーベルもCD盤面もSwan Song、これは嬉しいじゃないですか。
世の中ではあまり(ほとんど?)話題になっていないようですが、
バドカンのファンとしていえば、これは今年のロック界のいける
かなり大きなニュースなのです。
CD2枚組で、Disc1は1977年5月23日ヒューストン公演、
4作目のアルバムBURNIN' SKYを受けたツアーのもので、
そのアルバムからの曲が中心となっていいます。
そしてDisc2は1979年3月9日ロンドンのウェンブリー公演。
こちらは5作目DESOLATION ANGELESのツアーからですが、
Hey Joeのみ1979年6月26日ワシントン公演のものです。
インナースリーヴには1979年英国ツアーのパンフレットか
何かの宣伝写真があってこれがまた嬉しい。
CD1枚なので何曲かはカットしているかもしれないですが、
ライヴの雰囲気をたっぷりと味わうことができますね。
2枚で同じ曲はShooting StarとFeel Like Making Love
の2曲だけというのも嬉しいところですが、そうするために、
やはり何曲かカットしたのかなと思わなくもない。
あああとどちらにもサイモン・カークのDrum Soloがあります。
まあしかしそれは些細なことで、やっぱりバドカンいいですね。
演奏も歌もレコードとあまり変えていないのが何よりいい。
観客との一体感もあってその場が幸せそう。
そうそう音質は1枚目はまあまあで2枚目は少しいいかな。
2枚通して聴くと、最後の最後にCan't Get Enouoghが出てきて、
やっぱりこの曲のグルーヴ感と歌心は最高、となりますね。
個人的には、最も好きなアルバムRUN WITH THE PACK
からの曲が少ないのがちょっとだけ残念なところですが、だから
できれば続けてもう少し前のライヴも出してほしい、と(笑)。
☆6枚目
ANTONIN DVORAK : SLAVONIC DANCES
Nikolaus Harnoncourt
Chamber Orchestra of Europe
2002
クラシックも2枚、先ずは、先日亡くなられた
アーノンクールが手兵のヨーロッパ室内管弦楽団を振った
ドヴォルザーク「スラヴ舞曲集」。
アーノンクールの演奏はテンポが速いと前に触れましたが、
舞曲集であるこれはその速さが切れの鋭さにつながっていて
気持ちが舞い上がらざるを得ない高揚感があります。
1曲目のNo.1 Furiant (Presto)からもう気持ち掴まれます。
もちろんそういう速い曲ばかりではないのですが、これは
アーノンクールの中でもとりわけお気に入りの演奏になりましたね。
賑やかなので寝る前には聴けないのが難点ですが(笑)、
仕事から帰宅して元気づけにはとてもいい1枚です。
これも弟にレコファンで買ってきてもらった5枚の中の1枚ですが、
Amazonの中古にも出品されていて、ネットでは580円、
一方店頭では800円、ネットの方が安いことが分かりました。
ただ、Amazonの中古は送料257円が加算されるので、
それを考えると店頭価格の方が安いということになりますね。
ただし今回は5枚買うと200円引きだから600円で買えて、
結果としては安かったということになりました。
ところでレコファンは以前新宿や池袋など何軒かあり、
秋葉原にもあって東京にいた頃はよく行っていましたが、
今は店舗が渋谷と横浜だけになったようです。
CDが売れない時代だからとはいえ、寂しいですね。
せめて渋谷店は残ってもらいたい、東京の楽しみでもあるし。
弟に店の様子を聞いたところ、免税となっているため、
平日午後は外国人客が多かったとのことですが、そうか、
そういう道もあったのだと少しほっとしました。
さてここからは「5枚で200円引き」の残り3枚。
これが実はドーナツ盤ですが、それを紹介します。
☆7枚目

#9 Dream
John Lennon
1974
「夢の夢」
ビートルズとそのメンバーのシングル盤を集めています。
なんていきなり宣言してしまいましたが、中高生の頃に
中古ドーナツ盤を結構買っていて、ポールのは8割くらい
あるんじゃないかなというくらいに揃っています。
当時はものによっては1000円で3枚買えましたからね。
少し前、ここまで揃っているのだからいっそのこと今後少しずつ
買い集めて揃えようと、決意は大袈裟だけど、思いました。
ところがビートルズ関係のレコードは近年やはり
プレミアがつくようになり、ヒットしたもので500円以下、
1000円するのも珍しくなくなりました。
中古ドーナツ盤となると札幌では数店しかない上に少ない。
ブックオフでもLPはありますがシングルレコードは見たことがない。
だからやはり東京で買う、となりますね。
今回弟にレコファンで見てもらったところ、2枚ありました。
その1枚目がジョン・レノン「夢の夢」。
当時の定価500円ですが、これは1450円の200円引き。
ううん、ちょっとした出費ですかね。
シングルレコードは使われている写真も見ものですが、
これはジョンらしくていいスナップ写真ですね。
そして昔のドーナツ盤は「タタキ文句」も面白い。
書き出しましょう。
素敵な想い出も今は昔・・・
胸にしみわたるようなジョンの優しさあふれるロッカ・バラード!!
ジム・ケルトナー、ジェシー・エド・デイヴィス、
ニッキー・ホプキンス等が共演!
「ロッカ・バラード」という言葉は実に久し振りにきいた(笑)。
ジョンはまだまだ有名曲で持っていないのが多いですが、
高いんですよね、やっぱり、ポールよりも。
☆8枚目

Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
George Harrison
1973
「ギヴ・ミー・ラヴ」
続いてジョージ・ハリスン2曲目のNo.1ヒット曲。
写真は「バングラデシュ・コンサート」のものでしょうきっと。
しかし顔がピンボケ気味なのが気になります。
「タタキ文句」はないのですが、「歌とギター・ジョージ・ハリスン」
という表記に時代を感じます。
ジョージは持っていないものの方が多いですが、
そもそも出回った数が少なくて集めるのは大変そうです。
これは750円の200円引き。
☆9枚目
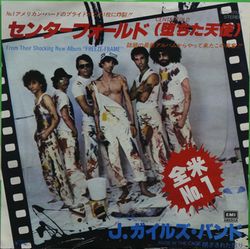
Centerfold
The J. Geils Band
1981
「センターフォールド(堕ちた天使)」
最後はビートルズ関係以外のJ・ガイルズ・バンド。
"J"でジョン・レノンを探していた時にたまたまあったものだとか。
これが入ったアルバムFREEZE-FRAMEは、僕が
ビートルズ以外で初めて買った洋楽LPであり、
思い出も思い入れも愛着もとても深いのですが、
ドーナツ盤は持っていなかったので「記念買い」しました。
これは450円の200円引き。
こちらも「タタキ文句」を
No.1アメリカン・ハードのプライドがこの1枚に炸裂!!
話題の最新アルバムからやって来たこの興奮!!
全米No.1
そうか、Jガイルズ・バンドはアメリカン「ハード」だったんだ。
でもこの「ハード」の捉え方が今とは少し違う気もします。
それとこの曲は「堕ちた天使」が正式な邦題ではなく、
原題をカタカナ表記したものとの併記だったんですね。
それにしても懐かしすぎる、ということで今回は終わります。
02

いかがでしたか。
今日のA公園展望台の一本桜。
近寄ると何輪か花が残っているのですが、もう葉桜ですね。
先述の通り今月来月は新譜ラッシュである上、
旧譜でもまだ紹介しきれていないものがあるので、
6月にならないうちにまたこの記事を上げるかもしれません。
最後は昨日の3ショット、車に戻った1枚を。
03

2016年04月06日
最近買ったCDをさらりと2016年4月
01

最近買ったCDさらりと紹介記事です。
今回からタイトルの「新譜旧譜合わせて」という言葉をやめ、
記事では新譜のみ「新譜」と明記してゆきます。
今回は8枚(点)、では早速。
☆1枚目
DIG IN DEEP
Bonnie Raitt
(2016)
ボニー・レイットの新譜、詳しくは
一昨日上げたこちらの記事をご覧ください。
書いているうちに長くなり、独立した記事にしたのでした。
☆2枚目
CARRYING A TORCH
Tom Jones
(1991)
トム・ジョーンズのこれはぽちわかやさんの紹介で買いました。
あらためてありがとうございます。
あのヴァン・モリソンがトム・ジョーンズをプロデュースしていた
なんて、まったく知らなかった、ある意味衝撃でした。
最初はミスマッチ感覚のように思えたけれど、聴いてみて納得。
ヴァン・モリソンも静かで穏やかなようで熱い人ですからね。
ヴァンさんの曲や音楽が持つエネルギーを、
トムさんがうまく引き出している、といえばいいかな。
ヴァンさんが書いた曲は1、2、4、12と4曲だけですが、
他の人が書いた曲も不思議とヴァン・モリソン風に
聴こえてきてしまうこの不思議。
特に3曲目Strange Boatはブックレットを見るまで、
ヴァン・モリソンの曲と信じて疑わなかったのですが
プロデューサーの色がここまで出るというのはある意味驚き。
それだけヴァンさんの個性が強烈なのでしょうね。
そしてその強烈さに対抗できる個性の持ち主はそうはいない。
トム・ジョーンズがその人だった。
聴き込んで考えるだに、これは最高の組み合わせだと
唸らされるようになってきました。
ちなみに作曲者として著名な人は他に、
ダイアン・ウォーレンとアルバート・ハモンド、
そしてポール・キャラックと、トム・ジョーンズもこの頃は
「メキメキ」で復活する直前のスランプ時期であり、
「本物の音楽」として聴かせることに傾注していたことが、
作曲者と曲の質を見ても分かります。
当時あまり売れなかったようで、僕も実は
まったく当時の記憶がないのですが、この後開き直って
「メキメキ」が売れて第一線に復活したといったところでしょうね。
売れなかったのはやはり僕のように「一瞬ミスマッチ感覚」に
襲われた人が多かったのでしょうね。
僕も当時からヴァン・モリソンを聴いていれば買ったかも、
と後で幾らでも思うことができるのですが(笑)、でもひとまず、
このアルバムを作ってくれたことに感謝ですね。
ほんと、ヴァンさんよく引き受けてくれたよなあ。
ヴァン・モリソン「外伝」として聴ける、なんとも嬉しいことか。
ちなみに、昨年春に出たヴァン・モリソンの本を見ると、
なんとというか、当たり前というか、これも紹介されていて
要するに読んでいなかったのでした・・・
☆3枚目、4枚目
GIVE ME THE NIGHT
(1980)
20/20
(1984)
George Benson
ジョージ・ベンソン2枚買いました。
順序は逆ですが、20/20は先頃記事を上げた
Nothing's Gonna Change My Love For You
を聴きたかったからで、もちろんその曲は気に入った。
ただ、アルバム全体としては、良くも悪くも80年代サウンドで、
リアルタイムだった僕には、懐かしくもちょっとくすぐったい音。
僕はジョージ・ベンソンそれまで2枚しか聴いていなかったですが、
この音は予想外でした。
ただ、音に慣れると曲は素晴らしくて聴きやすいアルバム。
最後のYou Are The Love Of My Lifeは、
ロバータ・フラックとのデュエットが素晴らしく
「至宝」ともいえるラヴバラード。
つまりこのアルバムには必殺ラヴバラードが2曲もある。
サウンドのマイナス面を補ってあまりある、ということですね。
一方その4作前のGIVE ME THE NIGHTは素晴らしい。
こんなに素晴らしいとは予想していなかった、申し訳ないけれど。
クインシー・ジョーンズと組んだことが売りともいえますが、
なるほど、クインシーが作るサウンドはきらびやかな響きで、
エッジが鋭く、都会的で洒落たサウンドが、
ジョージ・ベンソンのスター性をうまく引き出しているのでしょう。
同じクインシーで同じ頃のマイケル・ジャクソン
OFF THE WALLを思い出させてくれるサウンドでもあり、
ここがまた嬉しいところで、特に1曲目Love X Loveは曲の雰囲気が
マイケルのRock With Youに似ていて思わずにんまり。
そういえばOFF THE WALLのリイシュー盤出たばかりですね。
実は買った時に、リリース順でこっちを先に聴いていたので、
余計に20/20のサウンドにあれっと思ったのでした。
そして2枚聴いてあらためて思った。
ジョージ・ベンソン、歌がうまい。
うまいというより、表現力の引き出しが多いというか。
Nothing's...のようなラヴソングも、Give Me The Nightのような
ホップしたのりの曲も、Masquaradeのようなディープな歌い方も、
そしてGIVE...のラストTurn Out The Lamplightのような大人しい
曲をしみじみと、どれも自分のものとしてしっかりと歌っている。
僕が特に驚いたのはGive...の軽やかさで、軽いのに
しっかりと伝わってくる、すごいと思いました。
そして...Lamplightは隠れた名曲、とも。
ジョージ・ベンソン、はまったかな(笑)。
ひとまず廉価盤で出ているこの間の3枚を
次から買って聴いてみます。
☆5枚目
COOL STRUTTIN'
Sonny Clark
(1958)
ソニー・クラークのこれはジャズの最も有名なアルバムジャケットの
ひとつであり、日本のジャズ喫茶でいちばんリクエストが多かった
アルバムと言われているそうですね。
今更ながら買って聴きましたが、やはりというか、いいですね。
曲の旋律の掴みが強力で、ポップともいえるほどで、
人気があるのも分かりました。
と書きましたが、実は買って最初に聴いた時は
「インプロビゼーションが長い」という印象しか残らなくて、
どうしてこれが人気があったのだろうとすら思いました。
でも、2回目に聴いた後1週間ほど聴かなくて、せっかく
買ったのだからもったいないと、ただそれだけ思って
3回目をかけたときに、聴こえ方が一変し、ポップに感じました。
特に2曲目Blue Minor、ほのかにラテンの香りがする旋律が好き。
どうやら、最初は曲がポップだとは感じなかったようで、
やっぱり曲覚えが悪い弊害が・・・(笑)。
ただ、そこまで到達した上であらためて、このアルバムというか
この人の音楽には、ポップでつかみやすい部分と
インプロビゼーションの部分の二面性があるのでは、
という感じもしてきました。
いや、この人だけではない、時代だったのかもしれないですが、
ポップな方向から外れてしまったことを故中村とうよう氏が
嘆くように書いていたことを思い出しました。
僕は演奏もできないし、技術的な面は何も言えないのですが、
あくまでも感覚として、これはポップな部分が気に入りました。
そして僕はこれをなぜか朝起きて最初に聴くことが多い。
ジャズは夜というイメージがあるかもしれないですが、
朝に聴くのも結構いいですよ(笑)。
実は、ジャズのCDを買うのは半年振り、CDを聴くのですら
2カ月振りくらいだったのですが、ジョージ・ベンソンが
流れを呼んでくれたのでしょうね(笑)。
ところでこれ、中古でかなり出回っているようですね。
ジャケット買いして失敗したという人が多いのかな・・・(笑)。
☆6枚目
Maurice Rave
L'ENFANT ET LES SORTILEGES SHEHERAZADE
Seiji Ozawa(Condt) / Saito Kinen Orchestra
Isabel Leonard, Susan Graham
(2015)
小澤征爾指揮 ラヴェル:歌劇『子どもと魔法』
サイトウ・キネン・オーケストラ
レナード、グレアム
小澤征爾が初めてグラミー賞を受賞したと
日本でも話題になりましたが、そのCDを買いました。
受賞したのは「最優秀オペラ録音賞」で、小澤さんというより
むしろ裏方さんに与えられた賞でありますが、でも指揮したのは
間違いのない事実、小澤さんが受賞したと言っても
問題ないでしょうし、僕自身も受賞は嬉しかったです。
小澤さんはこれを機に、あまり知られていないオペラを
より多くの人に知って聴いてもらいたいということを
ニュースで語っていましたが、ほんとにそうですね。
僕はオペラに詳しいわけではないけれど、この作品は
知らなかったから、小澤さんの願い通りになっていますね。
ただですね、申し訳ないというか、今の僕はオペラを聴く
心の流れにはないようで、作品としてどうという感慨を、
今回は持つことができませんでした。
でもオペラもまあ好きだし、いずれ心の流れが来るでしょう。
買ってよかったとは当然思っています、念のため。
☆7枚目
Mozart
THE FOUR HORN CONCERTOS
Alan Civil(Horn)
Rudolf Kempe(Condt)
Royal Philharmonic Orchestra
(1966)
モーツァルト:ホルン協奏曲全集
アラン・シヴィル(ホルン)
ルドルフ・ケンペ指揮
ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団
先日のビートルズFor No Oneの記事において、間奏の
ホルンのソロを演奏している当時フィルハーモニア管弦楽団の
主席ホルン奏者だったアラン・シヴィルの話を紹介しました。
それでシヴィルさんのクラシックのCDも聴いてみたくなり、
調べると、このCDが最近廉価盤で出ていたことを知り即注文。
奇しくもFor No Oneと同じ1966年に録音されたもので、
指揮ルドルフ・ケンペ、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団演奏。
曲自体の感想。
ホルンの音色が天衣無縫なモーツァルトの音楽に合っている。
まあ、実際はどういう人か分からないですが・・・『アマデウス』・・・
先ず僕が思ったのはそれでした。
「音楽は天使の言葉を通訳できる人間が人間に分かる
ことばに翻訳したもの」、とも言われますが、ホルンの音色は
天使の声にいちばん近いのではないかと。
天使のお喋りを聴いているようにも感じます。
もちろん聴いたことはないですが・・・(笑)。
もしくは、子象が遊んでいるような雰囲気で、特にTr5、
第3番第3楽章はほんとにそんな感じがしますよ。
まあ、子象が遊ぶ姿も映像でしか観たことはないですが・・・(笑)。
演奏では、ホルンの音が一瞬だけ外れているように聴こえるのは、
ギターでいうチョーキング=ベンディングのような効果があって、
いい意味での揺らぎが出ていると感じました。
ホルンは演奏したことがないので僕には分からないですが、
これはホルンの構造上のことなのか、それともテクニックなのか、
とにかく音としてはそこがなんだか妙に気に入りました。
ルドルフ・ケンペは今でも人気が高い指揮者ですが、
僕は彼の指揮する演奏は初めて聴きました。
しかしこれは協奏曲で主役はあくまでもホルン奏者だから、
ケンペの演奏がどうということは特に感じなかった(すいません)。
60年代の録音としては音は優れていると感じました。
面白いのが、第1番1楽章つまりCDの最初のトラック、
これが「北の国から」のあの曲に旋律がよく似ている。
♪あ~あ~あああああ~ああ というやつですね。
最初の4小節は旋律がほんとによく似ていて、その次の小節への
移行も同じで、移ってからの2拍目までの旋律も似ている。
偶然なのでしょうけど、でもさだまさしがその曲を好きだったとか。
いつもいいますが、これはほんとに偶然楽しいというだけです。
(クラシックなので旋律拝借しても問題ないでしょうけど)。
このCDは明るくて軽くて(いい意味で)、聴くタイミングを選ばない。
真面目に聴くのもいいし、30分くらい時間が空いた時に途中まで
聴くのもいい、そして軽めの本を読む時にもいい。
途中までと書きましたが全部で 曲あるので、
まったくの途中ではなく何番まで、という聴き方ができますし。
アラン・シヴィルさんの他のCDも探してみないと。
モーツァルト以外のホルンを使った曲も聴いてみたい。
まあ交響曲でもホルンが目立つ曲はあるけれど、それ以上に。
在籍していたオーケストラのその時代の録音のCDを買えば、
まあ、必然的にいるということになるのでしょうけど。
そうそう、大事なことを忘れてた、For No Oneに関して、
アラン・シヴィルさんはこんなこと言っていました。
『あなたがやったモーツァルトのホルン協奏曲はよかった』
なんて私に言う人はめったにいないが、
『あそこにいる白髪のおじさんね、
彼はビートルズと共演したんだよ!』
と言う人はたくさんいる。
とんでもない!
貴方の「モーツァルト:ホルン協奏曲」は
素晴らしいですよ!!
☆8枚(点)目
J.S.Bach
BRANDENBURG CONCERTOS 1-6
Benjamin Britten(Condt)
English Chamber Orchestra
(1968)
バッハ:ブランデンブルク協奏曲
ベンジャミン・ブリテン指揮
イギリス室内管弦楽団
ビートルズ関係をもう1枚。
遡って、昨秋上げた213曲のPenny Laneの記事で
トランペットを吹いていたと紹介したデヴィッド・メイスン。
元トラフィックの人とは同姓同名の別人。
ポールは、BBCテレビで放送されていたイギリス室内管弦楽団の
バッハ:ブランデンブルク協奏曲を観て聴いて
あのトランペットを入れたいと思いつき、会社の人が
連絡を取ってメイスンさんを呼んで録音したという話。
探すとこれが、あったんですよ、まさにそれ。
ただし録音が1968年だからPenny Laneより後ですが、
イギリス室内管弦楽団の演奏であるところまで一緒。
しかも中古で安く状態が優れたものが手に入りました。
聴いてすぐに、これは音がいい、と先ず思いました。
サウンドという意味以上に物理的な音の響きがいい。
楽器の音がクリアで、全体に透明感があってすがすがしい響き。
教会で録音されているということでもちろん屋内ですが、
そのまま宇宙につながりそうな壮大な音に感心しました。
演奏も、僕はこの曲、モダン楽器の演奏によるものとしては、
イタリアのイ・ムジチのCDを聴いたことがありますが、
イ・ムジチがきらびやかなのに対してこちらは清明。
それぞれの良さがあるでしょうけど僕はこちらがより好きです。
僕はかなり気に入ったのですが、ブランデンブルク協奏曲の
名演名盤をネットでいろいろ調べてみたところ、僕が見た限り、
これを挙げている人はひとりしかいらっしゃらなかった。
そのひとりも順番としては何枚目、というくらい。
バッハは今は古楽器演奏が主流ともいえる状況に
なっているようで、1960年代のモダン楽器演奏なんて、
前時代的なものという感覚があるのかもしれないですね。
残念といえばそうですが、仕方ない。
指揮ベンジャミン・ブリテンは現代音楽作曲家としてより有名で、
「戦争レクイエム」が代表作とのことですが、その曲は
名前と存在は知っているけれど聴いたことはありません。
名盤としての人気がないのは指揮者にも関係があるのかな。
僕は、今後古楽器含め他の演奏を聴くことがあっても、
これが決定打となりそうな気がしています。
ビートルズ絡み、ええ、音楽は気持ちで聴くものですからね(笑)。
なお、デヴィッド・メイスンさんは2011年に亡くなられていたそうで、
Penny Laneの記事ではそのことには触れていませんでした。
ここにご冥福をお祈りし、件の記事に書き足しておきます。
02

今回はクラシックでも横につなげて聴くことができる、
ということを実証してみました、というのは大袈裟か(笑)。
ネット時代になり、その辺の情報を素人でも集められるようになり、
音楽を聴く幅も広がってきたということでしょうね。
最後は今朝の3ショット。
特に変わったところはない普通の1枚にて失礼します。
あ、でもそうだ、家の周りの雪を集めて捨てている
うちの庭にはまだ1m以上の雪の山があります。
03


最近買ったCDさらりと紹介記事です。
今回からタイトルの「新譜旧譜合わせて」という言葉をやめ、
記事では新譜のみ「新譜」と明記してゆきます。
今回は8枚(点)、では早速。
☆1枚目
DIG IN DEEP
Bonnie Raitt
(2016)
ボニー・レイットの新譜、詳しくは
一昨日上げたこちらの記事をご覧ください。
書いているうちに長くなり、独立した記事にしたのでした。
☆2枚目
CARRYING A TORCH
Tom Jones
(1991)
トム・ジョーンズのこれはぽちわかやさんの紹介で買いました。
あらためてありがとうございます。
あのヴァン・モリソンがトム・ジョーンズをプロデュースしていた
なんて、まったく知らなかった、ある意味衝撃でした。
最初はミスマッチ感覚のように思えたけれど、聴いてみて納得。
ヴァン・モリソンも静かで穏やかなようで熱い人ですからね。
ヴァンさんの曲や音楽が持つエネルギーを、
トムさんがうまく引き出している、といえばいいかな。
ヴァンさんが書いた曲は1、2、4、12と4曲だけですが、
他の人が書いた曲も不思議とヴァン・モリソン風に
聴こえてきてしまうこの不思議。
特に3曲目Strange Boatはブックレットを見るまで、
ヴァン・モリソンの曲と信じて疑わなかったのですが
プロデューサーの色がここまで出るというのはある意味驚き。
それだけヴァンさんの個性が強烈なのでしょうね。
そしてその強烈さに対抗できる個性の持ち主はそうはいない。
トム・ジョーンズがその人だった。
聴き込んで考えるだに、これは最高の組み合わせだと
唸らされるようになってきました。
ちなみに作曲者として著名な人は他に、
ダイアン・ウォーレンとアルバート・ハモンド、
そしてポール・キャラックと、トム・ジョーンズもこの頃は
「メキメキ」で復活する直前のスランプ時期であり、
「本物の音楽」として聴かせることに傾注していたことが、
作曲者と曲の質を見ても分かります。
当時あまり売れなかったようで、僕も実は
まったく当時の記憶がないのですが、この後開き直って
「メキメキ」が売れて第一線に復活したといったところでしょうね。
売れなかったのはやはり僕のように「一瞬ミスマッチ感覚」に
襲われた人が多かったのでしょうね。
僕も当時からヴァン・モリソンを聴いていれば買ったかも、
と後で幾らでも思うことができるのですが(笑)、でもひとまず、
このアルバムを作ってくれたことに感謝ですね。
ほんと、ヴァンさんよく引き受けてくれたよなあ。
ヴァン・モリソン「外伝」として聴ける、なんとも嬉しいことか。
ちなみに、昨年春に出たヴァン・モリソンの本を見ると、
なんとというか、当たり前というか、これも紹介されていて
要するに読んでいなかったのでした・・・
☆3枚目、4枚目
GIVE ME THE NIGHT
(1980)
20/20
(1984)
George Benson
ジョージ・ベンソン2枚買いました。
順序は逆ですが、20/20は先頃記事を上げた
Nothing's Gonna Change My Love For You
を聴きたかったからで、もちろんその曲は気に入った。
ただ、アルバム全体としては、良くも悪くも80年代サウンドで、
リアルタイムだった僕には、懐かしくもちょっとくすぐったい音。
僕はジョージ・ベンソンそれまで2枚しか聴いていなかったですが、
この音は予想外でした。
ただ、音に慣れると曲は素晴らしくて聴きやすいアルバム。
最後のYou Are The Love Of My Lifeは、
ロバータ・フラックとのデュエットが素晴らしく
「至宝」ともいえるラヴバラード。
つまりこのアルバムには必殺ラヴバラードが2曲もある。
サウンドのマイナス面を補ってあまりある、ということですね。
一方その4作前のGIVE ME THE NIGHTは素晴らしい。
こんなに素晴らしいとは予想していなかった、申し訳ないけれど。
クインシー・ジョーンズと組んだことが売りともいえますが、
なるほど、クインシーが作るサウンドはきらびやかな響きで、
エッジが鋭く、都会的で洒落たサウンドが、
ジョージ・ベンソンのスター性をうまく引き出しているのでしょう。
同じクインシーで同じ頃のマイケル・ジャクソン
OFF THE WALLを思い出させてくれるサウンドでもあり、
ここがまた嬉しいところで、特に1曲目Love X Loveは曲の雰囲気が
マイケルのRock With Youに似ていて思わずにんまり。
そういえばOFF THE WALLのリイシュー盤出たばかりですね。
実は買った時に、リリース順でこっちを先に聴いていたので、
余計に20/20のサウンドにあれっと思ったのでした。
そして2枚聴いてあらためて思った。
ジョージ・ベンソン、歌がうまい。
うまいというより、表現力の引き出しが多いというか。
Nothing's...のようなラヴソングも、Give Me The Nightのような
ホップしたのりの曲も、Masquaradeのようなディープな歌い方も、
そしてGIVE...のラストTurn Out The Lamplightのような大人しい
曲をしみじみと、どれも自分のものとしてしっかりと歌っている。
僕が特に驚いたのはGive...の軽やかさで、軽いのに
しっかりと伝わってくる、すごいと思いました。
そして...Lamplightは隠れた名曲、とも。
ジョージ・ベンソン、はまったかな(笑)。
ひとまず廉価盤で出ているこの間の3枚を
次から買って聴いてみます。
☆5枚目
COOL STRUTTIN'
Sonny Clark
(1958)
ソニー・クラークのこれはジャズの最も有名なアルバムジャケットの
ひとつであり、日本のジャズ喫茶でいちばんリクエストが多かった
アルバムと言われているそうですね。
今更ながら買って聴きましたが、やはりというか、いいですね。
曲の旋律の掴みが強力で、ポップともいえるほどで、
人気があるのも分かりました。
と書きましたが、実は買って最初に聴いた時は
「インプロビゼーションが長い」という印象しか残らなくて、
どうしてこれが人気があったのだろうとすら思いました。
でも、2回目に聴いた後1週間ほど聴かなくて、せっかく
買ったのだからもったいないと、ただそれだけ思って
3回目をかけたときに、聴こえ方が一変し、ポップに感じました。
特に2曲目Blue Minor、ほのかにラテンの香りがする旋律が好き。
どうやら、最初は曲がポップだとは感じなかったようで、
やっぱり曲覚えが悪い弊害が・・・(笑)。
ただ、そこまで到達した上であらためて、このアルバムというか
この人の音楽には、ポップでつかみやすい部分と
インプロビゼーションの部分の二面性があるのでは、
という感じもしてきました。
いや、この人だけではない、時代だったのかもしれないですが、
ポップな方向から外れてしまったことを故中村とうよう氏が
嘆くように書いていたことを思い出しました。
僕は演奏もできないし、技術的な面は何も言えないのですが、
あくまでも感覚として、これはポップな部分が気に入りました。
そして僕はこれをなぜか朝起きて最初に聴くことが多い。
ジャズは夜というイメージがあるかもしれないですが、
朝に聴くのも結構いいですよ(笑)。
実は、ジャズのCDを買うのは半年振り、CDを聴くのですら
2カ月振りくらいだったのですが、ジョージ・ベンソンが
流れを呼んでくれたのでしょうね(笑)。
ところでこれ、中古でかなり出回っているようですね。
ジャケット買いして失敗したという人が多いのかな・・・(笑)。
☆6枚目
Maurice Rave
L'ENFANT ET LES SORTILEGES SHEHERAZADE
Seiji Ozawa(Condt) / Saito Kinen Orchestra
Isabel Leonard, Susan Graham
(2015)
小澤征爾指揮 ラヴェル:歌劇『子どもと魔法』
サイトウ・キネン・オーケストラ
レナード、グレアム
小澤征爾が初めてグラミー賞を受賞したと
日本でも話題になりましたが、そのCDを買いました。
受賞したのは「最優秀オペラ録音賞」で、小澤さんというより
むしろ裏方さんに与えられた賞でありますが、でも指揮したのは
間違いのない事実、小澤さんが受賞したと言っても
問題ないでしょうし、僕自身も受賞は嬉しかったです。
小澤さんはこれを機に、あまり知られていないオペラを
より多くの人に知って聴いてもらいたいということを
ニュースで語っていましたが、ほんとにそうですね。
僕はオペラに詳しいわけではないけれど、この作品は
知らなかったから、小澤さんの願い通りになっていますね。
ただですね、申し訳ないというか、今の僕はオペラを聴く
心の流れにはないようで、作品としてどうという感慨を、
今回は持つことができませんでした。
でもオペラもまあ好きだし、いずれ心の流れが来るでしょう。
買ってよかったとは当然思っています、念のため。
☆7枚目
Mozart
THE FOUR HORN CONCERTOS
Alan Civil(Horn)
Rudolf Kempe(Condt)
Royal Philharmonic Orchestra
(1966)
モーツァルト:ホルン協奏曲全集
アラン・シヴィル(ホルン)
ルドルフ・ケンペ指揮
ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団
先日のビートルズFor No Oneの記事において、間奏の
ホルンのソロを演奏している当時フィルハーモニア管弦楽団の
主席ホルン奏者だったアラン・シヴィルの話を紹介しました。
それでシヴィルさんのクラシックのCDも聴いてみたくなり、
調べると、このCDが最近廉価盤で出ていたことを知り即注文。
奇しくもFor No Oneと同じ1966年に録音されたもので、
指揮ルドルフ・ケンペ、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団演奏。
曲自体の感想。
ホルンの音色が天衣無縫なモーツァルトの音楽に合っている。
まあ、実際はどういう人か分からないですが・・・『アマデウス』・・・
先ず僕が思ったのはそれでした。
「音楽は天使の言葉を通訳できる人間が人間に分かる
ことばに翻訳したもの」、とも言われますが、ホルンの音色は
天使の声にいちばん近いのではないかと。
天使のお喋りを聴いているようにも感じます。
もちろん聴いたことはないですが・・・(笑)。
もしくは、子象が遊んでいるような雰囲気で、特にTr5、
第3番第3楽章はほんとにそんな感じがしますよ。
まあ、子象が遊ぶ姿も映像でしか観たことはないですが・・・(笑)。
演奏では、ホルンの音が一瞬だけ外れているように聴こえるのは、
ギターでいうチョーキング=ベンディングのような効果があって、
いい意味での揺らぎが出ていると感じました。
ホルンは演奏したことがないので僕には分からないですが、
これはホルンの構造上のことなのか、それともテクニックなのか、
とにかく音としてはそこがなんだか妙に気に入りました。
ルドルフ・ケンペは今でも人気が高い指揮者ですが、
僕は彼の指揮する演奏は初めて聴きました。
しかしこれは協奏曲で主役はあくまでもホルン奏者だから、
ケンペの演奏がどうということは特に感じなかった(すいません)。
60年代の録音としては音は優れていると感じました。
面白いのが、第1番1楽章つまりCDの最初のトラック、
これが「北の国から」のあの曲に旋律がよく似ている。
♪あ~あ~あああああ~ああ というやつですね。
最初の4小節は旋律がほんとによく似ていて、その次の小節への
移行も同じで、移ってからの2拍目までの旋律も似ている。
偶然なのでしょうけど、でもさだまさしがその曲を好きだったとか。
いつもいいますが、これはほんとに偶然楽しいというだけです。
(クラシックなので旋律拝借しても問題ないでしょうけど)。
このCDは明るくて軽くて(いい意味で)、聴くタイミングを選ばない。
真面目に聴くのもいいし、30分くらい時間が空いた時に途中まで
聴くのもいい、そして軽めの本を読む時にもいい。
途中までと書きましたが全部で 曲あるので、
まったくの途中ではなく何番まで、という聴き方ができますし。
アラン・シヴィルさんの他のCDも探してみないと。
モーツァルト以外のホルンを使った曲も聴いてみたい。
まあ交響曲でもホルンが目立つ曲はあるけれど、それ以上に。
在籍していたオーケストラのその時代の録音のCDを買えば、
まあ、必然的にいるということになるのでしょうけど。
そうそう、大事なことを忘れてた、For No Oneに関して、
アラン・シヴィルさんはこんなこと言っていました。
『あなたがやったモーツァルトのホルン協奏曲はよかった』
なんて私に言う人はめったにいないが、
『あそこにいる白髪のおじさんね、
彼はビートルズと共演したんだよ!』
と言う人はたくさんいる。
とんでもない!
貴方の「モーツァルト:ホルン協奏曲」は
素晴らしいですよ!!
☆8枚(点)目
J.S.Bach
BRANDENBURG CONCERTOS 1-6
Benjamin Britten(Condt)
English Chamber Orchestra
(1968)
バッハ:ブランデンブルク協奏曲
ベンジャミン・ブリテン指揮
イギリス室内管弦楽団
ビートルズ関係をもう1枚。
遡って、昨秋上げた213曲のPenny Laneの記事で
トランペットを吹いていたと紹介したデヴィッド・メイスン。
元トラフィックの人とは同姓同名の別人。
ポールは、BBCテレビで放送されていたイギリス室内管弦楽団の
バッハ:ブランデンブルク協奏曲を観て聴いて
あのトランペットを入れたいと思いつき、会社の人が
連絡を取ってメイスンさんを呼んで録音したという話。
探すとこれが、あったんですよ、まさにそれ。
ただし録音が1968年だからPenny Laneより後ですが、
イギリス室内管弦楽団の演奏であるところまで一緒。
しかも中古で安く状態が優れたものが手に入りました。
聴いてすぐに、これは音がいい、と先ず思いました。
サウンドという意味以上に物理的な音の響きがいい。
楽器の音がクリアで、全体に透明感があってすがすがしい響き。
教会で録音されているということでもちろん屋内ですが、
そのまま宇宙につながりそうな壮大な音に感心しました。
演奏も、僕はこの曲、モダン楽器の演奏によるものとしては、
イタリアのイ・ムジチのCDを聴いたことがありますが、
イ・ムジチがきらびやかなのに対してこちらは清明。
それぞれの良さがあるでしょうけど僕はこちらがより好きです。
僕はかなり気に入ったのですが、ブランデンブルク協奏曲の
名演名盤をネットでいろいろ調べてみたところ、僕が見た限り、
これを挙げている人はひとりしかいらっしゃらなかった。
そのひとりも順番としては何枚目、というくらい。
バッハは今は古楽器演奏が主流ともいえる状況に
なっているようで、1960年代のモダン楽器演奏なんて、
前時代的なものという感覚があるのかもしれないですね。
残念といえばそうですが、仕方ない。
指揮ベンジャミン・ブリテンは現代音楽作曲家としてより有名で、
「戦争レクイエム」が代表作とのことですが、その曲は
名前と存在は知っているけれど聴いたことはありません。
名盤としての人気がないのは指揮者にも関係があるのかな。
僕は、今後古楽器含め他の演奏を聴くことがあっても、
これが決定打となりそうな気がしています。
ビートルズ絡み、ええ、音楽は気持ちで聴くものですからね(笑)。
なお、デヴィッド・メイスンさんは2011年に亡くなられていたそうで、
Penny Laneの記事ではそのことには触れていませんでした。
ここにご冥福をお祈りし、件の記事に書き足しておきます。
02

今回はクラシックでも横につなげて聴くことができる、
ということを実証してみました、というのは大袈裟か(笑)。
ネット時代になり、その辺の情報を素人でも集められるようになり、
音楽を聴く幅も広がってきたということでしょうね。
最後は今朝の3ショット。
特に変わったところはない普通の1枚にて失礼します。
あ、でもそうだ、家の周りの雪を集めて捨てている
うちの庭にはまだ1m以上の雪の山があります。
03

2016年02月21日
最近買ったCDを新譜旧譜合わせてさらりと2016年2月
01

最近買ったCDさらりと紹介記事。
今月は9点(組)です。
☆1点目
25
Adel
(2015)
アデルの新譜は記事にしたので、詳しくはこちらをお読みください。
ほんとうにいい、もはや僕の中ではスタンダード級。
先日のグラミー授賞式ではAll I Askを歌っていたようです。
☆2点目
DARK SKY ISLAND
Enya
(2015)
エンヤの新譜、タイトルの通り今回は重たくて暗い沈んだ曲が多い。
エンヤの音楽は以前も書いたように、はじめから完成した壮大な
絵のような世界があり、そこから1作ごとに違う部分を切り取ってきて
音楽として聴かせてくれる、というものに僕には感じられる。
今回は少し裏の部分を切り取って来たのかな。
そのおかげで、今作は今までよりもうんと人間臭く感じられます。
もちろん今までが人間味がなかったというわけではないけれど、
人間が見ていた妖精物語(人間との共通性)を描いているのではなく、
妖精物語を見ている人間の気持ちの揺れを描いている、というかな。
今作は、最初に聴いて「おおっ!?」という手ごたえがありました。
もちろん明るい歌もあるし、エンヤらしい音楽には違いない。
エンヤ自体の「妖精」から「人間」へのメタモルフォーゼかもしれない。
ところでエンヤは昨年12月に、USJのステージにサプライズ出演して
Orinoco Flowとこの中のEchoes In Rainを歌ったニュースを見ました。
なんでも彼女はUSJのクリスマスツリーがきれいでどうしても見たい
と自ら望んで来日したそうですが、なんというか、お嬢様ですよね。
でも僕はそのニュースを見てすごくほっとするものを感じました。
そのEchoes In Rainは、"Alleluia"と繰り返し歌うサビが、
どこかしらユーモラスかつなんとなく寂しさが漂う独特の響きで、
最初に聴いた時から強く印象に残った曲でした。
ここでその曲を。
Echoes In Rain
Enya
☆3点目
PERFECTAMUNDO
Billy Gibbons and The BFG's
(2015)
ビリー・ギボンズ初のソロアルバム(名義はプロジェクト)。
眼鏡を外した写真はZZトップではなくソロだからかな。
当然のことながらハードでヘヴィでブルージーな
ZZトップ的な音を予想し期待したところ、肩すかしを食らいました。
音の隙間が多く、押してくるというよりはゆらゆら漂う感じ。
そして根底に流れるラテン風味、リズムの違いも大きい。
3曲目にはラップまで登場。
これほどまでに予想と違うアルバムは久しぶり。
キース・リチャーズのソロが予想外にローリング・ストーンズ的
だったのと正反対ということになりますかね。
最初は面食らいましたが、でも音楽としてのクオリティは
当然のことながら高く、聴いていて心地よくなってきました。
メロディのセンスは逆にこうすることでより浮き立っていて、
この人が売れたのはやはりそうだったかと納得。
考えてみれば、ハードでヘヴィなブルーズに大胆にも電子楽器を
採り入れて大ヒットしたELIMINATORがあるわけだから、
新しいこと、変わったことを常に心掛けていた人なのでしょう。
カヴァー曲が多い中、ヴァン・モリソンでも有名な
Baby Please Don't Goの崩し方が洒落ていて面白い。
懇願するのは疲れるけどひとまず言うだけ言っとくか、
みたいなノリで流れていくのは聴いていて楽しい。
歌詞がスペイン語(多分)の曲もあり、そもそもタイトルも
スペイン語風ですが、一貫したラテン趣味はむしろ気持ちいい。
ZZらしい音を求める人には「問題作」かもしれないけれど、
純粋にロック音楽としてみるとこれは「快作」といっていいでしょう。
それにしても年輪の深い顔をしている。
いるんだけど、この目つき、まだまだ反骨精神は失っていない、
永遠の「老け顔の若者」といったところでしょう。
ではここで1曲
Treat Her Right
Billy Gibbons & The BFG's
☆4点目
Carmel
Joe Sample
(1979)
ジョー・サンプル、廉価盤があるうちにもう1枚買いました。
僕が感じたのは、「虹の彼方へ」が人間的ドラマ色が濃いのに対し、
「渚にて」はもっと情景描写側に大きく寄っているということでした。
気持ちの波は「虹」が大きい、一方こちらは流れにたゆたう感じ。
とまあこれはあくまでも僕の感じ方です、念のため。
今回も「懐かしい」音の響きに満ちていましたが、
時代の音に抗うのはもはや人間として無意味な抵抗ですね(笑)。
僕は好きです、いいなあと、ほのかに甘い香りもしてきます。
でも懐古趣味が嫌いな人は、単なる「時代の音」なのかもしれない。
もちろんそれを司るキーボードの音の滑らかさ、素晴らしい。
ところでこの原題はCarmel、カーメルって確か、
クリント・イーストウッドがかつて市長をしていた市ですよね。
イーストウッドはジャズマニアだけど、このアルバムも聴いたのかな。
ではその曲を、ジャケット写真の静止画ですが。
Carmel
Joe Sample
☆5点目
DIRTY HOUSE BLUES
Lightnin' Hopkins
ライトニン・ホプキンスの初期の音源を集めた2枚組CD。
録音された年は1948年から1954年の間。
ブルーズが分からないなりに少しずつ聴いている僕ですが、
ライトニン・ホプキンスは今回初めて聴いてみました。
最初に思ったのは、歌い方があっさりしているというか、
まっすぐというか、情に流されない、むしろ論理的と感じさせるもので、
メッセージソングを歌うにはいいのではないか、ということ。
デルタブルーズの人なのかなと想像していたのですが、多分違う、
そういう感じではない、やはりフォークブルーズなのかな。
一応Wikipdiaを見ると、"electric blues""country blues"
"Texas blues"となっていましたが、意外と土臭くなかったというか、
そこも上記のように感じた部分。
ドラムスやベースは入っているけれど基本ギター弾き語りといった
響きで、彼自身の「個の力」が強い人、とお見受けしました。
それにしても、ほんとうにブルーズは奥が深い。
僕なんてまだ「奥が深い」と言えるほどまでにも達していない。
分からないけれど好きで聴いているのは確かであり、
落ち着いたらまた他の聴いたことがない人を聴いてみたいです。
ところで、これを出しているNOT NOW MUSICは
サム・クックの音源も出していますが、この値段(千円くらい)で
この音質、ありがたいですね。
ですが、このCD、異様に音量が大きくて、他のCD、
特にクラシックに続けて聴くと驚くほど大きいのでした。
☆6点目
10 OVERTURES
Riccardo Chailly
/ Orchestra Filarmonica Della Scala
ロッシーニ序曲集
ロッシーニはオペラそのものもいいけれど、
序曲集はエッセンスが凝縮されていてより楽しく聴くことができます。
実際問題としても、序曲だから本編より短くて聴きやすいのですが。
「ウィリアム・テル」序曲はあまりにも有名な曲ですが、
「セビリアの理髪師」序曲もきっと耳にしたことがある人は多いはず。
そして僕はもちろん「どろぼうかささぎ」序曲がお気に入り(笑)。
イタリア人指揮者のリッカルド・シャイーは旋律を歌わせることに
長けている指揮者であり、オケはミラノ・スカラ座とくれば、
まさにこの演奏にはうってつけ。
気持ちをすっきりさせたい時にいいクラシックCDです。
☆7点目
BOULEZ CONDUCTS STRAVINSKY
1月に亡くなられた指揮者・作曲家ピエール・ブーレーズ。
彼が指揮をしDGに録音を残したストラヴィンスキーの曲を集めた
ボックスセットです。
ミグの父さんに教えていただき、すぐに買い求めました。
ありがとうございます。
ネットの評を読むと現在は廃盤になっている歌曲ものが
収録されているのが価値が高いとのことであり、
その他管弦楽曲などを集めた6枚組ですが、僕は、
一通り聴いた後、「火の鳥」「春の祭典」「ペトルーシュカ」
の入ったDisc1と2のみを繰り返し聴いています。
だから全体がどうというのは言えないのですが、でも
「ペトルーシュカ」と「春の祭典」が特に気に入り
ずっとCDプレイヤーに入っています。
ひとまずその3曲について、曲自体にも演奏にも迫力があって、
ブーレーズの演奏は言われる通り精緻な作りで揺らぎが少ない、
と感じましたが、まだまだ聴き込みが必要です(申し訳ない)。
☆8点目
BEETHOVEN : SYMPHONY NO.4 & NO.5
Nikolaus Harnoncout
/ Concertus Musicus Wien
(2016)
アーノンクール:ベートーヴェン交響曲第4番&第5番《運命》
このCDは最初ここで紹介するつもりでしたが、
書いているうちに十分記事ひとつ分の長さになったので、
後日またあらためて独立した記事にします。
ここでは摘要だけ書いておくと、御年86歳のアーノンクール、
昨年演奏活動からの引退を宣言。
最後の録音として2月に出たのがこのCDです。
☆9点目
WATER
Helene Grimaud
(2016)
グリモー様の新譜がついに出ました!
僕が「グリモー様」とここで言うようになって初めての新譜ですね。
ところが。
今回の「アルバム」は、水をテーマにとった古今東西作曲家の
短い曲の間をニティン・ソーニー作曲のパッセージでつなぐというもの。
取り上げられているのは順に、ベリオ、武満徹、フォーレ、ラヴェル、
アルベニス、リスト、ヤナーチェク、ドビュッシー。
日本人としては武満徹の作品があるのが嬉しいですね。
それぞれの曲はまさにみずみずしくて素晴らしい。
つなぎの曲を入れ「アルバム」として聴かせるアイディアもいい。
でも、そう言えるのは多分、僕がファンだから。
特に旧来のクラシックファンは、それぞれの曲を楽しみたいのでは。
グリモーはクラシックの枠を超えて「アルバム」として聴かせようと
考えている、と僕は以前何度か書きましたが、今回はそれが
より具体的な形となって表されたものといえるでしょう。
まさに体を流れる水の如く次から次へと曲が流れていく様は
BGM的に流しておくにはとてもいいCDだと思いますが、
それはもしかして「アルバム」としてはほめていないかもしれない。
評価というのは大袈裟だけど、何といっていいか難しいCDです、正直。
ただ、彼女がやりたかったことはこうだったんだと僕の中で
証明できたのは、ファンとしては嬉しくもあります。
もしかして気持ちが通じている・・・なんて、言いませんが(笑)。
ところで僕が買ったCDは10分ほどのボーナストラックが入っていて、
彼女が幾つかの曲について解説し弾いてみるというもの。
彼女の声は初めて聞きましたが(ネットで聞く機会あっただろうけど)、
最初は正直、喋りが出てきて戸惑いました。
クラシックでそれはいいのだろうか、と余計な心配も。
ただ、彼女の声は低く落ち着いていて、語りも悪くないので
(英語が微妙にフランス語訛りっぽいけど)、聴いているうちに
それはそれで気に入ってしまいました。
ジャケットの写真はまさに水のごとくみずみずしく、
若くてかわいらしい雰囲気に撮れていますね。
最後にこのアルバムのトレイラー(プロモ)映像です。
今年に入ってロック系の魅力的なリイシュー盤が
幾つか出ていますが、次回はそれを中心に紹介したいと思います。
来月には上げられるかな。
02


最近買ったCDさらりと紹介記事。
今月は9点(組)です。
☆1点目
25
Adel
(2015)
アデルの新譜は記事にしたので、詳しくはこちらをお読みください。
ほんとうにいい、もはや僕の中ではスタンダード級。
先日のグラミー授賞式ではAll I Askを歌っていたようです。
☆2点目
DARK SKY ISLAND
Enya
(2015)
エンヤの新譜、タイトルの通り今回は重たくて暗い沈んだ曲が多い。
エンヤの音楽は以前も書いたように、はじめから完成した壮大な
絵のような世界があり、そこから1作ごとに違う部分を切り取ってきて
音楽として聴かせてくれる、というものに僕には感じられる。
今回は少し裏の部分を切り取って来たのかな。
そのおかげで、今作は今までよりもうんと人間臭く感じられます。
もちろん今までが人間味がなかったというわけではないけれど、
人間が見ていた妖精物語(人間との共通性)を描いているのではなく、
妖精物語を見ている人間の気持ちの揺れを描いている、というかな。
今作は、最初に聴いて「おおっ!?」という手ごたえがありました。
もちろん明るい歌もあるし、エンヤらしい音楽には違いない。
エンヤ自体の「妖精」から「人間」へのメタモルフォーゼかもしれない。
ところでエンヤは昨年12月に、USJのステージにサプライズ出演して
Orinoco Flowとこの中のEchoes In Rainを歌ったニュースを見ました。
なんでも彼女はUSJのクリスマスツリーがきれいでどうしても見たい
と自ら望んで来日したそうですが、なんというか、お嬢様ですよね。
でも僕はそのニュースを見てすごくほっとするものを感じました。
そのEchoes In Rainは、"Alleluia"と繰り返し歌うサビが、
どこかしらユーモラスかつなんとなく寂しさが漂う独特の響きで、
最初に聴いた時から強く印象に残った曲でした。
ここでその曲を。
Echoes In Rain
Enya
☆3点目
PERFECTAMUNDO
Billy Gibbons and The BFG's
(2015)
ビリー・ギボンズ初のソロアルバム(名義はプロジェクト)。
眼鏡を外した写真はZZトップではなくソロだからかな。
当然のことながらハードでヘヴィでブルージーな
ZZトップ的な音を予想し期待したところ、肩すかしを食らいました。
音の隙間が多く、押してくるというよりはゆらゆら漂う感じ。
そして根底に流れるラテン風味、リズムの違いも大きい。
3曲目にはラップまで登場。
これほどまでに予想と違うアルバムは久しぶり。
キース・リチャーズのソロが予想外にローリング・ストーンズ的
だったのと正反対ということになりますかね。
最初は面食らいましたが、でも音楽としてのクオリティは
当然のことながら高く、聴いていて心地よくなってきました。
メロディのセンスは逆にこうすることでより浮き立っていて、
この人が売れたのはやはりそうだったかと納得。
考えてみれば、ハードでヘヴィなブルーズに大胆にも電子楽器を
採り入れて大ヒットしたELIMINATORがあるわけだから、
新しいこと、変わったことを常に心掛けていた人なのでしょう。
カヴァー曲が多い中、ヴァン・モリソンでも有名な
Baby Please Don't Goの崩し方が洒落ていて面白い。
懇願するのは疲れるけどひとまず言うだけ言っとくか、
みたいなノリで流れていくのは聴いていて楽しい。
歌詞がスペイン語(多分)の曲もあり、そもそもタイトルも
スペイン語風ですが、一貫したラテン趣味はむしろ気持ちいい。
ZZらしい音を求める人には「問題作」かもしれないけれど、
純粋にロック音楽としてみるとこれは「快作」といっていいでしょう。
それにしても年輪の深い顔をしている。
いるんだけど、この目つき、まだまだ反骨精神は失っていない、
永遠の「老け顔の若者」といったところでしょう。
ではここで1曲
Treat Her Right
Billy Gibbons & The BFG's
☆4点目
Carmel
Joe Sample
(1979)
ジョー・サンプル、廉価盤があるうちにもう1枚買いました。
僕が感じたのは、「虹の彼方へ」が人間的ドラマ色が濃いのに対し、
「渚にて」はもっと情景描写側に大きく寄っているということでした。
気持ちの波は「虹」が大きい、一方こちらは流れにたゆたう感じ。
とまあこれはあくまでも僕の感じ方です、念のため。
今回も「懐かしい」音の響きに満ちていましたが、
時代の音に抗うのはもはや人間として無意味な抵抗ですね(笑)。
僕は好きです、いいなあと、ほのかに甘い香りもしてきます。
でも懐古趣味が嫌いな人は、単なる「時代の音」なのかもしれない。
もちろんそれを司るキーボードの音の滑らかさ、素晴らしい。
ところでこの原題はCarmel、カーメルって確か、
クリント・イーストウッドがかつて市長をしていた市ですよね。
イーストウッドはジャズマニアだけど、このアルバムも聴いたのかな。
ではその曲を、ジャケット写真の静止画ですが。
Carmel
Joe Sample
☆5点目
DIRTY HOUSE BLUES
Lightnin' Hopkins
ライトニン・ホプキンスの初期の音源を集めた2枚組CD。
録音された年は1948年から1954年の間。
ブルーズが分からないなりに少しずつ聴いている僕ですが、
ライトニン・ホプキンスは今回初めて聴いてみました。
最初に思ったのは、歌い方があっさりしているというか、
まっすぐというか、情に流されない、むしろ論理的と感じさせるもので、
メッセージソングを歌うにはいいのではないか、ということ。
デルタブルーズの人なのかなと想像していたのですが、多分違う、
そういう感じではない、やはりフォークブルーズなのかな。
一応Wikipdiaを見ると、"electric blues""country blues"
"Texas blues"となっていましたが、意外と土臭くなかったというか、
そこも上記のように感じた部分。
ドラムスやベースは入っているけれど基本ギター弾き語りといった
響きで、彼自身の「個の力」が強い人、とお見受けしました。
それにしても、ほんとうにブルーズは奥が深い。
僕なんてまだ「奥が深い」と言えるほどまでにも達していない。
分からないけれど好きで聴いているのは確かであり、
落ち着いたらまた他の聴いたことがない人を聴いてみたいです。
ところで、これを出しているNOT NOW MUSICは
サム・クックの音源も出していますが、この値段(千円くらい)で
この音質、ありがたいですね。
ですが、このCD、異様に音量が大きくて、他のCD、
特にクラシックに続けて聴くと驚くほど大きいのでした。
☆6点目
10 OVERTURES
Riccardo Chailly
/ Orchestra Filarmonica Della Scala
ロッシーニ序曲集
ロッシーニはオペラそのものもいいけれど、
序曲集はエッセンスが凝縮されていてより楽しく聴くことができます。
実際問題としても、序曲だから本編より短くて聴きやすいのですが。
「ウィリアム・テル」序曲はあまりにも有名な曲ですが、
「セビリアの理髪師」序曲もきっと耳にしたことがある人は多いはず。
そして僕はもちろん「どろぼうかささぎ」序曲がお気に入り(笑)。
イタリア人指揮者のリッカルド・シャイーは旋律を歌わせることに
長けている指揮者であり、オケはミラノ・スカラ座とくれば、
まさにこの演奏にはうってつけ。
気持ちをすっきりさせたい時にいいクラシックCDです。
☆7点目
BOULEZ CONDUCTS STRAVINSKY
1月に亡くなられた指揮者・作曲家ピエール・ブーレーズ。
彼が指揮をしDGに録音を残したストラヴィンスキーの曲を集めた
ボックスセットです。
ミグの父さんに教えていただき、すぐに買い求めました。
ありがとうございます。
ネットの評を読むと現在は廃盤になっている歌曲ものが
収録されているのが価値が高いとのことであり、
その他管弦楽曲などを集めた6枚組ですが、僕は、
一通り聴いた後、「火の鳥」「春の祭典」「ペトルーシュカ」
の入ったDisc1と2のみを繰り返し聴いています。
だから全体がどうというのは言えないのですが、でも
「ペトルーシュカ」と「春の祭典」が特に気に入り
ずっとCDプレイヤーに入っています。
ひとまずその3曲について、曲自体にも演奏にも迫力があって、
ブーレーズの演奏は言われる通り精緻な作りで揺らぎが少ない、
と感じましたが、まだまだ聴き込みが必要です(申し訳ない)。
☆8点目
BEETHOVEN : SYMPHONY NO.4 & NO.5
Nikolaus Harnoncout
/ Concertus Musicus Wien
(2016)
アーノンクール:ベートーヴェン交響曲第4番&第5番《運命》
このCDは最初ここで紹介するつもりでしたが、
書いているうちに十分記事ひとつ分の長さになったので、
後日またあらためて独立した記事にします。
ここでは摘要だけ書いておくと、御年86歳のアーノンクール、
昨年演奏活動からの引退を宣言。
最後の録音として2月に出たのがこのCDです。
☆9点目
WATER
Helene Grimaud
(2016)
グリモー様の新譜がついに出ました!
僕が「グリモー様」とここで言うようになって初めての新譜ですね。
ところが。
今回の「アルバム」は、水をテーマにとった古今東西作曲家の
短い曲の間をニティン・ソーニー作曲のパッセージでつなぐというもの。
取り上げられているのは順に、ベリオ、武満徹、フォーレ、ラヴェル、
アルベニス、リスト、ヤナーチェク、ドビュッシー。
日本人としては武満徹の作品があるのが嬉しいですね。
それぞれの曲はまさにみずみずしくて素晴らしい。
つなぎの曲を入れ「アルバム」として聴かせるアイディアもいい。
でも、そう言えるのは多分、僕がファンだから。
特に旧来のクラシックファンは、それぞれの曲を楽しみたいのでは。
グリモーはクラシックの枠を超えて「アルバム」として聴かせようと
考えている、と僕は以前何度か書きましたが、今回はそれが
より具体的な形となって表されたものといえるでしょう。
まさに体を流れる水の如く次から次へと曲が流れていく様は
BGM的に流しておくにはとてもいいCDだと思いますが、
それはもしかして「アルバム」としてはほめていないかもしれない。
評価というのは大袈裟だけど、何といっていいか難しいCDです、正直。
ただ、彼女がやりたかったことはこうだったんだと僕の中で
証明できたのは、ファンとしては嬉しくもあります。
もしかして気持ちが通じている・・・なんて、言いませんが(笑)。
ところで僕が買ったCDは10分ほどのボーナストラックが入っていて、
彼女が幾つかの曲について解説し弾いてみるというもの。
彼女の声は初めて聞きましたが(ネットで聞く機会あっただろうけど)、
最初は正直、喋りが出てきて戸惑いました。
クラシックでそれはいいのだろうか、と余計な心配も。
ただ、彼女の声は低く落ち着いていて、語りも悪くないので
(英語が微妙にフランス語訛りっぽいけど)、聴いているうちに
それはそれで気に入ってしまいました。
ジャケットの写真はまさに水のごとくみずみずしく、
若くてかわいらしい雰囲気に撮れていますね。
最後にこのアルバムのトレイラー(プロモ)映像です。
今年に入ってロック系の魅力的なリイシュー盤が
幾つか出ていますが、次回はそれを中心に紹介したいと思います。
来月には上げられるかな。
02

2015年12月31日
2015年のCD新譜Top10+
01

毎年大晦日恒例、良かったCDの記事です。
昨年まではポピュラー音楽の新録音による新譜のみを
ここで取り上げてきましたが、今年から変えました。
ポピュラー音楽の新録音の新譜はTop10として紹介し、
後半では旧譜でもリイシュー盤でも、ジャズもクラシックも含め、
初めて聴いた音源はすべて対象にします。
★新譜Top10
☆1位
CROSSEYED HEART
Keith Richards
栄えある2015年新譜の第1位はキース・リチャーズ!!
予想していたよりもうんとローリング・ストーンズっぽいのが嬉しい。
昨年のストーンズのコンサートでキースはいかにもおじいさん
という感じで、アルバムももっと枯れていると予想していたので、
この颯爽とした姿にはいい意味で驚かされました。
しかも、事前に何も知らずに聴き進めると、11曲目Illusionで
なんとノラ・ジョーンズの声が!
思わず「ノラだ!」と言いそうになってしまいました!
キースなかなかやるじゃん(笑)。
僕の選ぶベストチューンは、でも、もろストーンズのTroubleで。
☆3位
DUETS : RE-WORKING THE CATALOGUE
Van Morrison
ヴァン・モリソンの新譜が出たからには入れないわけにはゆかない。
自分の曲を1曲ずつゲストを招いてデュエットした企画盤ですが、
もはやスタンダードといえる曲にヴァンさんの存在感の重さを感じます。
ゲストもスティーヴ・ウィンウッド、マーク・ノップラー、ジョージ・ベンソン、
メイヴィス・ステイプルズ、タジ・マハール、マイケル・ブーブレから
ジョス・ストーンと幅広いジャンルや年代の人が集まっていますが、
なんといってもSome Peace Of Mind、ボビー・ウーマック最後の声。
涙を誘い、感謝の念が湧いてきます。
ベストチューンもその曲、意味が大きいですね。
☆4位
CASS COUNTY
Don Henley
ドン・ヘンリーの新譜は、郷愁を帯びたカントリー路線。
ただ、カントリーチャートで1位を記録したからカントリーなのだろうけど、
本人はカントリーだどうだとは特に意識せずに聴いていた、
小さい頃の音楽をやってみたかったということでしょう。
それが基礎となり、アメリカの「国民ロック」であるイーグルスになった。
この郷愁、音の響き以上にドンの気持ちが色濃く反映されています。
ところでこの邦題、「カス」だったのか、「キャス」ではないのか・・・
なんだか「カス」と書かれると妙に間抜けな・・・
ベストチューンは郷愁マックスのTake A Picture Of This。
☆5位
TENDERNESS
JD Souther
JDサウザーの新譜は、セルフカヴァー集NATURAL HISTORY
以来4年振り、しかし寡作の彼にしては早いリリースでした。
普通のロックに慣れているとこの音はジャズっぽいと感じるのですが、
JDにはその辺がニュートラルな感覚なのだろうなという自然さがある音。
声の若々しさは相変わらず、そのせいかこちらはドン・ヘンリーとは逆で、
懐かしいというよりは、今でも青春を謳歌している感じがしますね。
60歳になった今でも、夜の酒場で、照れ笑いを浮かべながら
口説き文句を言っているのかな、なんて姿を想像します。
僕はJDよりはるかに年下だけど、このアルバムより老けている。
そう感じてしまうところが自分としては寂しいのですが(笑)。
でも逆にいえば、僕の中に眠っているそういう心が
触発される(た)のかもしれない。
ベストチューンはDance Real Slow、表題曲がない代わりに、
この曲で"Tenderly"と歌うのが印象的、真に優しい音楽です。
☆6位
THE BOOK OF SOULS
Iron Maiden
ブルース・ディッキンソンが咽頭癌との闘病生活。
心配しましたが、活動再開できるほどに回復。
晴れてリリースされたアイアン・メイデンの新譜は2枚組超大作。
宇宙に飛んだ前作とは違いそれこそ地に足がついた音作り。
1970年代ハードロックぽさが色濃いのは意外でした。
作品としては文句なく大好きで弟の評価も高いのですが、
やはり2枚組というのは聴くのに心的抵抗がある。
構えて聴かなければならないし、日々物理的に時間が足りない。
僕が、途中でやめたりピックアップして聴ける性格だったら
よかったかもしれないですが・・・(笑)。
ベストチューンは、これほどまでに70年代っぽいとはと驚かされた
1曲目のIf Eternyty Should Fail。
☆7位
SHADOWS IN THE NIGHT
Bob Dylan
ボブ・ディランの新作はなんと、彼のアイドルだったという
フランク・シナトラを中心としたスタンダード集。
音楽の「ミスマッチ感覚」がこれほどまでにスリリングなものとは。
しかも、そんなものを落ち着いてじっくりと聴かされてしまうとは、
ディランはほんとうに歌うことが好きなんだなと再確認したしだい。
来年また来日公演がありますが、この中の曲は歌うのかな?
行きたいけど、ううん、4月は無理だな・・・
ベストチューンはLucky Old Sun、もったりとした中に
光明が差し込んでくるような味わいのある歌唱です。
☆8位
BORN TO PLAY GUITAR
Buddy Guy
バディ・ガイには、おおこれぞ「ドブルーズ」という音を聴かせてもらえた。
前作ではロックっぽい音に寄り過ぎた、それはそれで悪くはない。
ブルーズを好んで聴くようになってほんとによかったと実感。
しかし驚いたのが、ヴァン・モリソンの参加。
その曲だけどう聴いてもヴァン・モリソンの世界。
冷静にいえば浮いているんだけど、ヴァン・モリソンだから
その浮き具合が嬉しいことこの上ない。
でもやっぱり「ドブルーズ」を求める人にはただ浮いているだけかな。
ベストチューンはもちろんその
Flesh & Bone (Dedicated to B.B.King)。
今年亡くなられたB.B.キングに捧げられたものでもあります。
☆9位
A FOOL TO CARE
Boz Scaggs
ボズ・スキャッグスのR&Bフリークぶりを堪能できる1枚。
ボズ、今年は札幌に来てくれました、感謝。
コンサートでもこの中の曲を演奏しましたが、終演後のロビーには、
この新作を買い求める人の列が出来ていたのは、
新譜が出ていたことを知らなかった人が多かったのでしょう。
僕が行ったコンサートでCDを買うのにこれだけ行列ができたのを
見たのは初めてでした。
ベストチューンは国内盤ボーナストラックで申し訳ないですが、
インプレッションズのGypsy Woman。
でも、コンサートではアンコールのLast Tango On 16th Street
が印象的でした。
☆10位
UPTOWN SPECIAL
Mark Ronson
80年代洋楽で育った人間には音の響きが懐かしい。
もちろん安っぽいキーボードはもっとしっかりした音になっていて、
物理的な音の響きは同じではないけれど、サウンドプロダクションが。
冒頭いきなりスティヴィー・ワンダーのハーモニカが入った曲で
始まりますが、80年代にはハーモニカで客演することが多かったことも
思い出され、うまい仕掛けです。
気合を入れて聴くものではなく、かけておくと気持ちがいい音楽。
懐かしいという感慨はやはり人の心を動かすものなのだ。
「パクリ」とか「二番煎じ」などと言う人もいるかもしれないが、
僕はそこまで冷淡にはなれない、音楽を愛しているから。
それに「懐かしさ」という感慨は齢を追うごとに大切なものになってきている。
過去にしがみついているのではない。
過去の良い思い出があるから人間は生きてゆけるのだから。
その極め付けがUptown Funkであり、2015年に出会った新曲で、
同率1位でこの曲が好き、当然このアルバムのベストチューンもそれ。
次点として3枚を短く
・BLACK MESSIAH ディアンジェロ
プリンスっぽいのは意外でした、癖になる1枚
・TRACKER マーク・ノップラー
「現代のトラッド」路線はますます充実してきました。
・4 NIGHTS OF 40 YEARS LIVE ロバート・クレイ・バンド
活動40周年を凝縮したダイジェスト的ライヴ盤。
02

レンズ曇っちゃったぁ・・・(笑)
続いて旧譜部門。
ポップス、ジャズ、クラシックという順番です。
☆
SONGBOOK
Allen Toussaint
(2013)
アラン・トゥーサンは今年スペインで亡くなられました。
前夜までコンサートを行っており、あまりに急なことで・・・
このCDはピアノ弾き語りにより自分の曲を紹介したライヴ盤で、
彼は近年何度か来日して小さな会場でのコンサートを行っており、
また来日したらこんなコンサートに行きたいと思っていました。
それが、かなわぬ夢に。
今年も多くのミュージシャンが亡くなられましたが、僕個人としては、
急だったことも含め、アラン・トゥーサンの訃報が最もショックでした。
R.I.P.
ベストチューンはWith You In My Arms。
アーロン・ネヴィルで知っていた曲ですが、この曲の優しさといったら。
☆
LET'S MAKE A DEAL
Z.Z.Hill
(1978)
Facebookで記事を見るまで名前すら知らなかったZ.Z.ヒル。
早速買い求めると、もうそれこそはまりました。
純粋なソウルがディスコに駆逐されかけていた70年代後半に
孤軍奮闘するマラコレーベルから出た本格的ソウル。
マラコの話はピーター・バラカンさんの本で読んでいて、いつか
聴いてみたいと思っていたのがここでつながりました。
純粋なソウルだけど新しさもあるUniversal Loveがベストチューン。
☆
DREAM ON
George Duke
(1982)
ジョージ・デュークのShine Onが例のAMの洋楽リクエスト番組で
かかっていて、僕はその曲を知らず、ジョージ・デュークが大好きな
友だちにメールで話を聞くと、彼の日本で最も有名な曲だという。
知らないのも悔しく(笑)、早速買って聴いてみたところ、はまりました。
ほぼフュージョンといえるファンキーなR&B、でしょうか。
もう少し泥臭い人かと思っていたら都会的でスマートな音楽。
いい意味で、真剣に聴くのではなくかけておくと非常にいいですね。
なお、気に入ったので近い年代のもう1枚を買ったのですが、
同じような感じで(当たり前か)、最初ほどインパクトがなかった、
ということは一応付け加えておきます。
ベストチューンはやっぱりShine On。
☆
WHAT TIME IS IT?
The Time
(1982)
先日、NFLミネソタ・バイキングスのホームの試合を観ていたところ、
プレイの合間の現地映像でザ・タイムのJungle Loveがかかっていて、
ミネアポリスサウンドは今でも息づいているんだあ、と妙に感動。
その曲はこのアルバムには入っていませんが、それを含め、
ザ・タイムのカタログが今年国内リマスター廉価盤でリリース。
20年くらい前からずっとザ・タイムを聴きたいと思っていたのが
ついに叶いました。
アルバムではこれ、キレと粘りの驚異的な共存が素晴らしい。
777-9311がベストチューン、さいたまのソウルマニア友だち絶賛。
余談ですが、今年はR&B系旧譜の当たり年だったようですね。
☆
THE VICAR ST. SESSIONS VOL.1
Paul Brady And His Band
(2005)
ポール・ブレイディが昨年の好評を受け再来日公演を行う、
というニュースをFBで見るまで、僕は名前すら知りませんでした。
調べると英国のフォーク歌手、なんとヴァン・モリソンがゲスト参加した
ライヴ盤があるというので買い求めたのがこれ、よかった。
フォークですがちょっと面白い曲を書く人だなって。
ヴァン・モリソンはIrish Heartbeatを共演していますが、
彼が"Van Morrison!"と紹介して会場が異様に盛り上がる、
ライヴ盤だからその音が入っていて、ヴァン・モリソンを
コンサートで観て聴けるなんてとんでもなく羨ましいなあ、と。
ベストチューンはもちろんそれですが、全体的に気に入りました。
☆
DUST BOWL BALLADS
Woody Guthrie
(1940)
村上春樹の本で紹介されていたのを読んだ後買ったウディ・ガスリー。
これがほんとうに気に入りました。
純粋に歌として素晴らしい、だからメッセージも強調される。
重たい話を明るい声で歌うからこそ、より重たく響いてくる。
少し聴いてからまた他のCDも買ってみよう。
☆
OPEN SESAME
Freddie Hubbard
(1960)
フレディ・ハバードのこれ、タイトルの如くひとつの物語を紡いでいます。
似たようなモチーフが何度も出てきて強調されていて、
物語に気持ちよく浸ったまま最後までたどり着きます。
ジャズはインプロビゼーションを楽しむもの、そうかもしれないけれど、
アルバム至上主義者の僕は、このように作り上げられた音楽を
より身近に、分かりやすいと感じます。
ジャズでこういう作品があるのは意外でもありました。
ただ、これ逆に、聴く以上は物語に浸っていたいので、
気軽にかけることができない、そんな大切な1枚となりました。
☆
ADAM'S APPLE
Wayne Shorter
(1966)
一方、ウェイン・ショーターのこれ、はっきり言います。
なぜ、どこが、どういいのか僕にはまるで分かりません。
でも、なぜかこのCDがとっても気に入りました。
今年買ったジャズのCDではいちばんかけた回数が多かったはず。
きっと分からないけどいいというのもジャスの魅力なのでは、と。
ウェイン・ショーター自体僕が大好きなジャズマンではありますが。
☆
RAINBOW SEEKER
Joe Sample
(1978)
ジョー・サンプルのこれもまた懐かしい音。
しかし、マーク・ロンソンのように追体験としての懐かしさではなく、
僕が洋楽を聴く前に世の中に流れていた音楽であって、
音楽自体ではなく、小学生時代を懐かしく思い出したという感じ。
何だろうね、人間のこの懐かしむという気持ちは(笑)。
もちろん音楽としてもとても気に入ったのですが、正直、
5年前の僕なら気に入らなかったかもしれない。
7年前にソウルを真剣に聴くようになり、そこからジャズも見直し、
フュージョンにつながった今だからこそ好きになったようなもので、
やっぱり音楽には聴くタイミングがあるんだなと再認識。
ベストチューンはMelodies Of Love、この手の脆い曲を聴いて
感動したのは久し振りのことでした。
☆
BRAHMS:PIANO CONCERTOS Nos.1 & 2
Helene Grimaud
(2013)
☆
MOZART:PIANO CONCERTOS Nos.19 & 23
Helene Grimaud
(2011)
☆
RACHMANINOV:PIANO SONATA No.2;
CHOPIN:PIANO SONATA No.2,
BARCAROLLE, BERCEUSE
Helene Grimaud
(2006)
2015年は結局、エレーヌ・グリモー様の年だったわけです(笑)。
その中から3点、特に気に入ったものを。
ブラームス・ピアノ協奏曲は元々大好きな曲でしたが、
グリモーの精緻で清らかな演奏に魅力を再発見。
特に2番はオケもウィーンフィルとあって、この曲の決定盤かな。
モーツアルトは、グリモーの生真面目さと曲の遊び心が
合わないかなと聴く前は危惧していましたが、さにあらず。
実は彼女もユーモアがあるけれど普段は隠しているのかな。
ピアニストとしての技量以上の奥深さを感じたCDでした。
ラフマニノフとショパンのピアノソナタを集めたCD。
ここは当然オケがないソロ演奏曲ですが、彼女の演奏は
リズム感、ドライヴ感、グルーヴ感がいかにも現代的で、
要するにノリのいい音楽であることが分かりました。
ショパンの2番ソナタは例の「葬送」ですが、僕はこれ、
寝る前に聴くとなんだか妙に落ち着くんですよね。
ただ、このCDのジャケットは今風の女の子っぽ過ぎて、
音楽はそうだとしても、ちょっと違うかなあ、と・・・
いやもちろんお美しい!
☆
SCHUBERT: FORELLEN-QUINTETT
(1993)
もちろんクラシックはグリモー様だけではないですよ。
シューベルト:ピアノ五重奏曲「ます」。
ジェイムス・レヴァインをピアノに迎えたこの盤も、
僕の中ではリファレンス、最も気に入った盤となりそうです。
今や軸足を指揮者の方に移しているレヴァインですが、
ピアニストとしても優れ技巧と感性の持ち主だと分かりました。
それにこのCDは鱒が水面を跳ねる絵のジャケットがいい。
グリモーのショパンとともに今年最も多く聴いたクラシックCDです。
それにしても楽しい!
☆
BEETHOVEN:COMPLETE PIANO SONATA
Maurizio Pollini
今年最後に紹介するCDは
マウリツィオ・ポリーニのベートーヴェン・ピアノソナタ全集。
ベートーヴェンが優れたメロディメイカーであることに気づきました。
そして、ピアノソナタ第12番 変イ長調「葬送」の第2楽章、
まさに「葬送」の部分は、今年聴いたCDで最も心に響いてきた。
僕が死ぬ時はこの曲をかけてほしいですね。
8枚組を全部聴き込むにはまだ至っていないのですが、
途中からジャズっぽいリズムになる曲もあったりと、ベートーヴェンは
強面でいながらユーモアのある人だったんだと分かりました。
ポリーニの演奏はどうだ、というのは正直まだ自分の言葉で
言うことができないのですが、これはとっても気に入りました。
今後当面ベートーヴェンのソナタは他のピアニストのCDは要らないなと。
それにしても、これが5000円くらいで買えてしまうのだから、
クラシックの箱ものCDも安くなりましたね。
だから次々買ってしまいそうで危険でもあるのですが・・・(笑)。
03

いかがでしたか!
今年は家でCDを聴く時間の半分はクラシックでした。
でも、それは別に意識したものではなく、自然な流れ。
2016年はどういう音楽を気に入って聴くかも分からない。
自分の中に何が聴きたいか、自然と浮かんでくるのが楽しいのです。
だから来年も基本はそのスタンスで聴いていくことでしょう。
さて、今年1年お読みいただきありがとうございます。
来年も平常通り元日、つまり明日から記事を上げてゆきます。
倒れたり不測の事態がない限りは、ですが(笑)、
だからさらりとご挨拶のみにて失礼いたします。
みなさまよいお年をお迎えください。
04


毎年大晦日恒例、良かったCDの記事です。
昨年まではポピュラー音楽の新録音による新譜のみを
ここで取り上げてきましたが、今年から変えました。
ポピュラー音楽の新録音の新譜はTop10として紹介し、
後半では旧譜でもリイシュー盤でも、ジャズもクラシックも含め、
初めて聴いた音源はすべて対象にします。
★新譜Top10
☆1位
CROSSEYED HEART
Keith Richards
栄えある2015年新譜の第1位はキース・リチャーズ!!
予想していたよりもうんとローリング・ストーンズっぽいのが嬉しい。
昨年のストーンズのコンサートでキースはいかにもおじいさん
という感じで、アルバムももっと枯れていると予想していたので、
この颯爽とした姿にはいい意味で驚かされました。
しかも、事前に何も知らずに聴き進めると、11曲目Illusionで
なんとノラ・ジョーンズの声が!
思わず「ノラだ!」と言いそうになってしまいました!
キースなかなかやるじゃん(笑)。
僕の選ぶベストチューンは、でも、もろストーンズのTroubleで。
☆3位
DUETS : RE-WORKING THE CATALOGUE
Van Morrison
ヴァン・モリソンの新譜が出たからには入れないわけにはゆかない。
自分の曲を1曲ずつゲストを招いてデュエットした企画盤ですが、
もはやスタンダードといえる曲にヴァンさんの存在感の重さを感じます。
ゲストもスティーヴ・ウィンウッド、マーク・ノップラー、ジョージ・ベンソン、
メイヴィス・ステイプルズ、タジ・マハール、マイケル・ブーブレから
ジョス・ストーンと幅広いジャンルや年代の人が集まっていますが、
なんといってもSome Peace Of Mind、ボビー・ウーマック最後の声。
涙を誘い、感謝の念が湧いてきます。
ベストチューンもその曲、意味が大きいですね。
☆4位
CASS COUNTY
Don Henley
ドン・ヘンリーの新譜は、郷愁を帯びたカントリー路線。
ただ、カントリーチャートで1位を記録したからカントリーなのだろうけど、
本人はカントリーだどうだとは特に意識せずに聴いていた、
小さい頃の音楽をやってみたかったということでしょう。
それが基礎となり、アメリカの「国民ロック」であるイーグルスになった。
この郷愁、音の響き以上にドンの気持ちが色濃く反映されています。
ところでこの邦題、「カス」だったのか、「キャス」ではないのか・・・
なんだか「カス」と書かれると妙に間抜けな・・・
ベストチューンは郷愁マックスのTake A Picture Of This。
☆5位
TENDERNESS
JD Souther
JDサウザーの新譜は、セルフカヴァー集NATURAL HISTORY
以来4年振り、しかし寡作の彼にしては早いリリースでした。
普通のロックに慣れているとこの音はジャズっぽいと感じるのですが、
JDにはその辺がニュートラルな感覚なのだろうなという自然さがある音。
声の若々しさは相変わらず、そのせいかこちらはドン・ヘンリーとは逆で、
懐かしいというよりは、今でも青春を謳歌している感じがしますね。
60歳になった今でも、夜の酒場で、照れ笑いを浮かべながら
口説き文句を言っているのかな、なんて姿を想像します。
僕はJDよりはるかに年下だけど、このアルバムより老けている。
そう感じてしまうところが自分としては寂しいのですが(笑)。
でも逆にいえば、僕の中に眠っているそういう心が
触発される(た)のかもしれない。
ベストチューンはDance Real Slow、表題曲がない代わりに、
この曲で"Tenderly"と歌うのが印象的、真に優しい音楽です。
☆6位
THE BOOK OF SOULS
Iron Maiden
ブルース・ディッキンソンが咽頭癌との闘病生活。
心配しましたが、活動再開できるほどに回復。
晴れてリリースされたアイアン・メイデンの新譜は2枚組超大作。
宇宙に飛んだ前作とは違いそれこそ地に足がついた音作り。
1970年代ハードロックぽさが色濃いのは意外でした。
作品としては文句なく大好きで弟の評価も高いのですが、
やはり2枚組というのは聴くのに心的抵抗がある。
構えて聴かなければならないし、日々物理的に時間が足りない。
僕が、途中でやめたりピックアップして聴ける性格だったら
よかったかもしれないですが・・・(笑)。
ベストチューンは、これほどまでに70年代っぽいとはと驚かされた
1曲目のIf Eternyty Should Fail。
☆7位
SHADOWS IN THE NIGHT
Bob Dylan
ボブ・ディランの新作はなんと、彼のアイドルだったという
フランク・シナトラを中心としたスタンダード集。
音楽の「ミスマッチ感覚」がこれほどまでにスリリングなものとは。
しかも、そんなものを落ち着いてじっくりと聴かされてしまうとは、
ディランはほんとうに歌うことが好きなんだなと再確認したしだい。
来年また来日公演がありますが、この中の曲は歌うのかな?
行きたいけど、ううん、4月は無理だな・・・
ベストチューンはLucky Old Sun、もったりとした中に
光明が差し込んでくるような味わいのある歌唱です。
☆8位
BORN TO PLAY GUITAR
Buddy Guy
バディ・ガイには、おおこれぞ「ドブルーズ」という音を聴かせてもらえた。
前作ではロックっぽい音に寄り過ぎた、それはそれで悪くはない。
ブルーズを好んで聴くようになってほんとによかったと実感。
しかし驚いたのが、ヴァン・モリソンの参加。
その曲だけどう聴いてもヴァン・モリソンの世界。
冷静にいえば浮いているんだけど、ヴァン・モリソンだから
その浮き具合が嬉しいことこの上ない。
でもやっぱり「ドブルーズ」を求める人にはただ浮いているだけかな。
ベストチューンはもちろんその
Flesh & Bone (Dedicated to B.B.King)。
今年亡くなられたB.B.キングに捧げられたものでもあります。
☆9位
A FOOL TO CARE
Boz Scaggs
ボズ・スキャッグスのR&Bフリークぶりを堪能できる1枚。
ボズ、今年は札幌に来てくれました、感謝。
コンサートでもこの中の曲を演奏しましたが、終演後のロビーには、
この新作を買い求める人の列が出来ていたのは、
新譜が出ていたことを知らなかった人が多かったのでしょう。
僕が行ったコンサートでCDを買うのにこれだけ行列ができたのを
見たのは初めてでした。
ベストチューンは国内盤ボーナストラックで申し訳ないですが、
インプレッションズのGypsy Woman。
でも、コンサートではアンコールのLast Tango On 16th Street
が印象的でした。
☆10位
UPTOWN SPECIAL
Mark Ronson
80年代洋楽で育った人間には音の響きが懐かしい。
もちろん安っぽいキーボードはもっとしっかりした音になっていて、
物理的な音の響きは同じではないけれど、サウンドプロダクションが。
冒頭いきなりスティヴィー・ワンダーのハーモニカが入った曲で
始まりますが、80年代にはハーモニカで客演することが多かったことも
思い出され、うまい仕掛けです。
気合を入れて聴くものではなく、かけておくと気持ちがいい音楽。
懐かしいという感慨はやはり人の心を動かすものなのだ。
「パクリ」とか「二番煎じ」などと言う人もいるかもしれないが、
僕はそこまで冷淡にはなれない、音楽を愛しているから。
それに「懐かしさ」という感慨は齢を追うごとに大切なものになってきている。
過去にしがみついているのではない。
過去の良い思い出があるから人間は生きてゆけるのだから。
その極め付けがUptown Funkであり、2015年に出会った新曲で、
同率1位でこの曲が好き、当然このアルバムのベストチューンもそれ。
次点として3枚を短く
・BLACK MESSIAH ディアンジェロ
プリンスっぽいのは意外でした、癖になる1枚
・TRACKER マーク・ノップラー
「現代のトラッド」路線はますます充実してきました。
・4 NIGHTS OF 40 YEARS LIVE ロバート・クレイ・バンド
活動40周年を凝縮したダイジェスト的ライヴ盤。
02

レンズ曇っちゃったぁ・・・(笑)
続いて旧譜部門。
ポップス、ジャズ、クラシックという順番です。
☆
SONGBOOK
Allen Toussaint
(2013)
アラン・トゥーサンは今年スペインで亡くなられました。
前夜までコンサートを行っており、あまりに急なことで・・・
このCDはピアノ弾き語りにより自分の曲を紹介したライヴ盤で、
彼は近年何度か来日して小さな会場でのコンサートを行っており、
また来日したらこんなコンサートに行きたいと思っていました。
それが、かなわぬ夢に。
今年も多くのミュージシャンが亡くなられましたが、僕個人としては、
急だったことも含め、アラン・トゥーサンの訃報が最もショックでした。
R.I.P.
ベストチューンはWith You In My Arms。
アーロン・ネヴィルで知っていた曲ですが、この曲の優しさといったら。
☆
LET'S MAKE A DEAL
Z.Z.Hill
(1978)
Facebookで記事を見るまで名前すら知らなかったZ.Z.ヒル。
早速買い求めると、もうそれこそはまりました。
純粋なソウルがディスコに駆逐されかけていた70年代後半に
孤軍奮闘するマラコレーベルから出た本格的ソウル。
マラコの話はピーター・バラカンさんの本で読んでいて、いつか
聴いてみたいと思っていたのがここでつながりました。
純粋なソウルだけど新しさもあるUniversal Loveがベストチューン。
☆
DREAM ON
George Duke
(1982)
ジョージ・デュークのShine Onが例のAMの洋楽リクエスト番組で
かかっていて、僕はその曲を知らず、ジョージ・デュークが大好きな
友だちにメールで話を聞くと、彼の日本で最も有名な曲だという。
知らないのも悔しく(笑)、早速買って聴いてみたところ、はまりました。
ほぼフュージョンといえるファンキーなR&B、でしょうか。
もう少し泥臭い人かと思っていたら都会的でスマートな音楽。
いい意味で、真剣に聴くのではなくかけておくと非常にいいですね。
なお、気に入ったので近い年代のもう1枚を買ったのですが、
同じような感じで(当たり前か)、最初ほどインパクトがなかった、
ということは一応付け加えておきます。
ベストチューンはやっぱりShine On。
☆
WHAT TIME IS IT?
The Time
(1982)
先日、NFLミネソタ・バイキングスのホームの試合を観ていたところ、
プレイの合間の現地映像でザ・タイムのJungle Loveがかかっていて、
ミネアポリスサウンドは今でも息づいているんだあ、と妙に感動。
その曲はこのアルバムには入っていませんが、それを含め、
ザ・タイムのカタログが今年国内リマスター廉価盤でリリース。
20年くらい前からずっとザ・タイムを聴きたいと思っていたのが
ついに叶いました。
アルバムではこれ、キレと粘りの驚異的な共存が素晴らしい。
777-9311がベストチューン、さいたまのソウルマニア友だち絶賛。
余談ですが、今年はR&B系旧譜の当たり年だったようですね。
☆
THE VICAR ST. SESSIONS VOL.1
Paul Brady And His Band
(2005)
ポール・ブレイディが昨年の好評を受け再来日公演を行う、
というニュースをFBで見るまで、僕は名前すら知りませんでした。
調べると英国のフォーク歌手、なんとヴァン・モリソンがゲスト参加した
ライヴ盤があるというので買い求めたのがこれ、よかった。
フォークですがちょっと面白い曲を書く人だなって。
ヴァン・モリソンはIrish Heartbeatを共演していますが、
彼が"Van Morrison!"と紹介して会場が異様に盛り上がる、
ライヴ盤だからその音が入っていて、ヴァン・モリソンを
コンサートで観て聴けるなんてとんでもなく羨ましいなあ、と。
ベストチューンはもちろんそれですが、全体的に気に入りました。
☆
DUST BOWL BALLADS
Woody Guthrie
(1940)
村上春樹の本で紹介されていたのを読んだ後買ったウディ・ガスリー。
これがほんとうに気に入りました。
純粋に歌として素晴らしい、だからメッセージも強調される。
重たい話を明るい声で歌うからこそ、より重たく響いてくる。
少し聴いてからまた他のCDも買ってみよう。
☆
OPEN SESAME
Freddie Hubbard
(1960)
フレディ・ハバードのこれ、タイトルの如くひとつの物語を紡いでいます。
似たようなモチーフが何度も出てきて強調されていて、
物語に気持ちよく浸ったまま最後までたどり着きます。
ジャズはインプロビゼーションを楽しむもの、そうかもしれないけれど、
アルバム至上主義者の僕は、このように作り上げられた音楽を
より身近に、分かりやすいと感じます。
ジャズでこういう作品があるのは意外でもありました。
ただ、これ逆に、聴く以上は物語に浸っていたいので、
気軽にかけることができない、そんな大切な1枚となりました。
☆
ADAM'S APPLE
Wayne Shorter
(1966)
一方、ウェイン・ショーターのこれ、はっきり言います。
なぜ、どこが、どういいのか僕にはまるで分かりません。
でも、なぜかこのCDがとっても気に入りました。
今年買ったジャズのCDではいちばんかけた回数が多かったはず。
きっと分からないけどいいというのもジャスの魅力なのでは、と。
ウェイン・ショーター自体僕が大好きなジャズマンではありますが。
☆
RAINBOW SEEKER
Joe Sample
(1978)
ジョー・サンプルのこれもまた懐かしい音。
しかし、マーク・ロンソンのように追体験としての懐かしさではなく、
僕が洋楽を聴く前に世の中に流れていた音楽であって、
音楽自体ではなく、小学生時代を懐かしく思い出したという感じ。
何だろうね、人間のこの懐かしむという気持ちは(笑)。
もちろん音楽としてもとても気に入ったのですが、正直、
5年前の僕なら気に入らなかったかもしれない。
7年前にソウルを真剣に聴くようになり、そこからジャズも見直し、
フュージョンにつながった今だからこそ好きになったようなもので、
やっぱり音楽には聴くタイミングがあるんだなと再認識。
ベストチューンはMelodies Of Love、この手の脆い曲を聴いて
感動したのは久し振りのことでした。
☆
BRAHMS:PIANO CONCERTOS Nos.1 & 2
Helene Grimaud
(2013)
☆
MOZART:PIANO CONCERTOS Nos.19 & 23
Helene Grimaud
(2011)
☆
RACHMANINOV:PIANO SONATA No.2;
CHOPIN:PIANO SONATA No.2,
BARCAROLLE, BERCEUSE
Helene Grimaud
(2006)
2015年は結局、エレーヌ・グリモー様の年だったわけです(笑)。
その中から3点、特に気に入ったものを。
ブラームス・ピアノ協奏曲は元々大好きな曲でしたが、
グリモーの精緻で清らかな演奏に魅力を再発見。
特に2番はオケもウィーンフィルとあって、この曲の決定盤かな。
モーツアルトは、グリモーの生真面目さと曲の遊び心が
合わないかなと聴く前は危惧していましたが、さにあらず。
実は彼女もユーモアがあるけれど普段は隠しているのかな。
ピアニストとしての技量以上の奥深さを感じたCDでした。
ラフマニノフとショパンのピアノソナタを集めたCD。
ここは当然オケがないソロ演奏曲ですが、彼女の演奏は
リズム感、ドライヴ感、グルーヴ感がいかにも現代的で、
要するにノリのいい音楽であることが分かりました。
ショパンの2番ソナタは例の「葬送」ですが、僕はこれ、
寝る前に聴くとなんだか妙に落ち着くんですよね。
ただ、このCDのジャケットは今風の女の子っぽ過ぎて、
音楽はそうだとしても、ちょっと違うかなあ、と・・・
いやもちろんお美しい!
☆
SCHUBERT: FORELLEN-QUINTETT
(1993)
もちろんクラシックはグリモー様だけではないですよ。
シューベルト:ピアノ五重奏曲「ます」。
ジェイムス・レヴァインをピアノに迎えたこの盤も、
僕の中ではリファレンス、最も気に入った盤となりそうです。
今や軸足を指揮者の方に移しているレヴァインですが、
ピアニストとしても優れ技巧と感性の持ち主だと分かりました。
それにこのCDは鱒が水面を跳ねる絵のジャケットがいい。
グリモーのショパンとともに今年最も多く聴いたクラシックCDです。
それにしても楽しい!
☆
BEETHOVEN:COMPLETE PIANO SONATA
Maurizio Pollini
今年最後に紹介するCDは
マウリツィオ・ポリーニのベートーヴェン・ピアノソナタ全集。
ベートーヴェンが優れたメロディメイカーであることに気づきました。
そして、ピアノソナタ第12番 変イ長調「葬送」の第2楽章、
まさに「葬送」の部分は、今年聴いたCDで最も心に響いてきた。
僕が死ぬ時はこの曲をかけてほしいですね。
8枚組を全部聴き込むにはまだ至っていないのですが、
途中からジャズっぽいリズムになる曲もあったりと、ベートーヴェンは
強面でいながらユーモアのある人だったんだと分かりました。
ポリーニの演奏はどうだ、というのは正直まだ自分の言葉で
言うことができないのですが、これはとっても気に入りました。
今後当面ベートーヴェンのソナタは他のピアニストのCDは要らないなと。
それにしても、これが5000円くらいで買えてしまうのだから、
クラシックの箱ものCDも安くなりましたね。
だから次々買ってしまいそうで危険でもあるのですが・・・(笑)。
03

いかがでしたか!
今年は家でCDを聴く時間の半分はクラシックでした。
でも、それは別に意識したものではなく、自然な流れ。
2016年はどういう音楽を気に入って聴くかも分からない。
自分の中に何が聴きたいか、自然と浮かんでくるのが楽しいのです。
だから来年も基本はそのスタンスで聴いていくことでしょう。
さて、今年1年お読みいただきありがとうございます。
来年も平常通り元日、つまり明日から記事を上げてゆきます。
倒れたり不測の事態がない限りは、ですが(笑)、
だからさらりとご挨拶のみにて失礼いたします。
みなさまよいお年をお迎えください。
04

2015年11月25日
最近買ったCDを新譜旧譜合わせてさらりと2015年11月
01

最近買ったCDさらりと紹介記事です。
今回は7枚+ほんとにさらりと2枚あります。
では早速。
☆1枚目
CAS COUNTY
Don Henley
(2015)
ドン・ヘンリー実に15年振りのスタジオアルバム新作が出ました。
つまり、今世紀初めてのアルバムということになりますね。
今作はテキサス州にある彼の出身地からタイトルをとったとのこと。
15年振りの新作ということでかなり期待して臨みました。
実際に聴くと・・・カントリーっぽい、いや、カントリーじゃん。
断っておきますが、、僕はカントリー系も聴くし、
カントリーが嫌いというわけでは決してありません。
でも、これに関しては、ロック的なガツンとくる手応えがあまりなく、
僕の期待と予想とは違うもので、正直最初は戸惑いました。
新作が出ると聞いた時僕が真っ先に思い浮かべたドンの曲が、
AORっぽい雰囲気をたたえたソロ3作目のNew York Minuteであり、
そういう都会的な世界を求めていたふしがあったので。
しかし、せっかくの新作だからと2回3回と聴き進めてゆくと、
これはこれでとても素晴らしいアルバムと思うようになりました。
イーグルスがそもそもカントリーっぽい音楽でしたが、中でも今作は
強引にいえば2作目DESPERADOに近い路線ではあるし、
逆にAORっぽい路線の方が「後付」なのではないか、と。
そしてやっぱりドン・ヘンリーの歌メロは心地よくて、気がつくと
聴き終るごとに数曲を口ずさむようになりました。
4曲目Waiting Tablesは特にイーグルス2作目っぽくて素晴らしい。
カントリー路線の話を続けると、カントリー系の参加ゲストが豪華で、
ミランダ・ランバート(1曲目)、マール・ハガード(2曲目)、
マルティナ・マクブライド(7曲目)、トリーシャ・イヤーウッド(9曲目)、
そしてドリー・パートン(10曲目)となっています。
(曲順は僕が買った16曲入りDeluxe Editionによるもの)。
1曲目Branble Roseは正統的なワルツのカントリー。
ところが、聴いていくと、ミランダの他に男性の声が聴こえてくる。
なんとミック・ジャガーではないか!
ミックの声がカントリーとはあまりにもミスマッチで可笑しいくらい。
多分ミックもカントリーらしく歌おうとはしておらず、当たり前だけど、
いつものミックのスロウな歌い方に徹しているだけ。
僕はここに、ドン・ヘンリーの「ロック魂」を感じました。
そのミスマッチ感覚こそがロックである、という。
そしてこの曲で、ローリング・ストーンズのBEGGAR'S BANQUET
を思い出し、カントリーのようでカントリーではないロックという
あのアルバムの持つ大きな意味を再確認したのでした。
ついでにいえば、最後の曲Where Am I Nowはアップテンポで
これもイーグルスっぽい曲ですが、最後という感じがしない曲で、
ここにも予定調和的ではないドンの「ロック魂」を感じたのでした。
このアルバムはビルボードのカントリーチャートで1位を獲得。
カントリー側からも歓迎されているようですが、一方でそのような
「ロック魂」も感じられる素晴らしいアルバムです。
僕も、最初に抵抗感があった反動で聴く度に好きになり、
今年の新譜でTop5入り間違いないというくらいになりました。
ただ、ですね、弟はやっぱり気に入っていないようでして、
ドン・ヘンリーに何を求めるかで聴こえ方が違うアルバムであるのは
間違いないと、これだけは最後に書き添えておきます。
☆2枚目
PICKING UP THE PIECES
Jewel
(2015)
ジュエルの新作です。
彼女は2008年のPERFECTLY CLEARでカントリーに「転身」。
その作品は素晴らしく、カントリーチャートでも1位に輝き、その後
カントリー路線もう1枚と子ども向けアルバム2枚を出しましたが、
今回は久し振りにデビュー当時のフォーク路線に戻っています。
最初から聴いていた僕には、音としての懐かしさがありました。
しかし、カントリーとフォークは一聴すると似たようなものですが、
ジュエルのように明らかに違って聴こえるというのは、
演奏者の気持ちの問題というよりは、それ以上に、表現方法などで
カントリーには様式のようなものがある、ということなのでしょうね。
この辺り、ドン・ヘンリーとの比較で聴き比べてみると面白いですね。
ただ、ロドニー・クロウェルと1曲、ドリー・パートンと1曲共演していて、
カントリーへの気持ちはまだ続いています。
特に前者は曲そのものもカントリーに聴こえますが、この場合は
ロドニー・クロウェルの歌い方にもそう感じさせる大きな要因があります。
ミック・ジャガーの歌い方をカントリーと感じなかったのとの裏表ですね。
歌は、怒ったような泣いているような、演劇的な歌い方の曲があり、
恐いほど歌の表現力がある人と再確認しましたが、でも、そこを
強調し過ぎると人によっては聴くのがきついかも、とも思います。
1作目に戻ったということで、曲は2作目以降のポップスを強く
意識したものではなく、あくまでもフォークだから、これもやはり
ポピュラリティがあるかどうかといわれれば、少々きついかな。
ところで、という話が2つ続きますが、ジュエルは離婚したそうで。
今回のアルバムリリース情報でそのことを知ったのですが、あれ、
少し前までFacebookで旦那さんと子どもさんと一緒に休日を楽しむ
写真が上がっていて、幸せそうだなと思っていたので、驚きました。
離婚したという記事は見なかったので、隠したかったのかな。
何でもオープンにしたい人には思えなかったので、納得ですが。
もうひとつ、このリンクの大きさでは分かりにくいですが、
ジャケット写真の彼女は胸の谷間が見えているんですよね。
彼女は2作目から豊満な胸を強調し始めたのですが、それは
彼女自身の意向というよりはレコード会社の戦略なのかな、
と思っていたました、いや、思いたかっただけかな。
ところが、今回「出直し」ともいえるこの作品でもやっぱり胸を
強調しているということは、自分自身の意向かのかもしれない。
離婚した直後にこの写真、というのがどうにも意味深、だけど
逆にそういう状況だから敢えてそうしたのかもしれない。
ともあれ、初心に帰ったということで、ジュエルの第2ステージが
始まったと見ていいのでしょう、これからも楽しみです。
☆
DEF LEPPARD
Def Leppard
(2015)
先頃の来日公演を成功裏に終わらせたデフ・レパードの新譜です。
今回はアルバムタイトルを自らのバンド名にしていますね。
こうした例は、デビュー作もしくはメジャーデビュー作の場合と、
THE BEATLESのようにキャリアの途中で心機一転という場合が
ありますが、デフ・レパードはもちろん後者。
カヴァーも含めた11作目のスタジオアルバムですから。
この時期にこのタイトルをつけたのは、ずばり、音楽的に
80年代の若かった頃に戻るという意味なのでしょうね、きっと。
アルバムはその通り、HYSTERIAの頃を意識した音作りで、
1曲目Let's Goはもう嬉しくなるくらいに当時のフィーリング。
4曲目We Belongは2番でジョー・エリオット以外のメンバー、
フィル・コリン、ヴィヴィアン・キャンベル、リック・サヴェージ、
リック・アレンがヴォーカルを取っていて、
バンドの一体感を強調しています。
ただ、他のメンバーの声はインタビューでしか聴いたことがないので、
どれが誰の声かがいまいち分からない・・・(笑)。
一方3曲目Man EnoughはクイーンのAnother One Bites The Dust
のようにメロディアスなベースが前に出ている曲ですが、僕は、
ベースの音があまり大きく聴こえないことがデフレパのほぼ唯一の
「不満」だったので、こういう曲もできるじゃん、と嬉しくなりました。
ただ、ギターの音が80年代の「べったり」とした音ではなく、
エッジが鋭い音であるのは今風のところかな。
雰囲気は80年代だけど音は80年代ではない、というか。
ギターでいえば、曲のつなぎのちょっとしたギターフレーズが
やっぱり上手くて、「じゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃ」
などと、ギターフレーズも口ずさむことがままあります。
曲は、ソウルの影響がある都会的なモダンな響き、
もっといえば80年代のHR/HM系以外のUK勢のような感じの曲が
散見されて、意外と言えば意外でした。
もうひとつ、デフ・レパードは一応HR/HM系に分類されますが、
今の音はハードロックでもないよい意味で普通のロック、ですね。
ビートルズっぽいとまでは言わないけれど、齢をとってハードさが
薄れたのかな、結局行き着くところはここだったんだ、と。
まあでも、僕はよく言いますが、そもそも「ロック」という音楽は
何某かのハードさがあるものであるので、デフ・レパードは結局
「ただのロックバンド」ということになるのでしょう、もちろんいい意味で。
曲でいえば9曲目Battle Of My Own、アコースティックギターを
基調としたボ・ディドリーのリズムの70年代風の曲、これがいい。
もっといえばレッド・ツェッペリンのアコースティックな曲っぽい雰囲気で
とても気に入りましたね、タイトルもそれっぽいし、狙ってるなきっと。
このアルバムは、期待が大きかったわけでもない代わりに、
そこそこ以上はいいだろうと予想していて、その通りという感じ。
もちろん彼らの音楽は大好きだけど、デフ・レパードというバンドは、
その人となりが大好きでずっと応援してきたので、
今回もここでぜひ取り上げたいと思ったのでした。
やっぱり、聴いているといいですからね。
あ、もちろんというか、これは弟が買ったものなのですが(笑)。
☆4枚目
RAINBOW SEEKER
Joe Sample
(1978)
昨年亡くなられたジョー・サンプル。
いつか聴いてみようと思ったところ、ぽちわかやさんが
書き込みで触れておられたのを読み、ネットで調べると
1000円で出ているのを知って購入したもの。
ぽちわかやさん、ありがとうございます。
音楽はいわゆるフュージョン、いかにもその時代の音というのが
なんだか懐かしく感じられました。
1978年は小学5年で、ヤクルトが初優勝した年ですが、
当時は音楽を聞いていなかったのに懐かしいと感じるのは、
やっぱりその時代の音というものがあるのでしょうね。
しかし、4曲目Melodies Of Loveは、どこかで聴いたことがある。
実は、ぽちわかやさんに書き込みをいただいた数日前に、
ラジオでジョー・サンプルの曲がかかっていたのですが、
曲名を覚えられず、どの曲か分からなかった。
これを聴いて、そうだあの時の曲だ、と分かりました。
1回しか聴いていないのに覚えていたというのは、
曲の覚えが人数倍悪い僕も捨てたもんじゃないと思ったのですが、
もしかして、その昔、大人になってからでも、ラジオか何かで
聞き知っていたのかもしれないですね。
この曲は崩れ落ちそうな繊細さとまろやかな甘さが魅力で、
日本でも人気があったであろうことが想像され、売れたのは、
そして名盤といわれるには確かな理由があると思いました。
最後の「旅立ち」はピアノ独奏曲、「さすらい」という感じもしますが、
クラシックのピアノ曲にはない自由さに詩的な響きを感じて、
へえ、こういう音楽もあるんだなあと今更ながら思いました。
僕は少し前にウェイン・ショーターをたくさん聴いていましたが、
最近、実は、即興的要素が強いジャズは、それがいい時もあるけど、
聴くという心構えが必要で、僕の場合はかけておくのは向かない、
ということに気づきました(今だけの心の波かもしれないですが)。
その点フュージョン系は「なにか音楽をかけたい」という時には
主にリズムが安定していて聴きやすい、だからこのアルバムは
ちょうどいいと思いました。
☆5枚目
SCHUMANN : MUSIC FOR OBOE AND PIANO
Douglas Boyd / Maria Joao Pires
(1993)
シューマン「オーボエとピアノの作品集」です。
オーボエって、まあ言ってしまえばマイナーな木管楽器ですよね。
オーケストラに必ずいるけれど、目立つことが少ない。
そんなオーボエに光を当てたのがこの作品、これが素晴らしい。
ダグラス・ボイドはオーボエ奏者の第一人者でスコットランドの人。
マリア・ジョアン・ピリスはポルトガルのピアニストですが、
この2人の織りなす音楽は、聴いていて気持ちがやすらぎます。
オーボエはクラリネットの古いやつ、のようなイメージを僕は持って
いましたが、木管楽器の音色は自然に響いてくる、これがいいですね。
音が自然と揺らいでいるのは、薪ストーブの炎の揺らぎを眺めるのと
同じような感覚に襲われます。
ピリスは札幌に来た際にコンサートに行ったことがあるお気に入りの
ピアニストですが、女性らしい感覚で聴く者を包み込む演奏、
という点において優れたピアニストだと思います。
主張するというよりは、そっと近くにいる、という感じで、オーボエという
地味な楽器の演奏を引き立てるには最適任者ではないかな。
このCDが面白いのは、ジャズを聴くのと似たような感覚に陥ること。
リズムはもちろんジャズのそれではないし、即興性もないので、
ジャズじゃないといわれればもう身も蓋もないです、確かに。
でも、ピアノと管楽器による割と自由な感覚の演奏という点で、
小さな会場はパーティでジャズを聴くのと同じような感覚を
味わえるのではないか、と僕は感じました。
つまり、ジャンルを飛び越えた「真の音楽」ということ。
街中のジャズ祭りなどで、クラリネットによる編曲で
この曲がそっと演奏されていてもまるで違和感がなさそう。
テナーサックスでもよさそうですね、調の問題があるかもですが。
ところでオーボエって、聴き慣れてみるとちゃんとあるもので、
例えば有名なドボルザーク「新世界より」の第2楽章、「家路」として
知られるあの旋律を奏でているのがオーボエだったんだ、と。
そういう発見があることも、これを聴いてよかったところですね。
このCDはかなりとっても気に入りました、今月でいちばんかな。
☆6枚目
THE COMPLETE SONY RECORDINGS
Hilary Hahn (Violin)
クラシック続いてはヒラリー・ハーン。
ミグの父さんが一押しのヴァイオリニストであるとの話をうかがい、
ネットで探したところ、いいタイミングでSONY時代の録音を
すべて集めた5枚組ボックスものがでると知って即注文。
ミグの父さん、ありがとうございます。
ただし、話を聞いてから出るまでがひと月以上あったので、
届くまでがあまりにも待ち遠しかった(笑)。
ミグの父さんいわく「クールビューティー」とのことで、
写真を見てもそういうイメージはあったのですが、まさにその通り。
どこがどうとはうまく表現できないのは申し訳ないのですが、
例えば、おそらくほとんどの方が耳にしたことがあると思われる
メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の甘くて哀愁が漂う旋律、
彼女が奏でると甘さを排除したシャープな音になっていて、
圧倒されるようなすごい音だなあと、或る意味驚き、感心しました。
彼女のヴァイオリンの音色そのものが鋭くて、音を聴くだけで
胸がすかっとする、そんなヴァイオリニスト、と僕は感じました。
一方で、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲では、最後の楽章の
跳ね踊るような楽しい旋律はほんとうに楽しくて、この辺は
若さがよい方向に出ているのかな、とも思いました。
ブラームスを僕は常々ベートーヴェンの次に好きな作曲家と
書いていますが、ブラームスのヴァイオリン協奏曲はこれまで
まともに聴いたことがなく、このセットにはそれも入っているので
その曲になじんでゆけるのも個人的にはよかったところです。
ヒラリー・ハーンは今はドイツ・グラモフォンに移籍していますが、
今度はDGのCDも買ってみようと思います。
最近、クラシックではピアノ楽曲を買って聴くことが多いので、
これでヴァイオリンの道も開けました。
☆7枚目
RESONANCES
Helene Grimaud
(2010)
そして今月のエレーヌ・グリモー様ですよ。
このジャケット、顔が大きくないけれど、女性らしさが出ていていい。
トレイ裏の写真は顔が大きく写っていて、りりしくてやっぱりいい。
内容はいつものように、作曲家誰それの何というタイトルではなく、
「共鳴」と題して4人の作曲家のピアノ独奏曲を集めたもの。
1曲目がモーツァルトのピアノソナタ第8番で、全集以外では
演奏されることがあまり多くない曲を選ぶのも彼女らしい。
しかしもっと彼女らしいのは、2曲目アルバン・ベルクのピアノソナタ、
3曲目リストのピアノソナタ、4曲目がバルトークのピアノ曲と、
いきなりモーツァルトから100年以上後の近代の作曲家の曲を
取り上げていることでしょう。
こうした発想って、今までのクラシックではあまりなかったのでは。
僕はファンだからまったく何も考えず素直に受け入れられましたが、
人によってはモーツァルトと近代を一緒に聴くのは違和感があるかも。
やっぱりグリモーは、もちろん素晴らしい作曲家の曲があっての上で、
作曲家の個性よりも自分の色を出したい人なのでしょう。
このれも気に入りましたが、彼女のリズム感が好き、と分かりました。
ピアノ曲ってひとりで弾くだけに、リズム感も当然のことながら
ピアノ演奏者自身から出てくるものに他ならない。
少し速くてホップ気味のグリモーのリズム感が僕は好きなんだ、と。
そしてこのCDの裏トレイに記されている紹介文(英文)によれば、
彼女のピアノは「知性」と「感情」のバランスの上に成り立っている、
ということですが、僕は「知性」の方により引かれているようですね。
ただ、今回ひとつ気になったのが、録音状態が、悪いとはもちろん
いわないんだけど、8月の記事で紹介したショパン・ラフマニノフの
ふくよかな音の広がりではなく、若干細い感じがしたこと。
ところで、グリモー様のDGから出ているCD、買っていないのは
もうあと2枚しかないので、そろそろ新しいのを聴きたい。
そうしないと「今月のグリモー様」が終わってしまうから・・・(笑)。
☆+2枚
ASTRAL WEEKS
(1969)
HIS BAND AND THE STREET CHOIR
(1970)
Van Morrison
最後はおまけとして、ヴァン・モリソンの2枚を紹介します。
ヴァン・モリソンがWarnerに残した音源のうち2枚が、今月、
ボーナストラック付リマスター・リイシュー盤として出ました。
MOONDANCEは一昨年先に出ていましたが、
これでワーナーからのリイシュー盤は完結となりました。
1970年のHIS BAND AND THE STREET CHOIRは
既に記事にしておりますので、こちらからご覧ください。
で、問題はASTRAL WEEKS。
評論家や玄人筋の人には評価が高いのですが、
僕は正直、これが苦手というか、僕の頭と感性では
それほどまでにいいと言われるのが分からないのです・・・
ただ、それは、僕が考え過ぎているかもしれない。
事実、今回また買って聴いたところ、前よりは幾らか、だいぶ、
音楽として素直に入って来たように感じました。
アストラルは近いうちに記事にできればと思っています。
02

いかがでしたか。
来月もこの記事、あるかな、どうだろう。
新譜でまだ紹介していないものが残っているし。
ただ、少しゆっくりと聴いて年明けでもいいかな。
どうなるか分からないので一応今年のまとめをすれば、
グリモー様の影響でクラシックを聴く機会が増えましたね。
一見すると関係性はないんだけど、でも自分の中では
クラシックと連動してジャズやフュージョンも聴く機会が増えました。
まあ、僕は批評家でも何でもないので、聴きたい時に聴きたい曲を
聴いてゆくだけですが、自分の気持ちの流れがどうなるのか、
実は、自分でも楽しみな部分がありますね。
今のところ、クラシックは減らない傾向にあります。
最後は今朝の3ショット。
01は午後に晴れてから撮ったものですが、03は朝の
まだ降っている時に撮影、レンズのフィルターが曇ってます。
札幌で11月に40cm以上雪が積もったのは62年振りだそうで、
写真02はA公園ですが、11月ではまだ除雪の態勢が整っておらず、
除雪ができなかったので、この後に閉鎖になりました。
聞くところによれば、30cm以上積もったところに無理に入ってきて
数台が一時埋まって動けなくなったそうです。
僕の車も、それら埋まった人が脱出した跡の雪がない場所が
あったので動けただけで、それがなければどうだったか。
たまたま仕事が休みでよかった。
自然には無理に抗わない方がいいですね。
03


最近買ったCDさらりと紹介記事です。
今回は7枚+ほんとにさらりと2枚あります。
では早速。
☆1枚目
CAS COUNTY
Don Henley
(2015)
ドン・ヘンリー実に15年振りのスタジオアルバム新作が出ました。
つまり、今世紀初めてのアルバムということになりますね。
今作はテキサス州にある彼の出身地からタイトルをとったとのこと。
15年振りの新作ということでかなり期待して臨みました。
実際に聴くと・・・カントリーっぽい、いや、カントリーじゃん。
断っておきますが、、僕はカントリー系も聴くし、
カントリーが嫌いというわけでは決してありません。
でも、これに関しては、ロック的なガツンとくる手応えがあまりなく、
僕の期待と予想とは違うもので、正直最初は戸惑いました。
新作が出ると聞いた時僕が真っ先に思い浮かべたドンの曲が、
AORっぽい雰囲気をたたえたソロ3作目のNew York Minuteであり、
そういう都会的な世界を求めていたふしがあったので。
しかし、せっかくの新作だからと2回3回と聴き進めてゆくと、
これはこれでとても素晴らしいアルバムと思うようになりました。
イーグルスがそもそもカントリーっぽい音楽でしたが、中でも今作は
強引にいえば2作目DESPERADOに近い路線ではあるし、
逆にAORっぽい路線の方が「後付」なのではないか、と。
そしてやっぱりドン・ヘンリーの歌メロは心地よくて、気がつくと
聴き終るごとに数曲を口ずさむようになりました。
4曲目Waiting Tablesは特にイーグルス2作目っぽくて素晴らしい。
カントリー路線の話を続けると、カントリー系の参加ゲストが豪華で、
ミランダ・ランバート(1曲目)、マール・ハガード(2曲目)、
マルティナ・マクブライド(7曲目)、トリーシャ・イヤーウッド(9曲目)、
そしてドリー・パートン(10曲目)となっています。
(曲順は僕が買った16曲入りDeluxe Editionによるもの)。
1曲目Branble Roseは正統的なワルツのカントリー。
ところが、聴いていくと、ミランダの他に男性の声が聴こえてくる。
なんとミック・ジャガーではないか!
ミックの声がカントリーとはあまりにもミスマッチで可笑しいくらい。
多分ミックもカントリーらしく歌おうとはしておらず、当たり前だけど、
いつものミックのスロウな歌い方に徹しているだけ。
僕はここに、ドン・ヘンリーの「ロック魂」を感じました。
そのミスマッチ感覚こそがロックである、という。
そしてこの曲で、ローリング・ストーンズのBEGGAR'S BANQUET
を思い出し、カントリーのようでカントリーではないロックという
あのアルバムの持つ大きな意味を再確認したのでした。
ついでにいえば、最後の曲Where Am I Nowはアップテンポで
これもイーグルスっぽい曲ですが、最後という感じがしない曲で、
ここにも予定調和的ではないドンの「ロック魂」を感じたのでした。
このアルバムはビルボードのカントリーチャートで1位を獲得。
カントリー側からも歓迎されているようですが、一方でそのような
「ロック魂」も感じられる素晴らしいアルバムです。
僕も、最初に抵抗感があった反動で聴く度に好きになり、
今年の新譜でTop5入り間違いないというくらいになりました。
ただ、ですね、弟はやっぱり気に入っていないようでして、
ドン・ヘンリーに何を求めるかで聴こえ方が違うアルバムであるのは
間違いないと、これだけは最後に書き添えておきます。
☆2枚目
PICKING UP THE PIECES
Jewel
(2015)
ジュエルの新作です。
彼女は2008年のPERFECTLY CLEARでカントリーに「転身」。
その作品は素晴らしく、カントリーチャートでも1位に輝き、その後
カントリー路線もう1枚と子ども向けアルバム2枚を出しましたが、
今回は久し振りにデビュー当時のフォーク路線に戻っています。
最初から聴いていた僕には、音としての懐かしさがありました。
しかし、カントリーとフォークは一聴すると似たようなものですが、
ジュエルのように明らかに違って聴こえるというのは、
演奏者の気持ちの問題というよりは、それ以上に、表現方法などで
カントリーには様式のようなものがある、ということなのでしょうね。
この辺り、ドン・ヘンリーとの比較で聴き比べてみると面白いですね。
ただ、ロドニー・クロウェルと1曲、ドリー・パートンと1曲共演していて、
カントリーへの気持ちはまだ続いています。
特に前者は曲そのものもカントリーに聴こえますが、この場合は
ロドニー・クロウェルの歌い方にもそう感じさせる大きな要因があります。
ミック・ジャガーの歌い方をカントリーと感じなかったのとの裏表ですね。
歌は、怒ったような泣いているような、演劇的な歌い方の曲があり、
恐いほど歌の表現力がある人と再確認しましたが、でも、そこを
強調し過ぎると人によっては聴くのがきついかも、とも思います。
1作目に戻ったということで、曲は2作目以降のポップスを強く
意識したものではなく、あくまでもフォークだから、これもやはり
ポピュラリティがあるかどうかといわれれば、少々きついかな。
ところで、という話が2つ続きますが、ジュエルは離婚したそうで。
今回のアルバムリリース情報でそのことを知ったのですが、あれ、
少し前までFacebookで旦那さんと子どもさんと一緒に休日を楽しむ
写真が上がっていて、幸せそうだなと思っていたので、驚きました。
離婚したという記事は見なかったので、隠したかったのかな。
何でもオープンにしたい人には思えなかったので、納得ですが。
もうひとつ、このリンクの大きさでは分かりにくいですが、
ジャケット写真の彼女は胸の谷間が見えているんですよね。
彼女は2作目から豊満な胸を強調し始めたのですが、それは
彼女自身の意向というよりはレコード会社の戦略なのかな、
と思っていたました、いや、思いたかっただけかな。
ところが、今回「出直し」ともいえるこの作品でもやっぱり胸を
強調しているということは、自分自身の意向かのかもしれない。
離婚した直後にこの写真、というのがどうにも意味深、だけど
逆にそういう状況だから敢えてそうしたのかもしれない。
ともあれ、初心に帰ったということで、ジュエルの第2ステージが
始まったと見ていいのでしょう、これからも楽しみです。
☆
DEF LEPPARD
Def Leppard
(2015)
先頃の来日公演を成功裏に終わらせたデフ・レパードの新譜です。
今回はアルバムタイトルを自らのバンド名にしていますね。
こうした例は、デビュー作もしくはメジャーデビュー作の場合と、
THE BEATLESのようにキャリアの途中で心機一転という場合が
ありますが、デフ・レパードはもちろん後者。
カヴァーも含めた11作目のスタジオアルバムですから。
この時期にこのタイトルをつけたのは、ずばり、音楽的に
80年代の若かった頃に戻るという意味なのでしょうね、きっと。
アルバムはその通り、HYSTERIAの頃を意識した音作りで、
1曲目Let's Goはもう嬉しくなるくらいに当時のフィーリング。
4曲目We Belongは2番でジョー・エリオット以外のメンバー、
フィル・コリン、ヴィヴィアン・キャンベル、リック・サヴェージ、
リック・アレンがヴォーカルを取っていて、
バンドの一体感を強調しています。
ただ、他のメンバーの声はインタビューでしか聴いたことがないので、
どれが誰の声かがいまいち分からない・・・(笑)。
一方3曲目Man EnoughはクイーンのAnother One Bites The Dust
のようにメロディアスなベースが前に出ている曲ですが、僕は、
ベースの音があまり大きく聴こえないことがデフレパのほぼ唯一の
「不満」だったので、こういう曲もできるじゃん、と嬉しくなりました。
ただ、ギターの音が80年代の「べったり」とした音ではなく、
エッジが鋭い音であるのは今風のところかな。
雰囲気は80年代だけど音は80年代ではない、というか。
ギターでいえば、曲のつなぎのちょっとしたギターフレーズが
やっぱり上手くて、「じゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃ」
などと、ギターフレーズも口ずさむことがままあります。
曲は、ソウルの影響がある都会的なモダンな響き、
もっといえば80年代のHR/HM系以外のUK勢のような感じの曲が
散見されて、意外と言えば意外でした。
もうひとつ、デフ・レパードは一応HR/HM系に分類されますが、
今の音はハードロックでもないよい意味で普通のロック、ですね。
ビートルズっぽいとまでは言わないけれど、齢をとってハードさが
薄れたのかな、結局行き着くところはここだったんだ、と。
まあでも、僕はよく言いますが、そもそも「ロック」という音楽は
何某かのハードさがあるものであるので、デフ・レパードは結局
「ただのロックバンド」ということになるのでしょう、もちろんいい意味で。
曲でいえば9曲目Battle Of My Own、アコースティックギターを
基調としたボ・ディドリーのリズムの70年代風の曲、これがいい。
もっといえばレッド・ツェッペリンのアコースティックな曲っぽい雰囲気で
とても気に入りましたね、タイトルもそれっぽいし、狙ってるなきっと。
このアルバムは、期待が大きかったわけでもない代わりに、
そこそこ以上はいいだろうと予想していて、その通りという感じ。
もちろん彼らの音楽は大好きだけど、デフ・レパードというバンドは、
その人となりが大好きでずっと応援してきたので、
今回もここでぜひ取り上げたいと思ったのでした。
やっぱり、聴いているといいですからね。
あ、もちろんというか、これは弟が買ったものなのですが(笑)。
☆4枚目
RAINBOW SEEKER
Joe Sample
(1978)
昨年亡くなられたジョー・サンプル。
いつか聴いてみようと思ったところ、ぽちわかやさんが
書き込みで触れておられたのを読み、ネットで調べると
1000円で出ているのを知って購入したもの。
ぽちわかやさん、ありがとうございます。
音楽はいわゆるフュージョン、いかにもその時代の音というのが
なんだか懐かしく感じられました。
1978年は小学5年で、ヤクルトが初優勝した年ですが、
当時は音楽を聞いていなかったのに懐かしいと感じるのは、
やっぱりその時代の音というものがあるのでしょうね。
しかし、4曲目Melodies Of Loveは、どこかで聴いたことがある。
実は、ぽちわかやさんに書き込みをいただいた数日前に、
ラジオでジョー・サンプルの曲がかかっていたのですが、
曲名を覚えられず、どの曲か分からなかった。
これを聴いて、そうだあの時の曲だ、と分かりました。
1回しか聴いていないのに覚えていたというのは、
曲の覚えが人数倍悪い僕も捨てたもんじゃないと思ったのですが、
もしかして、その昔、大人になってからでも、ラジオか何かで
聞き知っていたのかもしれないですね。
この曲は崩れ落ちそうな繊細さとまろやかな甘さが魅力で、
日本でも人気があったであろうことが想像され、売れたのは、
そして名盤といわれるには確かな理由があると思いました。
最後の「旅立ち」はピアノ独奏曲、「さすらい」という感じもしますが、
クラシックのピアノ曲にはない自由さに詩的な響きを感じて、
へえ、こういう音楽もあるんだなあと今更ながら思いました。
僕は少し前にウェイン・ショーターをたくさん聴いていましたが、
最近、実は、即興的要素が強いジャズは、それがいい時もあるけど、
聴くという心構えが必要で、僕の場合はかけておくのは向かない、
ということに気づきました(今だけの心の波かもしれないですが)。
その点フュージョン系は「なにか音楽をかけたい」という時には
主にリズムが安定していて聴きやすい、だからこのアルバムは
ちょうどいいと思いました。
☆5枚目
SCHUMANN : MUSIC FOR OBOE AND PIANO
Douglas Boyd / Maria Joao Pires
(1993)
シューマン「オーボエとピアノの作品集」です。
オーボエって、まあ言ってしまえばマイナーな木管楽器ですよね。
オーケストラに必ずいるけれど、目立つことが少ない。
そんなオーボエに光を当てたのがこの作品、これが素晴らしい。
ダグラス・ボイドはオーボエ奏者の第一人者でスコットランドの人。
マリア・ジョアン・ピリスはポルトガルのピアニストですが、
この2人の織りなす音楽は、聴いていて気持ちがやすらぎます。
オーボエはクラリネットの古いやつ、のようなイメージを僕は持って
いましたが、木管楽器の音色は自然に響いてくる、これがいいですね。
音が自然と揺らいでいるのは、薪ストーブの炎の揺らぎを眺めるのと
同じような感覚に襲われます。
ピリスは札幌に来た際にコンサートに行ったことがあるお気に入りの
ピアニストですが、女性らしい感覚で聴く者を包み込む演奏、
という点において優れたピアニストだと思います。
主張するというよりは、そっと近くにいる、という感じで、オーボエという
地味な楽器の演奏を引き立てるには最適任者ではないかな。
このCDが面白いのは、ジャズを聴くのと似たような感覚に陥ること。
リズムはもちろんジャズのそれではないし、即興性もないので、
ジャズじゃないといわれればもう身も蓋もないです、確かに。
でも、ピアノと管楽器による割と自由な感覚の演奏という点で、
小さな会場はパーティでジャズを聴くのと同じような感覚を
味わえるのではないか、と僕は感じました。
つまり、ジャンルを飛び越えた「真の音楽」ということ。
街中のジャズ祭りなどで、クラリネットによる編曲で
この曲がそっと演奏されていてもまるで違和感がなさそう。
テナーサックスでもよさそうですね、調の問題があるかもですが。
ところでオーボエって、聴き慣れてみるとちゃんとあるもので、
例えば有名なドボルザーク「新世界より」の第2楽章、「家路」として
知られるあの旋律を奏でているのがオーボエだったんだ、と。
そういう発見があることも、これを聴いてよかったところですね。
このCDはかなりとっても気に入りました、今月でいちばんかな。
☆6枚目
THE COMPLETE SONY RECORDINGS
Hilary Hahn (Violin)
クラシック続いてはヒラリー・ハーン。
ミグの父さんが一押しのヴァイオリニストであるとの話をうかがい、
ネットで探したところ、いいタイミングでSONY時代の録音を
すべて集めた5枚組ボックスものがでると知って即注文。
ミグの父さん、ありがとうございます。
ただし、話を聞いてから出るまでがひと月以上あったので、
届くまでがあまりにも待ち遠しかった(笑)。
ミグの父さんいわく「クールビューティー」とのことで、
写真を見てもそういうイメージはあったのですが、まさにその通り。
どこがどうとはうまく表現できないのは申し訳ないのですが、
例えば、おそらくほとんどの方が耳にしたことがあると思われる
メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の甘くて哀愁が漂う旋律、
彼女が奏でると甘さを排除したシャープな音になっていて、
圧倒されるようなすごい音だなあと、或る意味驚き、感心しました。
彼女のヴァイオリンの音色そのものが鋭くて、音を聴くだけで
胸がすかっとする、そんなヴァイオリニスト、と僕は感じました。
一方で、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲では、最後の楽章の
跳ね踊るような楽しい旋律はほんとうに楽しくて、この辺は
若さがよい方向に出ているのかな、とも思いました。
ブラームスを僕は常々ベートーヴェンの次に好きな作曲家と
書いていますが、ブラームスのヴァイオリン協奏曲はこれまで
まともに聴いたことがなく、このセットにはそれも入っているので
その曲になじんでゆけるのも個人的にはよかったところです。
ヒラリー・ハーンは今はドイツ・グラモフォンに移籍していますが、
今度はDGのCDも買ってみようと思います。
最近、クラシックではピアノ楽曲を買って聴くことが多いので、
これでヴァイオリンの道も開けました。
☆7枚目
RESONANCES
Helene Grimaud
(2010)
そして今月のエレーヌ・グリモー様ですよ。
このジャケット、顔が大きくないけれど、女性らしさが出ていていい。
トレイ裏の写真は顔が大きく写っていて、りりしくてやっぱりいい。
内容はいつものように、作曲家誰それの何というタイトルではなく、
「共鳴」と題して4人の作曲家のピアノ独奏曲を集めたもの。
1曲目がモーツァルトのピアノソナタ第8番で、全集以外では
演奏されることがあまり多くない曲を選ぶのも彼女らしい。
しかしもっと彼女らしいのは、2曲目アルバン・ベルクのピアノソナタ、
3曲目リストのピアノソナタ、4曲目がバルトークのピアノ曲と、
いきなりモーツァルトから100年以上後の近代の作曲家の曲を
取り上げていることでしょう。
こうした発想って、今までのクラシックではあまりなかったのでは。
僕はファンだからまったく何も考えず素直に受け入れられましたが、
人によってはモーツァルトと近代を一緒に聴くのは違和感があるかも。
やっぱりグリモーは、もちろん素晴らしい作曲家の曲があっての上で、
作曲家の個性よりも自分の色を出したい人なのでしょう。
このれも気に入りましたが、彼女のリズム感が好き、と分かりました。
ピアノ曲ってひとりで弾くだけに、リズム感も当然のことながら
ピアノ演奏者自身から出てくるものに他ならない。
少し速くてホップ気味のグリモーのリズム感が僕は好きなんだ、と。
そしてこのCDの裏トレイに記されている紹介文(英文)によれば、
彼女のピアノは「知性」と「感情」のバランスの上に成り立っている、
ということですが、僕は「知性」の方により引かれているようですね。
ただ、今回ひとつ気になったのが、録音状態が、悪いとはもちろん
いわないんだけど、8月の記事で紹介したショパン・ラフマニノフの
ふくよかな音の広がりではなく、若干細い感じがしたこと。
ところで、グリモー様のDGから出ているCD、買っていないのは
もうあと2枚しかないので、そろそろ新しいのを聴きたい。
そうしないと「今月のグリモー様」が終わってしまうから・・・(笑)。
☆+2枚
ASTRAL WEEKS
(1969)
HIS BAND AND THE STREET CHOIR
(1970)
Van Morrison
最後はおまけとして、ヴァン・モリソンの2枚を紹介します。
ヴァン・モリソンがWarnerに残した音源のうち2枚が、今月、
ボーナストラック付リマスター・リイシュー盤として出ました。
MOONDANCEは一昨年先に出ていましたが、
これでワーナーからのリイシュー盤は完結となりました。
1970年のHIS BAND AND THE STREET CHOIRは
既に記事にしておりますので、こちらからご覧ください。
で、問題はASTRAL WEEKS。
評論家や玄人筋の人には評価が高いのですが、
僕は正直、これが苦手というか、僕の頭と感性では
それほどまでにいいと言われるのが分からないのです・・・
ただ、それは、僕が考え過ぎているかもしれない。
事実、今回また買って聴いたところ、前よりは幾らか、だいぶ、
音楽として素直に入って来たように感じました。
アストラルは近いうちに記事にできればと思っています。
02

いかがでしたか。
来月もこの記事、あるかな、どうだろう。
新譜でまだ紹介していないものが残っているし。
ただ、少しゆっくりと聴いて年明けでもいいかな。
どうなるか分からないので一応今年のまとめをすれば、
グリモー様の影響でクラシックを聴く機会が増えましたね。
一見すると関係性はないんだけど、でも自分の中では
クラシックと連動してジャズやフュージョンも聴く機会が増えました。
まあ、僕は批評家でも何でもないので、聴きたい時に聴きたい曲を
聴いてゆくだけですが、自分の気持ちの流れがどうなるのか、
実は、自分でも楽しみな部分がありますね。
今のところ、クラシックは減らない傾向にあります。
最後は今朝の3ショット。
01は午後に晴れてから撮ったものですが、03は朝の
まだ降っている時に撮影、レンズのフィルターが曇ってます。
札幌で11月に40cm以上雪が積もったのは62年振りだそうで、
写真02はA公園ですが、11月ではまだ除雪の態勢が整っておらず、
除雪ができなかったので、この後に閉鎖になりました。
聞くところによれば、30cm以上積もったところに無理に入ってきて
数台が一時埋まって動けなくなったそうです。
僕の車も、それら埋まった人が脱出した跡の雪がない場所が
あったので動けただけで、それがなければどうだったか。
たまたま仕事が休みでよかった。
自然には無理に抗わない方がいいですね。
03




 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト


























