2017年12月03日
2017年11月の野鳥写真
01

2017年11月に撮影した野鳥写真をまとめました。
断りのないものはA公園で撮影したものです。
★
2017年11月2日
カケス(亜種ミヤマカケス)
どんぐりおいしいのかな。
02

★
2017年11月2日
キレンジャク
ヒレンジャク
右側の羽を広げた1羽がヒレンジャク、それ以外がキレンジャク。
今年豊作だったヤマブドウの実を食べているところ。
A公園は今年11月、キレンジャクとヒレンジャクが同じくらい
入っていましたが、それは珍しいことでした。
ヒレンジャクは今日現在まだ残っていますが、
キレンジャクはいなくなったもようです。
03

★
2017年11月2日
コゲラ
この頃はまだ木々に黄色い葉があったんだ。
04

★
2017年11月3日
ハイタカ
アカゲラを襲うも狩りに失敗し休んでいるところ。
雌の個体ですが、別の日に雄の個体もいました。
05

★
2017年11月5日
エナガ(亜種シマエナガ)
エナガはA公園のどこによく出るか、
おおよそ見えてきました。
でも出てくる時間には傾向のようなものがありません。
06

★2
017年11月7日
ヤマガラ
ヤマガラはどこに行っても人気者ですね。
07

★
2017年11月9日
カルガモ
彼女と帯広に行った日。
僕は緑丘公園で野鳥撮影をしていました。
公園には池があり、カモ類がいました。
カルガモ見るのは久し振り。
08

★
2017年11月9日
カワアイサ雌
カワアイサもいましたが、餌付けをしている人がいるようで、
寄って来る個体がいました。
僕はカワアイサが寄って来るのは初めてで驚きました。
なおこの日はコアカゲラを撮影したかったのですが、
残念ながら会うことができませんでした。
また行かなきゃ。
09

★
2017年11月11日
エナガ(亜種シマエナガ)
フルサイズでこれくらいまで近くで撮れたのですが、
ううん、写真的にはいまいちいまにいまさんくらい。
10

★
2017年11月11日
カケス(亜種ミヤマカケス)
今年A公園に居着いているカケスはサービスがよくて、
例年より近寄って撮らせてくれます。
11

★
2017年11月12日
カケス(亜種ミヤマカケス)
サービス精神がいい証拠に(笑)、
2日連続近くで撮らせてくれました。
12

★
2017年11月14日
ゴジュウカラ(亜種シロハラゴジュウカラ)
ゴジュウカラは通常営業です(笑)。
13

★
2017年11月17日
ウソ雌
ウソはこの冬A公園で声がよく聞かれますが、
写真が撮れるほど近くに来ることは少ない。
この時は僕が近寄ると4羽5羽くらいが飛び立って逃げましたが、
この1羽の雌だけ残ってナナカマドの実を食べ続けていました。
食いしん坊さん。
14

★
2017年11月23日
ハシブトガラ
ハシブトガラは11月29日に囀りを始めました。
例年クリスマス頃「初鳴き」、今年は早いぞ。
15

★
2017年11月24日
エナガ(亜種シマエナガ)
なかなか近くで撮れない。
でもA公園に行く日はほぼ毎日見ています。
16

★
2017年11月25日
ノスリ
11月、A公園周辺にノスリ幼鳥が居着いていました。
目撃者(撮影者)多数、僕もそのひとりになれました。
ノスリはA公園では春と秋に比較的よく出る以外あまり見られず、
周辺で越冬したこともないのですが、こんなことは初めて。
幼鳥で慣れていないのかな、いろんなことに。
ここ3日は目撃情報がなく、もういないかもしれないですが、
もう少し追ってゆきたいです。
17

★
2017年11月28日
カケス(亜種ミヤマカケス) 左
オオアカゲラ雄 右
オオアカゲラの雄がカラマツに来て木をつついていました。
A公園でオオアカゲラは冬になると比較的よく見られる
ようになりますが、なぜか雌が多くい。
だから雄が見られたのはなおのこと嬉しかった。
しかし、木をつついているとカケスがやって来て、
ちゃっかりその穴から餌をとろうとしていました。
(写真に見える大きな穴とは別の穴です念のため)。
オオアカゲラは逃げるだけ。
この後さらに遠くに逃げました。
こうして見ると、どちらも「ハトくらい」の大きさとはいいますが、
カケスの方が大きいですね。
18

★
2017年11月28日
シジュウカラ
というわけで今回はこの辺でさらばちゃ!
19

おっと、犬たちは元気ですよ。

2017年11月に撮影した野鳥写真をまとめました。
断りのないものはA公園で撮影したものです。
★
2017年11月2日
カケス(亜種ミヤマカケス)
どんぐりおいしいのかな。
02

★
2017年11月2日
キレンジャク
ヒレンジャク
右側の羽を広げた1羽がヒレンジャク、それ以外がキレンジャク。
今年豊作だったヤマブドウの実を食べているところ。
A公園は今年11月、キレンジャクとヒレンジャクが同じくらい
入っていましたが、それは珍しいことでした。
ヒレンジャクは今日現在まだ残っていますが、
キレンジャクはいなくなったもようです。
03

★
2017年11月2日
コゲラ
この頃はまだ木々に黄色い葉があったんだ。
04

★
2017年11月3日
ハイタカ
アカゲラを襲うも狩りに失敗し休んでいるところ。
雌の個体ですが、別の日に雄の個体もいました。
05

★
2017年11月5日
エナガ(亜種シマエナガ)
エナガはA公園のどこによく出るか、
おおよそ見えてきました。
でも出てくる時間には傾向のようなものがありません。
06

★2
017年11月7日
ヤマガラ
ヤマガラはどこに行っても人気者ですね。
07

★
2017年11月9日
カルガモ
彼女と帯広に行った日。
僕は緑丘公園で野鳥撮影をしていました。
公園には池があり、カモ類がいました。
カルガモ見るのは久し振り。
08

★
2017年11月9日
カワアイサ雌
カワアイサもいましたが、餌付けをしている人がいるようで、
寄って来る個体がいました。
僕はカワアイサが寄って来るのは初めてで驚きました。
なおこの日はコアカゲラを撮影したかったのですが、
残念ながら会うことができませんでした。
また行かなきゃ。
09

★
2017年11月11日
エナガ(亜種シマエナガ)
フルサイズでこれくらいまで近くで撮れたのですが、
ううん、写真的にはいまいちいまにいまさんくらい。
10

★
2017年11月11日
カケス(亜種ミヤマカケス)
今年A公園に居着いているカケスはサービスがよくて、
例年より近寄って撮らせてくれます。
11

★
2017年11月12日
カケス(亜種ミヤマカケス)
サービス精神がいい証拠に(笑)、
2日連続近くで撮らせてくれました。
12

★
2017年11月14日
ゴジュウカラ(亜種シロハラゴジュウカラ)
ゴジュウカラは通常営業です(笑)。
13

★
2017年11月17日
ウソ雌
ウソはこの冬A公園で声がよく聞かれますが、
写真が撮れるほど近くに来ることは少ない。
この時は僕が近寄ると4羽5羽くらいが飛び立って逃げましたが、
この1羽の雌だけ残ってナナカマドの実を食べ続けていました。
食いしん坊さん。
14

★
2017年11月23日
ハシブトガラ
ハシブトガラは11月29日に囀りを始めました。
例年クリスマス頃「初鳴き」、今年は早いぞ。
15

★
2017年11月24日
エナガ(亜種シマエナガ)
なかなか近くで撮れない。
でもA公園に行く日はほぼ毎日見ています。
16

★
2017年11月25日
ノスリ
11月、A公園周辺にノスリ幼鳥が居着いていました。
目撃者(撮影者)多数、僕もそのひとりになれました。
ノスリはA公園では春と秋に比較的よく出る以外あまり見られず、
周辺で越冬したこともないのですが、こんなことは初めて。
幼鳥で慣れていないのかな、いろんなことに。
ここ3日は目撃情報がなく、もういないかもしれないですが、
もう少し追ってゆきたいです。
17

★
2017年11月28日
カケス(亜種ミヤマカケス) 左
オオアカゲラ雄 右
オオアカゲラの雄がカラマツに来て木をつついていました。
A公園でオオアカゲラは冬になると比較的よく見られる
ようになりますが、なぜか雌が多くい。
だから雄が見られたのはなおのこと嬉しかった。
しかし、木をつついているとカケスがやって来て、
ちゃっかりその穴から餌をとろうとしていました。
(写真に見える大きな穴とは別の穴です念のため)。
オオアカゲラは逃げるだけ。
この後さらに遠くに逃げました。
こうして見ると、どちらも「ハトくらい」の大きさとはいいますが、
カケスの方が大きいですね。
18

★
2017年11月28日
シジュウカラ
というわけで今回はこの辺でさらばちゃ!
19

おっと、犬たちは元気ですよ。
2017年11月16日
2017年11月の六花亭「おやつ屋さん」とシマエナガ
01
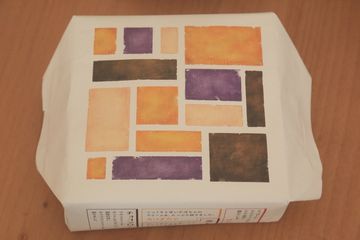
六花亭「おやつ屋さん」、2017年11月はモンブラン。
今月も彼女が買って2人で食べました。
02

「モンブラン」、本来の定義は栗を使ったもののようですが、
最近ではそういう形のケーキの総称として定着していますね。
でもこれ、日本だけなのかな?
モンブラン自体はその名の通りフランス発祥のもののようですが。
まあ能書きはともかく、食べましょう。
包装紙に書かれている叩き文句を引用しつつ、
食べた順番に紹介します。
03

りんご
さっぱりとした
りんごクリームの中には
りんご果肉が
隠れています。
おいしい、確かに。
でも彼女曰く、甘すぎる。
りんごのほのかな酸味がほとんど感じられない。
中のスポンジもこのクリームとは合っていない、とも。
04

かぼちゃ
こっくりと甘いかぼちゃの
クリームを、たっぷり絞りました。
これは見た目通りのおいしさ。
甘すぎないのはこれ以降のものには共通でした。
05

中はこうなっています。
僕はかぼちゃスイーツ大好き、大満足。
06

チョコマロン
マロンクリームを
サンドしたスポンジに
相性の良い
チョコマロンクリームを
絞りました。
チョコモンブランは市内に有名な店があって僕も大好きですが、
対抗心みたいなものもあったのかな、遊び心も混ざって。
あっさり系なのも同じ。
07

ただしこちらは「チョコマロン」、栗が入っています。
この栗が意外と小さくて、大きい栗を期待した人には、
多少肩透かしだったかもしれない。
僕たちも「あれっ」となりましたが、でもおいしいことには違いない。
栗を使っているのでこれは正真正銘モンブランなのかな。
でも、「白い山」という意味、これは白くない・・・まあいいか。
08

紫いも
目にも彩やかな紫いもの
クリームは濃厚で、
なめらかな口当たりです。
紫いものスイーツって見た目インパクト強いですよね。
食べた後舌が紫になっていないか鏡で見たり・・・しないけど(笑)。
これも
今回はパッケージデザインやケーキの見せ方がきれいで、
総合的に見れば今までで1、2を争うくらい気に入りました。
◇
さて後半は今月に入って撮影したシマエナガ。
09

11月7日撮影。
シマエナガはちょこまかと動きながら餌を探すので、
飛ぶ瞬間の写真が結構撮れます。
ただ、きれいに撮るにはシャッター速度を速くしないと
被写体ブレになります。
これはやや失敗写真ですが、まあ全体的には
悪くないのでここで使いました。
10

11月14日撮影
シマエナガは人を見ているのかな。
顔を背けた写真もまた撮れることがままあります。
これは最近では最も寄れた時のものですが、
顔がこっちを向いていたら最高の写真だった、惜しい。
11

同じ個体を追っていたところ、
柳の中でようやく顔が撮れました。
しかし遠い、体も幹に隠れているし。
シマエナガは立冬を過ぎて見られる機会が増えてきました。
また撮らせてくださいね、ありがとう。
12

おまけというか、ゴジュウカラ(亜種シロハラゴジュウカラ)。
一応当BLOGのシンボルですからね、時々出てもらわないと。
最後は犬たち3ショットにて。
13

青空の下、犬たちもやっぱり気分よかったのかな?
よかった、ということにさせてもらいましょう。
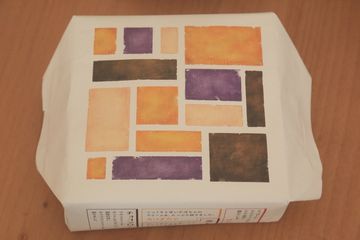
六花亭「おやつ屋さん」、2017年11月はモンブラン。
今月も彼女が買って2人で食べました。
02

「モンブラン」、本来の定義は栗を使ったもののようですが、
最近ではそういう形のケーキの総称として定着していますね。
でもこれ、日本だけなのかな?
モンブラン自体はその名の通りフランス発祥のもののようですが。
まあ能書きはともかく、食べましょう。
包装紙に書かれている叩き文句を引用しつつ、
食べた順番に紹介します。
03

りんご
さっぱりとした
りんごクリームの中には
りんご果肉が
隠れています。
おいしい、確かに。
でも彼女曰く、甘すぎる。
りんごのほのかな酸味がほとんど感じられない。
中のスポンジもこのクリームとは合っていない、とも。
04

かぼちゃ
こっくりと甘いかぼちゃの
クリームを、たっぷり絞りました。
これは見た目通りのおいしさ。
甘すぎないのはこれ以降のものには共通でした。
05

中はこうなっています。
僕はかぼちゃスイーツ大好き、大満足。
06

チョコマロン
マロンクリームを
サンドしたスポンジに
相性の良い
チョコマロンクリームを
絞りました。
チョコモンブランは市内に有名な店があって僕も大好きですが、
対抗心みたいなものもあったのかな、遊び心も混ざって。
あっさり系なのも同じ。
07

ただしこちらは「チョコマロン」、栗が入っています。
この栗が意外と小さくて、大きい栗を期待した人には、
多少肩透かしだったかもしれない。
僕たちも「あれっ」となりましたが、でもおいしいことには違いない。
栗を使っているのでこれは正真正銘モンブランなのかな。
でも、「白い山」という意味、これは白くない・・・まあいいか。
08

紫いも
目にも彩やかな紫いもの
クリームは濃厚で、
なめらかな口当たりです。
紫いものスイーツって見た目インパクト強いですよね。
食べた後舌が紫になっていないか鏡で見たり・・・しないけど(笑)。
これも
今回はパッケージデザインやケーキの見せ方がきれいで、
総合的に見れば今までで1、2を争うくらい気に入りました。
◇
さて後半は今月に入って撮影したシマエナガ。
09

11月7日撮影。
シマエナガはちょこまかと動きながら餌を探すので、
飛ぶ瞬間の写真が結構撮れます。
ただ、きれいに撮るにはシャッター速度を速くしないと
被写体ブレになります。
これはやや失敗写真ですが、まあ全体的には
悪くないのでここで使いました。
10

11月14日撮影
シマエナガは人を見ているのかな。
顔を背けた写真もまた撮れることがままあります。
これは最近では最も寄れた時のものですが、
顔がこっちを向いていたら最高の写真だった、惜しい。
11

同じ個体を追っていたところ、
柳の中でようやく顔が撮れました。
しかし遠い、体も幹に隠れているし。
シマエナガは立冬を過ぎて見られる機会が増えてきました。
また撮らせてくださいね、ありがとう。
12

おまけというか、ゴジュウカラ(亜種シロハラゴジュウカラ)。
一応当BLOGのシンボルですからね、時々出てもらわないと。
最後は犬たち3ショットにて。
13

青空の下、犬たちもやっぱり気分よかったのかな?
よかった、ということにさせてもらいましょう。
2017年09月11日
ヤマゲラ事情
01

ここ2週間ほど、A公園「森の家」の周りで
ヤマゲラの姿をよく見ます。
これは今朝撮影した雌の個体。
ヤマゲラはカラ類のように採餌中に声を出すことはあまりなく、
木をつつく音で気づくか、さもなくば鉢合わせしてしまい、
そこで初めて「キュキュッ」と声を出して飛んで逃げます。
しかし一度に遠くまで飛ぶことはめったになく、
5mから15mくらいの近い木や地面にすぐにとまります。
02

今朝の雌同一個体をもう1枚。
今朝は散策路脇の笹薮に生えた木の下の方で
採餌していたところに僕が通りかかって飛んで逃げた。
10mほど逃げた先で木にとまるのではなく地面に降り、
地面をつついて何かを食べ始めました。
そうなんです、ここ2週間で見られるヤマゲラの
もうひとつの共通項は、いつも地面か木の下の方にいる。
この期間、飛んで逃げた時以外はすべて、
僕の腰より下にいたところを最初に見つけました。
つまり、いつも下の方で何かを食べているということですが、
アリと考えると納得はできます。
アリ多いですからね、今の時期。
今朝はこの1羽以外に笹薮で少し大きめの音がしたので
探しましたが、ヤマゲラがもう1羽いたのか他の鳥かは分からず、
こちらの個体を追いかけているうちにもう一方は見失いました。
03

6日遡って9月5日撮影のこちらは雄の個体。
雄の個体ですが、顔の周りの羽がぽやぽやした感じで、
幼鳥と思われます。
木にとまっていますが、これもやはり最初に鉢合わせした時は、
僕の膝くらいの木の幹にいました。
04

同じ雄の幼鳥と思われる個体。
この時は見ていると木をどんどん登っていきました。
笹薮に生えた木の場合、ある程度上がってくれる方が
撮影はしやすいんですよね。
なんて人間の事情はいいとして、これ、目の周りが特に
不揃いな感じがして、見慣れたヤマゲラ成鳥とは少し違う。
最初の2枚、今朝撮影した雌は成鳥ですが、
となるとこの2羽は親子なのかもしれない。
餌の取り方をお母さんが子供に教えているのかな。
05

さらに6日遡って8月31日の1枚。
雌成鳥、この日からほぼ毎日ヤマゲラを見ていますが、
この時はこの個体の近くにもう1羽いたのを目視しました。
しましたが、飛ぶ後ろ姿を一瞬見ただけで、
頭に赤い部分があるかどうかは確認できず。
親子、母子だったのかな。
もし親子だとすれば、ある程度の期間一緒にいるとして、
でもそろそろお別れの時期を迎えることでしょう。
「森の家」の周りで見られるのももうそろそろ終わりかな。
その間また見て撮れるといいのですが。
06

この期間に見た他のキツツキの写真を2枚ほど。
アカゲラ雄、成鳥。
今年は結局幼鳥を見ることが少なかったので、
7月にお伝えしたように、アカゲラの羽が飛散していた、
その羽の持ち主は幼鳥だったのではないか、
巣立ち後すぐに襲われたのでは、と、考えずにはいられません。
07

クマゲラ雌、同じ時に撮った同一個体の他の写真を見ると、
虹彩が緑がかっていないので成鳥と思われますが、でも、
この時期にはもう幼鳥も緑みが抜けているかもしれず、
なんとも言えないです。
クマゲラは週に1回くらい「森の家」の周りで見ますが、
この前に見た8月下旬の時は雄の今年巣立った幼鳥でした。
それは虹彩の色でわかったのですが、でも、鳴き方も
幼鳥はなんとなくしゃきっとしない感じの声を出します。
あ、せっかくなのにコゲラを撮っていませんでした。
コゲラは声はよく聞きますが、そういえばこの間は、
近くでは見なかったのでした。
みなさん、撮らせてくれてありがとう。
さて犬たち。
08

今朝の3ショット。
もう朝は涼しいのですが、でも今朝はそういえば、
なんとなく湿度が高いように感じられました。
犬たちにはまだ涼しいとまではいかないかも。
09

久し振りなので3ショットをもう1枚。
秋の鳥が少ない時期、
ヤマゲラが近くでよく見られるのは嬉しいですね。
また撮れないかなぁ。

ここ2週間ほど、A公園「森の家」の周りで
ヤマゲラの姿をよく見ます。
これは今朝撮影した雌の個体。
ヤマゲラはカラ類のように採餌中に声を出すことはあまりなく、
木をつつく音で気づくか、さもなくば鉢合わせしてしまい、
そこで初めて「キュキュッ」と声を出して飛んで逃げます。
しかし一度に遠くまで飛ぶことはめったになく、
5mから15mくらいの近い木や地面にすぐにとまります。
02

今朝の雌同一個体をもう1枚。
今朝は散策路脇の笹薮に生えた木の下の方で
採餌していたところに僕が通りかかって飛んで逃げた。
10mほど逃げた先で木にとまるのではなく地面に降り、
地面をつついて何かを食べ始めました。
そうなんです、ここ2週間で見られるヤマゲラの
もうひとつの共通項は、いつも地面か木の下の方にいる。
この期間、飛んで逃げた時以外はすべて、
僕の腰より下にいたところを最初に見つけました。
つまり、いつも下の方で何かを食べているということですが、
アリと考えると納得はできます。
アリ多いですからね、今の時期。
今朝はこの1羽以外に笹薮で少し大きめの音がしたので
探しましたが、ヤマゲラがもう1羽いたのか他の鳥かは分からず、
こちらの個体を追いかけているうちにもう一方は見失いました。
03

6日遡って9月5日撮影のこちらは雄の個体。
雄の個体ですが、顔の周りの羽がぽやぽやした感じで、
幼鳥と思われます。
木にとまっていますが、これもやはり最初に鉢合わせした時は、
僕の膝くらいの木の幹にいました。
04

同じ雄の幼鳥と思われる個体。
この時は見ていると木をどんどん登っていきました。
笹薮に生えた木の場合、ある程度上がってくれる方が
撮影はしやすいんですよね。
なんて人間の事情はいいとして、これ、目の周りが特に
不揃いな感じがして、見慣れたヤマゲラ成鳥とは少し違う。
最初の2枚、今朝撮影した雌は成鳥ですが、
となるとこの2羽は親子なのかもしれない。
餌の取り方をお母さんが子供に教えているのかな。
05

さらに6日遡って8月31日の1枚。
雌成鳥、この日からほぼ毎日ヤマゲラを見ていますが、
この時はこの個体の近くにもう1羽いたのを目視しました。
しましたが、飛ぶ後ろ姿を一瞬見ただけで、
頭に赤い部分があるかどうかは確認できず。
親子、母子だったのかな。
もし親子だとすれば、ある程度の期間一緒にいるとして、
でもそろそろお別れの時期を迎えることでしょう。
「森の家」の周りで見られるのももうそろそろ終わりかな。
その間また見て撮れるといいのですが。
06

この期間に見た他のキツツキの写真を2枚ほど。
アカゲラ雄、成鳥。
今年は結局幼鳥を見ることが少なかったので、
7月にお伝えしたように、アカゲラの羽が飛散していた、
その羽の持ち主は幼鳥だったのではないか、
巣立ち後すぐに襲われたのでは、と、考えずにはいられません。
07

クマゲラ雌、同じ時に撮った同一個体の他の写真を見ると、
虹彩が緑がかっていないので成鳥と思われますが、でも、
この時期にはもう幼鳥も緑みが抜けているかもしれず、
なんとも言えないです。
クマゲラは週に1回くらい「森の家」の周りで見ますが、
この前に見た8月下旬の時は雄の今年巣立った幼鳥でした。
それは虹彩の色でわかったのですが、でも、鳴き方も
幼鳥はなんとなくしゃきっとしない感じの声を出します。
あ、せっかくなのにコゲラを撮っていませんでした。
コゲラは声はよく聞きますが、そういえばこの間は、
近くでは見なかったのでした。
みなさん、撮らせてくれてありがとう。
さて犬たち。
08

今朝の3ショット。
もう朝は涼しいのですが、でも今朝はそういえば、
なんとなく湿度が高いように感じられました。
犬たちにはまだ涼しいとまではいかないかも。
09

久し振りなので3ショットをもう1枚。
秋の鳥が少ない時期、
ヤマゲラが近くでよく見られるのは嬉しいですね。
また撮れないかなぁ。
2017年08月14日
ホオジロ幼鳥今年2回目
01

ホオジロの巣立ち幼鳥を見ました。
この写真は8月4日に撮影したものです。
尾羽がまだまともに生えていない、
まさにぽやっぽやといった感じ。
大丈夫かな、不安にさせられもしますね。
ホオジロの親子は今年一度記事にしています。
ホオジロの親子の記事リンク
今回の巣立ち幼鳥は2回目ということになります。
同じつがいが2度繁殖したのでしょうか。
前回の雛は6月20日頃に巣立っていました。
6月と8月に見られた場所は200mほど離れていますが、
同じつがいか、はたまた別のつがいが時期をずらして
営巣したものなのか?
ホオジロの繁殖の様子をウィキペディアから引用します。
(引用者は改行や表記変更など適宜施しています)。
繁殖期は日本では4-7月。
低木の枝や地上に枯れ草を組んで椀状の巣を作り、
一度に3-5個前後の卵を産む。(中略)
卵は白色で、黒褐色の斑点や曲線模様がある。
また、カッコウに托卵されることがある。
抱卵期間は約11日で、雌が抱卵する。
雛は約11日で巣立ちするが、
その後も親から給餌を受け約1ヶ月で親から独立する。
02

同じ日に撮った別の幼鳥、2羽いて運よく両方撮れました。
さて、仮に同じペアが2回繁殖を行ったとの仮定で計算してみます。
1回目の幼鳥が親から独立したと思われるのは7月20日頃。
その後産卵し、11日抱卵し、さらに11日で巣立つとすると、
8月11日頃に巣立ち幼鳥が見られるという計算になります。
ということは8月4日に2回目の巣立ち幼鳥がいたのは
1週間ほど早いということになります。
ということは、別の個体がたまたま近くで時期をずらして営巣?
でも、ホオジロの雄が近くで2羽でいるというのを、
今年はA公園では見ていません、春から夏までずっと。
だとすればやっぱり同じつがいの2回目かな。
幼鳥が独立する前から母鳥が抱卵していたというのは
(ホオジロは雌しか抱卵しない)、給餌は雌雄で行うため
可能性が低そうですが、でも雄だけが給餌することも
ないわけではないかもしれない。
そこはデータを持ち合わせていないので不明です。
巣立ちが早かったという可能性は、尾羽のない幼鳥を見ると
ないわけではないかもしれません。
もうひとつ、2羽いた1回目の幼鳥が巣だって早いうちに
どちらも外敵の獲物となってしまったために、
もう一度繁殖したという可能性はどうでしょう。
ウィキペディアの引用にはありませんが、天候などの理由により
春から秋の間に繁殖を2回以上行うのは、ホオジロに限らず、
シジュウカラなどで知られており、不思議はありません。
傍証といえるかどうか、あくまでも印象程度ですが、そういえば
7月半ばくらいから、1回目の幼鳥の姿を見ていなかった気が。
個体識別をしていなかったので(できないのですが)、
そこは分かりようがない。
でも、とにかく今年はホオジロ巣立ち幼鳥が時期を異にして
2回見られたことに間違いはありません。
03

04

こちら8月7日、幼鳥の3日後に撮影したホオジロ雌成長。
大きな芋虫を捕まえ、さてどうやって食べさせようか、
嘴でつまんで地面に叩きつけていましたが、
僕が見ている間の5分くらいではらちが明かないようでした。
最後まで見ていられればよかったのですが、そうもゆかず。
この芋虫はあの3日前に見た幼鳥に食べさせるのかな。
など、いろいろ考えるのが自然観察の楽しいところです。
撮らせてくれてありがとう。
さて犬たち。
05

最近は庭の椅子との取り合わせて撮るのがテーマ。
06

ここのところ記事の間隔があいているので、
今日は特別にもう1枚。
なお、「ペルセウス座流星群」、
今年は天気が悪くて見られませんでした、残念。
そして今年は本格的な夏が、ひとあし早く
7月上旬に来ただけで夏は終わりました。

ホオジロの巣立ち幼鳥を見ました。
この写真は8月4日に撮影したものです。
尾羽がまだまともに生えていない、
まさにぽやっぽやといった感じ。
大丈夫かな、不安にさせられもしますね。
ホオジロの親子は今年一度記事にしています。
ホオジロの親子の記事リンク
今回の巣立ち幼鳥は2回目ということになります。
同じつがいが2度繁殖したのでしょうか。
前回の雛は6月20日頃に巣立っていました。
6月と8月に見られた場所は200mほど離れていますが、
同じつがいか、はたまた別のつがいが時期をずらして
営巣したものなのか?
ホオジロの繁殖の様子をウィキペディアから引用します。
(引用者は改行や表記変更など適宜施しています)。
繁殖期は日本では4-7月。
低木の枝や地上に枯れ草を組んで椀状の巣を作り、
一度に3-5個前後の卵を産む。(中略)
卵は白色で、黒褐色の斑点や曲線模様がある。
また、カッコウに托卵されることがある。
抱卵期間は約11日で、雌が抱卵する。
雛は約11日で巣立ちするが、
その後も親から給餌を受け約1ヶ月で親から独立する。
02

同じ日に撮った別の幼鳥、2羽いて運よく両方撮れました。
さて、仮に同じペアが2回繁殖を行ったとの仮定で計算してみます。
1回目の幼鳥が親から独立したと思われるのは7月20日頃。
その後産卵し、11日抱卵し、さらに11日で巣立つとすると、
8月11日頃に巣立ち幼鳥が見られるという計算になります。
ということは8月4日に2回目の巣立ち幼鳥がいたのは
1週間ほど早いということになります。
ということは、別の個体がたまたま近くで時期をずらして営巣?
でも、ホオジロの雄が近くで2羽でいるというのを、
今年はA公園では見ていません、春から夏までずっと。
だとすればやっぱり同じつがいの2回目かな。
幼鳥が独立する前から母鳥が抱卵していたというのは
(ホオジロは雌しか抱卵しない)、給餌は雌雄で行うため
可能性が低そうですが、でも雄だけが給餌することも
ないわけではないかもしれない。
そこはデータを持ち合わせていないので不明です。
巣立ちが早かったという可能性は、尾羽のない幼鳥を見ると
ないわけではないかもしれません。
もうひとつ、2羽いた1回目の幼鳥が巣だって早いうちに
どちらも外敵の獲物となってしまったために、
もう一度繁殖したという可能性はどうでしょう。
ウィキペディアの引用にはありませんが、天候などの理由により
春から秋の間に繁殖を2回以上行うのは、ホオジロに限らず、
シジュウカラなどで知られており、不思議はありません。
傍証といえるかどうか、あくまでも印象程度ですが、そういえば
7月半ばくらいから、1回目の幼鳥の姿を見ていなかった気が。
個体識別をしていなかったので(できないのですが)、
そこは分かりようがない。
でも、とにかく今年はホオジロ巣立ち幼鳥が時期を異にして
2回見られたことに間違いはありません。
03

04

こちら8月7日、幼鳥の3日後に撮影したホオジロ雌成長。
大きな芋虫を捕まえ、さてどうやって食べさせようか、
嘴でつまんで地面に叩きつけていましたが、
僕が見ている間の5分くらいではらちが明かないようでした。
最後まで見ていられればよかったのですが、そうもゆかず。
この芋虫はあの3日前に見た幼鳥に食べさせるのかな。
など、いろいろ考えるのが自然観察の楽しいところです。
撮らせてくれてありがとう。
さて犬たち。
05

最近は庭の椅子との取り合わせて撮るのがテーマ。
06

ここのところ記事の間隔があいているので、
今日は特別にもう1枚。
なお、「ペルセウス座流星群」、
今年は天気が悪くて見られませんでした、残念。
そして今年は本格的な夏が、ひとあし早く
7月上旬に来ただけで夏は終わりました。
2017年07月21日
オオルリに悪いことしたかな・・・
01

オオルリ♂
A公園で久し振りに見ることができ、撮れました。
しかし、僕がいるあいだずっと警戒して囀りしていました。
普段より短く単調な鳴き声「フィフィーフィーフィージジツ」、と。
悪いことしたかな。
でも撮らせてくれてありがとう。
この後すぐにその場を去りました。
02

犬たち3ショット。
今年は庭にはオオルリ来なかったそういえば。

オオルリ♂
A公園で久し振りに見ることができ、撮れました。
しかし、僕がいるあいだずっと警戒して囀りしていました。
普段より短く単調な鳴き声「フィフィーフィーフィージジツ」、と。
悪いことしたかな。
でも撮らせてくれてありがとう。
この後すぐにその場を去りました。
02

犬たち3ショット。
今年は庭にはオオルリ来なかったそういえば。
2017年07月12日
コヨシキリは一生懸命歌う
01

コヨシキリが鳴いている草原に鳥見に行きました。
A公園では見られないコヨシキリ、実は大ファンなんです。
低い木にとまって囀りしていました。
02

コヨシキリは小さい体で大きな口を開けて、
とにかく一生懸命歌っているように見えるのが、
なんともかわいい、かわいすぎる!
だから大ファンなんです。
今年もあと何回か会いに行きたい、
撮らせてくれてありがとう。
03

その日の朝の犬たち。
真夏日になったけれど曇っていて、
風が意外と涼しい日でした。
近年は暑くなった暑くなったと言われていますが、
風が涼しいのはやっぱり北海道と思います。

コヨシキリが鳴いている草原に鳥見に行きました。
A公園では見られないコヨシキリ、実は大ファンなんです。
低い木にとまって囀りしていました。
02

コヨシキリは小さい体で大きな口を開けて、
とにかく一生懸命歌っているように見えるのが、
なんともかわいい、かわいすぎる!
だから大ファンなんです。
今年もあと何回か会いに行きたい、
撮らせてくれてありがとう。
03

その日の朝の犬たち。
真夏日になったけれど曇っていて、
風が意外と涼しい日でした。
近年は暑くなった暑くなったと言われていますが、
風が涼しいのはやっぱり北海道と思います。
2017年07月10日
ホオジロの親子
01T

5月に「優しいホオジロ」と題して(記事こちら)、
ホオジロが巣造りをしていた様子を報告しました。
繁殖は成功したようで、巣に幼鳥が2羽いるのを確認していました。
幼鳥は6月20日頃に巣立ちました。
地面に営巣するホオジロは巣が外敵に狙われやすいため、
卵からかえって10日ほどでもう幼鳥が巣立ち、
親子で巣から離れます。
先日、その親子を見かけました。
写真01Tに3羽写っていますが、左が雌の親、
あとの2羽は幼鳥です。
雄の親も近くにいて一緒に行動していました、ご安心を。
なお、この記事のホオジロの写真はすべてトリミングしています。
02T

03T

04T

口の中が赤くて嘴が黄色く大きい。
まだまだ幼鳥ですね。
一生懸命餌をねだっていたのがかわいい。
ホオジロは、巣立つのが早い代わりに、巣を出て暫くは
親が子に餌を上げて大きく育てていくようです。
05

これがホオジロの巣。
草で作ったきれいなお椀型の巣です。
完全に戻って来なくなったのを確認して撮影しました。
人が結構通る場所に営巣していて驚きました。
よく見つからなかったなあと。
でも、巣に入る時は慎重に人が見ていない瞬間を
狙うほど用心深かったし、そもそもほとんどの人が
そんなところに巣があるとは思わず素通りしたことでしょう。
06T

幼鳥。
顔の隈取がまだなく、一見ホオジロとは分からないですね。
これより少し育った8月のホオジロの幼鳥は見たことありますが、
ここまで若いのは初めて見ました。
もう少し、外で餌をもらう幼鳥の姿が見られるかな。
06

ホオジロがより身近に感じられた今年のA公園でした。
07

最後は昨日の犬たち3ショット。
日差しが強いと写真もきりっとして、ないか、こいつらは(笑)。

5月に「優しいホオジロ」と題して(記事こちら)、
ホオジロが巣造りをしていた様子を報告しました。
繁殖は成功したようで、巣に幼鳥が2羽いるのを確認していました。
幼鳥は6月20日頃に巣立ちました。
地面に営巣するホオジロは巣が外敵に狙われやすいため、
卵からかえって10日ほどでもう幼鳥が巣立ち、
親子で巣から離れます。
先日、その親子を見かけました。
写真01Tに3羽写っていますが、左が雌の親、
あとの2羽は幼鳥です。
雄の親も近くにいて一緒に行動していました、ご安心を。
なお、この記事のホオジロの写真はすべてトリミングしています。
02T

03T

04T

口の中が赤くて嘴が黄色く大きい。
まだまだ幼鳥ですね。
一生懸命餌をねだっていたのがかわいい。
ホオジロは、巣立つのが早い代わりに、巣を出て暫くは
親が子に餌を上げて大きく育てていくようです。
05

これがホオジロの巣。
草で作ったきれいなお椀型の巣です。
完全に戻って来なくなったのを確認して撮影しました。
人が結構通る場所に営巣していて驚きました。
よく見つからなかったなあと。
でも、巣に入る時は慎重に人が見ていない瞬間を
狙うほど用心深かったし、そもそもほとんどの人が
そんなところに巣があるとは思わず素通りしたことでしょう。
06T

幼鳥。
顔の隈取がまだなく、一見ホオジロとは分からないですね。
これより少し育った8月のホオジロの幼鳥は見たことありますが、
ここまで若いのは初めて見ました。
もう少し、外で餌をもらう幼鳥の姿が見られるかな。
06

ホオジロがより身近に感じられた今年のA公園でした。
07

最後は昨日の犬たち3ショット。
日差しが強いと写真もきりっとして、ないか、こいつらは(笑)。
2017年07月02日
2017年6月の鳥残し
01

2017年6月の鳥残し。
今回は、というかこれからもですが、構成上、
記事にしたものもなるべく取り上げてたいと思います。
だから「鳥まとめ」という方が適切かもしれないですが、
「鳥残し」という言葉が気に入っているのでタイトルは変えません。
2017年6月2日
クマゲラ
雄の個体、この頃雄雌交互によく現れるようになりましたが、
後から思えばそれほど遠くない場所に巣があって、
雛に餌をせっせと運んでいた、ということなのでしょう。
02

2017年6月3日
キビタキ
キビタキは今年も普通にいます。
が、昨年は数も多く近寄れる機会も多かったので、
今年は普通くらいにしか撮れていません。
03

2017年6月10日
ヤマガラ
シルエットクイズ、私は誰?
なあんて、ヤマガラともう書いてありますが、
だけど書かないと影になっていて分からないですね。
捕まえた昆虫の翅がシルエットでは強調されています。
04

2017年6月11日
ハシブトガラス
エゾヤマザクラの実を食べに来た。
しかし、この方たちが大挙して来るようになってから、
この木にアオバトがあまり来なくなった。
結果、アオバトはまともに撮れなかった・・・
05

2017年6月11日
ヒヨドリ
ヒヨドリは意地悪で、アオバトがやって来て実を食べると、
少しして大声で飛んで来てアオバトを追い払って食べていました。
でも、アオバトも自分より小さいヒヨはあまり気にしていないのか、
何度もやって来ていました。
ブトが大挙して訪れるまでは・・・
06

2017年6月12日
エナガ(亜種シマエナガ)
この日シマエナガ幼鳥が巣立ち、親子数羽の群れが
西の方から飛んで来て東に去りました。
内地の亜種エナガのように目に黒い帯がある
亜種シマエナガ幼鳥を、A公園では初めて撮れました。
07

2017年6月14日
ヤマゲラ
割と開けた道沿いの倒木で採餌するヤマゲラ。
この写真では分からないですが雄の個体であることを確認。
しかし、ちょっと遠すぎた、残念。
08

2017年6月15日
ツバメ
道の駅ニセコのツバメの雛。
もう無事に巣立ったかな。
09

2017年6月16日
ハシブトガラス
たまに無性に鳥を撮りたくなる時がある、何でもいいから・・・
10

2017年6月20日
アカゲラ
雄の個体、餌を採りに来ていたようですが、
ホップした瞬間のこの写真、楽しそうに見えませんか?
11

2017年6月23日
ゴジュウカラ
ゴジュウカラは5月下旬から6月中旬まで、
それまではいつでも見られたことがまるで嘘のように、
見かける機会がめっきり減ります。
しかしご安心あれ、幼鳥が巣立ったと思われる6月下旬から、
また普通に見られるようになります。
12

2017年6月23日
オオアカゲラ
同一個体かどうか分からないですが、雌のオオアカゲラが
今年は6月にもよく見られました。
これで今月コゲラが撮れていればA公園に通常いるキツツキ科
5種類制覇だったのですが・・・
シングルヒットを打てなくてサイクルヒットを逃した気分です(笑)。
13

2017年6月25日
クマゲラ
雄、また来ていました、まったく同じ桜の木に。
近くには巣立ち幼鳥もいた模様ですが、
この時は撮影できませんでした。
14

2017年6月29日
アオサギ
早朝から屯田遊水地に行ってきました。
ここから5枚は屯田遊水地で撮った写真で終わります。
アオサギは警戒心が強くすぐに飛び立ってしまいますが、
この時は間にヨシがあったせいか警戒心が薄く、
オリンパスOM-D+FD500mmF4.5Lセットで
画面からはみ出る程の大きさで撮れました。
15

2017年6月29日
アオジ
アオジはA公園でもきわめてよく見られますが、
見えやすい電線で囀る雄を見ることはほぼないですね。
そもそもA公園内には電線がないのです。
16

2017年6月29日
アリスイ
アリスイもA公園では数年に1回見られるというくらい。
そんな鳥が普通に見られるのがここの魅力。
17

2017年6月29日
オオヨシキリ
着いて最初に大声で迎えてくれたのが行々子様。
2羽いたと思われ、いる間ずっと「ギョギョシ」と聞こえてきました。
18

2017年6月29日
コヨシキリ
そして大小揃い踏み。
コヨシキリは一生懸命鳴いているように感じられるのが
とってもかわいらしい鳥ですね。
でも、声は結構オオヨシキリに似ていて、
ソフトにした「ギョギョシ」といった感じです。
19

最後は2017年6月30日の3ショット。
今月はレギュラーのハシブトガラを撮れませんでした。
今年は近いところに営巣しなかったのかな、育雛していると
思われる期間は姿を見ること自体少なかった。
ハシブトガラでそういうことは初めてじゃないかな。
でもそろそろまた見る機会が増えてきました、ご安心ください。
まあ、レギュラーにも時々休息は必要でしょうからね。

2017年6月の鳥残し。
今回は、というかこれからもですが、構成上、
記事にしたものもなるべく取り上げてたいと思います。
だから「鳥まとめ」という方が適切かもしれないですが、
「鳥残し」という言葉が気に入っているのでタイトルは変えません。
2017年6月2日
クマゲラ
雄の個体、この頃雄雌交互によく現れるようになりましたが、
後から思えばそれほど遠くない場所に巣があって、
雛に餌をせっせと運んでいた、ということなのでしょう。
02

2017年6月3日
キビタキ
キビタキは今年も普通にいます。
が、昨年は数も多く近寄れる機会も多かったので、
今年は普通くらいにしか撮れていません。
03

2017年6月10日
ヤマガラ
シルエットクイズ、私は誰?
なあんて、ヤマガラともう書いてありますが、
だけど書かないと影になっていて分からないですね。
捕まえた昆虫の翅がシルエットでは強調されています。
04

2017年6月11日
ハシブトガラス
エゾヤマザクラの実を食べに来た。
しかし、この方たちが大挙して来るようになってから、
この木にアオバトがあまり来なくなった。
結果、アオバトはまともに撮れなかった・・・
05

2017年6月11日
ヒヨドリ
ヒヨドリは意地悪で、アオバトがやって来て実を食べると、
少しして大声で飛んで来てアオバトを追い払って食べていました。
でも、アオバトも自分より小さいヒヨはあまり気にしていないのか、
何度もやって来ていました。
ブトが大挙して訪れるまでは・・・
06

2017年6月12日
エナガ(亜種シマエナガ)
この日シマエナガ幼鳥が巣立ち、親子数羽の群れが
西の方から飛んで来て東に去りました。
内地の亜種エナガのように目に黒い帯がある
亜種シマエナガ幼鳥を、A公園では初めて撮れました。
07

2017年6月14日
ヤマゲラ
割と開けた道沿いの倒木で採餌するヤマゲラ。
この写真では分からないですが雄の個体であることを確認。
しかし、ちょっと遠すぎた、残念。
08

2017年6月15日
ツバメ
道の駅ニセコのツバメの雛。
もう無事に巣立ったかな。
09

2017年6月16日
ハシブトガラス
たまに無性に鳥を撮りたくなる時がある、何でもいいから・・・
10

2017年6月20日
アカゲラ
雄の個体、餌を採りに来ていたようですが、
ホップした瞬間のこの写真、楽しそうに見えませんか?
11

2017年6月23日
ゴジュウカラ
ゴジュウカラは5月下旬から6月中旬まで、
それまではいつでも見られたことがまるで嘘のように、
見かける機会がめっきり減ります。
しかしご安心あれ、幼鳥が巣立ったと思われる6月下旬から、
また普通に見られるようになります。
12

2017年6月23日
オオアカゲラ
同一個体かどうか分からないですが、雌のオオアカゲラが
今年は6月にもよく見られました。
これで今月コゲラが撮れていればA公園に通常いるキツツキ科
5種類制覇だったのですが・・・
シングルヒットを打てなくてサイクルヒットを逃した気分です(笑)。
13

2017年6月25日
クマゲラ
雄、また来ていました、まったく同じ桜の木に。
近くには巣立ち幼鳥もいた模様ですが、
この時は撮影できませんでした。
14

2017年6月29日
アオサギ
早朝から屯田遊水地に行ってきました。
ここから5枚は屯田遊水地で撮った写真で終わります。
アオサギは警戒心が強くすぐに飛び立ってしまいますが、
この時は間にヨシがあったせいか警戒心が薄く、
オリンパスOM-D+FD500mmF4.5Lセットで
画面からはみ出る程の大きさで撮れました。
15

2017年6月29日
アオジ
アオジはA公園でもきわめてよく見られますが、
見えやすい電線で囀る雄を見ることはほぼないですね。
そもそもA公園内には電線がないのです。
16

2017年6月29日
アリスイ
アリスイもA公園では数年に1回見られるというくらい。
そんな鳥が普通に見られるのがここの魅力。
17

2017年6月29日
オオヨシキリ
着いて最初に大声で迎えてくれたのが行々子様。
2羽いたと思われ、いる間ずっと「ギョギョシ」と聞こえてきました。
18

2017年6月29日
コヨシキリ
そして大小揃い踏み。
コヨシキリは一生懸命鳴いているように感じられるのが
とってもかわいらしい鳥ですね。
でも、声は結構オオヨシキリに似ていて、
ソフトにした「ギョギョシ」といった感じです。
19

最後は2017年6月30日の3ショット。
今月はレギュラーのハシブトガラを撮れませんでした。
今年は近いところに営巣しなかったのかな、育雛していると
思われる期間は姿を見ること自体少なかった。
ハシブトガラでそういうことは初めてじゃないかな。
でもそろそろまた見る機会が増えてきました、ご安心ください。
まあ、レギュラーにも時々休息は必要でしょうからね。
2017年06月26日
雨上がりのクマゲラ
01

朝から時に土砂降りの雨が続いた昨日。
夕方、雨がようやく上がったところで、
クマゲラが現れました。
すぐ近くにいて、こちらが見えなかったのか
「キョッーン」とひと声鳴きましたが、
その声がとっても大きくて驚きました。
桜の枯れ枝をつついて餌を探しているところを、
木に隠れながら近寄って5mで撮影成功。
撮ってすぐに後退してその場を去りました。
撮らせてくれてありがとう。
02

その後のA公園。
ポーラも歩かなきゃね。

朝から時に土砂降りの雨が続いた昨日。
夕方、雨がようやく上がったところで、
クマゲラが現れました。
すぐ近くにいて、こちらが見えなかったのか
「キョッーン」とひと声鳴きましたが、
その声がとっても大きくて驚きました。
桜の枯れ枝をつついて餌を探しているところを、
木に隠れながら近寄って5mで撮影成功。
撮ってすぐに後退してその場を去りました。
撮らせてくれてありがとう。
02

その後のA公園。
ポーラも歩かなきゃね。
2017年06月19日
ニセコのツバメの巣
01

先日行った道の駅ニセコにツバメの巣が幾つかありました。
はじめに、野鳥の巣を撮ってネットで公開するのは
マナーとしてどうかという問題はありますが、
ツバメの場合は人の生活している場所に巣を作るものであり、
過度のストレスを与えなければ大丈夫と思われるので、
今回は敢えて記事にすることにしました。
衆目の下に置かれてむしろ守られる部分もあるでしょうから。
道の駅ニセコは一部が屋根が張り出した回廊のようになっていて、
軒下にお店が何軒か連なっています。
ツバメはそこに営巣していました。
戸が閉まる場所ではないし、トイレの上でもないので
夜は静かになるのでなかなかいい場所かもしれません。
待っていると、親鳥が餌をくわえて飛んで来ました。
雛の大きな口はかわいいですね。
02

床にはご親切ご丁寧にもこのような貼り紙が。
ツバメの巣の場合は食べられるわけでもないし、
よっぽどの悪意がある人ではない限り、
そっと見守って楽しんでくれるでしょうね。
03

巣の下には糞受けの傘が逆さに吊り下げられています。
人が利用する施設だから当然のことながら、
人への配慮もあるわけですね。
しかっし。
燕でビニール傘といえば・・・
この時頭の中で「東京音頭」が鳴っていました(笑)。
04

♪ あ~らよぉいよい
失礼いたしました。
05

最後お口直しに犬たちの3ショット。
うちはスズメは巣を作ったことはありますが、ツバメはないですね。
そもそも札幌にはツバメはいません、通過だけです。
しかしそのうち、札幌でも営巣するようになるかもしれません。

先日行った道の駅ニセコにツバメの巣が幾つかありました。
はじめに、野鳥の巣を撮ってネットで公開するのは
マナーとしてどうかという問題はありますが、
ツバメの場合は人の生活している場所に巣を作るものであり、
過度のストレスを与えなければ大丈夫と思われるので、
今回は敢えて記事にすることにしました。
衆目の下に置かれてむしろ守られる部分もあるでしょうから。
道の駅ニセコは一部が屋根が張り出した回廊のようになっていて、
軒下にお店が何軒か連なっています。
ツバメはそこに営巣していました。
戸が閉まる場所ではないし、トイレの上でもないので
夜は静かになるのでなかなかいい場所かもしれません。
待っていると、親鳥が餌をくわえて飛んで来ました。
雛の大きな口はかわいいですね。
02

床にはご親切ご丁寧にもこのような貼り紙が。
ツバメの巣の場合は食べられるわけでもないし、
よっぽどの悪意がある人ではない限り、
そっと見守って楽しんでくれるでしょうね。
03

巣の下には糞受けの傘が逆さに吊り下げられています。
人が利用する施設だから当然のことながら、
人への配慮もあるわけですね。
しかっし。
燕でビニール傘といえば・・・
この時頭の中で「東京音頭」が鳴っていました(笑)。
04

♪ あ~らよぉいよい
失礼いたしました。
05

最後お口直しに犬たちの3ショット。
うちはスズメは巣を作ったことはありますが、ツバメはないですね。
そもそも札幌にはツバメはいません、通過だけです。
しかしそのうち、札幌でも営巣するようになるかもしれません。



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト


























