2016年10月08日
Woman ジョン・レノン
01

◎Woman
▼ウーマン
☆John Lennon
★ジョン・レノン
released in 1980
10月9日はジョン・レノンの誕生日
1940年生まれ
今年で76歳
ジョンおめでとう!
この記事が上がった時点ではまだ10月8日ですが、
上がっている間に10月9日になる、ということで。
ジョン・レノンのWomanは、
僕がビートルズ以外で初めてシングルレコードを買った曲。
メンバーのソロだけどビートルズではない。
中学2年、1981年の秋から冬、1周忌の少し前のことだな、
ビートルズのレコードもそれまでLP3枚とシングル数枚しか
持っていなかった、ごくごく初期の頃に買った1枚になります。
ラジオで聴いて気に入って、近くのレコード屋で買いました。
当時は街まで行かなくても近くにレコード屋があったんです。
「追悼盤」の文字が今でも悲しいですね。
買ってすぐに歌詞を読んで覚えて歌いました。
"thoughtlessness"なんて中2には難しい単語でしたが、
でもまあ全体としては難しい内容ではありませんでした。
高校に入り、街にレコードを買いに行った時のこと。
立ち寄った書店で洋書のジョン・レノンの楽譜集を見つけ、
他に買おうと思っていたLP1枚を先送りにして買いました。
もちろんWomanの楽譜もあり、コード進行を覚えました。
キィが変ホ長調、E♭なんですよね。
この包み込むような優しさ、やはり音楽の調には独特の響きがある
ということが分かってきた頃だったと今にして思います。
♭だから当然カポをしない限りはバレーコードで弾き続ける上に、
コードチェンジが多くて難儀な曲でしたね。
おまけに、イントロの最初の音、E♭を抑えた上で小指で
2弦9フレットを抑えるE♭sus4、これが大変だった。
でも、弾けた時の嬉しさはまた格別、そんな曲でした。
音楽的にいえばアール・スリックの優しくもきらびやかなギターと、
トニー・レヴィンの包み込むようなベースが、
ジョンの耳元で囁くような優しい歌声に呼応していますね。
ここでいつもの『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』より。
***
これはヨーコと、ある意味ですべての女性に対する曲だ。
ぼくは女性とのつきあいの歴史は、とてもマッチョ(タフガイ的)で、
とてもくだらなかった。
概してひどく神経質で落ち着きがないくせに
攻撃的にふるまう典型的な男のタイプだったから、
とても貧しいものだった。
ほら、そういタイプの男は女性的な部分を隠そうとするんだけど、
ぼくには今でもそんなところがある。
でも、ぼくは今、優しくふるまっても構わないのだということを知った。
そっちの自分でいた方がくつろげるんだから。
心が荒んだ時、昔ならカウボーイ・ブーツを履こうとしていたけど、
今ならスニーカーを履くだろう。
それでいいんだ。
この曲は多分に自明な曲だね。
***
この本はこの曲を聴く前に買ってはいたのですが、
曲を知らないのに読んでも頭に入るわけがない、
買ってすぐには読まなかった。
じゃあなぜ買ったんだろうというのは僕自身不思議で、
ビートルズが好きだったというよりは、
有名なロックスターが射殺されたという社会的「事件」に
非常に大きなショックを受けていたのだと思う。
Womanを聴いてこの本を読んだところ、
曲を聴いて歌詞を読んで感じたことあまりにもそのままで
驚いた記憶があります。
音楽って伝える力がすごいんだな、と。
02

中学時代にビートルズを一緒に熱心に聴いていた
今は栃木にいる親友Oもこの曲が好きでしたが、
いつしか僕とOはこんな話をするようになりました。
「先に結婚する方が結婚式でこの曲を使おう」
それから17年後、Oが先に結婚、式でOはもちろん
この曲を使うつもりでした。
しかし、式場のホテルのミスで使われなかった。
ホテルはその他不手際が多く、Oも残念がっていました。
ちなみに、Oには結婚式で使う曲の候補を選んでほしいと頼まれ、
当時まだカセットテープの90分1本分録音して送りました。
その中でOが気に入って実際に使った曲で覚えているのは
So Much In Love アート・ガーファンクル
You're Still The One シャナイア・トウェイン
You Were Meant For Me ジュエル
あと2曲ほどあったのですが忘れてしまった。
ウェディングケーキの場面で使われた曲はO自身の希望で
Open Arms ジャーニー
でした。
式では使われなかったものの、僕はその時からこのWomanを
熱心には聴かなくなりました。
それまではジョンで好きなソロの曲を3曲挙げろと言われれば
必ず入れていたくらいでしたから。
先にOが結婚して気持ちが切れたのでしょうかね。
しかし、今は曲への情熱が戻ってきた。
毎日口ずさんでいます。
歌詞をみてみましょう。
***
(空の半分に宛てて)
Woman どうもうまく言えないんだ
浅はかな考えから気持ちがないまぜいなってしまって
結局、僕は一生君に借りがあるんだよ
Woman でもなんとか言葉で表してみたい
僕の心の中の愛情と感謝の念をね
君は成功することの意味を見せてくれているからさ
Ooh、そうだよね
Woman 君は分かってくれると思う
僕は大人に見えても心の中は子供だってことをね
覚えておいておくれ、僕の人生は君の手の中にあるんだよ
Woman 君の心のそばまで抱いておくれ
どれだけの距離があろうともふたりは離れ離れにはならない
そして僕たちは星に刻まれるんだ
Ooh、そうだよね
Woman どうかじっくりと話させておくれ
僕は決して君を悲しませたり苦しませたりはしないよ
そして何度も何度も何度も言わせてほしいんだ
I love you
これからもずっと愛しているよ
***
"Woman"はヨーコさんに呼びかけているのだと思いますが、
ここではハミングと同じく感覚的な言葉と捉え、
敢えて訳さずそのまま載せています。
ぐだぐだと理屈っぽく話しつつもったいつけて、
まるで駄々をこねる子供のよう。
でも結局言うことはひとつしかない。
I love you
転調する前まではサビでハミングと"well, well"しか言わない、
それも印象的な上に、最後に初めてI love youというなんて。
I Love Youと歌う曲は世の中に何百万とあれど、
I love youの言い方、そこまでの流れはこの曲が最高じゃないかと。
考えようによってはIn My Lifeと同じですね。
In My Lifeは「ノスタルジー」と言われますが、歌詞を読むと、
昔のことを愛してはいるけれど今は君がいちばん好きなんだ、
ただそれだけを言いたい、でも言うのに前振りが長い、というわけ。
それがジョン・レノンという人なのでしょうね。
歌詞の中で、
"Please remember my life is in your hands"
「覚えておいておくれ、僕の人生はすべて君の手の中にあるんだ」
というくだり、まあ母のように慕うオノ・ヨーコさんに忠誠を誓っていた
ジョンらしいといえばそうですが、でもこれは言い過ぎじゃないかい、
男女の仲ってそこまで無防備でいいの、と若い頃は思ったものです。
僕の心は子供だとか、一生借りがあるとか、この曲の歌詞の基本は
そこにあって、要するにジョンは甘えているわけですね、はい(笑)。
僕がいちばん好きなくだりはこれ
"However distance don't keep us apart
After all it is written in the stars"
「どれだけ離れていても僕たちの心を引き離すものはない
そして僕たちの名は星に刻まれるんだ」
星座の星は実際は近くにあるわけではない。
距離も時間も離れているけれど、ひとつの星座として
ずっと一緒にいる、と、僕は解釈しています。
死んでも一緒、という意味でもある。
クイーンというかフレディ・マーキュリーのMade In Heavenも
最後"Written in the stars"と歌っていますが、
ジョンのこのくだりが「死んでも一緒」と理解したのは、
クイーンのMade In Heavenを聴いた時のことでした。
若い頃は当然のことながら、ここで歌われているようなことを、
言葉の意味として頭では理解できても実感は伴わない。
伴うような年齢になる頃には僕の気持が冷めていた。
それが今、実感として分かるようになってきました。
ここで歌われているすべての言葉をその通りに感じられる。
ねえジョン、これってまさに俺のことじゃない、と。
After all
僕は、一生のパートナーとなる女性と出会うことができたのです。

◎Woman
▼ウーマン
☆John Lennon
★ジョン・レノン
released in 1980
10月9日はジョン・レノンの誕生日
1940年生まれ
今年で76歳
ジョンおめでとう!
この記事が上がった時点ではまだ10月8日ですが、
上がっている間に10月9日になる、ということで。
ジョン・レノンのWomanは、
僕がビートルズ以外で初めてシングルレコードを買った曲。
メンバーのソロだけどビートルズではない。
中学2年、1981年の秋から冬、1周忌の少し前のことだな、
ビートルズのレコードもそれまでLP3枚とシングル数枚しか
持っていなかった、ごくごく初期の頃に買った1枚になります。
ラジオで聴いて気に入って、近くのレコード屋で買いました。
当時は街まで行かなくても近くにレコード屋があったんです。
「追悼盤」の文字が今でも悲しいですね。
買ってすぐに歌詞を読んで覚えて歌いました。
"thoughtlessness"なんて中2には難しい単語でしたが、
でもまあ全体としては難しい内容ではありませんでした。
高校に入り、街にレコードを買いに行った時のこと。
立ち寄った書店で洋書のジョン・レノンの楽譜集を見つけ、
他に買おうと思っていたLP1枚を先送りにして買いました。
もちろんWomanの楽譜もあり、コード進行を覚えました。
キィが変ホ長調、E♭なんですよね。
この包み込むような優しさ、やはり音楽の調には独特の響きがある
ということが分かってきた頃だったと今にして思います。
♭だから当然カポをしない限りはバレーコードで弾き続ける上に、
コードチェンジが多くて難儀な曲でしたね。
おまけに、イントロの最初の音、E♭を抑えた上で小指で
2弦9フレットを抑えるE♭sus4、これが大変だった。
でも、弾けた時の嬉しさはまた格別、そんな曲でした。
音楽的にいえばアール・スリックの優しくもきらびやかなギターと、
トニー・レヴィンの包み込むようなベースが、
ジョンの耳元で囁くような優しい歌声に呼応していますね。
ここでいつもの『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』より。
***
これはヨーコと、ある意味ですべての女性に対する曲だ。
ぼくは女性とのつきあいの歴史は、とてもマッチョ(タフガイ的)で、
とてもくだらなかった。
概してひどく神経質で落ち着きがないくせに
攻撃的にふるまう典型的な男のタイプだったから、
とても貧しいものだった。
ほら、そういタイプの男は女性的な部分を隠そうとするんだけど、
ぼくには今でもそんなところがある。
でも、ぼくは今、優しくふるまっても構わないのだということを知った。
そっちの自分でいた方がくつろげるんだから。
心が荒んだ時、昔ならカウボーイ・ブーツを履こうとしていたけど、
今ならスニーカーを履くだろう。
それでいいんだ。
この曲は多分に自明な曲だね。
***
この本はこの曲を聴く前に買ってはいたのですが、
曲を知らないのに読んでも頭に入るわけがない、
買ってすぐには読まなかった。
じゃあなぜ買ったんだろうというのは僕自身不思議で、
ビートルズが好きだったというよりは、
有名なロックスターが射殺されたという社会的「事件」に
非常に大きなショックを受けていたのだと思う。
Womanを聴いてこの本を読んだところ、
曲を聴いて歌詞を読んで感じたことあまりにもそのままで
驚いた記憶があります。
音楽って伝える力がすごいんだな、と。
02

中学時代にビートルズを一緒に熱心に聴いていた
今は栃木にいる親友Oもこの曲が好きでしたが、
いつしか僕とOはこんな話をするようになりました。
「先に結婚する方が結婚式でこの曲を使おう」
それから17年後、Oが先に結婚、式でOはもちろん
この曲を使うつもりでした。
しかし、式場のホテルのミスで使われなかった。
ホテルはその他不手際が多く、Oも残念がっていました。
ちなみに、Oには結婚式で使う曲の候補を選んでほしいと頼まれ、
当時まだカセットテープの90分1本分録音して送りました。
その中でOが気に入って実際に使った曲で覚えているのは
So Much In Love アート・ガーファンクル
You're Still The One シャナイア・トウェイン
You Were Meant For Me ジュエル
あと2曲ほどあったのですが忘れてしまった。
ウェディングケーキの場面で使われた曲はO自身の希望で
Open Arms ジャーニー
でした。
式では使われなかったものの、僕はその時からこのWomanを
熱心には聴かなくなりました。
それまではジョンで好きなソロの曲を3曲挙げろと言われれば
必ず入れていたくらいでしたから。
先にOが結婚して気持ちが切れたのでしょうかね。
しかし、今は曲への情熱が戻ってきた。
毎日口ずさんでいます。
歌詞をみてみましょう。
***
(空の半分に宛てて)
Woman どうもうまく言えないんだ
浅はかな考えから気持ちがないまぜいなってしまって
結局、僕は一生君に借りがあるんだよ
Woman でもなんとか言葉で表してみたい
僕の心の中の愛情と感謝の念をね
君は成功することの意味を見せてくれているからさ
Ooh、そうだよね
Woman 君は分かってくれると思う
僕は大人に見えても心の中は子供だってことをね
覚えておいておくれ、僕の人生は君の手の中にあるんだよ
Woman 君の心のそばまで抱いておくれ
どれだけの距離があろうともふたりは離れ離れにはならない
そして僕たちは星に刻まれるんだ
Ooh、そうだよね
Woman どうかじっくりと話させておくれ
僕は決して君を悲しませたり苦しませたりはしないよ
そして何度も何度も何度も言わせてほしいんだ
I love you
これからもずっと愛しているよ
***
"Woman"はヨーコさんに呼びかけているのだと思いますが、
ここではハミングと同じく感覚的な言葉と捉え、
敢えて訳さずそのまま載せています。
ぐだぐだと理屈っぽく話しつつもったいつけて、
まるで駄々をこねる子供のよう。
でも結局言うことはひとつしかない。
I love you
転調する前まではサビでハミングと"well, well"しか言わない、
それも印象的な上に、最後に初めてI love youというなんて。
I Love Youと歌う曲は世の中に何百万とあれど、
I love youの言い方、そこまでの流れはこの曲が最高じゃないかと。
考えようによってはIn My Lifeと同じですね。
In My Lifeは「ノスタルジー」と言われますが、歌詞を読むと、
昔のことを愛してはいるけれど今は君がいちばん好きなんだ、
ただそれだけを言いたい、でも言うのに前振りが長い、というわけ。
それがジョン・レノンという人なのでしょうね。
歌詞の中で、
"Please remember my life is in your hands"
「覚えておいておくれ、僕の人生はすべて君の手の中にあるんだ」
というくだり、まあ母のように慕うオノ・ヨーコさんに忠誠を誓っていた
ジョンらしいといえばそうですが、でもこれは言い過ぎじゃないかい、
男女の仲ってそこまで無防備でいいの、と若い頃は思ったものです。
僕の心は子供だとか、一生借りがあるとか、この曲の歌詞の基本は
そこにあって、要するにジョンは甘えているわけですね、はい(笑)。
僕がいちばん好きなくだりはこれ
"However distance don't keep us apart
After all it is written in the stars"
「どれだけ離れていても僕たちの心を引き離すものはない
そして僕たちの名は星に刻まれるんだ」
星座の星は実際は近くにあるわけではない。
距離も時間も離れているけれど、ひとつの星座として
ずっと一緒にいる、と、僕は解釈しています。
死んでも一緒、という意味でもある。
クイーンというかフレディ・マーキュリーのMade In Heavenも
最後"Written in the stars"と歌っていますが、
ジョンのこのくだりが「死んでも一緒」と理解したのは、
クイーンのMade In Heavenを聴いた時のことでした。
若い頃は当然のことながら、ここで歌われているようなことを、
言葉の意味として頭では理解できても実感は伴わない。
伴うような年齢になる頃には僕の気持が冷めていた。
それが今、実感として分かるようになってきました。
ここで歌われているすべての言葉をその通りに感じられる。
ねえジョン、これってまさに俺のことじゃない、と。
After all
僕は、一生のパートナーとなる女性と出会うことができたのです。
2014年12月08日
Fame デヴィッド・ボウイwithジョン・レノン
01
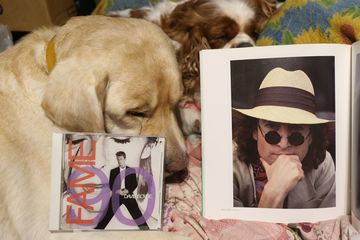
Fame
David Bowie with John Lennon (1975)
毎年12月8日はジョン・レノンの記事を上げています。
今年は、デヴィッド・ボウイがジョン・レノンと
共作共演したこの曲にしました。
先日、突然思い出し、爾来何度か頭に浮かんできて、
時々♪ふぇぇぇ~いむと口ずさんでいます。
ジョン・レノンとデヴィッド・ボウイ。
何というか、ミスマッチ感覚のようなものがありませんか。
僕は中学時代にこの曲のことを知り、そう感じました。
当時、デヴィッド・ボウイはちょうどLet's Danceと
映画『戦場のメリークリスマス』でテレビなどの露出度が高く、
ビートルズしか知らなかった僕でも知っていました。
デヴィッド・ボウイ自体はそれ以前から名前だけ知っていたので、
この人がそうなんだ、と頭の中でつながった時期でした。
当時のボウイ、日本においては人気絶頂期だったかもしれません。
この曲は中学高校と、ラジオやテレビで聴くことなく過ぎました。
大学時代、東京に行って、まだこの曲のCDは出ておらず、
よほど聴きたかったのか、中古のドーナツ盤を買って聴きました。
ということを、実は割と最近思い出しました。
7年前に父が亡くなり、東京の家を片付けていた時、
僕が東京に残したものが入った段ボールはこの中に、
この曲のドーナツ盤が見つかったのです。
懐かしいというより、そんなことあったんだ、と驚きました。
どこで買ったかも覚えていない。
探したのではなく、たまたま店頭で目に留まったのかもしれない。
この曲を初めて聴いたのがいつかも思い出せないので、
そのドーナツ盤を買った時に違いない。
自分でも不思議でした。
なお、今回はこのドーナツ盤の写真をと思いましたが、残念、
東京の弟の家に置いたままのようで、見つかりませんでした。
02

CDで初めて聴いたのは、1990年、
Fame '90というリミックスのCDが出た時です。
ベスト盤SOUND + VISIONからの「シングルカット」でした。
それからRYKOで過去のボウイのアルバムが漸くCD化され、そこで
これが収められたアルバムYOUNG AMERICANのアルバムを聴き、
さらにEMIに移り、リマスター盤が出て買い直しました。
Fameについて、Wikipediaから要約します。
1974年暮れ、ニューヨークにいたデヴィッド・ボウイは
ジョン・レノンとElectric Ladylandスタジオでセッションを行う。
どうしてセッションを行うことになったかの経緯は、申し訳ない、
分からなかったのですが、でも実はそこが知りたいですよね(笑)。
ジョンの伝記などを読めば分かるのかな。
ボウイのバンドを交えたセッションの中で、アルバムに収められた
Across The Universeを先ず録音。
その時、カルロス・アロマーが弾いたファンキーなギターフレーズを
聞いたジョンが突然"Fame!"と叫んだことからそのまま曲に発展、完成。
ボウイにとって初のビルボード誌No.1ヒットとなった、という曲です。
偶然から生まれた曲、いかにもロックらしいエピソードですね。
曲もまさに、作ったというよりひらめいたといった感が強い。
まあ、歌メロがいいとかそういうのではないかもですが、
ロックがファンクに注目していた1970年代らしいノリの1曲。
ジョンは、ボウイのヴォーカルを受けた高音の涼しい響きの
"Fame"というコーラス、短いけどジョンらしい声ですね。
しかもそれが1位になるなんて、まさにボウイのアメリカンドリーム。
しかもボウイは、ファンキーなこの曲の大ヒットにより、
「ソウル・トレイン」に白人として初めて出演という栄誉も授かりました。
作曲者クレジットは、Bowie, Alomar, Lennonとなっています。
ジョンにとって、自らが参加した曲としては、1974年の
Whatever Gets You Thru The Night 「真夜中を突っ走れ」
に続いてビートルズ解散後2曲目のNo.1ヒット。
作曲者としてはポール・マッカートニーとの共作Lennon-McCartneyで
エルトン・ジョン1974年のカヴァーLucy In The Sky With Diaonds
が1位になっているので、これで3曲目ということになります。
ここで先ずはFameを聴いてください。
2番の"What you get is no tomorrow"というくだりは
いかにもジョンらしい、と最初に聴いた時から思っています。
展開部の"Is it any wonder ?"という部分もそうですね。
なお、楽曲のYoung Americanでは、コーダの部分に
"I heard the news today, oh boy"と、
ビートルズのA Day In The Lifeからの引用が
女声コーラスにより挿入されていて、ニヤリとしてしまいます。
03

さて後半は、この曲にまつわる話と映像を。
ジョン・レノンは、1974年の「真夜中を突っ走て!」の
大ヒットにより再び注目を浴びるようになりました。
1975年3月1月に行われた第17回グラミー賞では、
年間最優秀レコード賞 Record Of The Yearのプレゼンターとして、
ポール・サイモンとともにステージに上がりました。
Fameはその年の7月にリリースされており、
プロモーションの意味合いもあったのかもしれません。
なお、賞は、オリヴィア・ニュートン・ジョンの
I Honestly Love Youが受賞しました。
2つ目の映像は、その時のものです。
ジョンは人前に立つのは久し振りで上がっていたのかな、
異様なハイテンションで、時々「おいおい」というジョークを
交えながらも終始ご機嫌な様子。
「ハイ、僕はジョン、昔ポールと仕事していた」
とジョンが話すと、「ポール」・サイモンも
「ハイ、僕はポール、昔アーティと仕事をしていた」
と切り返します。
さらに、後半でアート・ガーファンクルが呼ばれ
ステージに上がるところでもジョンはジョーク連発。
「リンダはいないのか」と言ったり。
本来はS&Gの2人が久し振りに同じ場所に立ったことが
話題になるべきだったのでしょうけれど、ここでのジョンは
今風にいえば「空気が読めない」人になっているような。
でも、それを言う人はいなかったのでしょうね(笑)。
授賞式では、ジョン、ポール、アーティにデヴィッド・ボウイと
ヨーコ・オノの5人によるショットも撮影されていますが、
先日、Facebookの何かの記事でその写真を見たのが、
Fameを思い出して口ずさむきっかけだったんだな、うん、そうだ。
そして、ジョン・レノンが公式の場で人前に立つのは、
この時が最後となったのでした。
04

ジョン・レノン。
毎年この日は特別な思い、新たな思いを抱きます。
でも、僕は、1年365と1/4日、ジョン・レノンのことを
一瞬たりとも考えることがない日はないと断言します。
ジョンへの思いは、特別ではあるけれど、普通のことでもある。
今年はこの日を、ごく日常的にさらりと過ごしたい。
だから、「ジョン・レノン度」が薄めというか、
ジョンが「主」ではない曲の話題を上げることにしました。
冒頭写真は、Fame '90のCDと、
写真集「ジョン・レノン家族生活」からのジョンの1枚でした。
05

2014年12月8日。
そして今日も、僕らの上には空だけがあった。
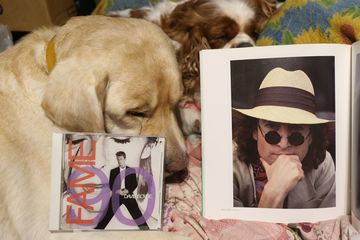
Fame
David Bowie with John Lennon (1975)
毎年12月8日はジョン・レノンの記事を上げています。
今年は、デヴィッド・ボウイがジョン・レノンと
共作共演したこの曲にしました。
先日、突然思い出し、爾来何度か頭に浮かんできて、
時々♪ふぇぇぇ~いむと口ずさんでいます。
ジョン・レノンとデヴィッド・ボウイ。
何というか、ミスマッチ感覚のようなものがありませんか。
僕は中学時代にこの曲のことを知り、そう感じました。
当時、デヴィッド・ボウイはちょうどLet's Danceと
映画『戦場のメリークリスマス』でテレビなどの露出度が高く、
ビートルズしか知らなかった僕でも知っていました。
デヴィッド・ボウイ自体はそれ以前から名前だけ知っていたので、
この人がそうなんだ、と頭の中でつながった時期でした。
当時のボウイ、日本においては人気絶頂期だったかもしれません。
この曲は中学高校と、ラジオやテレビで聴くことなく過ぎました。
大学時代、東京に行って、まだこの曲のCDは出ておらず、
よほど聴きたかったのか、中古のドーナツ盤を買って聴きました。
ということを、実は割と最近思い出しました。
7年前に父が亡くなり、東京の家を片付けていた時、
僕が東京に残したものが入った段ボールはこの中に、
この曲のドーナツ盤が見つかったのです。
懐かしいというより、そんなことあったんだ、と驚きました。
どこで買ったかも覚えていない。
探したのではなく、たまたま店頭で目に留まったのかもしれない。
この曲を初めて聴いたのがいつかも思い出せないので、
そのドーナツ盤を買った時に違いない。
自分でも不思議でした。
なお、今回はこのドーナツ盤の写真をと思いましたが、残念、
東京の弟の家に置いたままのようで、見つかりませんでした。
02

CDで初めて聴いたのは、1990年、
Fame '90というリミックスのCDが出た時です。
ベスト盤SOUND + VISIONからの「シングルカット」でした。
それからRYKOで過去のボウイのアルバムが漸くCD化され、そこで
これが収められたアルバムYOUNG AMERICANのアルバムを聴き、
さらにEMIに移り、リマスター盤が出て買い直しました。
Fameについて、Wikipediaから要約します。
1974年暮れ、ニューヨークにいたデヴィッド・ボウイは
ジョン・レノンとElectric Ladylandスタジオでセッションを行う。
どうしてセッションを行うことになったかの経緯は、申し訳ない、
分からなかったのですが、でも実はそこが知りたいですよね(笑)。
ジョンの伝記などを読めば分かるのかな。
ボウイのバンドを交えたセッションの中で、アルバムに収められた
Across The Universeを先ず録音。
その時、カルロス・アロマーが弾いたファンキーなギターフレーズを
聞いたジョンが突然"Fame!"と叫んだことからそのまま曲に発展、完成。
ボウイにとって初のビルボード誌No.1ヒットとなった、という曲です。
偶然から生まれた曲、いかにもロックらしいエピソードですね。
曲もまさに、作ったというよりひらめいたといった感が強い。
まあ、歌メロがいいとかそういうのではないかもですが、
ロックがファンクに注目していた1970年代らしいノリの1曲。
ジョンは、ボウイのヴォーカルを受けた高音の涼しい響きの
"Fame"というコーラス、短いけどジョンらしい声ですね。
しかもそれが1位になるなんて、まさにボウイのアメリカンドリーム。
しかもボウイは、ファンキーなこの曲の大ヒットにより、
「ソウル・トレイン」に白人として初めて出演という栄誉も授かりました。
作曲者クレジットは、Bowie, Alomar, Lennonとなっています。
ジョンにとって、自らが参加した曲としては、1974年の
Whatever Gets You Thru The Night 「真夜中を突っ走れ」
に続いてビートルズ解散後2曲目のNo.1ヒット。
作曲者としてはポール・マッカートニーとの共作Lennon-McCartneyで
エルトン・ジョン1974年のカヴァーLucy In The Sky With Diaonds
が1位になっているので、これで3曲目ということになります。
ここで先ずはFameを聴いてください。
2番の"What you get is no tomorrow"というくだりは
いかにもジョンらしい、と最初に聴いた時から思っています。
展開部の"Is it any wonder ?"という部分もそうですね。
なお、楽曲のYoung Americanでは、コーダの部分に
"I heard the news today, oh boy"と、
ビートルズのA Day In The Lifeからの引用が
女声コーラスにより挿入されていて、ニヤリとしてしまいます。
03

さて後半は、この曲にまつわる話と映像を。
ジョン・レノンは、1974年の「真夜中を突っ走て!」の
大ヒットにより再び注目を浴びるようになりました。
1975年3月1月に行われた第17回グラミー賞では、
年間最優秀レコード賞 Record Of The Yearのプレゼンターとして、
ポール・サイモンとともにステージに上がりました。
Fameはその年の7月にリリースされており、
プロモーションの意味合いもあったのかもしれません。
なお、賞は、オリヴィア・ニュートン・ジョンの
I Honestly Love Youが受賞しました。
2つ目の映像は、その時のものです。
ジョンは人前に立つのは久し振りで上がっていたのかな、
異様なハイテンションで、時々「おいおい」というジョークを
交えながらも終始ご機嫌な様子。
「ハイ、僕はジョン、昔ポールと仕事していた」
とジョンが話すと、「ポール」・サイモンも
「ハイ、僕はポール、昔アーティと仕事をしていた」
と切り返します。
さらに、後半でアート・ガーファンクルが呼ばれ
ステージに上がるところでもジョンはジョーク連発。
「リンダはいないのか」と言ったり。
本来はS&Gの2人が久し振りに同じ場所に立ったことが
話題になるべきだったのでしょうけれど、ここでのジョンは
今風にいえば「空気が読めない」人になっているような。
でも、それを言う人はいなかったのでしょうね(笑)。
授賞式では、ジョン、ポール、アーティにデヴィッド・ボウイと
ヨーコ・オノの5人によるショットも撮影されていますが、
先日、Facebookの何かの記事でその写真を見たのが、
Fameを思い出して口ずさむきっかけだったんだな、うん、そうだ。
そして、ジョン・レノンが公式の場で人前に立つのは、
この時が最後となったのでした。
04

ジョン・レノン。
毎年この日は特別な思い、新たな思いを抱きます。
でも、僕は、1年365と1/4日、ジョン・レノンのことを
一瞬たりとも考えることがない日はないと断言します。
ジョンへの思いは、特別ではあるけれど、普通のことでもある。
今年はこの日を、ごく日常的にさらりと過ごしたい。
だから、「ジョン・レノン度」が薄めというか、
ジョンが「主」ではない曲の話題を上げることにしました。
冒頭写真は、Fame '90のCDと、
写真集「ジョン・レノン家族生活」からのジョンの1枚でした。
05

2014年12月8日。
そして今日も、僕らの上には空だけがあった。
2014年06月07日
Cold Turkey 冷たい七面鳥 ジョン・レノン
日程の都合で、1日だけ家に帰ってきました。
明日の昼過ぎにはまた出発しますが、
1日だけでも、犬たちと戯れられるのは、
気持ちの面でもよかったです。
さて、今回の遠征中に突然思いついた曲の記事を、
急きょ書いて上げます。
ある思い出話を、思い出したからです。
01

Cold Turkey John Lennon
冷たい七面鳥 ジョン・レノン released in 1969
♪Cold turkey has got me on the run
ジョン・レノンの代表曲のひとつ、のはず。
1969年、まだビートルズが(かろうじて)健在だった頃に、
ジョンのソロとして発表されました。
この曲はシングルでのみリリースされたため、
LPで初めて聴くことが出来たのは、
1975年発表のベスト盤SHAVED FISHでした。
そのベスト盤は、僕が最初に買ったジョン・レノンのLPで、
ゆえにとっても思い入れが深いものです。
お小遣いが限られた中学生には、
Imagineも、あれも、これも入っていてうれしかったですね。
02

この、ジョン生前に唯一リリースされたベスト盤、
SHAVED FISH、敢えて「アルバム」と呼びますが、これが、
ジョンの音楽生活そのものを表し切っている見事な編集で、
アルバムとしても聴き応え十分。
ジャケットのイラストも、曲をうまく1枚でドラマ化しています。
惜しむらくは、ジョン・レノンの生前発表のアルバムは現在は、
すべてがリマスター盤が出ているのですが、
これはベスト盤のせいか、リマスター盤化されていないこと。
素晴らしい「アルバム」なので、ぜひ、リマスター化を。
もちろん、僕が好きなベスト盤の1位か2位です。
と書くと、こんなに誉めているジョンのベスト並に
好きなベスト盤があるのか、と気になるかもしれません(笑)。
そのもう1枚も、できれば近いうちに記事にします。
一応、最後にCDのリンクも施しておきましたが、
繰り返します、このCDはリマスター盤ではありません。
03

「正味二オンス詰」という日本語が泣かせます。
曲いきましょう。
この曲を最初に聴いた時の「恐さ」は、今でも忘れません。
「恐かった」のです。
音からしてほとんどハードロックといえるもので、
しかもそこを「狂気」が支配している・・・
ギターをかきむしるように弾くという表現がまさにぴったり。
ジョンの苦悩、疲弊、焦り、憤怒、孤独感、失望などの
マイナスの感情を表し切ってまだ足りない、という感じ。
中学生だった僕は、それが最初は「恐かった」のです。
しかし、その「恐さ」は「スリリングさ」であることに
そしてそれがロックの本質でもあることに、
この曲を聴いてゆくうちに気づきました。
僕はそれと、いつも言いますが、元々ハードな音が好きだったようで、
表現は「恐かった」けど、音的には最初から魅了されました。
ギターリフがしっかりしていてかっこいいのが、
ハードロックであるなによりの証拠!
それと、ベースの冷たいグルーヴ感が、不思議な響きです。
そうそう、cold turkey=「冷たい七面鳥」とは何か?
クリスマスでパーティに遅れたことではありません(笑)。
薬の助けを借りずに突然麻薬を断つこと
ジョンは、それを求めたけど、出来なかったのか。
良心の呵責に苛まれた結果が、この曲なのか。
このところよく引用している
「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」
にも、この曲に関する言及があるので、紹介します。
JL:あの歌は自明だよ。
麻薬反対の歌なのに、禁止されちゃったな。
麻薬については、とっても馬鹿なことをやってるんだ。
麻薬問題の原因を見ようとしないんだ。
なぜ麻薬を使うのか?
何から逃れるためなのか?
生きることっていうのはそれほど厳しいことなのか?
アルコールやタバコの助けなしに何もできないほど
ひどい状況の中でぼくらは生きてるのか?
アスピリン、睡眠薬、覚醒剤、鎮静剤はみんな
-ヘロインやコカインはともかくとして-
精神安定剤とアンフェタミンの周辺にあるものにすぎないんだ。
この後ジョンは、インタビュアーの
「今は麻薬をやっているか?」との質問に、
「いや使ってないよ」と答えています。
ジョンの人生でも、主夫時代は、
数少ない「安定した時期」だったのかもしれません。
しかし、ジョンはこの後すぐに、
永遠の安らぎを得てしまうのです・・・
04

こちらは、ジョンの死後に出たベスト盤のLP。
なんと、このベストにおいて、この曲はカットされていました。
もちろん、ジョンの全ソロキャリアからの選曲を
うまくLPの枠に収めるのは至難の業ではあるでしょう。
さらにもうひとつ、おそらくですが、
このベストにはジョンの生前の最後のアルバム
DOUBLE FANTASYからのジョンの曲が、
1曲を除いて全て収録されていますが、
DFは当時ゲフィンレコードからリリースされていて、
ゲフィンは当時はワーナーの傘下(現在はユニヴァーサル)、
一方、ジョンの主夫時代の前まではビートルズの名残りで
EMIからリリースされていて、両者のバランスを取るため、
この曲が割を食ったのではないか、と。
それにしても、この曲を落とさなくても、と思いますが、
一方で、ここからはいつもの僕の邪推ですが(笑)、
ジョンの死後間もない時期、
まだジョンの仕事を「正面から」評価出来ない雰囲気があり、
そしてジョンを「神格化」しようという(誰かの)「操作」により、
ダーティなイメージがあって実際に騒がしいこの曲は、
真っ先にリストから外れたのかもしれません。
それは理解できないでもないですし、
実際に、この曲だけは雰囲気が合わないように思いますし、
ましてや放送禁止になったような曲ですから・・・
ただ、やはりレコード会社も気になっていたのか、
こちらのベストがCD化された際に、
Cold Turkeyは追加収録されました。
ただしそのCDは今はカタログ外のようで、
代わりに、下に紹介する新しいベスト盤があります。
この曲は、オリジナルも素晴らしいですが、
さらにいえば、こちらのリンクにある
SOMETIME IN NEW YORK CITYに収録された
Live Jamバージョンがまたまた素晴らしいのです。
1969年のチャリティ・コンサートからの音源ですが、
なんといっても面子が凄いったらありゃしない!
ジョン・レノン Vo/Gt
ヨーコ・オノ Vo
エリック・クラプトン Gt
クラウス・フォアマン Bs
アラン・ホワイト Ds
ここまでが「プラスティック・オノ・バンド」の「固定」メンバー。
さらに
キース・ムーン Per
ビリー・プレストン Org
デラニー&ボニー Gt
ボビー・キーズ Sax
ジム・プライス Tp
ジム・ゴードン Ds
ジョージ・ハリスン Gt
あまりにも豪華なので太字赤字にするのが面倒なくらい・・・(笑)。
それはともかく、これはほんとに凄いんです。
ハードロック的なかっこいいギターリフが、
ここでは加速して勢いがついています。
ジョンは1ヵ所間違ってますが、そんなこと関係ない(笑)。
大学に入り、このバージョンの存在を知ってから、
僕のこの曲への愛着と評価はさらに高まりました。
ただし、このアルバム、LPと初期CDでは2枚組で、
2枚目はまるまるライヴだったのが、
現行CDでは1枚に集約され、この曲は
「ボーナストラック」扱いになっています。
現行のリマスター盤ベスト。
まあこれも、ジョンの仕事は網羅されていて、
やはりジョンのベスト盤は素晴らしくはあります。
さて、最後に「どうでもいい」お話を(笑)。
この曲を記事にしようと思ったのは、
ふと、この曲にまつわる思い出を、
遠征で車を運転している時に思い出したからです。
大学1年の夏休みだから、二十歳の頃(僕は一浪です)。
大学の夏休みで東京から札幌の実家に帰ってきていました。
ある日の夜8時頃、家に電話がかかってきて、
母が受話器を取って出ました。
無言電話でした。
ひたすら無言。
母はすぐに電話を切って、電話の模様を僕と弟に話しました。
少しして、またかかってきました。
今度は弟が出ましたが、やはり無言のまま。
僕が代わって、もしもしと呼びかけましたが、ほんとに無言。
しかも、周りの音もまったく聞こえない。
すぐに僕は電話を切りました。
家族で、もしまたきたらどうしようかと話しました。
そこで僕がひらめいたのが・・・
次にその無言電話がかかってきたら、
この曲、Cold Turkeyの最後の部分、
演奏が激しくなり、ジョンがうめき声を上げている部分を
ラジカセでかけて受話器に当てよう、というものです。
当時はまだカセットテープで聴いていたので、
すぐにテープを探してラジカセでその部分を出しておき、
電話の前で準備をしていました。
すると、10分もしないうちに、また電話がかかってきました。
予想通り、無言でした。
僕は、ラジカセの再生ボタンを押し、この曲をかけました。
効果てきめん!
相手はすぐに電話を切り、以降、
その無言電話は、まったくかかってきませんでした。
やっぱり「恐かった」のかな・・・
で、余談だかメインだか分からないのですが、
その無言電話は、僕あてだったのではないかと、その時思いました。
というのも、僕はその数日前に失恋していたのです。
ただ、失恋というと、一方的にこっちが振られたように見えますが、
一応、本人の名誉のために言わせていただくと(笑)、
「最後のひとこと」は確かに僕が言葉で言われましたが、
状況としては、どちらからともなく・・・という感じ。
お互い離れ離れになっていましたし。
ただ、その女性はそんなことをするような人には思えない、
真面目な人だったので、違うとは思いつつ、
タイミングがあまりにもあまりにもで・・・
でも、当時の若かった僕には、
人の心がよく分からなくて(今も分からないですが)、
そんな真面目な人がそんなことするはずはない、
と決め付けていましたが、
案外、そうでもないのかもしれません、分かりませんが・・・
ともあれ、そんなことを遠征中に車を運転していて思い出し、
携帯メールで箇条書きにして自分のPCに送り、
それを文章としてまとめたのがこの記事です。
思い付きの割には、やっぱり長くなりましたが・・・(笑)。
05

今回はポーラが大活躍!
って、寝ている横に置いて撮っただけですが(笑)。
明日の昼過ぎにはまた出発しますが、
1日だけでも、犬たちと戯れられるのは、
気持ちの面でもよかったです。
さて、今回の遠征中に突然思いついた曲の記事を、
急きょ書いて上げます。
ある思い出話を、思い出したからです。
01

Cold Turkey John Lennon
冷たい七面鳥 ジョン・レノン released in 1969
♪Cold turkey has got me on the run
ジョン・レノンの代表曲のひとつ、のはず。
1969年、まだビートルズが(かろうじて)健在だった頃に、
ジョンのソロとして発表されました。
この曲はシングルでのみリリースされたため、
LPで初めて聴くことが出来たのは、
1975年発表のベスト盤SHAVED FISHでした。
そのベスト盤は、僕が最初に買ったジョン・レノンのLPで、
ゆえにとっても思い入れが深いものです。
お小遣いが限られた中学生には、
Imagineも、あれも、これも入っていてうれしかったですね。
02

この、ジョン生前に唯一リリースされたベスト盤、
SHAVED FISH、敢えて「アルバム」と呼びますが、これが、
ジョンの音楽生活そのものを表し切っている見事な編集で、
アルバムとしても聴き応え十分。
ジャケットのイラストも、曲をうまく1枚でドラマ化しています。
惜しむらくは、ジョン・レノンの生前発表のアルバムは現在は、
すべてがリマスター盤が出ているのですが、
これはベスト盤のせいか、リマスター盤化されていないこと。
素晴らしい「アルバム」なので、ぜひ、リマスター化を。
もちろん、僕が好きなベスト盤の1位か2位です。
と書くと、こんなに誉めているジョンのベスト並に
好きなベスト盤があるのか、と気になるかもしれません(笑)。
そのもう1枚も、できれば近いうちに記事にします。
一応、最後にCDのリンクも施しておきましたが、
繰り返します、このCDはリマスター盤ではありません。
03

「正味二オンス詰」という日本語が泣かせます。
曲いきましょう。
この曲を最初に聴いた時の「恐さ」は、今でも忘れません。
「恐かった」のです。
音からしてほとんどハードロックといえるもので、
しかもそこを「狂気」が支配している・・・
ギターをかきむしるように弾くという表現がまさにぴったり。
ジョンの苦悩、疲弊、焦り、憤怒、孤独感、失望などの
マイナスの感情を表し切ってまだ足りない、という感じ。
中学生だった僕は、それが最初は「恐かった」のです。
しかし、その「恐さ」は「スリリングさ」であることに
そしてそれがロックの本質でもあることに、
この曲を聴いてゆくうちに気づきました。
僕はそれと、いつも言いますが、元々ハードな音が好きだったようで、
表現は「恐かった」けど、音的には最初から魅了されました。
ギターリフがしっかりしていてかっこいいのが、
ハードロックであるなによりの証拠!
それと、ベースの冷たいグルーヴ感が、不思議な響きです。
そうそう、cold turkey=「冷たい七面鳥」とは何か?
クリスマスでパーティに遅れたことではありません(笑)。
薬の助けを借りずに突然麻薬を断つこと
ジョンは、それを求めたけど、出来なかったのか。
良心の呵責に苛まれた結果が、この曲なのか。
このところよく引用している
「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」
にも、この曲に関する言及があるので、紹介します。
JL:あの歌は自明だよ。
麻薬反対の歌なのに、禁止されちゃったな。
麻薬については、とっても馬鹿なことをやってるんだ。
麻薬問題の原因を見ようとしないんだ。
なぜ麻薬を使うのか?
何から逃れるためなのか?
生きることっていうのはそれほど厳しいことなのか?
アルコールやタバコの助けなしに何もできないほど
ひどい状況の中でぼくらは生きてるのか?
アスピリン、睡眠薬、覚醒剤、鎮静剤はみんな
-ヘロインやコカインはともかくとして-
精神安定剤とアンフェタミンの周辺にあるものにすぎないんだ。
この後ジョンは、インタビュアーの
「今は麻薬をやっているか?」との質問に、
「いや使ってないよ」と答えています。
ジョンの人生でも、主夫時代は、
数少ない「安定した時期」だったのかもしれません。
しかし、ジョンはこの後すぐに、
永遠の安らぎを得てしまうのです・・・
04

こちらは、ジョンの死後に出たベスト盤のLP。
なんと、このベストにおいて、この曲はカットされていました。
もちろん、ジョンの全ソロキャリアからの選曲を
うまくLPの枠に収めるのは至難の業ではあるでしょう。
さらにもうひとつ、おそらくですが、
このベストにはジョンの生前の最後のアルバム
DOUBLE FANTASYからのジョンの曲が、
1曲を除いて全て収録されていますが、
DFは当時ゲフィンレコードからリリースされていて、
ゲフィンは当時はワーナーの傘下(現在はユニヴァーサル)、
一方、ジョンの主夫時代の前まではビートルズの名残りで
EMIからリリースされていて、両者のバランスを取るため、
この曲が割を食ったのではないか、と。
それにしても、この曲を落とさなくても、と思いますが、
一方で、ここからはいつもの僕の邪推ですが(笑)、
ジョンの死後間もない時期、
まだジョンの仕事を「正面から」評価出来ない雰囲気があり、
そしてジョンを「神格化」しようという(誰かの)「操作」により、
ダーティなイメージがあって実際に騒がしいこの曲は、
真っ先にリストから外れたのかもしれません。
それは理解できないでもないですし、
実際に、この曲だけは雰囲気が合わないように思いますし、
ましてや放送禁止になったような曲ですから・・・
ただ、やはりレコード会社も気になっていたのか、
こちらのベストがCD化された際に、
Cold Turkeyは追加収録されました。
ただしそのCDは今はカタログ外のようで、
代わりに、下に紹介する新しいベスト盤があります。
この曲は、オリジナルも素晴らしいですが、
さらにいえば、こちらのリンクにある
SOMETIME IN NEW YORK CITYに収録された
Live Jamバージョンがまたまた素晴らしいのです。
1969年のチャリティ・コンサートからの音源ですが、
なんといっても面子が凄いったらありゃしない!
ジョン・レノン Vo/Gt
ヨーコ・オノ Vo
エリック・クラプトン Gt
クラウス・フォアマン Bs
アラン・ホワイト Ds
ここまでが「プラスティック・オノ・バンド」の「固定」メンバー。
さらに
キース・ムーン Per
ビリー・プレストン Org
デラニー&ボニー Gt
ボビー・キーズ Sax
ジム・プライス Tp
ジム・ゴードン Ds
ジョージ・ハリスン Gt
あまりにも豪華なので太字赤字にするのが面倒なくらい・・・(笑)。
それはともかく、これはほんとに凄いんです。
ハードロック的なかっこいいギターリフが、
ここでは加速して勢いがついています。
ジョンは1ヵ所間違ってますが、そんなこと関係ない(笑)。
大学に入り、このバージョンの存在を知ってから、
僕のこの曲への愛着と評価はさらに高まりました。
ただし、このアルバム、LPと初期CDでは2枚組で、
2枚目はまるまるライヴだったのが、
現行CDでは1枚に集約され、この曲は
「ボーナストラック」扱いになっています。
現行のリマスター盤ベスト。
まあこれも、ジョンの仕事は網羅されていて、
やはりジョンのベスト盤は素晴らしくはあります。
さて、最後に「どうでもいい」お話を(笑)。
この曲を記事にしようと思ったのは、
ふと、この曲にまつわる思い出を、
遠征で車を運転している時に思い出したからです。
大学1年の夏休みだから、二十歳の頃(僕は一浪です)。
大学の夏休みで東京から札幌の実家に帰ってきていました。
ある日の夜8時頃、家に電話がかかってきて、
母が受話器を取って出ました。
無言電話でした。
ひたすら無言。
母はすぐに電話を切って、電話の模様を僕と弟に話しました。
少しして、またかかってきました。
今度は弟が出ましたが、やはり無言のまま。
僕が代わって、もしもしと呼びかけましたが、ほんとに無言。
しかも、周りの音もまったく聞こえない。
すぐに僕は電話を切りました。
家族で、もしまたきたらどうしようかと話しました。
そこで僕がひらめいたのが・・・
次にその無言電話がかかってきたら、
この曲、Cold Turkeyの最後の部分、
演奏が激しくなり、ジョンがうめき声を上げている部分を
ラジカセでかけて受話器に当てよう、というものです。
当時はまだカセットテープで聴いていたので、
すぐにテープを探してラジカセでその部分を出しておき、
電話の前で準備をしていました。
すると、10分もしないうちに、また電話がかかってきました。
予想通り、無言でした。
僕は、ラジカセの再生ボタンを押し、この曲をかけました。
効果てきめん!
相手はすぐに電話を切り、以降、
その無言電話は、まったくかかってきませんでした。
やっぱり「恐かった」のかな・・・
で、余談だかメインだか分からないのですが、
その無言電話は、僕あてだったのではないかと、その時思いました。
というのも、僕はその数日前に失恋していたのです。
ただ、失恋というと、一方的にこっちが振られたように見えますが、
一応、本人の名誉のために言わせていただくと(笑)、
「最後のひとこと」は確かに僕が言葉で言われましたが、
状況としては、どちらからともなく・・・という感じ。
お互い離れ離れになっていましたし。
ただ、その女性はそんなことをするような人には思えない、
真面目な人だったので、違うとは思いつつ、
タイミングがあまりにもあまりにもで・・・
でも、当時の若かった僕には、
人の心がよく分からなくて(今も分からないですが)、
そんな真面目な人がそんなことするはずはない、
と決め付けていましたが、
案外、そうでもないのかもしれません、分かりませんが・・・
ともあれ、そんなことを遠征中に車を運転していて思い出し、
携帯メールで箇条書きにして自分のPCに送り、
それを文章としてまとめたのがこの記事です。
思い付きの割には、やっぱり長くなりましたが・・・(笑)。
05

今回はポーラが大活躍!
って、寝ている横に置いて撮っただけですが(笑)。
2013年12月08日
Instant Karma! ジョン・レノン
01

Instant Karma! John Lennon
インスタント・カーマ ジョン・レノン (1970)
12月8日。
ジョン・レノンの日です。
僕がロックを、洋楽を好きになったのはジョンのおかげ。
毎年この日は、ジョンの記事を上げています。
写真のベスト盤LPは、ジョンの死後に編集されリリースされたもので、
当時のEMIの音源とGEFFENの音源がレーベルを超えて
一緒に入っているのが話題を呼びました。
もっとも、そのような事情によりGEFFENからの当時は唯一の
アルバムであるジョンの遺作DOUBLE FANTASYからは、
ジョンの曲の7曲中6曲が収録されているのですが。
1989年にCD化された際に、
Move Over Mrs. LとCold Turkeyが追加収録されました。
前者はジョニー・ウィンターに提供した曲を自ら歌ったものですが、
実はボツになったテイクであり、ジョニーに「やった」とのこと。
後者はLPに収録されていなかったのが不思議ですが、でも、
ジョンを「美化」したかったのかな、死の直後は。
僕は大好きなんですけどね、ジョン流のヘヴィメタルとして。
今回はこのベスト盤から、Instant Karma!を取り上げます。
他の曲については触れません、またの機会に。
02 雲に隠れているけれど、12月8日の太陽

先ずはInstant Karma!のリリースのいきさつについて、
「レコードコレクターズ」増刊「ザ・ビートルズ・ソロ・ワークス」から引用します。
なお、引用者は一部手を加えています。
■1970年1月27日
Cold Turkeyに次ぐプラスティック・オノ・バンドの3枚目のシングルとして、
ジョンが69年11月にリミックスを行ったYou Know My Nameか、
Make Love Not Warのどちらかが発売されるという噂があったが、
それらに代わって登場したのがInstant Karma!である。
なお、後に、You Know My Nameはザ・ビートルズの
Let It BeのシングルB面として、Make Love Not Warは
ジョンのソロ作品としてMind Gamesのタイトルで発売された。
ジョンはこの曲を70年1月27日の朝に作り、
その後すぐにアビィ・ロード・スタジオを予約。
そしてその日の夜にジョージ・ハリスン(ギター、ピアノ)、
クラウス・ヴーアマン(ベース、ピアノ)、アラン・ホワイト(ドラムス、ピアノ)、
ビリー・プレストン(オルガン)、マル・エヴァンス(手拍子、チャイム)
らとレコーディングを行った。
さらに、共同プロデューサーのフィル・スペクターとともに
ミキシングも手がけて、わずか1日で完成させた。
なお、コーラスには、スタジオ近くのナイトクラブで酒を飲んでいた人々
(ビリー・プレストンが呼び寄せた)とアラン・クラインが加わっている。
酒を飲んでいた人々を呼び寄せたというのがなんだか面白い。
アラン・クラインはあのYou Never Give Me Your Moneyの人、
悪徳マネージャーですね。
それにしても、ほんとうに「インスタント」に出来た曲ですが、
それは曲が持つ力がそうさせたに違いない。
そんな曲が朝に浮かんでしまった、もうそこから始まっているのでしょう。
ドラムスがリンゴじゃないのがちょっと寂しいけれど、
でもアラン・ホワイトも大好きだからいいか、今はイエスの人、
あ、「イエスマン」という意味ではなくて。
なお、2月11日にはBBCの人気テレビ番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」に
録音メンバーとヨーコ・オノを従えて出演し、歌と演奏を披露、
ヨーコはそばでメッセージを書いた紙を掲げるパフォーマンスを行った
という逸話も紹介されています。
ちなみにこの時は「指パク」、と僕が勝手に呼んでいるのですが、
ジョンの歌は生だけど演奏は事前に録音されたもの(レコードか?)
を使ったそうです。
当時のジョンはメッセージを発することに執心したアジテイターでもあり、
それが受け入れられる時代でもあったことが、
この曲を書かせたもう一つの力だったのでしょう。
◇
続いておなじみ『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』から、
ジョンのこの曲へのコメントを引用します。
JL:ふと思いついた曲。
誰もがKARMA(因縁)を追いかけていた。
特に60年代はね。
だけどカルマというのは、人の過去や未来に影響を与えると同時に、
インスタントなものだと、僕にはひらめいたんだ。
人が今やっていることへの反応が絶対ある。
そのことをみんなはよく理解しておくべきなんだ。
同じように僕はアートのひとつの形式としてコマーシャルや宣伝に
すごく興味がある。
とても面白いよ。
だからインスタント・カルマのアイディアというのは、
インスタント・コーヒーのアイディアみたいなもので、
何かを新しい形態で示すことなんだよ。
その辺が僕はとにかくちょいと好きだったんだ。
「因縁」はスポーツでよく使いますが、ううん、正直、
ジョンのこの話、僕には今一つよく分からない部分があります。
そこで、『新明解国語辞典 第7版』で「因縁」を引いてみました。
引用します。
いんねん【因縁】(「いんえん」の変化)
〔「因」は直接の原因、「縁」は間接の原因の意。
一切の事象は、この因・縁が相月(アイガツ)して成る、
というのが仏教の基本的な考え方〕
①宿命による、動かせない環境や関係。
「前世からの-と〔運命と思って〕あきらめる/
何かの-だ/浅からぬ-〔ゆかり〕/お前なんかに-をつけられる
〔=ゆすったりする目的で、言いがかりを言われる〕覚えは無い」
②そうなった(深い)わけ。「いわれ-、故事来歴」
つまり、人は「因縁」がなくても何かの力が作用しあい、影響しあっている、
それは昔からの知り合いでも今朝初めて会った人でも、或いは
まったく知らない人でもさして変わりはない、だからうまくやってゆこう。
というのがジョンのメッセージかな。
「一目ぼれ」もある意味同じことかもしれない(いや違うか)。
誰もがKARMAを追いかけていたというのは、混迷する時代に、
人々が少しでも落ち着かせるためにその原因を探り出そうとしていた、
ということかもしれない。
何だかわからない敵と戦うのは恐い、それであるならなぜそうなったかを
はっきりとさせたほうが戦いやすい。
この曲は大好きでずっと歌ってきたけれど、今まで僕は、あまり深く考えず、
ただ「月や星や太陽のように人々が輝けるよう応援する曲」とだけ感じていた、
そんな気がしてきました、うん、きっとそうに違いない。
03 2013年12月8日の月、月齢5.1

僕がこの曲を初めて聴いたのは、1981年、中学2年の多分11月のこと。
1981年10月から、北海道ではHBCラジオでビートルズの歴史を追う
ラジオ番組が放送されました。
今でいうナヴィゲイター、当時そんな言葉はまだ日本語にはなかった、
総合司会は星加ルミ子さん。
僕は当時はビートルズの小冊子で彼女の名前を知ったばかりで、
ああこの人が伝説のあの人なんだと思いながら聴いていました。
放送が土曜日20時からで1時間、記憶にある限り毎週聴き続け、
多分12月までの放送、でも11月だったかもしれない。
そういえば僕はその時からドリフを見なくなったっけ。
僕は中2の8月からビートルズを聴き始め、10月であれば
まだLP2、3枚しか買っていなかった頃で、その他ラジオで録音した曲を
含めても50曲くらいしか知らなくて、その番組で
ビートルズの知らない曲を聴くのも楽しみでした。
ただ、レコードを買った際に小冊子をもらい、本も1冊買って読んでいたので、
213曲すべてについて、聴いたことがなくても一応の知識はありました。
そんなある日、強烈なブギーに乗ったこの曲が流れてきました。
すごい。
かっこいい。
こんなに力がみなぎった曲がこの世の中にあったのか。
衝撃を受けました。
おそらく、僕が初めて聴いて最も大きな衝撃を受けた曲だと思います。
しかし、ジョンが歌っていることは分かりましたが、曲名が分からない。
番組はカセットテープに録音していたので、番組が終わって、
何度も何度も聴き返したところ、歌い出しのところでジョンが
「ンスタントカマ」と歌っているのが聴こえました。
そうか、ビートルズではなくジョンの曲か!
爾来、今までずっと大好きで、ジョンの好きな曲を
5曲選べといわれれば必ず入れますね。
ジョン・レノンは基本ブルーズですよね。
ブルーズというか、ブルーズから流れてきたブルージーさを
自然と表すことができる音楽。
特に「ホワイトアルバム」からその傾向が強くなり、
頂点に達したのがこの後の「ジョンの魂」。
年代的にこの曲もそこにはまります。
しかもこの曲は速い。
たたみかけてくるスリルがたまらない。
ギターで弾いてみると、コード進行が凝っていてかっこよかった。
A→F#m(×3)→F→G→A、これだけでブルージーな響き。
もちろん歌メロもいい。
AメロとBメロは早口だけど、そのパワーを
アンセム的に盛り上がるCメロ=コーラスで爆発させている。
コーラスの部分の歌詞はこうです。
"Well we all shine on,
like the moon and the stars and the sun"
「僕らは輝き続ける、月や星々や太陽のように」
シェイクスピアの大仰なセリフのようであるのは
いかにも英国人というところでしょうけど、ここで上手いのは、
"moon"と"stars"と"sun"の並べ方。
普通、"sun and moon"というよう"sun"が先にきそうなものを、
ここはこの旋律に合う語呂と韻を鑑みて
"sun"を最後に持ってきているのだと思う。
試しに他の順番でこの旋律に乗せて歌ってみると(全部で6通り)、
やっぱりこの順番がいちばんよく聴こえます。
まあ、"on"と"sun"は厳密には母音の音が違うので韻を踏んでいるとは
言えないけれど、でも"on"は"son"になると"sun"と同じ音になるし
強引とまではいかない、納得させられるものではあります。
コーラスは最後のところで、まるで疲れたように声がおとなしくなるのが
リアルでいいし、ジョンかっこいいと思わずにはいられない部分。
ひとつ面白いのは、Aメロのヴァースの3番目のくだりで
エルヴィス・プレスリーを真似たような歌い方をするところ。
しかし当時のエルヴィスはもう「太ったエルヴィス」だった。
だからジョンは、茶化しているというよりは、かつての英雄だった
エルヴィスに本物のロックンロール魂を取り戻してほしかったのかな。
僕が歌う時ももちろんエルヴィスの真似をしますね。
ジョンのブルージーなブギー・ロックンロールの最高傑作にして
名曲だと信じて疑わない。
ただ、ですね。
この曲、今はあまり人気がないかな、そんな気がする。
Power To The Peopleのようにメッセージも歌もシンプルではないし
(こっちは近年人気が高まっている印象がありますが)。
ところで僕は、中高生時代、ビートルズとメンバーの
国内盤のシングルレコードを集めていました。
当時はまだ中古で1枚300円くらいでたくさん売られていましたが、
ビートルズの最初に出たジャケットのものはだいたい揃えました
(アップルになって出直したものもあるけれどジャケットは古いまま)。
ポール・マッカートニーのシングルも、1980年までのもので
持っていないのは幾つあるかな、くらいに。
でも、ジョンについては、今レコードの棚を見ると、
ImagineとMind Gamesしかありませんでした。
あれ、もっと買ったはずだけどな、
「冷たい七面鳥」という文字を見た記憶もあるし・・・
というわけで、「インスタント・カーマ!」もありません。
記事にしたので、この際だから探して買いたい、ヤフオクであるかな。
04

ポールばかりでNEWはいまだに聴き続けているけれど、
今日ばかりはポールも許してくれるでしょう(笑)。

Instant Karma! John Lennon
インスタント・カーマ ジョン・レノン (1970)
12月8日。
ジョン・レノンの日です。
僕がロックを、洋楽を好きになったのはジョンのおかげ。
毎年この日は、ジョンの記事を上げています。
写真のベスト盤LPは、ジョンの死後に編集されリリースされたもので、
当時のEMIの音源とGEFFENの音源がレーベルを超えて
一緒に入っているのが話題を呼びました。
もっとも、そのような事情によりGEFFENからの当時は唯一の
アルバムであるジョンの遺作DOUBLE FANTASYからは、
ジョンの曲の7曲中6曲が収録されているのですが。
1989年にCD化された際に、
Move Over Mrs. LとCold Turkeyが追加収録されました。
前者はジョニー・ウィンターに提供した曲を自ら歌ったものですが、
実はボツになったテイクであり、ジョニーに「やった」とのこと。
後者はLPに収録されていなかったのが不思議ですが、でも、
ジョンを「美化」したかったのかな、死の直後は。
僕は大好きなんですけどね、ジョン流のヘヴィメタルとして。
今回はこのベスト盤から、Instant Karma!を取り上げます。
他の曲については触れません、またの機会に。
02 雲に隠れているけれど、12月8日の太陽

先ずはInstant Karma!のリリースのいきさつについて、
「レコードコレクターズ」増刊「ザ・ビートルズ・ソロ・ワークス」から引用します。
なお、引用者は一部手を加えています。
■1970年1月27日
Cold Turkeyに次ぐプラスティック・オノ・バンドの3枚目のシングルとして、
ジョンが69年11月にリミックスを行ったYou Know My Nameか、
Make Love Not Warのどちらかが発売されるという噂があったが、
それらに代わって登場したのがInstant Karma!である。
なお、後に、You Know My Nameはザ・ビートルズの
Let It BeのシングルB面として、Make Love Not Warは
ジョンのソロ作品としてMind Gamesのタイトルで発売された。
ジョンはこの曲を70年1月27日の朝に作り、
その後すぐにアビィ・ロード・スタジオを予約。
そしてその日の夜にジョージ・ハリスン(ギター、ピアノ)、
クラウス・ヴーアマン(ベース、ピアノ)、アラン・ホワイト(ドラムス、ピアノ)、
ビリー・プレストン(オルガン)、マル・エヴァンス(手拍子、チャイム)
らとレコーディングを行った。
さらに、共同プロデューサーのフィル・スペクターとともに
ミキシングも手がけて、わずか1日で完成させた。
なお、コーラスには、スタジオ近くのナイトクラブで酒を飲んでいた人々
(ビリー・プレストンが呼び寄せた)とアラン・クラインが加わっている。
酒を飲んでいた人々を呼び寄せたというのがなんだか面白い。
アラン・クラインはあのYou Never Give Me Your Moneyの人、
悪徳マネージャーですね。
それにしても、ほんとうに「インスタント」に出来た曲ですが、
それは曲が持つ力がそうさせたに違いない。
そんな曲が朝に浮かんでしまった、もうそこから始まっているのでしょう。
ドラムスがリンゴじゃないのがちょっと寂しいけれど、
でもアラン・ホワイトも大好きだからいいか、今はイエスの人、
あ、「イエスマン」という意味ではなくて。
なお、2月11日にはBBCの人気テレビ番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」に
録音メンバーとヨーコ・オノを従えて出演し、歌と演奏を披露、
ヨーコはそばでメッセージを書いた紙を掲げるパフォーマンスを行った
という逸話も紹介されています。
ちなみにこの時は「指パク」、と僕が勝手に呼んでいるのですが、
ジョンの歌は生だけど演奏は事前に録音されたもの(レコードか?)
を使ったそうです。
当時のジョンはメッセージを発することに執心したアジテイターでもあり、
それが受け入れられる時代でもあったことが、
この曲を書かせたもう一つの力だったのでしょう。
◇
続いておなじみ『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』から、
ジョンのこの曲へのコメントを引用します。
JL:ふと思いついた曲。
誰もがKARMA(因縁)を追いかけていた。
特に60年代はね。
だけどカルマというのは、人の過去や未来に影響を与えると同時に、
インスタントなものだと、僕にはひらめいたんだ。
人が今やっていることへの反応が絶対ある。
そのことをみんなはよく理解しておくべきなんだ。
同じように僕はアートのひとつの形式としてコマーシャルや宣伝に
すごく興味がある。
とても面白いよ。
だからインスタント・カルマのアイディアというのは、
インスタント・コーヒーのアイディアみたいなもので、
何かを新しい形態で示すことなんだよ。
その辺が僕はとにかくちょいと好きだったんだ。
「因縁」はスポーツでよく使いますが、ううん、正直、
ジョンのこの話、僕には今一つよく分からない部分があります。
そこで、『新明解国語辞典 第7版』で「因縁」を引いてみました。
引用します。
いんねん【因縁】(「いんえん」の変化)
〔「因」は直接の原因、「縁」は間接の原因の意。
一切の事象は、この因・縁が相月(アイガツ)して成る、
というのが仏教の基本的な考え方〕
①宿命による、動かせない環境や関係。
「前世からの-と〔運命と思って〕あきらめる/
何かの-だ/浅からぬ-〔ゆかり〕/お前なんかに-をつけられる
〔=ゆすったりする目的で、言いがかりを言われる〕覚えは無い」
②そうなった(深い)わけ。「いわれ-、故事来歴」
つまり、人は「因縁」がなくても何かの力が作用しあい、影響しあっている、
それは昔からの知り合いでも今朝初めて会った人でも、或いは
まったく知らない人でもさして変わりはない、だからうまくやってゆこう。
というのがジョンのメッセージかな。
「一目ぼれ」もある意味同じことかもしれない(いや違うか)。
誰もがKARMAを追いかけていたというのは、混迷する時代に、
人々が少しでも落ち着かせるためにその原因を探り出そうとしていた、
ということかもしれない。
何だかわからない敵と戦うのは恐い、それであるならなぜそうなったかを
はっきりとさせたほうが戦いやすい。
この曲は大好きでずっと歌ってきたけれど、今まで僕は、あまり深く考えず、
ただ「月や星や太陽のように人々が輝けるよう応援する曲」とだけ感じていた、
そんな気がしてきました、うん、きっとそうに違いない。
03 2013年12月8日の月、月齢5.1

僕がこの曲を初めて聴いたのは、1981年、中学2年の多分11月のこと。
1981年10月から、北海道ではHBCラジオでビートルズの歴史を追う
ラジオ番組が放送されました。
今でいうナヴィゲイター、当時そんな言葉はまだ日本語にはなかった、
総合司会は星加ルミ子さん。
僕は当時はビートルズの小冊子で彼女の名前を知ったばかりで、
ああこの人が伝説のあの人なんだと思いながら聴いていました。
放送が土曜日20時からで1時間、記憶にある限り毎週聴き続け、
多分12月までの放送、でも11月だったかもしれない。
そういえば僕はその時からドリフを見なくなったっけ。
僕は中2の8月からビートルズを聴き始め、10月であれば
まだLP2、3枚しか買っていなかった頃で、その他ラジオで録音した曲を
含めても50曲くらいしか知らなくて、その番組で
ビートルズの知らない曲を聴くのも楽しみでした。
ただ、レコードを買った際に小冊子をもらい、本も1冊買って読んでいたので、
213曲すべてについて、聴いたことがなくても一応の知識はありました。
そんなある日、強烈なブギーに乗ったこの曲が流れてきました。
すごい。
かっこいい。
こんなに力がみなぎった曲がこの世の中にあったのか。
衝撃を受けました。
おそらく、僕が初めて聴いて最も大きな衝撃を受けた曲だと思います。
しかし、ジョンが歌っていることは分かりましたが、曲名が分からない。
番組はカセットテープに録音していたので、番組が終わって、
何度も何度も聴き返したところ、歌い出しのところでジョンが
「ンスタントカマ」と歌っているのが聴こえました。
そうか、ビートルズではなくジョンの曲か!
爾来、今までずっと大好きで、ジョンの好きな曲を
5曲選べといわれれば必ず入れますね。
ジョン・レノンは基本ブルーズですよね。
ブルーズというか、ブルーズから流れてきたブルージーさを
自然と表すことができる音楽。
特に「ホワイトアルバム」からその傾向が強くなり、
頂点に達したのがこの後の「ジョンの魂」。
年代的にこの曲もそこにはまります。
しかもこの曲は速い。
たたみかけてくるスリルがたまらない。
ギターで弾いてみると、コード進行が凝っていてかっこよかった。
A→F#m(×3)→F→G→A、これだけでブルージーな響き。
もちろん歌メロもいい。
AメロとBメロは早口だけど、そのパワーを
アンセム的に盛り上がるCメロ=コーラスで爆発させている。
コーラスの部分の歌詞はこうです。
"Well we all shine on,
like the moon and the stars and the sun"
「僕らは輝き続ける、月や星々や太陽のように」
シェイクスピアの大仰なセリフのようであるのは
いかにも英国人というところでしょうけど、ここで上手いのは、
"moon"と"stars"と"sun"の並べ方。
普通、"sun and moon"というよう"sun"が先にきそうなものを、
ここはこの旋律に合う語呂と韻を鑑みて
"sun"を最後に持ってきているのだと思う。
試しに他の順番でこの旋律に乗せて歌ってみると(全部で6通り)、
やっぱりこの順番がいちばんよく聴こえます。
まあ、"on"と"sun"は厳密には母音の音が違うので韻を踏んでいるとは
言えないけれど、でも"on"は"son"になると"sun"と同じ音になるし
強引とまではいかない、納得させられるものではあります。
コーラスは最後のところで、まるで疲れたように声がおとなしくなるのが
リアルでいいし、ジョンかっこいいと思わずにはいられない部分。
ひとつ面白いのは、Aメロのヴァースの3番目のくだりで
エルヴィス・プレスリーを真似たような歌い方をするところ。
しかし当時のエルヴィスはもう「太ったエルヴィス」だった。
だからジョンは、茶化しているというよりは、かつての英雄だった
エルヴィスに本物のロックンロール魂を取り戻してほしかったのかな。
僕が歌う時ももちろんエルヴィスの真似をしますね。
ジョンのブルージーなブギー・ロックンロールの最高傑作にして
名曲だと信じて疑わない。
ただ、ですね。
この曲、今はあまり人気がないかな、そんな気がする。
Power To The Peopleのようにメッセージも歌もシンプルではないし
(こっちは近年人気が高まっている印象がありますが)。
ところで僕は、中高生時代、ビートルズとメンバーの
国内盤のシングルレコードを集めていました。
当時はまだ中古で1枚300円くらいでたくさん売られていましたが、
ビートルズの最初に出たジャケットのものはだいたい揃えました
(アップルになって出直したものもあるけれどジャケットは古いまま)。
ポール・マッカートニーのシングルも、1980年までのもので
持っていないのは幾つあるかな、くらいに。
でも、ジョンについては、今レコードの棚を見ると、
ImagineとMind Gamesしかありませんでした。
あれ、もっと買ったはずだけどな、
「冷たい七面鳥」という文字を見た記憶もあるし・・・
というわけで、「インスタント・カーマ!」もありません。
記事にしたので、この際だから探して買いたい、ヤフオクであるかな。
04

ポールばかりでNEWはいまだに聴き続けているけれど、
今日ばかりはポールも許してくれるでしょう(笑)。
2013年10月22日
WALLS AND BRIDGES ジョン・レノン
01

WALLS AND BRIDGES John Lennon
心の壁、愛の橋 ジョン・レノン (1974)
新しいリマスター盤とボックスセットが出た勢いで、
今日もジョン・レノンいきます。
今回については、今日に記事を上げることに少し意味があります。
このアルバムは、5年前に前のリマスター盤がリリースされ、
その頃にBLOGを始めたばかりの僕は一度記事にしていました。
しかし、その間にいろいろと分かったことがあって、
新リマスター盤記念でまた記事にすることにしました。
人間は幾つになっても学んでゆくものなんだなと。
このアルバムは、ジョン・レノン名義の
スタジオ録音の新録音の曲が入ったアルバムとして数えると、
ソロ5枚目のアルバムということになります。
これは、僕が高校時代、最初に買ったジョンのソロのLPでした。
最初に聴いたのは、借りていてそのまま僕のものになった
ROCK 'N' ROLLであることは前の記事(こちら)でも触れました。
当時は、いつもビートルズのLPを買いに行くレコード店が2軒あり、
そのうちの1軒「キクヤ」に、当時35歳くらいの洋楽担当の男性がいて、
その人と仲良くなり、ビートルズのグッズをもらったりしていました。
或る日、当時はまだジョンのソロアルバムを買ったことがなかったので、
そろそろどれか買いたいけど何がいいですかと店員さんに聞くと、
その人はこれをすすめたので、その場で買って帰りました。
第一印象は・・・
とにかくジョンのヴォーカルが熱い、もうひとつ、
音がすっきりしないで不必要なくらいに厚い、でした。
ジョン自身のプロデュースですが、ジョンという人は
あまり全体を見通せる人じゃないのかなとも思いました。
それは違う、このアルバムは狙ったものかもしれないのですが、
僕は、スカッとした感じがなくて、重たい雰囲気を感じ取りました。
ただ、まとわりつくような歌はさすがジョンで、暫く聴き込みました。
このアルバムは、ヨーコさんと別れていた期間、
いわば「失われた週末」時代に作られたアルバムですが、
当時の僕の感想は実は、単に音楽を聴いてそう感じただけではなく、
書籍などで予備知識を「刷り込まれた」状態でのものだったので、
余計にこのアルバムはとっても重たく感じました。
ほんとはそれはよくないのかもしれないですが、
当時は好奇心が旺盛だったので、仕方ないですかね。
ここで本日は、ビートルズ The Beatlesや
ジョンのアルバムの記事ではいつも引用している、
「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、
この時代についてのジョンのコメントを引用します。
なお、引用者は、改行と一部表記の変更を行っています。
ジョン・レノン(以降JL):そう。
70年代の初めにぼくたちは別居していたんだが、
ヨーコがぼくを追放したんだ。
不意に、ぼくは、宇宙の真ん中に漂っている筏の上で
ひとりぼっちにされたのさ。
プレイボーイ(以降PB):で、どうなりました?
JL:最初はこう思ったさ。
ワーイ、万歳!
独身生活に戻ったんだもの。
ワーイ、だよ。
でも、ある日目が醒めて、考えたね。
こりゃなんだ?
おれは家に帰りたい!
でも、ヨーコは帰らせてくれなかったんだ。
(中略)
しょちゅう電話で話していて、ぼくは
「こんなのは嫌だ。ぼくはだめになりそうになっているんだ。
家に帰りたい。お願いだ」って言ってたよ。
でもヨーコは
「あなたにはまだ、家に帰る心の準備ができてないわ」
って言ったものさ。
PB:「心の準備ができていない」というのは
どういう意味だったんですか?
JL:ヨーコにはヨーコなりのやり方があるのさ。
他人にはわからないにしても。(後略)
PB:で、酒の瓶へ逆戻りですか?
JL:自分が感じていることを酒の瓶の中へ隠そうとしてただけさ。
狂っていただけなんだ。
18ヵ月続いた「失われた週末」だった。
あれほど酒を飲んだことはなかったね。
酒の瓶の中で溺れてやろうと思って、
芸能界の大酒飲みと付き合ってたよ。
PB:例えば?
JL:ハリー・ニルソン、ボビー・キーズ、キース・ムーン
といった連中だよ。
ぼくたちは自制できなかったんだ。
(中略)
まあ、とにかくひどいもんだった。
ぼくはこいつから逃げださなきゃならなかった。
(中略)
誰が先に死ぬか、といった調子だったんだ。
かわいそうに、キース(・ムーン)が先に死んだんだ。
PB:なぜそんな自滅を?
JL:ぼくについては、別居していたのが理由だった。
耐えられなかったんだ。
他の連中にもそれぞれ理由があって、
みんなで酒で溺れ死にしようじゃないかってことになったんだよ。
ぼくの立場からすれば、そのように見えたね。
(中略)
今あの時期のことを考えると嫌になるね。
自分からすすんで、大馬鹿者になったんだからな。
でも、いい教訓だったんだろうね。
ハリー・ニルソン Harry Nilssonと
ボビーキーズ Bobby Keysは
このアルバムにも参加していますが、もうひとり
キース・ムーン Keith Moonはいわずとしれた
ザ・フー The Whoのあのドラマーのことですね。
そしてリンゴ・スター Ringo Starrもこの飲み友だちだったらしく、
そのつながりでキースのソロアルバムにはリンゴも参加しています。
ジョンはここで、みんなそれぞれ問題があったと言っていますが、
ニルソンはあの、バッドフィンガー Badfingerをカバーした
Without YouがNo.1になってしまい、ソングライターとして、
歌手として、悩んでいたのでしょうかね。
02 2010年10月22日のA公園の木々の色づき

ミュージシャンの話が出たところで、このアルバムのブックレットは、
曲ごとに参加メンバーが明記されていますが、
その中からおなじみの何人かを紹介すると、
ギターのジェシ・エド・デイヴィス Jesse Ed Davis、
ベースのクラウス・フォアマン Kraus Voormann、
ドラムスのジム・ケルトナー Jim Keltner、
この3人はTr12以外のバンド演奏の全曲に参加、また
ピアノのニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins
も2、5、10、12以外に参加しています。
フォアマンはあのREVOLVERのジャケットのデザインをした朋友、
ホプキンスはRevolutionに参加とビートルズ時代からの付き合い、
ケルトナーはスタジオミュージシャンの鏡ともいえる人、
デイヴィスは飲み友だちのひとりと、そして上記のニルソンとキーズ、
それにエルトン・ジョン Elton Johnという強力な助っ人を得て、
このアルバムはなんとか作り上げられ、それなりにヒットしました。
確かに、お店の人がおすすめしてくれたのも、今では分かります(笑)。
そして、仲間というのは、何にしてもいいものですね。
このアルバムの、僕が音楽的に気になる部分を2つ。
ひとつ。
このアルバムはファンクの影響が出ていますね。
影響は、軽微なものから本格的なものまで数曲で感じられ、
曲によっては完全なファンクというのもあります。
ジョンもポール・マッカートニー同様、周りで流行っていることを
黙って見過ごせない人だったのかもしれません(笑)。
ただ、ジョンのバンドはリズムがファンクになりきれていなくて、
特にドラムスがまっすぐ進んでいて曲も垂直に近い感じを受けます。
ドラムスとは、音と音の間の音がない部分のノリの違いが
リズム感の違いとしえ感じられるのではないかと思います。
喩えていうなら、フィールドアスレチックなどでよくある、
飛び石状に置かれた丸太を渡る際に、同じ時間をかけるにしても、
歩いて進むか、小走りで進むか、跳んで進むかの違いで、
同じ時間で進み同じタイミングで丸太を踏んだとしても、
途中の感覚はぜんぜん違って感じるし外からもそう見える。
やっぱり跳ねて進むのがファンクでしょうかね。
ということに、この5年間に音楽の趣味が広がって気づきました。
もうひとつ。
このアルバムには、ジョンにしては珍しく、
曲の中で一度しか出てこない部分がある曲が多いこと。
具体的には、Tr1、3、4、5、6、11と6曲あり、
Tr12がカバーのため、それが過半となっています。
試しにアルバムIMAGINEはそれが1曲もないですし、
ビートルズでもあまり多くはないので、これは異様ともえいます。
ヨーコさんと離れて、曲作りでもいろいろ悩んで迷って、
試行錯誤をしていたのかもしれないですね。
そして、シングルヒットしたTr2とTr7にはそれがないのも、
或いは、曲作りの何かを物語っているのかもしれません。
さて、聴いてゆきますか。
なお、このアルバムについてはちょっとした問題があって、
いつもの「プレイボーイ・インタビュー」にプラスして、
後に再編された「ジョンとヨーコ ラストインタビュー」
からも引用し紹介してゆきます。
またこのアルバムは、
「心の壁、愛の橋」という邦題も素晴らしくて好きですが、
曲の邦題もなかなかいいので、今回は、邦題がある曲については
邦題も記してゆきます。
なお、このアルバムの曲の作曲者は、
ジョン・レノンひとりが書いたもの以外のみ
曲名の下に明記しました、ご了承ください。
(All songs written by John Lennon except as noted)
03 快晴の陽光を浴びるススキ

Tr1:Going Down On Love
「愛を生き抜こう」
GB:いきなり襲ってくるパーカッションの響きが、
それまで僕が体験したことがないものだったので、
ジョンがこうきたかというのがまず意表を突かれました。
ジョンも張り切って歌っていて、最上ではないけど掴みはOKという、
アルバム1曲目としてはいい感じで始まっています。
Tr2:Whatever Gets You Thru The Night
「真夜中を突っ走れ」
JL:プロデューサーのジャック・ダグラスが言ったみたいに、
これはノベルティ・レコードだ。
ビートルズを解散してから作った曲で
ナンバー・ワンまでいったのはこの曲だけだ。
ミュージシャンのできはあまりよくないけど、
詞はなかなか気に入っている。
「イマジン」なんかよりはコマーシャルではあるけどね。
「イマジン」がナンバー・ワンになり、この曲が39位になるべきだ
というのがぼくの意見だ。
どうもその辺がわかんないね。そんなものさ。
GB:当時はまさに時代の人として君臨していた
エルトン・ジョンとの世紀のデュエットが実現。
これが売れないわけがなく、ジョンのソロ初のNo.1ヒットに。
ジョンはチャートにはそれほどこだわっていなかったのかな、
と思う反面、コメントでもそのことに触れているように、やはり
ショービズに生きていた以上、関心事ではあったのですね。
なお、ビートルズのメンバーがソロでビルボードでNo.1を
獲得したのは、ジョンが4人の中でいちばん遅かったのでした。
この曲はほんとに小難しいことは一切いらない、
とにかく楽しく乗って聴き通す、それだけの曲。
ただ、僕が最初に聴いた時は、ロックンロールにしては
まっすぐではなく少しうねっていると感じたのですが、
それもファンクの影響なのかなと今にして思います。
そして僕は当時、若くてとんがったロック野郎だったせいで、
これはジョンらしくないと思い、まあ好きかなくらいでしたが、
年を経るごとにだんだんと大好きになっていきました。
"Don't need a watch to waste your time"
というくだりはジョンらしく含蓄があっていいですし。
曲はジョンひとりが書いていますが、やはりヨーコさんと離れ、
そんな気分の毎日だったのかもしれません。
だけど酒が入って突っ走れたのかな・・・(笑)・・・
そしてなんといっても、この共演がきっかけとなり、
エルトンは自らのコンサートにジョンをゲストとして招き、
その会場にヨーコさんを招待していて仲直りのきっかけを作った
という話を語らないわけにはゆかないでしょうね。
その演奏は、エルトンのライヴ盤やレノンのボックスセットで
聴くことができますが、それはまたいつかの機会にでも。
それにしてもこの曲のエルトンの癖のある鼻についた歌い方、
♪ ほぅっみぃだぁ~りんかもんっ りっすんとぅめっ
僕は今でも、聴く度に真似て歌ってしまいます(笑)。
それと、Thruとスペルを省略形にしているポップなセンスも、
受けたのかもしれません。
Tr3:Old Dirt Road
枯れた道
(music by John Lennon, lyrics by John & Harry Nilsson)
JL:ハリー・ニルソンとぼくがいっしょに書いた。
単なるひとつの歌さ。
ほら、いっしょにウォッカの瓶にへばりついていたら、
いっしょになんかやってみようかなんて気になって
できちゃったっていう曲。
GB:できちゃった、の割にはとってもいい曲だけどなぁ(笑)。
クレジットを見ると、歌詞をハリー・ニルソンと共作し、
曲はジョンひとりが書いているようですが、
ジョンの曲のクレジットに、他人の名前が入るのは珍しいですね。
これはまさに秋にぴったりの一遍。
ぽわ~っというギターの音が妙に明るく温かい響きで、
枯れているというよりは、秋にぬくもりを求めて彷徨う感じかな。
Tr4:What You Got
JL:ヨーコのことを歌ってるんだ。
ものの価値は失って初めてわかるものだ。
GB:この曲はファンクチューンと言っていいですね。
リズムやギターののりが少し斜めに動いているのを感じます。
この曲は特に、歌い方が熱いというか声が割れて荒れていると感じて、
それも酒の影響だったのかな、凄いんだけど、でも、
「凄い」という言葉に含まれる良くない面も出ているような気もします。
なお、この曲の1回しか出てこない部分にこんな歌詞があって、
"Well it's Saturday night and I just gotta rip it up"
ROCK 'N' ROLLに収められているRip It Upの歌詞を
いただいているのが面白い。
R&Rは諸事情により録音の中断が余儀なくされたわけですが、
そこで久しぶりにその曲に接して歌詞を思い出したのかな。
ジョンはつくづく、行動が素直に曲に表れる人ですね(笑)。
Tr5:Bless You
果てしなき愛(ブレッス・ユー)
JL:この曲を書いた時、ぼくは震え上がっていた。
ヨーコからまたく離れて、
自分が必要な唯一のものを失った気分だった。
ミック・ジャガーはこの曲から
「ミス・ユー」を作ったんじゃないかと思う。
スタジオで、エンジニアがぼくにこう言った。
「テンポを早くしたらヒット・ソングになるのにね」
彼は正しかった。
「ミス・ユー」はぼくの曲を早くしたものじゃないか?
ぼくはミックのレコードの方が好きだ。
ミックのしたことには何の悪感情も持ってはいない。
ミックは無意識だったかもしれないし、
そうではなかったかもしれない。
でもミュージックはすべての人の所有物なんだ。
人が所有しているなんて考えるのは、
音楽出版社くらいのものさ。
GB:僕がこのインタビューを読んだのは中学生の頃で、
実はまだジョンはおろかビートルズも聴く前だったのですが、
この話はとても印象に残っていて、特にジョンが言う
(音楽は)人が所有していると考えるのは音楽出版社くらいのものさ、
というところに感動しました。
曲はジョンが説明する通りで、僕が何か言うものでもないかな。
でも、
♪あははぁ~ ふううううう~む
というハミングは、ローリング・ストーンズ The Rolling Stones
のMiss Youに、そうですね、そっくりと言っていいですかね。
Tr6:Scared
心のしとねは何処
GB:この曲のコメントについて説明します。
古いほうの本「プレイボーイ」では、
「ミックがいただいた」のはこの曲のこととして記されていますが、
新しいほうでは、前の曲Bless Youの話となっています。
おそらくジョンが思い出していたのは前の曲のことであって、
古い本は編集の手違いでそうなったのだと思います。
しかし、こちらには"Like a rolling stone"という歌詞があって、
ミック・ジャガー Mick Jaggerはもしかして、
このアルバムはジョンが自分にあてたメッセージだと思い、
2曲セットでMiss Youに仕立て上げたのかも(笑)。
あ、ちなみに僕はMiss You大好きですよ。
僕はこの曲の重さは高校生の頃はちょっと苦手でした。
A面最後がこれというのも、なんだか放り出されたように感じました。
ブラスのアレンジはマスル・ショールズを意識してますかね。
それにしても「しとね」、僕は当時国語辞典を引きました(笑)。
04 A公園の木々のトンネルの道も色づきはまばら

Tr7:#9 Dream
夢の夢
JL:書きなぐりの曲だ。
僕が見た夢を曲にしたんだ。
GB:この曲はだけど大好きですね。
シングルカットされ、なんだかできすぎた話ですが
ビルボード誌でそれこそ9位のヒットを記録。
今回のアルバムでは、Tr2とこれがヒットしたというのは、
ジョンにしてみれば「つまらない」曲がヒットしたわけですが、
その辺の一般聴衆との感覚のずれがあったのかもしれません。
もちろんヒットするからいい曲だ、ヒットしない曲こそいい曲だ、
僕はどちらにもくみしない、というかどちらもアリの人間ですが。
この曲を聴くと、薄紫に染まった朝焼け雲の上にいる気分になります。
夢を歌っていますが、"Seems so real to me"という部分が印象的。
サビの英語ではない謎の言葉も、Across The Universに続いて、
ジョンの言葉遊びの楽しさを感じます。
女声コーラスにはもちろんヨーコさんはいませんが、
その辺りもまた複雑な「失われた週末」を物語っています。
Tr8:Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox)
予期せぬ驚き
JL:ただのくだらない曲だよ。
GB:あらら身も蓋もない・・・
ユーモラスなギターの響きのイントロはファンクだけど、
歌が始まると普通のジョン・レノン節という感じですね。
鳥が出てくるのは鳥好きにはうれしいです(笑)。
ダブルトラックのヴォーカルが炸裂し熱さを強調しています。
でも、もう少しソフトに歌えば、もっと優しい響きの曲だったのに・・・
Tr9:Steel And Glass
鋼(はがね)のように、ガラスの如く
JL:何か辛辣な曲を書きたいと思ったが、
気分がさほどのらなかった。
でも音楽的には面白いものが盛りこめた。
GB:重々しく、ある意味このアルバムを表象する曲かな。
僕は後にHow Do You Sleep ?を聴き、これに似ていると思いました。
なお、こちらのほうが後ですが、僕はこちらを先に聴きました。
だからこれは、ジョン流のブルーズPart2という感じですかね。
そう思って今回のリマスター盤のヨーコさんの解説を読むと、
そのようなことが書いてありました。
ジョンが声を伸ばして苦しそうに歌うのも印象的ですが、
そのバックのストリングスがどこまで音が上っていくのと
聴きながら戸惑うくらいの緊迫感でジョンの心をなぞっています。
Tr10:Beef Jerky
GB:ビーフジャーキーはお酒のよいお伴(笑)。
この曲のクレジットには面白いことが書いてあります。
Guitars:Booker Table and the Maitre d's
ジョンは、ブッカーT&MG's Booker T. & MG'sのヒット曲
Green Onionsのような
インストゥルメンタルの聴きやすい曲を作りたかったのかな。
しかしこれもドラムスはまっすぐに進んでいて粘りがないですね。
いつも言いますが、僕は当時はLPをカセットテープに録音して
寝る前にかけて聴いていましたが、この曲は、Aメロの途中で
6拍子になるのが、半分眠い中で妙に気になりました。
賑やかな掛け声も、UFOのようなSEも当時は意味不明でした。
あ、今でも意味不明ですが、でも、妙なかたちで印象に残る
そんな曲ではあると思います。
それから、このアルバムは全体に、クラウスのベースの音が、
「ブンブン」と「ゴロンゴロン」の間という感じの
太くて丸い音で迫ってきます。
Tr11:Nobody Loves You (When You're Down And Out)
愛の不毛
JL:そうさ、タイトルがすべてを語っているよ。
ヨーコと離れていた期間のぼくがまさにこの通りだった。
ぼくはいつも、フランク・シナトラがこれを歌ったら
どうなるだろうって思うんだ。
理由はわからないけど、
これはいわゆるシナトラ・エスク(風)だよ。
彼ならきっと完全に歌いこなすだろう。
聞いてるかい、シナトラ君。
きいには何の意味もない曲以外のものが必要なんだ。
ほら、この曲をあげよう。
ホーンのアレンジからなにからみんな君のためにできてる。
だけど、お願いだからぼくにプロデュースしてくれ
なんて言わないでくれよ。
GB:ジョンの自信家ぶりがあふれるコメントですね。
Bメロがもがくようにたどたどしく歌っているけど、
全体として妙にすがすがしい響きの曲なのはどうしてかな。
この曲の味付け過剰は、僕は最初に聴いて思いました。
最初は静かに始まるので、そのまま進んでくれればよかったのに・・・
とはいえもちろん好きですし、僕は隠れた名曲だと思っていて、
アコースティックギター1本で歌うといい感じになるのではないかと。
曲名はエリック・クラプトン Eric Claptonも歌っている
ブルーズの名曲のタイトルをもじったものでしょう。
そして、この曲の歌詞にはこんなくだり
♪ Nobody sees you when you're on cloud 9
がありますが、ジョージ・ハリスン George Harrisonが
CLOUD NINEをリリースした際にこの歌詞を思い出し、
ジョージはそこからとったのかなと思ったのですが、
実はテンプテーションズ The Temptationsが60年代に
アルバムCLOUD NINE(記事はこちら)を出していて、
そこが大元であると分かりました。
まあ"cloud nine"は辞書にも載っている慣用句ですが、
テンプスのそれが、音楽マニアであったジョンやジョージの
頭にないなんてことは、考えてみれば逆に不自然ですからね。
こうして音楽のつながりを感じるのは、楽しいことですね。
Tr12:Ya Ya
(M.Robinson / L. Dorsey / C. L. Lewis)
JL:裁判の結果、契約上の義務でモリス・レヴィに書いた曲。
みっともない話で、なんでそんなことになったのかと後悔もしたけど、
事実は事実。
そうなってしまったんだから。
ジュリアンがドラムを叩き、ぼくはピアノに向かって
"Ya Ya"と歌った。
GB:先日のROCK 'N' ROLLの記事でも触れましたが、
ビートルズのCome Togetherが
チャック・ベリー Chuck BerryのYou Can't Catch Meの
盗作ではないかと問題になった結果、録音したもの。
ただ、ジョンは勘違いか何かで「書いた」と話していたようですが、
もちろん「歌った」でしょうね。
事実は事実と認めているジョンの潔さは人間としてほっとします。
ジュリアン・レノン Julian Lennonがドラムスということですが、
ヨーコさんと離れ、家族の絆が欲しかったのでしょうかね。
この曲を歌うことになったきっかけはきっかけとして、
ジョンらしい曲でアルバムが終わります。
恒例、Amazonでの2010年10月22日時点でのランキング、
国内盤10,757位、輸入盤が55,624位。
ちなみにボックスセットは国内盤322位、輸入盤925位と、
やはりまだ、買う人は箱で買っているようですね。
何度も言いますが、このアルバムは、
ジョンがヨーコさんと離れている時期に作られて
確かに重たい、孤独を感じる曲でありアルバムですが、でも、
聴いていてこちらがめいってしまうというほどではなく、
耐えられないほど深刻ということでもないと思うようになりました。
或いは、心を紛らせていたことがポジティヴな響きになったのか。
そしてジョンは意外とオプティミストであり、だめな人間であるかのように
歌の中で振舞ってはみても、芯はしっかりしている人間、
そんな感じがしてきました。
何よりエンターテイメントの中で生きていた人間なので、
自らの気持ちの暗い部分を曲に反映させてはいても、
聴く人には何か前向きなものを残したかったのでしょうね。
まあ、今となっては、ヨーコさんのもとに戻った事実を知って
聴いているので、その部分がそうさせるのかもしれません。
もうとつ、愛する人も大切だけど仲間も大切、ということも、
ジョンの話や出来あがった意外と前向きな音楽からも感じます。
だから、やっぱりこのアルバムは大好きですね。
ただ、良さが分かるのに、高校生には少し早かったかな(笑)。
05

最後に。
本日、2010年10月22日、
guitarbirdのBLOG「自然と音楽を愛する者」は
5周年を迎えました。
今までお読みいただいたみなさま、
ありがとうございます!
ここまで続けてこられたのは、
ひとえに読んでいただけるみなさまのおかげです。
5年というのはひとつの節目ともいえますが、
僕は今のところ今後も続けてゆくつもりですあり、
しかし感謝の気持ちはお伝えしたく、
長い記事の最後に隠れるように、あっさりとそのことに触れ、
これからも先に進ませていただきたいと思います。
しかし、5年という節目ではあるので、
今年はジョン・レノンのアルバムを
この日に記事にさせていただきました(笑)。
これからもよろしくお願いします。
追伸:ちなみに、毎年話していますが、
当時はまだBLOGのことがよく分からず、
翌日に誤ってその記事に上書きして違う記事としてしまったがために、
2005年10月22日の記事は、間抜けなことに、残っていないのです。
だから見かけ上は10月23日に始まったように見えますが、
勘違いではありません、ご了承ください(笑)。

WALLS AND BRIDGES John Lennon
心の壁、愛の橋 ジョン・レノン (1974)
新しいリマスター盤とボックスセットが出た勢いで、
今日もジョン・レノンいきます。
今回については、今日に記事を上げることに少し意味があります。
このアルバムは、5年前に前のリマスター盤がリリースされ、
その頃にBLOGを始めたばかりの僕は一度記事にしていました。
しかし、その間にいろいろと分かったことがあって、
新リマスター盤記念でまた記事にすることにしました。
人間は幾つになっても学んでゆくものなんだなと。
このアルバムは、ジョン・レノン名義の
スタジオ録音の新録音の曲が入ったアルバムとして数えると、
ソロ5枚目のアルバムということになります。
これは、僕が高校時代、最初に買ったジョンのソロのLPでした。
最初に聴いたのは、借りていてそのまま僕のものになった
ROCK 'N' ROLLであることは前の記事(こちら)でも触れました。
当時は、いつもビートルズのLPを買いに行くレコード店が2軒あり、
そのうちの1軒「キクヤ」に、当時35歳くらいの洋楽担当の男性がいて、
その人と仲良くなり、ビートルズのグッズをもらったりしていました。
或る日、当時はまだジョンのソロアルバムを買ったことがなかったので、
そろそろどれか買いたいけど何がいいですかと店員さんに聞くと、
その人はこれをすすめたので、その場で買って帰りました。
第一印象は・・・
とにかくジョンのヴォーカルが熱い、もうひとつ、
音がすっきりしないで不必要なくらいに厚い、でした。
ジョン自身のプロデュースですが、ジョンという人は
あまり全体を見通せる人じゃないのかなとも思いました。
それは違う、このアルバムは狙ったものかもしれないのですが、
僕は、スカッとした感じがなくて、重たい雰囲気を感じ取りました。
ただ、まとわりつくような歌はさすがジョンで、暫く聴き込みました。
このアルバムは、ヨーコさんと別れていた期間、
いわば「失われた週末」時代に作られたアルバムですが、
当時の僕の感想は実は、単に音楽を聴いてそう感じただけではなく、
書籍などで予備知識を「刷り込まれた」状態でのものだったので、
余計にこのアルバムはとっても重たく感じました。
ほんとはそれはよくないのかもしれないですが、
当時は好奇心が旺盛だったので、仕方ないですかね。
ここで本日は、ビートルズ The Beatlesや
ジョンのアルバムの記事ではいつも引用している、
「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、
この時代についてのジョンのコメントを引用します。
なお、引用者は、改行と一部表記の変更を行っています。
ジョン・レノン(以降JL):そう。
70年代の初めにぼくたちは別居していたんだが、
ヨーコがぼくを追放したんだ。
不意に、ぼくは、宇宙の真ん中に漂っている筏の上で
ひとりぼっちにされたのさ。
プレイボーイ(以降PB):で、どうなりました?
JL:最初はこう思ったさ。
ワーイ、万歳!
独身生活に戻ったんだもの。
ワーイ、だよ。
でも、ある日目が醒めて、考えたね。
こりゃなんだ?
おれは家に帰りたい!
でも、ヨーコは帰らせてくれなかったんだ。
(中略)
しょちゅう電話で話していて、ぼくは
「こんなのは嫌だ。ぼくはだめになりそうになっているんだ。
家に帰りたい。お願いだ」って言ってたよ。
でもヨーコは
「あなたにはまだ、家に帰る心の準備ができてないわ」
って言ったものさ。
PB:「心の準備ができていない」というのは
どういう意味だったんですか?
JL:ヨーコにはヨーコなりのやり方があるのさ。
他人にはわからないにしても。(後略)
PB:で、酒の瓶へ逆戻りですか?
JL:自分が感じていることを酒の瓶の中へ隠そうとしてただけさ。
狂っていただけなんだ。
18ヵ月続いた「失われた週末」だった。
あれほど酒を飲んだことはなかったね。
酒の瓶の中で溺れてやろうと思って、
芸能界の大酒飲みと付き合ってたよ。
PB:例えば?
JL:ハリー・ニルソン、ボビー・キーズ、キース・ムーン
といった連中だよ。
ぼくたちは自制できなかったんだ。
(中略)
まあ、とにかくひどいもんだった。
ぼくはこいつから逃げださなきゃならなかった。
(中略)
誰が先に死ぬか、といった調子だったんだ。
かわいそうに、キース(・ムーン)が先に死んだんだ。
PB:なぜそんな自滅を?
JL:ぼくについては、別居していたのが理由だった。
耐えられなかったんだ。
他の連中にもそれぞれ理由があって、
みんなで酒で溺れ死にしようじゃないかってことになったんだよ。
ぼくの立場からすれば、そのように見えたね。
(中略)
今あの時期のことを考えると嫌になるね。
自分からすすんで、大馬鹿者になったんだからな。
でも、いい教訓だったんだろうね。
ハリー・ニルソン Harry Nilssonと
ボビーキーズ Bobby Keysは
このアルバムにも参加していますが、もうひとり
キース・ムーン Keith Moonはいわずとしれた
ザ・フー The Whoのあのドラマーのことですね。
そしてリンゴ・スター Ringo Starrもこの飲み友だちだったらしく、
そのつながりでキースのソロアルバムにはリンゴも参加しています。
ジョンはここで、みんなそれぞれ問題があったと言っていますが、
ニルソンはあの、バッドフィンガー Badfingerをカバーした
Without YouがNo.1になってしまい、ソングライターとして、
歌手として、悩んでいたのでしょうかね。
02 2010年10月22日のA公園の木々の色づき

ミュージシャンの話が出たところで、このアルバムのブックレットは、
曲ごとに参加メンバーが明記されていますが、
その中からおなじみの何人かを紹介すると、
ギターのジェシ・エド・デイヴィス Jesse Ed Davis、
ベースのクラウス・フォアマン Kraus Voormann、
ドラムスのジム・ケルトナー Jim Keltner、
この3人はTr12以外のバンド演奏の全曲に参加、また
ピアノのニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins
も2、5、10、12以外に参加しています。
フォアマンはあのREVOLVERのジャケットのデザインをした朋友、
ホプキンスはRevolutionに参加とビートルズ時代からの付き合い、
ケルトナーはスタジオミュージシャンの鏡ともいえる人、
デイヴィスは飲み友だちのひとりと、そして上記のニルソンとキーズ、
それにエルトン・ジョン Elton Johnという強力な助っ人を得て、
このアルバムはなんとか作り上げられ、それなりにヒットしました。
確かに、お店の人がおすすめしてくれたのも、今では分かります(笑)。
そして、仲間というのは、何にしてもいいものですね。
このアルバムの、僕が音楽的に気になる部分を2つ。
ひとつ。
このアルバムはファンクの影響が出ていますね。
影響は、軽微なものから本格的なものまで数曲で感じられ、
曲によっては完全なファンクというのもあります。
ジョンもポール・マッカートニー同様、周りで流行っていることを
黙って見過ごせない人だったのかもしれません(笑)。
ただ、ジョンのバンドはリズムがファンクになりきれていなくて、
特にドラムスがまっすぐ進んでいて曲も垂直に近い感じを受けます。
ドラムスとは、音と音の間の音がない部分のノリの違いが
リズム感の違いとしえ感じられるのではないかと思います。
喩えていうなら、フィールドアスレチックなどでよくある、
飛び石状に置かれた丸太を渡る際に、同じ時間をかけるにしても、
歩いて進むか、小走りで進むか、跳んで進むかの違いで、
同じ時間で進み同じタイミングで丸太を踏んだとしても、
途中の感覚はぜんぜん違って感じるし外からもそう見える。
やっぱり跳ねて進むのがファンクでしょうかね。
ということに、この5年間に音楽の趣味が広がって気づきました。
もうひとつ。
このアルバムには、ジョンにしては珍しく、
曲の中で一度しか出てこない部分がある曲が多いこと。
具体的には、Tr1、3、4、5、6、11と6曲あり、
Tr12がカバーのため、それが過半となっています。
試しにアルバムIMAGINEはそれが1曲もないですし、
ビートルズでもあまり多くはないので、これは異様ともえいます。
ヨーコさんと離れて、曲作りでもいろいろ悩んで迷って、
試行錯誤をしていたのかもしれないですね。
そして、シングルヒットしたTr2とTr7にはそれがないのも、
或いは、曲作りの何かを物語っているのかもしれません。
さて、聴いてゆきますか。
なお、このアルバムについてはちょっとした問題があって、
いつもの「プレイボーイ・インタビュー」にプラスして、
後に再編された「ジョンとヨーコ ラストインタビュー」
からも引用し紹介してゆきます。
またこのアルバムは、
「心の壁、愛の橋」という邦題も素晴らしくて好きですが、
曲の邦題もなかなかいいので、今回は、邦題がある曲については
邦題も記してゆきます。
なお、このアルバムの曲の作曲者は、
ジョン・レノンひとりが書いたもの以外のみ
曲名の下に明記しました、ご了承ください。
(All songs written by John Lennon except as noted)
03 快晴の陽光を浴びるススキ

Tr1:Going Down On Love
「愛を生き抜こう」
GB:いきなり襲ってくるパーカッションの響きが、
それまで僕が体験したことがないものだったので、
ジョンがこうきたかというのがまず意表を突かれました。
ジョンも張り切って歌っていて、最上ではないけど掴みはOKという、
アルバム1曲目としてはいい感じで始まっています。
Tr2:Whatever Gets You Thru The Night
「真夜中を突っ走れ」
JL:プロデューサーのジャック・ダグラスが言ったみたいに、
これはノベルティ・レコードだ。
ビートルズを解散してから作った曲で
ナンバー・ワンまでいったのはこの曲だけだ。
ミュージシャンのできはあまりよくないけど、
詞はなかなか気に入っている。
「イマジン」なんかよりはコマーシャルではあるけどね。
「イマジン」がナンバー・ワンになり、この曲が39位になるべきだ
というのがぼくの意見だ。
どうもその辺がわかんないね。そんなものさ。
GB:当時はまさに時代の人として君臨していた
エルトン・ジョンとの世紀のデュエットが実現。
これが売れないわけがなく、ジョンのソロ初のNo.1ヒットに。
ジョンはチャートにはそれほどこだわっていなかったのかな、
と思う反面、コメントでもそのことに触れているように、やはり
ショービズに生きていた以上、関心事ではあったのですね。
なお、ビートルズのメンバーがソロでビルボードでNo.1を
獲得したのは、ジョンが4人の中でいちばん遅かったのでした。
この曲はほんとに小難しいことは一切いらない、
とにかく楽しく乗って聴き通す、それだけの曲。
ただ、僕が最初に聴いた時は、ロックンロールにしては
まっすぐではなく少しうねっていると感じたのですが、
それもファンクの影響なのかなと今にして思います。
そして僕は当時、若くてとんがったロック野郎だったせいで、
これはジョンらしくないと思い、まあ好きかなくらいでしたが、
年を経るごとにだんだんと大好きになっていきました。
"Don't need a watch to waste your time"
というくだりはジョンらしく含蓄があっていいですし。
曲はジョンひとりが書いていますが、やはりヨーコさんと離れ、
そんな気分の毎日だったのかもしれません。
だけど酒が入って突っ走れたのかな・・・(笑)・・・
そしてなんといっても、この共演がきっかけとなり、
エルトンは自らのコンサートにジョンをゲストとして招き、
その会場にヨーコさんを招待していて仲直りのきっかけを作った
という話を語らないわけにはゆかないでしょうね。
その演奏は、エルトンのライヴ盤やレノンのボックスセットで
聴くことができますが、それはまたいつかの機会にでも。
それにしてもこの曲のエルトンの癖のある鼻についた歌い方、
♪ ほぅっみぃだぁ~りんかもんっ りっすんとぅめっ
僕は今でも、聴く度に真似て歌ってしまいます(笑)。
それと、Thruとスペルを省略形にしているポップなセンスも、
受けたのかもしれません。
Tr3:Old Dirt Road
枯れた道
(music by John Lennon, lyrics by John & Harry Nilsson)
JL:ハリー・ニルソンとぼくがいっしょに書いた。
単なるひとつの歌さ。
ほら、いっしょにウォッカの瓶にへばりついていたら、
いっしょになんかやってみようかなんて気になって
できちゃったっていう曲。
GB:できちゃった、の割にはとってもいい曲だけどなぁ(笑)。
クレジットを見ると、歌詞をハリー・ニルソンと共作し、
曲はジョンひとりが書いているようですが、
ジョンの曲のクレジットに、他人の名前が入るのは珍しいですね。
これはまさに秋にぴったりの一遍。
ぽわ~っというギターの音が妙に明るく温かい響きで、
枯れているというよりは、秋にぬくもりを求めて彷徨う感じかな。
Tr4:What You Got
JL:ヨーコのことを歌ってるんだ。
ものの価値は失って初めてわかるものだ。
GB:この曲はファンクチューンと言っていいですね。
リズムやギターののりが少し斜めに動いているのを感じます。
この曲は特に、歌い方が熱いというか声が割れて荒れていると感じて、
それも酒の影響だったのかな、凄いんだけど、でも、
「凄い」という言葉に含まれる良くない面も出ているような気もします。
なお、この曲の1回しか出てこない部分にこんな歌詞があって、
"Well it's Saturday night and I just gotta rip it up"
ROCK 'N' ROLLに収められているRip It Upの歌詞を
いただいているのが面白い。
R&Rは諸事情により録音の中断が余儀なくされたわけですが、
そこで久しぶりにその曲に接して歌詞を思い出したのかな。
ジョンはつくづく、行動が素直に曲に表れる人ですね(笑)。
Tr5:Bless You
果てしなき愛(ブレッス・ユー)
JL:この曲を書いた時、ぼくは震え上がっていた。
ヨーコからまたく離れて、
自分が必要な唯一のものを失った気分だった。
ミック・ジャガーはこの曲から
「ミス・ユー」を作ったんじゃないかと思う。
スタジオで、エンジニアがぼくにこう言った。
「テンポを早くしたらヒット・ソングになるのにね」
彼は正しかった。
「ミス・ユー」はぼくの曲を早くしたものじゃないか?
ぼくはミックのレコードの方が好きだ。
ミックのしたことには何の悪感情も持ってはいない。
ミックは無意識だったかもしれないし、
そうではなかったかもしれない。
でもミュージックはすべての人の所有物なんだ。
人が所有しているなんて考えるのは、
音楽出版社くらいのものさ。
GB:僕がこのインタビューを読んだのは中学生の頃で、
実はまだジョンはおろかビートルズも聴く前だったのですが、
この話はとても印象に残っていて、特にジョンが言う
(音楽は)人が所有していると考えるのは音楽出版社くらいのものさ、
というところに感動しました。
曲はジョンが説明する通りで、僕が何か言うものでもないかな。
でも、
♪あははぁ~ ふううううう~む
というハミングは、ローリング・ストーンズ The Rolling Stones
のMiss Youに、そうですね、そっくりと言っていいですかね。
Tr6:Scared
心のしとねは何処
GB:この曲のコメントについて説明します。
古いほうの本「プレイボーイ」では、
「ミックがいただいた」のはこの曲のこととして記されていますが、
新しいほうでは、前の曲Bless Youの話となっています。
おそらくジョンが思い出していたのは前の曲のことであって、
古い本は編集の手違いでそうなったのだと思います。
しかし、こちらには"Like a rolling stone"という歌詞があって、
ミック・ジャガー Mick Jaggerはもしかして、
このアルバムはジョンが自分にあてたメッセージだと思い、
2曲セットでMiss Youに仕立て上げたのかも(笑)。
あ、ちなみに僕はMiss You大好きですよ。
僕はこの曲の重さは高校生の頃はちょっと苦手でした。
A面最後がこれというのも、なんだか放り出されたように感じました。
ブラスのアレンジはマスル・ショールズを意識してますかね。
それにしても「しとね」、僕は当時国語辞典を引きました(笑)。
04 A公園の木々のトンネルの道も色づきはまばら

Tr7:#9 Dream
夢の夢
JL:書きなぐりの曲だ。
僕が見た夢を曲にしたんだ。
GB:この曲はだけど大好きですね。
シングルカットされ、なんだかできすぎた話ですが
ビルボード誌でそれこそ9位のヒットを記録。
今回のアルバムでは、Tr2とこれがヒットしたというのは、
ジョンにしてみれば「つまらない」曲がヒットしたわけですが、
その辺の一般聴衆との感覚のずれがあったのかもしれません。
もちろんヒットするからいい曲だ、ヒットしない曲こそいい曲だ、
僕はどちらにもくみしない、というかどちらもアリの人間ですが。
この曲を聴くと、薄紫に染まった朝焼け雲の上にいる気分になります。
夢を歌っていますが、"Seems so real to me"という部分が印象的。
サビの英語ではない謎の言葉も、Across The Universに続いて、
ジョンの言葉遊びの楽しさを感じます。
女声コーラスにはもちろんヨーコさんはいませんが、
その辺りもまた複雑な「失われた週末」を物語っています。
Tr8:Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox)
予期せぬ驚き
JL:ただのくだらない曲だよ。
GB:あらら身も蓋もない・・・
ユーモラスなギターの響きのイントロはファンクだけど、
歌が始まると普通のジョン・レノン節という感じですね。
鳥が出てくるのは鳥好きにはうれしいです(笑)。
ダブルトラックのヴォーカルが炸裂し熱さを強調しています。
でも、もう少しソフトに歌えば、もっと優しい響きの曲だったのに・・・
Tr9:Steel And Glass
鋼(はがね)のように、ガラスの如く
JL:何か辛辣な曲を書きたいと思ったが、
気分がさほどのらなかった。
でも音楽的には面白いものが盛りこめた。
GB:重々しく、ある意味このアルバムを表象する曲かな。
僕は後にHow Do You Sleep ?を聴き、これに似ていると思いました。
なお、こちらのほうが後ですが、僕はこちらを先に聴きました。
だからこれは、ジョン流のブルーズPart2という感じですかね。
そう思って今回のリマスター盤のヨーコさんの解説を読むと、
そのようなことが書いてありました。
ジョンが声を伸ばして苦しそうに歌うのも印象的ですが、
そのバックのストリングスがどこまで音が上っていくのと
聴きながら戸惑うくらいの緊迫感でジョンの心をなぞっています。
Tr10:Beef Jerky
GB:ビーフジャーキーはお酒のよいお伴(笑)。
この曲のクレジットには面白いことが書いてあります。
Guitars:Booker Table and the Maitre d's
ジョンは、ブッカーT&MG's Booker T. & MG'sのヒット曲
Green Onionsのような
インストゥルメンタルの聴きやすい曲を作りたかったのかな。
しかしこれもドラムスはまっすぐに進んでいて粘りがないですね。
いつも言いますが、僕は当時はLPをカセットテープに録音して
寝る前にかけて聴いていましたが、この曲は、Aメロの途中で
6拍子になるのが、半分眠い中で妙に気になりました。
賑やかな掛け声も、UFOのようなSEも当時は意味不明でした。
あ、今でも意味不明ですが、でも、妙なかたちで印象に残る
そんな曲ではあると思います。
それから、このアルバムは全体に、クラウスのベースの音が、
「ブンブン」と「ゴロンゴロン」の間という感じの
太くて丸い音で迫ってきます。
Tr11:Nobody Loves You (When You're Down And Out)
愛の不毛
JL:そうさ、タイトルがすべてを語っているよ。
ヨーコと離れていた期間のぼくがまさにこの通りだった。
ぼくはいつも、フランク・シナトラがこれを歌ったら
どうなるだろうって思うんだ。
理由はわからないけど、
これはいわゆるシナトラ・エスク(風)だよ。
彼ならきっと完全に歌いこなすだろう。
聞いてるかい、シナトラ君。
きいには何の意味もない曲以外のものが必要なんだ。
ほら、この曲をあげよう。
ホーンのアレンジからなにからみんな君のためにできてる。
だけど、お願いだからぼくにプロデュースしてくれ
なんて言わないでくれよ。
GB:ジョンの自信家ぶりがあふれるコメントですね。
Bメロがもがくようにたどたどしく歌っているけど、
全体として妙にすがすがしい響きの曲なのはどうしてかな。
この曲の味付け過剰は、僕は最初に聴いて思いました。
最初は静かに始まるので、そのまま進んでくれればよかったのに・・・
とはいえもちろん好きですし、僕は隠れた名曲だと思っていて、
アコースティックギター1本で歌うといい感じになるのではないかと。
曲名はエリック・クラプトン Eric Claptonも歌っている
ブルーズの名曲のタイトルをもじったものでしょう。
そして、この曲の歌詞にはこんなくだり
♪ Nobody sees you when you're on cloud 9
がありますが、ジョージ・ハリスン George Harrisonが
CLOUD NINEをリリースした際にこの歌詞を思い出し、
ジョージはそこからとったのかなと思ったのですが、
実はテンプテーションズ The Temptationsが60年代に
アルバムCLOUD NINE(記事はこちら)を出していて、
そこが大元であると分かりました。
まあ"cloud nine"は辞書にも載っている慣用句ですが、
テンプスのそれが、音楽マニアであったジョンやジョージの
頭にないなんてことは、考えてみれば逆に不自然ですからね。
こうして音楽のつながりを感じるのは、楽しいことですね。
Tr12:Ya Ya
(M.Robinson / L. Dorsey / C. L. Lewis)
JL:裁判の結果、契約上の義務でモリス・レヴィに書いた曲。
みっともない話で、なんでそんなことになったのかと後悔もしたけど、
事実は事実。
そうなってしまったんだから。
ジュリアンがドラムを叩き、ぼくはピアノに向かって
"Ya Ya"と歌った。
GB:先日のROCK 'N' ROLLの記事でも触れましたが、
ビートルズのCome Togetherが
チャック・ベリー Chuck BerryのYou Can't Catch Meの
盗作ではないかと問題になった結果、録音したもの。
ただ、ジョンは勘違いか何かで「書いた」と話していたようですが、
もちろん「歌った」でしょうね。
事実は事実と認めているジョンの潔さは人間としてほっとします。
ジュリアン・レノン Julian Lennonがドラムスということですが、
ヨーコさんと離れ、家族の絆が欲しかったのでしょうかね。
この曲を歌うことになったきっかけはきっかけとして、
ジョンらしい曲でアルバムが終わります。
恒例、Amazonでの2010年10月22日時点でのランキング、
国内盤10,757位、輸入盤が55,624位。
ちなみにボックスセットは国内盤322位、輸入盤925位と、
やはりまだ、買う人は箱で買っているようですね。
何度も言いますが、このアルバムは、
ジョンがヨーコさんと離れている時期に作られて
確かに重たい、孤独を感じる曲でありアルバムですが、でも、
聴いていてこちらがめいってしまうというほどではなく、
耐えられないほど深刻ということでもないと思うようになりました。
或いは、心を紛らせていたことがポジティヴな響きになったのか。
そしてジョンは意外とオプティミストであり、だめな人間であるかのように
歌の中で振舞ってはみても、芯はしっかりしている人間、
そんな感じがしてきました。
何よりエンターテイメントの中で生きていた人間なので、
自らの気持ちの暗い部分を曲に反映させてはいても、
聴く人には何か前向きなものを残したかったのでしょうね。
まあ、今となっては、ヨーコさんのもとに戻った事実を知って
聴いているので、その部分がそうさせるのかもしれません。
もうとつ、愛する人も大切だけど仲間も大切、ということも、
ジョンの話や出来あがった意外と前向きな音楽からも感じます。
だから、やっぱりこのアルバムは大好きですね。
ただ、良さが分かるのに、高校生には少し早かったかな(笑)。
05

最後に。
本日、2010年10月22日、
guitarbirdのBLOG「自然と音楽を愛する者」は
5周年を迎えました。
今までお読みいただいたみなさま、
ありがとうございます!
ここまで続けてこられたのは、
ひとえに読んでいただけるみなさまのおかげです。
5年というのはひとつの節目ともいえますが、
僕は今のところ今後も続けてゆくつもりですあり、
しかし感謝の気持ちはお伝えしたく、
長い記事の最後に隠れるように、あっさりとそのことに触れ、
これからも先に進ませていただきたいと思います。
しかし、5年という節目ではあるので、
今年はジョン・レノンのアルバムを
この日に記事にさせていただきました(笑)。
これからもよろしくお願いします。
追伸:ちなみに、毎年話していますが、
当時はまだBLOGのことがよく分からず、
翌日に誤ってその記事に上書きして違う記事としてしまったがために、
2005年10月22日の記事は、間抜けなことに、残っていないのです。
だから見かけ上は10月23日に始まったように見えますが、
勘違いではありません、ご了承ください(笑)。
2013年10月09日
MIND GAMES ジョン・レノン
01

MIND GAMES John Lennon
マインド・ゲームス(ヌートピア宣言) ジョン・レノン
10月9日はジョン・レノンの誕生日
今年で73歳、になっていたはず
ジョンおめでとう!
毎年ジョン・レノンのアルバムを記事にしていますが、
と思ったけど無理矢理ジョンにこじつけた年もあったっけ(笑)、
ともあれこの日は毎年、ジョンへの思いを記事にしています。
今年は素直にアルバムを取り上げます。
ジョン・レノンの、ビートルズ解散後の、
スタジオ録音の新曲が含まれたアルバムとしては4作目。
この前がライヴを含んだ変則的な2枚組でした。
このアルバムは、僕が中高生の頃は世間の評価があまり高くなく、
ジョン・レノンが好きな人だから聴ける、でも少々地味だ、
みたいな言われ方をしていました。
だから、と評論家のせいにしていますが(笑)、
僕はこのアルバム、二十歳を過ぎて、CDで初めて聴きました。
でも、初めて聴いて、こんなにもいいのは予想外でした。
つくづく、評論家の言うことを鵜呑みにしてはいけない、と・・・
まあ、その頃はもう僕の中でジョンへの信心みたいなものが
固まっていたので素直に受け入れられたのかもですが。
なんといっても曲がみな素晴らしい。
歌が基本の僕としてはすんなりと心の奥まで入ってきました。
ここでのジョンの音楽は楽観的な雰囲気、悪く言えば緩い。
ヨーコさんとの生活が刺激から安定に変わってきた
と感じていた時期なのかな。
しかし、皮肉にも、この後でジョンとヨーコは別居することになり、
ジョンは家を飛び出し、「失われた週末」が始まるのでした。
お互いに安定よりは刺激の人間だったのかもしれない。
このアルバムは、ギターのデヴィッド・スピノザ、
サックスのマイケル・ブレッカーそしておなじみジム・ケルトナー
といったニューヨークのミュージシャンを迎えて録音しています。
でも、このアルバムがいまいち評価が高くなかったのは、
ジョン・レノンにこのサウンドは合わないと感じた人が多かったのかな。
前作までは身内で固めたバンドらしいサウンドでしたが、
いきなりプロの音を身にまとって出て来たことに違和感があった。
しかも、ジョンの力唱型のヴォーカルスタイルが、
都会風のこじゃれた音に合わない感じもしないでもないし。
まあ、ジョンだって最新のサウンドには気持ちが動かされたでしょうし、
ニューヨークに移り住んでその音楽に刺激を受けないわけがない。
ジョンも、悪く言えば節操がないんだけど、やりたいと思ったことを
素直にやれる実行力があるのはさすがというか。
でも、ロックの魅力のひとつは、自分と異質なものを受け入れた上で
ぎこちなく表現することだから、このアルバムの違和感は、
すなわち、ロック本来の魅力だと言えるのではないか。
このアルバムは、だからこそ面白い。
音楽の世界においてあれだけのものを作り上げておきながら、
新たにぎこちないものを作ってしまったジョン・レノンという人が。
ポール・マッカートニーが自分の道を進んでいたのとは対照的。
でも、ジョンにとってはそうすることが自然だったのでしょう。
曲も、ヒットソングが並んでいるというよりは、
ちょっとしたスケッチ、しかし中身の濃いスケッチが
並んでいるといった趣きがあります。
曲はすべてジョン・レノンが作曲しています。
02 「心のゲーム」ハウ編

Tr1:Mind Games
この曲には例のジョン自身によるコメントがあります。
いつもの『プレイボーイ・インタビュー』から引用しますが、
引用者は適宜表記変更及び改行を施しています。
JL:この曲はもともと"Make Love Not War"と呼ばれていた。
でも今じゃもう口にできないほど陳腐な言葉になってしまった。
だから、僕は同じ意味のメッセージを別の言葉で書いたんだ。
"Mind games, mind guerrilla"ってね。
Imagineなんかと同じだよ。
これはいい演奏さ。
いつ聞いてもこのサウンドはいいな。
ぼくたちが60年代にずっと言い続けてきたこと
-ラヴ・アンド・ピースをその言葉を使わないで
表現しただけのことだ。
ラヴ・アンド・ピースなんてもうジョークになっちゃったものね。
GB:この曲は僕もほんとうに好きです。
ジョンの曲で好きな10曲を選ぶと必ず入るし、ジョンの歌の中でも
僕が何気なく口ずさむことが極めて多い1曲でもあります。
ジョンはサウンドがいいなと言っていますが、ほんとうにそう。
地平線を前にした暖かい日の夜明け、というイメージ、僕には。
まあそれはジャケットのイメージを引きずっているのですが。
イントロからずっと流れるジョンの短いスライド奏法のギターが、
まるで鐘の音のように鳴り響き続けている。
鐘の音は祈りの音、ジョンのメッセージが音でも巧く表されている。
"Love is the answer""Yes is the answer"というのは
ジョンがほんとうに訴えたかったことをこれ以上ないほど
簡潔にかつ深く表したくだりで感動します。
この曲について話し始めると優に記事ひとつになってしまうので、
続きはまたの機会ということで、次の曲に進みます。
Tr2:Tight A$
アメリカ移住を機にアメリカをおちょくってみた曲名。
"Tight as ..."と歌っていくのでこのA$は「アズ」と読むのでしょうけど、
僕は普段は日本語で「タイトエードル」と言ってしまう(笑)。
ジョンがファンキーな響きの音楽が好きだったことが分かる
ファンキーなギターの音が心地よい、これはスピノザかな。
そしてペダルスティールギターが気持ちよく鳴っている。
ギターの間奏もいい、いかにもプロの仕事という響きですね。
この曲のジョンのコメントは英語版に載っているので紹介します。
なお、英語版のものは以降も引用者が翻訳しています。
JL:ゴミ箱行きの曲さ。
こんな感じの曲をやってみたかっただけ。
テックス・メックスのサウンドだね、今ならありふれているけれど、
その頃はまだあまり多くの人がそれをやってはいなかったな。
GB:あ、そうですか・・・(笑)。
Tr3:Aisumasen (I'm Sorry)
「あいすません、ヨーコさぁん」
正しくは「あいすみません」でしょうけど、英語圏の人には
「みま」と続くのが発音しにくいのでしょうね。
むしろ「あいすんません」のほうが言いやすかったのでは。
でもそれだと日本語としてはちょっとおかしい。
単純に音に合わせて母音をひとつ削ったのかもしれない。
いずれにせよ完全な日本語ではないのは、
日本人がすぐそばにいたのにどうして、と思ってしまう。
ちょっとだけヨーコさんに抵抗したかったのかな(笑)。
まあ、気持ちは伝わるからいいんだけど。
ジョンがブルーズが好きなことが分かる、ジョン流に崩したブルーズ。
ピアノの「ポロロッン」という音がGodを彷彿とさせるのは、
早くもジョンは自分自身を茶化しているのか。
「ジョンの魂」の頃の苦悩から抜け出したということを
認めた上で世の中に言いたかったのかもしれない。
いずれにせよこの頃は心は穏やかだったようですね。
そして、ヨーコさんにすっかりひれ伏しているというか・・・
Mind Gamesにも「愛とは降伏することだ」という歌詞もあるし。
いややはなんとも、という感じもしないでもないですが。
Tr4:One Day (At A Time)
先ずは英語版からの引用。
JL:これは人生に対する考え方さ。
どのように生きてゆくかということ。
ファルセットで最後まで歌うのはヨーコのアイディアだ。
GB:この曲は好きみたいですね、というかいつものジョンらしい曲。
裏声で歌う抒情的な曲だけど、ジョンの歌い方には
切なさ、哀愁、虚しさ、といったものがほとんど感じられない。
だから切迫感を出すためにファルセットにしたら、と。
この曲は最初に聴いて、すごくいい曲だと思いました。
ところで、この曲が面白いのは、2番の2'18"の部分。
1番では"Good for you too"と歌うところに女声コーラスが被り、
2番でもそうなると思いきやジョンは"Good for us too"と歌い
コーラスはそのままなので歌とコーラスが違うことを言っている。
つくづく、突き詰めないで作った緩いアルバムだな、と。
でも、失敗だったら録り直すだろうに、そうしなかったのは、
間違うことが意図的だったのか、意図的に残したのか、それとも、
ヴォーカルがこれ以上いいのが録れなかったので仕方なく、か。
なんて考えるのは楽しい、だから緩い音楽もいい(笑)。
この曲はエルトン・ジョンがカヴァーしていますが、
むしろエルトンの色に合っているかもしれない。
Tr5:Bring On The Lucy (Freeda People)
レゲェが流行ってたんだな、ロックを席巻してたんだなって。
ジョン自身もこの後Do You Wanna Danceを録音するけれど、
面白いのは、ジョンの2曲とレッド・ツェッペリンのD'yer Ma'ker
「ジャメイカー」のサウンドプロダクションが似ていること。
ロックでレゲェ、まだまだ創生期で幅が狭かったのかな。
最初に話して呼びかけるのも、仲間意識を出そうとしているように感じる。
これもスライド奏法のギターが縦横無尽に駆け巡るのが気持ちいい。
ただ、この能天気ともいえる明るい曲の中で
"Stop killing!"と叫ぶのが、はっとさせられる。
でもこれも、型にはまらない平和のアピールと受け取れます。
"Lucy"って何、なんて野暮なことは言いっこなし(笑)。
ただ、もうジョンの後だけど、アフリカで発見された原人の化石に
"Lucy"と名付けられたので、今では僕はそれも思い出します。
Tr6:Nutopian International Anthem
このアルバムは最初は「ヌートピア宣言」と邦題がついていました。
ヌードみたい、とか、ヌートリアみたい、とか思いましたが(笑)、
今はその邦題は帯の復刻などでしか使われていないようです。
さて、この「曲」は6秒間の無音。
Wikipediaによれば、ヨーコさん曰く、その6秒の間に頭に
思い浮かんだ曲が「ヌートピア宣言」のテーマ曲なのだそうで。
うまいですね、だって、ヨーコさんの前衛芸術をジョンのアルバムに
違和感なく取り入れて「聴かせて」いるのだから。
しかしこれ、LPであればA面の最後だから、この「曲」が終わると
レコードの針が上がって円盤が止まるわけですが、僕は
CDで初めて聴いたので、ただ曲と曲の間が長いだけなのだと・・・
いや、CDを聴く前からこの「曲」が無音であるのは知っていたけれど、
なんとなく終わってしまっていました。
CDの弊害でしょうかね、でも仕方ない。
03 「心のゲーム」マーサ編

Tr7:Intuition
唸るというよりはうめき声のような強烈なベースから始まるこの曲、
どことなくフレンチポップのような響き、と僕はずっと思っていますが、
それがどうしてかは分からない。
確かに当時はミシェル・ポルナレフが流行っていたようだけど、
どうもこれは、影響を受けたというよりは、たまたまのような気が。
この曲もジョンの声は曲に対して多少重たすぎる気がするけれど、
内容が内容なだけに軽いポップスとはまた違う、そこがいいともいえる。
曲も、サビの最後"Intuition takes you anywhere"という部分が、
とってつけたように急に明るくなるのがジョンにしては珍しく
詰めが甘い気がするんだけど、でも時にはそういうのもいい。
なんせ「本能」で作っているのだし、基本の歌メロがとってもいいから。
「本能」という曲をジョンが作ったのは、やっぱり、と思ったものです。
引用した部分の歌詞も含蓄があってジョンらしい。
この曲では高音がためらいながら踊るピアノソロがよくて、
どの曲にも演奏で聴きどころがあるのがさすがはプロの仕事。
1曲目の次に僕がこの中で好きな曲はこれですね。
Tr8:Out The Blue
この曲も英語版から。
JL:これまたただのラヴソングさ、何も意味はない。
GB:でも、ただのラヴソングもまたいいじゃないですか(笑)。
これは「突然に」という意味ですが、普通は"of"が入るようで、
ジョンへのインタビュアーも"Of"を入れてジョンに聞いています。
僕がこれをCDで初めて聴いた頃ちょうどデビー・ギブソンが
Out Of The Blueをヒットさせてもいましたが、ということは、
"of"を抜くのはジョン独自の表現なのかもしれない。
この曲は、ジョンに余裕がない時に録音すると
もっと切迫感があって「名曲度」が上がったかもしれない。
惜しいというか、でもそう感じさせるところがこのアルバムの
作りが緩い、ということなのでしょう。
そうなんです、ジョンの音楽は、聴き手がいろいろ思うことがある、
つけいる隙があるからこそいいのだと思います。
もちろん僕は、ジョンもポールもどちらも好き。
僕は、こういう音楽が好き、というよりは、個性を楽しむほうだから。
この曲は低音を微妙に歪ませたピアノソロが刺さるようで印象的。
"Like a U.F.O. you came to me"というくだり、当時UFOが
流行っていたようで、それを見逃さないのはさすがにジョン。
Tr9:Only People
この曲にもジョンの言葉が。
JL:これはひとつの歌としては失敗作だね。
僕はいいラインを思いついたけど、
それをまともな形にするだけの言葉が思いつかなかった。
GB:そういわれればこの曲には強引さがありますね。
言っていることも(バカみたいに)シンプルな言葉だし。
ジョンのヴォーカルも強すぎる、力がこもり過ぎているし。
ただ、1作目2作目にはない無邪気にはほっとするものがあります。
ところで、このアルバムはベースが目立つ曲が多くて、
そこも僕が大好きな部分ですね。
Tr10:I Know (I Know)
ジョンの言葉。
JL:これまた何もない曲さ。
GB:先ほどからジョンの言葉を読んでいると、このアルバムは
1曲目と4曲目以外はあまり気に入っていないのかな。
緩いのがいい、と僕はほんとうにそう思うんだけど、でも
ジョンとしてはほんとうはもっとしゃきっとしたかったのかな。
僕のようなことをいうと怒られるかもしれない・・・
イントロのギターがI've Got A Feelingと同じ。
ジョンはよほど気に入ったフレーズなのでしょうね。
歌詞には"It's getting better all the time"などと出てくるし、
何もない割には聴きどころがある曲。
雰囲気的にはカントリーっぽさがあります。
ところで、このアルバムは()がついた曲が多いですね。
言いたいことをうまくまとめ切れなかったのかもしれない。
Tr11:You Are Here
ジョンの言葉がもう1曲。
JL:バラードの伝統にのっとりつつラテン風にやってみた曲。
GB:優しい曲が続く。
スライドギターがいい。
ラテン風にやってみた、というからには、やっぱりジョンは
音楽に対してセンスが鋭敏で、かつ自分でもやってみよう
という意気が強かったことがあらためて分かります。
それにしても、ジョンの優しい曲が持つ人の心を包み込むような
感触は、ほんと、ジョン・レノンが好きでよかったなあ、と。
歌詞に"Tokio"と出てくるのは無条件でうれしい(笑)。
Tr12:Meat City
僕がいつもいう「ロックの照れ隠し」
前の曲で優しさを見せてしまったところで
威勢のいい曲で大見得を切ってしまう。
いきなり"Well"と大声で叫んで叫ばれたからには。
ちなみに"Well"はジョンの歌の中での口癖ですね。
ファンキーなロックンロールをアルバム最後に持ってきました。
でもこの曲は最初、ジョンもこんな曲をやるんだと少々驚きました。
音楽的にもこのファンキーさに驚かされたのですが、それ以上に
なんというか、品がないですよね、「肉の街」なんて。
品がないというか、ジョンは食べ物に対しては妙にストイックだけど、
でもこれは欲望を包み隠さず、不意に表れてしまっている感じが。
でも、『マジカル・ミステリー・ツアー』でスコップを持って
食べ物をテーブルに「くべる」給仕をやっていたのはジョンだった。
でもそれはポールのアイディアで、ジョンは食べることに対して
ストイックだからこそあのシーンが印象に残ったのでしょう。
映画『フェリーニのローマ』の最初の部分で、とにかく食べる
シーンがあって、それも思い出した。
それはともかく、AメロからBメロに移る辺りのリズムが崩れるのは
ジョンの仲間だけではできなかったのではないか、という
最後までプロの技を聴かせてくれるアルバム。
ギターの音が不自然に硬いのも生々しい。
"People are dancing like there's no tomorrow"
というくだりもやっぱりジョン・レノンらしくて素晴らしい。
なんだかんだで爽快な気分にさせられる曲で終わります。
あらためてじっくりと聴くと、歌詞がとにかく素晴らしい。
歌詞については、ポピュラー音楽の世界ではいまだに、
ジョン・レノンに並び称される人はいないと思います。
ここまで書いてきてこういうのもなんですが、
僕はやっぱり「あばたもえくぼ」という人間かな。
断っておきますが、僕がここで書いたことはすべて、
自分の気持ちには正直に書いています。
ほんとうに大好きですよ、このアルバムは。
でも、ジョン・レノンが特に好きではない人がこれを聴くと
果たしてどう感じらるのか、書いていて急に気になってきました。
音楽に人の意見は関係な、自分の好き嫌いでいいのでしょうけど、
しかし一方、人と音楽の話をするのも楽しいわけで。
でも、そう思わせる作品を作ってしまったジョン・レノンこそが
人がどう思うかを割と気にしていたのかもしれない、と
インタビューを読む度に思いますね。
さて、今年はなんとか間に合ったという感じです。
もっとも、時差があるので、英国や米国の時間では、
まだまだ余裕で10月9日ですが(笑)。
さて、最後は「心のゲーム」ポーラ編。
でも、IMAGINEのジャケットのようになってしまいました(笑)。
04


MIND GAMES John Lennon
マインド・ゲームス(ヌートピア宣言) ジョン・レノン
10月9日はジョン・レノンの誕生日
今年で73歳、になっていたはず
ジョンおめでとう!
毎年ジョン・レノンのアルバムを記事にしていますが、
と思ったけど無理矢理ジョンにこじつけた年もあったっけ(笑)、
ともあれこの日は毎年、ジョンへの思いを記事にしています。
今年は素直にアルバムを取り上げます。
ジョン・レノンの、ビートルズ解散後の、
スタジオ録音の新曲が含まれたアルバムとしては4作目。
この前がライヴを含んだ変則的な2枚組でした。
このアルバムは、僕が中高生の頃は世間の評価があまり高くなく、
ジョン・レノンが好きな人だから聴ける、でも少々地味だ、
みたいな言われ方をしていました。
だから、と評論家のせいにしていますが(笑)、
僕はこのアルバム、二十歳を過ぎて、CDで初めて聴きました。
でも、初めて聴いて、こんなにもいいのは予想外でした。
つくづく、評論家の言うことを鵜呑みにしてはいけない、と・・・
まあ、その頃はもう僕の中でジョンへの信心みたいなものが
固まっていたので素直に受け入れられたのかもですが。
なんといっても曲がみな素晴らしい。
歌が基本の僕としてはすんなりと心の奥まで入ってきました。
ここでのジョンの音楽は楽観的な雰囲気、悪く言えば緩い。
ヨーコさんとの生活が刺激から安定に変わってきた
と感じていた時期なのかな。
しかし、皮肉にも、この後でジョンとヨーコは別居することになり、
ジョンは家を飛び出し、「失われた週末」が始まるのでした。
お互いに安定よりは刺激の人間だったのかもしれない。
このアルバムは、ギターのデヴィッド・スピノザ、
サックスのマイケル・ブレッカーそしておなじみジム・ケルトナー
といったニューヨークのミュージシャンを迎えて録音しています。
でも、このアルバムがいまいち評価が高くなかったのは、
ジョン・レノンにこのサウンドは合わないと感じた人が多かったのかな。
前作までは身内で固めたバンドらしいサウンドでしたが、
いきなりプロの音を身にまとって出て来たことに違和感があった。
しかも、ジョンの力唱型のヴォーカルスタイルが、
都会風のこじゃれた音に合わない感じもしないでもないし。
まあ、ジョンだって最新のサウンドには気持ちが動かされたでしょうし、
ニューヨークに移り住んでその音楽に刺激を受けないわけがない。
ジョンも、悪く言えば節操がないんだけど、やりたいと思ったことを
素直にやれる実行力があるのはさすがというか。
でも、ロックの魅力のひとつは、自分と異質なものを受け入れた上で
ぎこちなく表現することだから、このアルバムの違和感は、
すなわち、ロック本来の魅力だと言えるのではないか。
このアルバムは、だからこそ面白い。
音楽の世界においてあれだけのものを作り上げておきながら、
新たにぎこちないものを作ってしまったジョン・レノンという人が。
ポール・マッカートニーが自分の道を進んでいたのとは対照的。
でも、ジョンにとってはそうすることが自然だったのでしょう。
曲も、ヒットソングが並んでいるというよりは、
ちょっとしたスケッチ、しかし中身の濃いスケッチが
並んでいるといった趣きがあります。
曲はすべてジョン・レノンが作曲しています。
02 「心のゲーム」ハウ編

Tr1:Mind Games
この曲には例のジョン自身によるコメントがあります。
いつもの『プレイボーイ・インタビュー』から引用しますが、
引用者は適宜表記変更及び改行を施しています。
JL:この曲はもともと"Make Love Not War"と呼ばれていた。
でも今じゃもう口にできないほど陳腐な言葉になってしまった。
だから、僕は同じ意味のメッセージを別の言葉で書いたんだ。
"Mind games, mind guerrilla"ってね。
Imagineなんかと同じだよ。
これはいい演奏さ。
いつ聞いてもこのサウンドはいいな。
ぼくたちが60年代にずっと言い続けてきたこと
-ラヴ・アンド・ピースをその言葉を使わないで
表現しただけのことだ。
ラヴ・アンド・ピースなんてもうジョークになっちゃったものね。
GB:この曲は僕もほんとうに好きです。
ジョンの曲で好きな10曲を選ぶと必ず入るし、ジョンの歌の中でも
僕が何気なく口ずさむことが極めて多い1曲でもあります。
ジョンはサウンドがいいなと言っていますが、ほんとうにそう。
地平線を前にした暖かい日の夜明け、というイメージ、僕には。
まあそれはジャケットのイメージを引きずっているのですが。
イントロからずっと流れるジョンの短いスライド奏法のギターが、
まるで鐘の音のように鳴り響き続けている。
鐘の音は祈りの音、ジョンのメッセージが音でも巧く表されている。
"Love is the answer""Yes is the answer"というのは
ジョンがほんとうに訴えたかったことをこれ以上ないほど
簡潔にかつ深く表したくだりで感動します。
この曲について話し始めると優に記事ひとつになってしまうので、
続きはまたの機会ということで、次の曲に進みます。
Tr2:Tight A$
アメリカ移住を機にアメリカをおちょくってみた曲名。
"Tight as ..."と歌っていくのでこのA$は「アズ」と読むのでしょうけど、
僕は普段は日本語で「タイトエードル」と言ってしまう(笑)。
ジョンがファンキーな響きの音楽が好きだったことが分かる
ファンキーなギターの音が心地よい、これはスピノザかな。
そしてペダルスティールギターが気持ちよく鳴っている。
ギターの間奏もいい、いかにもプロの仕事という響きですね。
この曲のジョンのコメントは英語版に載っているので紹介します。
なお、英語版のものは以降も引用者が翻訳しています。
JL:ゴミ箱行きの曲さ。
こんな感じの曲をやってみたかっただけ。
テックス・メックスのサウンドだね、今ならありふれているけれど、
その頃はまだあまり多くの人がそれをやってはいなかったな。
GB:あ、そうですか・・・(笑)。
Tr3:Aisumasen (I'm Sorry)
「あいすません、ヨーコさぁん」
正しくは「あいすみません」でしょうけど、英語圏の人には
「みま」と続くのが発音しにくいのでしょうね。
むしろ「あいすんません」のほうが言いやすかったのでは。
でもそれだと日本語としてはちょっとおかしい。
単純に音に合わせて母音をひとつ削ったのかもしれない。
いずれにせよ完全な日本語ではないのは、
日本人がすぐそばにいたのにどうして、と思ってしまう。
ちょっとだけヨーコさんに抵抗したかったのかな(笑)。
まあ、気持ちは伝わるからいいんだけど。
ジョンがブルーズが好きなことが分かる、ジョン流に崩したブルーズ。
ピアノの「ポロロッン」という音がGodを彷彿とさせるのは、
早くもジョンは自分自身を茶化しているのか。
「ジョンの魂」の頃の苦悩から抜け出したということを
認めた上で世の中に言いたかったのかもしれない。
いずれにせよこの頃は心は穏やかだったようですね。
そして、ヨーコさんにすっかりひれ伏しているというか・・・
Mind Gamesにも「愛とは降伏することだ」という歌詞もあるし。
いややはなんとも、という感じもしないでもないですが。
Tr4:One Day (At A Time)
先ずは英語版からの引用。
JL:これは人生に対する考え方さ。
どのように生きてゆくかということ。
ファルセットで最後まで歌うのはヨーコのアイディアだ。
GB:この曲は好きみたいですね、というかいつものジョンらしい曲。
裏声で歌う抒情的な曲だけど、ジョンの歌い方には
切なさ、哀愁、虚しさ、といったものがほとんど感じられない。
だから切迫感を出すためにファルセットにしたら、と。
この曲は最初に聴いて、すごくいい曲だと思いました。
ところで、この曲が面白いのは、2番の2'18"の部分。
1番では"Good for you too"と歌うところに女声コーラスが被り、
2番でもそうなると思いきやジョンは"Good for us too"と歌い
コーラスはそのままなので歌とコーラスが違うことを言っている。
つくづく、突き詰めないで作った緩いアルバムだな、と。
でも、失敗だったら録り直すだろうに、そうしなかったのは、
間違うことが意図的だったのか、意図的に残したのか、それとも、
ヴォーカルがこれ以上いいのが録れなかったので仕方なく、か。
なんて考えるのは楽しい、だから緩い音楽もいい(笑)。
この曲はエルトン・ジョンがカヴァーしていますが、
むしろエルトンの色に合っているかもしれない。
Tr5:Bring On The Lucy (Freeda People)
レゲェが流行ってたんだな、ロックを席巻してたんだなって。
ジョン自身もこの後Do You Wanna Danceを録音するけれど、
面白いのは、ジョンの2曲とレッド・ツェッペリンのD'yer Ma'ker
「ジャメイカー」のサウンドプロダクションが似ていること。
ロックでレゲェ、まだまだ創生期で幅が狭かったのかな。
最初に話して呼びかけるのも、仲間意識を出そうとしているように感じる。
これもスライド奏法のギターが縦横無尽に駆け巡るのが気持ちいい。
ただ、この能天気ともいえる明るい曲の中で
"Stop killing!"と叫ぶのが、はっとさせられる。
でもこれも、型にはまらない平和のアピールと受け取れます。
"Lucy"って何、なんて野暮なことは言いっこなし(笑)。
ただ、もうジョンの後だけど、アフリカで発見された原人の化石に
"Lucy"と名付けられたので、今では僕はそれも思い出します。
Tr6:Nutopian International Anthem
このアルバムは最初は「ヌートピア宣言」と邦題がついていました。
ヌードみたい、とか、ヌートリアみたい、とか思いましたが(笑)、
今はその邦題は帯の復刻などでしか使われていないようです。
さて、この「曲」は6秒間の無音。
Wikipediaによれば、ヨーコさん曰く、その6秒の間に頭に
思い浮かんだ曲が「ヌートピア宣言」のテーマ曲なのだそうで。
うまいですね、だって、ヨーコさんの前衛芸術をジョンのアルバムに
違和感なく取り入れて「聴かせて」いるのだから。
しかしこれ、LPであればA面の最後だから、この「曲」が終わると
レコードの針が上がって円盤が止まるわけですが、僕は
CDで初めて聴いたので、ただ曲と曲の間が長いだけなのだと・・・
いや、CDを聴く前からこの「曲」が無音であるのは知っていたけれど、
なんとなく終わってしまっていました。
CDの弊害でしょうかね、でも仕方ない。
03 「心のゲーム」マーサ編

Tr7:Intuition
唸るというよりはうめき声のような強烈なベースから始まるこの曲、
どことなくフレンチポップのような響き、と僕はずっと思っていますが、
それがどうしてかは分からない。
確かに当時はミシェル・ポルナレフが流行っていたようだけど、
どうもこれは、影響を受けたというよりは、たまたまのような気が。
この曲もジョンの声は曲に対して多少重たすぎる気がするけれど、
内容が内容なだけに軽いポップスとはまた違う、そこがいいともいえる。
曲も、サビの最後"Intuition takes you anywhere"という部分が、
とってつけたように急に明るくなるのがジョンにしては珍しく
詰めが甘い気がするんだけど、でも時にはそういうのもいい。
なんせ「本能」で作っているのだし、基本の歌メロがとってもいいから。
「本能」という曲をジョンが作ったのは、やっぱり、と思ったものです。
引用した部分の歌詞も含蓄があってジョンらしい。
この曲では高音がためらいながら踊るピアノソロがよくて、
どの曲にも演奏で聴きどころがあるのがさすがはプロの仕事。
1曲目の次に僕がこの中で好きな曲はこれですね。
Tr8:Out The Blue
この曲も英語版から。
JL:これまたただのラヴソングさ、何も意味はない。
GB:でも、ただのラヴソングもまたいいじゃないですか(笑)。
これは「突然に」という意味ですが、普通は"of"が入るようで、
ジョンへのインタビュアーも"Of"を入れてジョンに聞いています。
僕がこれをCDで初めて聴いた頃ちょうどデビー・ギブソンが
Out Of The Blueをヒットさせてもいましたが、ということは、
"of"を抜くのはジョン独自の表現なのかもしれない。
この曲は、ジョンに余裕がない時に録音すると
もっと切迫感があって「名曲度」が上がったかもしれない。
惜しいというか、でもそう感じさせるところがこのアルバムの
作りが緩い、ということなのでしょう。
そうなんです、ジョンの音楽は、聴き手がいろいろ思うことがある、
つけいる隙があるからこそいいのだと思います。
もちろん僕は、ジョンもポールもどちらも好き。
僕は、こういう音楽が好き、というよりは、個性を楽しむほうだから。
この曲は低音を微妙に歪ませたピアノソロが刺さるようで印象的。
"Like a U.F.O. you came to me"というくだり、当時UFOが
流行っていたようで、それを見逃さないのはさすがにジョン。
Tr9:Only People
この曲にもジョンの言葉が。
JL:これはひとつの歌としては失敗作だね。
僕はいいラインを思いついたけど、
それをまともな形にするだけの言葉が思いつかなかった。
GB:そういわれればこの曲には強引さがありますね。
言っていることも(バカみたいに)シンプルな言葉だし。
ジョンのヴォーカルも強すぎる、力がこもり過ぎているし。
ただ、1作目2作目にはない無邪気にはほっとするものがあります。
ところで、このアルバムはベースが目立つ曲が多くて、
そこも僕が大好きな部分ですね。
Tr10:I Know (I Know)
ジョンの言葉。
JL:これまた何もない曲さ。
GB:先ほどからジョンの言葉を読んでいると、このアルバムは
1曲目と4曲目以外はあまり気に入っていないのかな。
緩いのがいい、と僕はほんとうにそう思うんだけど、でも
ジョンとしてはほんとうはもっとしゃきっとしたかったのかな。
僕のようなことをいうと怒られるかもしれない・・・
イントロのギターがI've Got A Feelingと同じ。
ジョンはよほど気に入ったフレーズなのでしょうね。
歌詞には"It's getting better all the time"などと出てくるし、
何もない割には聴きどころがある曲。
雰囲気的にはカントリーっぽさがあります。
ところで、このアルバムは()がついた曲が多いですね。
言いたいことをうまくまとめ切れなかったのかもしれない。
Tr11:You Are Here
ジョンの言葉がもう1曲。
JL:バラードの伝統にのっとりつつラテン風にやってみた曲。
GB:優しい曲が続く。
スライドギターがいい。
ラテン風にやってみた、というからには、やっぱりジョンは
音楽に対してセンスが鋭敏で、かつ自分でもやってみよう
という意気が強かったことがあらためて分かります。
それにしても、ジョンの優しい曲が持つ人の心を包み込むような
感触は、ほんと、ジョン・レノンが好きでよかったなあ、と。
歌詞に"Tokio"と出てくるのは無条件でうれしい(笑)。
Tr12:Meat City
僕がいつもいう「ロックの照れ隠し」
前の曲で優しさを見せてしまったところで
威勢のいい曲で大見得を切ってしまう。
いきなり"Well"と大声で叫んで叫ばれたからには。
ちなみに"Well"はジョンの歌の中での口癖ですね。
ファンキーなロックンロールをアルバム最後に持ってきました。
でもこの曲は最初、ジョンもこんな曲をやるんだと少々驚きました。
音楽的にもこのファンキーさに驚かされたのですが、それ以上に
なんというか、品がないですよね、「肉の街」なんて。
品がないというか、ジョンは食べ物に対しては妙にストイックだけど、
でもこれは欲望を包み隠さず、不意に表れてしまっている感じが。
でも、『マジカル・ミステリー・ツアー』でスコップを持って
食べ物をテーブルに「くべる」給仕をやっていたのはジョンだった。
でもそれはポールのアイディアで、ジョンは食べることに対して
ストイックだからこそあのシーンが印象に残ったのでしょう。
映画『フェリーニのローマ』の最初の部分で、とにかく食べる
シーンがあって、それも思い出した。
それはともかく、AメロからBメロに移る辺りのリズムが崩れるのは
ジョンの仲間だけではできなかったのではないか、という
最後までプロの技を聴かせてくれるアルバム。
ギターの音が不自然に硬いのも生々しい。
"People are dancing like there's no tomorrow"
というくだりもやっぱりジョン・レノンらしくて素晴らしい。
なんだかんだで爽快な気分にさせられる曲で終わります。
あらためてじっくりと聴くと、歌詞がとにかく素晴らしい。
歌詞については、ポピュラー音楽の世界ではいまだに、
ジョン・レノンに並び称される人はいないと思います。
ここまで書いてきてこういうのもなんですが、
僕はやっぱり「あばたもえくぼ」という人間かな。
断っておきますが、僕がここで書いたことはすべて、
自分の気持ちには正直に書いています。
ほんとうに大好きですよ、このアルバムは。
でも、ジョン・レノンが特に好きではない人がこれを聴くと
果たしてどう感じらるのか、書いていて急に気になってきました。
音楽に人の意見は関係な、自分の好き嫌いでいいのでしょうけど、
しかし一方、人と音楽の話をするのも楽しいわけで。
でも、そう思わせる作品を作ってしまったジョン・レノンこそが
人がどう思うかを割と気にしていたのかもしれない、と
インタビューを読む度に思いますね。
さて、今年はなんとか間に合ったという感じです。
もっとも、時差があるので、英国や米国の時間では、
まだまだ余裕で10月9日ですが(笑)。
さて、最後は「心のゲーム」ポーラ編。
でも、IMAGINEのジャケットのようになってしまいました(笑)。
04

2013年05月02日
ジョン・レノンのジュークボックスの41曲
01

ジョン・レノン・ミュージアム
2010年9月30日をもって閉館となります。
http://www.taisei.co.jp/museum/
僕は、3月に一度行って記事にしていたのですが、
4月に、もう一度、行きました。
おそらくこれが最後となるでしょう。
4月には、閉館へ向けての特別展
「ジョンとヨーコ 新たなる出発 "Starting Over"」
が行われていました。
展示内容については公式サイトをご覧いただくこととして、
僕がその中でとっても興味を持ったものが
ジョン・レノンのジュークボックスとその41曲
でした。
02

ジョンが、1966年の全米ツアーの際に携行していたという
ドーナツ盤が40枚入る小型のジュークボックスが
そこには展示されていました。
館内は撮影禁止のため写真でお見せすることはできませんが、
ジュークボックスとはいっても、よく映画で出てくるような
人がよしかかれるほど大きな直立したものではなく、
小型の冷蔵庫くらいのものでした。
しかし、いずれにせよ、手軽に持ち運びできるほど小さくはないもの。
でも、ジョンは、「持ち歩いて」いたそうです。
もちろん、ローディさんが運んでいたのでしょうけどね。
だって、ジョンが背負子で担ぐ姿なんか、想像できないし(笑)。
展示されていた機械は同型機だということですが、そこには、
当時ジョンが好んで聴いていた41枚のドーナツ盤が収められており、
その横には、そのA面の曲目が書き出されて説明が付された
パネルが掲示されていました。
ちなみに、機械は40枚入るものだったのですが、
なぜ41枚だったのかは、申し訳ない、忘れてしまいました・・・
いずれにせよ、ジョンは、A面B面合わせて80曲と2曲を
ツアーの合間の時間に聴き込んでいたということです。
曲のパネルを、最初はゆっくりと見てゆきましたが、
そのうち僕は、この曲を全部聴きたいと思い始めました。
ジョンが好きな曲だから、やっぱり。
しかし館内は撮影禁止のため写真で残すことはできず、
知っている曲はあるにせよ41曲も覚える記憶力もないので、
さて、どうしようかと、しばし考えました。
もちろんその間、誰も見てない瞬間があったので、
写真を撮ってしまうことも考えたのですが、やりませんでした。
ボイスレコーダーがあれば、録音禁止とは書いていないので、
曲を読み上げて録音すればいいことに気づきましたが、
もちろん僕は、ボイスレコーダーを持ち歩く人間でもないし。
しょうがない、書き写すか。
と思ったのですが、折悪しく、ミュージアムには、
入館前の場所に、100円が戻ってくるコインロッカーがあって、
荷物はすべてそこに預けて見学していたので、
書くものも持ち合わせていませんでした。
諦めるか・・・
と思い、出口に向かったところで、目に入ったのが
03
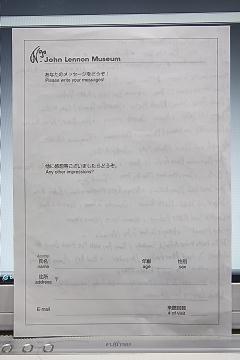
ミュージアムのアンケート用紙でした。
もちろん記入用のペンもテーブルに置いてあります。
そうか、これだ!
1枚いただき、ボールペンも借りて戻り、
41曲を書き写すことにしました。
41曲、ただ曲名とアーティスト名を書くだけでしたが、
それでも20分くらいはかかったと思います。
ようやく終わりました。
04

こんな感じです、ふぅ、疲れた。
この紙を、途中でもらったチラシの間にはさんで
外に出ました。
後で気づいたのですが、この紙をもらったことは、
結果としてミュージアムの記念品にもなったので、
よかった、うれしくなってきました。
でも、ミュージアム関係者のかた、ごめんなさい・・・
05 エントランスホールのジョンの写真のコラージュ

今回は、メモしたものを書き起こすという意味も込めて、
その41曲を書き出して紹介したいと思います。
しかし、41曲の長いリストを途中に入れると
記事としては読みにくいかと思い、リストは巻末に回しました。
ご興味があるかたは、そちらをじっくりとご覧ください。
そしてここでは、その中から何曲かをピックアップして
僕が思うことなどを書き連ねてゆきます。
06

01:In The Midnight Hour / Wilson Pickett
根拠も何もないのですが、ジョンがこの曲を好きと聞いて
何かちょっと意外な感じがしました。
03:Tracks Of My Tears / Smokey Robinson & The Miracles
スモーキー・ロビンソンのあまりにも素晴らしいこの曲、
一度記事にしているので、こちらもご覧ください。
スモーキーは他にも33、36、39、41と計5枚があって、
やっぱりジョンはスモーキーが大好きで、
歌詞にこだわっていたんだなあと実感。
スモーキー好き人間としても、感無量でした。
04:My Girl / Otis Redding
テンプテーションズ Temptationsのオリジナルではなく、
オーティス・レディングで選んでいたのがミソ。
テンプスのはソフト過ぎるのかな・・・
だけどこれを選んでいるところで、01の意外さが消えました。
ジョンもやっぱり熱唱系も好きなんですね。
ちなみにこれもスモーキー・ロビンソンの手になる曲。
06:High-Heel Sneakers / Len Barry
これは、ポール・マッカートニー Paul McCartneyが
UNPLUGGEDでカバーしていて知っていましたが、
そろそろオリジナルを聴いてみたいですね。
14:Long Tall Sally / Little Richard
15:Money / Barrett Strong
26:Twist And Shout / The Isley Brothers
37:Bad Boy / Larry Williams
ビートルズが公式にカバーした曲が4曲ありました。
14はビートルズではポールが歌っていますが、
ほんとはジョンが歌いたかったのかな(笑)。
15はジョンが歌い、ソロのコンサートでも演奏した大のお気に入り。
26は昨年、四半世紀を経て初めてオリジナルを聴きました(笑)。
37、ラリー・ウィリアムスは一方、そろそろ買って聴きたい・・・
これらの曲は、自分たちがカバーした後でも
好んで聴いていたのが興味深いですね。
07

17:Positively 4th Street
ジョンがボブ・ディランを大好きだったのは有名な話ですが、
これはシングルのみのリリース、だからここにあって当然ですね。
きっとLPの曲はLPで聴いていたでしょうから。
18:Daydream / Lovin' Spoonful
24:Do You Believe In Magic / Lovin' Spoonful
ラヴィン・スプーンフルが2曲あったのが意外でした。
僕は、彼らはつい最近聴き始めたばかりで、
24は最初に買った彼らのアルバムの表題曲で好きですが、
18の曲は知らなくて、次に彼らのCDを買うならそれと思い
ウィッシュリストに入れて数カ月が経っていました。
だからこれを見て、ジョンに頭を叩かれたような気がして、
札幌に帰ったらすぐにAmazonで注文しようと思いました。
しかし、その3日後、関内のディスクユニオンに行くと、
まさにそのCDのリイシューの国内盤の中古があったのです。
ただ、僕は海外盤を買ってきていたので少し悩みましたが、
これはきっとジョンに導かれたのだと思い、買いました。
そして件の曲"Daydream"を聴いて驚きました。
「あ、この曲知ってる!」
20年かそこら前にCMで使われていて、出だしのところは
口ずさめるくらいに知っている曲だったのです。
僕はCMで使われた曲は割とこまめにチェックしているのですが、
この曲はどうしてそこで誰の曲かまでたどり着かなかったのか、
自分でも不思議でした。
でも多分当時は、僕の人生でいちばん音楽への熱が低かった、
そんな頃だったのだと思います。
ともあれ、この曲については、よかった、
落ち着くところに落ち着いた感じがします。
08

20:Slippin' And Slidin' / Buddy Holly
21:Be-Bop-A-Lula / Gene Vincent
29:Slippin' And Slidin' / Little Richard
34:Bring It On Home To Me / The Animals
こちらはジョンがROCK 'N' ROLLでカバーした曲。
20と29は同じ曲を違う人で入れているのが興味深い。
しかし僕はこれ、バディのはまだ聴いたことがない。
25:Some Other Guy / The Big Three
これはビートルズのバージョンがBBCで聴けます。
27:She Said Yeah / Larry Williams
僕はこの曲を、ローリング・ストーンズ Rolling Stones
のカバーで知りました。
22:No Particular Place To Go / Chuck Berry
28:Brown Eyed Handsome Man / Chuck Berry
チャック・ベリーが2曲あるのは納得ですね。
もっと多くないところがいかにもジョンらしいというか(笑)。
28はポール・マッカートニーが、ほとんどがカバー曲の
アルバムRUN DEVIL RUNでカバーしていますが、
アコーディオンを入れたポールのバージョンも僕は大好きです。
38:Agent Double-O-Soul / Edwin Starr
この曲はうちにベスト盤があるからあるはずだよな・・・
と思いつつ、その時点では知らない曲で、
札幌に帰って早速聴くと、カッコいい曲でした。
だけど、この中で僕が知っている曲の中では、
群を抜いて「黒い」のですが、それをジョンが好きというのは
少し意外な感じがしました。
しかし、エドウィン・スターの代表曲はWarですが、
後にそういうメッセージソングを発表していて、
ジョンはその辺りに近しいものを感じたのかもしれません。
ベスト盤を聴いているととにかくカッコいいので
エドウィン・スターから先ず聴こうかな。
09

以上、知っている曲についてさらりと触れましたが、
僕がCDを持っている曲は、18曲でした。
この記事を上げたのを機に、僕は、少しずつ、
残りの23曲のCDを買って聴いてゆこうと思いました。
今年の目標、そうですね、今年度、くらいでちょうどいいかな。
ミュージアムの話をもうひとつ。
3月に行った際には「出張中」だった、
ジョンがニューヨークのコンサートで使っていた、
レス・ポールJrが戻ってきていて、見ることができました。
よかった!
実物を見ると、僕のレス・ポールJrとは違い、
コントロールノブが2つしかないタイプのものでしたが、
でも、いいんです、同じということにしておきます(笑)。
10

それまで行ったことがなかったくせに
いまさらこんなこと言うのもなんですが、でも、
ミュージアムがなくなるのは、かなり、とっても残念です。
駅から降りて、車が通る道路を歩くことなく、
デッキでつながっていてゆっくりと歩ける場所もいいですし、
JR上野駅から30分で着けるのも、僕にはいいところでした。
横には「さいたまスーパーアリーナ」がありますが、僕は多分、
いつかきっと、そこにコンサートに行くことがあると思います。
その時に、ジョンの写真がないのを見ると、寂しいだろうなぁ。
心の拠り所としてはもちろんジョンは永遠に変わらないけど、
でも、実際に、場所としての拠り所があるというのは、
それはそれで素敵なことだと思い直しました。
でも、ヨーコさんが
「10年も続くと思っていなかった、そのことに感謝します」
と、あくまでも前向きにメッセージを発してくれているのが
ほっとする部分で、ありがたいことだと思います。
ありがとう。
11

「Ai ジョン・レノンが見た日本」(ちくま文庫)
単行本は持っているけど、文庫版は持っていないので
買うつもりだったこの本も、ミュージアムのショップにありました。
そしてこの写真は、いつものおまけで、
ジョンの顔をハウの顔に重ねて撮ろうとしたところ、
大きさが合いませんでした(笑)。
★☆
01 In The Midnight Hour / Wilson Pickett
02 Rescue Me / Fon Tella Bass
03 Tracks Of My Tears / Smokey Robinson & The Miracles
04 My Girl / Otis Redding
05 1-2-3 / Len Barry
06 High Heel Sneaker / Tommy Tucker
07 The Walls / Jimmy McCraddin
08 Gonna Send Me To Georgia / Timmy Show
09 First I Look At The Purse / The Contours
10 New Orleans / Gary US Bands
11 Watch Your Step / Bobby Parker
12 Daddy Rollin' Stone / Derek Martin
13 Short Fat Fannie / Larry Williams
14 Long Tall Sally / Little Richard
15 Money / Barrett Strong
16 Hey Baby / Bruce Channel
17 Positively 4th Street / Bob Dylan
18 Daydream / Lovin' Spoonful
19 Turquoise / Donovan
20 Slippin' And Slidin' / Buddy Holly
21 Be-Bop-A-Lula / Gene Vincent
22 No Particular Place To Go / Chuck Berry
23 Steppin' Out / Paul Revere & The Raiders
24 Do You Believe In Magic ? / Lovin' Spoonful
25 Some Other Guy / The Big Three
26 Twist And Shout / The Isley Brothers
27 She Said Yeah / Larry Williams
28 Brown Eyed Handsome Man / Chuck Berry
29 Slippin' And Slidin' / Little Richard
30 Quarter To Three / Gary U.S. Bands
31 Oh My Soul / Little Richard
32 Woman Love / Gene V
33 Shop Around / Smokey Robinson & The Miracles
34 Bring It On Home To Me / The Animals
35 If You Gotta Make A Fool Of Somebody
/ James Ray with THe Hatch Davie Orchestra
36 What's So Good About Goodbye
/ Smokey Robinson & The Miracles
37 Bad Boy / Larry Williams
38 Agent Double-O-Soul / Edwin Starr
39 I've Been Good To You
/ Smokey Robinson & The Miracles
40 Oh I Apologize / Barrett Strong
41 Who's Loving You / Smokey Robinson & The Miracles

ジョン・レノン・ミュージアム
2010年9月30日をもって閉館となります。
http://www.taisei.co.jp/museum/
僕は、3月に一度行って記事にしていたのですが、
4月に、もう一度、行きました。
おそらくこれが最後となるでしょう。
4月には、閉館へ向けての特別展
「ジョンとヨーコ 新たなる出発 "Starting Over"」
が行われていました。
展示内容については公式サイトをご覧いただくこととして、
僕がその中でとっても興味を持ったものが
ジョン・レノンのジュークボックスとその41曲
でした。
02

ジョンが、1966年の全米ツアーの際に携行していたという
ドーナツ盤が40枚入る小型のジュークボックスが
そこには展示されていました。
館内は撮影禁止のため写真でお見せすることはできませんが、
ジュークボックスとはいっても、よく映画で出てくるような
人がよしかかれるほど大きな直立したものではなく、
小型の冷蔵庫くらいのものでした。
しかし、いずれにせよ、手軽に持ち運びできるほど小さくはないもの。
でも、ジョンは、「持ち歩いて」いたそうです。
もちろん、ローディさんが運んでいたのでしょうけどね。
だって、ジョンが背負子で担ぐ姿なんか、想像できないし(笑)。
展示されていた機械は同型機だということですが、そこには、
当時ジョンが好んで聴いていた41枚のドーナツ盤が収められており、
その横には、そのA面の曲目が書き出されて説明が付された
パネルが掲示されていました。
ちなみに、機械は40枚入るものだったのですが、
なぜ41枚だったのかは、申し訳ない、忘れてしまいました・・・
いずれにせよ、ジョンは、A面B面合わせて80曲と2曲を
ツアーの合間の時間に聴き込んでいたということです。
曲のパネルを、最初はゆっくりと見てゆきましたが、
そのうち僕は、この曲を全部聴きたいと思い始めました。
ジョンが好きな曲だから、やっぱり。
しかし館内は撮影禁止のため写真で残すことはできず、
知っている曲はあるにせよ41曲も覚える記憶力もないので、
さて、どうしようかと、しばし考えました。
もちろんその間、誰も見てない瞬間があったので、
写真を撮ってしまうことも考えたのですが、やりませんでした。
ボイスレコーダーがあれば、録音禁止とは書いていないので、
曲を読み上げて録音すればいいことに気づきましたが、
もちろん僕は、ボイスレコーダーを持ち歩く人間でもないし。
しょうがない、書き写すか。
と思ったのですが、折悪しく、ミュージアムには、
入館前の場所に、100円が戻ってくるコインロッカーがあって、
荷物はすべてそこに預けて見学していたので、
書くものも持ち合わせていませんでした。
諦めるか・・・
と思い、出口に向かったところで、目に入ったのが
03
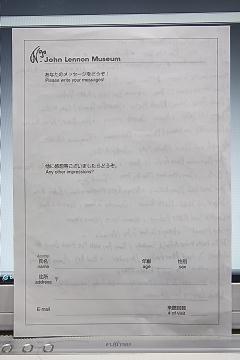
ミュージアムのアンケート用紙でした。
もちろん記入用のペンもテーブルに置いてあります。
そうか、これだ!
1枚いただき、ボールペンも借りて戻り、
41曲を書き写すことにしました。
41曲、ただ曲名とアーティスト名を書くだけでしたが、
それでも20分くらいはかかったと思います。
ようやく終わりました。
04

こんな感じです、ふぅ、疲れた。
この紙を、途中でもらったチラシの間にはさんで
外に出ました。
後で気づいたのですが、この紙をもらったことは、
結果としてミュージアムの記念品にもなったので、
よかった、うれしくなってきました。
でも、ミュージアム関係者のかた、ごめんなさい・・・
05 エントランスホールのジョンの写真のコラージュ

今回は、メモしたものを書き起こすという意味も込めて、
その41曲を書き出して紹介したいと思います。
しかし、41曲の長いリストを途中に入れると
記事としては読みにくいかと思い、リストは巻末に回しました。
ご興味があるかたは、そちらをじっくりとご覧ください。
そしてここでは、その中から何曲かをピックアップして
僕が思うことなどを書き連ねてゆきます。
06

01:In The Midnight Hour / Wilson Pickett
根拠も何もないのですが、ジョンがこの曲を好きと聞いて
何かちょっと意外な感じがしました。
03:Tracks Of My Tears / Smokey Robinson & The Miracles
スモーキー・ロビンソンのあまりにも素晴らしいこの曲、
一度記事にしているので、こちらもご覧ください。
スモーキーは他にも33、36、39、41と計5枚があって、
やっぱりジョンはスモーキーが大好きで、
歌詞にこだわっていたんだなあと実感。
スモーキー好き人間としても、感無量でした。
04:My Girl / Otis Redding
テンプテーションズ Temptationsのオリジナルではなく、
オーティス・レディングで選んでいたのがミソ。
テンプスのはソフト過ぎるのかな・・・
だけどこれを選んでいるところで、01の意外さが消えました。
ジョンもやっぱり熱唱系も好きなんですね。
ちなみにこれもスモーキー・ロビンソンの手になる曲。
06:High-Heel Sneakers / Len Barry
これは、ポール・マッカートニー Paul McCartneyが
UNPLUGGEDでカバーしていて知っていましたが、
そろそろオリジナルを聴いてみたいですね。
14:Long Tall Sally / Little Richard
15:Money / Barrett Strong
26:Twist And Shout / The Isley Brothers
37:Bad Boy / Larry Williams
ビートルズが公式にカバーした曲が4曲ありました。
14はビートルズではポールが歌っていますが、
ほんとはジョンが歌いたかったのかな(笑)。
15はジョンが歌い、ソロのコンサートでも演奏した大のお気に入り。
26は昨年、四半世紀を経て初めてオリジナルを聴きました(笑)。
37、ラリー・ウィリアムスは一方、そろそろ買って聴きたい・・・
これらの曲は、自分たちがカバーした後でも
好んで聴いていたのが興味深いですね。
07

17:Positively 4th Street
ジョンがボブ・ディランを大好きだったのは有名な話ですが、
これはシングルのみのリリース、だからここにあって当然ですね。
きっとLPの曲はLPで聴いていたでしょうから。
18:Daydream / Lovin' Spoonful
24:Do You Believe In Magic / Lovin' Spoonful
ラヴィン・スプーンフルが2曲あったのが意外でした。
僕は、彼らはつい最近聴き始めたばかりで、
24は最初に買った彼らのアルバムの表題曲で好きですが、
18の曲は知らなくて、次に彼らのCDを買うならそれと思い
ウィッシュリストに入れて数カ月が経っていました。
だからこれを見て、ジョンに頭を叩かれたような気がして、
札幌に帰ったらすぐにAmazonで注文しようと思いました。
しかし、その3日後、関内のディスクユニオンに行くと、
まさにそのCDのリイシューの国内盤の中古があったのです。
ただ、僕は海外盤を買ってきていたので少し悩みましたが、
これはきっとジョンに導かれたのだと思い、買いました。
そして件の曲"Daydream"を聴いて驚きました。
「あ、この曲知ってる!」
20年かそこら前にCMで使われていて、出だしのところは
口ずさめるくらいに知っている曲だったのです。
僕はCMで使われた曲は割とこまめにチェックしているのですが、
この曲はどうしてそこで誰の曲かまでたどり着かなかったのか、
自分でも不思議でした。
でも多分当時は、僕の人生でいちばん音楽への熱が低かった、
そんな頃だったのだと思います。
ともあれ、この曲については、よかった、
落ち着くところに落ち着いた感じがします。
08

20:Slippin' And Slidin' / Buddy Holly
21:Be-Bop-A-Lula / Gene Vincent
29:Slippin' And Slidin' / Little Richard
34:Bring It On Home To Me / The Animals
こちらはジョンがROCK 'N' ROLLでカバーした曲。
20と29は同じ曲を違う人で入れているのが興味深い。
しかし僕はこれ、バディのはまだ聴いたことがない。
25:Some Other Guy / The Big Three
これはビートルズのバージョンがBBCで聴けます。
27:She Said Yeah / Larry Williams
僕はこの曲を、ローリング・ストーンズ Rolling Stones
のカバーで知りました。
22:No Particular Place To Go / Chuck Berry
28:Brown Eyed Handsome Man / Chuck Berry
チャック・ベリーが2曲あるのは納得ですね。
もっと多くないところがいかにもジョンらしいというか(笑)。
28はポール・マッカートニーが、ほとんどがカバー曲の
アルバムRUN DEVIL RUNでカバーしていますが、
アコーディオンを入れたポールのバージョンも僕は大好きです。
38:Agent Double-O-Soul / Edwin Starr
この曲はうちにベスト盤があるからあるはずだよな・・・
と思いつつ、その時点では知らない曲で、
札幌に帰って早速聴くと、カッコいい曲でした。
だけど、この中で僕が知っている曲の中では、
群を抜いて「黒い」のですが、それをジョンが好きというのは
少し意外な感じがしました。
しかし、エドウィン・スターの代表曲はWarですが、
後にそういうメッセージソングを発表していて、
ジョンはその辺りに近しいものを感じたのかもしれません。
ベスト盤を聴いているととにかくカッコいいので
エドウィン・スターから先ず聴こうかな。
09

以上、知っている曲についてさらりと触れましたが、
僕がCDを持っている曲は、18曲でした。
この記事を上げたのを機に、僕は、少しずつ、
残りの23曲のCDを買って聴いてゆこうと思いました。
今年の目標、そうですね、今年度、くらいでちょうどいいかな。
ミュージアムの話をもうひとつ。
3月に行った際には「出張中」だった、
ジョンがニューヨークのコンサートで使っていた、
レス・ポールJrが戻ってきていて、見ることができました。
よかった!
実物を見ると、僕のレス・ポールJrとは違い、
コントロールノブが2つしかないタイプのものでしたが、
でも、いいんです、同じということにしておきます(笑)。
10

それまで行ったことがなかったくせに
いまさらこんなこと言うのもなんですが、でも、
ミュージアムがなくなるのは、かなり、とっても残念です。
駅から降りて、車が通る道路を歩くことなく、
デッキでつながっていてゆっくりと歩ける場所もいいですし、
JR上野駅から30分で着けるのも、僕にはいいところでした。
横には「さいたまスーパーアリーナ」がありますが、僕は多分、
いつかきっと、そこにコンサートに行くことがあると思います。
その時に、ジョンの写真がないのを見ると、寂しいだろうなぁ。
心の拠り所としてはもちろんジョンは永遠に変わらないけど、
でも、実際に、場所としての拠り所があるというのは、
それはそれで素敵なことだと思い直しました。
でも、ヨーコさんが
「10年も続くと思っていなかった、そのことに感謝します」
と、あくまでも前向きにメッセージを発してくれているのが
ほっとする部分で、ありがたいことだと思います。
ありがとう。
11

「Ai ジョン・レノンが見た日本」(ちくま文庫)
単行本は持っているけど、文庫版は持っていないので
買うつもりだったこの本も、ミュージアムのショップにありました。
そしてこの写真は、いつものおまけで、
ジョンの顔をハウの顔に重ねて撮ろうとしたところ、
大きさが合いませんでした(笑)。
★☆
01 In The Midnight Hour / Wilson Pickett
02 Rescue Me / Fon Tella Bass
03 Tracks Of My Tears / Smokey Robinson & The Miracles
04 My Girl / Otis Redding
05 1-2-3 / Len Barry
06 High Heel Sneaker / Tommy Tucker
07 The Walls / Jimmy McCraddin
08 Gonna Send Me To Georgia / Timmy Show
09 First I Look At The Purse / The Contours
10 New Orleans / Gary US Bands
11 Watch Your Step / Bobby Parker
12 Daddy Rollin' Stone / Derek Martin
13 Short Fat Fannie / Larry Williams
14 Long Tall Sally / Little Richard
15 Money / Barrett Strong
16 Hey Baby / Bruce Channel
17 Positively 4th Street / Bob Dylan
18 Daydream / Lovin' Spoonful
19 Turquoise / Donovan
20 Slippin' And Slidin' / Buddy Holly
21 Be-Bop-A-Lula / Gene Vincent
22 No Particular Place To Go / Chuck Berry
23 Steppin' Out / Paul Revere & The Raiders
24 Do You Believe In Magic ? / Lovin' Spoonful
25 Some Other Guy / The Big Three
26 Twist And Shout / The Isley Brothers
27 She Said Yeah / Larry Williams
28 Brown Eyed Handsome Man / Chuck Berry
29 Slippin' And Slidin' / Little Richard
30 Quarter To Three / Gary U.S. Bands
31 Oh My Soul / Little Richard
32 Woman Love / Gene V
33 Shop Around / Smokey Robinson & The Miracles
34 Bring It On Home To Me / The Animals
35 If You Gotta Make A Fool Of Somebody
/ James Ray with THe Hatch Davie Orchestra
36 What's So Good About Goodbye
/ Smokey Robinson & The Miracles
37 Bad Boy / Larry Williams
38 Agent Double-O-Soul / Edwin Starr
39 I've Been Good To You
/ Smokey Robinson & The Miracles
40 Oh I Apologize / Barrett Strong
41 Who's Loving You / Smokey Robinson & The Miracles
2013年03月20日
ジョン・レノン・ミュージアムとDOUBLE FANTASY
いつものように
写真など音楽とは関係ないコメントも
大歓迎です!
01 犬もダブル、LPとCDでアルバムもダブル

DOUBLE FANTASY John Lennon & Yoko Ono
ダブル・ファンタジー ジョン・レノン&ヨーコ・オノ
released in 1980
ジョン・レノン・ミュージアムが、
2010年9月30日をもって閉館となります。
僕は行ったことはなかったので、
コンサートで東京に行った際に行きました。
中は撮影禁止のため写真での紹介ができないのですが、
行ったことは何かのかたちで記事に残そうと思っていました。
そこで思いついたのが、アルバムもしくは曲の記事に織り込むこと。
そしてやはりここは、このアルバムがよいのではないかと。
ミュージアムの感想を少しだけ話します。
展示物が豊富で見ていて楽しくなり、文字情報が多いので
読みながら歩くと意外と時間がかかりましたが、とても充実していました。
特に面白かった展示を幾つか。
★キャバーン・クラブを再現したまさに洞窟のような狭くて暗いブース。
実際のキャバーンの広さでその空間が再現されていたようで、
奥の画面ではキャバーン時代のビートルズのライヴ映像が流れていて、
当時の会場の雰囲気を、意外なほどによく感じることができました。
★ジョンがヨーコさんと出会った個展において、
天上に小さく"Yes"と書いたヨーコさんの前衛芸術を再現していて、
階段を登ってその文字を見るのは面白かったです。
実際には虫眼鏡があったのですが、それでも雰囲気は分かりました。
「Yesだから気に入った。他の言葉ならすぐに退出していた」
というのは、ジョンが、ヨーコさんとの出会いを回想した言葉。
★出口の前に、白い壁を椅子に座って眺める広場があり、そこには、
ジョンの歌詞の一節が日本語と英語で書き出されていて、
それを読むだけでも、たくさんの言葉を紡ぎ出した人だったんだな
と感慨にふけりました。
そしてこれは、自分でも、ジョンに限らずですが、
好きな歌詞を書き出して何かの形にしてみたいと思いました。
★残念だったのは、ジョンがニュー・ヨークのコンサートで使っていた、
レス・ポールJrが貸し出し中で写真しか見られなかったことです。
僕が持っているのと似ているあのレス・ポール。
お土産も計4点を買いました。
グッズショップは入場料を払わなくても入れる場所にあるので、
2日後に、ショップだけもう一度行って買い足しもしました。
写真02は、買い足したトートバッグ。
展示されていた、ジョンが描いた世界平和を訴えるオットセイの絵が
とっても楽しくて、そのグッズがあれば買いたいと思っていたところ、
これを見つけました。
そういえば僕は、シェリル・クロウとジャクソン・ブラウンのコンサートでも、
トートバッグを買いましたが、もはやトート集めが趣味なのかも(笑)。
02 ミュージアムのお土産、オットセイのトートバッグ

アルバムの話にいきます。
このアルバムは、ショーン君が生まれたのを機に、
1976年引退して主夫生活をしていたジョン・レノンが、
5年振りに録音し発表したアルバム。
その5年間、リンゴ・スターにCookin' (In The Kitchen Of Love)
という曲を書いて手伝った以外は、音楽から離れて暮らし、
レコード会社の契約もない、まさに自由な生活を営んでいました。
主夫時代に家族で来日していた話は今では有名ですが、
ミュージアムではその様子の写真を見るのも楽しかったです。
ジョンが、ほんとに「ただのお父さん」だったことが微笑ましかった。
なんでも、また音楽をやろうと思ったきっかけが、ショーン君に、
「パパはビートルズだったの?」と聞かれたことだったのだとか。
アルバムは、ヨーコ・オノとの対話形式で構成されていて、
2人の曲が7曲ずつ、ほぼ交互に出てきます。
録音は、1980年8月6日から9月24日までの間、
ニュー・ヨークのスタジオ「ヒット・ファクトリー」で行われました。
ジョンは、再出発、というより「まったく新たな出発」に際して
新たにミュージシャンを募りましたが、それが以下のメンバーです。
ジャック・ダグラス Jack Douglas (プロデュース)
アール・スリック Earl Slick (ギター)
ヒュー・マクラケン Hugh McCracken (ギター)
トニー・レヴィン Tony Levin (ベース)
ジョージ・スモール George Small (キーボード)
アンディ・ニューマーク Andy Newmark (ドラムス)
アーサー・ジェンキンス・Jr Arthur Jenkins Jr. (パーカッション)
アール・スリックは今はDavid Bowieのバンドにいますが、
かつて、Brian Setzerが抜けたStray Catsの2人と
ファントム、ロッカー&スリックというバンドを組んでいたこともあります。
その音源はCDでは手に入らないようなのですが。
トニー・レヴィンは後にPeter Gabrielのバンドなどで活躍し、
まさにロック界の「ベースの巨人」の一人となってゆきます。
僕は彼を、Anderson, Bruford, Wakeman Howeの来日公演で
見たことがありますが、実は、そのことは後で知りました・・・
なお、この時、かつてWALLS AND BRIDGESなどで共演した
ジェシ・エド・デイヴィス Jesse-Ed Davisが参加したいと伝えたところ、
ジョンのほうから断ったという逸話もあります。
ジェシ・エド・デイヴィスは、ジョンがヨーコさんと別居していた頃の
「飲み友達」の一人でしたが、ジョンは、「新たなる出発」に際して、
その頃のことを思い出したくなかったのかもしれません。
アルバムは1980年11月17日に発売されました。
そして、1980年12月8日、すべてが一変しました。
今回も恒例の「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、
ジョンのコメントを引用してゆきます。
このアルバムのジョンの曲はすべてにジョンのコメントがあります。
また、ジョンの言葉を中心に進めてゆき、長くなりすぎるので、
僕の思いはなるべく短めに進めてゆきます。
なお、引用について、一部表記の変更と改行を引用者が施しています。
それから、曲名の右のJはジョン、Yはヨーコがヴォーカルという意味です。
03 ミュージアムの入り口のジョン、above us only sky

Tr1:(Just Like) Starting Over J
この曲には、ヨーコさんのコメントもあるので、ジョンに続けて紹介します。
なお、ヨーコさんの部分については引用者が大幅に手を加えています。
JL:歌詞どおりの曲。ヨーコが仕事中で、
ショーンを連れてバミューダに行っていた時に書いた。
そういう形でできた。
他の曲はもうできていて、これとCleanup Timeはいわば、
仕事を終えた後の楽しみというような感じだった。
この曲は50年代風のサウンドだけど、
その手のサウンドをぼくは一度も書いていないんだ。
あの時代はぼくの時代だし、ぼくは共感を覚えていたんだ。
で、ぼくは考えたわけさ。やってみようじゃないかって。
ビートルズ時代にそれをやったら冗談だと思われただろう。
好きで使い古しをやる奴もいないからね。
でも、今となっては、それはもう使い古しじゃなくなったんだからさ。
「翼をひろげて飛ぼう!」 "It's time to spread our wings and fly"
というフレーズをぼくは取っちゃうところだった。
というのも、なんてこった、みんなきっと
「ウィングスってなんのことを言ってるのだろう」
て言うだろうと思ったんでね。
この曲は、ウィングスとはいかなる関係もない。
※ジョンが「ウィングス」 Wingsにこだわっているは、
ポール・マッカートニー&ウィングスを意味するものと思われる。
YO:(Just Like)Starting Overは
私を泣きたい気持ちにさせる曲なの。
60年代がどのようにして私たちに自由というものを-
性やその他の自由というものの一端を味わわせてくれたかを
ジョンが話したことがあったわ。
その後の70年代には、男と女は、なんとなく、
互いがどちらへ進もうとしているのかを見失ってしまって、
たくさんの家族や人間関係がバラバラになってしまったのよ。
ジョンはこの歌の中でこう言おうとしているの。
「いいだろう、60年代のぼくたちはエネルギーを持っていた。
70年代には、ぼくたちはばらばらになった。
でも、80年代には、もう一度やり直そうじゃないか」
GB:この曲はアルバムからの最初のシングルとしてリリースされ、
ジョンの死後、1980年12月27日から5週間No.1に輝きました。
それはジョンにとっても最後のNo.1ヒット曲でした。
この曲について何かを言おうとすると、胸が詰まります。
コード進行だけで聴かせるギターが素敵、とだけ今は書いておき、
いつかまた、個別の記事にしたい曲です。
Tr2:Kiss Kiss Kiss Y
この曲はヨーコさんのコメントがあるのでを紹介します。
YO:(Just Like) Starting Overの反対側の面には
私のKiss Kiss Kissが入っているの。
これは同じ問題の反対側の面を歌ったものよ。
クライマックスに達しようとしている女性の声が入っているのよ。
GB:「抱いてっ」て・・・今でも聴いているとこっ恥ずかしくなります・・・
中高生の頃は親の前では聴けなかった(笑)。
実は僕、このアルバムのジョンの曲については、
Tr5以外をまとめてFMで放送された際にエアチェックし
テープでジョンの曲だけをずっと繰り返し聴いていて、
レコードを買ったのは少し後のことだったのです。
だから、レコードではいきなりこの曲が出てきて、慌てました・・・
03:Cleanup Time J
JL:これはピアノのソロに詞をつけたものだ。
詩を読めば分かるけど、まるでストレートな曲なんだ。
バミューダから電話してまたジャック・ダグラスと話していたら、
70年代の事や、ドラッグやアルコールからぬけ出してきた
人達のことに話がいった。
彼が「そうさね、今は足を洗う時じゃないのかな?」と言った。
ぼくは「まったくだ」と答えて電話を切ったんだ。
そのまますぐにピアノに向かって、ブギーを弾きはじめたら、
Cleanup Timeという曲が出てきた。そして考えた。
これは何だ! タイトルだけじゃないか。
そこで、曲に合わせて詞を書いてみたんだ。
これはいわば、ジョンとヨーコが自分の宮殿である
ダコタハウスのことを歌っているんだね。
(歌いながら)女王様は会計事務所の一室にいる。
金勘定だ。王は台所にいるよ。
GB:この曲はなんというか、ソウルっぽいのかな、
最初に聴いた時に、ジョン・レノンらしくないと思いました。
といって、最初に聴いたのはまだ中学生で、
ジョンのことも洋楽のことも何も知らないに等しかったのですが、
少なくとも、それまで僕が接してきたジョンとは違うな、って。
しかし、クールで都会的に洗練された響き、
これがニューヨークの音なのかな、と思うようになった曲でもあります。
Tr4:Give Me Something Y
GB:ここでのヨーコさんの曲は攻めの一手という感じがしますが、
それで2人はつり合いがとれた、よいパートナーだったのでしょうね。
04 ミュージアムのお土産、ペンケース

Tr5:I'm Losing You J
JL:過去を歌った曲だけど、実際に書きはじめたのは、
バミューダからニューヨークのヨーコに電話をしたのに
通じなかった時だよ。
その時はぼくは気が狂うほど腹がたって、孤独で、
ひとりぼっちの気分を味わった。
それと、70年代初期の別居期間のことも入っている。
その頃、ぼくは、肉体的にも彼女に会えなくなってしまっていたんだ。
だから、この曲は、いついつのどれこれの事を歌ったものじゃない。
GB:続いてやはりジョンっぽくないなと感じた曲。
AORじゃないけど落ち着いた響きは時代の音だったのかもしれません。
しかしそれもきわめて自然に聴こえてくるのは、まさにジョン。
サビのタイトルの言葉をジョンが歌った後に入る、
狂おしいギターの音が効果的で昔からとっても好きです。
Tr6:I'm Moving On
GB:タイトルも曲のイメージもTr5からうまくつながっています。
Tr7:Beautiful Boy (Darling Boy) J
JL:さて、この曲については何を言えばいいんだろう。
これはショーンについて歌ったもの。
曲と詞が同時に頭に浮かんだ。
GB:こんな素敵な曲はそうはない、唯一無二。
いつ聴いても心が洗われるし、ほろっとさせられてしまう歌。
この曲は歌詞をすべて引用したいくらい大好きで、ジョンのみならず、
すべてのロックの楽曲で最も好きな歌詞のひとつ。
♪ Life is what happens to you
while you're busy making another plan
このくだりを読んだ時、歌詞の面白さを知ったような気がしました。
これもいつか単独の記事にして、もっともっと話したいです。
今ではジョンの代表曲のひとつに挙げられるでしょうね。
05 ミュージアムのエントランスホールにあるジョンのコラージュ

Tr8:Watching The Wheels J
JL:これは「ニュー・ヨーク・タイムズ」に掲載された
ジョンとヨーコからのラブレターをそのまま歌にしたような曲だ。
ぼくは前からこのこと-運命の輪廻-を見つめる事を続けていた。
人は、ぼくがなまけ者だとか、夢ばかりみて生きている人生だという。
ポップスター達ときたら、ぼくがレコードを作らないことを
マスコミの中でケチをつけていた。
ほんとに信じられなかった。
彼らはまるでぼくの義理の母のようにふるまうんだ。
それがミック(・ジャガー)だったか、誰だったか知りはしない。
これからの人生で、ぼくがもう1枚もレコードを作らないとしても、
一体彼らとどういう関係があるんだい。
GB:映画『イマジン』には、この曲のレコーディング風景があって、
ジョンはそこで「Imagineよりも重く」とスタジオで指示していました。
僕はその時、そうかこの曲は、最初のコード進行がC→Fなんだ、
と思い、家に帰ってギターで弾くと、その通りでした。
直接的なつながりはないのですが、僕はその時から、
これはImagineの続編というか補完の曲だと思うようになりました。
♪ People say I'm lazy, dreamin' my life away
サビの部分の滑るようなベースが好きですが、
ベースにのせられて踊りだしたいところをジョンが押さえこんでいる、
そんな感じがもします。
アルバムからの第3弾シングルカット曲で、最高位10位。
Tr9:Yes I'm Your Angel Y
GB:スタンダード風のお洒落な曲で、
ポール・マッカートニーが得意なディキシーランド・スタイル。
ジョンは、ポールが作ったWhen I'm Sixty-Fourのことを
「僕には夢の中でも思いつかない曲」と言っていたけど、
でも、ジョンはほんとはそうしたポールの曲が好きだったのかも。
そして、自分は作れないのでヨーコさんに作ってもらった。
なんて考えるとほのぼのとする曲ですね(笑)。
Tr10:Woman J
JL:これはヨーコと、ある意味ではすべての女性に対する曲だ。
ぼくは女性とのつきあいの歴史はとてもマッチョ(タフガイ的)で、
とてもくだらなかった。
概してひどく神経質で落ち着きがないくせに攻撃的にふるまう
典型的な男のタイプだったから、とても貧しいものだった。
ほら、そういうタイプの男は女性的な部分を隠そうとするんだけど、
ぼくには今でもそんなところがある。
でも、ぼくは今、優しくふるまっても構わないのだという事を知った。
そっちの自分でいたほうがくつろげるんだから。
心が荒んだ時、昔ならカウボーイ・ブーツをはこうとしていたけど、
今ならスニーカーをはくだろう。
それでいいんだ。
この曲は多分に自明な曲だね。
GB:これは僕が初めて買ったジョンのレコードです。
ラジオで最初に聴いて、とにかくその美しさに感動して、
すぐに近くのレコード屋さんでドーナツ盤を買い求めました。
シングルチャートでは惜しくも最高位2位。
この曲は、40の男が、無防備といってもいいほどに、ここまでも
心がきれいになれるものなのかというところにひたすら感動します。
そして、普通に喋ると恥ずかしくてしょうがないようなことを
まるでおとぎ話のように仕立て上げたジョン。
子どもの心で大人の気持ちを歌っているのが、よく伝わるところでしょう。
この曲も歌詞をすべて引用したいくらいに心にしみてきます。
そして僕は数年後、Rod Stewartが歌っていた、 Van Morrisonの
Have I Told You Latelyを聴き、歌詞をじっくりと読んだ時、
この曲の続編に出会えたような気がしてうれしかったです。
実生活では、どちらもまだ自分には訪れていない状況だし、
これからも訪れるかどうか分からないのですが・・・
でも、正直、この曲は、自分の心がしっかりしていないと感じる時は、
聴いていると、ある意味つらくなる曲でもあります・・・
それにしても、この曲のジョンの達観といったら。
と、やはり、この曲だけは話を短くできなかったです(笑)。
Tr11:Beautiful Boys Y
GB:これはTr7へのヨーコさんのアンサーソングのようなものですが、
ほの暗い雰囲気に包まれスパニッシュ・ギターも入るこの曲は、
ショーン君が生まれるまでの大変さを物語っているようにも感じます。
Tr12:Dear Yoko J
JL:うーん、何て言えばいいんだろう。
(歌いながら)♪もう何年もたったのに、まだ・・・・・・♪
この言葉がすべてを物語っているな。
この曲は最高さ。
ほら、あるだろう、「ディア・サンドラ」とか、
どっかの歌手が実在しなかったりする女のことを歌ってる歌が。
そんな曖昧な人のことじゃなくて、
これはたまたま、ぼくの妻の歌なんだ。
GB:うーん、何て言えばいいんだろう(笑)。
この曲は大好きですよ!
キレがあってホップするギターの音が楽しいです。
Tr13:Everyman Has A Woman Who Loves Him Y
GB:アルバムではヨーコさんが歌っていますが、これはジョンの死後に、
ジョンが歌ったバージョンのビデオクリップが作られ流されていたので、
僕には、ジョンのことが直結してしまい、聴くのがちょっとつらい曲です。
Tr14:Hard Times Are Over YwithJ
GB:最後はデュエットでしめるという流れが素晴らしく、
ジョンとヨーコのそれまでの夢というか理想の音楽が
ついに現実となった、そんなメッセージを感じます。
そして、この話の続きは、後に再び出てきます。
このアルバム、当時はGeffenからリリースされていて、
CD化時代の初期にはGeffenからCDが出ていましたが、
現在は権利関係が移ってCapitolから出ています。
そして現行盤は、デモなどのボーナストラックが3曲収録されています。
僭越ながら、個人的な逸話をひとつ。
このアルバムは、1982年度のグラミー賞において、
最優秀アルバム賞を受賞しました。
そのことを、中学生時代の僕は一般のニュースを見て知りました。
当時は、音楽の話題を一般のニュースで取り上げられることは、
それこそジョンの死やポール・マッカートニーの逮捕といった、
事件性があるもの以外はほとんどなかったので、
僕はそのニュースがとてもうれしかったのです。
そして、当時購読していた『FMファン』の読者のページに、
そのことを文章にまとめて投稿したところ、採用されて載りました。
雑誌を買ってページを開き、そこに自分の名前を見つけたのは
とてもうれしかったですが、レコードのギフト券をもらえたことが、
もっとうれしかったです(笑)。
いつも引用しているジョンのインタビューは、当然のことながら
このアルバムのプロモーションの一環として行われたもので、
このアルバムについてのジョンのコメントも紹介します。
(DOUBLE FANTASY「ふたつの幻想」とはどういう意味ですか?)
JL:花だよ、フリージアの一種だよ。
でも、ぼくたちにとっての意味は、
ふたりの人間が同時に同じイメージを描いた時、
それが秘訣だってことだね。
一緒になったふたりの人間がふたつの違ったイメージを描き、
その時点では強いほうが自分のほうの幻想を
実現できるということもあるけど、一方、
寄せ集め以外の何物もでもないものしか手に入らないこともある。
(新しいアルバムに盛られたメッセージを簡単に話してください)
JL:非常に簡単に言うと、
ふたりの人間の間のごく普通のことについてなんだよ。
歌詞は単刀直入でね。率直でストレートなんだ。
GB:「ダブル・ファンタジー」は、フリージアの品種だったのですね。
ネットで調べたところ、ジョンが見たのは黄色い八重咲きの品種で
しかし今はその品種はほとんど栽培されなくなっているらしく、
世界中でこの花の品種を探している人がいることを知りました。
最後に、ジョン・レノン・ミュージアムに行ってみて、
そこが思いの外気持ちのよい空間であることを感じました。
「さいたま新都心」駅からデッキでつながっていて、
車の往来とは関係なくゆっくりと歩いてゆけるのがいいです。
入館しなくてもグッズが買えたり、ジョンの大きな写真が見られるのは
そこに行くだけでも楽しくなります。
しかも、弟の家がある入谷からだと、鶯谷駅から京浜東北線を使い、
ドアトゥドアで1時間かからないで行けるのは気持ちが楽です。
それまでは行かなかった人間なので偉そうなことは言えないですが、
なくなるというのは、やはり、残念ですね。
でも、最後に行けてよかったです。
閉館までにもう1回行けないかな、と、今は思い始めています。
写真も、ここで使った3枚と他1枚しか撮らなかったのが、
今となってはやはり、もう少し撮ればよかったなぁと。
最後は、ジョン・レノン・ミュージアムのジョンの写真を。
06

JLM、札幌に再開館しないかな(笑)。
写真など音楽とは関係ないコメントも
大歓迎です!
01 犬もダブル、LPとCDでアルバムもダブル

DOUBLE FANTASY John Lennon & Yoko Ono
ダブル・ファンタジー ジョン・レノン&ヨーコ・オノ
released in 1980
ジョン・レノン・ミュージアムが、
2010年9月30日をもって閉館となります。
僕は行ったことはなかったので、
コンサートで東京に行った際に行きました。
中は撮影禁止のため写真での紹介ができないのですが、
行ったことは何かのかたちで記事に残そうと思っていました。
そこで思いついたのが、アルバムもしくは曲の記事に織り込むこと。
そしてやはりここは、このアルバムがよいのではないかと。
ミュージアムの感想を少しだけ話します。
展示物が豊富で見ていて楽しくなり、文字情報が多いので
読みながら歩くと意外と時間がかかりましたが、とても充実していました。
特に面白かった展示を幾つか。
★キャバーン・クラブを再現したまさに洞窟のような狭くて暗いブース。
実際のキャバーンの広さでその空間が再現されていたようで、
奥の画面ではキャバーン時代のビートルズのライヴ映像が流れていて、
当時の会場の雰囲気を、意外なほどによく感じることができました。
★ジョンがヨーコさんと出会った個展において、
天上に小さく"Yes"と書いたヨーコさんの前衛芸術を再現していて、
階段を登ってその文字を見るのは面白かったです。
実際には虫眼鏡があったのですが、それでも雰囲気は分かりました。
「Yesだから気に入った。他の言葉ならすぐに退出していた」
というのは、ジョンが、ヨーコさんとの出会いを回想した言葉。
★出口の前に、白い壁を椅子に座って眺める広場があり、そこには、
ジョンの歌詞の一節が日本語と英語で書き出されていて、
それを読むだけでも、たくさんの言葉を紡ぎ出した人だったんだな
と感慨にふけりました。
そしてこれは、自分でも、ジョンに限らずですが、
好きな歌詞を書き出して何かの形にしてみたいと思いました。
★残念だったのは、ジョンがニュー・ヨークのコンサートで使っていた、
レス・ポールJrが貸し出し中で写真しか見られなかったことです。
僕が持っているのと似ているあのレス・ポール。
お土産も計4点を買いました。
グッズショップは入場料を払わなくても入れる場所にあるので、
2日後に、ショップだけもう一度行って買い足しもしました。
写真02は、買い足したトートバッグ。
展示されていた、ジョンが描いた世界平和を訴えるオットセイの絵が
とっても楽しくて、そのグッズがあれば買いたいと思っていたところ、
これを見つけました。
そういえば僕は、シェリル・クロウとジャクソン・ブラウンのコンサートでも、
トートバッグを買いましたが、もはやトート集めが趣味なのかも(笑)。
02 ミュージアムのお土産、オットセイのトートバッグ

アルバムの話にいきます。
このアルバムは、ショーン君が生まれたのを機に、
1976年引退して主夫生活をしていたジョン・レノンが、
5年振りに録音し発表したアルバム。
その5年間、リンゴ・スターにCookin' (In The Kitchen Of Love)
という曲を書いて手伝った以外は、音楽から離れて暮らし、
レコード会社の契約もない、まさに自由な生活を営んでいました。
主夫時代に家族で来日していた話は今では有名ですが、
ミュージアムではその様子の写真を見るのも楽しかったです。
ジョンが、ほんとに「ただのお父さん」だったことが微笑ましかった。
なんでも、また音楽をやろうと思ったきっかけが、ショーン君に、
「パパはビートルズだったの?」と聞かれたことだったのだとか。
アルバムは、ヨーコ・オノとの対話形式で構成されていて、
2人の曲が7曲ずつ、ほぼ交互に出てきます。
録音は、1980年8月6日から9月24日までの間、
ニュー・ヨークのスタジオ「ヒット・ファクトリー」で行われました。
ジョンは、再出発、というより「まったく新たな出発」に際して
新たにミュージシャンを募りましたが、それが以下のメンバーです。
ジャック・ダグラス Jack Douglas (プロデュース)
アール・スリック Earl Slick (ギター)
ヒュー・マクラケン Hugh McCracken (ギター)
トニー・レヴィン Tony Levin (ベース)
ジョージ・スモール George Small (キーボード)
アンディ・ニューマーク Andy Newmark (ドラムス)
アーサー・ジェンキンス・Jr Arthur Jenkins Jr. (パーカッション)
アール・スリックは今はDavid Bowieのバンドにいますが、
かつて、Brian Setzerが抜けたStray Catsの2人と
ファントム、ロッカー&スリックというバンドを組んでいたこともあります。
その音源はCDでは手に入らないようなのですが。
トニー・レヴィンは後にPeter Gabrielのバンドなどで活躍し、
まさにロック界の「ベースの巨人」の一人となってゆきます。
僕は彼を、Anderson, Bruford, Wakeman Howeの来日公演で
見たことがありますが、実は、そのことは後で知りました・・・
なお、この時、かつてWALLS AND BRIDGESなどで共演した
ジェシ・エド・デイヴィス Jesse-Ed Davisが参加したいと伝えたところ、
ジョンのほうから断ったという逸話もあります。
ジェシ・エド・デイヴィスは、ジョンがヨーコさんと別居していた頃の
「飲み友達」の一人でしたが、ジョンは、「新たなる出発」に際して、
その頃のことを思い出したくなかったのかもしれません。
アルバムは1980年11月17日に発売されました。
そして、1980年12月8日、すべてが一変しました。
今回も恒例の「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、
ジョンのコメントを引用してゆきます。
このアルバムのジョンの曲はすべてにジョンのコメントがあります。
また、ジョンの言葉を中心に進めてゆき、長くなりすぎるので、
僕の思いはなるべく短めに進めてゆきます。
なお、引用について、一部表記の変更と改行を引用者が施しています。
それから、曲名の右のJはジョン、Yはヨーコがヴォーカルという意味です。
03 ミュージアムの入り口のジョン、above us only sky

Tr1:(Just Like) Starting Over J
この曲には、ヨーコさんのコメントもあるので、ジョンに続けて紹介します。
なお、ヨーコさんの部分については引用者が大幅に手を加えています。
JL:歌詞どおりの曲。ヨーコが仕事中で、
ショーンを連れてバミューダに行っていた時に書いた。
そういう形でできた。
他の曲はもうできていて、これとCleanup Timeはいわば、
仕事を終えた後の楽しみというような感じだった。
この曲は50年代風のサウンドだけど、
その手のサウンドをぼくは一度も書いていないんだ。
あの時代はぼくの時代だし、ぼくは共感を覚えていたんだ。
で、ぼくは考えたわけさ。やってみようじゃないかって。
ビートルズ時代にそれをやったら冗談だと思われただろう。
好きで使い古しをやる奴もいないからね。
でも、今となっては、それはもう使い古しじゃなくなったんだからさ。
「翼をひろげて飛ぼう!」 "It's time to spread our wings and fly"
というフレーズをぼくは取っちゃうところだった。
というのも、なんてこった、みんなきっと
「ウィングスってなんのことを言ってるのだろう」
て言うだろうと思ったんでね。
この曲は、ウィングスとはいかなる関係もない。
※ジョンが「ウィングス」 Wingsにこだわっているは、
ポール・マッカートニー&ウィングスを意味するものと思われる。
YO:(Just Like)Starting Overは
私を泣きたい気持ちにさせる曲なの。
60年代がどのようにして私たちに自由というものを-
性やその他の自由というものの一端を味わわせてくれたかを
ジョンが話したことがあったわ。
その後の70年代には、男と女は、なんとなく、
互いがどちらへ進もうとしているのかを見失ってしまって、
たくさんの家族や人間関係がバラバラになってしまったのよ。
ジョンはこの歌の中でこう言おうとしているの。
「いいだろう、60年代のぼくたちはエネルギーを持っていた。
70年代には、ぼくたちはばらばらになった。
でも、80年代には、もう一度やり直そうじゃないか」
GB:この曲はアルバムからの最初のシングルとしてリリースされ、
ジョンの死後、1980年12月27日から5週間No.1に輝きました。
それはジョンにとっても最後のNo.1ヒット曲でした。
この曲について何かを言おうとすると、胸が詰まります。
コード進行だけで聴かせるギターが素敵、とだけ今は書いておき、
いつかまた、個別の記事にしたい曲です。
Tr2:Kiss Kiss Kiss Y
この曲はヨーコさんのコメントがあるのでを紹介します。
YO:(Just Like) Starting Overの反対側の面には
私のKiss Kiss Kissが入っているの。
これは同じ問題の反対側の面を歌ったものよ。
クライマックスに達しようとしている女性の声が入っているのよ。
GB:「抱いてっ」て・・・今でも聴いているとこっ恥ずかしくなります・・・
中高生の頃は親の前では聴けなかった(笑)。
実は僕、このアルバムのジョンの曲については、
Tr5以外をまとめてFMで放送された際にエアチェックし
テープでジョンの曲だけをずっと繰り返し聴いていて、
レコードを買ったのは少し後のことだったのです。
だから、レコードではいきなりこの曲が出てきて、慌てました・・・
03:Cleanup Time J
JL:これはピアノのソロに詞をつけたものだ。
詩を読めば分かるけど、まるでストレートな曲なんだ。
バミューダから電話してまたジャック・ダグラスと話していたら、
70年代の事や、ドラッグやアルコールからぬけ出してきた
人達のことに話がいった。
彼が「そうさね、今は足を洗う時じゃないのかな?」と言った。
ぼくは「まったくだ」と答えて電話を切ったんだ。
そのまますぐにピアノに向かって、ブギーを弾きはじめたら、
Cleanup Timeという曲が出てきた。そして考えた。
これは何だ! タイトルだけじゃないか。
そこで、曲に合わせて詞を書いてみたんだ。
これはいわば、ジョンとヨーコが自分の宮殿である
ダコタハウスのことを歌っているんだね。
(歌いながら)女王様は会計事務所の一室にいる。
金勘定だ。王は台所にいるよ。
GB:この曲はなんというか、ソウルっぽいのかな、
最初に聴いた時に、ジョン・レノンらしくないと思いました。
といって、最初に聴いたのはまだ中学生で、
ジョンのことも洋楽のことも何も知らないに等しかったのですが、
少なくとも、それまで僕が接してきたジョンとは違うな、って。
しかし、クールで都会的に洗練された響き、
これがニューヨークの音なのかな、と思うようになった曲でもあります。
Tr4:Give Me Something Y
GB:ここでのヨーコさんの曲は攻めの一手という感じがしますが、
それで2人はつり合いがとれた、よいパートナーだったのでしょうね。
04 ミュージアムのお土産、ペンケース

Tr5:I'm Losing You J
JL:過去を歌った曲だけど、実際に書きはじめたのは、
バミューダからニューヨークのヨーコに電話をしたのに
通じなかった時だよ。
その時はぼくは気が狂うほど腹がたって、孤独で、
ひとりぼっちの気分を味わった。
それと、70年代初期の別居期間のことも入っている。
その頃、ぼくは、肉体的にも彼女に会えなくなってしまっていたんだ。
だから、この曲は、いついつのどれこれの事を歌ったものじゃない。
GB:続いてやはりジョンっぽくないなと感じた曲。
AORじゃないけど落ち着いた響きは時代の音だったのかもしれません。
しかしそれもきわめて自然に聴こえてくるのは、まさにジョン。
サビのタイトルの言葉をジョンが歌った後に入る、
狂おしいギターの音が効果的で昔からとっても好きです。
Tr6:I'm Moving On
GB:タイトルも曲のイメージもTr5からうまくつながっています。
Tr7:Beautiful Boy (Darling Boy) J
JL:さて、この曲については何を言えばいいんだろう。
これはショーンについて歌ったもの。
曲と詞が同時に頭に浮かんだ。
GB:こんな素敵な曲はそうはない、唯一無二。
いつ聴いても心が洗われるし、ほろっとさせられてしまう歌。
この曲は歌詞をすべて引用したいくらい大好きで、ジョンのみならず、
すべてのロックの楽曲で最も好きな歌詞のひとつ。
♪ Life is what happens to you
while you're busy making another plan
このくだりを読んだ時、歌詞の面白さを知ったような気がしました。
これもいつか単独の記事にして、もっともっと話したいです。
今ではジョンの代表曲のひとつに挙げられるでしょうね。
05 ミュージアムのエントランスホールにあるジョンのコラージュ

Tr8:Watching The Wheels J
JL:これは「ニュー・ヨーク・タイムズ」に掲載された
ジョンとヨーコからのラブレターをそのまま歌にしたような曲だ。
ぼくは前からこのこと-運命の輪廻-を見つめる事を続けていた。
人は、ぼくがなまけ者だとか、夢ばかりみて生きている人生だという。
ポップスター達ときたら、ぼくがレコードを作らないことを
マスコミの中でケチをつけていた。
ほんとに信じられなかった。
彼らはまるでぼくの義理の母のようにふるまうんだ。
それがミック(・ジャガー)だったか、誰だったか知りはしない。
これからの人生で、ぼくがもう1枚もレコードを作らないとしても、
一体彼らとどういう関係があるんだい。
GB:映画『イマジン』には、この曲のレコーディング風景があって、
ジョンはそこで「Imagineよりも重く」とスタジオで指示していました。
僕はその時、そうかこの曲は、最初のコード進行がC→Fなんだ、
と思い、家に帰ってギターで弾くと、その通りでした。
直接的なつながりはないのですが、僕はその時から、
これはImagineの続編というか補完の曲だと思うようになりました。
♪ People say I'm lazy, dreamin' my life away
サビの部分の滑るようなベースが好きですが、
ベースにのせられて踊りだしたいところをジョンが押さえこんでいる、
そんな感じがもします。
アルバムからの第3弾シングルカット曲で、最高位10位。
Tr9:Yes I'm Your Angel Y
GB:スタンダード風のお洒落な曲で、
ポール・マッカートニーが得意なディキシーランド・スタイル。
ジョンは、ポールが作ったWhen I'm Sixty-Fourのことを
「僕には夢の中でも思いつかない曲」と言っていたけど、
でも、ジョンはほんとはそうしたポールの曲が好きだったのかも。
そして、自分は作れないのでヨーコさんに作ってもらった。
なんて考えるとほのぼのとする曲ですね(笑)。
Tr10:Woman J
JL:これはヨーコと、ある意味ではすべての女性に対する曲だ。
ぼくは女性とのつきあいの歴史はとてもマッチョ(タフガイ的)で、
とてもくだらなかった。
概してひどく神経質で落ち着きがないくせに攻撃的にふるまう
典型的な男のタイプだったから、とても貧しいものだった。
ほら、そういうタイプの男は女性的な部分を隠そうとするんだけど、
ぼくには今でもそんなところがある。
でも、ぼくは今、優しくふるまっても構わないのだという事を知った。
そっちの自分でいたほうがくつろげるんだから。
心が荒んだ時、昔ならカウボーイ・ブーツをはこうとしていたけど、
今ならスニーカーをはくだろう。
それでいいんだ。
この曲は多分に自明な曲だね。
GB:これは僕が初めて買ったジョンのレコードです。
ラジオで最初に聴いて、とにかくその美しさに感動して、
すぐに近くのレコード屋さんでドーナツ盤を買い求めました。
シングルチャートでは惜しくも最高位2位。
この曲は、40の男が、無防備といってもいいほどに、ここまでも
心がきれいになれるものなのかというところにひたすら感動します。
そして、普通に喋ると恥ずかしくてしょうがないようなことを
まるでおとぎ話のように仕立て上げたジョン。
子どもの心で大人の気持ちを歌っているのが、よく伝わるところでしょう。
この曲も歌詞をすべて引用したいくらいに心にしみてきます。
そして僕は数年後、Rod Stewartが歌っていた、 Van Morrisonの
Have I Told You Latelyを聴き、歌詞をじっくりと読んだ時、
この曲の続編に出会えたような気がしてうれしかったです。
実生活では、どちらもまだ自分には訪れていない状況だし、
これからも訪れるかどうか分からないのですが・・・
でも、正直、この曲は、自分の心がしっかりしていないと感じる時は、
聴いていると、ある意味つらくなる曲でもあります・・・
それにしても、この曲のジョンの達観といったら。
と、やはり、この曲だけは話を短くできなかったです(笑)。
Tr11:Beautiful Boys Y
GB:これはTr7へのヨーコさんのアンサーソングのようなものですが、
ほの暗い雰囲気に包まれスパニッシュ・ギターも入るこの曲は、
ショーン君が生まれるまでの大変さを物語っているようにも感じます。
Tr12:Dear Yoko J
JL:うーん、何て言えばいいんだろう。
(歌いながら)♪もう何年もたったのに、まだ・・・・・・♪
この言葉がすべてを物語っているな。
この曲は最高さ。
ほら、あるだろう、「ディア・サンドラ」とか、
どっかの歌手が実在しなかったりする女のことを歌ってる歌が。
そんな曖昧な人のことじゃなくて、
これはたまたま、ぼくの妻の歌なんだ。
GB:うーん、何て言えばいいんだろう(笑)。
この曲は大好きですよ!
キレがあってホップするギターの音が楽しいです。
Tr13:Everyman Has A Woman Who Loves Him Y
GB:アルバムではヨーコさんが歌っていますが、これはジョンの死後に、
ジョンが歌ったバージョンのビデオクリップが作られ流されていたので、
僕には、ジョンのことが直結してしまい、聴くのがちょっとつらい曲です。
Tr14:Hard Times Are Over YwithJ
GB:最後はデュエットでしめるという流れが素晴らしく、
ジョンとヨーコのそれまでの夢というか理想の音楽が
ついに現実となった、そんなメッセージを感じます。
そして、この話の続きは、後に再び出てきます。
このアルバム、当時はGeffenからリリースされていて、
CD化時代の初期にはGeffenからCDが出ていましたが、
現在は権利関係が移ってCapitolから出ています。
そして現行盤は、デモなどのボーナストラックが3曲収録されています。
僭越ながら、個人的な逸話をひとつ。
このアルバムは、1982年度のグラミー賞において、
最優秀アルバム賞を受賞しました。
そのことを、中学生時代の僕は一般のニュースを見て知りました。
当時は、音楽の話題を一般のニュースで取り上げられることは、
それこそジョンの死やポール・マッカートニーの逮捕といった、
事件性があるもの以外はほとんどなかったので、
僕はそのニュースがとてもうれしかったのです。
そして、当時購読していた『FMファン』の読者のページに、
そのことを文章にまとめて投稿したところ、採用されて載りました。
雑誌を買ってページを開き、そこに自分の名前を見つけたのは
とてもうれしかったですが、レコードのギフト券をもらえたことが、
もっとうれしかったです(笑)。
いつも引用しているジョンのインタビューは、当然のことながら
このアルバムのプロモーションの一環として行われたもので、
このアルバムについてのジョンのコメントも紹介します。
(DOUBLE FANTASY「ふたつの幻想」とはどういう意味ですか?)
JL:花だよ、フリージアの一種だよ。
でも、ぼくたちにとっての意味は、
ふたりの人間が同時に同じイメージを描いた時、
それが秘訣だってことだね。
一緒になったふたりの人間がふたつの違ったイメージを描き、
その時点では強いほうが自分のほうの幻想を
実現できるということもあるけど、一方、
寄せ集め以外の何物もでもないものしか手に入らないこともある。
(新しいアルバムに盛られたメッセージを簡単に話してください)
JL:非常に簡単に言うと、
ふたりの人間の間のごく普通のことについてなんだよ。
歌詞は単刀直入でね。率直でストレートなんだ。
GB:「ダブル・ファンタジー」は、フリージアの品種だったのですね。
ネットで調べたところ、ジョンが見たのは黄色い八重咲きの品種で
しかし今はその品種はほとんど栽培されなくなっているらしく、
世界中でこの花の品種を探している人がいることを知りました。
最後に、ジョン・レノン・ミュージアムに行ってみて、
そこが思いの外気持ちのよい空間であることを感じました。
「さいたま新都心」駅からデッキでつながっていて、
車の往来とは関係なくゆっくりと歩いてゆけるのがいいです。
入館しなくてもグッズが買えたり、ジョンの大きな写真が見られるのは
そこに行くだけでも楽しくなります。
しかも、弟の家がある入谷からだと、鶯谷駅から京浜東北線を使い、
ドアトゥドアで1時間かからないで行けるのは気持ちが楽です。
それまでは行かなかった人間なので偉そうなことは言えないですが、
なくなるというのは、やはり、残念ですね。
でも、最後に行けてよかったです。
閉館までにもう1回行けないかな、と、今は思い始めています。
写真も、ここで使った3枚と他1枚しか撮らなかったのが、
今となってはやはり、もう少し撮ればよかったなぁと。
最後は、ジョン・レノン・ミュージアムのジョンの写真を。
06

JLM、札幌に再開館しないかな(笑)。
2012年12月08日
Jealous Guy ジョン・レノン
01

今年も12月8日、ジョン・レノンの日がきました。
日本でいえば、もう三十三回忌、ということになるのか。
今日は、ジョン・レノンの曲の話をします。
Jealous Guy
John Lennon
IMAGINE (1971)
written by John Lennon
02

The Playboy Intervies with John Lennon & Yoko Ono
本題の前に、Masterさんから、1冊の洋書をいただきました。
ありがとうございます!
僕は、集英社から出ている翻訳本を持っていて、BLOGでも
今までにそこから多くを引用して記事を書いてきましたが、
原書には、翻訳本では触れられていない曲がたくさんあります。
僕は、もう31年間、翻訳本で触れられているのものですべてだと
思い込んで生きてきたので、他にもあったということに驚くと同時に、
ちょっとだけ、集英社に騙され続けていたのか、と思ったり。
Jealous Guyも、翻訳本には載っていません。
というわけで早速、いただいた洋書を役立たせていただき、
Jealous Guyについてのジョンのコメントを紹介します。
なお、日本語訳は引用者が行っています。
JL:ぼくの曲、メロディはインドで書いた。
歌詞は自明のものだね。
ぼくはとても嫉妬深く、所有欲が大きい人間だった。
不安だらけの男だった。
自分の女性を小さな箱の中に入れ、閉じ込めておき、
相手をしてほしい時だけ箱から出したい、そんな奴だ。
彼女は外界とコミュニケーションをとることは許されていない。
ぼく以外とは。
なぜなら、そうすることでぼくが不安になるからだ。
Jealous Guyはそもそもインドで、つまり1968年に作られており、
世の中に出るまで3年ほどがかかっているのですね。
歌詞は後から書かれたものということですが、未完成のテイクを
LET IT BE...NAKEDのボーナスディスクに収められた、
1969年のリハーサルの模様の中で聴くことができます。
CDの6'31"辺りから、ポールの言葉に続いてフェイドインして始まり、
40秒かそこらで、なんとなく他の曲に移って終わるものですが、
そこではBメロが歌われていて、歌詞はこうなっています。
"I'm just a child of nature,
I don't need much to set me free
I'm just a child of narure..."
最初は、自由を謳歌する、むしろ開放する曲だったのですね。
ジョンがインドで作った曲といえば僕は、
Dear Prudence(記事こちら)を真っ先に思い浮かべますが、
それは閉じこもってしまったひとりの女性を開放しようとする曲。
一方こちらは、最初は同じように開放する曲だったのが、
後にヨーコへの思いに重ね合わせて歌詞が書き換えられたものが、
逆に女性を閉じ込めてしまう曲になったのは、皮肉というか。
この2曲は、ジョンの心の裏表を表した対の曲なのかもしれない。
しかしいずれも、ジョンの優しさがにじみ出ている曲ではありますね。
ところで、ビートルズ時代にリハーサルまでしていたこの曲を、
結果としてビートルズ時代には録音せずお蔵入りにしたのは、
ポールがMother Nature's Sonを作曲して歌ったことにより、
Child Of Natureでは二番煎じと思われるのが嫌だったのかな、
と邪推もしてしまいます(笑)。
03 2012年12月8日最初の1枚、今朝の空

この曲は今では、ジョン・レノンの曲の人気投票をすると
常にTop10入りは固いというくらい人気がある曲となりましたが、
僕がビートルズを聴き始めた頃はまだ、アルバムの中の1曲で、
僕が初めて買ったジョンのLPであり、ジョンの生前に出た唯一の
ベスト盤でもあるSHAVED FISHには収められていません。
しかし、ジョンの死後に当時のレーベルを超えて編集された
ベスト盤THE JOHN LENNON COLLECTIONには収録され、
僕が初めて聴いたのはそのLPでした。
また、ジョン自身がナレーションを務める伝記映画「イマジン」の
公開時にリリースされたシングルCDにも収録されました。
写真01にあるジョンの顔のイラストの白いCDがそれです。
なお、その写真のIMAGINEのLPは、EMI100周年を記念した
へヴィヴィニール盤ですが、まだ聴いたことがありません・・・
この曲は、あくまでも僕の感じで、僕が大学生になる頃までは、
アルバムの中の1曲で、好きな人は大好きだけど、多くの人が
ジョンの好きな曲の上位に挙げるわけでもなかった記憶があります。
それが変わったのは、やはりCDの時代になったからでしょうね。
ここから書くことはこの曲に限ったことではないですが、
考えられる要因を幾つか挙げてみます。
先ずは、CDという新しい媒体により、過去の音楽が、
魅力的な新しい商品として世の中に出ることにより、
それらを知らなかった若い世代が大量に、しかも気軽に
古い音楽に接する機会が得られるようになったこと。
CDは頭出しが容易で1曲1曲を聴きやすくなったのも、
曲に対しての思い入れができやすい部分でしょう。
ただし、アルバムを飛ばして聴く人も増えたかもしれないけれど。
CDで出直すことにより、リリース当時のことが切り離されて
曲だけで語られるようになったことも大きいですね。
大ヒット曲であろうがアルバムの中の曲であろうが、時間が経つと
忘れ去られるというか関係なくなり、余計な情報もなくなって、
流行りとは関係なく聴くことにより曲の良さだけで判断する。
そしてもうひとつ、ネットで思いを共有しやすくなったこと。
ネット社会になる前は、著名人ではない一般人が世の中に向けて
自分の思いを発信するのは結構大変でした。
出来ても、地域限定もしくは同好の志の仲間内くらいなもの。
それが今では、ネット環境さえあれば誰でも簡単に、
世界に向けて思いを発信することが可能な社会となっていて、
同じ思いの人を見つけてつながりやすくなっていますね。
逆に、情報が振れ過ぎて同じ思いの人もなかなかつながりにくい
ということはあるにしても、それは状況の問題ですから。
僕は、偉そうな言い方に聞こえるとは思いますが、
Jealous Guyという曲が、隠れた名曲から真の名曲へと
いわば「成長」してゆく過程を見てきたことになるんですよね。
僕はもちろんこの曲は大好きでしたが、自分自身のそうした
「体験」も重ね合わせ、特に思い入れが強い1曲にもなりました。
04 今朝の月

曲についてよくいわれることですが、不器用な男の生き様を、
これほどまでにうまく表した曲もそうはないでしょうね。
どちらかというと男性により支持が多い曲かもしれません。
昔、高倉健さんの「不器用ですから」というCMがありましたが、
それ以降、不器用であることにもなにがしかの美点がある、
というような意識が世の中に広まったような気もしています。
そうか、それもこの曲の人気には関係あるのかな。
歌詞はまったく持ってバカ正直で、レコードを通して聴いて、
アーティストの心の在り方がこれほどまでにリアルに伝わるのは、
やはりジョン・レノンならでは。
僕は特に次の部分の歌詞でそれを強く感じます。
"I was swallowing my pain"
「僕は苦痛をのみ込もうとしていた」
苦痛を飲み込んでも、その場は凌げるかもしれないけれど、
体の中に残ってしまいますよね。
苦痛を吐き出すことはしかし、別の大変な苦痛を伴うことにもなり、
その時のジョンにはそれができなかったのかもしれない。
そこまでする覚悟がない、そんなことするくらいだったら、
今だけ凌げればそれでいい。
常に物事を深く考えようとするジョンとしては刹那的というか、
いずれにせよ、苦悶の時代を象徴する曲でもありますね。
録音には多数の著名ミュージシャンが参加。
ピアノは英国の一流セッションマンのニッキー・ホプキンス、
ギターにバッドフィンガーのトム・エヴァンズ、
ヴァイブラフォンにイエスのアラン・ホワイト、
ドラムスには僕のCD10枚に1枚はいるであろうジム・ケルトナー、
そしてベースは朋友クラウス・フォアマン。
"I didn't mean to hurt you"の後に入るベースラインがいいですね。
歌メロは最高によくてよく口ずさみ、歌いますが、
歌手ではない僕でも気持ちが入りやすい曲だと感じます。
まあ、悪酔い、自己陶酔ですけどね(笑)。
歌メロで注目はBメロ、不器用さを表しているかのように、
音が落ち着かない感じがするところですね。
特に、"I'm sorry that I'll make you cry"の部分の後半、
音が不安定にふっと跳ね上がる、こんな旋律ありかって、
僕は初めて聴いた時に思いました。
そういう点でもきわめて個性的な曲といえるでしょうね。
さて後半は、この曲の僕が好きなカヴァーを4曲紹介します。
05

Jealous Guy
Donny Hathaway
LIVE (1972)
ダニー・ハサウェイ、ライヴの名盤中の名盤から。
ホンキートンク調の素っ頓狂ともいえる高い音のピアノで始まり、
ダニーは、軽く、しかし言葉を選ぶようにしっかりと歌う。
2番以降で歌メロを崩すと、思いのほか本格的なソウルに。
まあ、ソウルは曲は関係ないですからね、あくまでも歌い手の心。
3分ほどであっさりと歌うのですが、ジョンのオリジナルが出てから
すぐに自分のものにしているところに、ダニーの思いを感じます。
音楽を通して人間としての理想を求めてゆきたいという思い。
06

Jealous Guy
(Rod Stewart &) Faces
COAST TO COAST : OVERTURE AND BEGINNERS (1974)
ロッド・スチュワートもライヴ盤で歌っています。
当然のことながら、これもまたロッド自身のものにしていますね。
特に2番の歌い出し"I was feeling insecure"という部分の
エモーショナルに歌い上げるロッドにはぞくぞくっときてしまう。
フェイシズというバンドで歌うことにより、歌手も含めて、
不器用な男の塊のようなパワーを感じますね。
でも、ロッドはどちらかというと不器用じゃないかな(笑)。
今日久しぶりにこのCDを聴いてとてもよかった、暫く聴くかな。
ところで、このアルバムはちょっとしたいわくつきなのです。
ロッド・スチュワートは当時はフェイシズのメンバーでしたが、
ソロ名義で出したMaggie MayがNo.1ヒットとなり人気爆発、
バンドとソロで並行して活動するようになりました。
ロッドは当時ソロアーティストとしてはMercuryと契約、一方
フェイシズはWarner Brothersとの契約で、このアルバムを出す際、
アメリカではロッドのMercuryが、それ以外はフェイシズのWarnerが
レコードを出すというかたちになりました。
しかし結局ロッドはその後でWarnerと契約します。
そんな経緯が今でも尾を引いているかどうかは分からないですが、
ロッドやフェイシズの他のアルバムは今ではリマスター盤CDが
出ているけれど、これだけCDの時代の最初に一度出たきり。
今では中古市場で新品以上の値段がついています。
いい加減、リマスター盤が出てくれないかな。
でも、音質があまりよくなくて、リマスター盤が出ていないのは、
過去の経緯とは関係なく、単にそのせいかもしれないですが。
07

Jealous Guy
Roxy Music (1981)
ロキシー・ミュージックのこの曲は、一昨年に一度、
「ジョン・レノンを想う曲」の記事(こちら)で取り上げました。
今回は、その部分をもう一度掲載させていただきます。
ロキシー・ミュージックとジョン・レノン。
僕は最初にその話を聞いて、変わった組み合わせだなと思いました。
でも、ブライアン・フェリーがカバーアルバムを出していることを知り、
彼の音楽の趣向の広さを知った今はもう納得しています。
この曲は、ジョンの追悼のために録音してシングル化され、
話題が話題を呼んで英国でNo.1になったそうです。
音楽は、演奏も歌い方もロキシーそのものなのですが、この曲は、
素朴だからこそ、ロキシーの色にもうまく染まっています。
この曲、今ではすっかりジョン・レノンの名曲として親しまれていますが、
当時はまだアルバムの中の1曲に過ぎなかったという渋い選曲が、
彼らのセンスのよさと音楽への愛情を感じずにはいられません。
寂しいんだけど、悲しいんだけど、虚しいんだけど、
でも立ち上がろうよというメッセージを感じる好演奏ですね。
08

Jealous Guy
Youssou N'Dour
MAKE SOME NOISE
THE AMNESTY INTERNATIONAL CAMPAIGN TO
SAVE DARFUR (2007)
最後はセネガルの星、ユッスー・ンドゥール。
西スーダンのダルフール紛争により人権を抑圧されている人々の
窮状を訴えようというアムネスティのキャンペーンの一環として、
豪華アーティストが大挙してジョンの曲をカヴァーした2枚組CDから。
ユッスー・ンドゥールはいわばアフリカ大陸を代表して参加している
わけですが、そんな彼が選んだのがこの曲。
注目すべきは、Aメロの部分を英語ではなく、何語か分からない、
おそらくアフリカの、本人もしくはスーダンの言語で歌っていること。
紛争のキャンペーンにしては明るく楽観的な響きを感じ取れますが、
それは、ジョンのような考えをみんなが持てば紛争はなくなる、
ジョンは敢えてこの歌では醜い姿をさらけ出しているだけだ、
ジョンでもそうなんだからみんな大丈夫、という意味かもしれない。
ユッスー・ンドゥールは少しずつ聴いて行っている人ですが、
歌にメッセージを込めて普通に聴かせるのが上手い人ですね。
だから、ジョンとつながってゆくのだと思う。
09 Imagine...何を想像する・・・

いかがでしたか。
書くまでは、今回はそれほど長くならないかなと思っていたのですが、
いざ始めると、やっぱり普通に長くなりました・・・(笑)・・・
08のCDは他にも大好きなアーティスト、素晴らしいカヴァーが
まだまだあって、その話もしたかったのですが、もはや長すぎ。
来年以降にまた話ができれば、と思います。
ところで最後に、この曲自体ではなく、この曲を通して思ったこと。
口笛って不思議ですよね。
Jealous Guyは口笛が印象的なロックの楽曲のひとつですよね。
僕も、この曲を聴くと大抵は口笛を一緒に吹きます。
もっとも夜は、蛇が出てくるのでやらないですが(笑)。
それはともかく、今日も一緒に吹いていたけど、口笛っていったい、
どのようなメカニズムで音程を決めて出すことができるんだろう、と、
自分で吹きながらとっても不思議に思いました。
まあしかし、それをいうなら、声だってそうですけどね、
人間の体って、自分のものでありながら不思議なことも多いですね。
ちなみに僕が口笛を吹けるようになったのは、やはりというか
ビートルズを聴くようになってからで、小学生時代はできなかった。
ただもちろんうまくなはくて、ビリー・ジョエルのThe Strangerの
いちばん高い音は出せません。
そこが来たら、その音だけ出さないでごまかします(笑)。
僕はもうジョンよりも長く生きていることになりますが、
こうなったらまだまだ生きてゆきたいと思いますね。
毎年言いますが、
僕は別に今日だからジョンのことを考えているわけではなく、
毎日、日常生活のひとつとして普通に考えています。
では、また
10


今年も12月8日、ジョン・レノンの日がきました。
日本でいえば、もう三十三回忌、ということになるのか。
今日は、ジョン・レノンの曲の話をします。
Jealous Guy
John Lennon
IMAGINE (1971)
written by John Lennon
02

The Playboy Intervies with John Lennon & Yoko Ono
本題の前に、Masterさんから、1冊の洋書をいただきました。
ありがとうございます!
僕は、集英社から出ている翻訳本を持っていて、BLOGでも
今までにそこから多くを引用して記事を書いてきましたが、
原書には、翻訳本では触れられていない曲がたくさんあります。
僕は、もう31年間、翻訳本で触れられているのものですべてだと
思い込んで生きてきたので、他にもあったということに驚くと同時に、
ちょっとだけ、集英社に騙され続けていたのか、と思ったり。
Jealous Guyも、翻訳本には載っていません。
というわけで早速、いただいた洋書を役立たせていただき、
Jealous Guyについてのジョンのコメントを紹介します。
なお、日本語訳は引用者が行っています。
JL:ぼくの曲、メロディはインドで書いた。
歌詞は自明のものだね。
ぼくはとても嫉妬深く、所有欲が大きい人間だった。
不安だらけの男だった。
自分の女性を小さな箱の中に入れ、閉じ込めておき、
相手をしてほしい時だけ箱から出したい、そんな奴だ。
彼女は外界とコミュニケーションをとることは許されていない。
ぼく以外とは。
なぜなら、そうすることでぼくが不安になるからだ。
Jealous Guyはそもそもインドで、つまり1968年に作られており、
世の中に出るまで3年ほどがかかっているのですね。
歌詞は後から書かれたものということですが、未完成のテイクを
LET IT BE...NAKEDのボーナスディスクに収められた、
1969年のリハーサルの模様の中で聴くことができます。
CDの6'31"辺りから、ポールの言葉に続いてフェイドインして始まり、
40秒かそこらで、なんとなく他の曲に移って終わるものですが、
そこではBメロが歌われていて、歌詞はこうなっています。
"I'm just a child of nature,
I don't need much to set me free
I'm just a child of narure..."
最初は、自由を謳歌する、むしろ開放する曲だったのですね。
ジョンがインドで作った曲といえば僕は、
Dear Prudence(記事こちら)を真っ先に思い浮かべますが、
それは閉じこもってしまったひとりの女性を開放しようとする曲。
一方こちらは、最初は同じように開放する曲だったのが、
後にヨーコへの思いに重ね合わせて歌詞が書き換えられたものが、
逆に女性を閉じ込めてしまう曲になったのは、皮肉というか。
この2曲は、ジョンの心の裏表を表した対の曲なのかもしれない。
しかしいずれも、ジョンの優しさがにじみ出ている曲ではありますね。
ところで、ビートルズ時代にリハーサルまでしていたこの曲を、
結果としてビートルズ時代には録音せずお蔵入りにしたのは、
ポールがMother Nature's Sonを作曲して歌ったことにより、
Child Of Natureでは二番煎じと思われるのが嫌だったのかな、
と邪推もしてしまいます(笑)。
03 2012年12月8日最初の1枚、今朝の空

この曲は今では、ジョン・レノンの曲の人気投票をすると
常にTop10入りは固いというくらい人気がある曲となりましたが、
僕がビートルズを聴き始めた頃はまだ、アルバムの中の1曲で、
僕が初めて買ったジョンのLPであり、ジョンの生前に出た唯一の
ベスト盤でもあるSHAVED FISHには収められていません。
しかし、ジョンの死後に当時のレーベルを超えて編集された
ベスト盤THE JOHN LENNON COLLECTIONには収録され、
僕が初めて聴いたのはそのLPでした。
また、ジョン自身がナレーションを務める伝記映画「イマジン」の
公開時にリリースされたシングルCDにも収録されました。
写真01にあるジョンの顔のイラストの白いCDがそれです。
なお、その写真のIMAGINEのLPは、EMI100周年を記念した
へヴィヴィニール盤ですが、まだ聴いたことがありません・・・
この曲は、あくまでも僕の感じで、僕が大学生になる頃までは、
アルバムの中の1曲で、好きな人は大好きだけど、多くの人が
ジョンの好きな曲の上位に挙げるわけでもなかった記憶があります。
それが変わったのは、やはりCDの時代になったからでしょうね。
ここから書くことはこの曲に限ったことではないですが、
考えられる要因を幾つか挙げてみます。
先ずは、CDという新しい媒体により、過去の音楽が、
魅力的な新しい商品として世の中に出ることにより、
それらを知らなかった若い世代が大量に、しかも気軽に
古い音楽に接する機会が得られるようになったこと。
CDは頭出しが容易で1曲1曲を聴きやすくなったのも、
曲に対しての思い入れができやすい部分でしょう。
ただし、アルバムを飛ばして聴く人も増えたかもしれないけれど。
CDで出直すことにより、リリース当時のことが切り離されて
曲だけで語られるようになったことも大きいですね。
大ヒット曲であろうがアルバムの中の曲であろうが、時間が経つと
忘れ去られるというか関係なくなり、余計な情報もなくなって、
流行りとは関係なく聴くことにより曲の良さだけで判断する。
そしてもうひとつ、ネットで思いを共有しやすくなったこと。
ネット社会になる前は、著名人ではない一般人が世の中に向けて
自分の思いを発信するのは結構大変でした。
出来ても、地域限定もしくは同好の志の仲間内くらいなもの。
それが今では、ネット環境さえあれば誰でも簡単に、
世界に向けて思いを発信することが可能な社会となっていて、
同じ思いの人を見つけてつながりやすくなっていますね。
逆に、情報が振れ過ぎて同じ思いの人もなかなかつながりにくい
ということはあるにしても、それは状況の問題ですから。
僕は、偉そうな言い方に聞こえるとは思いますが、
Jealous Guyという曲が、隠れた名曲から真の名曲へと
いわば「成長」してゆく過程を見てきたことになるんですよね。
僕はもちろんこの曲は大好きでしたが、自分自身のそうした
「体験」も重ね合わせ、特に思い入れが強い1曲にもなりました。
04 今朝の月

曲についてよくいわれることですが、不器用な男の生き様を、
これほどまでにうまく表した曲もそうはないでしょうね。
どちらかというと男性により支持が多い曲かもしれません。
昔、高倉健さんの「不器用ですから」というCMがありましたが、
それ以降、不器用であることにもなにがしかの美点がある、
というような意識が世の中に広まったような気もしています。
そうか、それもこの曲の人気には関係あるのかな。
歌詞はまったく持ってバカ正直で、レコードを通して聴いて、
アーティストの心の在り方がこれほどまでにリアルに伝わるのは、
やはりジョン・レノンならでは。
僕は特に次の部分の歌詞でそれを強く感じます。
"I was swallowing my pain"
「僕は苦痛をのみ込もうとしていた」
苦痛を飲み込んでも、その場は凌げるかもしれないけれど、
体の中に残ってしまいますよね。
苦痛を吐き出すことはしかし、別の大変な苦痛を伴うことにもなり、
その時のジョンにはそれができなかったのかもしれない。
そこまでする覚悟がない、そんなことするくらいだったら、
今だけ凌げればそれでいい。
常に物事を深く考えようとするジョンとしては刹那的というか、
いずれにせよ、苦悶の時代を象徴する曲でもありますね。
録音には多数の著名ミュージシャンが参加。
ピアノは英国の一流セッションマンのニッキー・ホプキンス、
ギターにバッドフィンガーのトム・エヴァンズ、
ヴァイブラフォンにイエスのアラン・ホワイト、
ドラムスには僕のCD10枚に1枚はいるであろうジム・ケルトナー、
そしてベースは朋友クラウス・フォアマン。
"I didn't mean to hurt you"の後に入るベースラインがいいですね。
歌メロは最高によくてよく口ずさみ、歌いますが、
歌手ではない僕でも気持ちが入りやすい曲だと感じます。
まあ、悪酔い、自己陶酔ですけどね(笑)。
歌メロで注目はBメロ、不器用さを表しているかのように、
音が落ち着かない感じがするところですね。
特に、"I'm sorry that I'll make you cry"の部分の後半、
音が不安定にふっと跳ね上がる、こんな旋律ありかって、
僕は初めて聴いた時に思いました。
そういう点でもきわめて個性的な曲といえるでしょうね。
さて後半は、この曲の僕が好きなカヴァーを4曲紹介します。
05

Jealous Guy
Donny Hathaway
LIVE (1972)
ダニー・ハサウェイ、ライヴの名盤中の名盤から。
ホンキートンク調の素っ頓狂ともいえる高い音のピアノで始まり、
ダニーは、軽く、しかし言葉を選ぶようにしっかりと歌う。
2番以降で歌メロを崩すと、思いのほか本格的なソウルに。
まあ、ソウルは曲は関係ないですからね、あくまでも歌い手の心。
3分ほどであっさりと歌うのですが、ジョンのオリジナルが出てから
すぐに自分のものにしているところに、ダニーの思いを感じます。
音楽を通して人間としての理想を求めてゆきたいという思い。
06

Jealous Guy
(Rod Stewart &) Faces
COAST TO COAST : OVERTURE AND BEGINNERS (1974)
ロッド・スチュワートもライヴ盤で歌っています。
当然のことながら、これもまたロッド自身のものにしていますね。
特に2番の歌い出し"I was feeling insecure"という部分の
エモーショナルに歌い上げるロッドにはぞくぞくっときてしまう。
フェイシズというバンドで歌うことにより、歌手も含めて、
不器用な男の塊のようなパワーを感じますね。
でも、ロッドはどちらかというと不器用じゃないかな(笑)。
今日久しぶりにこのCDを聴いてとてもよかった、暫く聴くかな。
ところで、このアルバムはちょっとしたいわくつきなのです。
ロッド・スチュワートは当時はフェイシズのメンバーでしたが、
ソロ名義で出したMaggie MayがNo.1ヒットとなり人気爆発、
バンドとソロで並行して活動するようになりました。
ロッドは当時ソロアーティストとしてはMercuryと契約、一方
フェイシズはWarner Brothersとの契約で、このアルバムを出す際、
アメリカではロッドのMercuryが、それ以外はフェイシズのWarnerが
レコードを出すというかたちになりました。
しかし結局ロッドはその後でWarnerと契約します。
そんな経緯が今でも尾を引いているかどうかは分からないですが、
ロッドやフェイシズの他のアルバムは今ではリマスター盤CDが
出ているけれど、これだけCDの時代の最初に一度出たきり。
今では中古市場で新品以上の値段がついています。
いい加減、リマスター盤が出てくれないかな。
でも、音質があまりよくなくて、リマスター盤が出ていないのは、
過去の経緯とは関係なく、単にそのせいかもしれないですが。
07

Jealous Guy
Roxy Music (1981)
ロキシー・ミュージックのこの曲は、一昨年に一度、
「ジョン・レノンを想う曲」の記事(こちら)で取り上げました。
今回は、その部分をもう一度掲載させていただきます。
ロキシー・ミュージックとジョン・レノン。
僕は最初にその話を聞いて、変わった組み合わせだなと思いました。
でも、ブライアン・フェリーがカバーアルバムを出していることを知り、
彼の音楽の趣向の広さを知った今はもう納得しています。
この曲は、ジョンの追悼のために録音してシングル化され、
話題が話題を呼んで英国でNo.1になったそうです。
音楽は、演奏も歌い方もロキシーそのものなのですが、この曲は、
素朴だからこそ、ロキシーの色にもうまく染まっています。
この曲、今ではすっかりジョン・レノンの名曲として親しまれていますが、
当時はまだアルバムの中の1曲に過ぎなかったという渋い選曲が、
彼らのセンスのよさと音楽への愛情を感じずにはいられません。
寂しいんだけど、悲しいんだけど、虚しいんだけど、
でも立ち上がろうよというメッセージを感じる好演奏ですね。
08

Jealous Guy
Youssou N'Dour
MAKE SOME NOISE
THE AMNESTY INTERNATIONAL CAMPAIGN TO
SAVE DARFUR (2007)
最後はセネガルの星、ユッスー・ンドゥール。
西スーダンのダルフール紛争により人権を抑圧されている人々の
窮状を訴えようというアムネスティのキャンペーンの一環として、
豪華アーティストが大挙してジョンの曲をカヴァーした2枚組CDから。
ユッスー・ンドゥールはいわばアフリカ大陸を代表して参加している
わけですが、そんな彼が選んだのがこの曲。
注目すべきは、Aメロの部分を英語ではなく、何語か分からない、
おそらくアフリカの、本人もしくはスーダンの言語で歌っていること。
紛争のキャンペーンにしては明るく楽観的な響きを感じ取れますが、
それは、ジョンのような考えをみんなが持てば紛争はなくなる、
ジョンは敢えてこの歌では醜い姿をさらけ出しているだけだ、
ジョンでもそうなんだからみんな大丈夫、という意味かもしれない。
ユッスー・ンドゥールは少しずつ聴いて行っている人ですが、
歌にメッセージを込めて普通に聴かせるのが上手い人ですね。
だから、ジョンとつながってゆくのだと思う。
09 Imagine...何を想像する・・・

いかがでしたか。
書くまでは、今回はそれほど長くならないかなと思っていたのですが、
いざ始めると、やっぱり普通に長くなりました・・・(笑)・・・
08のCDは他にも大好きなアーティスト、素晴らしいカヴァーが
まだまだあって、その話もしたかったのですが、もはや長すぎ。
来年以降にまた話ができれば、と思います。
ところで最後に、この曲自体ではなく、この曲を通して思ったこと。
口笛って不思議ですよね。
Jealous Guyは口笛が印象的なロックの楽曲のひとつですよね。
僕も、この曲を聴くと大抵は口笛を一緒に吹きます。
もっとも夜は、蛇が出てくるのでやらないですが(笑)。
それはともかく、今日も一緒に吹いていたけど、口笛っていったい、
どのようなメカニズムで音程を決めて出すことができるんだろう、と、
自分で吹きながらとっても不思議に思いました。
まあしかし、それをいうなら、声だってそうですけどね、
人間の体って、自分のものでありながら不思議なことも多いですね。
ちなみに僕が口笛を吹けるようになったのは、やはりというか
ビートルズを聴くようになってからで、小学生時代はできなかった。
ただもちろんうまくなはくて、ビリー・ジョエルのThe Strangerの
いちばん高い音は出せません。
そこが来たら、その音だけ出さないでごまかします(笑)。
僕はもうジョンよりも長く生きていることになりますが、
こうなったらまだまだ生きてゆきたいと思いますね。
毎年言いますが、
僕は別に今日だからジョンのことを考えているわけではなく、
毎日、日常生活のひとつとして普通に考えています。
では、また
10

2011年12月08日
Happy Xmas (War Is Over)
01

今日は31年目、32回目の12月8日。
毎年僕はこの日はジョン・レノンの記事を上げていますが、
今年は少し迷って、でもやはり続けることにも意味はあるのだし
ジョンの記事を上げることにしました。
この日は幾つになっても特別な日だと自分でも分かりました。
迷ったくらいだから何を書くか考えていなかったのですが、
そういえばこの話題はまだだったと気づきました。
Happy Xmas (War Is Over)
ジョン・レノンの日は12月であるため、この曲は31年前から
また別の意味が加わるようになった感があります。
僕はその前は知らないけど、もしかしてその年まで、この曲は
12月になってもそれほど巷で流れていなかったのかもしれません。
分からない、あくまでも想像ですが。
この曲について、いつもの
「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」に
ジョン自身の言葉があるのでそれを書き出します。
なお改行は引用者が施しています。
JL:ヨーコと僕がこれを書いた。
それ以上何も言うことはないね。
メッセージはいつも同じだ。
ぼくらにもボタンを押す人間と同じように責任があるってことさ。
何者かがぼくらに力を与えたり、奪ったりするのだとか、
何者かがぼくらを戦争に行かせたり、行かせなかったりするとか、
天の神は別個の存在だとか、国家や宗教でぼくらはみんな
区分けされているとかいう考え方、そんなのは、
みんなゴミと同じさ。
誰かに何かをさせられているから、自分の意志が通せないと
考えているかぎり、世の中を動かせっこないさ。
この曲はほんとうに歌として素晴らしい。
特に僕は、コーラスの部分
War is over, if you want it
War is over now
たった16個の音が並んでいるだけのその部分が、
聴いていて、口ずさんでいて、とっても感動します。
この部分は全体の流れとは別に存在する感じがするし、
声が高いから、ヨーコさんが作ったのかもしれないですね。
今はクリスマスアルバムの季節ですが、
この曲も多くのアーティストにカバーされています。
今回は、オリジナルを含めて10のヴァージョンを集めてみました。
いつものようにYou-Tube画像などはありませんけど。
なお、この際だから話すと、僕がYou-Tube画像を貼らないのは、
言葉で音楽の楽しさを伝えられたら、と思うからです。
時代遅れの上に僕の能力では力不足であるのは分かっていますが、
でも、これからもそうしてゆきます。
02

★1曲目
John & Yoko The Plastic Ono Band
with THe Harlem Community Choir
オリジナルヴァージョンです。
写真は、2003年に30周年を記念してリリースされたシングルCDで、
名義が上記のようになっているのでそのまま書き出しました。
この曲がいいのはやっぱり子どものコーラスですからね。
もはや誰もが知っているはずの曲。
★2曲目
Medley : a.Happy Xmas (War Is Over)
b.Give Peace A Chance (Reprise)
John Lennon
SHAVED FISH (1975)
これはジョンが引退し主夫生活に入る際にリリースされた
ベスト盤に収録されているヴァージョン。
Happy...の演奏が終わり切る前に、ジョンの唯一のコンサートとなった
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」のエンディングで演奏された
Give Peace A Chanceをリプライズとして重ねメドレーとしたもので、
Happy...自体は同じテイクが用いられています。
リプライズにはスティーヴィー・ワンダーも参加しています。
このアルバムは編集が最高にいいベスト盤ですが、
リマスター化はされない模様なのが残念でなりません。
03
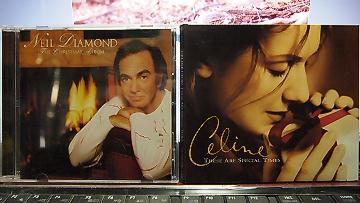
★3曲目
Neil Diamond
THE CHRISTMAS ALBUM (1992)
ニール・ダイアモンドはとにかく熱いそして厚いですね。
いい意味であざとく歌うとこの人の右に出る者はなし。
まあそれが苦手な人は苦手なのでしょうけど、
大仰に朗々と歌い上げていますが違和感はありません。
僕は結構好きです、それにしても厚い(笑)。
★4曲目
Celine Dion
THESE ARE THE SPECIAL TIMES (1998)
セリーヌ・ディオンのこれは3拍子ではなく4拍子になっていて、
新しい感覚の、しかし落ち着いた雰囲気に仕上がっています。
熱唱型なのはNDと同じかな、そういえばこの2人はなんとなく
音楽業界の中での存在感が似ているような気がしてきました。
このクリスマスアルバムはかなりいいですよ。
04

★5曲目
Carreras, Domingo, Pavarotti
THE THREE TENORS CHRISTMAS (2000)
ホセ・カレーラス、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァロッティ、
「3大テノール」が1999年に行ったクリスマスコンサートのライヴ盤から。
曲目を見るとクラシックからトラッドまでクリスマスソングを
取り上げていますがポップフィールドからはこれだけのようです。
そういえばパヴァロッティも鬼籍入りしましたね。
★6曲目
Carly Simon
CHRISTMAS IS ALMOST HERE (2002)
カーリー・サイモンのこれは彼女らしくフォークタッチで
この中ではいちばん普通な感じの響きです。
それにしても口が大き・・・あ、いや、失礼・・・
でも僕の知り合いで僕より年上の女性が、若い頃に彼女を見て、
向こうの美人とは口が大きいものなのだと思ったと話していました。
05

★7曲目
Sarah McLachlan
WINTERSONG (2006)
サラ・マクラクランのこの曲は気持ち入りまくりで、
気持ちの熱さはこの中でもいちばんだと思います。
この曲は、ここで紹介したほかのアーティストのアルバムにおいては
ほとんどが後ろから何番目か最後というくらい後ろに入っているのが
サラだけ前半のそれも1曲目というのが興味深いです。
気持ちは熱くても、サラにはまだ序章というところかな。
なお、僕がいちばん好きなクリスマスアルバムはこれなのです。
その後に「本命」シェリル・クロウも出たのですが、やっぱり。
あまりにも僕の気持ちが入っているので、今は逆に
このアルバムは気軽に聴けなくなってしまっています。
それってでも、サラにしてはうれしくないのかも(笑)。
記事にするのに久しぶりに聴いたら・・・
★8曲目
Sarah Brightman
A WINTER SYMPONY (2007)
サラ続きのサラ・ブライトマン。
彼女の声は人間の声じゃない、天使、妖精ですね。
アレンジも何も関係ない、とにかく彼女の声に圧倒されますが、
彼女の存在自体がこの世のものでもないという感じすらします。
ところで余談、サラのこのアルバムのこの次の曲は
ビー・ジーズのFirst Of Mayで、歌詞の中に
"When I was small, and Christmas Trees were tall"
とあるのですが、この曲がクリスマスソングとして歌われるのを
僕は今回初めて聴きました。
06

★9曲目
Tommy Shaw,Steve Lukather,Marco Mendoza,Kenny Aronoff
WE WISH YOU A METAL XMAS
AND A HEADBANGING NEW YEAR (2008)
最後はメタル系アーティストが集まったクリスマスアルバムから、
トミー・ショー、スティーヴ・ルカサー、マルコ・メンドーサと
ケニー・アロノフの4人の演奏を。
トミー・ショーやルカサーもメタルなのか、と細かいことは抜きにして、
メタルっぽくなっただけで根幹は意外と忠実なカバーです。
ただオリジナルにはない間奏が設けられ、待ってましたとばかりに
スティーヴ・ルカサーのギターソロが入るのもメタルらしいところ。
なお、写真06はCDが1枚しかなく片方はハウの顔ですが(笑)、
これは、REOスピードワゴンの昨年出たクリスマスアルバムでも
歌われていることを昨日知り、まだそれは買っていおらず、
注文して届いて聴いたら写真を差し替えて文章も追記するつもりで
そのようにしたものです。
さて、ここでもう1曲触れておきたい曲が。
07

Stewball
Peter, Paul & Mary
IN THE WIND (1963)
ピーター・ポール&マリーのこの曲を僕が聴いていたところ、
弟が「この曲はHappy Xmasに似てないか」と言い出しました。
似てる、確かに。
僕と弟はそれは大発見だと思っていたのですが、
Wikipediaを見ると既にそうであると記されていてがっかり(笑)。
盗作という話ではないので、これはいい影響ということでしょうね。
機会があればぜひPPMのこの曲も聴いてみてください。
というわけで、Happy Xmas (War Is Over)
うちには9曲、近々1曲追加予定(笑)。
それにしてもこの曲はどんなスタイルでも映えますね。
男性女性も関係なく歌われているのはジョンもうれしいでしょうね。
もう少し、他の話題を続けます。
08

「絵本ジョン・レノン・センス」 ちくま文庫
ジョン・レノン(著) 片岡義男・加藤直(訳)
ジョンが初めて書いた本IN HIS OWN WRITEが
今年の8月にちくま文庫版として新たに出ていました。
僕は知らなくて今週になってタワレコで買いました。
やっぱりちくま文庫はいい本が多いなあ。
09

日量パンのホワイトリース
今日、イオンで、クリスマスリースみたいな
こんなパンを見つけて買いました。
形がいい上においしそう!
でも一瞬、ホワイト「ソ」-スに見えてしまった・・・(笑)・・・
10

2011年12月8日のA公園の風景
なんだかジョン・レノンらしい風景だと思いながら撮りました。

今日は31年目、32回目の12月8日。
毎年僕はこの日はジョン・レノンの記事を上げていますが、
今年は少し迷って、でもやはり続けることにも意味はあるのだし
ジョンの記事を上げることにしました。
この日は幾つになっても特別な日だと自分でも分かりました。
迷ったくらいだから何を書くか考えていなかったのですが、
そういえばこの話題はまだだったと気づきました。
Happy Xmas (War Is Over)
ジョン・レノンの日は12月であるため、この曲は31年前から
また別の意味が加わるようになった感があります。
僕はその前は知らないけど、もしかしてその年まで、この曲は
12月になってもそれほど巷で流れていなかったのかもしれません。
分からない、あくまでも想像ですが。
この曲について、いつもの
「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」に
ジョン自身の言葉があるのでそれを書き出します。
なお改行は引用者が施しています。
JL:ヨーコと僕がこれを書いた。
それ以上何も言うことはないね。
メッセージはいつも同じだ。
ぼくらにもボタンを押す人間と同じように責任があるってことさ。
何者かがぼくらに力を与えたり、奪ったりするのだとか、
何者かがぼくらを戦争に行かせたり、行かせなかったりするとか、
天の神は別個の存在だとか、国家や宗教でぼくらはみんな
区分けされているとかいう考え方、そんなのは、
みんなゴミと同じさ。
誰かに何かをさせられているから、自分の意志が通せないと
考えているかぎり、世の中を動かせっこないさ。
この曲はほんとうに歌として素晴らしい。
特に僕は、コーラスの部分
War is over, if you want it
War is over now
たった16個の音が並んでいるだけのその部分が、
聴いていて、口ずさんでいて、とっても感動します。
この部分は全体の流れとは別に存在する感じがするし、
声が高いから、ヨーコさんが作ったのかもしれないですね。
今はクリスマスアルバムの季節ですが、
この曲も多くのアーティストにカバーされています。
今回は、オリジナルを含めて10のヴァージョンを集めてみました。
いつものようにYou-Tube画像などはありませんけど。
なお、この際だから話すと、僕がYou-Tube画像を貼らないのは、
言葉で音楽の楽しさを伝えられたら、と思うからです。
時代遅れの上に僕の能力では力不足であるのは分かっていますが、
でも、これからもそうしてゆきます。
02

★1曲目
John & Yoko The Plastic Ono Band
with THe Harlem Community Choir
オリジナルヴァージョンです。
写真は、2003年に30周年を記念してリリースされたシングルCDで、
名義が上記のようになっているのでそのまま書き出しました。
この曲がいいのはやっぱり子どものコーラスですからね。
もはや誰もが知っているはずの曲。
★2曲目
Medley : a.Happy Xmas (War Is Over)
b.Give Peace A Chance (Reprise)
John Lennon
SHAVED FISH (1975)
これはジョンが引退し主夫生活に入る際にリリースされた
ベスト盤に収録されているヴァージョン。
Happy...の演奏が終わり切る前に、ジョンの唯一のコンサートとなった
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」のエンディングで演奏された
Give Peace A Chanceをリプライズとして重ねメドレーとしたもので、
Happy...自体は同じテイクが用いられています。
リプライズにはスティーヴィー・ワンダーも参加しています。
このアルバムは編集が最高にいいベスト盤ですが、
リマスター化はされない模様なのが残念でなりません。
03
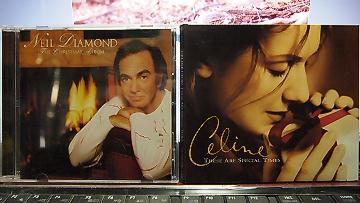
★3曲目
Neil Diamond
THE CHRISTMAS ALBUM (1992)
ニール・ダイアモンドはとにかく熱いそして厚いですね。
いい意味であざとく歌うとこの人の右に出る者はなし。
まあそれが苦手な人は苦手なのでしょうけど、
大仰に朗々と歌い上げていますが違和感はありません。
僕は結構好きです、それにしても厚い(笑)。
★4曲目
Celine Dion
THESE ARE THE SPECIAL TIMES (1998)
セリーヌ・ディオンのこれは3拍子ではなく4拍子になっていて、
新しい感覚の、しかし落ち着いた雰囲気に仕上がっています。
熱唱型なのはNDと同じかな、そういえばこの2人はなんとなく
音楽業界の中での存在感が似ているような気がしてきました。
このクリスマスアルバムはかなりいいですよ。
04

★5曲目
Carreras, Domingo, Pavarotti
THE THREE TENORS CHRISTMAS (2000)
ホセ・カレーラス、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァロッティ、
「3大テノール」が1999年に行ったクリスマスコンサートのライヴ盤から。
曲目を見るとクラシックからトラッドまでクリスマスソングを
取り上げていますがポップフィールドからはこれだけのようです。
そういえばパヴァロッティも鬼籍入りしましたね。
★6曲目
Carly Simon
CHRISTMAS IS ALMOST HERE (2002)
カーリー・サイモンのこれは彼女らしくフォークタッチで
この中ではいちばん普通な感じの響きです。
それにしても口が大き・・・あ、いや、失礼・・・
でも僕の知り合いで僕より年上の女性が、若い頃に彼女を見て、
向こうの美人とは口が大きいものなのだと思ったと話していました。
05

★7曲目
Sarah McLachlan
WINTERSONG (2006)
サラ・マクラクランのこの曲は気持ち入りまくりで、
気持ちの熱さはこの中でもいちばんだと思います。
この曲は、ここで紹介したほかのアーティストのアルバムにおいては
ほとんどが後ろから何番目か最後というくらい後ろに入っているのが
サラだけ前半のそれも1曲目というのが興味深いです。
気持ちは熱くても、サラにはまだ序章というところかな。
なお、僕がいちばん好きなクリスマスアルバムはこれなのです。
その後に「本命」シェリル・クロウも出たのですが、やっぱり。
あまりにも僕の気持ちが入っているので、今は逆に
このアルバムは気軽に聴けなくなってしまっています。
それってでも、サラにしてはうれしくないのかも(笑)。
記事にするのに久しぶりに聴いたら・・・
★8曲目
Sarah Brightman
A WINTER SYMPONY (2007)
サラ続きのサラ・ブライトマン。
彼女の声は人間の声じゃない、天使、妖精ですね。
アレンジも何も関係ない、とにかく彼女の声に圧倒されますが、
彼女の存在自体がこの世のものでもないという感じすらします。
ところで余談、サラのこのアルバムのこの次の曲は
ビー・ジーズのFirst Of Mayで、歌詞の中に
"When I was small, and Christmas Trees were tall"
とあるのですが、この曲がクリスマスソングとして歌われるのを
僕は今回初めて聴きました。
06

★9曲目
Tommy Shaw,Steve Lukather,Marco Mendoza,Kenny Aronoff
WE WISH YOU A METAL XMAS
AND A HEADBANGING NEW YEAR (2008)
最後はメタル系アーティストが集まったクリスマスアルバムから、
トミー・ショー、スティーヴ・ルカサー、マルコ・メンドーサと
ケニー・アロノフの4人の演奏を。
トミー・ショーやルカサーもメタルなのか、と細かいことは抜きにして、
メタルっぽくなっただけで根幹は意外と忠実なカバーです。
ただオリジナルにはない間奏が設けられ、待ってましたとばかりに
スティーヴ・ルカサーのギターソロが入るのもメタルらしいところ。
なお、写真06はCDが1枚しかなく片方はハウの顔ですが(笑)、
これは、REOスピードワゴンの昨年出たクリスマスアルバムでも
歌われていることを昨日知り、まだそれは買っていおらず、
注文して届いて聴いたら写真を差し替えて文章も追記するつもりで
そのようにしたものです。
さて、ここでもう1曲触れておきたい曲が。
07

Stewball
Peter, Paul & Mary
IN THE WIND (1963)
ピーター・ポール&マリーのこの曲を僕が聴いていたところ、
弟が「この曲はHappy Xmasに似てないか」と言い出しました。
似てる、確かに。
僕と弟はそれは大発見だと思っていたのですが、
Wikipediaを見ると既にそうであると記されていてがっかり(笑)。
盗作という話ではないので、これはいい影響ということでしょうね。
機会があればぜひPPMのこの曲も聴いてみてください。
というわけで、Happy Xmas (War Is Over)
うちには9曲、近々1曲追加予定(笑)。
それにしてもこの曲はどんなスタイルでも映えますね。
男性女性も関係なく歌われているのはジョンもうれしいでしょうね。
もう少し、他の話題を続けます。
08

「絵本ジョン・レノン・センス」 ちくま文庫
ジョン・レノン(著) 片岡義男・加藤直(訳)
ジョンが初めて書いた本IN HIS OWN WRITEが
今年の8月にちくま文庫版として新たに出ていました。
僕は知らなくて今週になってタワレコで買いました。
やっぱりちくま文庫はいい本が多いなあ。
09

日量パンのホワイトリース
今日、イオンで、クリスマスリースみたいな
こんなパンを見つけて買いました。
形がいい上においしそう!
でも一瞬、ホワイト「ソ」-スに見えてしまった・・・(笑)・・・
10

2011年12月8日のA公園の風景
なんだかジョン・レノンらしい風景だと思いながら撮りました。



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

























