2013年10月11日
BAND ON THE RUN ポール・マッカートニー
01

BAND ON THE RUN Paul McCartney & Wings (1973)
バンド・オン・ザ・ラン ポール・マッカートニー&ウィングス
ポール・マッカートニー&ウィングスの傑作アルバムが
リマスター盤として再発されました。
今回は、アルバム本編だけの通常盤、
ボーナス音源を集めたCDとDVDがついた特別盤、さらには、
それプラス特別音源CDがついた豪華盤の3種類が出ました。
これは、ポール・マッカートニーのカタログの所有権が、
UNIVERSAL傘下のHEAR MUSICへ移ったことに伴うもので、
今後は他のアルバムも次々と再発されることが予想されます。
最初にこれが出たのは、最高傑作と言われているからでしょうけれど、
その辺はファンとしては納得できます。
今日は、リマスター盤のリリースを記念して、
ついに、このアルバムの記事を上げます。
僕も、このアルバムは、僕のリアルタイムに出たものではない
ポールのアルバムではいちばん好きです。
リアルタイムを含めるとTUG OF WARがいちばんなのですが、
とにかくこのアルバムの完成度の高さは驚異的ですらあります。
そんな大好きなアルバムで、僕には重い存在であるから、
今まではなかなか記事にしようという気持ちになれませんでした。
しかし、いくらんなんでもこの機会を逃すとファンじゃないな、と、
ようやく重い腰と気持ちを上げた次第です。
しかしこのアルバムは、別のかたちで一度記事にしていました。
僕は、何を隠そう、このアルバムのコレクターでして、
LP、CD合わせて14枚持っている、その「自慢」記事でした。
ご興味があるかたはこちらの記事へどうぞ。
ちなみに、今回はひとまず豪華盤と特別盤を買ったので、
現時点でうちにあるこのアルバムは16枚となりました。
このアルバムを最初に買ったのは、中学3年の秋だったかな。
国内盤ピクチャーLPが売られていたのを、普段あまり行かなかった
札幌市内のレコード店で見つけ、少しして買いに行きました。
当時はもうビートルズ関係の本をよく読んでいたので、
このアルバムがポールの最高傑作であるとの予備知識はありましたが、
聴くと、予想をはるかに超えて素晴らしいアルバムだと感じました。
といっても、当時はビートルズ以外は20枚も聴いてなかった、
という若僧でしたが、それでもこの完成度の高さに感動しました。
少しして、高校受験に合格した15歳の3月に2枚目のLPを買いました。
合格のお祝いをもらい、ポールのLPを3枚同時に買ったうちの1枚で、
一緒に買ったのは、この前のRED ROSE SPEEDWAYと、
この後のVENUS AND MARSとの3枚、手堅いでしょ(笑)。
このアルバムは、ナイジェリアのラゴスで録音されました。
当時は街を歩くだけでも危ないと言われていたそうですが、
ポールはなぜかそこで録音したいと言い出してバンドと向かいます。
しかしギターのヘンリー・マカロック Henry McCullochと
ドラムスのデニー・シーウェル Denny Seiwllが脱退してしまい、
ポール、奥さんのリンダ・マッカートニー Linda McCartneyそして
ギターのデニー・レイン Denny Laineの3人で
基本的には録音が進められました(他にも参加者あり)。
ポールはだからここではドラムスも担当しています。
しかし、なぜナイジェリアに行きたかったのかはよく分からない。
きっとポールの本能の導き、思いつきなのかもしれません。
というのも、ポールがこの時点で(今もだけど)自分の音楽に
アフリカ的な要素を採り入れようとは思っていなかったはずで、
このアルバムにもアフリカらしさはほとんど感じられないからです。
強いて言えば、録音状態の空気感がそれっぽいかもしれない。
アルバムを聴いて僕は夏をイメージするのも、そんなところかな。
ナイジェリアはアフリカでもサッカーが強い国ですが、
しかし僕は、中学時代にそのことを聞いたがために、いまだに、
ナイジェリアやラゴスと聞くと、このアルバムを思い出してしまう・・・
このアルバムについて話をする時、
ジャケットのことに触れないわけにはゆかないですね。
表題曲の歌詞のイメージ、刑務所を脱獄したバンドの写真は、
名の知れた俳優などを招いて撮影した力作。
ポールの妥協を許さない姿勢がここにも感じられます。
02

03

今回の限定盤の本には参加者が明記されてるので、
番号に沿って紹介します。
1.Michael Parkinson
マイケル・パーキンソンは英国の著述家。
逃げているのに手を広げてポーズをとっているのが面白い(笑)。
2.Kenny Lynch
ケニー・リンチは英国のシンガーソングライター兼俳優。
僕は音楽を聴いたことがなく映像も見たことはないのですが
そう聞くと、音楽にはちょっと興味が出てきました。
3.Paul McCartney
4.James Coburn
ジェイムス・コバーンは日本でもよく知られた俳優ですね。
僕が大好きなオードリー・ヘプバーンの「シャレード」では、
これが彼のデビュー作であると紹介されています。
また、1990年頃だったかな、たばこのCMに出ていて、
「スピーク・ラーク」は流行語のようにもなりました。
アクが強いけど人間味がある演技は僕も好きでしたが、
2002年に亡くなりました。
5.Clement Freud
クレメント・フロイドは英国のキャスター、政治家。
"Sir"の称号が与えられていましたが、2009年没。
6.Linda McCartney
リンダ・マッカートニーは言わずと知れた「うちのカミさん」。
1997年に亡くなりましたが、それまでは、ポールは、
僕が知る限りでは離婚をしたことがない唯一のロッカーでした。
7.Christopher Lee
クリストファー・リーも"Sir"の称号が与えられている英国の俳優。
なぜここに招かれているのかは、
ポール自らが主題歌Live And Let Dieを歌った
「007死ぬのは奴らだ」に出演しているから、
と書けば、それ以上の説明は要らないかな(笑)。
8.Denny Laine
デニー・レインはポールが頼りにしていたギタリスト。
9.John Conteh
ジョン・コンテは英国人で元ボクシングの世界チャンピオン。
このアルバムの音楽的な特徴として挙げたいのが、
ポールのベース演奏を味わうアルバム、です。
僕が最も好きなベーシストはもちろんポール・マッカートニーですが、
これはロックという音楽におけるベースの名演アルバムとして
筆頭格に挙げられるものだと僕はずっと思っています。
ブックレットにあるスタジオでの録音風景の写真の中に、
ポールがフェンダー・ジャズベースを持った写真があります。
ポールはABBEY ROADの頃からジャズベースを使っているらしく、
それ以降のポールのアルバムでのベースの音は、
ジャズベースのものが多いのかもしれません。
力強くてメロディアスで迫力があってグルーヴ感あふれる、
ポールのペース演奏の真骨頂。
このアルバムが他のポールのアルバムとひと味違うのは、
まさにこのベースにあると思います。
このアルバムの曲は、1曲を除いて
ポール&リンダ・マッカートニーが作詞作曲をしています。
(All songs written by Paul & Linda McCartney
except as noted)
さて、聴いてゆきますか。
04 2010年11月14日の朝の空と雲

Tr1:Band On The Run
メドレーとは名乗っていないけど3部構成のメドレー形式の曲。
ポールが得意なスタイルですね。
第一部は静かなバラード。
刑務所で終身刑を受けた男の心情を歌っていますが、
その割にはなぜか楽観的であまり寂しげではないのは、
この先の物語を予感させるもの、そしてポールらしいところ。
第二部はマイナー調のミドルテンポのロックンロール。
もし外に出たらこんなことをしたい、と願望を歌っていますが、
この部分は切迫感と緊張感がありますね。
なお、この第二部の最後、2'04"あたりの部分
"If I ever get out of here"の低音のコーラスが
ジョン・レノン John Lennonの声に似ているので、
当時は、ジョン・レノンが参加したのかと話題になったそうです。
実際はもちろん違うようですが、しかし、
バスルーム・エコーがかかったような声は確かに似ています。
参加メンバーを見る限りはポールが歌っているのだと思いますが、
ポールの願望なのか、単なる茶目っ気とジョークなのか、
世の中を騒がせたかったのか、或いはほんとにただの偶然か。
第三部は軽やかなフォーク調の本編ともいえるポップな部分で、
いかにもポールらしい口ずさみやすい歌メロ。
この部分で頻繁に入るエレクトリック・ギターのオブリガードの音色が、
そういえばなんとなくトロピカルな雰囲気かな。
この曲はシングルカットされ、ポール3曲目のNo.1となりました。
とここでこのアルバムについて少し補足を。
ビートルズ解散後のポールは、試行錯誤が続いていて、
他の3人に比べるとあまり評価が高くはなく、このアルバムも、
リリース前はあまり期待されていなかったそうなのです。
しかしいざ出てみるとこれが誰が聴いても素晴らしい内容であり、
世の中や評論家のポールを見る目が変わったことは、後から
シングルカットされたこの曲がNo.1になったことからも推察されます。
Tr2:Jet
ポール・マッカートニー「入門編」の曲。
僕が初めて聴いたポールの曲のひとつだからですが、
重たい響きに軽い歌メロ、軽やかなコーラスとギター、
爽快だけどずしんと重たく響いてくるこのこの曲は、
ポールの音楽を象徴する曲のひとつではないかと思います。
歌メロもいいのですがこの曲はサウンドが楽しいですね。
特に途中のピアノの高音連弾は気持ちが浮揚します。
まるでジェット機のエンジンの前に立っているようなサウンド。
この曲のベースは本来の役割である下支えに徹していて、
フレーズとしてはあまり目立たない、適材適所の演奏ですね。
歌詞はポールには珍しく断片的な心情を重ねているものですが、
ひとつ注目の単語が"Suffragette"。
「婦人参政権論者」というこの単語は、政治的活動もしていた
ジョンを意識したとも考えられますが、もうひとつ考えたのは、
この前年にデヴィッド・ボウイ David Bowieが
Suffragette Cityを出していたこと。
ポールは意味云々よりも単にその単語の音の響きが気に入って、
こんな曲を作ってみたのかもしれません。
ポールの言葉への鋭さ、言葉遊び感覚がいきています。
もうひとつ、Jetというのはポールが犬の名前だという話。
ポールは、ビートルズ時代にも自分の犬の名前からとった曲を
作っていて、Martha My Dearがそれですが、
ポールが犬好きであるのは、犬好きとしてうれしいですよ(笑)。
アルバムからの最初のシングル、ビルボード最高位7位を記録。
Tr3:Bluebird
犬に続いて鳥の歌、僕が好きにならないわけがない(笑)。
ポール得意のアコースティック小品系のしっとりとした曲。
Bluebirdと歌うコーラスは誰のパートをとっても歌メロがよく、
僕は歌う度にパートを違えて口ずさみます。
♪ At last we will be free you'll bluebird
鳥と自由を絡めるというモチーフはロックにはよくあって、
例えばレイナード・スキナードのFreebirdは名曲中の名曲、
またジョン・レンンが作っていたFree As A Birdは、1990年代に
ビートルズの「新曲」としてリリースされヒットしました。
この曲は、コーラスが微妙に虚しく寂しい響きなのは、
自由というものは実はなかなか手に入らないものだ、
というメッセージが暗に込められているのかな。
ジェットで飛べなくても自力で飛べる、ということかな(笑)。
この曲はアコースティックギターが前面に出ていますが、
この透明さと精彩さはギター弾き語りではおそらく出せなくて、
アレンジの妙、鋭さを感じます。
そしてここでもベースが歌っています。
そうそう、かつてうちの車もブルーバードだったことがありますが、
この曲の存在を後で知って、うれしかったというより、やっぱり僕は
ビートルズを好きになるべくしてなったんだと思いました(笑)。
Tr4:Mrs. Vandebilt
「ほっ、へいほぅ ほっ、へいほぅ」
この曲はなんといってもこれですね。
この曲にはとっても面白い個人的な逸話があります。
高校時代、僕の家は学校から近かったので、放課後によく
友だちが帰る前にちょっと寄って、音楽を聴いて話していました。
当時は基本的にはみんなはヒットチャートものを聴いていたので、
このような古い曲を聴かせると珍しがっていましたが、
このアルバムを聴かせたうちの2人が、家を出る時に
「ほっ、へいほぅ」と口ずさんでいたのです。
それだけ印象的な曲ですが、この話にはまだ続きがあります。
その後にまた別の音楽が好きな友だちが家に来た際に
このアルバムをかけて、僕は友だちにこう言いました。
「この曲はうちに来て聴いた人は必ず帰りに口ずさむんだよ」
するとその友だちは「俺はそんなことはしない」と宣言しました。
しかし、その友だちもやっぱり、帰りに口ずさんだのです。
「ほっ、へいほう」
友だちが見せたバツの悪そうな顔ったらなかったですね。
曲はほの暗い、ちょっと哀愁系のフォークソング。
ポールの声はエフェクトをかけていて、くぐもったように聴こえます。
この曲のベースはまるで怒っています。
特に0'44"のところの「ぐぅ~ん」というグリッサンドの音が凄い。
それでいてベースだけでも旋律として聴かせます。
一度しか出てこないパッセージの部分の高音コーラスの悲しい響きと、
ポールにしてはブルージーなギターソロも印象的。
内容は「バンガロー・ビル」のポール版みたいなものかな。
そう考えるとやっぱりポールはずっとジョンを意識していたのかな。
なお、Vandebiltについて調べると、スペルが1文字違う
Vanderbiltというアメリカの資産家一族があって、
その名を冠した大学がアメリカのナッシュヴィルにあるのですが、
となるとポールは、資産家の婦人の孤独を歌いたかったのかな。
それとも、ナッシュヴィルといえばカントリー、もしかして、
ポールのカントリー好きが顔をのぞかせているのか。
サックスはHowie Caseyというミュージシャンによるもの。
Tr5:Let Me Roll It
ポールの傑作「ブルーズ」
この曲はほんとにベースが歌いまくっています。
テクニック的には僕が弾けるくらいなので難しくはないですが、
このベースには陶酔しますね(笑)。
4'25"あたりのハーモニカのような音がポールの声だったというのは
サウンド的にも面白い。
1993年の東京ドーム公演で演奏して僕はうれしかったのですが、
会場の反応がとっても微妙でした・・・
05 ジャズベースを持ったポール、ブックレットより
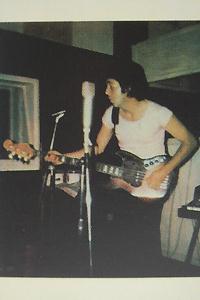
Tr6:Mamunia
B面最初は軽やかでポップなアコースティックギターの曲。
ドシラソファミレドと下がってくるギターの音がとっても印象的。
この曲は歌詞がいいのです。
♪ The rain comes falling from the sky,
To fill the stream that fills the sea
And that's where life began for you and me
"Mamunia"て何だろうと考えて、辞書を引いても出ておらず、
"Mammal"=哺乳類からの造語かなと思ったことがありますが、
だとすれば、哺乳類は水の中から陸に上がったという説に
この歌詞はのっとっているのが興味深いところ。
エコが叫ばれる今の世の中、先見の明があったともいえますが、
それはポールの嗅覚というか本脳の素晴らしさを証明しています。
ポールが何かをすると付け焼刃的であるのは否めないのですが、
逆にいえばそれだけ本能の人で、知識はひとまず関係なく、
自分が信じたところに突き進む人であるのは間違いないでしょう。
音楽的な面で感動的なのが、一度しか出てこない以下の部分
♪ Lay donw your umbrellas, strip off your plastic macs
「傘を置いて、雨合羽を脱ぎ捨てよう!」と呼び掛ける部分の
解放感ある歌メロを温かく歌うポールにはじーんときます。
雨といってもじっとりとしていなくて爽快なのも、
英国よりはアフリカ的なものを感じる部分かもしれません。
Tr1もそうですが、印象的な旋律を奏でるキーボードは、
スティーヴィー・ワンダーの影響かな、曲をさらに魅力的にしています。
雨の名曲、エコの曲としてもっと注目されていいと思います。
Tr7:No Words
(Paul & Linda McCartney, Denny Laine)
甘くとろけるような歌メロはまさにポール節。
このアルバムにあるから甘すぎずにちょうどいい甘さ。
そう感じさせるのは、曲の甘さに反比例するかのような
強めの音のエレクトリック・ギターが引き締めているからかな。
このアルバムはつくづく音への細かい配慮が感じられます。
この曲の注目はこちらも一度しか出てこない部分で、
ポールの声が裏返るほどに音が高くなってゆくところの切なさは、
どちらかというと普段はあまり感情的には歌わないポールも、
こんな歌い方が出来るんだって驚き感動しました。
この曲はコーラスというよりは歌メロが2つあるという曲で、
そのどちらを歌ってもじーんと胸にきます。
強い音のエレクトリック・ギターのソロが始まったと思うと、
さっとフェイドアウトしてしまうのが、もったいない気もするけど、
そこをさらっとやるのがまたポールらしいところ。
この曲はデニー・レインも作曲者に名を連ねていますが、
そのせいか、デニーのコーラスがよく聞こえてきます。
Tr8:Picasso's Last Words (Drink To Me)
パブロ・ピカソはこのアルバムがリリースされた1973年に
亡くなっていますが、ピカソの遺言がこうだったのかは、
僕は知りません、調べがつきませんでした。
♪ Drink to me, drink to my health
「僕の健康のために乾杯」とは、それにしても皮肉ですね。
確かに曲は酔っぱらったようによたよたとした感じ。
得意のディキシーランド・スタイルで曲は始まりますが、
途中でオーケストラを主体としたアレンジの部分に展開し
Jetのモチーフなどをはさんで最後は「ほっ、へいほぅ」で終わる。
お遊びといえばお遊びの緩い曲ですが、この曲は、
このアルバムのここにあるからこそ印象的と言えるでしょう。
ポールの場合、SGT. PEPPER'Sもそうだけど、
凄いアルバムを凄く聴かせて聴くものを構えさせようという気持ちは
さらさらなくって、真剣になればなるほどユーモアの味付けが濃くなり、
その場がなごんでまろやかになる、そんなキャラクターだと思います。
(だから後のTUG OF WARの真剣さが僕には驚きでした。)
クラリネットはポールのお父さんが得意な楽器だっただけに
ポールも使い方がうまいですね。
そのクラリネットは、特に誰が演奏と明記されていないので、
きっとポールが吹いているのでしょうね。
そういえば最後の「ほっ、へいほぅ」の部分の
パーカッシヴな響きとコーラスがアフリカっぽい要素かもしれない。
Tr9:Nineteen Hundred And Eighty Five
最後は来るべき未来の年へ向けての壮大な序曲。
といって、それは今からみるともう四半世紀も前のこと、か・・・
曲自体はホンキートンク調の軽やかなロックンロールですが、
これは、ポールにしては珍しく、歌メロを聴かせるというよりは、
交響的な響きをもって全体で聴かせる曲になっています。
後にポールはクラシックにも挑戦したけど、そういえばこの曲、
そもそもポールは元々クラシックも好んで聴いていましたし、
後にそういうことをするということが垣間見えてきて面白い。
最後にストリングスが入るのですが、でもこの曲は、
最初からそれを予感させる響きを持っています。
オーケストラのアレンジはトニー・ヴィスコンティ Tony Visconti
が担当していますが、後でロンドンでオーバーダブされたものです。
しかし大仰にやるだけではやはりポールらしくない。
この曲はポールのお茶らけみたいな軽い歌い方が
ちょうどいいユーモアをまぶして聴きやすくなっています。
途中でブレイクしてコーラスだけが残る部分も音として印象的。
アウトロに向かう部分では、ピアノにオーケストラからキーボードそれに
クラリネットまで手当たり次第に鳴らした喧騒のような雰囲気の中、
したたかに統制をとって最後まで進み、オーケストラで締めて終わる。
またそのアウトロ前のポールがうめき声のような声を出す部分は
ドラムスをはじめ全体がそういえばアフリカっぽい雰囲気はある。
冒頭に僕は、アフリカっぽさはまるで感じないと書いたけど、
最初に聴いてから今までにいろいろな音楽を聴いてきたせいか、
アフリカの影響らしきものを微妙に感じるようになったようです。
そして最後にタイトル曲のモチーフが出てくるのはSGTからの得意技。
最後はダイナミックに最後らしい曲でしめていて、
こうして格式ある名盤が生まれたのでした。
06 青い鳥・・・じゃないけどコゲラ・・・

ここで、ボーナス音源から2曲。
Disc2
Tr1:Helen Wheels
アメリカでシングルとしてリリースされ10位を記録するヒットに。
それを受けて、後にリリースされたこのアルバムのUSA盤のみ、
この曲が、B面3曲目、No Wordsの後に入れられたため、
このアルバムはアメリカのみ10曲となっています。
僕は、実は、最初に買った日本盤ピクチャーLPが
アメリカ盤を基にしているものだった関係で、
最初に聴いたこのアルバムにこの曲が入っていたのでした。
アルバムは単なる音源の寄せ集めではなく、アーティストが
収録曲や曲順を考えて出すのが基本であるので、
勝手に曲を間に入れるのは暴挙といえるかもしれません。
ただ、このアルバムは不思議なことに、これがあったといって、
全体の印象がさほど悪くはならないのです。
それはこのアルバムのいい意味での緩さのせいかなと思います。
曲は僕が「カンザス・シティ系」と呼ぶスタイルの、
ポールお得意の軽快なロックンロール。
最後の「ばぁ~いば~い」とお化けみたいな声で言うのは、
もう遊んでいるとしか思えない、そんな緩い曲。
Tr2:Country Dreamer
「愛しのヘレン」のシングルB面曲。
タイトルの通り、ポールのカントリー趣味が出ていて、
ポールの音楽のルーツが垣間見えます。
Amazonの本日のランク、リンク左の国内盤限定盤が224位、
国内盤豪華限定盤が388位と、僕が思っていたより上でした。
でも通常盤はリンク右の国内盤が33468位、海外盤が12014位と、
ジョン同様やはり高いものから売れていくのですね。
かくなる僕も、まだ通常盤は買っていないのですが、
まあ、これは限定じゃないので急いではいませんから。
そうそう、新しいリマスター盤の音質は
きわめて自然に聴こえてくる、作り込みをしていないと感じられますが、
それはジョン・レノンもジェイムス・テイラーも同様でした。
長々と書きましたが・・・
これは単純に、純粋に素晴らしいアルバムです。
スポーツ選手でも、超一流選手になるほど、凄いプレイを
いとも簡単にプレイしているように見えて感動しますが、
このアルバムはまさにそのような感じですね。
ポールはこの度、過去のカタログをすべて、
HEAR MUSICに移籍して再リリースしたと書きました。
でも、ずっと昔からビートルズやポールを聴いてきたものとしては、
ポールのCDからEMIの文字がなくなるのは寂しいですね。
まあ、ポールはまだまだ前に進みたがっているのだし、
ポールの意志なのでそれは尊重しますが。
そういえばクイーンも同様にEMIからUNIVERSALに版権が移り、
来年から再発されるというアナウンスがありました。
時代は変わるのかな。
とここで写真をもう1枚。
06

左は今回のこのアルバムの特別盤、
右はジョン・レノンの「心の壁、愛の橋」の新リマスター盤。
ポールはUNIVERSALに移籍、一方ジョンはEMIのままですが、
このように装丁のデザインが同じようなイメージになっているのは、
会社の枠を超えて統一させたのかもしれないですね。
だとすれば、ファンとしては少しうれしいところです。
でもやっぱり、ジョンはEMIに残ったけどポールは離れた・・・
複雑です。
もしかしてポール自身にも複雑な思いがあるのかも。

BAND ON THE RUN Paul McCartney & Wings (1973)
バンド・オン・ザ・ラン ポール・マッカートニー&ウィングス
ポール・マッカートニー&ウィングスの傑作アルバムが
リマスター盤として再発されました。
今回は、アルバム本編だけの通常盤、
ボーナス音源を集めたCDとDVDがついた特別盤、さらには、
それプラス特別音源CDがついた豪華盤の3種類が出ました。
これは、ポール・マッカートニーのカタログの所有権が、
UNIVERSAL傘下のHEAR MUSICへ移ったことに伴うもので、
今後は他のアルバムも次々と再発されることが予想されます。
最初にこれが出たのは、最高傑作と言われているからでしょうけれど、
その辺はファンとしては納得できます。
今日は、リマスター盤のリリースを記念して、
ついに、このアルバムの記事を上げます。
僕も、このアルバムは、僕のリアルタイムに出たものではない
ポールのアルバムではいちばん好きです。
リアルタイムを含めるとTUG OF WARがいちばんなのですが、
とにかくこのアルバムの完成度の高さは驚異的ですらあります。
そんな大好きなアルバムで、僕には重い存在であるから、
今まではなかなか記事にしようという気持ちになれませんでした。
しかし、いくらんなんでもこの機会を逃すとファンじゃないな、と、
ようやく重い腰と気持ちを上げた次第です。
しかしこのアルバムは、別のかたちで一度記事にしていました。
僕は、何を隠そう、このアルバムのコレクターでして、
LP、CD合わせて14枚持っている、その「自慢」記事でした。
ご興味があるかたはこちらの記事へどうぞ。
ちなみに、今回はひとまず豪華盤と特別盤を買ったので、
現時点でうちにあるこのアルバムは16枚となりました。
このアルバムを最初に買ったのは、中学3年の秋だったかな。
国内盤ピクチャーLPが売られていたのを、普段あまり行かなかった
札幌市内のレコード店で見つけ、少しして買いに行きました。
当時はもうビートルズ関係の本をよく読んでいたので、
このアルバムがポールの最高傑作であるとの予備知識はありましたが、
聴くと、予想をはるかに超えて素晴らしいアルバムだと感じました。
といっても、当時はビートルズ以外は20枚も聴いてなかった、
という若僧でしたが、それでもこの完成度の高さに感動しました。
少しして、高校受験に合格した15歳の3月に2枚目のLPを買いました。
合格のお祝いをもらい、ポールのLPを3枚同時に買ったうちの1枚で、
一緒に買ったのは、この前のRED ROSE SPEEDWAYと、
この後のVENUS AND MARSとの3枚、手堅いでしょ(笑)。
このアルバムは、ナイジェリアのラゴスで録音されました。
当時は街を歩くだけでも危ないと言われていたそうですが、
ポールはなぜかそこで録音したいと言い出してバンドと向かいます。
しかしギターのヘンリー・マカロック Henry McCullochと
ドラムスのデニー・シーウェル Denny Seiwllが脱退してしまい、
ポール、奥さんのリンダ・マッカートニー Linda McCartneyそして
ギターのデニー・レイン Denny Laineの3人で
基本的には録音が進められました(他にも参加者あり)。
ポールはだからここではドラムスも担当しています。
しかし、なぜナイジェリアに行きたかったのかはよく分からない。
きっとポールの本能の導き、思いつきなのかもしれません。
というのも、ポールがこの時点で(今もだけど)自分の音楽に
アフリカ的な要素を採り入れようとは思っていなかったはずで、
このアルバムにもアフリカらしさはほとんど感じられないからです。
強いて言えば、録音状態の空気感がそれっぽいかもしれない。
アルバムを聴いて僕は夏をイメージするのも、そんなところかな。
ナイジェリアはアフリカでもサッカーが強い国ですが、
しかし僕は、中学時代にそのことを聞いたがために、いまだに、
ナイジェリアやラゴスと聞くと、このアルバムを思い出してしまう・・・
このアルバムについて話をする時、
ジャケットのことに触れないわけにはゆかないですね。
表題曲の歌詞のイメージ、刑務所を脱獄したバンドの写真は、
名の知れた俳優などを招いて撮影した力作。
ポールの妥協を許さない姿勢がここにも感じられます。
02

03

今回の限定盤の本には参加者が明記されてるので、
番号に沿って紹介します。
1.Michael Parkinson
マイケル・パーキンソンは英国の著述家。
逃げているのに手を広げてポーズをとっているのが面白い(笑)。
2.Kenny Lynch
ケニー・リンチは英国のシンガーソングライター兼俳優。
僕は音楽を聴いたことがなく映像も見たことはないのですが
そう聞くと、音楽にはちょっと興味が出てきました。
3.Paul McCartney
4.James Coburn
ジェイムス・コバーンは日本でもよく知られた俳優ですね。
僕が大好きなオードリー・ヘプバーンの「シャレード」では、
これが彼のデビュー作であると紹介されています。
また、1990年頃だったかな、たばこのCMに出ていて、
「スピーク・ラーク」は流行語のようにもなりました。
アクが強いけど人間味がある演技は僕も好きでしたが、
2002年に亡くなりました。
5.Clement Freud
クレメント・フロイドは英国のキャスター、政治家。
"Sir"の称号が与えられていましたが、2009年没。
6.Linda McCartney
リンダ・マッカートニーは言わずと知れた「うちのカミさん」。
1997年に亡くなりましたが、それまでは、ポールは、
僕が知る限りでは離婚をしたことがない唯一のロッカーでした。
7.Christopher Lee
クリストファー・リーも"Sir"の称号が与えられている英国の俳優。
なぜここに招かれているのかは、
ポール自らが主題歌Live And Let Dieを歌った
「007死ぬのは奴らだ」に出演しているから、
と書けば、それ以上の説明は要らないかな(笑)。
8.Denny Laine
デニー・レインはポールが頼りにしていたギタリスト。
9.John Conteh
ジョン・コンテは英国人で元ボクシングの世界チャンピオン。
このアルバムの音楽的な特徴として挙げたいのが、
ポールのベース演奏を味わうアルバム、です。
僕が最も好きなベーシストはもちろんポール・マッカートニーですが、
これはロックという音楽におけるベースの名演アルバムとして
筆頭格に挙げられるものだと僕はずっと思っています。
ブックレットにあるスタジオでの録音風景の写真の中に、
ポールがフェンダー・ジャズベースを持った写真があります。
ポールはABBEY ROADの頃からジャズベースを使っているらしく、
それ以降のポールのアルバムでのベースの音は、
ジャズベースのものが多いのかもしれません。
力強くてメロディアスで迫力があってグルーヴ感あふれる、
ポールのペース演奏の真骨頂。
このアルバムが他のポールのアルバムとひと味違うのは、
まさにこのベースにあると思います。
このアルバムの曲は、1曲を除いて
ポール&リンダ・マッカートニーが作詞作曲をしています。
(All songs written by Paul & Linda McCartney
except as noted)
さて、聴いてゆきますか。
04 2010年11月14日の朝の空と雲

Tr1:Band On The Run
メドレーとは名乗っていないけど3部構成のメドレー形式の曲。
ポールが得意なスタイルですね。
第一部は静かなバラード。
刑務所で終身刑を受けた男の心情を歌っていますが、
その割にはなぜか楽観的であまり寂しげではないのは、
この先の物語を予感させるもの、そしてポールらしいところ。
第二部はマイナー調のミドルテンポのロックンロール。
もし外に出たらこんなことをしたい、と願望を歌っていますが、
この部分は切迫感と緊張感がありますね。
なお、この第二部の最後、2'04"あたりの部分
"If I ever get out of here"の低音のコーラスが
ジョン・レノン John Lennonの声に似ているので、
当時は、ジョン・レノンが参加したのかと話題になったそうです。
実際はもちろん違うようですが、しかし、
バスルーム・エコーがかかったような声は確かに似ています。
参加メンバーを見る限りはポールが歌っているのだと思いますが、
ポールの願望なのか、単なる茶目っ気とジョークなのか、
世の中を騒がせたかったのか、或いはほんとにただの偶然か。
第三部は軽やかなフォーク調の本編ともいえるポップな部分で、
いかにもポールらしい口ずさみやすい歌メロ。
この部分で頻繁に入るエレクトリック・ギターのオブリガードの音色が、
そういえばなんとなくトロピカルな雰囲気かな。
この曲はシングルカットされ、ポール3曲目のNo.1となりました。
とここでこのアルバムについて少し補足を。
ビートルズ解散後のポールは、試行錯誤が続いていて、
他の3人に比べるとあまり評価が高くはなく、このアルバムも、
リリース前はあまり期待されていなかったそうなのです。
しかしいざ出てみるとこれが誰が聴いても素晴らしい内容であり、
世の中や評論家のポールを見る目が変わったことは、後から
シングルカットされたこの曲がNo.1になったことからも推察されます。
Tr2:Jet
ポール・マッカートニー「入門編」の曲。
僕が初めて聴いたポールの曲のひとつだからですが、
重たい響きに軽い歌メロ、軽やかなコーラスとギター、
爽快だけどずしんと重たく響いてくるこのこの曲は、
ポールの音楽を象徴する曲のひとつではないかと思います。
歌メロもいいのですがこの曲はサウンドが楽しいですね。
特に途中のピアノの高音連弾は気持ちが浮揚します。
まるでジェット機のエンジンの前に立っているようなサウンド。
この曲のベースは本来の役割である下支えに徹していて、
フレーズとしてはあまり目立たない、適材適所の演奏ですね。
歌詞はポールには珍しく断片的な心情を重ねているものですが、
ひとつ注目の単語が"Suffragette"。
「婦人参政権論者」というこの単語は、政治的活動もしていた
ジョンを意識したとも考えられますが、もうひとつ考えたのは、
この前年にデヴィッド・ボウイ David Bowieが
Suffragette Cityを出していたこと。
ポールは意味云々よりも単にその単語の音の響きが気に入って、
こんな曲を作ってみたのかもしれません。
ポールの言葉への鋭さ、言葉遊び感覚がいきています。
もうひとつ、Jetというのはポールが犬の名前だという話。
ポールは、ビートルズ時代にも自分の犬の名前からとった曲を
作っていて、Martha My Dearがそれですが、
ポールが犬好きであるのは、犬好きとしてうれしいですよ(笑)。
アルバムからの最初のシングル、ビルボード最高位7位を記録。
Tr3:Bluebird
犬に続いて鳥の歌、僕が好きにならないわけがない(笑)。
ポール得意のアコースティック小品系のしっとりとした曲。
Bluebirdと歌うコーラスは誰のパートをとっても歌メロがよく、
僕は歌う度にパートを違えて口ずさみます。
♪ At last we will be free you'll bluebird
鳥と自由を絡めるというモチーフはロックにはよくあって、
例えばレイナード・スキナードのFreebirdは名曲中の名曲、
またジョン・レンンが作っていたFree As A Birdは、1990年代に
ビートルズの「新曲」としてリリースされヒットしました。
この曲は、コーラスが微妙に虚しく寂しい響きなのは、
自由というものは実はなかなか手に入らないものだ、
というメッセージが暗に込められているのかな。
ジェットで飛べなくても自力で飛べる、ということかな(笑)。
この曲はアコースティックギターが前面に出ていますが、
この透明さと精彩さはギター弾き語りではおそらく出せなくて、
アレンジの妙、鋭さを感じます。
そしてここでもベースが歌っています。
そうそう、かつてうちの車もブルーバードだったことがありますが、
この曲の存在を後で知って、うれしかったというより、やっぱり僕は
ビートルズを好きになるべくしてなったんだと思いました(笑)。
Tr4:Mrs. Vandebilt
「ほっ、へいほぅ ほっ、へいほぅ」
この曲はなんといってもこれですね。
この曲にはとっても面白い個人的な逸話があります。
高校時代、僕の家は学校から近かったので、放課後によく
友だちが帰る前にちょっと寄って、音楽を聴いて話していました。
当時は基本的にはみんなはヒットチャートものを聴いていたので、
このような古い曲を聴かせると珍しがっていましたが、
このアルバムを聴かせたうちの2人が、家を出る時に
「ほっ、へいほぅ」と口ずさんでいたのです。
それだけ印象的な曲ですが、この話にはまだ続きがあります。
その後にまた別の音楽が好きな友だちが家に来た際に
このアルバムをかけて、僕は友だちにこう言いました。
「この曲はうちに来て聴いた人は必ず帰りに口ずさむんだよ」
するとその友だちは「俺はそんなことはしない」と宣言しました。
しかし、その友だちもやっぱり、帰りに口ずさんだのです。
「ほっ、へいほう」
友だちが見せたバツの悪そうな顔ったらなかったですね。
曲はほの暗い、ちょっと哀愁系のフォークソング。
ポールの声はエフェクトをかけていて、くぐもったように聴こえます。
この曲のベースはまるで怒っています。
特に0'44"のところの「ぐぅ~ん」というグリッサンドの音が凄い。
それでいてベースだけでも旋律として聴かせます。
一度しか出てこないパッセージの部分の高音コーラスの悲しい響きと、
ポールにしてはブルージーなギターソロも印象的。
内容は「バンガロー・ビル」のポール版みたいなものかな。
そう考えるとやっぱりポールはずっとジョンを意識していたのかな。
なお、Vandebiltについて調べると、スペルが1文字違う
Vanderbiltというアメリカの資産家一族があって、
その名を冠した大学がアメリカのナッシュヴィルにあるのですが、
となるとポールは、資産家の婦人の孤独を歌いたかったのかな。
それとも、ナッシュヴィルといえばカントリー、もしかして、
ポールのカントリー好きが顔をのぞかせているのか。
サックスはHowie Caseyというミュージシャンによるもの。
Tr5:Let Me Roll It
ポールの傑作「ブルーズ」
この曲はほんとにベースが歌いまくっています。
テクニック的には僕が弾けるくらいなので難しくはないですが、
このベースには陶酔しますね(笑)。
4'25"あたりのハーモニカのような音がポールの声だったというのは
サウンド的にも面白い。
1993年の東京ドーム公演で演奏して僕はうれしかったのですが、
会場の反応がとっても微妙でした・・・
05 ジャズベースを持ったポール、ブックレットより
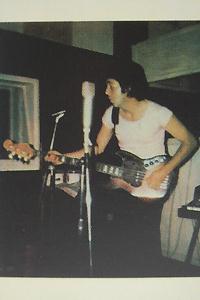
Tr6:Mamunia
B面最初は軽やかでポップなアコースティックギターの曲。
ドシラソファミレドと下がってくるギターの音がとっても印象的。
この曲は歌詞がいいのです。
♪ The rain comes falling from the sky,
To fill the stream that fills the sea
And that's where life began for you and me
"Mamunia"て何だろうと考えて、辞書を引いても出ておらず、
"Mammal"=哺乳類からの造語かなと思ったことがありますが、
だとすれば、哺乳類は水の中から陸に上がったという説に
この歌詞はのっとっているのが興味深いところ。
エコが叫ばれる今の世の中、先見の明があったともいえますが、
それはポールの嗅覚というか本脳の素晴らしさを証明しています。
ポールが何かをすると付け焼刃的であるのは否めないのですが、
逆にいえばそれだけ本能の人で、知識はひとまず関係なく、
自分が信じたところに突き進む人であるのは間違いないでしょう。
音楽的な面で感動的なのが、一度しか出てこない以下の部分
♪ Lay donw your umbrellas, strip off your plastic macs
「傘を置いて、雨合羽を脱ぎ捨てよう!」と呼び掛ける部分の
解放感ある歌メロを温かく歌うポールにはじーんときます。
雨といってもじっとりとしていなくて爽快なのも、
英国よりはアフリカ的なものを感じる部分かもしれません。
Tr1もそうですが、印象的な旋律を奏でるキーボードは、
スティーヴィー・ワンダーの影響かな、曲をさらに魅力的にしています。
雨の名曲、エコの曲としてもっと注目されていいと思います。
Tr7:No Words
(Paul & Linda McCartney, Denny Laine)
甘くとろけるような歌メロはまさにポール節。
このアルバムにあるから甘すぎずにちょうどいい甘さ。
そう感じさせるのは、曲の甘さに反比例するかのような
強めの音のエレクトリック・ギターが引き締めているからかな。
このアルバムはつくづく音への細かい配慮が感じられます。
この曲の注目はこちらも一度しか出てこない部分で、
ポールの声が裏返るほどに音が高くなってゆくところの切なさは、
どちらかというと普段はあまり感情的には歌わないポールも、
こんな歌い方が出来るんだって驚き感動しました。
この曲はコーラスというよりは歌メロが2つあるという曲で、
そのどちらを歌ってもじーんと胸にきます。
強い音のエレクトリック・ギターのソロが始まったと思うと、
さっとフェイドアウトしてしまうのが、もったいない気もするけど、
そこをさらっとやるのがまたポールらしいところ。
この曲はデニー・レインも作曲者に名を連ねていますが、
そのせいか、デニーのコーラスがよく聞こえてきます。
Tr8:Picasso's Last Words (Drink To Me)
パブロ・ピカソはこのアルバムがリリースされた1973年に
亡くなっていますが、ピカソの遺言がこうだったのかは、
僕は知りません、調べがつきませんでした。
♪ Drink to me, drink to my health
「僕の健康のために乾杯」とは、それにしても皮肉ですね。
確かに曲は酔っぱらったようによたよたとした感じ。
得意のディキシーランド・スタイルで曲は始まりますが、
途中でオーケストラを主体としたアレンジの部分に展開し
Jetのモチーフなどをはさんで最後は「ほっ、へいほぅ」で終わる。
お遊びといえばお遊びの緩い曲ですが、この曲は、
このアルバムのここにあるからこそ印象的と言えるでしょう。
ポールの場合、SGT. PEPPER'Sもそうだけど、
凄いアルバムを凄く聴かせて聴くものを構えさせようという気持ちは
さらさらなくって、真剣になればなるほどユーモアの味付けが濃くなり、
その場がなごんでまろやかになる、そんなキャラクターだと思います。
(だから後のTUG OF WARの真剣さが僕には驚きでした。)
クラリネットはポールのお父さんが得意な楽器だっただけに
ポールも使い方がうまいですね。
そのクラリネットは、特に誰が演奏と明記されていないので、
きっとポールが吹いているのでしょうね。
そういえば最後の「ほっ、へいほぅ」の部分の
パーカッシヴな響きとコーラスがアフリカっぽい要素かもしれない。
Tr9:Nineteen Hundred And Eighty Five
最後は来るべき未来の年へ向けての壮大な序曲。
といって、それは今からみるともう四半世紀も前のこと、か・・・
曲自体はホンキートンク調の軽やかなロックンロールですが、
これは、ポールにしては珍しく、歌メロを聴かせるというよりは、
交響的な響きをもって全体で聴かせる曲になっています。
後にポールはクラシックにも挑戦したけど、そういえばこの曲、
そもそもポールは元々クラシックも好んで聴いていましたし、
後にそういうことをするということが垣間見えてきて面白い。
最後にストリングスが入るのですが、でもこの曲は、
最初からそれを予感させる響きを持っています。
オーケストラのアレンジはトニー・ヴィスコンティ Tony Visconti
が担当していますが、後でロンドンでオーバーダブされたものです。
しかし大仰にやるだけではやはりポールらしくない。
この曲はポールのお茶らけみたいな軽い歌い方が
ちょうどいいユーモアをまぶして聴きやすくなっています。
途中でブレイクしてコーラスだけが残る部分も音として印象的。
アウトロに向かう部分では、ピアノにオーケストラからキーボードそれに
クラリネットまで手当たり次第に鳴らした喧騒のような雰囲気の中、
したたかに統制をとって最後まで進み、オーケストラで締めて終わる。
またそのアウトロ前のポールがうめき声のような声を出す部分は
ドラムスをはじめ全体がそういえばアフリカっぽい雰囲気はある。
冒頭に僕は、アフリカっぽさはまるで感じないと書いたけど、
最初に聴いてから今までにいろいろな音楽を聴いてきたせいか、
アフリカの影響らしきものを微妙に感じるようになったようです。
そして最後にタイトル曲のモチーフが出てくるのはSGTからの得意技。
最後はダイナミックに最後らしい曲でしめていて、
こうして格式ある名盤が生まれたのでした。
06 青い鳥・・・じゃないけどコゲラ・・・

ここで、ボーナス音源から2曲。
Disc2
Tr1:Helen Wheels
アメリカでシングルとしてリリースされ10位を記録するヒットに。
それを受けて、後にリリースされたこのアルバムのUSA盤のみ、
この曲が、B面3曲目、No Wordsの後に入れられたため、
このアルバムはアメリカのみ10曲となっています。
僕は、実は、最初に買った日本盤ピクチャーLPが
アメリカ盤を基にしているものだった関係で、
最初に聴いたこのアルバムにこの曲が入っていたのでした。
アルバムは単なる音源の寄せ集めではなく、アーティストが
収録曲や曲順を考えて出すのが基本であるので、
勝手に曲を間に入れるのは暴挙といえるかもしれません。
ただ、このアルバムは不思議なことに、これがあったといって、
全体の印象がさほど悪くはならないのです。
それはこのアルバムのいい意味での緩さのせいかなと思います。
曲は僕が「カンザス・シティ系」と呼ぶスタイルの、
ポールお得意の軽快なロックンロール。
最後の「ばぁ~いば~い」とお化けみたいな声で言うのは、
もう遊んでいるとしか思えない、そんな緩い曲。
Tr2:Country Dreamer
「愛しのヘレン」のシングルB面曲。
タイトルの通り、ポールのカントリー趣味が出ていて、
ポールの音楽のルーツが垣間見えます。
Amazonの本日のランク、リンク左の国内盤限定盤が224位、
国内盤豪華限定盤が388位と、僕が思っていたより上でした。
でも通常盤はリンク右の国内盤が33468位、海外盤が12014位と、
ジョン同様やはり高いものから売れていくのですね。
かくなる僕も、まだ通常盤は買っていないのですが、
まあ、これは限定じゃないので急いではいませんから。
そうそう、新しいリマスター盤の音質は
きわめて自然に聴こえてくる、作り込みをしていないと感じられますが、
それはジョン・レノンもジェイムス・テイラーも同様でした。
長々と書きましたが・・・
これは単純に、純粋に素晴らしいアルバムです。
スポーツ選手でも、超一流選手になるほど、凄いプレイを
いとも簡単にプレイしているように見えて感動しますが、
このアルバムはまさにそのような感じですね。
ポールはこの度、過去のカタログをすべて、
HEAR MUSICに移籍して再リリースしたと書きました。
でも、ずっと昔からビートルズやポールを聴いてきたものとしては、
ポールのCDからEMIの文字がなくなるのは寂しいですね。
まあ、ポールはまだまだ前に進みたがっているのだし、
ポールの意志なのでそれは尊重しますが。
そういえばクイーンも同様にEMIからUNIVERSALに版権が移り、
来年から再発されるというアナウンスがありました。
時代は変わるのかな。
とここで写真をもう1枚。
06

左は今回のこのアルバムの特別盤、
右はジョン・レノンの「心の壁、愛の橋」の新リマスター盤。
ポールはUNIVERSALに移籍、一方ジョンはEMIのままですが、
このように装丁のデザインが同じようなイメージになっているのは、
会社の枠を超えて統一させたのかもしれないですね。
だとすれば、ファンとしては少しうれしいところです。
でもやっぱり、ジョンはEMIに残ったけどポールは離れた・・・
複雑です。
もしかしてポール自身にも複雑な思いがあるのかも。
Posted by guitarbird at 16:54
│Paul



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト


































